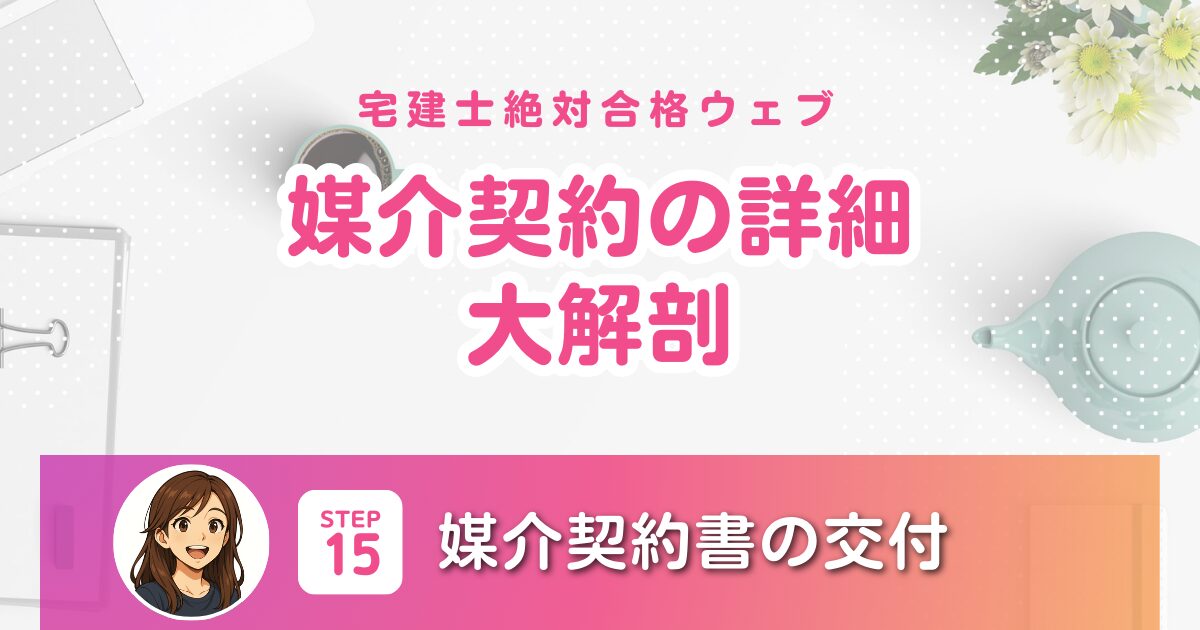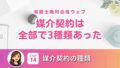媒介契約を結んだけど、不動産会社から渡された契約書…「これって何が書いてあるの?」「そもそも、この書類って必ずもらえるものなの?」「サインするのは誰?」なんて、細かいルールや書類の中身について、疑問に思ったことはありませんか?
前回は媒介契約の「種類」について詳しく見ましたが、今回はその契約を結んだ後に交付される「媒介契約書(宅建業法34条の2に基づく書面なので「34条書面」とも言います!)」にスポットを当てて、その交付ルールや記載されている内容、さらには「標準媒介契約約款」って何?という疑問まで、しっかり解説していきます! ここを理解すれば、契約内容の確認もバッチリですよ!

契約書って文字が多くて読むのが大変…って思いがちですが、ポイントを押さえれば大丈夫! 一緒に見ていきましょう!
この記事でわかること
- 媒介契約書がなぜ交付されるのか、その目的
- 媒介契約書の交付に関する基本ルール(対象契約、時期、誰が記名押印するかなど)
- 媒介契約書にどんなことが記載されているのか(主な記載事項)
- 「標準媒介契約約款」とは何か、使う義務はあるのか
- 媒介契約を結ぶ前に、業者から確認しておきたいポイント
トラブル防止の第一歩!媒介契約書(34条書面)の交付ルール
なぜ書面が必要?媒介契約書交付の目的
そもそも、なんでわざわざ媒介契約書という書面を作成して交付する必要があるんでしょうか?
それは、後々のトラブルを防ぐためです!
口約束だけで仲介をお願いすると、「どの物件を探してもらう約束だったっけ?」「仲介手数料はいくらって言ってた?」「いつまでに相手を見つけてくれるの?」など、後になってから「言った」「言わない」の水掛け論になってしまう可能性がありますよね。
そこで、どんな物件について、どんな種類の媒介契約(一般・専任・専属専任)で、有効期間はいつまでで、報酬はいくらか…といった契約の内容を、きちんと書面に残して明確にしておくことで、依頼者(あなた)と宅建業者との間の認識のズレや、将来的な紛争を防ぐ、という大切な目的があるんです。
いつ、誰が、どうやって?交付の基本ルールをチェック!
では、この媒介契約書の交付について、宅建業法で定められている基本的なルールを見ていきましょう! ここ、試験で頻出の重要ポイントが満載ですよ!
- どんな契約の時に交付義務があるの?(対象契約)
- 売買または交換の媒介(仲介)または代理の契約を締結した場合です。
超重要! 賃貸借(アパートやマンションの賃貸など)の媒介や代理の場合は、媒介契約書の作成・交付義務はありません! もちろん、親切な業者さんが任意で作成してくれることはありますが、法律上の義務ではないんです! ここ、本当によくひっかけ問題で出ます!
- いつ交付するの?(交付時期)
- 媒介契約を締結した後、遅滞なく(=合理的な期間内に速やかに)交付しなければなりません。
- 誰が作成して交付するの?(作成・交付者)
- 宅地建物取引業者(不動産会社)です。
- 誰が書面に記名押印するの?
- これも宅地建物取引業者です!
これも超重要! 記名押印するのは、宅建士(取引士)」ではありません! 会社(業者)としての記名押印が必要です。重要事項説明書(35条書面)は宅建士の記名が必要でしたが、媒介契約書(34条書面)は違うんです! この違い、絶対に覚えてくださいね!
- 書面の内容を説明する義務はあるの?
- 法律上、媒介契約書の内容について、宅建士が説明する義務はありません。交付するだけでOKです。(もちろん、実際には担当者が説明してくれることがほとんどですが)
- したがって、説明自体は宅建士でなくても、誰が行っても問題ありません。
この交付ルールのポイントをまとめると…
<チェックリスト>
この5点、しっかり頭に入れてくださいね!
紙じゃなくてもOK!電磁的方法による交付
以前は紙の書面での交付が原則でしたが、現在は、依頼者(あなた)の承諾があれば、媒介契約書に記載すべき事項を、メールにPDFファイルを添付して送るなど、電磁的な方法で提供することも可能になっています。
これにより、郵送の手間や時間を省けたり、書類の保管がしやすくなったりと、双方にとってメリットがありますね。ただし、あくまでも依頼者の承諾が必要、という点は忘れないでください。
交付義務はないけど…やっておきたい事前説明
法律上、媒介契約書の説明義務はない、とお伝えしましたが、だからといって業者が何も説明しなくて良いわけではありません。
国土交通省のガイドライン(宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方)では、より良い取引のために、以下のような対応が望ましいとされています。
- 媒介契約を結ぶ前に、依頼者に対して、これから行おうとしている媒介業務の範囲などについて、書面を交付して説明すること。
- 契約を結ぶ際には、一般・専任・専属専任の3つの媒介契約の違いを十分に説明し、依頼者の意思をしっかり確認してから契約すること。
- もし、売主か買主のどちらか一方からだけ媒介の依頼を受けることを約束した場合には、その旨を契約書に明記すること。(例えば「買主側の仲介だけを担当します」といった場合ですね)

法律の義務ではないけれど、やっぱり事前にしっかり説明してくれる業者さんの方が安心できますよね! こういう点も、業者選びの参考になるかもしれません。
契約書には何が書いてある?主な記載事項と標準約款
さて、いよいよ媒介契約書(34条書面)に具体的にどんなことが書かれているのか、その中身を見ていきましょう!
ここをチェック!媒介契約書の主な記載事項リスト
宅建業法で定められている、媒介契約書に記載しなければならない主な事項は以下の通りです。(全部を完璧に暗記する必要はありませんよ! 「ふむふむ、こんなことが書いてあるんだな」くらいの感じでOKです!)
- 宅地又は建物を特定するために必要な表示: 物件の所在地、地番、家屋番号など、どの不動産についての契約か分かるように特定する情報です。
- 宅地又は建物を売買すべき価額又は評価額: いくらで売りたい(買いたい)か、交換の場合はその評価額ですね。
宅建業者がこの価額について意見を述べる場合は、ただ「〇〇円くらいですね」と言うだけでなく、その根拠(周辺の取引事例や公示価格など)を明らかにしなければなりません! これは大事なルール!
- 媒介契約の種類: 一般媒介なのか、専任媒介なのか、専属専任媒介なのか、その種別を明記します。
- 有効期間及び解除に関する事項: 契約期間はいつまでか、どんな場合に契約を解除できるか、などが書かれています。(専任・専属専任の場合は最長3ヶ月!)
- 指定流通機構(レインズ)への登録に関する事項: レインズに登録するかどうか。
専任・専属専任で登録が義務付けられている場合はもちろん、一般媒介で登録しない場合でも、「登録しない」と記載する必要があります! 「登録に関する事項」なので、有無をはっきりさせる必要があるんですね。
- 報酬に関する事項: いわゆる仲介手数料ですね。契約が成立した場合に、依頼者が宅建業者に支払う報酬の額や、その算出方法などが記載されます。
- 建物状況調査(インスペクション)を実施する者のあっせんに関する事項(既存建物=中古建物の場合):
- 中古住宅の取引で、依頼者がインスペクション(専門家による建物診断)を希望する場合に、宅建業者が調査を実施する業者を紹介(あっせん)するかどうか、という点について記載します。(平成30年の法改正で追加されました!)
- 当該媒介契約の有効期間中に依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼するときの制限や、自ら発見した相手方と契約するときの制限(専任媒介、専属専任媒介の場合): 専任・専属ならではの制限事項について記載します。
- その他、契約違反に対する措置など: 約束を守らなかった場合にどうなるか、といった内容です。
- 標準媒介契約約款に基づくか否かの別: 後述する「標準媒介契約約款」というひな形に基づいて作成された契約書かどうか、という点です。
「標準媒介契約約款」って聞いたことある?
媒介契約書の記載事項の中に「標準媒介契約約款に基づくか否かの別」とありましたね。この「標準媒介契約約款(ひょうじゅんばいかいけいやくやっかん)」って、一体何なのでしょうか?
- 標準媒介契約約款とは?
- これは、国土交通省が定めた、媒介契約の標準的な契約条項(ひな形)のことです。
- 宅建業法で定められた記載事項だけでは、まだカバーしきれない部分もあり、消費者(依頼者)をよりしっかり保護するために、国が「こういう内容で契約するのが標準的ですよ」というモデルを示しているんですね。
- 使う義務はあるの?
- いいえ、法律上の使用義務はありません。宅建業者は、この標準約款を使わなくてもOKです。
- 使わない場合はどうする?
- もし標準約款に基づかないオリジナルの契約書を使う場合は、媒介契約書に「この契約は、国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づくものではありません」とはっきり記載すれば、宅建業法違反にはなりません。
- でも、国は使ってほしい?
- はい、その通りです。国土交通省のガイドラインでは、「特別な事情がある場合を除き、標準媒介契約約款を使用することが望ましい」として、その使用を推奨しています。
メリット・デメリット
- 標準約款を使うメリット: 国が作ったひな形なので、内容が網羅的で、依頼者にとって不利な条項が入っている心配が少ないという安心感があります。
- 標準約款を使わない場合の注意点: 業者独自の契約内容になっている可能性があるので、どんな内容になっているか、自分に不利な点はないか、より注意深く確認する必要があります。
実際には、多くの宅建業者がこの標準媒介契約約款をベースにして媒介契約書を作成しています。皆さんが不動産会社で目にする契約書も、おそらくこれに基づいている可能性が高いですよ!
希望物件が決まってない時の記載方法
ちなみに、物件を「買いたい」「交換したい」という依頼で媒介契約を結ぶ場合、まだ具体的に「このマンションのこの部屋が欲しい!」というように物件が決まっていないケースもありますよね。
そんな時は、媒介契約書に希望する物件の具体的な所在地などを書けません。その代わりに、「物件の種類(マンション、戸建てなど)、希望価額、広さ、間取り、希望エリア、その他の希望条件」といった内容を記載することになります。
契約前に確認しよう!依頼者への周知が望ましいこと
最後に、媒介契約を結ぶにあたって、私たち依頼者がより安心して契約できるよう、宅建業者に対して、事前に説明したり注意喚起したりすることが望ましいとされている事項がいくつかあります。これもガイドラインで示されている内容です。
業者から説明を受けたいポイント5選!
媒介契約を結ぶ前に、特に以下の点について業者さんから説明を受けたり、自分から確認したりすると良いでしょう。
- 標準約款の活用について: 「特別な事情がなければ、国が作った標準約款を使うのが一般的ですよ」という点。もし使わないのであれば、その理由や契約内容の違いなどを確認したいですね。
- 契約タイプの選択権: 「一般・専任・専属専任の3種類があって、どれを選ぶかは最終的に依頼者であるあなた次第ですよ」という点。それぞれのメリット・デメリットの説明を受けた上で、自分で選ぶ権利があることを認識しましょう。
- 報酬(仲介手数料)について: 報酬額には法律で上限(売買価格の3%+6万円+消費税など)が定められていますが、それはあくまで「上限」です。「上限額=必ず請求される額」ではなく、具体的な報酬額は、業者が提供するサービス内容などを考慮して、依頼者と業者との間で協議して決めるものだ、という点を理解しておくことが大切です。
- レインズ登録の確認方法: もし専任・専属専任契約を結んでレインズに登録された場合、「業者から交付される登録済証で、ちゃんと登録されたことを確認できますよ」という点。
- 契約違反時のペナルティ: 「もし依頼者が契約内容に違反した場合(例:専属専任なのに他の業者に依頼した、など)は、違約金や、かかった費用の支払いを求められる可能性があるので、契約書の内容はしっかり読んで理解しておきましょうね」という注意喚起。
賢い依頼者になるために
これらの点を踏まえて、私たち依頼者としては…
- 分からないこと、疑問に思ったことは、遠慮せずにどんどん業者さんに質問する!
- 渡された契約書は、「よく分からないから…」と丸投げせず、しっかり目を通して内容を確認する!
という姿勢が、後悔しない不動産取引のためにはとても重要になってきます。

業者さんを信頼するのはもちろん大事ですが、任せっきりにせず、自分でも契約内容をしっかり理解しようとすることが、最終的に自分の身を守ることにつながりますからね!」
まとめ
媒介契約書の交付ルールと記載内容、そして標準媒介契約約款について、理解は深まりましたか?
媒介契約書(34条書面)は、売買・交換の媒介契約において、宅建業者が遅滞なく作成・交付する義務があり、業者の記名押印が必要です(賃貸は義務なし、宅建士の記名押印ではない!)。
記載事項は多岐にわたりますが、特に価額の根拠明示義務やレインズ登録の有無、標準約款に基づくか否かといった点は意識しておきたいポイントです。そして、国が推奨する標準媒介契約約款の存在も知っておくと良いでしょう。
- 媒介契約書の交付: 売買・交換の媒介で義務あり(賃貸は×)。契約後遅滞なく。
- 作成・交付・記名押印: 宅建業者が行う(宅建士ではない!)。
- 説明義務: なし。
- 主な記載事項: 物件特定、価額(根拠明示!)、契約種類、有効期間、レインズ登録(有無記載!)、報酬、インスペクションあっせん、標準約款の別など。
- 標準媒介契約約款: 国交省のひな形。使用義務はないが推奨されている。
- 依頼者の心得: 契約タイプは自分で選ぶ!報酬は協議!契約書はよく読む!
媒介契約書は、あなたと不動産会社との大切な約束事を記した書類です。内容をしっかり理解し、納得の上で契約を進めてくださいね!

媒介契約書のルールもこれでバッチリですね! 細かい違いが多いですが、一つ一つクリアしていけば大丈夫! 次のステップも頑張りましょう!