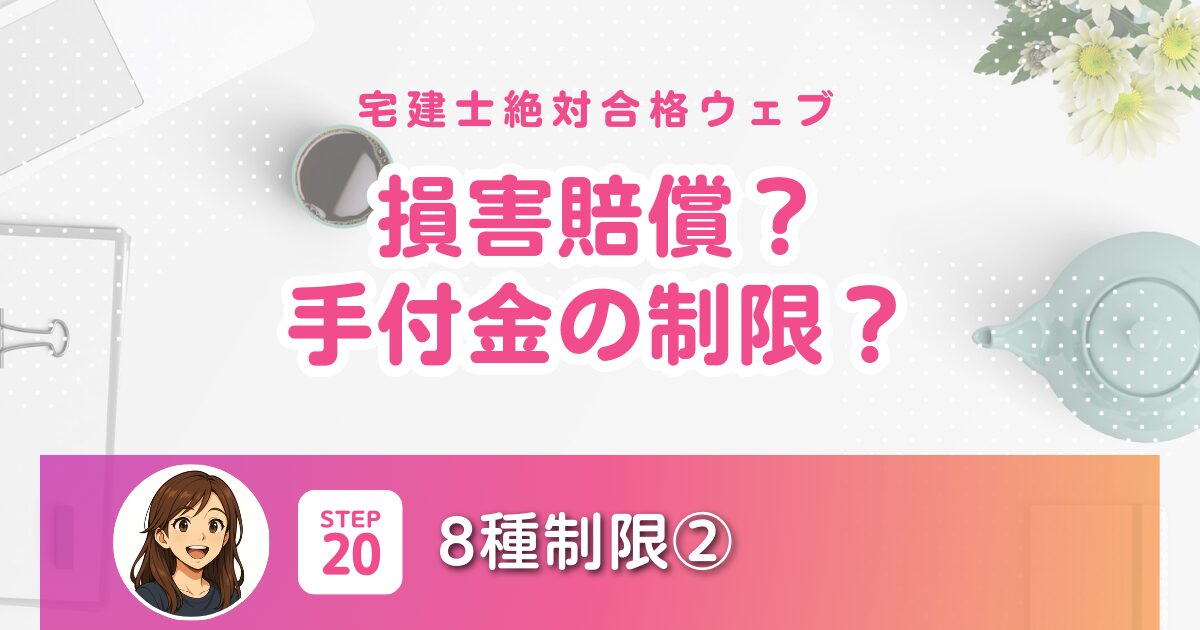宅建の勉強、進んでますか〜? たくさん覚えることがあって、頭がパンクしそう!ってなっていませんか? 特に「権利関係」と並んで難関なのが「宅建業法」ですよね。その中でも、「8種制限」って、なんか名前からして難しそうだし、種類が多くてごっちゃになりやすいポイントじゃないですか?
この8種制限って、宅建業者が自ら売主になるときに、知識や経験の少ない一般の買主さんを守るための、すごーく大事なルールなんです! だから、試験でも「ここは絶対落とせない!」っていう超重要分野なんですよ。
この記事では、そんな8種制限の中から、特にややこしい&試験に出やすい「損害賠償額の予定等の制限」「手付額等の制限」「自己の所有に属しない物件の売買制限」の3つに絞って、私が不動産会社で培った知識も交えながら、とことん分かりやすく解説していきます!
<この記事でわかること>
- 損害賠償額の予定って何?なぜ制限があるの?上限はいくら?
- 手付金の制限ルールと、ややこしい解約手付の仕組み
- 手付解除ができるタイミングと、できないタイミング
- 他人の物やまだ完成してない物件を売っちゃダメな理由と、売ってもOKな例外ケース
- 8種制限(損害賠償・手付・他人物売買)を攻略するポイント
【8種制限②】損害賠償額の予定等の制限
まず1つ目は、「損害賠償額の予定等の制限」について見ていきましょう!
そもそも「損害賠償額の予定」って何?

契約って、約束事ですよね。もし、その約束が守られなかったら…? これを「債務不履行(さいむふりこう)」って言います。
例えば、買主さんが約束した日までに代金を支払わなかったり、売主さんが物件を引き渡さなかったり…こういう場合に、約束を破られた側は損害を受けますよね。その損害を埋め合わせしてもらうのが「損害賠償」です。
でも、実際にどれくらいの損害が出たのかって、後から計算するのが結構大変だし、金額をめぐってトラブルになることも多いんです…。「いや、そんなに損害出てないでしょ!」「いやいや、これだけ損害が出てるんだ!」みたいに、水掛け論になっちゃう。
そこで、「もし約束違反があったら、損害賠償として〇〇円支払いましょうね」って、契約を結ぶときに、あらかじめ金額を決めておくことがあるんです。これが「損害賠償額の予定」です。
損害賠償額の予定とは?
契約違反(債務不履行)があった場合に支払う損害賠償の金額を、あらかじめ契約で決めておくこと。これをしておけば、いざという時に「損害額はいくらか?」ってもめる必要がなくなります。スムーズに解決できるっていうメリットがあるんですね。
なぜ「制限」が必要なの? 宅建業法の上限ルール!
損害賠償額を事前に決めておけるのは便利なんですけど、ここで一つ問題が…。
もし、宅建業者さんが、その立場を利用して、すっごく高額な損害賠償額を契約に盛り込んだらどうでしょう?
例えば、「もし買主さんがローン審査に落ちて契約解除になったら、違約金として物件価格の半分を支払ってもらいます!」みたいな。

えー!そんなの、怖くて契約できないですよね!?
そうなんです。知識や経験が少ない一般の買主さんは、「そういうものなのかな…」って、不利な条件を飲んでしまうかもしれない。そうなると、万が一の時に、とんでもない金額を請求されて、破産しちゃう…なんてことにもなりかねません。
そこで、宅建業法の出番です!
宅建業法では、宅建業者が自ら売主となり、宅建業者でない一般の人(買主)と不動産の売買契約を結ぶ場合に、買主さんを守るために、この損害賠償額の予定に上限を設けているんです。
損害賠償額の予定等の制限(宅建業法第38条)
- 対象となる契約: 宅建業者が自ら売主、買主が宅建業者でない場合
- 制限の内容:
- 損害賠償額の予定と違約金(※)を合計した額が、代金の10分の2(=2割)を超えてはいけない。
- もし、10分の2を超える部分を定めても、その超えた部分は無効になる。
- 趣旨: 高額な賠償額や違約金から、弱い立場にある買主を保護するため。
※「違約金」も、契約違反があった場合に支払うお金として、あらかじめ定めておくものです。損害賠償額の予定と似たような性質を持っているので、ここではセットで考えます。
例で見てみよう!
3,000万円のマンションの売買契約(売主:宅建業者、買主:一般消費者)
- OKな例:
- 損害賠償額の予定:400万円、違約金:200万円 → 合計600万円(=代金の2割)
- 損害賠償額の予定:500万円(代金の約16.7%)
- 違約金:600万円(代金の2割)
- NGな例:
- 損害賠償額の予定:700万円 → 代金の2割(600万円)を超える100万円分は無効。請求できるのは600万円まで。
- 損害賠償額の予定:400万円、違約金:300万円 → 合計700万円。代金の2割(600万円)を超える100万円分は無効。請求できるのは合計600万円まで。
この制限は、あくまで「宅建業者が自ら売主」で「買主が宅建業者でない」場合に適用されます。
- 業者間の取引(売主も買主も宅建業者)
- 宅建業者が媒介(仲介)や代理をするだけの場合
- 売主が一般の人で、買主が宅建業者の場合
これらのケースでは、この2割ルールは適用されません。当事者間の合意で自由に決めることができます(もちろん、あまりにも法外な金額は公序良俗違反で無効になる可能性はありますが)。

なるほど! 誰と誰の契約か、っていうのがポイントなんですね!
もし損害賠償額の予定を定めなかったら?
じゃあ、もし契約の時に損害賠償額の予定や違約金をまったく決めなかった場合はどうなるんでしょう?
その場合は、実際に発生した損害額、つまり「実損額」を証明して請求することになります。
例えば、買主の債務不履行で契約が解除になり、売主(宅建業者)が別の買主を探すために広告費がかかったり、物件の価値が下がってしまったりした場合、その実際にかかった費用や損害分を請求できる、ということです。
もちろん、この場合も、本当にそれだけの損害があったのかどうか、証明が必要になるので、やっぱり後々もめる可能性はありますよね。だから、多くの契約では、トラブル防止のために、上限の範囲内で損害賠償額の予定が定められています。
【8種制限③】手付額等の制限
続いては、「手付額等の制限」です!これも買主さん保護のための大事なルールですよ。
「手付金」ってそもそも何? 解約手付を理解しよう!
不動産売買契約を結ぶとき、買主さんから売主さんへ、「この契約、ちゃんと守りますよ」という証拠金のような意味合いで支払われるお金があります。これが「手付金」です。

契約成立の証として、最初に支払うお金、ってイメージですね! この手付金は、通常、売買代金の一部に充てられます。
手付金には、実はいくつか種類があるんですが、宅建の試験対策として、そして実務でも一番重要なのが「解約手付(かいやくてつけ)」です!
解約手付とは?
一定の条件のもとで、契約を解除する権利を確保するための手付金のこと。
具体的には、こんなルールになっています。
- 買主から解除する場合: 支払った手付金を放棄する(=返してもらわない)ことで、契約を解除できる。
- 売主から解除する場合: 受け取った手付金の倍額を買主に支払う(=手付金を返して、さらに同額を上乗せして支払う)ことで、契約を解除できる。これを「手付倍返し(てつけばいがえし)」とか「倍額償還(ばいがくしょうかん)」って言います。
これ、どういうことかというと、契約を結んだけど、「やっぱりやめたいな…」って思った時に、一定のペナルティ(手付金の放棄 or 倍返し)を払えば、理由を問われずに契約を解除できるっていう仕組みなんです。
家を買うって、すごく大きな決断ですよね。契約した後で、「もっといい物件があったかも…」とか「やっぱり資金計画が厳しいかも…」って、気持ちが変わることもあるかもしれません。

「お試し期間」みたいなもの、と考えると分かりやすいかも?
手付解除ができるのは「いつまで」? 履行の着手に注意!
ただし、この解約手付による解除(手付解除)は、いつでもできるわけではありません! ここ、めちゃくちゃ重要なのでしっかり押さえてくださいね!
手付解除ができるのは、「契約の相手方が、契約内容の実現に向けた具体的な行動(=履行の着手)を始めるまで」と決められています。
「履行(りこう)に着手(ちゃくしゅ)する」って、ちょっと難しい言葉ですよね。具体的にどういうことかというと…
- 売主側の履行の着手の例:
- 物件の引渡し準備として、買主の希望に合わせてリフォーム工事を始めた。
- 所有権移転登記の申請手続きを始めた。
- 物件を引き渡した(これはもう履行そのものですね)。
- 買主側の履行の着手の例:
- 中間金(内金)を支払った。
- 引越し業者を手配した(これは状況によりますが、履行の着手とみなされる可能性あり)。
- 代金の残額を支払った(これも履行そのもの)。

相手がもう契約を進める準備を始めちゃってたら、さすがに「やっぱやーめた!」は通用しないってことですね。
もし相手が履行に着手した後に契約を解除したい場合は、手付解除ではなく、さっき出てきた「債務不履行」による解除や、あるいは当事者間の話し合い(合意解除)など、別の方法を考えることになります。この場合、損害賠償の問題が出てくる可能性が高いです。
なぜ手付金にも「制限」があるの? やっぱり上限は2割!
さて、本題の「手付額等の制限」です。これも、さっきの損害賠償額の予定の制限と同じような理由で設けられています。
もし、宅建業者さんが「手付金として、代金の半分を払ってください!」なんて要求してきたらどうでしょう?
買主さんとしては、もし後で気が変わっても、そんな大金を放棄するのはあまりにも痛すぎますよね…。事実上、手付解除ができなくなってしまいます。つまり、高額な手付金は、買主さんの「解約する権利」を奪ってしまうことになりかねないんです。
そこで、またまた宅建業法の登場です!
宅建業法では、宅建業者が自ら売主となり、宅建業者でない一般の人(買主)と不動産の売買契約を結ぶ場合に、手付金の額にも上限を定めています。
手付額等の制限(宅建業法第39条)
- 対象となる契約: 宅建業者が自ら売主、買主が宅建業者でない場合
- 制限の内容:
- 宅建業者は、代金の10分の2(=2割)を超える額の手付金を受け取ってはならない。
- もし、10分の2を超える手付金を受け取る特約を結んでも、その超える部分については無効になる。(買主は超えた分を支払う義務がない、すでに支払っていたら返還を請求できる)
- この場合の手付は、当事者がどんな名目にしようと、すべて「解約手付」としての性質を持つ。
- 趣旨: 高額な手付金によって買主の解約権が事実上奪われるのを防ぎ、買主を保護するため。
<例>5,000万円の土地の売買契約(売主:宅建業者、買主:一般消費者)
- OKな例:
- 手付金:800万円(代金の16%)
- 手付金:1,000万円(代金の2割)
- NGな例:
- 手付金:1,200万円 → 代金の2割(1,000万円)を超える200万円分は無効。買主は1,000万円まで支払えばOK。もし1,200万円支払ってしまっていたら、200万円の返還を請求できる。
ここでも大事なのは、「宅建業者が自ら売主」「買主が宅建業者でない」という条件です。業者間の取引などでは、この2割ルールは適用されません。
そしてもう一つ! このルールが適用される場合、買主さんが支払う手付金は、たとえ契約書に「これは証約手付(契約成立の証拠としての手付)ですよ」って書いてあったとしても、必ず「解約手付」の性質を持つことになります。つまり、買主さんは必ず手付放棄による解除権を持つ、ということです。これも買主さんをしっかり守るためのルールなんですね!

損害賠償額の予定も、手付金も、上限は「代金の2割」! セットで覚えておくといいですね。
【8種制限④】自己の所有に属さない物件の売買制限
さあ、8種制限の3つ目、「自己の所有に属さない宅地又は建物の売買契約締結の制限」です! ちょっと長い名前ですね。
これは、簡単に言うと、「自分が持ってない不動産を、自分が売主になって売る契約をしちゃダメですよ」っていうルールです。
「自己の所有に属さない物件」ってどんなの?
具体的に、このルールで売ることが制限される「自己の所有に属さない物件」とは、主に次の2つを指します。
- 他人物件: 他の人が所有している土地や建物。
- 未完成物件: まだ完成していない建物や、造成工事が終わっていない宅地。

え? 他人の物を売る契約って、そもそもアリなの? って思いません? 実は、民法では「他人物売買」自体は有効なんです。売主は、後でその物をちゃんと手に入れて、買主に引き渡す義務を負う、っていう仕組みなんですね。
でも、不動産取引って、扱う金額も大きいし、権利関係も複雑ですよね。もし、宅建業者が「〇〇さんの土地、私が売ってあげますよ!」って言って買主さんと契約したけど、結局その土地を〇〇さんから買い取れなかったら…? 買主さんは代金を払ったのに、土地を手に入れられない!なんていう、大きなトラブルになる可能性があります。
未完成物件も同じです。完成前に契約したけど、工事が途中でストップしてしまったり、完成しなかったりしたら、買主さんは非常に困ってしまいます。
そこで、宅建業法では、宅建業者が自ら売主となる場合に、このようなリスクから買主さんを守るために、原則として他人物売買や未完成物件の売買契約を禁止しているんです。
自己の所有に属さない物件の売買制限(宅建業法第33条の2)
- 対象となる契約: 宅建業者が自ら売主となる売買契約(予約を含む)
- 原則: 宅建業者は、自己の所有に属さない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約を締結してはならない。
- 対象物件:
- 他人が所有している物件
- 未完成の物件
- 趣旨: 買主が物件を取得できないリスクや、完成しないリスクから保護するため。
禁止の「例外」アリ!契約できるケースは?
原則禁止!…なんですが、これにはちゃんと例外があります。つまり、「こういう条件を満たしていれば、他人の物や未完成物件でも、宅建業者が売主になって契約してもOKですよ」っていう場合があるんです。ここが試験でもよく問われるポイント!
例外①:他人物件の場合
他人の物件であっても、宅建業者がその物件を確実に手に入れる見込みがある場合は、例外的に売買契約を結ぶことが認められます。
他人物売買が例外的に認められるケース:
宅建業者が、その物件の所有者との間で、すでに「取得する契約(予約も含む)」を締結している場合。
つまり、「売主になる宅建業者さんが、元の持ち主からその物件を買い取る契約(や予約)をちゃんとしてますよ」っていう状態なら、買主さんに売る契約をしてもOK、ということです。これなら、宅建業者さんがちゃんと物件を手に入れて、買主さんに引き渡せる可能性が高いですよね。

ただ口約束とかじゃなくて、ちゃんと「取得する契約」を結んでることが条件なんですね!
注意!停止条件付きの取得契約はダメ!
ここで注意が必要なのが、「停止条件(ていしじょうけん)付き」の取得契約の場合は、まだ例外として認められない、ということです。
「停止条件付き契約」っていうのは、「〇〇という条件が満たされたら、契約の効力が発生しますよ」っていう契約のこと。例えば、「銀行の融資が下りたら、この土地を買います」みたいな契約です。
この場合、条件が満たされるまでは、宅建業者さんが確実に物件を取得できるとは限りませんよね? だから、停止条件付きの契約を結んでいるだけでは、「自己の所有に属さない物件」として扱われ、自ら売主となる売買契約は禁止されたままなんです。
例外②:未完成物件の場合
まだ完成していない建物や宅地の場合はどうでしょう? 新築マンションとか、造成中の宅地とか、完成前に契約することって普通にありますよね。
これも、買主さんが支払ったお金が無駄にならないように、ちゃんと保護措置が取られていれば、例外的に契約OKとなります。
<未完成物件の売買が例外的に認められるケース>
その契約に関して、手付金等の保全措置が講じられている場合。
「手付金等の保全措置」っていうのは、もし万が一、物件が完成しなかったり、引き渡されなかったりした場合に、買主さんが支払った手付金や中間金などがちゃんと返ってくるようにするための仕組みのことです。銀行などによる保証とか、保険事業者の保証保険とか、いくつか方法があります。(保全措置の詳しい内容は、また別の機会にしっかり解説しますね!)

未完成物件の場合は、「もしもの時にお金がちゃんと返ってくる保証が付いてるなら、契約してもOKですよ」ってことですね! 安心!
ここまでのポイント整理
| 制限の種類 | 対象契約 | 制限内容 | 例外/ポイント |
| 損害賠償額の予定等 | 業者売主、買主非業者 | 損害賠償額の予定+違約金 ≦ 代金の2/10 (超える部分は無効) | 定めない場合は実損額請求 |
| 手付額等 | 業者売主、買主非業者 | 受領できる手付金 ≦ 代金の2/10 (超える部分は無効) | ・必ず解約手付扱い ・手付解除は相手方の履行着手まで |
| 自己所有でない物件の売買 | 業者売主 (相手が業者でも非業者でも適用!) | 原則、他人物件・未完成物件の売主となる契約は禁止 | 例外あり ・他人物:取得契約(予約含む)締結済み (停止条件付はNG) ・未完成物件:手付金等保全措置あり |

あれ?「自己所有でない物件の売買制限」だけ、買主が宅建業者かどうかの区別がないですね…? そうなんです! この制限は、買主が宅建業者であっても適用されるんです! ちょっと他の2つと違うので、注意してくださいね!
まとめ
お疲れ様でした! 今回は、宅建業法の8種制限の中から、「損害賠償額の予定等の制限」「手付額等の制限」「自己の所有に属さない物件の売買制限」の3つを詳しく見てきました。
どれも、宅建業者が自ら売主となる場合に、買主さんを守るための大事なルールでしたね! 数字や条件が細かい部分もありますが、なぜそのような制限があるのか、という「趣旨」を理解すると、記憶に残りやすくなると思いますよ。
最後に、今日のポイントをもう一度おさらいしておきましょう!
- 損害賠償額の予定と違約金の合計額は、代金の2割まで! 超える部分は無効です。(業者売主、買主非業者の場合)
- 手付金も、受け取れるのは代金の2割まで! 超える部分は無効です。(業者売主、買主非業者の場合)
- ↑の場合の手付金は必ず解約手付となり、手付解除は相手方が履行に着手するまで可能です。
- 宅建業者は、原則として他人物件や未完成物件を自ら売主として売買契約できません。
- 例外として、他人物件は取得契約(予約含む、停止条件付は×)を結んでいればOK、未完成物件は手付金等の保全措置があればOKです。(これは買主が業者でも適用!)
8種制限は、他にもあと4つあります。一つひとつは難しくても、こうやって分解して、理由や具体例と一緒に理解していけば、必ず得意分野にできます!

今回の内容、しっかりマスターできましたか? この調子で、他の制限もどんどん攻略していきましょうね!