宅建士の勉強、順調ですか? 前回に引き続き、今回も「8種制限」の攻略を進めていきましょう! 8種制限って、本当に細かいルールが多いですよね…。「手付金の保全措置」とか、「割賦(かっぷ)販売」とか、「所有権留保(しょゆうけんりゅうほ)」とか…普段あまり聞き慣れない言葉も出てきて、ちょっと戸惑っていませんか?
でも、安心してください! これらも、これまで見てきた制限と同じように、不動産取引に慣れていない買主さんを、不測の事態や不利な契約から守るための、とっても大切なルールなんです。特に、万が一売主の宅建業者が倒産してしまった場合でも、支払った手付金などがちゃんと返ってくるようにする「手付金等保全措置」は、買主さんにとって最後の砦とも言える重要な仕組みですよ。
この記事では、8種制限のラストスパートとして、
- 手付金等保全措置
- 割賦販売契約における解除等の制限
- 割賦販売契約における所有権留保等の禁止
- 契約不適合責任についての特約の制限
この4つのルールについて、掘り下げて解説していきます! それぞれのルールが「なぜ必要なのか」「どんな場合に適用されるのか」「具体的な内容は?」といったポイントを、しっかり押さえていきましょう。
この記事を読めば、保全措置が必要になる金額のラインや、割賦販売特有の注意点、契約不適合責任でどこまでが有効な特約なのか、といった試験で狙われやすいポイントがクリアになります。「8種制限、ややこしいけど、もう怖くない!」って思えるようになりますよ!

さあ、最後の関門を突破して、8種制限マスターを目指しましょう!
この記事でわかること
- 手付金等の保全措置が必要になるケース、不要になるケースの具体的な基準
- 保全措置の3つの種類と、それぞれの特徴
- 割賦販売(分割払い)で買主を守るためのルール(解除制限・所有権留保禁止)
- 契約不適合責任に関する特約で、無効になるもの・有効になるものの違い
【8種制限⑤】手付金等保全措置 倒産リスクから守る!保全措置が必要・不要なケースと方法をチェック
まずは、買主さんのお金を守るための重要なセーフティーネット、「手付金等保全措置」について見ていきましょう。
「手付金等」って何のこと? 保全措置はなぜ必要?
不動産の売買契約では、契約を結んでから実際に物件が引き渡されるまでに、買主さんから売主さんへ何回かに分けてお金が支払われることがあります。
- 契約時に支払う「手付金」
- 引渡し前に支払う「中間金(内金)」など
これらのように、「契約を結んだ後、物件の引渡し前に支払われて、最終的に売買代金の一部となるお金」のことを、宅建業法ではまとめて「手付金等」と呼んでいます。
手付金等とは?
契約締結日から物件引渡し前までに、買主から売主(宅建業者)へ支払われるお金で、売買代金に充当されるもの。(名目は問わない)
例:手付金、中間金など
さて、ここで考えてみてください。もし、買主さんが手付金や中間金を支払った後、物件の引渡しを待っている間に、売主である宅建業者が倒産してしまったら…?
最悪の場合、支払ったお金が戻ってこず、大きな損害を受けてしまう可能性があります。これは、買主さんにとって、あまりにも酷な話ですよね。
そこで、宅建業法は、宅建業者が自ら売主となり、宅建業者でない買主から手付金等を受け取る場合には、原則として、その手付金等がちゃんと返ってくることを保証するための措置(=保全措置)を講じることを義務付けているんです!
保全措置が「不要」になるケースがある! 金額と登記をチェック!
「原則として保全措置が必要」ということは、例外的に保全措置が不要になるケースもある、ということです。ここ、試験でめちゃくちゃ狙われやすいので、しっかり区別できるようにしましょう!
保全措置が不要になるのは、以下の3つのパターンです。
- 買主への所有権移転登記がされた場合→ もう物件の所有権が買主さんのものになっていれば、たとえ売主が倒産しても、買主さんが手付金等を失うリスクは基本的にないですよね。だから保全は不要です。
- 受領する手付金等の額が一定基準以下の場合→ 少額の手付金等のために、毎回保全措置を義務付けるのは、業者さんにとっても手間やコストがかかりすぎます。そこで、リスクが比較的小さいと考えられる一定の金額以下の場合は、保全措置が免除されています。この基準額が、物件が完成しているか、未完成かで異なるので注意が必要です!
- 未完成物件の場合: 受領する手付金等の額が代金の5%以下で、かつ1,000万円以下のとき
- 完成物件の場合: 受領する手付金等の額が代金の10%以下で、かつ1,000万円以下のとき
- この「%」と「金額」の基準は、両方を満たす必要があります。「かつ」が重要です! 片方だけ満たしていてもダメですよ。
具体例で見てみよう!
(1) 未完成物件(新築マンションなど)を5,000万円で購入する場合
- 代金の5% = 250万円
- 基準:250万円以下(5%以下)で、かつ1,000万円以下
- ⇒ 250万円を超える手付金等を受け取る場合は、保全措置が必要。
- 手付金200万円 → 保全措置不要
- 手付金300万円 → 保全措置必要
- 手付金800万円 → 保全措置必要
(2) 完成物件(中古住宅など)を3,000万円で購入する場合
- 代金の10% = 300万円
- 基準:300万円以下(10%以下)で、かつ1,000万円以下
- ⇒ 300万円を超える手付金等を受け取る場合は、保全措置が必要。
- 手付金300万円 → 保全措置不要
- 手付金500万円 → 保全措置必要
(3) 完成物件を1億2,000万円で購入する場合
- 代金の10% = 1,200万円
- 基準:代金の10%以下で、かつ1,000万円以下
- ⇒ 代金の10%(1,200万円)は1,000万円を超えています。この場合、1,000万円を超える手付金等を受け取る場合は、保全措置が必要。
- 手付金1,000万円 → 保全措置不要
- 手付金1,100万円 → 保全措置必要
保全措置にはどんな種類があるの?
じゃあ、具体的にどんな方法で手付金等を保全するのでしょうか? 宅建業法で認められている保全措置は、主に次の3つのタイプがあります。
手付金等の保全措置の種類
- 銀行等による保証(保証委託契約)
- 内容:宅建業者が銀行などと保証委託契約を結び、もしもの時は銀行が代わりに手付金等を返還してくれる、というもの。宅建業者は、買主さんにその保証書を交付します。
- 対象物件:完成物件・未完成物件どちらもOK!
- 保険事業者による保証保険(保証保険契約)
- 内容:宅建業者が保険会社と保証保険契約を結び、もしもの時は保険金として手付金等が支払われる、というもの。宅建業者は、買主さんにその保険証券(またはそれに代わる書面)を交付します。
- 対象物件:完成物件・未完成物件どちらもOK!
- 指定保管機関による保管
- 内容:国土交通大臣が指定した機関(不動産保証協会など)が、宅建業者に代わって買主さんから手付金等を預かり、保管してくれる、というもの。
- 対象物件:完成物件のみOK! 未完成物件には使えません!

どの方法で保全措置を講じるかは、宅建業者が選びます。買主さんは、契約時にどの方法が取られているか、しっかり確認することが大切ですね!
【8種制限⑥⑦】割賦販売の制限 分割払いでも安心!不利な特約を禁止する2つのルール(解除制限・所有権留保禁止)
次は、不動産を分割払いで購入する「割賦販売」に関する制限を見ていきましょう。これも買主さんを保護するためのルールです。
そもそも「割賦販売」って?
割賦販売(かっぷはんばい)とは、代金を一括ではなく、分割で支払う契約方法のことです。月々支払っていくので、「ローン」と似たようなイメージですね。分割で支払うお金のことを「賦払金(ふばらいきん)」とも言います。
高額な不動産を買うときに、一度に全額を用意するのが難しい場合などに利用されることがあります。
【8種制限⑥】ルール①:すぐに契約解除や一括請求はできない!(解除等の制限)
割賦販売で心配なのが、「もし、うっかり1回だけ支払いが遅れちゃったら、すぐに契約解除されたり、残りの代金を全部一括で払え!って言われたりするの…?」ということですよね。
ご安心ください! 宅建業法では、宅建業者が自ら売主となる割賦販売契約において、買主さんの賦払金の支払いが遅れたとしても、すぐに契約解除や残代金全額の一括請求はできないように、手続きに制限を設けています。
割賦販売契約の解除等の制限(宅建業法第42条)
- 対象: 宅建業者が自ら売主となる割賦販売契約
- 制限: 買主の賦払金の支払遅延を理由として…
- 契約を解除したり、
- 残っている代金の全額支払いを請求したりする場合には、
- 必ず、30日以上の相当な期間を定めて、
- 書面で支払いを催告(さいこく=要求すること)し、
- その期間内に支払いがない場合でなければ、行うことができない。
- 特約の効力: このルールに反する特約で、買主に不利なものは無効となる。
つまり、業者さんは「〇月〇日までに支払ってくださいね。もし支払われなければ、契約解除になりますよ」という内容を、最低でも30日以上の猶予期間を設けて、書面で買主さんに伝えなければならない、ということです。口頭での催告や、期間が30日未満の催告ではダメなんです。
もし契約書に「1回でも支払いが遅れたら、催告なしで即契約解除!」とか「催告期間は1週間!」なんて書かれていても、それは無効になります。ちゃんと法律で定められた手順を踏まないと、解除や一括請求は認められません。
【8種制限⑦】ルール②:物件を引き渡したら、所有権もちゃんと移す!(所有権留保等の禁止)
もう一つ、割賦販売で問題になりがちなのが、「所有権」の問題です。
「代金を全部払い終わるまでは、物件の所有権は売主(宅建業者)のものにしておきますよ」という状態を「所有権留保(しょゆうけんりゅうほ)」と言います。
確かに、売主さんからすれば、代金を全額回収できるまでは、所有権を手元に置いておきたい気持ちも分かります。でも、買主さんからすると、もう物件に住み始めて、分割で代金も払っているのに、いつまでも所有権が自分に移らないのは不安ですよね。もし売主が倒産したら、所有権を失ってしまうリスクもあります。
そこで、宅建業法は、宅建業者が自ら売主となる割賦販売契約においては、原則として所有権留保を禁止しています。
所有権留保等の禁止(宅建業法第43条)
- 対象: 宅建業者が自ら売主となる割賦販売契約
- 原則: 宅建業者は、その物件を買主に引き渡すまでに、所有権移転登記の申請をしなければならない。 (=引渡しと同時に所有権も買主に移さなければならない)
- 趣旨: 買主の地位を安定させ、二重譲渡や売主倒産のリスクから保護するため。
つまり、分割払いの途中であっても、物件の引渡しをするなら、原則として所有権も買主に移転させなさい、ということです。
例外的に所有権留保がOKな場合もある
ただし、これも原則禁止なので、例外的に所有権留保が認められるケースがあります。これは、逆に業者さん側を保護するための規定です。
考えてみてください。例えば、3,000万円の物件を割賦販売して、買主さんからまだ手付金100万円しか受け取っていないのに、すぐに所有権を移転してしまったら…? もし買主さんがその後、全然払ってくれなくなったら、業者さんは大損害ですよね。
そこで、以下のような場合には、例外的に所有権を留保(=所有権移転登記をしないこと)が認められています。
所有権留保が例外的に認められる場合
- 買主から受け取った金額(賦払金含む)の合計が、代金の10分の3以下の場合 → まだ受け取っている金額が少ないうちは、業者さんを守るために留保OK。
- 買主が、残っている代金の支払いについて、担保を提供するなどの見込みがないと認められる場合 → 買主さんに支払い能力や信用力が乏しく、残代金を回収できるか非常に不安な場合も、留保が認められることがあります。

基本は「引渡しまでに所有権移転!」だけど、業者さんにとってリスクが高すぎる場合は例外がある、と覚えておきましょう!
【8種制限⑧】契約不適合責任の特約制限 買主不利は許さない!民法との違いと通知期間のルール
さあ、8種制限の最後の項目、「契約不適合責任(けいやくふてきごうせきにん)についての特約の制限」です! これは、買った物件に欠陥などがあった場合のルールですね。
「契約不適合責任」ってなんだっけ?(民法の基本)
まず、基本のおさらいです。売買契約で引き渡された物件が、
- 種類(例:注文したのはAタイプなのにBタイプだった)
- 品質(例:雨漏りがする、シロアリ被害があった)
- 数量(例:土地の面積が契約より少なかった)
について、契約の内容と違う(=契約に適合しない)場合、売主さんが買主さんに対して負う責任のことを「契約不適合責任」と言います。(以前は「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」と呼ばれていましたね)
この場合、買主さんは、民法のルールに基づいて、売主さんに対して以下のような請求ができます。
- ① 追完請求(ついかんせいきゅう): 直してもらう、足りない分を引き渡してもらう、代わりの物を引き渡してもらう請求
- ② 代金減額請求(だいきんげんがくせいきゅう): 代金をまけてもらう請求
- ③ 損害賠償請求(そんがいばいしょうせいきゅう): 損害を受けた分を賠償してもらう請求
- ④ 契約の解除(けいやくのかいじょ): 契約自体をなかったことにする
そして、「種類」または「品質」に関する契約不適合の場合、買主さんは、原則として、その不適合を知った時から1年以内に、そのことを売主さんに通知しないと、上記の①~④の請求ができなくなってしまいます。
民法上の契約不適合責任(基本ルール)
- 買主の権利: ①追完請求、②代金減額請求、③損害賠償請求、④解除
- 通知期間(種類・品質の場合): 不適合を知った時から1年以内に売主へ通知
宅建業法による「特約」の制限! 買主不利はNG!
民法では、この契約不適合責任について、「売主は一切責任を負いません」とか「責任を負うのは引き渡しから半年間だけです」といった特約(当事者間の特別な約束)を結ぶことも、原則として自由なんです。(※ただし、売主が不適合を知っていたのに告げなかった場合は、免責特約は無効になります)
でも、もし知識のない一般の買主さんが、宅建業者さんから「契約不適合責任は一切負いませんよ」っていう不利な特約を結ばされてしまったら…? 後で家に欠陥が見つかっても、何も請求できないなんてことになったら、大変ですよね。
そこで、やっぱり宅建業法の出番です!
宅建業者が自ら売主となり、宅建業者でない買主と契約する場合、契約不適合責任に関して、民法のルールよりも買主にとって不利になるような特約を結ぶことを禁止しています。
契約不適合責任の特約制限(宅建業法第40条)
- 対象: 宅建業者が自ら売主、買主が宅建業者でない場合
- 制限: 契約不適合責任について、民法の規定(買主の権利や通知期間)よりも買主に不利となる特約は、無効となる。
- 無効になった場合: 特約が無効になると、民法の原則(知った時から1年以内の通知など)が適用される。
例えば、以下のような特約は、買主に不利なので無効になります。
- 「売主は契約不適合責任を一切負わない」
- 「契約不適合責任の追及は、追完請求に限る」
- 「不適合の通知期間は、引渡しから6ヶ月以内とする」
- 「不適合の通知期間は、買主が知った時から半年以内とする」
唯一OKな「買主に有利な」特約とは?
じゃあ、どんな特約なら有効なのでしょうか? 宅建業法が認めているのは、民法のルールよりも買主にとって有利になる特約です。
具体的に、試験でよく問われるのは「通知期間」に関する特約です。
民法では「不適合を知った時から1年以内」の通知が必要でした。でも、「知った時」って、いつ知ったか証明するのが難しい場合もありますよね。
そこで、宅建業法では、通知期間のスタート地点を「知った時」ではなく「物件の引渡しの日」からカウントする特約について、以下のように定めています。
有効となる通知期間の特約
不適合を通知すべき期間を、「物件の引渡しの日から2年以上」とする特約。
これは、民法の「知った時から1年」よりも、買主さんにとっては期間が明確になり、かつ長くなる可能性があるので、有利な特約として認められているんです。
無効となる通知期間の特約
- 「引渡しの日から1年」とする特約 → 民法より不利になる可能性があるので無効
- 「引渡しの日から1年半」とする特約 → 2年未満なので無効

「引渡しから2年以上」ならOK! それより短い期間にするのは買主に不利だからダメ、ってことですね!
もし、無効な特約(例:「引渡しから1年」)を結んでしまった場合は、その特約が無効になり、代わりに民法の原則(=不適合を知った時から1年以内の通知)が適用されることになります。
(補足)住宅瑕疵担保履行法について
ちなみに、特に新築住宅の場合、もし売主の業者が倒産してしまって、欠陥が見つかっても修理費用などを払ってもらえなくなったら大変ですよね。
この問題に対応するために、「住宅瑕疵担保履行法(じゅうたくかしたんぽりこうほう)」という法律が別に定められています。
この法律によって、新築住宅を供給する宅建業者や建設業者は、万が一倒産した場合でも、契約不適合責任(特に主要構造部分や雨水の浸入を防ぐ部分の欠陥)をちゃんと果たせるように、保険への加入または保証金の供託といった資力確保措置を講じることが義務付けられています。
8種制限とは別の法律ですが、関連知識として頭の片隅に置いておくと良いでしょう。
まとめ
はい、お疲れ様でした! これで8種制限の全8項目(のうち、重要な後半4項目)の解説が終了しました! 今回の内容も盛りだくさんでしたね。
最後に、今回の重要ポイントをまとめておきましょう。
- 手付金等保全措置:
- 業者売主・買主非業者の場合、原則必要。
- 不要なのは、①所有権移転登記済み、②未完成物件で代金の5%以下かつ1000万円以下、③完成物件で代金の10%以下かつ1000万円以下のとき。
- 方法は銀行保証、保険(完成・未完成OK)、指定保管機関(完成のみOK)の3つ。
- 割賦販売の制限:
- 業者売主の場合、支払遅延があっても30日以上の期間を定めて書面で催告しないと、解除や一括請求はできない(不利な特約は無効)。
- 原則、引渡しまでに所有権移転登記が必要(所有権留保禁止)。例外は受領額が代金の3/10以下等の場合。
- 契約不適合責任の特約制限:
- 業者売主・買主非業者の場合、民法より買主に不利な特約は無効。
- 通知期間を「引渡しから2年以上」とする特約は有効。それより短い特約は無効(無効なら民法の原則へ)。
8種制限は、一見複雑に見えますが、すべて「弱い立場にある買主さんを保護する」という共通の目的を持っています。その視点から各ルールを見直すと、なぜこのような制限が設けられているのか、より深く理解できるはずです。
試験では、細かい数字や条件、適用される契約の種類(誰が売主で、誰が買主か)などが問われやすいので、しっかり整理して覚えてくださいね。

8種制限、完全マスターできましたか? ここを乗り越えれば、宅建業法のかなりの部分を攻略できたも同然ですよ!自信を持ってくださいね!

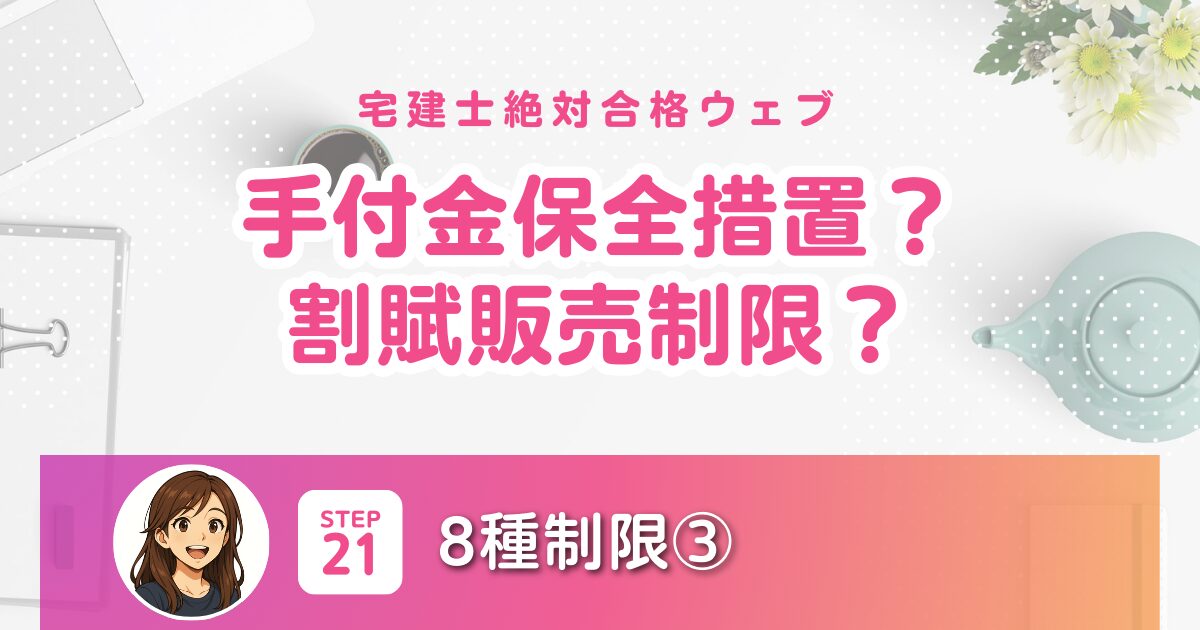
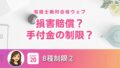
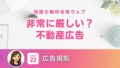
手付金等の保全措置(宅建業法第41条、第41条の2)