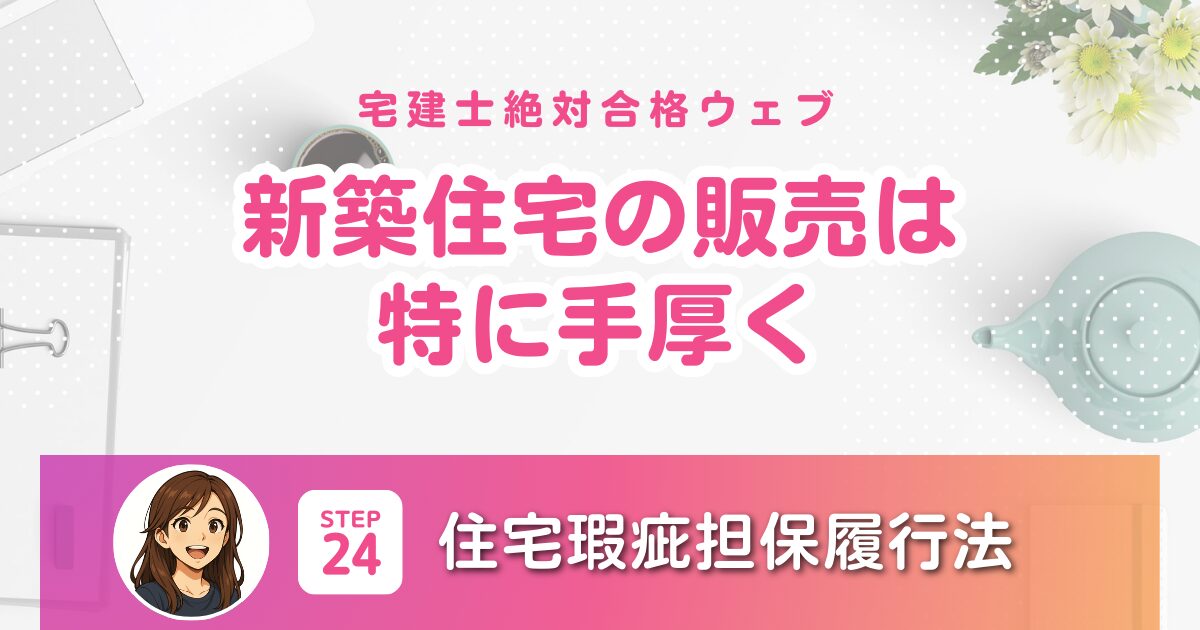今回は少し名前が長くて難しそうな法律、「住宅瑕疵担保履行法(じゅうたくかしたんぽりこうほう)」について取り上げます!「瑕疵(かし)」って言葉、もうすっかりお馴染みになりましたか? そう、欠陥のことですね。ピカピカの新築住宅を買ったのに、住み始めてすぐに雨漏りがしたり、基礎に問題が見つかったりしたら…本当にショックですよね。
しかも、もしその欠陥を直してもらおうと思ったら、売主の宅建業者さんや建設会社さんが倒産してしまっていた…なんてことになったら、修理費用は誰が負担してくれるの? 泣き寝入りするしかないの? って、ものすごく不安になりませんか?
そんな、新築住宅を買った買主さんの「万が一の不安」を解消するために作られたのが、この住宅瑕疵担保履行法なんです! この法律があるおかげで、新築住宅の特に重要な部分については、売主さん(宅建業者や建設業者)は10年間の責任を負うことが義務付けられ、さらに、その責任をちゃんとお金で果たせるように資力(お金の力)を確保しておく仕組み(保証金の供託 or 保険への加入)が整えられているんですよ。
この記事では、そんな買主さんの強い味方である「住宅瑕疵担保履行法」について、
- そもそも、新築住宅のどんな欠陥について、どれくらいの期間、売主は責任を負うの?(品確法との関連も!)
- その責任を果たすためのお金の準備、「資力確保措置」って具体的にどういうこと?(保証金と保険、どっち?)
という2つの大きなポイントを中心に、誰が、いつまでに、何をしないといけないのか、試験で問われる重要知識をギュッと凝縮して解説していきます!
この法律の対象となる住宅や取引の範囲、保証金や保険の細かいルール、買主さんへの説明義務など、ややこしい部分もしっかり整理できますよ。

さあ、住宅瑕疵担保履行法をマスターして、安心して取引できる知識と、試験での得点力を身につけましょう!
<この記事でわかること>
- 新築住宅の特に重要な部分に対する売主の10年間の瑕疵担保責任(品確法の特例)
- 住宅瑕疵担保履行法がなぜ必要なのか?(資力確保の重要性)
- 資力確保措置(保証金供託 or 保険加入)の対象となる業者、住宅、取引
- 保証金供託のルール(届出期限、ペナルティなど)
- 瑕疵担保責任保険の加入要件(保険金額、期間など)
【10年保証が義務!】新築住宅の重要部分に関する売主の特別な責任(品確法との連携プレー!)
まず、住宅瑕疵担保履行法を理解する上で、前提となる大事なルールがあります。それは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」で定められている、新築住宅の売主の特別な瑕疵担保責任です。
品確法による新築住宅の瑕疵担保責任の特例
- 対象となる住宅:新築住宅
- ※「新築住宅」とは? → 建設工事の完了日から1年以内で、かつ、まだ人が住んだことのない住宅のこと。
- 対象となる部分: 住宅の中でも特に重要な部分!
- 構造耐力上主要な部分: 建物の骨組みにあたる部分(例:基礎、柱、はり、壁、床版、土台など)
- 雨水の浸入を防止する部分: 雨漏りを防ぐための部分(例:屋根、外壁、窓などの開口部)
- 責任期間: これらの部分に瑕疵(欠陥)が見つかった場合、売主(や請負人)は、物件の引渡しから10年間、その責任を負わなければならない!
- 買主の権利: 買主は、売主に対して、契約解除(※目的達成不可の場合)、損害賠償請求、修補請求(修理の要求)ができる。
- 特約の制限: この10年間の責任期間を短くするような、買主に不利な特約は無効!
- 無過失責任: 売主に過失(落ち度)がなくても、責任を負わなければならない!
通常の不動産(中古住宅など)の場合、契約不適合責任の通知期間について「引渡しから2年以上」とする特約は有効でしたが、新築住宅のこの重要部分に関しては、法律で最低10年間の責任がガッチリ義務付けられている、というわけです。これは、買主さんにとっては非常に心強いルールですよね!

新築住宅の骨組みや雨漏りに関する部分は、特別に手厚く保護されているんですね!
【倒産しても大丈夫?】買主を守る!資力確保措置(保証金供託 or 保険加入)の仕組み
品確法で10年間の責任が定められたのは良いのですが、ここで冒頭の疑問に戻ります。「もし、その10年の間に、売主の業者さんが倒産してしまったら…?」
せっかく法律で責任が定められていても、責任を負うべき相手がいなくなってしまったり、お金がなくて修理や賠償ができなかったりしたら、意味がありませんよね。
そこで登場するのが、今回のメインテーマ、「住宅瑕疵担保履行法」です!
この法律は、品確法で定められた10年間の瑕疵担保責任を、売主(宅建業者や建設業者)が確実にお金で果たせるように、あらかじめ資力(お金)を確保しておくことを義務付けるための法律なんです。
<住宅瑕疵担保履行法による資力確保措置>
- 目的: 新築住宅の売主(宅建業者・建設業者)に、品確法上の10年間の瑕疵担保責任を履行するための資力を確保させ、買主を保護すること。
- 誰が措置を講じる?(対象者)
- 新築住宅を販売する宅地建物取引業者
- 新築住宅を建設する建設業者
- どんな住宅が対象?(対象物)
- 新築住宅のみ(品確法と同じ定義:完成後1年以内&未入居)
- ※事務所や店舗など、住宅以外の建物は対象外。
- どんな取引が対象?(対象取引)
- 宅建業者が自ら売主となり、宅建業者でない者(一般消費者など)が買主となる新築住宅の売買契約
- (建設業者が注文者に新築住宅を引き渡す請負契約も対象ですが、宅建試験では主に売買のケースが問われます)
- ※宅建業者が賃貸する場合や、売買を媒介(仲介)・代理するだけの場合は、この法律に基づく資力確保措置の義務は負いません。
- どうやって資力を確保する?(措置の内容) 以下のいずれかの方法を選択!
- 住宅販売瑕疵担保保証金(かし たんぽ ほしょうきん)を供託する
- 住宅瑕疵担保責任保険に加入する

お金を法務局に預けておく(供託)か、専門の保険に入るか、どっちかの方法で「もしもの時のお金」を準備しておきなさい!ってことですね。
買主への説明義務も忘れずに!
宅建業者は、この資力確保措置について、買主さんにちゃんと説明する義務があります。
- いつまでに? → 売買契約を締結するまでに。
- どうやって? → 措置の内容(供託なのか保険なのか、供託所の場所や保険法人の名称など)を記載した書面を交付して説明する。
- 誰が説明する? → この説明は、宅地建物取引士でなくてもOKです。(重要事項説明とは少し違うので注意!)
方法①:住宅販売瑕疵担保保証金の供託
まず、保証金を供託する方法について詳しく見てみましょう。
<保証金の供託ルール>
- 誰が供託する? → 売主である宅建業者
- どこに供託する? → 主たる事務所(本店)のもよりの供託所(法務局など)
- いくら供託する? → 基準日(毎年3月31日)から遡って過去10年間に引き渡した新築住宅の供給戸数に応じて、政令で定められた計算方法で算出された額。
(※具体的な計算式まで覚える必要はありませんが、「供給戸数に応じて額が決まる」と覚えておきましょう!) - いつまでに届け出る? → 毎年1回、基準日(3月31日)から3週間以内に、「保証金をちゃんと供託してますよ」という内容を、免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事(免許権者)に届け出なければならない。
- もし届け出なかったら?(ペナルティ) → 届け出をしなかった場合、その基準日の翌日から起算して50日を経過した日以降は、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することができなくなってしまいます! これは厳しい措置ですね!

毎年ちゃんと供託して、そのことを免許権者に報告しないと、新しい新築住宅を売れなくなっちゃうんですね!
方法②:住宅瑕疵担保責任保険への加入
もう一つの方法が、保険への加入です。こちらを選択する業者さんの方が多いかもしれません。
保険加入のルール
- どんな保険? → 国土交通大臣が指定した住宅瑕疵担保責任保険法人と、住宅瑕疵担保責任保険契約を締結する。
- メリット: この保険に加入すれば、上記の保証金の供託は不要になります。
- 保険証券の交付: 宅建業者は、保険契約を締結したら、その保険証券またはそれに代わる書面を買主に交付しなければなりません。
- 保険契約の主な要件: 加入する保険は、どんな内容でも良いわけではなく、ちゃんと買主が保護されるように、以下のような要件を満たす必要があります。
- 保険料: 売主である宅建業者(または建設業者)が支払うこと。
- 保険金額: 欠陥の修補費用などをカバーするため、2,000万円以上であること。
- 保険期間: 新築住宅の引渡しから10年以上有効であること(品確法の責任期間と対応)。
- 変更・解除の制限: 国土交通大臣の承認を受けた場合を除き、保険契約を勝手に変更したり、解除したりできないこと。
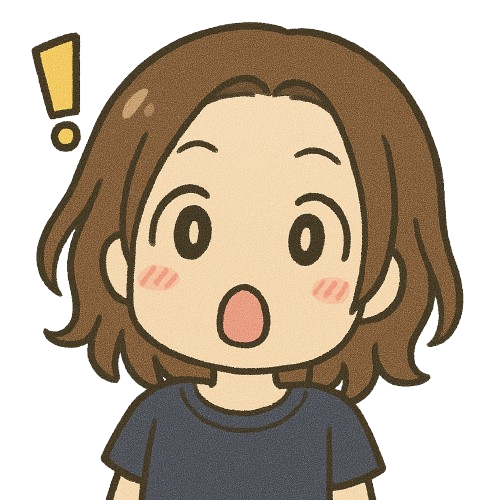
保険に入っておけば、万が一、売主の業者が倒産しても、保険法人が修補費用などを支払ってくれるので、買主さんは安心、というわけですね!
まとめ
お疲れ様でした! 今回は、「住宅瑕疵担保履行法」という、新築住宅の買主さんを守るための重要な法律について学びました。
ポイントを整理すると…
- 品確法により、新築住宅の構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分については、引渡しから10年間の瑕疵担保責任が売主に義務付けられている。
- 住宅瑕疵担保履行法は、上記の10年間の責任を売主が確実に果たせるように、資力確保措置を義務付ける法律である。
- 資力確保措置の対象は、宅建業者や建設業者が、自ら売主(または請負人)となる新築住宅の取引(買主が非業者の場合)。
- 資力確保の方法は、「住宅販売瑕疵担保保証金の供託」または「住宅瑕疵担保責任保険への加入」のいずれかを選択。
- 宅建業者は、契約締結までに、どちらの措置を講じているかを書面で買主に説明する必要がある(説明者は宅建士でなくてOK)。
- 保証金供託の場合は、毎年基準日(3/31)から3週間以内に免許権者へ届け出る必要があり、怠ると新規契約ができなくなるペナルティがある。
- 保険加入の場合は、保険金額2,000万円以上、保険期間10年以上などの要件を満たす必要がある。
この法律のおかげで、私たちは安心して新築住宅を購入しやすくなりました。宅建士としては、この法律の内容を正確に理解し、買主さんにきちんと説明できるようにしておくことが非常に重要です。試験でも頻出のテーマですので、しっかり復習しておきましょう!

これで、瑕疵担保責任に関するルールは、宅建業法、民法、品確法、そして住宅瑕疵担保履行法と、かなり深く理解できたのではないでしょうか! 自信を持って問題に取り組んでくださいね!