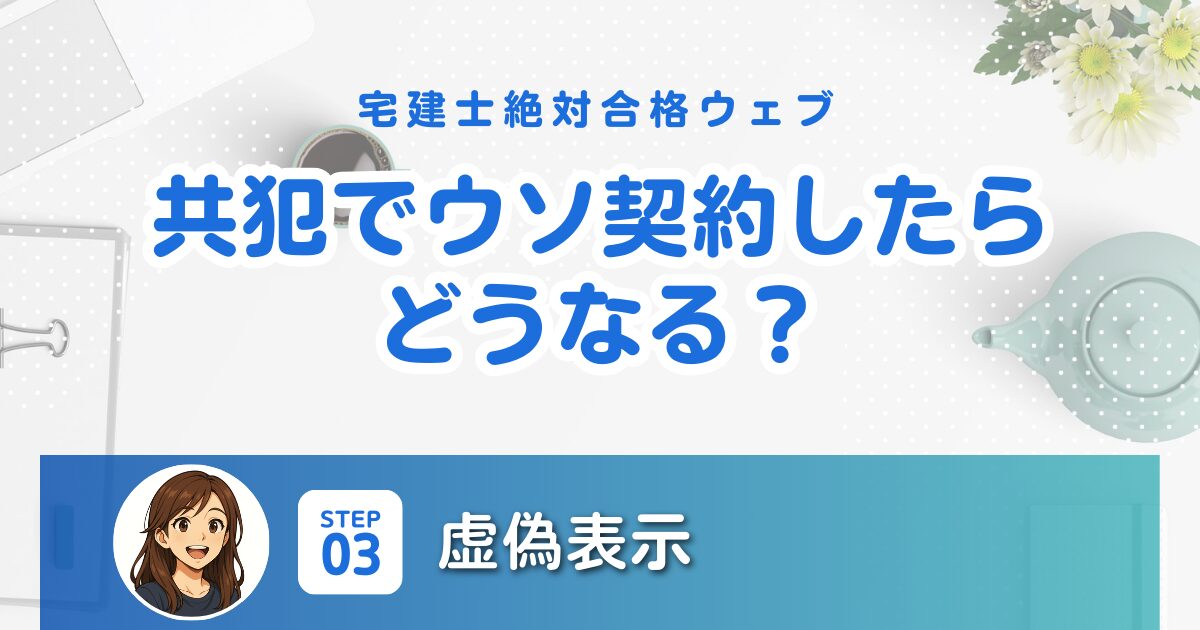前回は「心裡留保(しんりりゅうほ)」、つまり一人でする冗談や嘘の意思表示について学びましたね。今回はその兄弟分(?)とも言える「虚偽表示(きょぎひょうじ)」について見ていきましょう!
「虚偽」って言葉から、これも嘘が関係するんだな~って想像できますよね。でも、心裡留保とはちょっと違うんです。日常生活で例えるなら、友達と「ねえねえ、〇〇したことにしておこうよ!」みたいに、口裏を合わせるような場面、想像できますか?
もし、法律の世界で、そんな風に相手とグルになって、本当は違うのに契約したフリをしたら、その契約はどうなるんでしょう? 例えば、借金の取り立てから逃れるために、自分の大事な土地を友達に売ったフリをするとか…。これはさすがに許されない気がしますよね?
今回は、そんな「虚偽表示(きょぎひょうじ)」、別名「通謀虚偽表示(つうぼうきょぎひょうじ)」について、基本から応用まで徹底的に解説します! 心裡留保との違い、当事者間の効力、そして一番ややこしい善意の第三者や、さらにその先に出てくる転得者(てんとくしゃ)との関係まで、具体例や図をたっぷり使って、分かりやすく説明していきますね。

虚偽表示は、宅建試験の意思表示分野の中でも超ド級の重要テーマです! ここをしっかりマスターすれば、複雑な権利関係の問題も怖くなくなりますし、民法の得点力アップに直結しますよ。一緒に虚偽表示を完全攻略しちゃいましょう!
- 「虚偽表示(通謀虚偽表示)」の正確な意味と、心裡留保との決定的な違い
- 虚偽表示が当事者間では「常に無効」とされるシンプルな理由
- なぜ「善意の第三者」は、虚偽表示という嘘の取引から手厚く保護されるのか
- 第三者からさらに権利を買った「転得者」が登場した場合の権利関係のルール
- 民法94条(虚偽表示)の条文ポイントと、実際の宅建試験での問われ方
相手とグルになって嘘の契約!?「虚偽表示(通謀虚偽表示)」の基本をマスターしよう
まずは「虚偽表示」とは何なのか、基本的なところから押さえていきましょう。心裡留保との違いを意識すると、理解が深まりますよ!
「虚偽表示」ってどんな意味?心裡留保との違いは?
虚偽表示(きょぎひょうじ)とは、相手方と通じ合って(グルになって)、嘘の意思表示をすることです。「通謀虚偽表示(つうぼうきょぎひょうじ)」の「通謀」は、「互いに示し合わせて、悪だくみをすること」みたいな意味ですね。
- 虚偽の意思表示:心裡留保と同じく、真意(本当の気持ち)とは違う、嘘の意思表示があること。(例:本当は売る気がないのに「売る」と言う)
- 相手方との通謀:ここが心裡留保との決定的な違い! 意思表示をする本人だけでなく、相手方もその嘘を知っていて、協力(合意)していること。
心裡留保と虚偽表示の比較表
| 項目 | 心裡留保 | 虚偽表示(通謀虚偽表示) |
|---|---|---|
| 嘘をつく人 | 表意者のみ(単独犯) | 表意者と相手方(共犯) |
| 相手方の認識 | 嘘を知らない場合も、知っている場合もある | 必ず嘘だと知っていて、通じ合っている |
| キーワード | 冗談、嘘(単独) | 通謀、仮装(グルになって嘘をつく) |
| 条文 | 民法93条 | 民法94条 |
心裡留保は、言うなれば「一人でする嘘」。それに対して虚偽表示は、「二人でする嘘」、つまり共犯関係なんです。この「通謀」があるかないかが、両者を分ける大きなポイントですよ!

「通謀」って言葉がポイントですね! 相手とグルになってるかどうか、で見分けるんですね!
どんな時に成立する?虚偽表示の2つの成立要件
虚偽表示が成立するためには、法律的に次の2つの要件が必要です。
- 内心の真意と表示が食い違っている「虚偽の意思表示」が存在すること
- これは心裡留保と同じですね。例えば、売る気がないのに「売る」と言う、など。
- 表意者と相手方が「通謀」していること
- つまり、表意者が嘘の意思表示をすることを、相手方も認識し、それに合意(協力)していること。「よし、そういうことにしておこう!」という双方の意思の合致がある状態です。
この2つが揃って初めて、「虚偽表示」として扱われます。
【超重要】当事者間では「常に無効」!その理由とは?
さて、虚偽表示の効果はどうなるのでしょうか?
前回やった心裡留保は、相手方が善意無過失なら「有効」になる、という原則がありましたよね。
しかし、虚偽表示は違います!虚偽表示による意思表示は、当事者間(嘘をついた本人Aと、それに協力した相手方Bの間)では、「常に」「無効」です!
虚偽表示は当事者間では常に無効!
理由はとってもシンプル。だって、二人とも嘘だと分かってて、グルになってやってるんですから! 誰もその嘘の表示を信じていないし、その嘘の契約を法的に保護する必要なんて全くないですよね?
むしろ、そんな嘘の契約を有効にするわけにはいきません。だから、当事者間では問答無用で「無効」なんです。
心裡留保のように、「相手方が善意無過失なら有効」みたいな例外はありません。虚偽表示=当事者間では無効! と、スッキリ覚えちゃいましょう!
税金逃れの「仮装譲渡」とは?
虚偽表示の典型的な例としてよく挙げられるのが「仮装譲渡(かそうじょうと)」です。これは、本当は売買する意思がないのに、売買があったかのように見せかける(仮装する)ことです。
【具体例】
Aさんは事業に失敗して多額の借金を抱え、税金も滞納しています。このままだと、唯一の財産である自宅の土地が、債権者や市から差押えを受けてしまうかもしれません。
困ったAさんは、親友のBさんに相談し、「一時的に土地の名義だけ君に移させてくれないか?差押えを逃れるためなんだ。ほとぼりが冷めたらちゃんと返すから!」と持ちかけました。Bさんは事情を理解し、「分かった、協力するよ」と同意しました。
そして、AさんとBさんは売買契約書を作成し、登記(不動産の権利者を記録するもの)もAさんからBさんに移しました。でも、実際には代金の支払いはなく、Aさんはそのまま土地に住み続けています。
このAさんとBさんの間の土地の売買契約は、まさに虚偽表示(通謀虚偽表示)です。
- Aさん:本当は売る気がない(真意)のに、「売る」という表示をしている。
- Bさん:Aさんが売る気がないことを知りながら、売買に協力(通謀)している。
したがって、このA・B間の売買契約は、当事者間では「無効」となります。登記がBさんに移っていても、法律上は依然としてAさんの土地のまま、ということですね。
民法94条1項を確認!条文で見る当事者間のルール
この当事者間「無効」のルールも、民法の条文で確認しておきましょう。
(虚偽表示)
第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
すごく短いですが、これが虚偽表示の基本ルールです。「相手方と通じてした(=通謀した)」「虚偽の意思表示」は「無効」ですよ、と明確に書かれていますね。これが第1項の内容です。
第三者や転得者が登場!誰が保護される?権利関係を徹底解説!
虚偽表示がやっかいなのは、当事者だけで話が終わらない場合があるからです。
さっきの仮装譲渡の例で、土地の名義を持っているBさんが、悪いことを考えて、その土地を事情を知らないCさんに本当に売ってしまったら…?
A・B間の契約は無効なんだから、Aさんが「その土地は本当は俺のものだ!」ってCさんから取り返せるんでしょうか? それとも、何も知らずに買ったCさんが保護されるんでしょうか?
事情を知らない第三者は守られる!「善意の第三者」保護のルール (民法94条2項)
結論から言うと、ここでも「善意の第三者」が保護されます!これは、心裡留保の時と同じ考え方ですね。民法94条の第2項を見てみましょう。
(虚偽表示)
第九十四条 …(第1項は省略)…
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
はい、出ました! 「善意の第三者に対抗することができない」!
これは、
- A・B間の虚偽表示(仮装譲渡)は無効だよ(第1項)。
- でも、その無効という事実を、善意の第三者Cさんに対しては主張できないよ(対抗できないよ)、という意味です。
つまり、Cさんが善意(A・B間の売買が嘘(虚偽表示)だと知らなかった)であれば、AさんはCさんに対して「あの契約は無効だから土地を返せ!」とは言えないんです。結果として、Cさんが土地の所有権を確定的に取得することになります。
なぜ善意の第三者が保護されるの?(心裡留保との共通点)
理由は心裡留保の時と同じです。
- 取引の安全の保護:Cさんは、登記名義人であるBさんを信じて取引に入ったわけですよね。後から「あれは嘘でした」と言われて権利を失うのでは、安心して取引できません。善意のCさんを保護することで、世の中の取引の信用を守る必要があります。
- 嘘をついた側の責任(帰責性):そもそも、こんな問題が起きたのは、最初にAさんとBさんがグルになって嘘の表示(仮装譲渡)をしたからです。嘘の外観(Bさんが所有者であるかのような見た目)を作り出したAさんには、責任がありますよね。その嘘を信じた善意のCさんよりも、原因を作ったAさんの方が保護の必要性は低い、と考えられるわけです。

やっぱり、嘘をついた側より、何も知らずに信じた側を守ろう、ということですね。
第三者の保護に「無過失」や「登記」は必要?
ここで超重要なポイント!心裡留保の相手方が保護されるためには「善意無過失」が必要でしたよね?しかし、虚偽表示における第三者が保護されるためには、「善意」であれば十分で、「無過失」までは要求されません!
つまり、Cさんが事情を知らなかった(善意)のであれば、たとえ「ちょっと注意すれば気づけたかもね(過失あり)」という場合でも、Cさんは保護されるんです。
さらに! 第三者Cさんが、土地の登記を備えている必要もありません!
CさんがBさんから土地を買う契約をした時点で、Cさんが善意でありさえすれば、登記がまだBさんのままでも、あるいはAさんのままでも、CさんはAさんに対して「この土地は私のものです!」と主張できるんです。
<チェック> 虚偽表示における善意の第三者保護の要件
- 善意:必要! (A・B間の虚偽表示を知らないこと)
- 無過失:不要! (過失があっても善意ならOK)
- 登記:不要! (登記がなくても善意ならOK)
これは試験でめちゃくちゃ狙われます! 心裡留保の相手方保護(善意無過失が必要)と混同しないように、しっかり区別して覚えてくださいね!
「転得者」が登場したらどうなる?
話はまだ終わりません…! 今度は、第三者Cさんから、さらに土地を買った人、「転得者(てんとくしゃ)」Dさんが登場したらどうなるでしょうか?
A→(仮装譲渡:無効)→B→(転売)→C→(さらに転売)→転得者D
この場合、DさんがAさんに対して土地の所有権を主張できるかどうかは、間のCさんが善意だったか悪意だったかで場合分けして考える必要があります。
ケース1:第三者Cが「善意」の場合 → 転得者Dの善意・悪意は関係ない!
まず、間のCさんが善意だった場合です。
Cさんが善意であれば、その時点でCさんはAさんに対して完全に保護され、確定的に土地の所有権を取得しますよね。(民法94条2項)
ということは、Cさんは正当な権利者として、その土地を誰に売ろうが自由です。
したがって、Cさんから土地を買った転得者Dさんは、たとえDさん自身が悪意(A・B間の虚偽表示の事実を知っていた)だとしても、有効に所有権を取得できます!
これを「絶対的構成(ぜったいてきこうせい)」なんて言ったりします。一度、善意の第三者Cが現れて権利関係が確定したら、それ以降の人(転得者D)は、前の人(C)の権利をそのまま引き継ぐので、Dさん自身の善意・悪意は関係なくなる、という考え方です。
ケース2:第三者Cが「悪意」の場合 → 転得者Dが「善意」なら保護される!
次に、間のCさんが悪意(A・B間の虚偽表示を知っていた)だった場合です。
Cさんが悪意なら、Cさんは民法94条2項では保護されません。AさんはCさんに対して無効を主張できます。では、その悪意のCさんから土地を買った転得者Dさんはどうなるでしょう?
ここで判例は、転得者Dさんも民法94条2項の「第三者」に含まれると考えています。つまり、たとえ間のCさんが悪意であっても、転得者Dさん自身が「善意」であれば、Dさんは保護されるんです! Aさんは善意の転得者Dさんに対して、無効を主張できません。
逆に、転得者Dさんも悪意であれば、もちろん保護されません。この場合は、AさんはDさんに対して無効を主張できます。
<ポイント>
- Cが悪意でも、Dが善意 → Dは保護される! (AはDに対抗できない)
- Cが悪意で、かつDも悪意 → Dは保護されない (AはDに対抗できる)
まとめ
今回は、相手とグルになって嘘の契約をする「虚偽表示(通謀虚偽表示)」について、詳しく解説してきました。
虚偽表示とは、「相手方と通謀して(グルになって)する嘘の意思表示」のことでした。心裡留保(単独犯)との大きな違いは「通謀」がある点です。
そして、その効果は…
- 当事者間(A・B間):嘘だとお互い分かっているので、常に無効!
- 第三者(C)との関係:
- 第三者Cが善意であれば、たとえA・B間が無効でも、Cさんが保護される(AはCに無効を対抗できない)。
- この第三者保護には、無過失も登記も不要!「善意」だけでOK!
- 転得者(D)との関係:
- 間のCが善意なら、転得者Dは善意・悪意問わず保護される。
- 間のCが悪意でも、転得者Dが善意なら、Dは保護される。
虚偽表示は、心裡留保と並んで意思表示の基本であり、宅建試験でも頻出の超重要論点です。「当事者間は無効、でも善意の第三者は手厚く保護」という基本構造と、転得者が絡んだ場合のルールをしっかりマスターしてくださいね!

権利関係が複雑に見えても、一つひとつ登場人物の関係性を整理していけば必ず解けます! 諦めずに頑張っていきましょう!