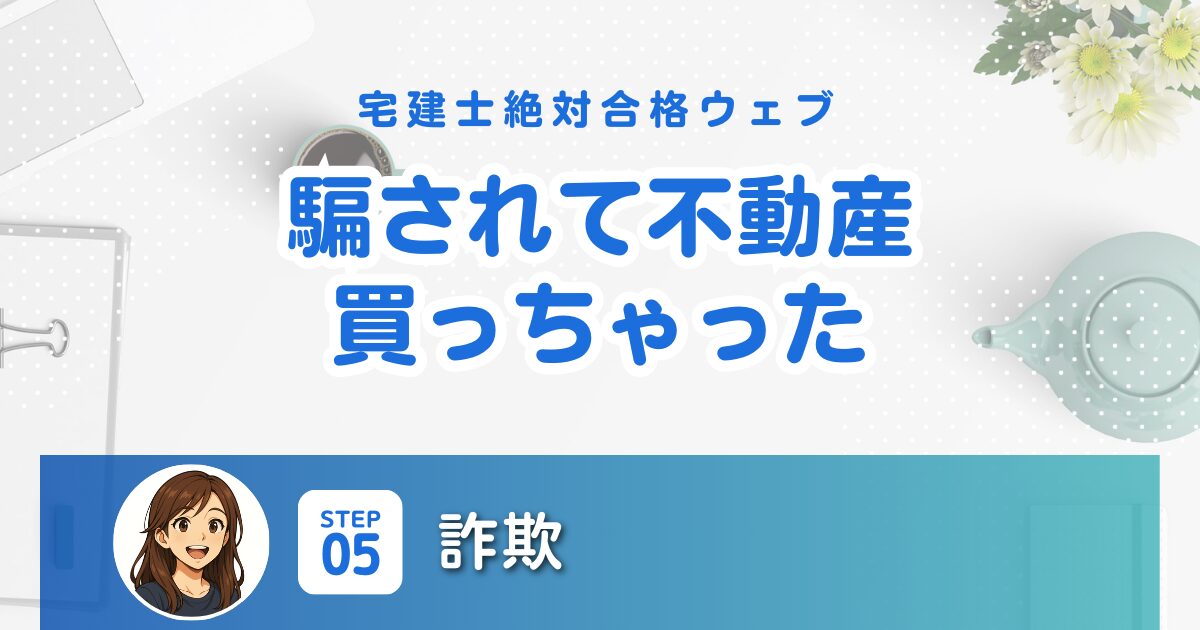今回のテーマは「詐欺」です。「詐欺って、ニュースとかではよく聞くけど、法律的にはどういう扱いになるの?」「もし騙されて契約しちゃったら、その契約ってどうなるんだろう…?」なんて、気になったことはありませんか?
どんな場合に契約を取り消せるのか、いつまでならOKなのか、そして契約の相手方じゃない第三者が絡んできた場合や、騙された後にさらに別の人が関わってきた場合など、パターンがいくつかあって、ちょっと複雑に感じてしまうかもしれませんよね。
でも大丈夫!この記事では、民法における「詐欺」の基本的な意味から、契約を取り消せる効果、前回学んだ「錯誤」との違い、取消しができる期間、そして試験で特に狙われやすい「第三者詐欺」や「詐欺による取消しと第三者の関係」について、具体的なケースを挙げながら、一つひとつ丁寧に解きほぐしていきます。

この記事をしっかり読めば、詐欺に関する様々なルールが整理できて、自信を持って問題にチャレンジできるようになりますよ! 錯誤との違いも明確にして、知識を確実に定着させましょう!
<この記事でわかること>
- 民法でいう「詐欺」の正確な意味と契約への影響(取消し)
- 「詐欺」と「錯誤」、どこが根本的に違うのか?
- 詐欺による契約取消しはいつまでできる?(期間制限)
- 契約相手じゃない人から騙された場合のルール(第三者詐欺)
- 騙された契約を取り消す前と後で、第三者との関係はどう変わる?
「詐欺」とは何か?効果と錯誤との違いを理解しよう
まずは、「詐欺」という言葉の意味、そして詐欺があった場合に契約がどうなるのか、さらに前回学んだ「錯誤」との違いなど、基本的な部分をしっかり押さえていきましょう!
「詐欺」=相手をだますこと(欺罔行為)
民法でいう「詐欺」とは、簡単に言うと「相手をだますこと」です。少し難しい法律用語では「欺罔(ぎもう)」と言ったりもしますが、意味は同じです。
相手にウソをついたり、都合の悪い事実を隠したりして、相手を勘違いさせて、その結果、契約を結ばせるような行為を指します。
- 例: 本当は価値のない絵画を「有名な画家の真作で、将来必ず値上がりしますよ!」と偽って、高額で売りつける。

意図的に相手を陥れる、悪質な行為というイメージですね。
騙されて結んだ契約はどうなる?~原則有効、でも「取消し」できる!~
では、詐欺によって結ばれてしまった契約は、法律上どう扱われるのでしょうか?
これも「錯誤」の場合と同じく、詐欺による意思表示(契約)は、直ちに無効になるわけではありません。 一応、契約としては有効に成立します。
しかし、騙された人を保護するために、騙された人は後からその契約を「取り消す」ことができるとされています(民法96条1項)。
詐欺も錯誤と同じく「無効」ではなく「取消し」!
ここ、重要なのでしっかり覚えてくださいね! 詐欺の場合も、契約の効力を最初から無かったことにする「無効」ではなく、一旦有効に成立した契約の効力を後から失わせる「取消し」ができる、というルールになっています。
取り消すかどうかは、騙された本人が決めることができます。
(詐欺又は強迫)
民法第96条1項 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
【重要】詐欺と錯誤は何が違うの?~意思と表示の一致・不一致~
「錯誤」も「詐欺」も、どちらも「取消し」ができる、という点は同じです。では、この二つは何が根本的に違うのでしょうか?
それは、「心の中で思っていること(意思)」と「実際に表示したこと(表示)」が一致しているかどうか、という点にあります。
- 錯誤の場合(復習):
- 「表示の錯誤」では、「甲土地を買う」と思っているのに「乙土地を買う」と言ってしまうように、意思と表示が食い違っていましたよね。
- 「動機の錯誤」でも、動機に勘違いはあるものの、「買おう」という意思自体はあって表示しているので、意思と表示は一致していますが、その前提となる動機形成の部分での認識と真実の不一致が問題となります。ただ、民法改正前の判例法理では、表示されていなければ保護されにくいという側面がありました。改正民法では、動機が表示されていなくても、その事情が法律行為の基礎とされていることが客観的に認められれば取消しの対象となりうると整理されました(民法95条1項2号)。
- 詐欺の場合:
- 騙されてはいるものの、本人はその時点では納得して契約を結んでいます。
- 例えば、価値のない宝石を「これは希少な宝石ですよ」と騙されて買う場合でも、騙された人はその時点では「この(価値があると信じている)宝石を買おう」と思って、「買います」と表示しています。つまり、意思(内心で思っていること)と表示(実際に言ったこと・書いたこと)自体は一致しているんです。
- 問題なのは、その意思決定の過程に、相手の「だます行為(欺罔)」があった、という点です。

意思と表示がズレてるのが錯誤、ズレてないけど騙されてるのが詐欺、ってことですね!
<詐欺と錯誤の違い 比較表>
| 項目 | 錯誤(主に表示の錯誤) | 詐欺 |
|---|---|---|
| 意思と表示 | 不一致 (思っていることと違う表示) | 一致 (騙されているが、その時点では納得) |
| 問題点 | 表意者の内心と表示のズレ | 相手方の「だます行為(欺罔)」 |
| 効果 | 取消し可能(要件あり) | 取消し可能 |
| 保護の対象者 | 主に勘違いした人(表意者) | 主に騙された人 |
この違いは、根本的な部分なのでしっかり理解しておきましょう!
いつまで取り消せる?詐欺取消権の期間制限
詐欺による契約は取り消せると言っても、いつまでも永久に取り消せるわけではありません。法律関係を安定させるために、取消権を行使できる期間には制限が設けられています。
詐欺による取消権は、以下のいずれかの期間が経過すると、時効によって消滅してしまいます(民法126条)。
<詐欺取消権の期間制限>
- 追認(ついにん)をすることができる時から5年間 行使しないとき。
- 行為の時(契約を結んだ時)から20年間 経過したとき。
「追認」とは、「この契約、やっぱり有効なものとして認めます」と後から承認することです。
詐欺の場合、「騙されていたことに気づき、かつ、自分で自由に意思決定できる状況になってから」が、追認できる時と考えられます。
つまり、「騙されたことに気づいてから5年」と考えておくと分かりやすいでしょう。
<期間制限のポイント>
- 騙されたことに気づいてから5年
- 契約してから20年
どちらか早い方の期間が経過すると、もう取消しはできなくなってしまうので注意が必要です。
「第三者が関わる詐欺」のパターンとルール
さて、ここからが詐欺の論点で特に複雑になりやすく、試験でもよく問われる部分です。
「第三者」、つまり契約の当事者(騙した人・騙された人)以外の人 が関わってきた場合に、法律関係がどうなるのかを見ていきましょう。
主に2つのパターンがあります。
パターン1:契約の相手方「じゃない人」から詐欺を受けた場合(第三者詐欺)
これは、契約を結ぶ相手方(例えば売主)ではなく、全く関係のない第三者から騙されて、その結果、相手方と契約を結んでしまった、というケースです。これを「第三者詐欺」と言います。
【ケース】
買主Bさんが、不動産ブローカーCから「この土地(Aさん所有)は将来ものすごく値上がりするから買った方がいい!」と嘘の情報を吹き込まれました(Cによる詐欺)。
その話を信じたBさんは、事情を全く知らない売主Aさんと、その土地の売買契約を結びました。
C(詐欺をした第三者) → B(騙された人) → A(契約の相手方)
CがBを騙し、BがAと契約。BはAとの契約を取り消せる?
この場合、BさんはCに騙されたわけですが、契約の相手方はAさんです。Aさんは詐欺には一切関与していません。
こんな時、Bさんは「Cに騙されたから!」という理由で、Aさんとの契約を取り消せるのでしょうか?
ルール:相手方が善意無過失なら取り消せない!
民法は、このような第三者詐欺の場合、契約の相手方(上の例ではAさん)が、Bさんが第三者Cから詐欺を受けていたという事実について、どう認識していたかによって結論を分けています(民法96条2項)。
- 相手方Aが「善意無過失」の場合:
- つまり、Aさんが「BさんがCに騙されていること」を知らず(善意)、かつ、知らなかったことについて落ち度もなかった(無過失)場合。
- この場合は、相手方Aさんが保護されます。Bさんは、Aさんとの契約を詐欺を理由に取り消すことはできません。
- 何も悪くないAさんを守る、ということですね。
- 相手方Aが「悪意」または「有過失」の場合:
- つまり、Aさんが「BさんがCに騙されていること」を知っていた(悪意)場合、または、知らなくても注意すれば知ることができたはず(有過失)だった場合。
- この場合は、もはやAさんを保護する必要性は低いので、騙されたBさんが保護されます。Bさんは、Aさんとの契約を詐欺を理由に取り消すことができます。
(詐欺又は強迫)
民法第96条2項 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り(悪意)、又は知ることができたとき(有過失)に限り、その意思表示を取り消すことができる。
具体例で確認①:買主Bが第三者Cに騙されて売主Aから買った場合
(上記のケースと同じ)
- Aが善意無過失 → Bは取消しできない。Aが保護される。
- Aが悪意または有過失 → Bは取消しできる。Bが保護される。
具体例で確認②:売主Aが第三者Cに騙されて買主Bに売った場合
今度は逆のパターンです。
【ケース】
売主Aさんが、第三者Cから「その土地は近々価値が暴落するから、早く手放した方がいい」と嘘をつかれました(Cによる詐欺)。
それを信じたAさんは、相場より安い価格で、事情を知らない買主Bさんに土地を売却してしまいました。
この場合もルールは同じです。騙されたのはAさんですが、契約の相手方はBさんです。
- 買主Bが「AさんがCに騙されていること」について善意無過失の場合 → Aは取消しできない。Bが保護される。
- 買主Bが悪意または有過失の場合 → Aは取消しできる。Aが保護される。
第三者詐欺のポイント
- 騙された人は、契約の相手方が「悪意」または「有過失」の場合に限り、取消しを主張できる。
- 相手方が「善意無過失」の場合は、取り消せない(相手方が保護される)。
パターン2:騙された人が第三者に売っちゃった場合(詐欺取消しと第三者)
次は、詐欺によって一旦契約が成立し、その後、騙した(または騙された)当事者から、さらに別の第三者に物が転売されたようなケースです。
この場合、騙された人が後から契約を取り消したときに、その第三者との関係がどうなるのかが問題になります。
これは、第三者が登場したタイミング(取消しの前か後か)によって、結論が変わってくるので注意が必要です!
状況設定:AがBに騙されて売却 → BがCに転売 → Aが詐欺に気づき取消し
まずは、基本的な状況設定を確認しましょう。
- Aさん(売主)が、Bさん(買主)に騙されて、自分の土地をBに売却しました。(A-B間の売買契約)
- その後、Bさんは、その土地を(Aさんが騙されていたことを知らないかもしれない)Cさんに転売しました。(B-C間の売買契約)
- さらにその後、Aさんは自分がBに騙されていたことに気づき、A-B間の売買契約を詐欺を理由に取り消しました。
この状況で、元の所有者であるAさんと、Bから土地を買ったCさん、どちらが土地の所有権を最終的に主張できるのでしょうか?
(1) 取消し「前」に第三者Cが登場した場合
これは、Aさんが詐欺に気づいて契約を取り消す「前に」、BさんがすでにCさんに土地を転売していたケースです。
つまり、Cさんは「詐欺による取消し前の第三者」ということになります。
A(騙された人) —(詐欺による売却)→ B(騙した人) —(転売)→ C(第三者)
(この転売の後で、AがA-B間契約を取消し)
この場合のルールは、「錯誤」の場合の第三者保護のルールと基本的に同じです。
つまり、第三者Cが、AさんがBに騙されていたという事実について「善意」でかつ「無過失」であれば、Cさんが保護されます(民法96条3項)。
- 第三者Cが「善意無過失」の場合:
- Aさんは、詐欺による取消しをCさんに対抗(主張)できません。
- つまり、Cさんが土地の所有権を取得します。Aさんは土地を取り戻せません。
- ここでも、事情を知らない善意無過失のCさんを保護するんですね。
- 第三者Cが「悪意」または「有過失」の場合:
- Aさんは、詐欺による取消しをCさんに対抗(主張)できます。
- つまり、Aさんが土地の所有権を取り戻せます。
(詐欺又は強迫)
民法第96条3項 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
詐欺取消し「前」の第三者保護は、善意「かつ」無過失が必要、と覚えておきましょう。
(2) 取消し「後」に第三者Cが登場した場合
今度は、AさんがBとの契約を詐欺で取り消した「後に」、Bさんが(あたかもまだ自分の物であるかのように装って)Cさんに土地を転売したケースです。
つまり、Cさんは「詐欺による取消し後の第三者」ということになります。
A(騙された人) —(詐欺による売却)→ B(騙した人)
↓
AがA-B間契約を取消し(この時点で所有権はAに戻るはず)
↓
しかし、BがCに転売
この場合、Aさんが契約を取り消した時点で、法律上は土地の所有権はAさんに戻っているはずです。それなのに、Bさんが権利がないはずの土地をCさんに売却した、という状況になります。
これは、あたかもAさんとCさんが、Bという同じ人から二重に土地を買った(あるいは、Aさんの所有権とCさんの所有権が対立する)ような関係、つまり「二重譲渡」に似た関係になると考えられます。
そして、このような場合の優劣は、先に「対抗要件」を備えた方が勝つ、というルールで決着します。
不動産の場合の対抗要件は「登記」です。
- ルール:対抗要件(登記)を先に備えた方が勝つ!
- AさんとCさんのうち、先に自分の名前で所有権移転登記をした方が、相手に対して「この土地は私のものだ!」と主張できます。
- この場合、第三者Cさんが善意か悪意かは関係ありません。たとえCさんが「AさんがBとの契約を取り消したこと」を知っていた(悪意)としても、Aさんより先に登記を備えれば、Cさんが勝つことになります。

取消しの後だと、善意・悪意関係なく、早い者勝ち(登記した者勝ち)になるんですね!
取消しの前後で第三者との関係のルールが変わる点に注意!
- 取消し前: 第三者が善意無過失なら第三者の勝ち。
- 取消し後: 先に登記した方の勝ち(善意・悪意は問わない)。
この「取消し後の第三者」との関係(対抗要件の先後で決まる)は、「時効完成後の第三者」との関係と同じ考え方をするので、セットで覚えておくと効率的ですよ!
まとめ
今回は、宅建試験の重要テーマ「詐欺」について、基本的な意味から、取消しの効果、錯誤との違い、期間制限、そして複雑な第三者が関わるケースまで、詳しく解説してきました。
特に第三者が関わるパターンは、誰がどのタイミングで登場し、その人が善意なのか悪意なのか、無過失なのか有過失なのか、そして取消しの前なのか後なのか…といった点を正確に把握することが重要です。
最後に、今回の重要ポイントをまとめておきましょう。
- 詐欺とは?: 相手をだますこと(欺罔)。意思と表示は一致しているが、意思決定過程に瑕疵がある。
- 詐欺の効果: 契約は一旦有効だが、騙された人は「取消し」が可能(民法96条1項)。
- 取消権の期間制限: 追認できる時(≒詐欺を知った時)から5年、または行為の時(契約時)から20年のいずれか早い方(民法126条)。
- 第三者詐欺: 契約相手でない第三者に騙された場合、契約相手が悪意または有過失のときに限り、取消し可能(民法96条2項)。相手が善意無過失なら取消不可。
- 詐欺取消しと第三者:
- 取消し「前」の第三者: 第三者が善意かつ無過失であれば保護され、取消しを対抗できない(民法96条3項)。
- 取消し「後」の第三者: 対抗要件(登記)を先に備えた方が勝つ(二重譲渡類似)。第三者の善意・悪意は問わない。
詐欺の論点は、事例問題で出題されることも多いので、具体的なケースを想定しながら、誰が保護されるのかを判断する練習を繰り返すことが大切です。

この記事が、あなたの宅建合格への道を少しでも明るく照らすことができたら嬉しいです!ややこしい部分も、一つずつクリアしていきましょう!