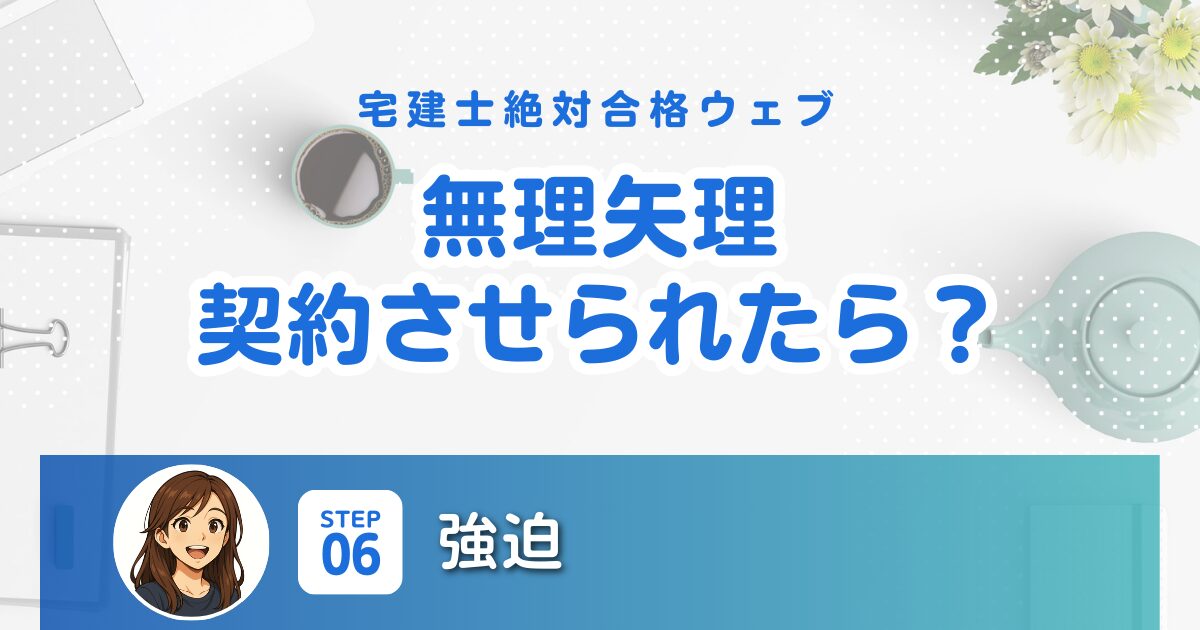前回は「詐欺」について学びましたが、今回はそれとセットでよく登場する「強迫」について解説していきますね!「強迫って、なんだか字面からして怖い感じ…」「もし脅されて無理やり契約させられたら、その契約ってどうなるの?」「詐欺と何が違うんだろう?」なんて、疑問に思ったことはありませんか?
第三者が関わってきた場合の扱いは、詐欺の場合と全く異なります。この違いをしっかり理解しておかないと、試験で思わぬ失点をしてしまうかも…!
そこでこの記事では、「強迫」の基本的な意味や契約を取り消せる効果はもちろん、一番大切な「詐欺との違い」、特に第三者が登場した場合のルールについて、比較しながら徹底的に解説していきます。なぜ強迫された人が詐欺の場合よりも手厚く保護されるのか、その理由までしっかり理解できるように説明しますね!

この記事を読めば、「強迫」に関するルールがスッキリ整理でき、詐欺との違いも明確になるので、権利関係の問題に対する自信がグッと深まりますよ!
この記事でわかること
- 民法でいう「強迫」の正確な意味と契約への効果(取消し)
- 意外と間違えやすい?「強迫」と「脅迫」の漢字の違い
- 「強迫」と「詐欺」の決定的な違い、特に第三者との関係におけるルールの差
- なぜ「強迫」された人は、「詐欺」の場合よりも手厚く保護されるのか?
- 第三者から強迫された場合や、取消し前の第三者との関係はどうなる?
「強迫」の基本をマスター!意味・効果と詐欺との共通点
まずは、「強迫」という言葉の意味や、強迫によってなされた契約がどうなるのか、基本的なところから見ていきましょう。詐欺との共通点もありますよ。
「強迫」とは?~相手を脅して怖がらせること~
民法でいう「強迫」とは、相手に対して害悪(危害や不利益)を加えることを告知して(つまり脅して)、相手を怖がらせること(畏怖させること)を言います。
- 例: BさんがAさんに対して、「この土地を安く売らないと、お前の家族に危害を加えるぞ!」と脅して、無理やり土地を安く買い取るような場合です。
漢字に注意!刑法の「脅迫」とは違う「強」の字!
ここで一つ、細かいですが注意点です。民法で使うのは「強迫」という字です。「脅す(おどす)」という字を使った刑法上の「脅迫罪」とは、使う漢字が違うんですね。宅建試験で記述式はありませんが、選択肢などで出てきたときに混乱しないように、頭の片隅に置いておくと良いかもしれません。
強迫された意思表示は「瑕疵ある意思表示」
強迫されて契約した場合、その人の意思表示はどう考えられるでしょうか?
例えば、上記の例で、AさんはBさんに脅されてはいますが、その場では「(怖くて仕方なく)土地を売ろう」と思って、「売ります」と表示しています。
この点では、「内心の意思(売りたい)」と「表示(売ります)」は、一応は一致していると考えることができます。この点は、詐欺の場合と同じですね。
しかし、その意思決定は、完全に自由な状態でなされたものではありません。相手からの不当な脅し(強迫)によって歪められています。
このように、意思表示の形成過程に問題があるものを「瑕疵(かし)ある意思表示」と言います。詐欺による意思表示も、強迫による意思表示も、この「瑕疵ある意思表示」にあたります。
完全に自由な意思決定ではない!
脅されて、怖くて仕方なく「イエス」と言わされている状態なので、真意に基づいた自由な意思決定とは言えませんよね。
強迫された契約の効果は?~詐欺と同じく「取消し」できる~
では、強迫によってなされた契約は、法律上どうなるのでしょうか?
これも詐欺の場合と同じで、強迫による意思表示(契約)は、直ちに無効になるわけではなく、一旦は有効ですが、後から「取り消す」ことができるとされています(民法96条1項)。
民法96条1項(詐欺又は強迫)
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
つまり、脅された人は、後から「あの契約は強迫によるものだったから、やっぱりやめます!」と主張して、契約の効力を失わせることができる、ということです。
ここまでは、詐欺と強迫は「取消しができる」という点で共通しています。しかし、この先、特に第三者が関わってきた場合のルールが大きく異なってくるのです!
「強迫」と「詐欺」の決定的な違いを比較解説!宅建試験の最重要ポイント!
ここからが今回の最重要ポイントです!「強迫」と「詐欺」、どちらも取り消せる点は同じですが、特に第三者との関係において、強迫された人の保護の度合いが、詐欺の場合よりも格段に手厚くなっています。この違いをしっかり理解することが、宅建試験攻略のカギとなります!
比較のために、まず詐欺の場合のルールを簡単におさらいしておきましょう。
おさらい:詐欺の場合のルール(第三者関連)
- 第三者詐欺の場合(契約相手じゃない人から騙された場合):
- 契約の相手方が善意無過失なら、騙された人は取り消せない(相手方が保護される)。
- 相手方が悪意または有過失なら、騙された人は取り消せる。
- 取消し「前」の第三者の場合(騙した人から転売などで取得した人):
- 第三者が善意無過失なら、その第三者は保護される(騙された人は対抗できない)。
- 第三者が悪意または有過失なら、保護されない(騙された人は対抗できる)。
詐欺の場合は、善意無過失の相手方や第三者を保護することで、「取引の安全」とのバランスを取っている、というイメージでしたね。
では、強迫の場合はどうなるのでしょうか? 驚きの違いがありますよ!
強迫の場合のルール①:第三者から強迫された場合(第三者強迫)
まず、契約の相手方ではない第三者から強迫を受けて、相手方と契約を結んでしまった「第三者強迫」のケースです。
【ケース】
Aさんが、第三者Cから「Bさんと土地の売買契約を結ばないと、ひどい目にあわすぞ!」と脅されました(Cによる強迫)。
怖くなったAさんは、事情を全く知らないBさんと、その土地の売買契約を結んでしまいました。
C(強迫した第三者) → A(強迫された人) → B(契約の相手方)
CがAを脅し、AがBと契約。AはBとの契約を取り消せる?
詐欺の場合は、相手方Bが善意無過失なら、Aは取り消せませんでしたよね。
しかし、強迫の場合は…
結論:相手方の善意・悪意に関係なく、常に取消しできる!
なんと、強迫の場合は、契約の相手方であるBさんが、AさんがCから脅されていることを知っていた(悪意)か、知らなかった(善意)か、知らなかったことに過失があった(有過失)かどうかにかかわらず、強迫されたAさんは常に契約を取り消すことができるのです!

これは大きな違いですね!詐欺の時みたいに、相手方が善意無過失でも関係ないんです。
たとえ相手方Bさんが全く事情を知らない(善意無過失)場合でも、強迫されたAさんの保護が優先される、ということです。
<比較表:第三者詐欺 vs 第三者強迫>
| ケース | 相手方の状態 | 取消しの可否 | 保護されるのは? |
| 第三者詐欺 | 善意無過失 | できない | 相手方 |
| 悪意または有過失 | できる | 騙された人(表意者) | |
| 第三者強迫 | 善意無過失 | できる | 強迫された人(表意者) |
| 悪意または有過失 | できる | 強迫された人(表意者) |
強迫の場合のルール②:取消し前の第三者との関係
次に、強迫によって契約が結ばれ、その後、強迫した(またはされた)人から、物が第三者に渡ってしまったケースです。これも、強迫された人が取消しを主張した場合、第三者との関係がどうなるかを見ていきます。
【ケース】
Aさんが、相手方Bさんから強迫されて、自分の土地をBに売却しました。
その後、Bさんは、その土地を(Aさんが脅されていたことを知らないかもしれない)Cさんに転売しました。
さらにその後、AさんはBとの契約を強迫を理由に取り消しました。
A(強迫された人) —(強迫による売却)→ B(強迫した人) —(転売)→ C(第三者)
(この転売の後で、AがA-B間契約を取消し)
詐欺の場合は、取消し前に登場した第三者Cが善意無過失であれば、Cさんが保護され、Aさんは土地を取り戻せませんでしたよね。
しかし、強迫の場合は、ここでも驚きの結論になります!
結論:第三者が善意無過失であっても、強迫された人は取消しを対抗できる!
なんと、強迫による取消しは、その後に登場した第三者Cさんが、たとえ善意無過失であったとしても、その効力を主張できるのです!
つまり、Aさんは、Cさんに対して「あの契約は強迫で取り消したのだから、土地を返してください!」と主張でき、土地を取り戻すことができるのです。

善意無過失の第三者よりも、強迫された人が優先されるんですね!
これは、民法96条3項が「詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない」と定めており、「強迫」についてはこの第三者保護規定の適用がない、と解釈されているためです。
<比較表:詐欺取消し前の第三者 vs 強迫取消し前の第三者>
| 取消しの原因 | 第三者の状態 | 取消しを対抗できるか? | 保護されるのは? |
| 詐欺 | 善意無過失 | できない | 第三者 |
| 悪意または有過失 | できる | 騙された人(表意者) | |
| 強迫 | 善意無過失 | できる | 強迫された人(表意者) |
| 悪意または有過失 | できる | 強迫された人(表意者) |
強迫の第三者関連ルールのまとめ
- 第三者強迫: 相手方の善意・悪意に関わらず、常に取消し可能。
- 取消し前の第三者: 第三者の善意・悪意・過失に関わらず、常に取消しを対抗可能。
つまり、強迫に関しては、常に強迫された本人が絶対的に保護される、と覚えてしまいましょう!
なぜ強迫はここまで手厚く保護されるの?
それにしても、なぜ強迫は、詐欺の場合と違って、善意無過失の相手方や第三者よりも、強迫された本人がここまで手厚く保護されるのでしょうか?
それには、以下のような理由があると考えられています。
- 意思決定の自由の侵害の度合いが大きい: 詐欺は、騙されてはいるものの、一応は自ら判断して意思表示をしています。しかし、強迫は、恐怖心によって意思決定の自由が完全に奪われている、あるいは極めて著しく制約されている状態です。この自由な意思決定を侵害する度合いが、詐欺よりも強迫の方がはるかに大きいと考えられます。
- 表意者(強迫された人)に落ち度(帰責性)がない: 詐欺の場合、騙された側にも「うっかり信じてしまった」という側面が全くないとは言えないかもしれません(もちろん、騙す方が悪いのは大前提ですが)。しかし、強迫の場合は、一方的に脅されている被害者であり、本人には何の落ち度もありません。保護されるべき度合いが高いと言えます。
- 取引の安全よりも、表意者の保護を優先: 民法は、個人の権利保護と、円滑な取引社会の維持(取引の安全)のバランスを常に考えています。詐欺の場合は、善意無過失の第三者を保護することで、取引の安全にも配慮しています。しかし、強迫という極めて悪質な行為に対しては、取引の安全を多少犠牲にしてでも、強迫された被害者の救済を最優先すべきである、という価値判断が働いていると考えられます。
まとめ
今回は、「強迫」について、その意味や効果、そして特に「詐欺」との決定的な違いに焦点を当てて解説しました。
第三者が関わる場面でのルールの違いは、本当に重要なので、しっかり整理して覚えてくださいね!
最後に、今回の最重要ポイントをまとめます。
- 強迫とは?: 相手を脅して怖がらせること。意思表示の形成過程に瑕疵がある。
- 強迫の効果: 契約は一旦有効だが、「取消し」が可能(民法96条1項)。
- 強迫と詐欺の決定的な違い:
- 第三者強迫: 詐欺と違い、契約の相手方が善意無過失であっても、常に取消し可能。
- 取消し前の第三者: 詐欺と違い、第三者が善意無過失であっても、常に取消しを対抗可能。
- 保護の優先順位: 強迫の場合は、常に強迫された本人が絶対的に保護される。取引の安全よりも表意者の保護が優先される。
- 保護の理由: 意思決定の自由の侵害度合いが極めて大きく、表意者に落ち度がないため。
詐欺と強迫は、セットで比較しながら学習することで、それぞれの特徴や違いがより明確になります。宅建試験では、この違いを突いた問題がよく出題されるので、今日の記事の内容をしっかり復習して、得点源にしてくださいね!

ややこしい権利関係も、一つずつ理解を深めていけば大丈夫!