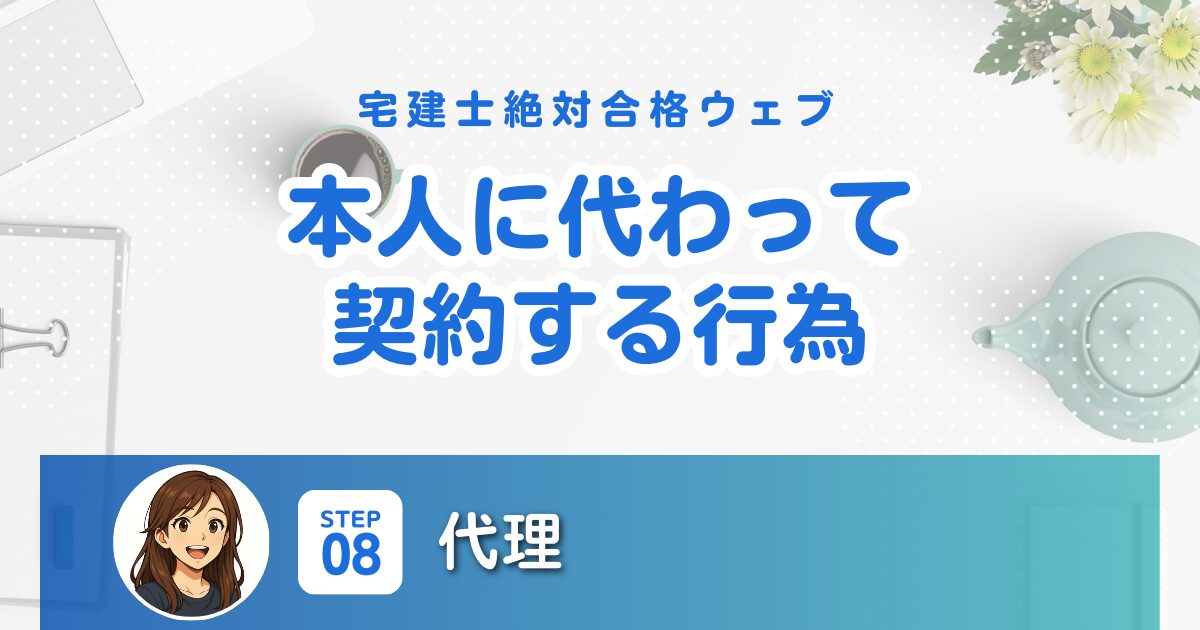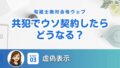権利関係の分野には、日常生活ではあまり使わない専門用語がたくさん出てきますよね。その中でも「代理」って、言葉は聞いたことあるけど、「無権代理」とか「表見代理」とか、さらには「復代理」なんて言葉も出てきて、なんだか複雑でわかりにくい…と感じていませんか?「誰が誰の代わりに何をして、その結果どうなるの?」って、頭の中で整理するのが大変ですよね。
でも、この「代理」の分野は、宅建試験では権利関係の超重要テーマの一つなんです!毎年必ずと言っていいほど出題されますし、実務でも、売買契約や賃貸借契約の場面で代理人が関わることは少なくありません。だからこそ、ここでしっかり基本から応用まで理解しておけば、試験の得点アップはもちろん、将来実務に出たときにも必ず役立ちますよ。

この記事では、代理の基本的な仕組みから、ちょっと複雑な無権代理や表見代理、そして自己契約・双方代理のルールまで、図や具体例を交えながら、できるだけわかりやすく解説していきます。
<この記事でわかること>
- 「代理」の基本的な仕組み(任意代理と法定代理の違い、成立要件など)
- 代理権がなくなるケース(代理権の消滅事由)
- 代理人がさらに代理人を選ぶ「復代理」のルール
- 代理権がない人がした契約はどうなる?「無権代理」と「表見代理」の関係
- 原則禁止の「自己契約」「双方代理」とその例外
代理の基本をおさえよう!代理っていったい?
まずは、「代理」の基本的な考え方やルールから確認していきましょう。ここをしっかり押さえることが、応用問題を理解する上での土台になりますよ。
代理とは本人の代わりに契約すること
代理とは、ある人(代理人)が別の人(本人)のために、第三者(相手方)との間で意思表示(契約など)を行い、その法律効果が直接本人に帰属する制度のことです。
簡単に言うと、代理人が本人の代わりに行った契約などの効果が、直接本人にもたらされる、ということですね。
例えば、あなたが忙しくて不動産の売買契約に立ち会えないときに、信頼できる友人Aさんにお願いして、代わりに契約してもらうようなケースが「代理」にあたります。この場合、あなたが「本人」、友人Aさんが「代理人」、不動産の買主が「相手方」となります。友人Aさんが買主と結んだ契約の効果(売買代金を受け取る権利や不動産を引き渡す義務など)は、直接あなたに発生するわけです。

本人が直接動かなくても法律行為ができるので、活動範囲を広げたり、専門家の知識を活用したりできる便利な制度なんですよ。
代理人の種類は2つ!任意代理と法定代理の違い
代理には、その発生原因によって大きく2つの種類があります。
- 任意代理(にんいだいり)
- 本人が自らの意思で「あなたに代理をお願いします」と代理権を与えることによって発生する代理。
- さっきの例のように、あなたが友人に「代わりに契約してきて」と頼むケースがこれにあたります。委任状を渡すことが多いですね。
- 法定代理(ほうていだいり)
- 法律の規定によって当然に代理権が与えられる代理。
- 本人の意思とは関係なく、法律で「この人は代理人です」と決まっているケースです。
- 例:未成年者に対する親権者、成年被後見人に対する成年後見人など。
- 前の記事で勉強した制限行為能力者の保護者(親権者、成年後見人など)は、法定代理人にあたるんですね!
この2つの違いは、後で出てくる「復代理」や「代理権の消滅」のルールにも関わってくるので、しっかり区別しておきましょう。
【意外なポイント】制限行為能力者も代理人になれる?
ここで一つ、引っかかりやすいポイントです。代理人になる人って、しっかりした判断能力が必要そうなイメージがありますよね?でも、実は…
制限行為能力者(未成年者、成年被後見人など)であっても、代理人になることができます!(民法第102条)
「えっ、大丈夫なの?」って思いますよね。これは、代理人が行った行為の効果は、最終的に本人に帰属するので、代理人自身の判断能力は必ずしも必要ない、と考えられているからです。
ただし、注意点が一つあります。
もし、本人があえて制限行為能力者を代理人に選んだ場合、後から「代理人が制限行為能力者だったから、やっぱり契約を取り消したい!」と主張することはできません。

自分で選んだんだから、その責任は本人が負ってね、ということですね。
代理が成立するための3つの条件とは?【代理権・顕名・代理行為】
代理人による行為が、有効な代理行為として本人に効果が帰属するためには、次の3つの要件を満たす必要があります。
1. 代理権がないと始まらない!
当然ですが、代理人には有効な代理権が存在していることが大前提です。本人から代理権を与えられていないのに勝手に代理人を名乗っても、それは原則として「無権代理」(後で詳しく説明します)になってしまいます。
2. 顕名(けんめい)が必要。「本人のために」と示すこと
顕名(けんめい)とは、代理人が相手方に対して、「これは本人のための行為ですよ」ということを示すことです。(民法第99条)
具体的には、「〇〇(本人)の代理人、△△(代理人)です」というように、本人の名前を示して契約などを行うことを指します。
なぜ顕名が必要かというと、相手方からすれば、目の前にいる人が自分のために契約しているのか、それとも誰かの代理で契約しているのかが分からないと、誰と契約したことになるのか困ってしまいますよね。
もし代理人が顕名をしないで契約した場合、原則として、その契約は代理人自身のものとみなされます。(代理人自身が契約の当事者になってしまう)
ただし、例外があります。代理人が顕名をしなくても、相手方が「あ、この人は〇〇さんの代理で来ているんだな」と知っていた(悪意)か、知ることができた(有過失)場合は、ちゃんと本人に効果が帰属します。
ちなみに、商行為(ビジネス上の取引など)の代理では、取引の迅速性が重視されるため、原則として顕名は不要とされています。これも豆知識として覚えておくといいかもしれません。
3. 有効な代理行為(契約など)
代理人が本人に代わって行う法律行為(売買契約、賃貸借契約など)自体が、有効に成立している必要があります。
いつ代理権はなくなるの?代理権の消滅事由をチェック!
一度与えられた代理権も、永遠に続くわけではありません。どんな場合に代理権がなくなるのか(消滅するのか)を見ていきましょう。これは任意代理と法定代理で共通する事由と、任意代理特有の事由があります。
<代理権の消滅事由の比較表>
| 消滅事由 | 本人について | 代理人について | 備考 |
|---|---|---|---|
| 死亡 | ○ | ○ | 本人・代理人どちらかが死亡すると代理権は消滅 |
| 破産手続開始の決定 | × (法定) ○ (任意) | ○ | 本人の破産は任意代理のみ消滅事由。代理人の破産はどちらも消滅 |
| 後見開始の審判 | × | ○ | 本人の後見開始は消滅事由ではない。代理人の後見開始は消滅 |
| 【任意代理のみ】 委任の終了(解除など) | ○ | N/A | 本人が「やっぱり頼むのやめた」と解除するなど |
<ポイント解説>
- 本人の破産: 任意代理(本人が自分で選んだ代理人)の場合、本人が破産すると代理権は消滅します。本人の財産状況が大きく変わるためです。しかし、法定代理(親権者など)の場合、本人が破産しても代理権は消滅しません。保護の必要性は変わらないからです。ここはよく狙われる違いです!
- 本人の後見開始: 以前は消滅事由でしたが、民法改正(2020年4月1日施行)により、本人が後見開始の審判を受けても代理権は消滅しないことになりました。本人の意思を尊重する流れからです。古いテキストを使っている方は注意してくださいね!
- 代理人の後見開始: 代理人が後見開始の審判を受けると、代理権は消滅します。
- 任意代理特有の事由: 任意代理は本人と代理人の信頼関係に基づくので、その基礎となる委任契約が終われば(例えば本人が解除した場合など)、代理権も消滅します。
【例外】不動産登記申請の代理権は本人が死亡しても消えない?
原則として本人が死亡すると代理権は消滅しますが、一つ実務上重要な例外があります。
不動産売買契約が終わった後、買主への所有権移転登記を司法書士に依頼していたとします。もし、登記申請をする前に売主(本人)が亡くなってしまうと、原則通りなら司法書士の代理権は消滅してしまいます。そうなると、改めて売主の相続人全員から登記手続きの承諾を得る必要が出てきて、大変な手間がかかったり、最悪の場合、登記ができなくなったりする恐れがあります。
そこで、判例では、このような不動産登記申請の代理権については、本人が死亡しても消滅しないという扱いを認めています。買主保護のための例外的な措置ですね。
復代理・無権代理・表見代理を理解しよう!
代理の基本がわかったところで、次はもう少し複雑なケースを見ていきましょう。「復代理」「無権代理」「表見代理」は、宅建試験でも頻出の論点です。
代理人がさらに代理人を選ぶ「復代理」とは?
復代理(ふくだいり)とは、代理人が、その権限内の行為を行わせるために、自己の責任でさらに別の人(復代理人)を選任し、本人を代理させることです。(民法第104条、第105条)
「代理人の代理人」ではなく、「本人の代理人」を、代理人が選ぶ、というイメージです。
例:
本人Aが代理人Bに土地売却の代理権を与え、Bが忙しいため、さらにCを復代理人として選任し、Cが相手方Dと売買契約を結んだ場合。
A(本人) —代理権授与—> B(代理人) —復代理人選任—> C(復代理人) —契約—> D(相手方)
復代理の仕組みと注意点
- 復代理人が行った効果は直接本人に帰属する: 上の例で、Cが行った契約の効果(代金請求権など)は、直接本人Aに帰属します。Bを経由するわけではありません。
- 復代理人を選んでも代理人の代理権は消滅しない: BはCを選んだ後も、依然としてAの代理人です。B自身もDと契約することができます。
- 復代理人の権限は元の代理人の権限を超えることはない: Bが土地売却の代理権しか持っていないのに、Cが建物の賃貸借契約を結ぶことはできません。
復代理人って誰の代理人?【本人の代理人です!】
ここ、すごく重要なので繰り返します!
復代理人は、代理人の代理人ではなく、本人の代理人です!
したがって、復代理人の行為について、本人が直接責任を負うことになります。試験でも「復代理人は代理人の代理人である」といったひっかけ問題が出やすいので注意してくださいね!
いつ復代理人を選べるの?責任はどうなる?【任意代理と法定代理の違い】
代理人が勝手に復代理人を選べてしまうと、本人は「知らない人に代理を任されてしまった!」と困るかもしれません。そこで、復代理人を選任できる要件と、選任した場合の代理人の責任について、任意代理と法定代理で異なるルールが定められています。
<復代理人の選任要件と代理人の責任の比較表>
| 種類 | 選任できる要件 | 代理人の責任(復代理人の行為に対する) |
|---|---|---|
| 法定代理 | いつでも自由に選任できる | 原則としてすべての責任を負う(復代理人のミスは自分のミスと同じ) ※やむを得ない事由がある場合は選任・監督責任のみ |
| 任意代理 | ①本人の許諾を得た場合 または ②やむを得ない事由がある場合のみ | 選任・監督についての責任のみ負う (ちゃんと選んで、ちゃんと監督していれば責任は問われないことが多い) |
- 法定代理人(親権者など)は、包括的な代理権を持つことが多く、補助者が必要な場面も想定されるため、比較的自由に復代理人を選べます。その代わり、選んだ復代理人の行為については、原則として全責任を負います。
- 任意代理人は、本人の信頼に基づいて選ばれているので、勝手に復代理人を選ぶことは原則できません。「本人の許可」か「病気などやむを得ない事情」が必要です。その代わり、責任は復代理人の「選び方」と「監督」に限られます。

法定代理の方が選任は自由だけど責任は重い、任意代理は選任は制限されるけど責任は軽い、というバランスになっているんですね!
代理権がないのに代理行為!?「無権代理」とは?
ここからは、トラブルになりやすいケース「無権代理」です。
無権代理ってどんな状況?契約はどうなる?
無権代理(むけんだいり)とは、代理権がないにもかかわらず他人の代理人と称して法律行為をしたり、与えられた代理権の範囲を超えて法律行為をしたりすることです。(民法第113条)
例:
本人Aから何の代理権も与えられていないCが、勝手にAの代理人と名乗って、A所有の土地を相手方Bに売却する契約を結んでしまった場合。
A(本人) —×(代理権なし)— C(無権代理人) —代理と称して契約—> B(相手方)
この場合、Cは無権代理人であり、Cが行った契約(AB間の売買契約)は、原則として本人Aには効果が及びません(無効)。
しかし、これだと相手方Bは「契約したのに土地が手に入らない!」と困ってしまいますし、場合によっては本人Aが「まあ、Cがやったことだけど、別にいいか」と思うかもしれません。そこで、民法では、本人と相手方の利害を調整するためのルールを設けています。
本人はどうできる?【追認権・追認拒絶権】
無権代理行為があった場合、本人Aは次のどちらかを選ぶことができます。
- 追認権(ついにんけん)
- 無権代理人が行った契約を、後から認めて有効なものとして確定させる権利です。
- 追認すると、契約は契約時にさかのぼって有効だったことになります。
- 追認の意思表示は、相手方Bにしても、無権代理人CにしてもOKです。
- 追認拒絶権(ついにんきょぜつけん)
- 無権代理人が行った契約を有効とは認めない、と確定させる権利です。
- これにより、契約は完全に無効となります。

本人に最終的な決定権があるんですね。
相手方はどうできる?【催告権・取消権・責任追及・表見代理】
一方、相手方Bにも、不安定な状況から抜け出すための権利が与えられています。
- 催告権(さいこくけん)
- 本人Aに対して、「この契約、追認しますか?拒絶しますか?相当な期間内に返事をください」と問い合わせる権利です。(民法第114条)
- この権利は、相手方Bが善意(Cが無権代理だと知らなかった)でも悪意(知っていた)でも行使できます。
- 期間内に本人から返事がなければ、追認を拒絶したものとみなされます。(契約は無効になる)
- 制限行為能力者の催告権とは結論が逆になることがあるので注意。
- 取消権(とりけしけん)
- 相手方Bが善意(Cが無権代理だと知らなかった)の場合に限り、本人Aが追認する前に、契約自体を取り消すことができる権利です。(民法第115条)
- 無権代理人への責任追及
- 相手方Bが善意無過失(知らず、かつ、知らなかったことに落ち度がない)の場合、無権代理人Cに対して、次のどちらかを選択して請求できます。(民法第117条)
- 履行請求:「契約通りに履行しろ!」(例:土地を引き渡せ)
- 損害賠償請求:「契約が有効だと信じたことによる損害を賠償しろ!」
- ただし、無権代理人C自身が制限行為能力者だった場合は、責任を追及できません。(制限行為能力者の保護が優先されるため)
- 相手方Bが善意無過失(知らず、かつ、知らなかったことに落ち度がない)の場合、無権代理人Cに対して、次のどちらかを選択して請求できます。(民法第117条)
- 表見代理の主張
- 相手方Bが善意無過失で、かつ、一定の条件(後述)を満たす場合、「これは有効な代理行為だ!」と本人Aに対して主張し、契約の履行を求めることができます。(これが次に説明する「表見代理」です)

相手方も色々な対抗手段を持っているんですね。特に善意無過失かどうかが重要になりそうです。
無権代理と相続が絡むとどうなる?【本人相続・代理人相続】
無権代理の関係者が死亡して相続が発生すると、少しややこしい問題が起こります。
- 無権代理人が本人を相続した場合
- 例:無権代理人Cが本人Aを単独で相続した。
- この場合、Cは本人の立場で追認を拒絶することはできません。自分で勝手な代理行為をしておきながら、相続した途端に「あの契約は無効だ!」と言うのは、信義に反する(ずるい)からです。原則として契約は有効なものとして扱われます。
- 本人が無権代理人を相続した場合
- 例:本人Aが無権代理人Cを単独で相続した。
- この場合、Aは本人の立場で追認を拒絶することができます。無権代理行為を認めるかどうかは、あくまで本人の意思が尊重されます。
- ただし、Aは無権代理人Cの地位も相続しているので、もし相手方Bが善意無過失であれば、BはAに対して無権代理人の責任(履行請求または損害賠償請求)を追及できる可能性があります。

相続が絡むと、誰が誰の権利・義務を引き継ぐのかがポイントになるんですね。
無権代理だけど有効に!?相手方を守る「表見代理」とは?
無権代理は原則として本人に効果が及びませんが、ある特別な場合には、あたかも有効な代理権があったかのように扱われ、本人に契約の効果が及ぶことがあります。これが表見代理(ひょうけんだいり)です。
表見代理が成立するってどういうこと?
表見代理とは、代理権がないにもかかわらず、外部から見ると正当な代理権があるかのような客観的な状況(外観)が存在し、その外観を信じた善意無過失の相手方を保護するために、本人に対して契約の効果を帰属させる制度です。
つまり、「本人にも、代理権があると相手が信じてしまうような原因を作った責任があるんだから、その結果を引き受けなさい」ということです。表見代理が成立すると、本人は契約上の責任を負わなければなりません。
<表見代理が成立するための共通要件>
- 代理権が存在しないこと(無権代理であること)
- 相手方が、代理権があると信じ、かつ、そう信じたことについて過失がないこと(善意無過失であること)
表見代理が成立する3つのパターン(+複合パターン)
では、具体的にどんな場合に「代理権があるかのような外観」があると認められるのでしょうか?民法では主に3つの類型を定めています。
- 代理権授与表示による表見代理(民法第109条)
- 本人が、実際には代理権を与えていないのに、「Cに代理権を与えました」と白紙の委任状を渡すなどして、相手方に対して代理権を与えたかのような表示をした場合。
- 例:AがBに対して「土地売却の件はCに任せた」と言ったが、実際にはCに代理権を与えていなかった。Bがそれを信じてCと契約した。
- 権限外の行為の表見代理(民法第110条)
- 代理人に与えられた代理権の範囲を超えて、代理人が別の行為をした場合。
- 例:AがCに「建物の賃貸」の代理権を与えたのに、Cが勝手に「土地の売却」契約をBとしてしまった。BはCが土地売却の権限もあると信じた。
- 基本となる代理権(この例では建物の賃貸権)は実際に存在している必要があります。
- 代理権消滅後の表見代理(民法第112条)
- 以前は代理権があったが、それが消滅した後に、元代理人が代理人と称して行為をした場合。
- 例:AがCに与えていた代理権が期間満了で消滅したのに、Cがまだ代理人であるかのように装ってBと契約した。Bは代理権が消滅したことを知らなかった。
さらに、これらの類型が複合して表見代理が成立することもあります。
例えば、「代理権授与の表示があった上で(①)、さらに権限外の行為をした(②)」場合や、「代理権消滅後に(③)、さらに権限外の行為をした(②)」場合などです。判例で認められています。
表見代理が成立したら、無権代理人への責任追及はできない?
表見代理が成立する可能性がある場合、相手方B(善意無過失)は、
- 表見代理を主張して、本人Aに契約の履行を求める
- 無権代理人の責任(民法第117条)として、無権代理人Cに履行または損害賠償を求める
このどちらかを選択することができます。

相手方にとっては、より確実に権利を実現できそうな方を選べるんですね!
表見代理が成立するからといって、無権代理人Cの責任が自動的になくなるわけではありません。相手方がどちらの道を選ぶか、ということです。
自己契約と双方代理は禁止?例外的にOKなケースも!
最後に、代理にまつわる禁止事項として「自己契約」と「双方代理」を見ておきましょう。原則として禁止されていますが、例外的に認められるケースもあります。
自分で自分と契約?「自己契約」がダメな理由
自己契約(じこけいやく)とは、代理人が、本人の代理人として、自分自身を相手方として契約を結ぶことです。(民法第108条第1項本文)
例:
本人Aが代理人Cに「A所有の土地をできるだけ高く売ってきて」と代理権を与えたのに、Cが「買主は私(C)です」として、自分に都合の良い安い価格で売買契約を結んでしまうケース。
A(本人・売主) —代理権授与—> C(代理人・買主)
自己契約は、代理人が自分の利益を優先して、本人の利益を害する恐れがあるため、原則として禁止されています。
もし自己契約が行われた場合、それは無権代理行為とみなされ、原則として本人に効果は及びません。本人が追認すれば有効になります。
一人で二人の代理人になる「双方代理」がダメな理由
双方代理(そうほうだいり)とは、同一の人物が、契約の当事者双方(例えば売主と買主)の代理人となって契約を結ぶことです。(民法第108条第1項本文)
例:
売主Aが代理人Cに「土地をできるだけ高く売ってきて」と依頼し、同時に買主Bも代理人Cに「同じ土地をできるだけ安く買ってきて」と依頼し、CがAとB双方の代理人として売買契約を結ぶケース。
A(本人・売主) —代理権授与—> C(双方の代理人) <—代理権授与— B(本人・買主)
双方代理も、一方の当事者の利益を図ると、もう一方の当事者の利益を害することになる(利益相反)ため、原則として禁止されています。
これも自己契約と同様に、行われた場合は無権代理行為とみなされ、原則として本人たちに効果は及びません。当事者双方が追認すれば有効になります。
【例外あり】自己契約・双方代理が有効になるケース
原則禁止の自己契約・双方代理ですが、例外的に有効となる場合があります。
自己契約・双方代理が例外的に有効となるケース(民法第108条第1項ただし書、第2項)
- 本人があらかじめ許諾した場合
- 自己契約:「私が買ってもいいよ」と本人が事前にOKしている。
- 双方代理:「Cさんが双方の代理人になることを、AさんBさん両方が事前にOKしている。」
- 債務の履行
- 法律行為の要素がなく、単に形式的に存在する債務を履行するだけの場合。
- 典型例:不動産登記の申請
- 売買契約が既に成立し、代金も支払い済みで、あとは所有権移転登記をするだけ、という段階で、司法書士が売主・買主双方の代理人となって登記申請をする場合。これは、既に確定した権利関係を登記簿に反映させるだけの形式的な手続きであり、当事者間に新たな利害対立が生じる恐れがないため、双方代理が認められています。

本人が納得しているか、争いようがない形式的な手続きならOK、ということですね!
まとめ
お疲れ様でした!今回は「代理」について、基本から応用まで幅広く見てきました。
代理は、本人の代わりに契約などを行う便利な制度ですが、「任意代理」と「法定代理」の違い、代理権の発生や消滅、そして「顕名」の必要性など、基本的なルールをしっかり押さえることが大切でしたね。
そして、応用編として、
- 復代理:代理人が選んだ「本人の」代理人。選任要件と責任が任意・法定で異なる。
- 無権代理:代理権がないのに代理行為をすること。原則無効だが、本人には「追認権・追認拒絶権」、相手方には「催告権・取消権・責任追及権」がある。
- 表見代理:無権代理でも、代理権があるかのような外観があり、相手方が善意無過失なら有効とみなされる制度。3つの類型(+複合)がある。
- 自己契約・双方代理:原則禁止(無権代理扱い)だが、「本人の許諾」と「債務の履行」の場合は例外的に有効。
これらの関係性を整理して理解することが、宅建試験攻略のカギになります。特に無権代理と表見代理は、誰がどんな場合にどういう権利を主張できるのか、図を書きながら覚えると効果的ですよ。
この記事のポイントまとめ
- 代理とは、代理人が本人のために行い、効果が本人に帰属する行為。任意代理と法定代理がある。
- 代理成立には「代理権の存在」「顕名」「有効な代理行為」が必要。
- 代理権は、本人・代理人の死亡、代理人の破産・後見開始、任意代理の委任終了などで消滅する(本人の破産は任意代理のみ消滅)。
- 復代理人は本人の代理人であり、選任要件・責任が任意代理と法定代理で異なる。
- 無権代理は原則本人に効果が帰属しないが、本人の追認権や相手方の催告権・取消権・責任追及権がある。
- 表見代理は、無権代理でも代理権があるような外観を信じた善意無過失の相手方を保護し、本人に効果を帰属させる制度(3類型+複合)。
- 自己契約・双方代理は、利益相反の恐れから原則禁止(無権代理)だが、本人の許諾や債務の履行の場合は例外的に有効。

最初は複雑に感じたかもしれませんが、一つ一つ丁寧に見ていけば、必ず理解できるようになります!繰り返し復習して、得意分野にしちゃいましょう!