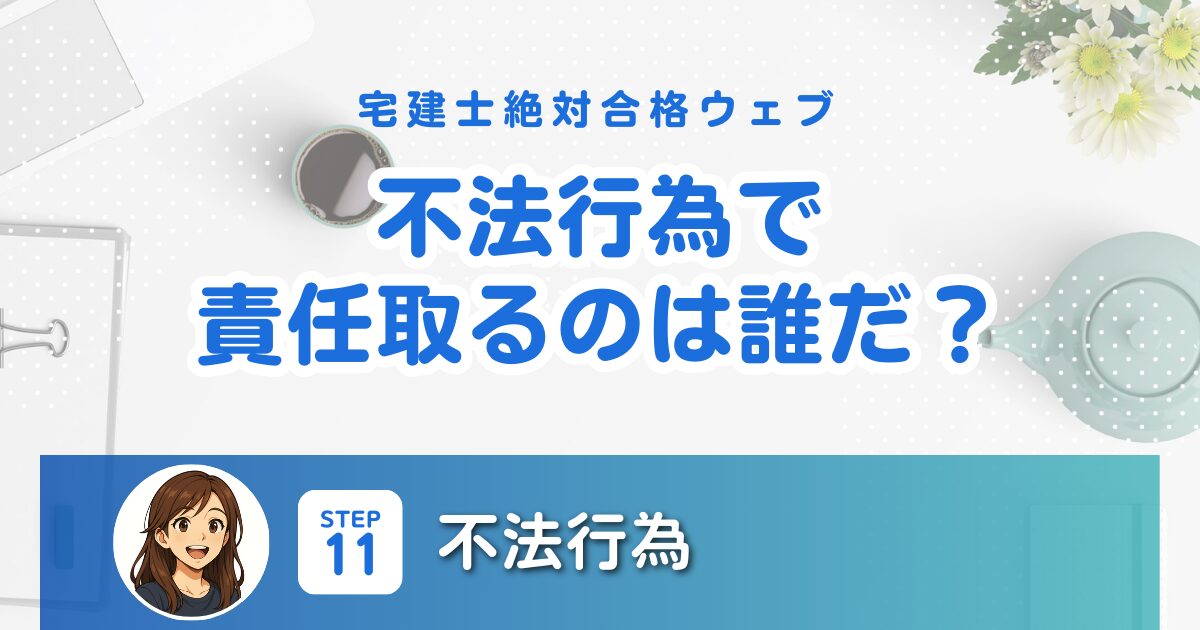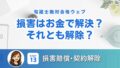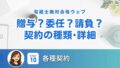宅建の勉強、毎日お疲れさまです!権利関係、特に民法の分野って、普段聞き慣れない言葉が多くて、最初はとっつきにくいって感じること、ありませんか?「不法行為」とか「使用者責任」とか「工作物責任」とか言われても、具体的にどういうことなのか、誰がどんな時に責任を負うのか、いまいちピンとこない…なんて方もいらっしゃるかもしれませんね。でも、これらの知識は、宅建試験では避けて通れない重要なポイントなんです。

今回は民法の「不法行為」について、その基本から、ちょっと複雑な特殊ケースまで、わかりやすく解説していきますね!
日常生活でも、交通事故や物の損壊、建物の欠陥による事故など、誰かに損害を与えてしまったり、逆に損害を受けてしまったりする可能性はゼロではありません。そんなときに「誰が」「誰に」「どんな責任を負うのか」を定めているのが、民法の不法行為に関するルールなんです。特に不動産に関わる仕事では、建物の管理責任(工作物責任)や、従業員のミス(使用者責任)などが現実的な問題として起こりうるので、しっかり理解しておきたいですね。
この記事では、不法行為の基本的な考え方から、宅建試験で特によく問われる特殊な不法行為である「使用者責任」「工作物責任」「共同不法行為」について、それぞれの成立要件や責任の所在、関連するルール(過失相殺、時効、求償権など)まで、具体例を交えながら丁寧に解説していきます。「なるほど、そういうことか!」と理解が深まるはずですよ。この記事を読めば、不法行為に関する苦手意識がなくなって、自信を持って問題に取り組めるようになるはずです!
この記事でわかること
- 不法行為とは何か、基本的な成立要件や効果について理解できる
- 使用者責任、工作物責任、共同不法行為の具体的な内容と責任の所在の対策がわかる
- 損害賠償請求権の消滅時効や過失相殺、相殺禁止ルールのポイントが整理できる
- 不法行為に関する宅建試験の重要ポイントとの違いがわかる
- 関連知識(債務不履行との比較など)を効率よく学習するヒントが明確になる
不法行為とは?損害賠償、過失相殺、時効を解説
まずは、全ての基本となる「不法行為」そのものについて見ていきましょう。これがしっかり理解できると、後で出てくる使用者責任などもスムーズに頭に入ってきますよ。

基本が大事!ここをしっかり押さえていきましょう!
不法行為の基本的な考え方
不法行為(ふほうこうい)って、ざっくり言うと、「わざと(故意)」または「うっかり(過失)」によって、他人の権利(例えば、所有権や身体、生命、名誉など)や法律上保護される利益を違法に侵害して損害を与えてしまった場合に、その損害を賠償する責任を負うこと、という民法の制度です。契約関係がない人同士の間でも発生するのが特徴ですね。
民法第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
例えば、日常生活で起こりうるこんなケースが典型的な不法行為にあたります。
- 運転中に不注意で前の車に追突してしまい、相手の車をへこませてしまった(過失による物損)。
- 隣の家の窓ガラスを、腹いせに石を投げて割ってしまった(故意による物損)。
- マンションの上の階の住人が、お風呂の水を出しっぱなしにして水漏れを起こし、下の階の部屋に損害を与えた(過失による財産侵害)。
- SNSで他人を誹謗中傷し、その人の社会的評価を低下させた(故意による名誉棄損)。
不法行為が成立するためには、いくつかの要件が必要です。簡単にまとめると以下のようになります。
【不法行為の主な成立要件】
- 加害者の故意または過失: わざとやったか、不注意があったか。
- 権利侵害・利益侵害: 被害者の権利や法律上保護される利益が侵害されたこと。
- 損害の発生: 実際に損害(財産的損害、精神的損害など)が発生したこと。
- 因果関係: 加害者の行為(侵害行為)と発生した損害との間に、原因と結果の関係があること。
- 加害者の責任能力: 加害者に、自分の行為の責任を判断できる能力があること。(※例外として、責任無能力者(幼児や重度の精神障がい者など)の監督義務者が代わりに責任を負う場合があります(民法714条))
これらの要件がすべて揃って初めて、加害者は被害者に対して、原則として金銭による損害賠償責任を負うことになるんですね。
不法行為による損害賠償と過失相殺のルール
不法行為があった場合、加害者は被害者に対して損害を賠償する義務を負いますが、もし被害者側にも不注意(過失)があった場合は、その賠償額はどうなるのでしょうか?
例えば、交通事故で考えてみましょう。加害者がスピード違反をしていたのは確かだけれど、被害者の歩行者も信号無視をしていた…といったケースです。この場合、加害者だけに損害の全責任を負わせるのは、ちょっと公平じゃない気がしますよね。
そこで登場するのが「過失相殺(かしつそうさい)」という考え方です。これは、被害者にも過失があった場合に、その過失の程度を考慮して、加害者が支払うべき損害賠償額を減額するというルールです(民法第722条2項)。
裁判所は、事故の状況などを詳しく調べ、加害者と被害者それぞれの過失の割合(例えば「加害者80%:被害者20%」など)を判断し、それに応じて賠償額を調整します。損害の公平な分担を図るための制度なんですね。
<注意!債務不履行との違い>
以前の記事でも触れましたが、契約違反である「債務不履行」の場合、債権者(被害者)に過失があれば、裁判所は必ず過失相殺を考慮しなければなりません(義務)。
一方、この「不法行為」の場合、条文上は、裁判所は過失相殺を「することができる」(裁量)とされています。ただし、実際には不法行為の場合でも、被害者に過失があればほとんどの場合、過失相殺が適用されます。この微妙な違いを、試験では意識しておきましょう。
【重要】不法行為の損害賠償請求権には消滅時効がある!
「権利はいつまでも主張できるわけではない」というのが法律の基本的な考え方です。不法行為によって損害賠償を請求できる権利(損害賠償請求権)も、永遠に存在するわけではなく、一定期間が経過すると「消滅時効(しょうめつじこう)」にかかり、権利が消滅してしまいます。請求するなら、早めに行動する必要がある、ということですね。
不法行為の消滅時効は、「どんな損害か(物損か人損か)」によって期間が異なるのが大きな特徴です。これは民法改正で期間が変わった点でもあるので、しっかり覚えましょう!
① 財産的な損害(物損)の場合の消滅時効 (主観的3年 / 客観的20年)
物を壊された場合や、お金をだまし取られた場合など、財産的な損害(物損)に関する損害賠償請求権の消滅時効は、以下のいずれか短い方の期間が経過したときです(民法第724条)。
- 主観的起算点: 被害者またはその法定代理人が「損害」および「加害者」を知った時から3年間行使しないとき。
- 客観的起算点: 不法行為の時から20年間行使しないとき。
「知った時」というのがポイントです。
例えば、当て逃げされて車に傷がついた場合、「損害」は認識していますが、「加害者」が誰かわからない間は、この「知った時」からの3年の時効はスタートしません。しかし、犯人が分からないままでも、事故(不法行為)の時から20年経てば、時効で権利は消滅してしまいます。
② 人の生命または身体の侵害(人損)の場合の消滅時効 (主観的5年 / 客観的20年)
交通事故でケガをした、医療ミスで後遺症が残った、暴行を受けて傷害を負ったなど、人の生命や身体に関する損害(人損)の損害賠償請求権は、物損の場合よりも被害者の保護を厚くするため、主観的起算点からの時効期間が長く設定されています(民法第724条の2)。
- 主観的起算点: 被害者またはその法定代理人が「損害」および「加害者」を知った時(権利を行使できることを知った時)から5年間行使しないとき。
- 客観的起算点: 不法行為の時(権利を行使できる時)から20年間行使しないとき。
客観的起算点の20年は物損と同じですが、主観的起算点が「3年」ではなく「5年」になっている点に注意してください。
消滅時効のポイント まとめ
- 時効には「主観的起算点(知った時から)」と「客観的起算点(行為の時から)」の2種類のリミットがある。
- 主観的起算点は「損害」と「加害者」の両方を知った時からカウント開始。
- 物損は3年 / 20年、人損は5年 / 20年。
この数字はしっかり覚えましょう!
損害賠償債務はいつから遅延する?履行遅滞の起算点
加害者が被害者に対して負う損害賠償の支払い義務(損害賠償債務)は、いつから支払いが遅れている状態(履行遅滞)になるのでしょうか? 遅滞になれば、その期間に応じた遅延損害金も発生します。
通常の契約に基づく金銭債務(例えば、借金の返済義務など)は、返済期限が来て、さらに債権者から「払ってください」と請求を受けてから遅滞になるのが原則ですが、不法行為の場合は扱いが異なります。
<重要ポイント!>
不法行為に基づく損害賠償債務は、特別な定めがない限り、不法行為が発生した時(=損害が発生した時)から、当然に履行遅滞となります。 請求の有無は関係ありません。
これは、被害者は損害を受けたその瞬間から賠償を受ける権利があるはずであり、加害者は直ちに賠償する義務を負うべきだ、という被害者保護の考え方に基づいています。したがって、不法行為があった日から実際に賠償金が支払われる日までの期間について、遅延損害金を請求できることになります。

請求しなくても、不法行為があった時から遅延損害金が発生する可能性があるんですね。被害者にとっては心強いルールです。
誰が損害賠償を請求できる?請求権者について(相続・胎児も含む)
基本的には、不法行為によって直接損害を受けた被害者本人が、加害者に対して損害賠償を請求します。
では、もし被害者が不法行為によって死亡してしまった場合は、誰が請求権者になるのでしょうか?
この場合、被害者が本来持っていたはずの損害賠償請求権(財産的な損害に対するものだけでなく、被害者自身の精神的苦痛に対する慰謝料請求権も含む)は、相続人に引き継がれます。
ここで重要なのは、たとえ被害者が事故などで即死した場合でも、判例では、「被害を受けた瞬間に損害賠償請求権や慰謝料請求権が発生し、それが相続の対象になる」と考えられている点です。もし即死だと権利が発生しないと考えると、事故後しばらくして亡くなった場合と比べて遺族が受け取れる賠償が少なくなってしまい、不公平だからです。
さらに、民法では胎児についても特別な保護規定があります。損害賠償請求に関しては、胎児は「既に生まれたものとみなされる」とされています(民法第721条)。
そのため、例えば、父親が不法行為で亡くなった場合、その時にまだ母親のお腹の中にいた胎児も、無事に生まれてくれば、相続人として父親自身の損害賠償請求権(父親自身の慰謝料請求権を含む)を相続し、加害者に請求することができるのです。
【被害者の近親者の固有の権利】
なお、被害者が死亡した場合や重い傷害を負った場合には、被害者本人の損害賠償請求権(を相続人が引き継ぐ)とは別に、被害者の父母、配偶者、及び子は、自分自身の精神的苦痛に対する慰謝料を加害者に請求できる場合があります(民法第711条)。これは相続する権利ではなく、近親者固有の権利として認められています。
【注意】加害者からは相殺できないケース(人の生命・身体の侵害)
「相殺(そうさい)」は、お互いに金銭債権などを持ち合っている場合に、それらを対当額で消滅させる(帳消しにする)便利な制度でしたね。
しかし、不法行為によって発生した損害賠償債務については、相殺が制限される場合があります。特に重要なのが、「人の生命または身体の侵害」による損害賠償債務です。
この場合、加害者側が、被害者に対して別の債権(例えば、以前お金を貸した返済請求権など)を持っていたとしても、その債権を自働債権として、生命・身体侵害による損害賠償債務(これを受働債権とする)と相殺することは禁止されています(民法第509条)。
<絶対NG!>
加害者が、生命・身体侵害による損害賠償債務を「受働債権」として相殺を主張すること → 禁止!
なぜでしょうか? もし、加害者からの相殺が許されるとしたら、極端な話、「借金を返さない相手を殴ってケガさせても、治療費は貸した金と相殺すればいいや」というような、暴力による債権回収を助長しかねません。

それは絶対にダメですよね!被害者は現実にお金を受け取って治療や生活に充てる必要があるのに…。
人の生命や身体という最も重要な利益を侵害した場合には、加害者にきちんと金銭で賠償させることで、被害者の現実的な救済を図る必要性が極めて高いのです。そのため、加害者側からの一方的な相殺は認められていないのです。
ただし、被害者側から、「加害者に対して持っている別の債権と、もらうべき損害賠償金を相殺してください」と主張することは認められています。あくまで禁止されているのは、加害者側からの相殺だという点を押さえておきましょう。
特殊な不法行為①:使用者責任とは?従業員のミスで会社が負う賠償責任と求償権
ここからは、通常の不法行為とは少し異なる、特殊な不法行為責任について見ていきましょう。まずは「使用者責任」です。
使用者責任の基本 – どんな場合に責任が発生するの?
使用者責任(しようしゃせきにん)とは、ある事業のために他人を使用する者(例:会社、個人事業主など。これを「使用者」といいます)が、その従業員(例:社員、アルバイトなど。これを「被用者」といいます)が仕事に関連して(事業の執行について)第三者に損害を与えた場合に、使用者も被害者に対して損害賠償責任を負う、という制度です(民法第715条)。
民法第715条(使用者等の責任)
1. ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2. 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3. (略)
例えば、こんなケースで使用者責任が問題になります。
- 不動産会社の営業担当者Aが、お客様Bを車で物件案内に連れて行く途中で、不注意により交通事故を起こし、お客様Bにケガをさせてしまった。
- 建設会社の作業員Cが、工事現場で誤って資材を落下させ、通行人Dに損害を与えた。
- 飲食店のアルバイトEが、レジ操作を間違えてお客さんFから過剰にお金を受け取ってしまった(不当利得とも関連しますが、不法行為責任も問われえます)。
これらの場合、実際に不法行為を行った従業員(A, C, E)はもちろん被害者(B, D, F)に対して損害賠償責任(民法709条)を負いますが、それとは別に、その従業員を雇っている会社(使用者)も、被害者に対して損害賠償責任(民法715条)を負うことになるのです。被害者は、従業員個人と会社の両方、またはどちらか一方に対して賠償を請求できます。
【使用者責任の主な成立要件】
- 使用関係の存在: 使用者と被用者の間に、実質的な指揮監督関係があること(雇用契約だけでなく、請負や委任でも実質的に指揮監督があれば認められる場合があります)。
- 事業の執行についての不法行為: 被用者の行為が、客観的に見て使用者の事業の範囲内、またはそれに関連する行為であること(例えば、営業の外回り中の事故など。休憩中の私的な行為は原則含まれませんが、外形上、職務行為と見える場合は責任を負うこともあります)。
- 被用者の不法行為の成立: 被用者の行為自体が、民法709条の不法行為の要件(故意・過失など)を満たしていること。
- 使用者の免責事由がないこと: 使用者が「被用者の選任・監督について相当の注意をしていた」こと、または「相当の注意をしても損害が発生したであろう」ことを証明できないこと。
特に4番目の免責事由ですが、これを会社側が証明するのは実際には非常に難しいとされています。よほどのことがない限り、会社も責任を免れることは難しいと考えておきましょう。これは、会社は従業員を使うことで利益を得ているのだから、その活動に伴うリスク(損害を与える可能性)も負担すべきだ(報償責任の原理)、という考え方や、資力のある会社に責任を負わせることで被害者救済を図る、という政策的な理由に基づいています。
使用者と従業員の間での求償関係はどうなる?
さて、会社(使用者)が被害者に損害賠償金を支払った場合、会社はその全額を、原因を作った従業員(被用者)に対して「あなたがやったことなんだから、会社が払った分を返しなさい!」と請求(求償:きゅうしょう)できるのでしょうか?
また逆に、もし従業員が自腹で被害者に賠償金を支払った場合、従業員は会社に対して「会社の仕事中に起きたことなんだから、会社も一部負担してください!」と求償できるのでしょうか?
この点について、民法には「何割まで求償できる」というような具体的な割合の規定はありません。しかし、判例は次のように考えています。
<重要!使用者⇔被用者間の求償>
使用者(会社)が賠償した場合に被用者(従業員)へ求償する場合も、
被用者(従業員)が賠償した場合に使用者(会社)へ求償する場合も、
どちらも無制限に全額請求できるわけではなく、「損害の公平な分担という見地から、信義則上相当と認められる限度」においてのみ、相手に求償できる、とされています。
つまり、「全額返せ!」とか「全額負担しろ!」とはならず、ケースバイケースで、それぞれの責任の度合いや状況に応じて、妥当な範囲に限って請求できる、ということです。例えば、会社の安全管理体制に問題があった場合や、従業員が通常業務の中で軽微なミスをした場合などは、会社から従業員への求償はかなり制限されるか、認められないこともあります。
被害者にも過失があった場合の過失相殺
使用者責任が問われるケースでも、もし被害者側に過失があった場合には、もちろん過失相殺が適用されます(民法715条3項が722条2項を準用)。
裁判所は、被害者側の過失の度合いを考慮して、使用者(や被用者)が支払うべき損害賠償額を減額することができます。
ここで少し細かい点ですが、過失相殺の対象となる「被害者側」の過失には、被害者本人の過失だけでなく、判例上、被害者の身分上・生活関係上一体とみられるような関係にある者(例えば、被害者が幼児の場合の親(監督義務者)や、被害者である従業員の同僚など)の過失も含まれる場合がある、とされています。使用者側にとっては、少し有利になる可能性のある解釈ですね。
被害者が即死した場合の損害賠償請求権の相続
これは、先ほどの「不法行為」の基本の項目で説明したことと全く同じ考え方になりますが、使用者責任の文脈でも重要なので再確認しましょう。
使用者責任が問われるようなケース(例:会社のトラック運転手の過失による死亡事故)で、被害者が即死してしまった場合でも、判例では、被害を受けた瞬間に、被害者本人に損害賠償請求権(自身の慰謝料請求権を含む)が発生し、それが相続人に承継されると考えられています。
したがって、被害者の遺族(相続人)は、加害者である従業員と、使用者である会社の両方に対して、被害者本人の損害賠償請求権(を相続したもの)と、遺族固有の慰謝料請求権を合わせて請求することができます。
特殊な不法行為②:工作物責任とは?建物の欠陥による事故の責任は誰にある?占有者と所有者の関係
次に、特殊な不法行為の2つ目、「工作物責任」です。これは、建物や塀、看板など、土地に設置された「工作物」の設置や保存に問題(瑕疵:かし)があって、それが原因で他人に損害を与えてしまった場合の責任に関するルールです。不動産に直接関わる責任なので、宅建士としては特にしっかり理解しておきたいですね!
工作物責任の基本 – どんな場合に問題になる?
工作物責任(こうさくぶつせきにん)とは、土地の工作物(建物、塀、擁壁、エレベーター、エスカレーター、看板、遊具など、土地に接着して人工的に作られた設備全般)の設置または保存に瑕疵(かし:欠陥や不備)があり、それによって他人に損害が生じた場合に、その工作物の占有者または所有者が負う損害賠償責任のことです(民法第717条)。
民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2. (略:竹木の栽植・支持の瑕疵も同様)
3. (略:占有者・所有者の求償権)
具体的には、以下のようなケースで工作物責任が問題になります。
- 古いアパートのベランダの手すりが腐食していて、賃借人が寄りかかった際に手すりが壊れて落下し、通行人にケガをさせてしまった。
- 店舗の入口に設置されていた自動ドアのセンサーが故障していて、お客さんがドアに挟まれて負傷した。
- 個人宅のブロック塀が、耐震基準を満たさない古いもので、地震で倒壊して隣家に損害を与えた。
責任を負うのは誰?占有者と所有者の責任順序
工作物の瑕疵によって損害が発生した場合、被害者は誰に対して損害賠償を請求すればよいのでしょうか? 民法は、責任を負う人の順番を明確に定めています。
第一次的な責任者:占有者
まず、被害者は、その工作物を現実に支配・管理している「占有者(せんゆうしゃ)」に対して損害賠償を請求します。占有者とは、例えば賃貸アパートであれば、通常はその部屋を借りている賃借人が該当します。(マンション全体に関わるような共用部分の瑕疵であれば、管理組合が占有者とされる場合もあります)。
占有者は、損害の発生を防止するために必要な注意をしていたこと(例えば、定期的に点検していた、異常に気づいてすぐに所有者に報告していたなど)を証明できれば、責任を免れることができます。
つまり、占有者の責任は「過失責任」に近い考え方です。必要な注意を怠っていた場合に責任を負い、「ちゃんと注意していましたよ!」と証明できればセーフ、ということです。
第二次的な責任者:所有者(無過失責任)
もし、占有者が「自分はちゃんと必要な注意をしていた!」と証明して責任を免れた場合、被害者はまだ救済されていませんよね。そこで、次に責任を負うのが、その工作物の「所有者(しょゆうしゃ)」です。賃貸アパートの例なら、大家さん(オーナー)ですね。
ここが最大のポイントです! 所有者の責任は「無過失責任(むかしつせきにん)」である、という点です。
つまり、所有者は、たとえ自分には何の過失(不注意)がなかったとしても、工作物に瑕疵(欠陥)が存在し、それによって損害が発生した以上は、責任を免れることができません。
「いや、私は遠方に住んでいて、管理は全部占有者に任せていたし、欠陥があるなんて知らなかったんだ!」と所有者が主張しても、ダメなのです。工作物を所有している以上、そこから生じる危険については最終的な責任を負うべきだ、という考え方(危険責任)と、被害者を確実に救済するという政策的な理由から、所有者には非常に重い責任が課せられています。
<工作物責任の順序 まとめ>
1. 占有者が第一次的責任(過失責任:必要な注意の証明で免責あり)
2. 占有者が免責された場合 → 所有者が第二次的責任(無過失責任:免責なし!)
この責任の順序と、特に所有者の無過失責任は、宅建試験で頻出なので絶対に覚えてください!
損害賠償をした占有者・所有者から工事業者への求償
ところで、工作物の瑕疵の原因が、そもそもその工作物を設置したり、修繕したりした工事業者(請負人など)のミスにあった場合はどうなるのでしょうか?
この場合、被害者に対して損害賠償を行った占有者や所有者は、その損害発生の真の原因を作った者(例えば、手抜き工事をした工事業者など)に対して、支払った賠償金の支払いを請求(求償)することができます(民法第717条3項)。
ただし、注意点として、被害者が直接、工事業者に工作物責任(民法717条)を追及するわけではありません。あくまで、717条に基づく責任は占有者・所有者が負い、その賠償金を支払った占有者・所有者が、後から原因者に対して求償する、という流れになります。(被害者が工事業者に対して、別の根拠(例えば通常の不法行為責任709条)で請求することはあり得ます)。
特殊な不法行為③:共同不法行為とは?複数人で損害を与えた場合の連帯責任と求償
最後に、特殊な不法行為の3つ目、「共同不法行為」について解説します。これは、一人ではなく、複数人が関わって不法行為が行われた場合のルールです。
共同不法行為の基本 – どんな場合に成立する?
共同不法行為(きょうどうふほうこうい)とは、数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えた場合に、関与した者(加害者)全員が連帯して被害者に対して損害賠償責任を負う、という制度です(民法第719条)。
民法第719条(共同不法行為者の責任)
1. 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2. 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。
共同不法行為が成立する主なケースは、条文にもある通り、大きく分けて2つです。
- 狭義の共同不法行為(客観的関連共同):
数人が文字通り「共同して」不法行為を行った場合。お互いに意思の連絡がなくても、それぞれの行為が客観的に関連し合って損害を発生させれば成立します。
(例:AさんとBさんが、それぞれ別の場所からCさんに向かって石を投げ、どちらかの石が当たってCさんがケガをした場合。AさんとBさんは共同不法行為者となります。) - 加害者不明の場合:
複数の人が関与した行為によって損害が発生したが、「具体的に誰のどの行為が直接の原因となって損害を与えたのか特定できない」場合。この場合も、関与した者全員が共同不法行為者として連帯責任を負います。
(例:デモ隊の群衆が暴徒化し、近くの店舗の窓ガラスが割られたが、具体的に誰が割ったのか分からない場合。その暴徒化した集団に参加していた者は、共同不法行為者とされる可能性があります。)
また、条文2項にあるように、不法行為をそそのかした人(教唆者:きょうさしゃ)や、手助けした人(幇助者:ほうじょしゃ)も、共同不法行為者とみなされ、連帯責任を負います。
この共同不法行為が成立すると、加害者となった複数人は、被害者に対して「連帯責任(れんたいせきにん)」を負います。これは、被害者は、加害者のうちの誰か一人に対して、損害額の全額を請求できる、という意味です。被害者にとっては、資力のある加害者を選んで請求できるため、損害の回復がより確実になるというメリットがあります。
加害者間の求償関係はどうなる?
では、連帯責任を負った加害者の一人(例えばAさん)が、被害者(Cさん)に損害の全額(または一部)を賠償した場合、そのAさんは、他の共同不法行為者(Bさん)に対して、何も請求できないのでしょうか?
そんなことはありません。賠償金を支払ったAさんは、他の共同不法行為者Bさんに対して、「君の責任分も私が代わりに払ったんだから、その分を返してくれ!」と請求(求償)することができます。
この求償できる金額(割合)は、それぞれの加害者の「負担部分(ふたんぶぶん)」に応じて決まります。負担部分は、それぞれの過失の割合や、損害発生への寄与度などを考慮して、最終的には裁判所が判断することになります。
例:
AさんとBさんの共同不法行為でCさんに100万円の損害が発生。Aさんの過失割合が70%、Bさんの過失割合が30%と判断された場合。もしAさんがCさんに100万円全額を賠償したら、AさんはBさんに対して、Bさんの負担部分である30万円(100万円 × 30%)を求償できます。
まとめ
今回は、宅建試験の民法分野で非常に重要な「不法行為」に関する4つのテーマ、①不法行為の基本、②使用者責任、③工作物責任、④共同不法行為について、それぞれの要件、効果、責任の所在、関連するルールなどを詳しく解説しました。
盛りだくさんな内容でしたけど、それぞれの制度の違いや、特に試験で狙われやすいポイントは掴めましたでしょうか?
不法行為のルールは、私たちの日常生活や経済活動の中で起こりうる様々なトラブル(権利侵害)に対して、誰がどのように責任を負い、被害者をどう救済するかを定める、民法の根幹をなす重要な制度です。宅建試験においては、単に言葉を覚えるだけでなく、
- それぞれの不法行為がどのような場面で問題となるのか(具体例)
- 誰が(加害者本人、使用者、占有者、所有者、共同行為者など)
- どのような要件のもとで(故意・過失、瑕疵、事業執行関連性など)
- どのような責任を(損害賠償、連帯責任、過失責任、無過失責任など)
- 誰に対して負うのか(被害者、他の加害者への求償など)
といった点を、体系的に整理して理解しておくことが、得点力アップの鍵となります。
この記事の重要ポイント 再確認!
- 不法行為(基本): 故意・過失による権利侵害。損害賠償責任が発生。過失相殺(裁量)、消滅時効(物損3年/20年、人損5年/20年)、履行遅滞(不法行為時から)、生命身体侵害の相殺禁止(加害者から)などを理解。
- 使用者責任: 従業員(被用者)の事業執行に関する不法行為について、使用者も責任を負う(原則免責困難)。使用者・被用者間の求償は信義則上相当な限度。
- 工作物責任: 工作物の設置・保存の瑕疵による損害。第一次責任は占有者(過失責任、免責あり)。占有者が免責された場合、第二次責任は所有者(無過失責任、免責なし!)。
- 共同不法行為: 複数人による不法行為。加害者は被害者に対し連帯責任を負う。加害者間では、それぞれの負担部分に応じて求償が可能。
これらのポイントを一つ一つ確実に押さえるとともに、「なぜそのようなルールになっているのか?(被害者保護の要請? 損害の公平な分担? 危険責任の考え方?)」といった制度趣旨や背景にも目を向けると、単なる暗記に終わらず、より深く、忘れにくい知識として定着するはずです。過去問演習を通じて、具体的な事例でどのように適用されるのかを確認することも非常に効果的ですよ。

権利関係は範囲が広く、難しいと感じるかもしれませんが、宅建合格のためには避けては通れません。今回の記事が、皆さんの不法行為分野の理解の一助となり、合格への道を力強く後押しできれば嬉しいです。