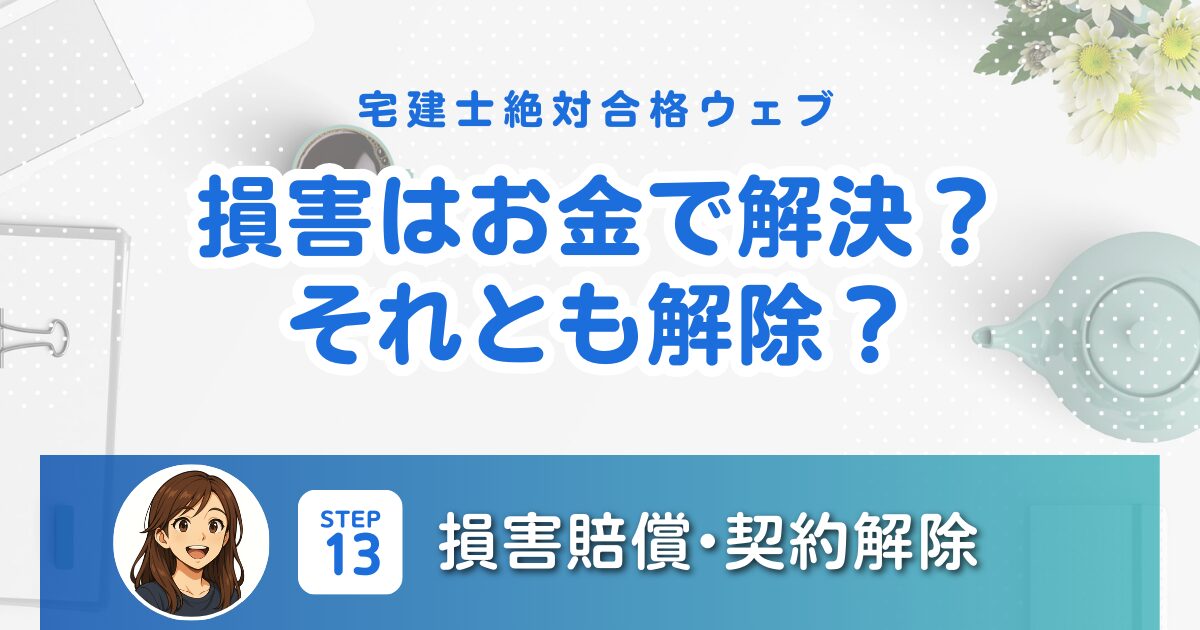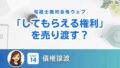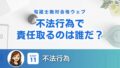権利関係の勉強をしていると、「損害賠償」とか「契約解除」って言葉、よく出てきますよね。でも、「具体的にどんな場合に請求できるの?」「解除って言っても、どうやってやるの?」「解除したらどうなるの?」って、意外と細かく聞かれると、あれ?ってなっちゃうこと、ありませんか?特に債務不履行とか不法行為とか、解除の催告がいる・いらないとか、ごちゃごちゃになりやすいですよね…。

今回は、宅建試験でも非常に重要な「損害賠償請求」と「契約解除」について、基本からしっかり解説していきますね。
これらのルールは、誰かのせいで損害を受けたり、契約の約束が守られなかったりしたときに、どうやってその問題を解決するか、という民法の基本的な仕組みなんです。特に不動産取引では、契約金額も大きくなることが多いですから、もしもの時のルールを知っておくことは、実務でもとても大切になりますよ。契約書にも必ずと言っていいほど関連条項が入っていますからね。
この記事では、損害賠償請求ができるケース(不法行為・債務不履行)や時効、被害者にも落ち度があった場合の過失相殺の考え方、そして契約解除の方法(催告が必要か不要か)や解除後の処理(原状回復義務など)、さらには解除前に第三者が関わってきた場合のルールまで、図や具体例を交えながら、わかりやすく丁寧に解説していきます。
この記事でわかること
- 損害賠償請求ができる主なケース(不法行為・債務不履行)とその要件について理解できる
- 損害賠償における過失相殺のルールと消滅時効の対策がわかる
- 契約解除の基本的な方法(催告解除・無催告解除)とその要件のポイントが整理できる
- 契約解除後の効果(原状回復義務)と第三者との関係との違いがわかる
- 宅建試験で押さえておくべき損害賠償・契約解除の重要ポイントが明確になる
損害賠償請求とは?不法行為・債務不履行での請求要件と過失相殺・時効
まずは「損害賠償請求」から見ていきましょう。なんとなく「お金を払ってもらうこと」というイメージはあると思いますが、法律上の意味やルールをしっかり理解しておくことが大切です。

ここをしっかり押さえると、トラブル解決の基本が見えてきますよ!
損害賠償請求の基本 – どんな時に請求できるの?
損害賠償請求(そんがいばいしょうせいきゅう)とは、簡単に言うと、他の人の違法な行為(ルール違反)によって自分が損害を受けた場合に、その損害を埋め合わせるために「お金を支払ってください」と請求することです。損害は、原則として金銭で評価され、その金額の支払いを求めることになります(金銭賠償の原則)。
損害賠償請求ができる代表的なケース(発生原因)は、主に以下の2つです。
① 不法行為があった場合(民法709条など)
不法行為(ふほうこうい)とは、故意(こい:わざと)または過失(かしつ:うっかり、不注意)によって、他人の権利や法律上保護される利益を違法に侵害し、それによって損害を与える行為のことでしたね。
一番イメージしやすいのは、交通事故かもしれません。他にも、隣の家の工事の騒音で体調を崩したとか、他人のペットに噛まれたとか、名誉を棄損されたとか、様々なケースがあります。
具体例:交通事故
加害者Aさんが車を運転中、スマートフォンを操作していて前方不注意となり、横断歩道を歩いていた歩行者Bさんに衝突し、Bさんにケガをさせてしまいました。この場合、Aさんの行為は「過失による不法行為」にあたります。被害者Bさんは、Aさんに対して、治療費、通院交通費、仕事ができなくなったことによる損害(休業損害)、精神的な苦痛に対する慰謝料などの損害賠償を請求できます。

② 債務不履行があった場合(民法415条など)
債務不履行(さいむふりこう)とは、契約などで約束した義務(債務)を、債務者の責めに帰すべき事由(せめにきすべきじゆう:故意や過失、またはそれに準じるもの)によって、正当な理由なく果たさないことでした。主に以下の3つのパターンがありましたね。
- 履行遅滞(りこうちたい): 約束の期限までに履行しないこと。(例:代金の支払いが遅れる)
- 履行不能(りこうふのう): 履行することが不可能になること。(例:売るはずだった建物が燃えてしまった)
- 不完全履行(ふかんぜんりこう): 一応履行はしたけれど、内容が不完全・不十分であること。(例:納品された商品の数が足りない、品質が悪い)
例えば、不動産の売買契約で、売主が約束の日に物件を引き渡さなかったり、買主が代金を支払わなかったりする場合が典型例です。
具体例:建物の引渡し遅延
売主Aさんと買主Bさんが中古マンションの売買契約を結び、10月20日に残代金の支払いと引き換えに鍵を引き渡す約束でした。買主Bさんは予定通り残代金を支払いましたが、売主Aさんが個人的な都合(引っ越し準備の遅れ)で、10月20日に鍵を引き渡すことができませんでした(Aさんの債務不履行:履行遅滞)。これにより、買主Bさんは予定していた引っ越しができず、1週間ホテルに宿泊せざるを得なくなりました。この場合、Bさんは、Aさんの債務不履行によって生じた損害(ホテル代など)について、Aさんに損害賠償請求できます。

<ポイント整理>
損害賠償請求の大きな原因は、主に「不法行為(契約関係がない場合が多い)」と「債務不履行(契約関係がある場合が多い)」の2つ! これをまずしっかり区別して押さえましょう。
被害者にも過失が… 過失相殺のルール【不法行為と債務不履行の違い】
損害が発生した原因について、加害者(債務者)だけが100%悪いとは限らないケースもありますよね。被害者(債権者)側にも不注意(過失)があった場合は、その損害の負担はどうなるのでしょうか? 「お互い様」の部分があるのに、加害者だけに全ての責任を負わせるのは公平ではありません。
そこで登場するのが「過失相殺(かしつそうさい)」という考え方です。これは、被害者(債権者)側の過失の程度に応じて、損害賠償額を減額したり、調整したりするルールです。文字通り、お互いの過失を差し引き(相殺)するようなイメージですね。
ただし、この過失相殺のルールは、損害賠償の原因が不法行為の場合と債務不履行の場合で、少し扱いが異なります。
不法行為の場合の過失相殺(裁判所の「裁量」)
不法行為(例:交通事故)による損害賠償請求の場合、被害者側にも過失があれば、裁判所は、その事実を考慮して、損害賠償の額を定めることができます(民法第722条2項)。
民法第722条(損害賠償の方法及び過失相殺)
2. 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
ポイントは、裁判所は過失相殺を「することができる」という点です。条文上は、必ずしなければならないわけではなく、裁判所の裁量に委ねられています。(ただし、実務上は、被害者に過失があれば、ほとんどの場合、その程度に応じて過失相殺が行われます)。
例:
赤信号を無視した車にはねられた歩行者のケースでも、もし歩行者にも「左右をよく確認せずに飛び出した」などの不注意(過失)があれば、その過失割合(例:10%)に応じて、受け取れる賠償額が減額されることがあります。
債務不履行の場合の過失相殺(裁判所の「義務」)
一方、債務不履行(例:契約違反)による損害賠償請求の場合、債権者(被害者)側に過失があれば、裁判所は、損害賠償の責任及びその金額を定めるにあたって、必ずその過失を考慮しなければなりません(民法第418条)。
民法第418条(過失相殺)
債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定めなければならない。
不法行為とは異なり、債務不履行の場合は、過失相殺をすることが裁判所の「義務」とされています。これは、契約という当事者間の合意に基づく関係においては、お互いに信頼関係があり、損害の発生や拡大を防ぐために協力すべき義務(信義則上の義務)がより強く期待されるため、債権者側の過失も厳格に考慮して、公平な負担を図るべき、という考え方に基づいています。
例:
先ほどの建物の引渡し遅延の例で、もし買主Bさん側にも、「売主Aさんから事前に求められていた書類の提出を怠っていた」など、引渡し遅延の原因となるような過失があった場合、裁判所は必ずその点を考慮して、Aさんが支払うべき損害賠償額を決定します。
<ここが違う!まとめ>
不法行為の過失相殺 → 裁判所の裁量(考慮できる)
債務不履行の過失相殺 → 裁判所の義務(考慮しなければならない)
この違いは、選択肢問題などで問われやすいので、しっかり区別して覚えてくださいね!
いつまでも請求できるわけじゃない!不法行為の損害賠償請求権の消滅時効
損害賠償を請求できる権利も、永遠に認められるわけではありません。一定の期間が経過すると「消滅時効(しょうめつじこう)」にかかり、権利が消滅してしまいます。「権利の上に眠る者を保護せず」という考え方ですね。
ここでは、特に期間が複雑な不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効について確認しましょう。(※債務不履行に基づく損害賠償請求権の時効は、原則として通常の債権の消滅時効のルール、つまり「権利を行使できることを知った時から5年」または「権利を行使できる時から10年(人の生命・身体の場合は20年)」が適用されます。)
不法行為の損害賠償請求権の時効は、「物損」か「人損(人の生命・身体の侵害)」かで期間が異なります。
① 財産的な損害(物損)の場合 (主観的3年 / 客観的20年)
物を壊された場合や、詐欺で財産をだまし取られた場合など、財産的な損害(物損)に関する損害賠償請求権の消滅時効は、以下のいずれか短い方の期間が経過したときです(民法第724条)。
- 主観的起算点: 被害者またはその法定代理人が「損害」および「加害者」を知った時から3年間行使しないとき。
- 客観的起算点: 不法行為の時から20年間行使しないとき。
「知った時から3年」という短い期間と、「行為の時から20年」という長期の期間、2つのリミットがある、と覚えてください。
② 人の生命または身体の侵害(人損)の場合 (主観的5年 / 客観的20年)
人の生命や身体が侵害された場合(例:交通事故でのケガや死亡)の損害賠償請求権は、被害者の保護をより厚くする必要があるため、物損よりも主観的起算点からの期間が長く設定されています(民法第724条の2)。
- 主観的起算点: 被害者またはその法定代理人が「損害」および「加害者」を知った時(権利を行使できることを知った時)から5年間行使しないとき。
- 客観的起算点: 不法行為の時(権利を行使できる時)から20年間行使しないとき。
客観的起算点の20年は物損と同じですが、主観的起算点が「3年」ではなく「5年」になっている点がポイントです。
<不法行為の時効まとめ>
・物損 → 知った時から3年 / 不法行為の時から20年
・人損 → 知った時から5年 / 不法行為の時から20年
(いずれも短い方の期間が経過すると時効完成)
数字をしっかり覚えましょう!
事前に賠償額を決めておく「損害賠償額の予定」とは?
債務不履行があった場合に、「実際にどれくらいの損害が発生したのか」を後から証明するのって、結構大変なことが多いんです。例えば、「引き渡しが遅れたせいで、予定していた転売のチャンスを逃して〇〇円損した!」とか言っても、その損害額を客観的な証拠で示すのは難しいですよね。
そこで、そうした立証の困難さを避け、紛争をあらかじめ予防するために、契約を結ぶ際に当事者間であらかじめ「もし約束違反(債務不履行)があった場合には、損害賠償として〇〇円支払う」と金額を決めておくことができます。これを「損害賠償額の予定(そんがいばいしょうがくのよてい)」といいます(民法第420条)。
損害賠償額の予定のメリット・効果
- 損害額の立証が不要: 実際に発生した損害額が予定額より多くても少なくても、原則として当事者はその予定額しか請求・支払いできません。損害の発生や損害額を具体的に証明する必要がなくなるので、手続きが簡単になります。
- 賠償額の増減は原則不可: 裁判所は、予定された賠償額を、実際の損害額に基づいて増やしたり減らしたりすることは原則としてできません(ただし、あまりに高額で公序良俗に反する場合は別)。
- 紛争の予防: 支払うべき金額が明確なので、後で賠償額をめぐって争うことを避けやすくなります。
契約書でよく見かける「違約金(いやくきん)」という名目で定められることもありますが、特に区別がなければ、法律上は損害賠償額の予定と推定されます。
【宅建業法】売主が宅建業者の場合の特別ルール(代金の20%上限)
不動産取引、特に私たち宅建業者が自ら売主となって、一般の買主(宅建業者ではない人)に宅地や建物を売る場合には、買主保護のための特別なルールが宅建業法で定められています。
宅建業法では、損害賠償額の予定や違約金を定める場合、それらを合算した額が「代金の額の10分の2(=20%)」を超えてはならない、と厳しく制限されています(宅建業法第38条)。
<超重要!宅建業法上の制限>
宅建業者が売主の場合、損害賠償額の予定+違約金 ≦ 代金の20%
もし、契約でこれを超える金額(例えば代金の30%とか)を定めても、その20%を超える部分は無効になります。(契約全体が無効になるわけではなく、超過部分だけが無効です)。買主は、最大でも代金の20%までしか支払う義務を負いません。
例:
宅建業者Aが売主、一般消費者Bが買主で、代金5,000万円の新築マンションの売買契約を締結。契約書に「買主Bの債務不履行の場合、違約金として代金の30%(1,500万円)を支払う」と定められていても、宅建業法38条により、1,000万円(代金の20%)を超える部分(500万円)は無効となります。Bが実際に支払う義務があるのは、最大1,000万円までです。
このルールは、知識や交渉力で劣る一般消費者が、不当に高額な違約金を請求されるのを防ぐためのものです。宅建士としては必須の知識ですね!
契約解除のルールをマスター!解除方法・効果・原状回復・第三者保護
次に、「契約解除」について詳しく見ていきましょう。契約関係を終了させるための、損害賠償と並んで重要な手段です。
契約をなかったことに!契約解除の基本的な考え方
契約解除(けいやくかいじょ)とは、一度は有効に成立した契約について、当事者の一方(または双方)の意思表示によって、契約の効力を最初(契約締結時)にさかのぼって消滅させることです。
つまり、契約を「はじめからなかったこと」にする、という強力な効果を持ちます。契約を結んだけれど、相手が約束を守ってくれない(債務不履行)などの場合に、その契約の拘束力から解放され、支払った代金などを取り戻すための重要な手段となります。
どうやって解除する?催告解除と無催告解除
では、具体的にどうすれば契約を解除できるのでしょうか? 民法では、解除の方法として、原則的な方法と、例外的にすぐに解除できる方法を定めています。
① 原則は「催告解除」 – 相当期間を定めてチャンスを与える
契約解除の原則的な方法は、まず相手方(債務を履行しない当事者)に対して「相当の期間」(例:「1週間以内に」など)を定めて、「その期間内に約束を果たしてください(履行してください)」と催告(さいこく:要求すること)し、それでも相手がその期間内に履行しない場合に、初めて契約を解除できる、というものです(民法第541条本文)。これを「催告解除」と言います。
民法第541条(催告による解除)
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
「相当の期間」が具体的に何日間かはケースバイケースですが、相手が準備して履行するのに通常必要と考えられる期間のことです。いきなり「解除だ!」と言うのではなく、まずは相手に履行する最後のチャンスを与えましょう、という考え方に基づいています。
ただし、催告期間が過ぎても履行されなかった場合でも、その不履行が契約全体から見て「軽微」な場合(ほんの少し遅れただけ、ほんの少し足りないだけ、など)は、解除までは認められない、という例外もあります。
② 例外的にすぐ解除できる「無催告解除」のケース
しかし、状況によっては、催告して履行を待っても意味がないような場合や、催告すること自体が相手にとって酷(こく)な場合があります。そのような場合には、催告をしなくても直ちに契約を解除することができます。これを「無催告解除(むさいこくかいじょ)」と言います。
民法で定められている、無催告解除ができる主なケースは以下の通りです(民法第542条)。
- 全部履行不能: 債務の全部の履行が不能であるとき。
(例:売買契約の目的物である特定の建物が、引渡し前に火事で全焼してしまった場合。もう物理的に引き渡せないので、催告しても無意味ですよね。) - 全部履行拒絶: 債務者が債務の全部の履行を明確に拒絶する意思を表示したとき。
(例:売買契約の売主が、「気が変わったから、絶対にあの土地は売らない!」と買主に明確に言い切った場合。催告しても履行する気がないのは明らかなので、すぐに解除できます。) - 一部不能・一部拒絶で目的達成不可: 債務の一部が履行不能である場合、または債務者が一部の履行を明確に拒絶した場合において、残りの部分だけでは契約をした目的を達することができないとき。
(例:結婚式で使う新郎新婦のペア衣装を注文したが、新婦のドレスだけが納品不能になった場合。新郎の衣装だけもらっても意味がないので、全体を無催告解除できます。) - 定期行為の履行遅滞: 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行されなければ契約をした目的を達することができない場合(これを「定期行為」といいます)に、その時期を経過したとき。
(例:誕生日のためのバースデーケーキの配達が、誕生日当日の夜までにされなかった場合。翌日に届けられても意味がないですよね。) - (催告解除の例外)催告しても無意味な場合: 上記①~④以外の場合でも、債務者が履行遅滞にあり、催告をしても債務者が履行する見込みがないことが明らかであるとき(民法第541条ただし書)。これも実質的には無催告解除に近い形です。
<催告の要否まとめ>
・原則 → 催告が必要(催告解除)
・例外(履行不能、履行拒絶、目的達成不能、定期行為など)→ 催告不要(無催告解除)
試験では、「このケースは催告が必要か不要か?」という形で問われることが多いので、しっかり区別できるようにしましょう。
契約解除の効果って?
契約が有効に解除されると、どのような法的な効果が生じるのでしょうか?
- 契約の遡及的(そきゅうてき)消滅: 解除された契約は、契約の時にさかのぼってはじめからなかったものと扱われます。これを解除の「遡及効(そきゅうこう)」と言います。
- 未履行債務の消滅: まだ履行されていない債務(例えば、まだ支払っていない代金や、まだ引き渡していない物)は、解除によって消滅し、履行する必要がなくなります。
- 原状回復義務の発生: すでに履行された部分(支払った代金や引き渡した物)については、お互いに元の状態に戻す義務が発生します(後述)。
- 形成権: 解除権は、権利を持つ人が相手方に対して「解除します」という一方的な意思表示をするだけで効力が発生します。相手方の同意や承諾は必要ありません。このような権利を「形成権(けいせいけん)」と言います。
元の状態に戻す「原状回復義務」とは?
契約が解除されて「初めからなかったこと」になると、契約に基づいてすでに行われた給付(例えば、支払ってしまった代金や、引き渡してしまった物など)は、そのままにしておくわけにはいきませんよね。
そこで、契約の解除によって、当事者はお互いに、受け取ったものを相手に返し、契約がなかった元の状態に戻す義務を負います。これを「原状回復義務(げんじょうかいふくぎむ)」と言います(民法第545条1項)。
お互いに元に戻す義務
例えば、土地の売買契約が買主の代金不払いを理由に解除された場合、
- すでに土地の引渡し(登記含む)を受けていた買主は、その土地を売主に返還する義務を負います。
- もし売主が手付金など一部の代金を受け取っていた場合は、その金銭を買主に返還する義務を負います。
【重要】金銭返還には利息!物には使用利益!
原状回復義務の内容で特に注意が必要なのは、以下の点です。
- 金銭を返還する場合: 受け取った金銭を返すときは、その金銭を受け取った時から年3%(法定利率)の利息を付けて返さなければなりません(民法第545条2項、404条)。
- 物を返還する場合: 受け取った物(例:建物)を返還する場合、その物を使用していた期間があれば、その使用によって得た利益(例:家賃相当額など)も併せて返還する必要があると解釈されています。
つまり、単純に受け取ったものを返すだけでなく、それによって得ていた利益も精算して返す、ということです。
原状回復義務は「同時履行の関係」
お互いが負うこの原状回復義務(例:売主の代金+利息返還義務と、買主の土地+使用利益返還義務)は、「同時履行の関係(どうじりこうのかんけい)」に立ちます(民法第546条が533条を準用)。
つまり、「あなたが代金を返してくれるまで、私も土地を返しませんよ」と、お互いに相手が義務を果たすまで自分の義務の履行を拒むことができるわけですね。これにより、当事者間の公平を図っています。
解除しても損害賠償は請求できる!
契約を解除したからといって、それで全てが解決するとは限りません。相手の債務不履行によって損害が発生している場合もありますよね。
民法では、契約を解除したとしても、それとは別に、相手の債務不履行によって生じた損害があれば、損害賠償を請求することを妨げない、と定めています(民法第545条4項)。
<重要!>
契約解除と損害賠償請求は両立する!
例えば、買主の代金不払いで売主が売買契約を解除した場合、売主は契約解除に加えて、もしその間に物件価格が下落して損害が出たとか、別の買主を探すための費用がかかったとかいう損害があれば、その賠償も買主に請求できる、ということです。
解除前に転売されたらどうなる?解除と第三者の関係
契約が解除されるまでの間に、契約の目的物(例えば不動産)が、当事者の一方からさらに第三者に転売されていたような場合は、どうなるのでしょうか? 解除の効果(契約が初めからなかったことになる)は、この第三者にまで及んでしまうのでしょうか?
例:
1. Aさん(売主)がBさん(買主)に土地を売却し、Bさんは代金を支払って所有権移転登記も済ませました。
2. その後、Bさんはその土地をさらにCさん(第三者)に転売し、Cさんも所有権移転登記を済ませました。
3. ところが、後日、Aさんが「Bとの契約は、Bの詐欺によるものだった!」として、AB間の売買契約を取り消しました。(※ここでは比較のため取消しを使いますが、解除でも考え方は同様です)
この場合、土地の所有権は元のAさんに戻るのでしょうか? それとも、転売を受けたCさんのものになるのでしょうか? Cさんとしては、登記まで信じて買ったのに、後から権利を失うのは困りますよね。
この点について、民法は第三者を保護する規定を置いています。ただし、契約「解除」の場合と、詐欺や強迫による「取消し」の場合、あるいは錯誤による「取消し」の場合などで、第三者保護の要件が少しずつ異なるので注意が必要です。ここでは、特に契約解除の場合のルールを確認します。
【重要】解除の場合は、登記があれば第三者が保護される(善意・悪意は問わない)
契約解除のケースでは、第三者Cさんが、その目的物について権利を保護されるための対抗要件(不動産の場合は「登記」)を備えていれば、たとえ解除の原因(例えばBの債務不履行など)について善意(知らなかった)であろうと悪意(知っていた)であろうと関係なく、保護されます(民法第545条1項ただし書)。
民法第545条(解除の効果)
1. 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
(※判例・通説は、この「第三者」は対抗要件を備えた第三者を指し、善意・悪意を問わないと解釈しています)
つまり、上の例がもし「Bの代金未払いを理由にAが契約を解除した」というケースであれば、Cさんが土地の登記を備えている限り、Aさんは解除を理由にCさんから土地を取り戻すことはできません。土地の所有権はCさんのものとして確定します。たとえCさんが「BはまだAにお金を払っていないらしい」と知っていた(悪意だった)としても、登記さえあれば保護されるのです。
<ポイント:解除と第三者>
解除の場合は、第三者の善意・悪意を問わず、登記(対抗要件)があれば保護される! これが鉄則です!しっかり覚えましょう。
詐欺取消しの場合との違いに注意!
ここで、よく比較される「詐欺による取消し」の場合の第三者保護ルールとの違いを明確にしておきましょう。混同しやすいポイントです。
詐欺による契約の取消しの場合、第三者保護のルールは以下のようになります(民法第96条3項、判例)。
- 取消し”前”に現れた第三者: 第三者が善意であり、かつ無過失であれば保護される。(登記の有無は問わない)
- 取消し”後”に現れた第三者: 取消しをした元の所有者と第三者との関係は、登記を先に備えた方が勝つという対抗問題(早い者勝ち)になる。
このように、詐欺取消しの場合は、第三者が現れたタイミング(取消しの前後)や、第三者の主観(善意無過失かどうか)によって扱いが異なります。解除の場合は、登記さえあれば善意・悪意を問わない、という点が大きな違いです。
<比較表:解除と詐欺取消しの第三者保護>
| 契約解除の場合 | 詐欺取消しの場合 | |
|---|---|---|
| 保護される第三者の要件 | 登記があれば善意・悪意を問わず保護される | 取消し前:善意無過失であれば(登記不要で)保護 取消し後:登記を先に備えた方が勝つ(善意・悪意は関係ない対抗問題) |
この違いは、試験で非常に問われやすいので、表にするなどしてしっかり整理しておきましょう!
解除権者が複数いる場合は?解除権の不可分性
契約の当事者の一方または双方が複数人いる場合(例えば、AさんとBさんが共有している土地をCさんに売却した場合など)は、解除権の行使や消滅について、特別なルールがあります。これを「解除権の不可分性(ふかぶんせい)」と言います(民法第544条)。基本的には「みんなで一緒に」という考え方です。
原則①:行使は「全員から」または「全員へ」
解除権を行使する場合、当事者の一方が複数人いるときは、契約の解除は、その全員から、またはその全員に対してしなければなりません(民法第544条1項)。
例:A・B共有の土地をCに売却した場合、買主Cが契約を解除するには、AとBの両方に対して解除の意思表示をする必要があります。逆に、売主A・Bが解除したい場合は、AとBの両方が共同でCに対して解除の意思表示をする必要があります。Aだけが勝手に解除することはできません。
原則②:消滅も「一蓮托生」
当事者の中の一人について解除権が消滅したときは、他の者についても解除権は消滅します(民法第544条2項)。
例:上の例で、もし売主Aの解除権だけが、時効にかかったり、Aが解除権を放棄したりして消滅した場合、Bの解除権もそれに引きずられて一緒に消滅してしまいます。Bだけが後から解除することはできなくなります。
このように、解除権は、行使するときも消滅するときも、基本的にセットで扱われる(不可分)のが原則です。
<例外もある>
ただし、この解除権の不可分性の原則には例外もあります。例えば、共有物の賃貸借契約の解除については、民法の共有に関する規定(管理行為は持分価格の過半数で決する)が優先されると考えられており、賃貸人である共有者全員の一致がなくても、過半数の賛成で解除できる場合があります。細かい点ですが、頭の片隅に置いておくと良いかもしれません。
まとめ
今回は、宅建民法の重要テーマである「損害賠償請求」と「契約解除」について、それぞれの基本的な考え方、要件、効果、そして関連する重要なルール(過失相殺、時効、原状回復、第三者保護、不可分性など)を詳しく解説しました。

どちらも契約に関連するトラブルが発生した際の解決手段として、非常に大切なルールでしたね。特に試験で問われやすいポイントを中心に、整理できましたでしょうか?
損害賠償請求は、不法行為や債務不履行によって受けた損害を金銭で回復するための手段です。その際には、被害者側の過失も考慮される「過失相殺」のルール(不法行為と債務不履行で扱いが違う点に注意!)や、権利が消滅してしまう「消滅時効」の期間(不法行為の物損・人損での違い)をしっかり理解しておくことが重要です。
また、宅建業者が売主となる場合の「損害賠償額の予定」の上限(代金の20%)は、宅建業法からの出題としても頻出なので、絶対に覚えておきましょう。
契約解除は、契約の拘束力から解放されるための手段です。原則として「催告解除」ですが、履行不能や履行拒絶などの特定のケースでは「無催告解除」ができるという区別、解除によって契約が遡及的に消滅し「原状回復義務」が生じること(金銭には利息、物には使用利益を付加し、同時履行の関係)、そして解除と損害賠償は両立することなどを押さえておく必要があります。
この記事のポイント 再確認!
- 損害賠償請求: 主な原因は不法行為と債務不履行。損害を金銭で賠償。
- 過失相殺: 不法行為では裁判所の裁量(考慮できる)、債務不履行では義務(考慮必須)。
- 不法行為の時効: 物損は知った時から3年/行為時から20年、人損は知った時から5年/行為時から20年。
- 損害賠償額の予定: 事前の取り決め。立証不要。宅建業者が売主の場合、代金の20%が上限(宅建業法)。
- 契約解除: 原則は催告解除。例外(履行不能、履行拒絶、定期行為など)は無催告解除。
- 解除の効果: 遡及効(初めから無効)。原状回復義務(金銭+利息、物+使用利益、同時履行)。
- 解除と損害賠償: 両立する。
- 解除と第三者: 登記があれば善意・悪意を問わず第三者が保護される。
- 解除権の不可分性: 原則、行使も消滅も全員で。
これらのルールは、一見すると覚えることが多くて大変に感じるかもしれません。でも、一つ一つのルールが「なぜそうなっているのか?(当事者間の公平を図るため? 被害者を保護するため? 取引の安全を守るため?)」という理由や趣旨を考えながら学習すると、単なる暗記ではなく、生きた知識として身につきやすくなります。
今回学んだ損害賠償と契約解除の知識を武器に、自信を持って試験に臨めるよう、頑張ってくださいね!