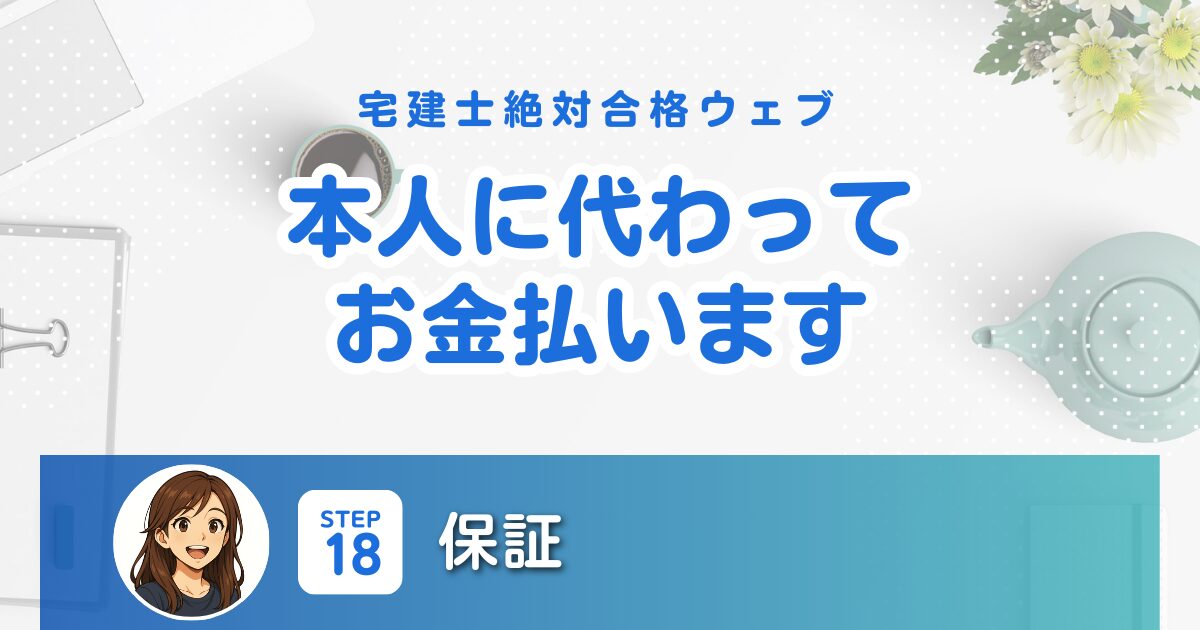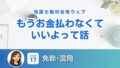権利関係、特に民法の債権のところって、普段聞き慣れない言葉がいっぱいで、ちょっと大変ですよね。「保証」っていう言葉はニュースとかで聞くけど、「連帯保証」とは何が違うの?とか、「物上保証人」って初めて聞いた!どんな人?「求償権」って、なんだか難しそう…なんて、疑問符がいっぱい浮かんでいませんか?
「保証」って、お金を貸す側(債権者さん)からすると、ちゃんとお金を返してもらうための安心材料になるし、借りる側(債務者さん)にとっては信用度がアップするメリットがあるんだけど、保証人になる人にとっては、かなりの覚悟が必要な大きな責任が伴います。だからこそ、どんなルールになっているのか、ちゃんと知っておくことがすごく大切なんです。
この記事では、保証契約ってそもそも何?っていう基本から、保証人になったらどこまで責任を負うの?保証人にも言い分ってあるの?(抗弁権)、そして、物上保証人って普通の保証人と何が違うの?立て替えたお金はどうなるの?(求償権)といった関連知識まで具体例を使いながら、できるだけわかりやすく解説していきます!

保証のルールはちょっと複雑だけど、一つずつ見ていけば大丈夫!一緒に頑張りましょうね!
<この記事でわかること>
- 保証契約の基本的な仕組みと登場人物について理解できる
- 保証人が負う責任の範囲と保証債務の性質(付従性・随伴性)がわかる
- 保証人が主張できる権利(催告の抗弁権・検索の抗弁権)のポイントが整理できる
- 物上保証人とは何か、普通の保証人との違いが明確になる
- 求償権とは何か、どんなときに誰に対して使えるのかがわかる
保証契約の基本!保証人のなり手・義務・権利(催告・検索の抗弁権)
まずは、基本となる「保証」の仕組みから、しっかり見ていきましょう。
保証とは? – 主債務者が払えない時に肩代わりする約束
保証っていうのは、主たる債務者(しゅたるさいむしゃ:お金を借りた本人とか、本来義務を負う人)がその債務(借金とか)をちゃんと履行しない場合に、保証人が代わりにその履行をする責任を負いますよ、という契約のことです(民法第446条)。
もっと簡単に言うと、「もし、お金借りた本人が返せなくなっちゃったら、私が代わりに払います!」っていう約束のことですね。
【例で見てみよう!】
Aさん(主たる債務者)がBさん(債権者)から1,000万円を借りました。そのとき、Cさん(保証人)が「Aさんが返せなかったら私が保証します」とBさんと約束(保証契約)しました。
もしAさんがBさんにお金を返せなくなったら、CさんはBさんに対して、Aさんの代わりに1,000万円を支払う義務を負うことになります。
保証契約は誰と誰が結ぶ? – 債権者と保証人!
ここで、意外と「あれ?」ってなりがちなポイント!しっかり押さえてくださいね。
保証契約っていうのは、お金を貸した側(債権者:上の例だとBさん)と、保証人になる人(Cさん)との間で結ばれる契約です。
よく、お金を借りるAさんが、友達とか親戚のCさんに「お願い!保証人になって!」って頼むシーンがありますよね。でも、保証契約そのものは、AさんとCさんの間で結ぶわけじゃなくて、あくまでBさんとCさんの間の契約なんです。ここ、間違えないようにしましょうね!
誰でも保証人になれる?保証人の資格について
保証人になるのに、何か特別な資格とか条件って必要なのでしょうか?
これは、誰が保証人を指名するかによって、少しルールが違います。
- 債権者(お金を貸すBさん)が保証人を指名する場合:
特に法律上の資格要件はありません。債権者のBさんが「この人(Cさん)なら大丈夫だろう」とOKすれば、基本的には誰でも(もちろん、Cさん本人のちゃんとした同意が必要ですよ!)保証人になることができます。 - 主たる債務者(お金を借りるAさん)が保証人を立てる義務を負っている場合:
例えば、賃貸借契約で「保証人を立てること」が義務付けられている場合などですね。この場合は、保証人になる人は、①「行為能力者」であること(例えば、未成年者や成年被後見人などでないこと)、かつ、②「弁済をする資力(お金を支払う能力)があること」が求められます(民法第450条1項)。もしAさんが、これらの条件を満たさない人を保証人として立ててきた場合、Bさんは「ちゃんとした別の人を保証人にしてください!」って請求できます。
【重要】保証契約は口約束じゃダメ!書面等が必要!
これは絶対に覚えてほしい、超重要ポイントです!
保証契約は、口約束だけでは法的に成立しません!必ず、「書面」で契約するか、または「電磁的記録(パソコンで作った契約書ファイルとか、メールとか)」でその内容が記録されていないと、効力が生じないんです(民法第446条2項、3項)。
【注意!】
どんなに親しい間柄でも、電話や口頭で「わかった、保証人になるよ!」と言っただけでは、法律上、保証契約は成立していません!無効なんです。
なんでこんなルールがあるかというと、保証人になるっていうのは、すごく重い責任を負うことになるから。軽い気持ちで「いいよ!」って言っちゃって、後で大変なことにならないように、書面とかデータっていう形でちゃんと残すことで、「本当に保証人になりますか?」って慎重に考えてもらうためなんですね。
保証人はどこまで責任を負う?保証債務の範囲
じゃあ、保証人になったら、具体的にどこまでの範囲のお金を払う責任があるんでしょうか?
保証人が負う保証債務の範囲は、主たる債務に関する元本(借りたお金そのもの)だけじゃなくて、それにかかる利息、違約金、損害賠償、その他その債務に付随する全てのものが含まれるのが原則です(民法第447条1項)。結構広いですよね!基本的には、主たる債務者のAさんが負うべきものぜーんぶをカバーする、って考えてください。
ただし、保証契約を結ぶときに、「保証するのは元本の1,000万円だけね」とか、「保証するのは最大でも500万円までね」みたいに、保証の範囲を限定する特別な約束(特約)をすることもできます。この特約があれば、保証人はその範囲内で責任を負えばOKです。
あと、これも大事なポイントですが、保証人の責任が、元の主たる債務者の責任よりも重くなることはありません。例えば、Aさんの借金の利息が年5%なのに、保証契約で「Cさんの保証債務の利息は年10%ね!」って勝手に決められても、Cさんが払う利息は元のAさんと同じ年5%までです(民法第448条)。保証人だからって、元より重いペナルティを負わされることはないんですね。
主債務に従う運命?保証債務の「付従性」と「随伴性」
保証債務には、主たる債務との間に切っても切れない関係を示す、2つの大事な性質があります。「付従性(ふじゅうせい)」と「随伴性(ずいはんせい)」です。ちょっと難しい言葉だけど、内容はそんなに難しくないですよ!
付従性 – 主債務が消えれば保証も消える
付従性っていうのは、保証債務は、あくまで主たる債務があって初めて存在する「影」のようなものだ、っていう性質です。だから、主たる債務が有効に成立していなかったら保証債務も成立しないし、主たる債務が消滅したら、保証債務も一緒に消滅するんです。主たる債務に「付(つ)き従(したが)う」ってイメージですね。
【具体例で見てみよう!】
AさんがBさんに借りた1,000万円のうち、200万円を返済したら、保証人Cさんの保証債務も、当然200万円減って、残り800万円になります。もしAさんが借金を全額返し終わったら、Cさんの保証債務も完全にゼロになります。
もし、BさんとCさんの間で保証契約を結んだ後に、AさんがBさんから勝手に追加で500万円を借り増ししたとしても、Cさんが保証する義務があるのは、最初の保証契約で約束した1,000万円の範囲だけです。後から増えた借金まで、Cさんが自動的に保証することにはなりません。
随伴性 – 債権が譲渡されれば保証もついていく
随伴性っていうのは、主たる債権(BさんがAさんにお金を返してもらう権利)が、Bさんから他の人(例えばDさん)に譲渡された場合、原則として、保証債務(Cさんから代わりに支払ってもらえる権利)も、その主たる債権と一緒に、新しい債権者のDさんに移転する、っていう性質です。主たる債権に「伴(ともな)って随(したが)って」保証も移動する、って感じです。
【具体例で見てみよう!】
債権者のBさんが、Aさんに対する貸金債権(Cさんの保証付き!)を、Dさんに売り渡した場合、保証人Cさんの保証義務は、これからは新しい債権者になったDさんに対して負うことになります。DさんはCさんに「Aさんが払わないなら、あなたが保証人だから払ってね」って言えるようになるんですね。

保証債務は主たる債務と一心同体、運命共同体みたいな感じなんですね。
保証人にも言い分がある!催告の抗弁権と検索の抗弁権
保証人って、なんだか責任ばっかり重くて大変そう…って思いますよね。でも、ちゃんと保証人を守るための権利も用意されているんです。それが「催告(さいこく)の抗弁権」と「検索(けんさく)の抗弁権」です。これは、債権者からいきなり「払って!」って言われたときに、「ちょっと待って!」って反論できる権利のことです。
【超重要!】
ただし、これらの権利は、後でちょっと触れる「連帯保証人」には認められていません! 普通の保証人だけの特権なので、しっかり区別してくださいね!
催告の抗弁権 – 「まず本人に請求して!」
催告の抗弁権っていうのは、債権者(Bさん)が、主たる債務者(Aさん)に請求する前に、いきなり保証人(Cさん)のところにやってきて「Aさんの借金、あなたが代わりに払ってください!」って請求してきた場合に、保証人Cさんが「いやいや、私に言う前に、まずは本人(Aさん)に請求してくださいよ!」って主張できる権利のことです(民法第452条)。
確かに、まずは本人に請求するのがスジってもんですよね!
検索の抗弁権 – 「まず本人の財産から取って!」
検索の抗弁権っていうのは、債権者Bさんが、ちゃんと主たる債務者Aさんに請求したんだけど払ってもらえなくて、それで保証人Cさんのところに請求に来た、っていう場合に、保証人Cさんが「ちょっと待ってください!Aさんには支払い能力(資力)もあるし、しかも差し押さえできる財産(例えば給料とか預金とか)も簡単に見つかるはずですから、まずはそっちから取り立ててくださいよ!」って主張できる権利のことです(民法第453条)。
ただ、この検索の抗弁権を主張するためには、保証人Cさん自身が、次の2つのことを証明しなきゃいけないんです。
- 主たる債務者Aさんに、弁済をする資力(支払い能力)があること。
- その執行(財産の差し押さえとか)が、容易(簡単)にできること。
これを証明するのって、実際には結構ハードルが高いんです。「Aさんにはお金があるはずだ!」って言うだけじゃダメで、具体的にどの財産を差し押さえられるかとかを示さないといけないので、なかなか使うのが難しい権利とも言われています。
【注意】これらの権利が使えない場合もある!
保証人を守るための催告の抗弁権と検索の抗弁権ですが、残念ながら使えないケースもあります。
催告の抗弁権が主張できない場合:(検索の抗弁権は関係なく、主張できます)
- 主たる債務者Aさんが、破産手続開始の決定を受けたとき。(もう支払い能力がないことが公的に認められているから)
- 主たる債務者Aさんの行方が知れないとき。(どこにいるかわからない人に請求しても意味がないから)
そして、何度も言いますが、「連帯保証人」には、この催告の抗弁権も、検索の抗弁権も、どちらも全く認められていません!
だから、連帯保証人になると、債権者からいきなり「払ってください」って言われても、「まず本人に言って」とか「本人の財産から取って」とかは一切言えないんです。主たる債務者とほぼ同じ立場、ものすごく重い責任を負うことになる、ってことですね。
物上保証とは?自分の財産で他人の借金を担保する仕組み
次に、「物上保証(ぶつじょうほしょう)」について見ていきましょう。これは、普通の保証とはちょっと違うやり方で、借金などの債務を担保する方法なんです。
物上保証人の立ち位置 – 担保を提供するだけの人
物上保証人っていうのは、自分自身はお金を借りたりしたわけじゃない(債務を負っていない)んだけど、他の人(主たる債務者)が負っている債務のために、自分が持っている財産(主に土地や建物などの不動産が多いです)を担保として提供した人のことを言います。
【例で見てみよう!】
Aさん(息子さん)が、事業を始めるためにBさん(銀行)から1,000万円を借りました。でも、Aさん自身には担保になるような財産がありませんでした。そこで、Cさん(お母さん)が、自分が持っている土地に、Aさんの借金のためにBさん(銀行)の抵当権を設定してあげました。
この場合、お母さんのCさんが「物上保証人」です。Cさんは、息子Aさんの借金を、お金で保証するんじゃなくて、「自分の土地」という「物(ぶつ)」で保証しているわけですね。だから「物上」保証人って言うんです。
普通の保証人との大きな違い – 弁済義務はない!
物上保証人さんの一番大事な特徴は、ここです!
物上保証人さんは、自分自身が借金を払う義務(弁済義務)を負っているわけではない、っていう点です!
普通の保証人さんや、さっき出てきた連帯保証人さんは、主たる債務者のAさんが払わなかったら、代わりに「お金を支払う義務」を負いますよね?
でも、物上保証人Cさんは、あくまで自分の土地を担保に入れただけ。だから、たとえ息子Aさんが借金を返せなくなっても、Cさん自身がB銀行に対して、ポケットマネーから借金を支払う義務は一切ないんです!
「物上保証人は、お金を払う義務はない!」
これが、普通の保証人との決定的な違いです!しっかり覚えてくださいね!
物上保証人の責任範囲 – 提供した財産の価値が限度
じゃあ、物上保証人さんは、どんな責任を負うことになるんでしょうか?
もし、主たる債務者のAさんが借金を返せなくなったら、債権者のB銀行は、担保として提供されているCさんのお母さんの土地(抵当不動産)を、裁判所に申し立てて競売(けいばい)にかけることができます。そして、その土地が売れたお金(売却代金)から、貸したお金を回収するんです。
つまり、物上保証人Cさんの責任っていうのは、担保として提供した財産(この場合は土地)の価値の範囲内に限定される、っていうことです。最悪の場合、担保に入れた土地は失ってしまうかもしれないけれど、それだけなんです。
もし、土地を競売しても、借金1,000万円全額は回収できなかったとしても、Cさんが足りない分を自分の他のお金で支払う必要は全くありません。提供した財産を失うだけで、責任はそこで終わり。これを専門用語で「物的有限責任(ぶつてきゆうげんせきにん)」と言います。責任が「物」の価値に「限定」されている、っていう意味ですね。

物上保証人って、最悪でも担保に入れた土地とか家を失うだけで済むんだ!普通の保証人よりは、リスクが限定されている感じなんですね。安心感がちょっと違うかも。
求償権とは?立て替えたお金を取り返す権利!保証人も物上保証人も
最後に、「求償権(きゅうしょうけん)」について見ていきましょう。これは、保証人さんや物上保証人さんが、主たる債務者のAさんのために、何かを負担した場合(お金を払ったり、財産を失ったりした場合)に、その負担した分を「返してね!」ってAさんに請求できる権利のことです。
求償権の基本 – 「立て替えた分、返してね!」
求償権っていうのは、他の人のために、借金を代わりに払ったり(弁済)、自分の財産を提供したりした人が、その本来払うべきだった人(主たる債務者など)に対して、「私があなたの代わりに負担した分を、私に払い戻してくださいね」って求めることができる権利のことです。
すごく簡単に言うと、「あなたの代わりに払っておいた分、返してね!」とか「あなたのせいで失った財産の分、弁償してね!」っていう権利ですね。
保証人が弁済した場合の求償 – 主たる債務者へ請求
保証人Cさんが、主たる債務者Aさんの代わりに、債権者Bさんに借金を弁済した場合、その保証人Cさんは、主たる債務者Aさんに対して求償権を取得します(民法第459条)。
Cさんは、自分がBさんに支払ったお金(元本だけじゃなくて、利息や遅延損害金も含みます)に加えて、弁済した日以降に発生する法律で定められた利息(法定利息)とか、弁済するためにどうしても必要だった費用(例えば、弁護士さんに頼んだ費用とか)なんかも上乗せして、Aさんに「払って!」って請求することができるんです。
物上保証人も求償できる! – 担保物がなくなった分
お金を払う義務はなかった物上保証人さんですが、ちゃんと求償権を持つことができます!
物上保証人Cさんが提供した担保の土地が、債権者Bさんによって競売にかけられて、その売れたお金で主たる債務者Aさんの借金が支払われた(弁済された)場合、物上保証人Cさんは、その弁済された金額に相当する分を、主たる債務者Aさんに対して「あなたの借金のせいで私の土地がなくなったんだから、その分のお金を返して!」って求償することができるんです(民法第351条、第372条で準用)。
たとえ、土地を競売しても借金の一部しか返せなかったとしても、その返せた部分についてはちゃんと求償できます。自分の大事な財産を、Aさんのために失ったわけですから、その分を請求できるのは当たり前っちゃ当たり前ですよね。
連帯保証人同士でも求償できる? – 負担部分を超えた場合
もし、連帯保証人が一人じゃなくて、複数人いる場合(例えば、BさんとCさんが二人ともAさんの連帯保証人になった場合)はどうなるでしょう?
この場合、連帯保証人の間では、普通、「最終的に、一人あたりどれくらいの割合で負担するか」っていう「負担部分」が決まっています(特に取り決めがなければ、頭数で割った平等な割合になります)。
そして、もし連帯保証人の一人(例えばBさん)が、自分の負担部分を超えて債権者に弁済した場合は、その超えて支払った部分について、他の連帯保証人(Cさん)に対して「あなたの分も立て替えて払ったんだから、あなたの負担分を私に払ってね!」って求償することができるんです(民法第465条、第442条)。
【例で見てみよう!】
Aさんの借金1,000万円について、BさんとCさんが二人で連帯保証人になりました。二人の間の負担部分は、特に決め事がなかったので、平等に500万円ずつとします。
もし、Bさんが債権者に1,000万円全額を一人で支払った場合、Bさんは、まず主たる債務者Aさんに対して1,000万円全額を求償できます。それとは別に、もう一人の連帯保証人であるCさんに対しても、Cさんの本来の負担部分である500万円について、「あなたの分も払ったから、500万円ちょうだい!」って求償できるんです。

保証人さんとか物上保証人さん、それに連帯保証人の間でも、ちゃんと立て替えた分を取り返せる(?)仕組みがあるんですね!これがないと、正直者がバカを見ちゃいますもんね。
まとめ
今回は、「保証」「物上保証」「求償権」について、詳しくお話ししてきました!
保証人さんの責任ってどれくらい重いのかな?とか、保証人さんにも言い分ってあったんだ!とか、物上保証人さんとは何が違うの?とか、そして、立て替えたお金ってちゃんと返してもらえるの?(求償権)とか、基本的なルール、つかめましたか?
【今日のポイントをおさらい!】
- 保証:主たる債務者が払わないときに代わりに払う義務。債権者と保証人の間で、書面か電磁的記録で契約しないとダメ!
- 保証人の責任:原則、元本・利息・損害賠償など全部カバー。でも主債務より重くはならない。付従性・随伴性あり。
- 保証人の権利:催告の抗弁権(まず本人に請求して!)、検索の抗弁権(まず本人の財産から取って!)。でも連帯保証人にはこれらの権利はない!
- 物上保証人:他人の借金のために、自分の財産(土地とか)を担保に入れる人。お金を払う義務(弁済義務)はない! 責任は、提供した財産の価値の範囲まで(物的有限責任)。
- 求償権:他人のために弁済したり財産を失ったりした場合に、その本人に「立て替えた分、返してね!」って言える権利。保証人も、物上保証人も持ってる。連帯保証人同士でも求償できる場合がある。
保証の制度は、お金を貸す人、借りる人、そして保証する人(物や人)、それぞれの立場と、どんな権利や義務があるのかを、ちゃんと正確に理解しておくことがすごく大切です。特に、保証契約は書面とかじゃないとダメっていうルール、保証人さんの「催告・検索の抗弁権」(連帯保証人にはない!)、物上保証人さんの「物的有限責任」、そして「求償権」が発生する場面とその内容は、試験でもよく問われるので、しっかり整理しておきましょうね!

ちょっと複雑なルールもあるけど、一つ一つ丁寧に見ていけば、絶対に得意分野にできるはず!過去問もたくさん解いて、知識を自分のものにしていきましょうね。