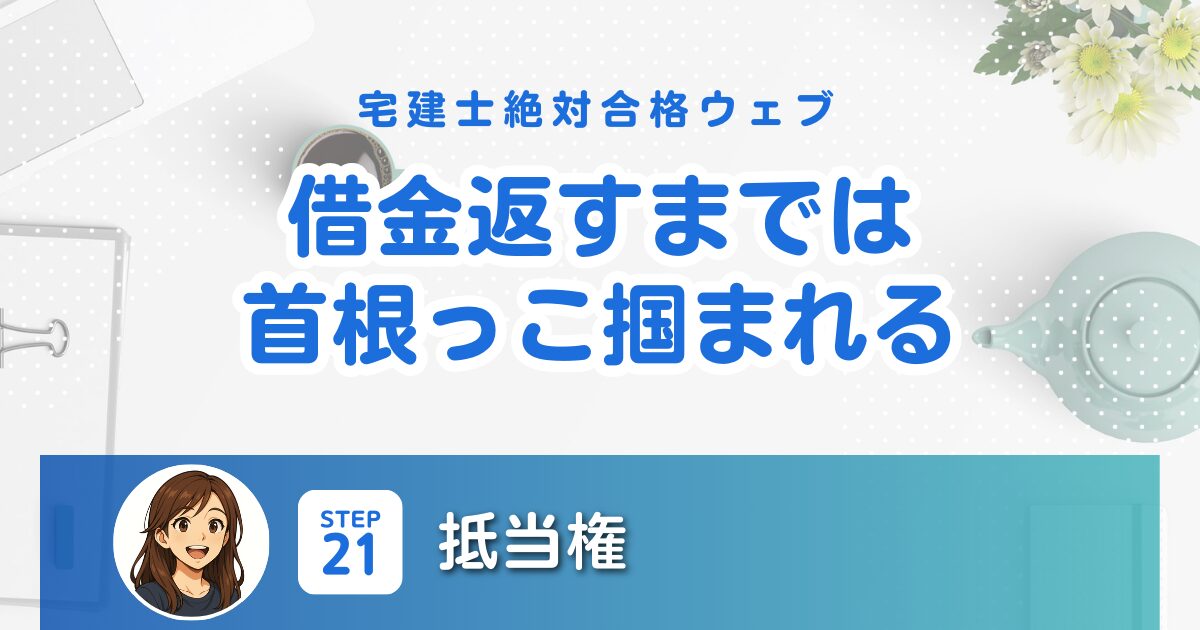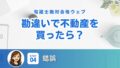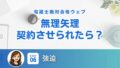宅建の勉強、お疲れさまです!権利関係の中でも、抵当権って言葉はよく聞くけど、具体的にどんなものか、どんなルールがあるのかって、ちょっと複雑でわかりにくいですよね。「担保物権の一種」って言われても、ピンとこない方もいるかもしれません。もしかして、「抵当権が付いている物件はなんだか怖い…」なんてイメージを持っていませんか?
でも、抵当権は不動産取引ではとっても身近な権利なんです。特に、住宅ローンを組むときには必ずと言っていいほど出てきます。宅建士として働く上でも、試験に合格するためにも、抵当権の仕組みをしっかり理解しておくことは、すごく大切なんですよ。
この記事では、そんな抵当権について、基本的なところから、ちょっと応用的な内容まで、わかりやすく解説していきます。抵当権の性質や効力、他の権利との関係など、試験で問われやすいポイントをしっかり押さえていきますので、安心してくださいね。

この記事を読めば、抵当権がどんな権利なのか、どんな場合にどうなるのかがスッキリ理解できるようになります。難しい法律用語も、できるだけかみ砕いて説明するので、一緒に頑張りましょう!
<この記事でわかること>
- 抵当権の基本的な仕組みと性質
- 抵当権の効力が及ぶ範囲(付合物・従物・果実)
- 抵当権の効力(競売)と順位の関係
- 抵当権付き不動産を買った人(第三取得者)を守るルール(代価弁済・抵当権消滅請求)
- 抵当権と賃借人の関係や、抵当権が侵害された場合の対抗策
【基本】抵当権ってなに?仕組みと性質を徹底解説!宅建試験で重要なポイント
まずは、抵当権の基本中の基本から見ていきましょう! ここをしっかり押さえることが、理解への第一歩ですよ。
抵当権の基本:お金を貸した時の保証!
抵当権とは、簡単に言うと、「お金を貸した側(債権者)が、お金を借りた側(債務者)が返済できなくなった場合に備えて、不動産などを担保にとる権利」のことです。これは担保物権という権利の一種なんですよ。

担保物権っていうのは、文字通り「担保」に関する「物」に対する「権利」ですね!
具体例で見てみましょう。
登場人物:
- Aさん:お金を借りる人(債務者)、土地の所有者(抵当権設定者)
- Bさん:お金を貸す人(債権者)、抵当権を持つ人(抵当権者)
状況:
- BさんがAさんにお金を貸します。(これが被担保債権、つまり担保されるお金のことです)
- その保証として、Aさんは自分の持っている土地に抵当権を設定します。
- Bさんはその土地に対する抵当権を取得します。
これが抵当権の基本的な仕組みです。
抵当権と質権の違いは?占有は誰がするの?
抵当権の大きな特徴は、「目的物の占有は債務者(抵当権設定者)のもとに留まる」という点です。
さっきの例だと、Aさんは土地に抵当権を設定した後も、引き続きその土地を自分で使い続けることができます。家を建てて住んだり、駐車場として貸したりしてもOKなんです。
これに対して、同じ担保物権でも質権(しちけん)というものがあります。質権の場合は、目的物(例えば、時計や宝石など)を債権者が預かって占有します。質屋さんをイメージするとわかりやすいかもしれませんね。
<ポイント>
- 抵当権:目的物は債務者が占有・使用し続ける。
- 質権:目的物は債権者が占有・保管する。
不動産のように、占有を移さずに利用価値を活かしたまま担保にできるのが、抵当権の便利なところなんです。
抵当権の重要な性質4つ【付従性・随伴性・不可分性・物上代位性】
抵当権には、担保物権に共通する大切な性質が4つあります。これはセットで覚えておきましょう!
<担保物権の4つの性質>
- 付従性(ふじゅうせい)
- 被担保債権(貸したお金)がなければ、抵当権も成立しません。
- 借金が返済されれば、抵当権も消滅します。
- 主役(借金)に従う脇役(抵当権)みたいなイメージです!
- 随伴性(ずいはんせい)
- 被担保債権(貸したお金を受け取る権利)が他の人に譲渡されると、抵当権も一緒にくっついて移転します。
- 債権と抵当権は常にセットで動く、ということです。
- 不可分性(ふかぶんせい)
- 被担保債権(貸したお金)が全額返済されるまで、抵当権は目的物の全部に対して効力を持ち続けます。
- 例えば、1000万円借りて500万円返済しても、抵当権が半分になったりはしません。全額返すまで、不動産全体に抵当権の効力が及んだままです。詳しくは後でまた説明しますね。
- 物上代位性(ぶつじょうだいいせい)
- 抵当権を設定した目的物(例えば建物)が火災で燃えてしまったり、収用されたりした場合、その代わりに支払われる保険金や補償金に対しても、抵当権の効力が及ぶという性質です。
- 建物がなくなっても、その価値が形を変えたもの(お金)から優先的に弁済を受けられるようにする、ということですね。
【しっかり理解】担保物権の不可分性とは?
さっき少し触れた「不可分性」について、もう少し詳しく見てみましょう。
「不可分」とは、「分けることができない」という意味です。何と何が分けられないかというと、「担保物権(抵当権)」と「被担保債権(貸したお金)」です。この二つは一体のものとして扱われます。
具体例:
- BさんがAさんに1000万円を貸し、Aさん所有の建物に抵当権を設定したとします。
- Aさんが頑張って借金を返し、残りが100万円になったとしても、Bさんの抵当権は、建物全体に対して効力を持ち続けます。
- 借金の一部だけ返しても、抵当権の一部だけが消えるということはありません。
- Aさんが1000万円全額を返すまで、抵当権は消滅しないということです。

「あと少しだから抵当権外して!」とは言えないんですね。
何に設定できる?抵当権の目的物【不動産・地上権・永小作権】
抵当権はどんなものに設定できるのでしょうか? 民法で定められています。
<抵当権を設定できるもの>
- 不動産(土地、建物)
- 地上権(他人の土地の上に建物などを所有するために、その土地を利用する権利)
- 永小作権(小作料を支払って他人の土地で耕作や牧畜をする権利)
特に注意したいのは、賃借権(ちんしゃくけん)には原則として抵当権を設定できないという点です。

賃借権は物を借りる権利(債権)なので、物に対する権利(物権)である抵当権の対象にはならないんですね。
抵当権は売ったりできる?抵当権の処分
抵当権を持っている債権者(Bさん)は、その抵当権を、抵当権設定者(Aさん)の承諾がなくても、他の人に売ったり(譲渡)、放棄したりすることができます。
また、自分の借金の担保として、持っている抵当権にさらに質権を設定する(転質:てんしち)ことも可能です。
抵当権は、債権者(抵当権者)が比較的自由に処分できる権利です。
どこまで効力が及ぶ?抵当権の範囲【付合物・従物・果実】
建物に抵当権を設定した場合、その効力は建物本体だけに及ぶのでしょうか? 実は、それだけではありません。原則として、以下の物にも抵当権の効力が及びます。
<抵当権の効力が及ぶ範囲の例>
- 付合物(ふごうぶつ)
- 意味:元の物にくっついて一体となり、簡単には分離できない物。
- 例:土地に生えている樹木、土地に固定された庭石、建物に増築された部分など。
- 効力:抵当権が設定された前か後かに関わらず、付合物には抵当権の効力が及びます。
- 従物(じゅうぶつ)
- 意味:主となる物(主物)の経済的な効用を高めるために、それに付属させられている独立した物。
- 例:建物(主物)に対する畳や建具、ガソリンスタンド(主物)に対する洗車機や給油機など。
- 効力:原則として、抵当権設定前から存在した従物には抵当権の効力が及びます。設定後に取り付けられた従物には、原則として効力は及びません。
- ただし、特約で設定後の従物にも効力を及ぼすことは可能です。
- 果実(かじつ)
- 意味:物から生じる収益のこと。
- 例:抵当権を設定した建物を賃貸した場合の賃料(法定果実)、畑から収穫される野菜(天然果実)など。
- 効力:原則として、抵当権の効力は果実には及びません。しかし! 被担保債権について債務不履行(お金が期限までに返ってこないなど)があった後は、その後に生じた果実(賃料など)にも抵当権の効力が及ぶようになります。これを「物上代位」と言います(さっき出てきた性質の一つですね!)。
抵当権の効力が及ぶ範囲の比較表
| 種類 | 例 | 効力が及ぶか? |
| 付合物 | 樹木、庭石、増築部分 | 設定の前後を問わず及ぶ |
| 従物 | 畳、建具、ガソリンスタンドの洗車機など | 原則として設定前に存在したものに及ぶ(設定後のものには及ばない) |
| 果実 | 賃料、農作物 | 原則として及ばないが、債務不履行後はその後に生じた果実に及ぶ(物上代位) |

どこまでがセットになるか、しっかり区別しておきましょうね!
いくらまで保証される?被担保債権の範囲【元本と利息】
抵当権によって、いくらまでのお金が優先的に回収できるのでしょうか? 債権者(Bさん)はAさんにお金を貸しているので、貸したお金(元本)だけでなく、通常は利息や損害金なども発生しますよね。
抵当権で担保される(優先的に弁済を受けられる)被担保債権の範囲は、原則として以下の通りです。
- 元本
- 利息
- 遅延損害金
ただし、利息や遅延損害金については、満期となった最後の2年分についてのみ、抵当権によって優先的に弁済を受けられます。
優先弁済の範囲:元本 + 利息・遅延損害金(最後の2年分)
なぜ「最後の2年分」という制限があるのでしょうか?
これは、後順位の抵当権者や他の債権者を保護するためです。
例えば、1番抵当権者(Bさん)が、何年分もの利息や損害金を制限なく優先的に回収できてしまうと、その後に抵当権を設定した2番抵当権者(Cさん)や、他の一般債権者が回収できる分がほとんどなくなってしまう可能性があります。それでは不公平ですよね。
もし、他に抵当権者や債権者がおらず、抵当権者(Bさん)しかいない場合は、この「最後の2年分」という制限はありません。利息や損害金の全額について、抵当権の効力が及びます。
【応用】抵当権の効力と順位、第三者との関係はどうなる?
基本がわかったところで、次はもう少し踏み込んだ内容を見ていきましょう。抵当権の実際の効力や、他の権利との関係は、宅建試験でもよく問われる重要なポイントです!
抵当権の効力:競売で優先的に弁済!
抵当権の最も重要な効力は、優先弁済的効力(ゆうせんべんさいてきこうりょく)です。
これは、債務者(Aさん)がお金を返せなくなった場合(債務不履行)、抵当権者(Bさん)が、抵当権を設定した目的物(不動産など)を競売(けいばい・きょうばい)にかけて、その売却代金から、他の債権者に先立って自分(Bさん)の貸したお金を回収できるという効力です。
抵当権者が競売を申し立てることを、「抵当権を実行する」と言います。
競売ってどういうこと?
競売とは、裁判所の手続きを通じて、抵当権の目的物(不動産など)を強制的に売却し、その代金を得ることです。オークションのような形式で、最も高い価格を提示した人がその不動産を買い受ける(落札する)ことができます。
<競売の流れ>
- 債務者Aが返済不能(債務不履行)
- 抵当権者Bが裁判所に競売を申し立てる(抵当権の実行)
- 裁判所が競売手続きを開始
- 不動産の情報が公開され、入札期間が設けられる
- 最も高い価格で入札した人(買受人)が落札
- 買受人が代金を裁判所に納付
- その代金から、抵当権者Bが優先的に弁済を受ける
- 残りがあれば、後順位の抵当権者や他の債権者に配当される

競売になってしまうと、元の所有者(Aさん)は家を失ってしまうことになりますね…。
複数の抵当権がある場合どうなる?抵当権の順位
一つの不動産に対して、抵当権はいくつでも設定することができます。例えば、AさんがBさんからお金を借りて1番抵当権を設定し、その後さらにCさんからもお金を借りて同じ不動産に2番抵当権を設定する、ということが可能です。
この場合、どの抵当権者が優先的に弁済を受けられるのでしょうか? それを決めるのが抵当権の順位です。
抵当権の順位は、原則として登記された順番によって決まります。先に登記された抵当権が1番抵当権、次に登記されたものが2番抵当権…となります。
そして、競売による売却代金からの弁済は、この登記の順位に従って行われます。
<抵当権の順位と弁済の順番>
- 1番抵当権者が、自分の債権額(元本+利息等最後の2年分)の範囲内で、まず優先的に弁済を受けます。
- 売却代金に残りがあれば、次に2番抵当権者が、同様に自分の債権額の範囲内で弁済を受けます。
- 以下、順位に従って弁済が行われます。

登記って本当に大事なんですね!順番が早いほど有利になるわけです。
<例>
- 不動産の競売価格:3000万円
- 1番抵当権者Bの債権:2500万円
- 2番抵当権者Cの債権:1000万円
この場合、
- まずBさんが2500万円全額の弁済を受けます。
- 残りは3000万円 – 2500万円 = 500万円です。
- 次にCさんが、残りの500万円の弁済を受けます。(Cさんの債権は1000万円ですが、500万円しか回収できません)
優先順位は変えられる?抵当権の順位変更
登記で決まった抵当権の順位ですが、実は関係する抵当権者全員の合意があれば、変更することができます。これを抵当権の順位変更といいます。
例えば、1番抵当権者のBさんと2番抵当権者のCさんが合意すれば、Cさんを1番、Bさんを2番に入れ替えることができます。
ただし、注意点があります。
- 利害関係人の承諾が必要:もし、抵当権の順位変更によって不利益を受ける他の利害関係人(例えば、転抵当権者など)がいる場合は、その人の承諾も必要になります。
- 登記が必要:順位変更の合意をしただけでは効力は生じません。変更後の順位を登記しなければ、効力は発生しません。
<順位変更の具体例>
- A所有の不動産(担保価値1000万円)
- 1番抵当権者B:債権2000万円
- 2番抵当権者C:債権1000万円
このままでは、競売になってもCさんはほとんど回収できません。しかし、もしBさんとCさんが合意して順位を変更し、Cさんが1番、Bさんが2番となれば、Cさんは1000万円全額を優先的に回収できるようになります。(ただし、Bさんの同意が必要ですが…)
「抵当権の順位の譲渡・放棄」や「抵当権自体の譲渡・放棄」といった、さらに細かい論点もありますが、これらは少し複雑なので、まずは基本となる順位変更のルールをしっかり押さえましょう。
【要注意】抵当権付き物件を買った人(第三取得者)を守るルール
抵当権が付いたままの不動産を、AさんからCさんが購入したとします。このCさんのことを第三取得者(だいさんしゅとくしゃ)といいます。
Cさんとしては、せっかく買ったのに、元の所有者Aさんが借金を返せなかったら、抵当権者Bさんに競売にかけられて家を失ってしまうかもしれません。それは困りますよね。
そこで、このような第三取得者Cさんを保護するための制度が2つあります。それが「代価弁済(だいかべんさい)」と「抵当権消滅請求(ていとうけんしょうめつせいきゅう)」です。
この2つは、誰がアクションを起こすかが違うので、比較して覚えると理解しやすいですよ!
抵当権者から請求!代価弁済とは?
代価弁済とは、抵当権者(Bさん)が、抵当不動産を買い受けた第三取得者(Cさん)に対して、「あなたが払う(または払った)売買代金を、元の所有者Aではなく、私(Bさん)に支払ってください」と請求し、Cさんがその請求に応じて代金をBさんに支払うことで、抵当権が消滅する制度です。
<代価弁済の解説図>
登場人物:
- A:元の所有者・債務者
- B:抵当権者・債権者(Aに1000万円貸している)
- C:第三取得者(Aから抵当権付き建物を800万円で購入)
流れ:
- CがAから建物を800万円で購入(代金支払い前 or 後)
- 抵当権者Bが、第三取得者Cに対して代価弁済を請求する。
- CがBの請求に応じて、売買代金800万円をBに支払う。
- Cが支払ったことで、Bの抵当権は消滅する。

抵当権者Bさんからアクションを起こすのが「代価弁済」なんですね!
Bさんにとっては、貸した1000万円のうち800万円しか回収できなくても、全く回収できないよりはマシ、と考える場合にこの請求をすることがあります。残りの200万円は無担保の債権としてAさんに請求することになります。
代価弁済は、所有権を買い受けた人だけでなく、地上権を買い受けた人に対しても請求できます。ただし、地上権の代価を支払っても抵当権そのものが消滅するわけではなく、地上権者に対して抵当権を主張できなくなる(=地上権の負担が付いたままの抵当権になる)という点に注意が必要です。
第三取得者から請求!抵当権消滅請求とは?
抵当権消滅請求とは、抵当不動産の所有権を取得した第三取得者(Cさん)が、抵当権者(Bさん)に対して、「この金額を支払うので、抵当権を消滅させてください」と請求することができる制度です。
登場人物:(代価弁済と同じ)
- A:元の所有者・債務者
- B:抵当権者・債権者(Aに1000万円貸している)
- C:第三取得者(Aから抵当権付き建物を800万円で購入)
流れ:
- CがAから建物を購入。
- 第三取得者Cが、抵当権者Bに対して抵当権消滅請求を行う。(通常、事前にBと協議して支払う金額を決めておきます)
- CがBに合意した金額(例えば800万円)を支払う。
- Bが抵当権の抹消登記手続きに協力し、抵当権が消滅する。

今度は、買った人(Cさん)からアクションを起こすのが「抵当権消滅請求」ですね!
Cさんにとっては、この制度を使えば、後から競売にかけられる心配なく、安心して不動産を取得できます。
注意点
- 債務者・保証人は請求できない:お金を借りている本人(債務者A)や、その借金の保証人、これらの人の相続人は、抵当権消滅請求をすることはできません。「自分で借金返して消しなさい」ということです。物上保証人から不動産を買い取った債務者も同様に請求できません。
- 請求の時期:抵当権消滅請求は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前にしなければなりません。差押えられてしまった後では、もう請求できません。
- みなし承諾:第三取得者Cが抵当権消滅請求の書面を抵当権者Bに送付した後、Bがその書面を受け取ってから2ヶ月以内に競売の申立てをしない場合、Bは抵当権消滅請求を承諾したものとみなされます。Cさんは定められた金額を供託することで抵当権を消滅させることができます。
代価弁済と抵当権消滅請求の違いまとめ
| 制度名 | 誰が請求する? | 誰に対して請求する? | 目的・効果 |
| 代価弁済 | 抵当権者 (B) | 第三取得者 (C) | 第三取得者が支払う代価を弁済させ、抵当権を消滅 |
| 抵当権消滅請求 | 第三取得者 (C) | 抵当権者 (B) | 第三取得者が一定額を支払い、抵当権を消滅させる |
どちらも第三取得者を保護するための制度ですが、アクションを起こす主体が逆、と覚えておきましょう!
抵当権と賃借人の関係はどうなる?【登記が重要!】
抵当権が設定されている不動産を借りている人(賃借人)は、もしその不動産が競売にかけられた場合、どうなるのでしょうか? 追い出されてしまうのでしょうか?
ここで重要になるのが、抵当権の設定登記と賃借権の関係(対抗力)です。原則として、先に登記や引渡しなどで対抗要件を備えた方が優先されます。
登場人物:
- A:大家さん(建物の所有者・債務者)
- B:抵当権者(Aにお金を貸し、建物に抵当権を設定)
- C:賃借人(Aから建物を借りている)
パターン1:抵当権設定登記よりも「前」に賃借権の対抗要件を備えた場合
- 賃借人Cが、Bの抵当権設定登記よりも前に、賃借権の登記をするか、建物の引渡しを受けていれば(借地借家法の対抗力)、Cは抵当権者Bに対抗できます。
- つまり、もしBが抵当権を実行して競売になり、新しい所有者(買受人)が現れても、賃借人Cは「私は正当な賃借人です!」と主張でき、原則としてそのまま住み続けることができます。
パターン2:抵当権設定登記よりも「後」に賃借権の対抗要件を備えた場合
- 賃借人Cが、Bの抵当権設定登記よりも後に賃借権の登記や引渡しを受けた場合、Cは原則として抵当権者Bに対抗できません。
- 競売によって新しい所有者が現れた場合、Cはその新しい所有者に対して賃借権を主張できず、建物を明け渡さなければならないのが原則です。

後から借りた人は、競売になると基本的には出て行かないといけないんですね…。
【例外】抵当権設定後でも対抗できるケース
原則は上記の通りですが、抵当権設定後の賃借人でも、以下のような場合には抵当権者に対抗できる(競売後も出て行かなくてよい)場合があります。
- 抵当権者の同意の登記がある場合:すべての抵当権者が同意し、その同意の登記があれば、賃借人は抵当権者に対抗できます。
- (旧)短期賃貸借保護制度:これは平成16年の民法改正で廃止された制度ですが、それ以前に設定された一定の短期の賃貸借は保護される場合があります。(試験対策としては優先度低めです)
- 建物の明渡し猶予制度:抵当権に対抗できない賃借人であっても、競売による買受人の買受けの時から6ヶ月間は、建物の明渡しが猶予されます。ただし、この間も買受人に賃料相当額を支払う必要があります。
- 抵当権と賃借権の優劣は、対抗要件(登記や引渡し)を備えた時期の先後で決まるのが原則。
- 抵当権設定後の賃借人は原則不利だが、例外的な保護措置もある。
抵当権を侵害されたらどうする?抵当権侵害への対抗策4つ
抵当権は、目的物の利用を債務者の元に留めながら、その担保価値を把握する権利です。そのため、もし誰かの行為によってその担保価値が減少したり、減少しそうになったりすると、抵当権者(Bさん)は困ってしまいます。貸したお金を回収できなくなるかもしれないからです。
このように、抵当権の目的物の価値が不当に減少させられることを抵当権侵害といいます。
抵当権侵害があった場合、抵当権者は主に以下の4つの方法で対抗することができます。
1. 侵害行為差止請求(しんがいこういさしとめせいきゅう)
- どんな時?:抵当権の目的物の価値をまさに減少させようとする行為が行われている場合。
- 何ができる?:その侵害行為をやめるように請求できます。
- 例:抵当権を設定した土地の上の立派な木(付合物)を、誰かが勝手に伐採して運び出そうとしている時に、「その木を運び出すのをやめてください!」と請求できます。
2. 返還請求(へんかんせいきゅう) ※間接的なもの
- どんな時?:抵当権の目的物の一部(付合物など)が持ち去られてしまった場合。
- 何ができる?:持ち去った人に対して、その物を元の所有者(抵当権設定者Aさん)に返すように請求できます。
- 注意点:抵当権者自身(Bさん)に直接返せ、とは請求できません。あくまで「元の場所(所有者のところ)に戻せ」という請求です。なぜなら、抵当権は占有を伴わない権利だからです。
3. 不法占有者に対する明渡請求(妨害排除請求:ぼうがいはいじょせいきゅう)
- どんな時?:抵当権を設定した不動産を、権限のない第三者が不法に占拠していて、そのせいで競売時の価格が著しく下がる恐れがある場合。
- 何ができる?:抵当権者(Bさん)が、その不法占有者に対して、直接自分(Bさん)に建物を明け渡すように請求できます。(判例で認められています)
- 例:抵当権付きの空き家に、誰かが勝手に住み着いてしまった場合、抵当権の実行(競売)を適切に行うために、抵当権者が「出て行って、私に明け渡しなさい!」と請求できます。

占有できないはずの抵当権者が明渡請求できるのは、競売をスムーズに進めるための例外的な措置なんですね。
4. 不法行為に基づく損害賠償請求(そんがいばいしょうせいきゅう)
- どんな時?:抵当権侵害によって、実際に損害が発生した場合(担保価値が減少し、被担保債権の回収が不足する可能性が生じた場合)。
- 何ができる?:侵害行為を行った人に対して、その損害の賠償を請求できます。
- 例:上記の不法占有者が、占有していた土地にゴミを大量に不法投棄し、土地の価値が下がってしまった場合、そのゴミの撤去費用などを損害として賠償請求できます。
<抵当権侵害への対抗策まとめ>
| 対抗策 | 状況 | 内容 |
| 侵害行為差止請求 | 侵害行為がまさに進行中 | 行為の中止を求める |
| 返還請求 | 目的物の一部が持ち去られた | 所有者への返還を求める |
| 明渡請求(妨害排除請求) | 不法占有により競売が困難 | 抵当権者自身への明渡しを求める(例外) |
| 損害賠償請求 | 侵害により損害が発生(回収不足の可能性) | 金銭による賠償を求める |
まとめ
今回は、宅建試験でも非常に重要な「抵当権」について、基本的な仕組みから応用的な論点まで詳しく見てきました。ちょっと複雑な部分もありましたが、いかがでしたか?
抵当権は、お金の貸し借りにおける担保として、不動産取引に深く関わっています。その性質や効力、他の権利との関係性を正しく理解しておくことが、宅建士には不可欠です。
最後に、今回学んだ重要ポイントをまとめておきましょう。
- 抵当権とは:債権者が、債務者の債務不履行に備えて不動産等を担保にとる権利(担保物権)。目的物の占有は設定者に残るのが特徴。
- 抵当権の性質:付従性、随伴性、不可分性、物上代位性の4つがある。
- 抵当権の目的物:不動産、地上権、永小作権(賃借権は×)。
- 抵当権の効力が及ぶ範囲:原則として付合物(設定前後問わず)、従物(設定前のみ)、果実(債務不履行後)にも及ぶ。
- 被担保債権の範囲:優先弁済されるのは原則、元本+利息・損害金(最後の2年分)。
- 抵当権の効力:債務不履行時には競売を申し立て、その代金から優先的に弁済を受けられる(優先弁済的効力)。
- 抵当権の順位:登記の先後で決まり、弁済もその順位に従う。関係者の合意と登記で順位変更も可能。
- 第三取得者の保護:抵当権付き不動産を買った人を保護するため、代価弁済(抵当権者からの請求)と抵当権消滅請求(第三取得者からの請求)がある。
- 抵当権と賃借権:原則として対抗要件(登記・引渡し)を先に備えた方が優先。抵当権設定後の賃借人は原則対抗できないが、例外や明渡し猶予制度もある。
- 抵当権侵害への対抗策:差止請求、返還請求(所有者へ)、明渡請求(不法占有者へ)、損害賠償請求などがある。

抵当権は覚えることが多いですが、一つ一つのルールや制度の意味を理解しながら学習を進めれば、必ず得意分野にできます! 具体例をイメージしながら、繰り返し復習してみてくださいね。