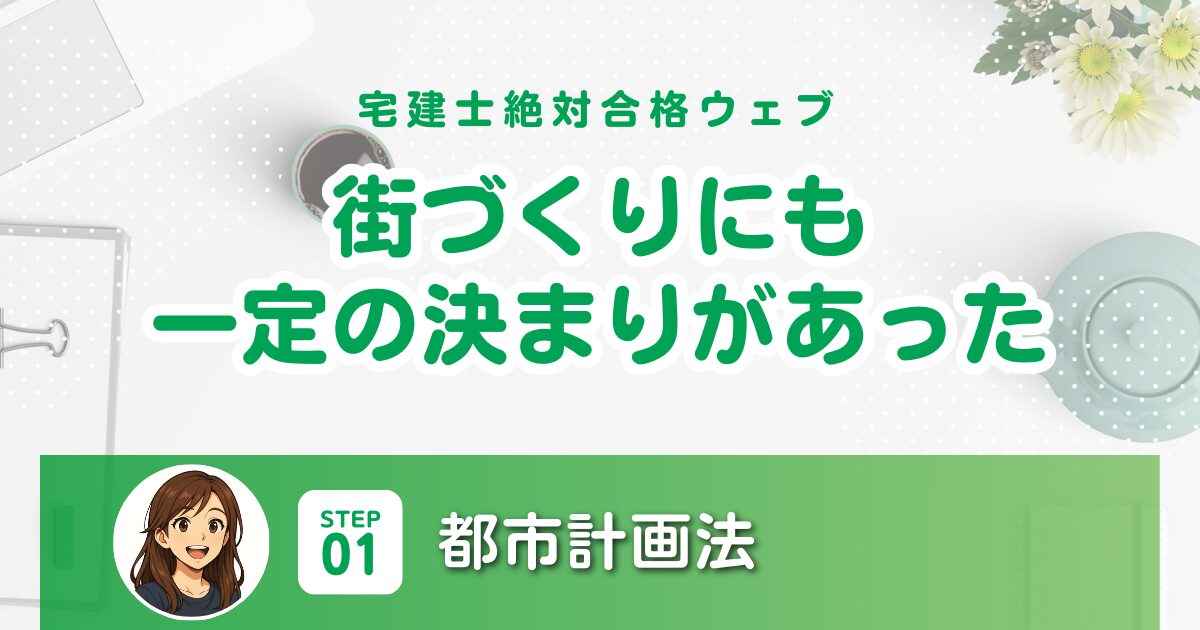宅建試験の学習範囲の中でも、「都市計画法」ってなんだか複雑でとっつきにくい…と感じていませんか? 「市街化区域」「市街化調整区域」「準都市計画区域」…似たような言葉がたくさん出てきて、頭の中がごちゃごちゃになっちゃう!なんて声もよく聞きます。
確かに、都市計画法は日本の街づくりに関する大きなルールなので、全体像を掴むのが少し大変かもしれません。でも、この法律が私たちの住む街をより良く、安全で快適にするためにどう役立っているのかを知ると、ぐっと理解が深まるはずです。それに、宅建試験では頻出の重要分野なので、避けては通れません!
この記事では、そんな都市計画法の「キホンのキ」から、特に混乱しやすい「区域の区分け」や「区域の指定手続き」、そして「準都市計画区域」といったポイントに絞って、わかりやすく解説していきます。この記事を最後まで読めば、「都市計画法って、こういう流れで街づくりを進めていく法律なんだ!」「区域ごとの違いやルールがやっと整理できた!」と思っていただけるはずです。

難しく考えず、一つずつ丁寧に見ていきましょう。都市計画法をしっかりマスターして、宅建合格に一歩近づきましょうね!
この記事でわかること
- 都市計画法の目的と街づくりの基本的な流れ
- 日本の国土がどのように区分されているか(都市計画区域、市街化区域、市街化調整区域、準都市計画区域など)
- 都市計画区域と準都市計画区域は誰がどのように指定するのか
- 都市計画区域と準都市計画区域の指定手続きの違い
- 準都市計画区域内で定められる規制(地域地区)の種類
街づくりのルール!都市計画法の目的と全体像、わかりにくい区域区分をスッキリ理解
まずは、都市計画法がどんな目的を持っていて、どんな流れで街づくりを進めていくのか、そして日本の土地がどのようにエリア分けされているのか、基本的なところから見ていきましょう。

ここをしっかり押さえることが、都市計画法理解の第一歩ですよ!
【なんのための法律?】都市計画法の目指すもの
都市計画法の大きな目的は、ひとことで言うと「健全で文化的な都市生活と機能的な都市活動を確保し、日本の国土の適切な発展と公共の福祉の増進に寄与すること」です。…ちょっと硬い表現ですね。
もっと簡単に言えば、「日本全体を、無秩序な開発から守り、計画的に、より住みやすく、機能的な街にしていくためのルール」ということです。
ここで大切なのは、「住みやすい」というのは、単に便利な商業施設がたくさんあるということだけではない、という点です。住宅地、商業地、工業地、そして緑地などの自然環境が、お互いにバランス良く配置され、調和が取れている状態を目指しています。そのための計画的な街づくりのルールを定めているのが、この都市計画法なんですね。
無秩序な開発を防ぎ、計画的な街づくりを進めるための法律、と理解しましょう。
【これで迷わない!】都市計画の大きな3つの流れ
都市計画法がわかりにくいと感じる理由の一つは、全体像が見えにくいからかもしれません。都市計画は、大きく以下の3つのステップで進められます。この流れを頭に入れておくと、個別のルールが理解しやすくなりますよ。
- 都市計画区域等の指定:まず、「どこで」街づくり計画を進めるのか、大まかなエリア(区域)を指定します。
- 都市計画の決定:次に、指定されたエリアごとに、「どんな街にするのか」具体的な計画(用途地域や道路、公園の計画など)を決定していきます。
- 都市計画制限(開発許可など):そして最後に、決定された計画を実現するために、個々の建築行為や開発行為に対して「やっていいこと」「やってはいけないこと」などの具体的なルール(制限)を設けます。
宅建試験では、この3つのステップそれぞれに関するルールが出題されます。今回は特にステップ1の「区域の指定」を中心に見ていきますね。
【超重要】日本の国土はどう分かれている?都市計画区域のキホンと種類
都市計画法では、計画的な街づくりを進めるために、日本の国土をいくつかのエリアに区分しています。この区分けが、都市計画法を理解する上で最も基本的で重要なポイントになります。
<都市計画区域等の区分の図>
(ここに、日本の国土がまず「都市計画区域」と「都市計画区域外」に分かれ、都市計画区域がさらに「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引都市計画区域」に分けられる場合があること、都市計画区域外に「準都市計画区域」が指定される場合があることを示すシンプルな図を挿入するイメージです)
都市計画区域とは?その中の3つのエリア(市街化区域・市街化調整区域・非線引区域)
まず、日本の国土は大きく「都市計画区域」と「都市計画区域外」に分けられます。
都市計画区域とは、一体の都市として総合的に整備・開発・保全する必要がある区域として指定されたエリアです。いわば、計画的な街づくりのメインステージとなる場所ですね。
そして、この都市計画区域は、その性質に応じてさらに以下の3つのいずれかに区分されることがあります(区分されない場合もあります)。
市街化区域:すでに市街地を形成している区域(既成市街地)または、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域積極的に建物を建てて、街として発展させていこう!というエリアです。
用途地域などを定めて、計画的な開発を誘導します。
市街化調整区域:市街化を抑制すべき区域。原則として、むやみに建物を建てたり開発したりするのは控えましょう、というエリアです。農地や森林などを守り、無秩序な市街地の拡大を防ぐ役割があります。
開発行為は原則として許可されません。「禁止」ではなく「抑制」という点に注意してくださいね。
非線引都市計画区域(ひせんびきとしけいかくくいき):上記の市街化区域にも市街化調整区域にも区分されていない都市計画区域のこと。
まだ市街化区域にするか調整区域にするか、はっきり線引き(区域区分)をしていない、中間的なエリアです。地方の都市計画区域などに多く見られます。
都市計画区域外とは?準都市計画区域ってなに?
都市計画区域として指定されなかったエリアが「都市計画区域外」です。
そして、この都市計画区域外の中にも、特別な注意が必要なエリアがあります。それが「準都市計画区域」です。
準都市計画区域:都市計画区域外の区域のうち、相当数の建築物などが既に存在したり、これから建築される見込みがあったりして、そのまま放置すれば、将来の計画的な街づくりに支障が生じるおそれがあると認められる区域
今はまだ都市計画区域ではないけれど、将来的に発展しそうな場所(例えば、高速道路のインターチェンジ周辺や主要な幹線道路沿いなど)で、今のうちからある程度のルール(土地利用の制限など)を定めておかないと、乱開発が進んで後々困ることになりそうなエリア、という感じです。準都市計画区域は、あくまで「都市計画区域外」に指定される、というのがポイントです!
「区域区分(線引き)」ってどういう意味?
先ほど出てきた「市街化区域」と「市街化調整区域」に分けることを、専門用語で「区域区分」と言います。都市計画区域に、この2つのエリアの線引きをするかどうか、ということです。
すべての都市計画区域で必ず区域区分が行われるわけではなく、区域区分が定められていない都市計画区域(=非線引都市計画区域)も存在します。
「区域区分が定められている都市計画区域」とは、「市街化区域」と「市街化調整区域」に分けられている区域のこと、「区域区分が定められていない都市計画区域」とは、「非線引都市計画区域」のこと、と理解しておきましょう。
どこが計画エリア?都市計画区域と準都市計画区域の指定ルールを徹底比較
さて、これらの区域が「誰によって」「どんな手続きで」指定されるのかを見ていきましょう。特に「都市計画区域」と「準都市計画区域」の指定ルールは比較しながら覚えるのが効果的です。
【誰が決めるの?】都市計画区域の指定権者と手続きの流れ
原則は都道府県、例外は国!指定権者の違い
都市計画区域を指定するのは誰でしょうか?
- 原則:その区域がある都道府県が指定します。
- 例外:指定しようとする区域が2つ以上の都府県にまたがる場合は、国土交通大臣が指定します。
例えば、東京都と埼玉県にまたがるような大きな都市計画区域を指定する場合は、国土交通大臣が登場する、というイメージですね。
指定する範囲は、市や町といった行政区画にとらわれずに、一体の都市として必要な範囲を指定できます。
指定手続きの違いを比較表でチェック!
指定する人が違うと、手続きの流れも少し異なります。比較して整理しましょう。
都道府県知事指定と国土交通大臣指定の手続き比較表
| 指定権者 | 指定できる場所 | 手続きの流れ |
|---|---|---|
| 都道府県知事 | 一つの都道府県内 |
|
| 国土交通大臣 | 2つ以上の都府県にわたる場合 |
|

都道府県が指定するときの方が、手続きが多いんですね!
都道府県指定の場合は「関係市町村」と「都道府県都市計画審議会」の意見聴取、そして「国交大臣への協議・同意」が必要ですが、国交大臣指定の場合は「関係都府県」の意見聴取だけでOK、という違いを押さえましょう。
5年ごとの見直し?基礎調査について
街の状況は常に変化します。そのため、都道府県は、指定された都市計画区域について、おおむね5年ごとに、人口規模、産業分類別の就業人口、市街地の面積、土地利用の現況、交通量などの都市計画に関する基礎調査を行わなければなりません。
この調査結果をもとに、必要があれば都市計画を見直していくんですね。
ちなみに、準都市計画区域については、5年ごとという義務はなく、「必要があると認めるとき」に基礎調査を行うことになっています。
都市計画はどこまで定める?区域外への例外ルール
都市計画(用途地域や地区計画など)は、原則として、指定された都市計画区域内で定めるものです。
ただし、例外があります。道路、公園、下水道といった「都市施設」に関する都市計画については、特に必要がある場合には、都市計画区域の外でも定めることができます。
考えてみれば、道路や下水道は都市計画区域の内外をつなぐものですから、区域外にも計画が必要な場合がありますよね。
【都市計画区域外の要注意エリア】準都市計画区域の指定ルール
次に、都市計画区域「外」に指定される「準都市計画区域」のルールを見ていきましょう。
準都市計画区域を指定できるのは誰?
準都市計画区域を指定するのは、必ず都道府県です。
都市計画区域の場合は、2つ以上の都府県にまたがる場合は国土交通大臣が指定する例外がありましたが、準都市計画区域にはこの例外はありません。都道府県知事だけが指定権者となります。これは重要な比較ポイントです!
指定の手続きは?都市計画区域指定との共通点
準都市計画区域を指定する際の手続きは、以下の通りです。
- あらかじめ、関係市町村および都道府県都市計画審議会の意見を聴く
- 国土交通大臣に協議し、その同意を得る
- 公告する(効力発生)
これは、さっき見た都市計画区域を都道府県が指定する場合の手続きと全く同じです。手続きは共通なので、セットで覚えやすいですね。
指定された後どうなる?廃止や変更のルール
準都市計画区域が指定された後、状況が変わることもあります。
- もし、準都市計画区域の全部が、新たに都市計画区域として指定された場合:
その準都市計画区域は、特別な手続きを経ることなく、当然に廃止されます。 - もし、準都市計画区域の一部だけが、新たに都市計画区域として指定された場合:
その準都市計画区域は、特別な手続きを経ることなく、廃止されるか、または都市計画区域と重複しない残りの区域に変更されたものとみなされます。
都市計画区域に「昇格」したら、準都市計画区域としての役割は終わる、というイメージですね。
【準都市計画区域の特別ルール】どんな規制がかけられる?定められる地域地区
準都市計画区域は、都市計画区域ほど積極的な開発は予定されていませんが、それでも「放置すると将来支障が生じるおそれがある」エリアです。そのため、無秩序な開発を防ぎ、土地利用を整えるために、一定の「地域地区」を定めることができます。
準都市計画区域で定められる8つの「地域地区」とは?
準都市計画区域内では、都市計画として以下の8種類の地域地区を定めることができます。
地域地区とは、都市計画で定められる土地利用のルールの一種で、エリアごとに建築物の用途や高さなどを制限するものです。
- 用途地域
- 特別用途地区(※用途地域が定められている場合に、その中で定めることができます)
- 特定用途制限地域
- 高度地区
- 景観地区
- 風致地区
- 緑地保全地域
- 伝統的建造物群保存地区
これらの地域地区を定めることで、準都市計画区域内においても、ある程度の土地利用のコントロールを行うことができるわけです。
【試験対策】全部覚える必要はある?ポイントを解説
「えっ、この8つ全部覚えるの…?」と不安になった方もいるかもしれませんね。
ユーザー提供情報にも「全て覚える必要はございません」とありましたが、宅建試験対策としては、「準都市計画区域でも用途地域などを定めることができる場合があるんだな」という程度の認識で、まずは十分でしょう。
特に重要なのは、「準都市計画区域内では、用途地域を定めることができる」という点です。これによって、建物の用途制限などが適用されることになるからです。
余裕があれば、他の地区についても「どんな目的の地区か」を大まかにイメージできるようになると、さらに理解が深まりますよ。(例えば、高度地区は高さ制限、景観地区は景観維持、風致地区は自然の趣維持など)

まずは「用途地域が定められる」ことをしっかり押さえておきましょう!
まとめ
今回は、都市計画法の基礎として、その目的や流れ、そして重要な「区域区分」、さらに「都市計画区域」と「準都市計画区域」の指定手続きやルールについて解説しました。
たくさんの区域名や手続きが出てきて少し大変だったかもしれませんが、それぞれの区域がどんな目的で設けられているのか、誰がどんな手続きで指定するのか、というポイントを押さえることで、だいぶ整理しやすくなったのではないでしょうか。
都市計画法は、私たちの身近な街づくりに関わる大切な法律です。試験対策としてだけでなく、不動産に関する知識としても、ぜひしっかりと理解しておきたい分野ですね。
最後に、今回の重要ポイントを振り返っておきましょう。
- 都市計画法の目的:無秩序な開発を防ぎ、計画的な街づくりを進めること。
- 都市計画の大きな流れ:①区域指定 → ②計画決定 → ③計画制限。
- 日本の国土区分:都市計画区域(市街化区域/市街化調整区域/非線引区域)と都市計画区域外(準都市計画区域/その他)に大別される。
- 市街化区域:積極的に市街化を図る区域(10年以内)。
- 市街化調整区域:市街化を抑制する区域(開発原則NG)。
- 準都市計画区域:都市計画区域外で、放置すると将来支障が出る恐れのある区域。
- 都市計画区域の指定:原則都道府県、2都府県以上は国交大臣。手続きに違いあり。基礎調査は5年ごと。
- 準都市計画区域の指定:都道府県のみ。指定手続きは都市計画区域の都道府県指定と同じ。
- 準都市計画区域で定められる地域地区:用途地域など8種類。乱開発防止のため。

宅建試験では、これらの区域の定義や指定権者、手続きの違いなどがよく問われます。繰り返し復習して、確実に得点できるように頑張りましょう!