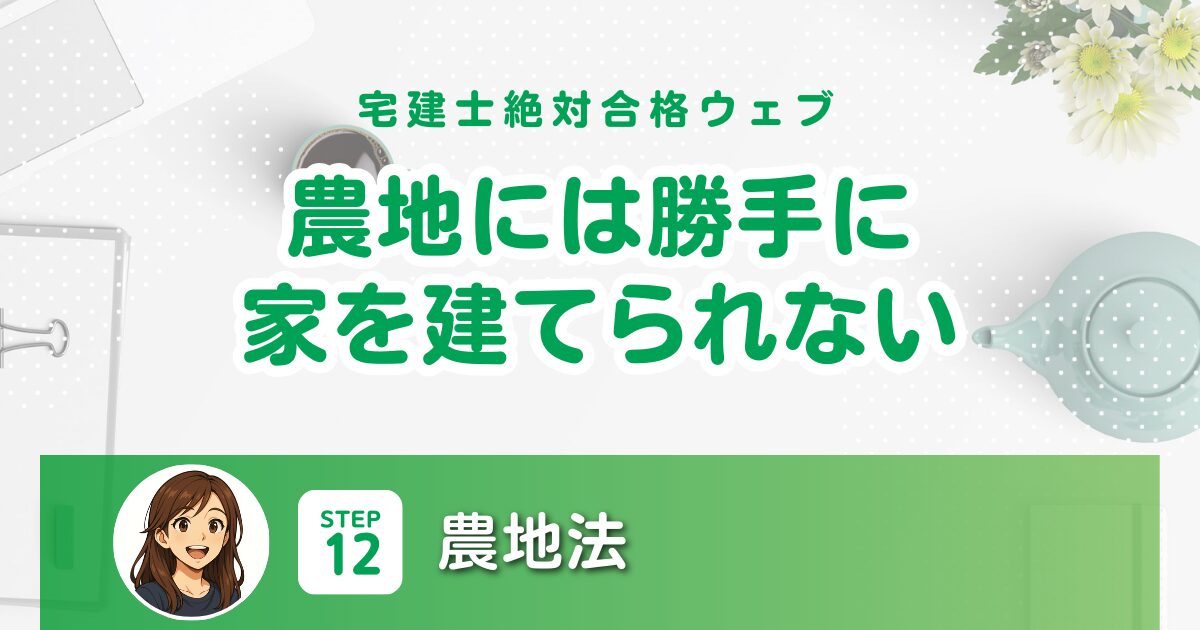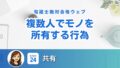法令上の制限は、覚えることが多くて大変…と感じていませんか?特に「農地法」は、数字の「3条」「4条」「5条」が出てきて、「どれがどの場面の話だっけ?」「許可が必要なのは誰から?」「市街化区域だとどうなるの?」なんて、混乱しやすいポイントがたくさんありますよね。
農地法は、日本の食料自給の基礎となる農地を守るための、とっても大切な法律です。だからこそ、農地を売ったり買ったり、他の用途に使ったりする際には、厳しいルールが定められているんですね。そして、この農地法の3条・4条・5条に関する知識は、宅建試験でも避けては通れない、超・超・重要分野なんです!毎年必ずと言っていいほど出題されています。
そこでこの記事では、農地法の基本である「農地とは何か?」から始まり、試験で最も重要な「3条許可」「4条許可」「5条許可」について、それぞれの違い、許可が必要なケース、手続き、罰則、例外などわかりやすく解説していきます。

この記事を読めば、農地法の3つの条文がスッキリ整理でき、それぞれの違いやポイントを自信を持って答えられるようになりますよ!
<この記事でわかること>
- 農地法における「農地」「採草放牧地」の定義
- 農地法3条・4条・5条がそれぞれどんな場面で適用されるのか
- 各条文の許可権者、手続きの違い
- 無許可の場合の契約の効力や厳しい罰則
- 市街化区域内の特例や、許可が不要になる例外ケース
農地法の基礎知識 | 農地・採草放牧地と権利移動・転用を理解しよう
まずは、農地法の基本となる用語の定義からしっかり押さえていきましょう。「農地」って具体的にどんな土地を指すのでしょうか?
「農地」と「採草放牧地」ってどんな土地?
農地とは?
農地法でいう「農地」とは、耕作の目的に供される土地のことを指します。田んぼや畑などが典型例ですね。
ここで重要なのは、農地かどうかは、登記簿上の地目(田、畑など)に関わらず、その土地の客観的な事実状態(現況)で判断されるということです。これを現況主義といいます。
たとえ登記地目が「宅地」や「山林」になっていても、実際に作物が育てられていれば、それは農地法の「農地」として扱われます。逆に、登記地目が「畑」でも、長年放置されていて、もはや耕作できる状態にないと客観的に判断されれば、農地とはみなされないこともあります。
採草放牧地(さいそうほうぼくち)とは?
「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作または養畜の事業のために、牧草などを刈り取ったり(採草)、家畜を放し飼いにしたり(放牧)する目的で使われる土地のことです。
牧場や採草地などがこれにあたります。これも農地と同様に、現況主義で判断されます。

農地と採草放牧地、どちらも農業に関わる土地ですが、法律上の扱いは少し違うんですね。
農地法3条に関わる「権利移動」とは?
農地法3条は、農地を農地のまま、または採草放牧地を採草放牧地のまま使うために、権利を移したり設定したりする場合のルールです。
ここでいう「権利移動」とは、具体的には以下の権利を設定したり、移転したりすることを指します。
- 所有権
- 地上権
- 永小作権(えいこさくけん)
- 質権
- 使用貸借権(しようたいしゃくけん)(=タダで貸し借りする権利)
- 賃借権
- その他、使用及び収益を目的とする権利
要するに、農地や採草放牧地を「使う権利」を誰かに渡したり、設定したりすることが「権利移動」にあたります。
ここで超重要な注意点!抵当権の設定は、土地の使用収益を目的とするものではない(お金を借りるための担保にするだけ)ので、この「権利移動」には含まれません。したがって、農地に抵当権を設定するだけであれば、農地法3条の許可は不要です!
農地法4条に関わる「転用」とは?
農地法4条は、農地を農地以外のものにする場合のルールです。
「転用」とは、文字通り、農地を、宅地、駐車場、工場用地、資材置場など、農地以外の用途に変えることを言います。
農地の所有者が自分で、その農地を潰して家を建てたり、駐車場にしたりする場合などが、この4条の「転用」にあたります。
ここでも注意点が2つ!
- 農地以外の土地(例えば宅地や山林)を、新たに農地にする場合は、農地法の「転用」には当たりません。(むしろ推奨される方向なので許可は不要です)
- 採草放牧地を、採草放牧地以外のもの(宅地など)に転用する場合は、農地法4条の許可は不要です!4条が規制するのはあくまで「農地」の転用だけです。

4条は「農地→農地以外」だけが対象なんですね!
農地法5条に関わる「転用目的権利移動」とは?
農地法5条は、農地または採草放牧地を、農地等以外のものにするために、権利移動をする場合のルールです。
これは、「転用」と「権利移動」がセットになったケースと考えるとわかりやすいです。
例えば、
- 農地を持っているAさんが、そこに家を建てたいBさんに、その農地を売る(所有権移転=権利移動+宅地への転用)
- 農地を持っているCさんが、駐車場として使いたいDさんに、その農地を貸す(賃借権設定=権利移動+駐車場への転用)
- 採草放牧地を持っているEさんが、工場を建てたいF社に、その土地を売る(所有権移転=権利移動+工場用地への転用)
といった場合が、この5条の「転用目的権利移動」にあたります。
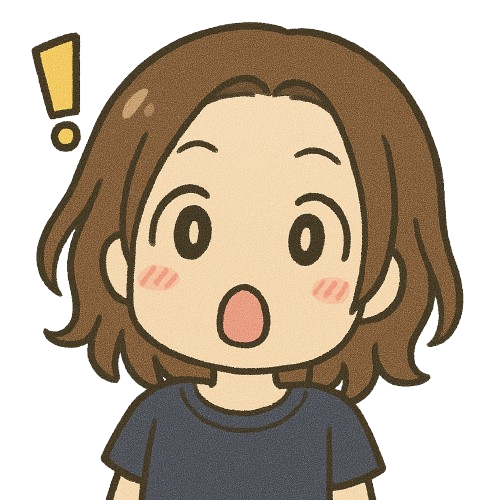
3条は権利移動だけ、4条は転用だけ、5条はその両方がセットになってるんですね!
【最重要】農地法3条・4条・5条を徹底比較! | 許可・罰則・特例・例外
さて、いよいよ農地法の核心、3条・4条・5条の具体的な内容を比較しながら見ていきましょう!それぞれの違いをしっかり区別することが、得点力アップの最大のポイントです!
3条・4条・5条、それぞれの適用場面と許可権者
まずは、どんな場面でどの条文の許可が必要になるのか、そして誰の許可が必要なのかを整理します。
- 【3条許可】権利移動
- 農地 → 農地(利用者の変更)
- 採草放牧地 → 採草放牧地(利用者の変更)
- 採草放牧地 → 農地(利用者の変更&利用目的変更)
- 【4条許可】転用(自己転用)
- 農地 → 宅地、駐車場、工場用地など(所有者は変わらず用途変更)
- ※採草放牧地の転用は許可不要!
- 【5条許可】転用目的権利移動
- 農地 → 宅地、駐車場など(利用者も変わり、用途も変わる)
- 採草放牧地 → 宅地、工場用地など(利用者も変わり、用途も変わる)
次に、許可を与える権限者(許可権者)です。これも条文によって異なります。
- 3条許可 ⇒ 原則として、その土地がある市町村の農業委員会
- 4条許可 ⇒ 原則として、都道府県知事(※農地が指定市町村内にある場合は、指定市町村の長)
- 5条許可 ⇒ 原則として、都道府県知事(※農地等が指定市町村内にある場合は、指定市町村の長)
3条だけ農業委員会、4条と5条は知事等と覚えましょう! なぜ違うかというと、3条は農地を農地として使い続けるための権利移動なので、地域の農業事情に詳しい農業委員会が判断するのが適しているからです。一方、4条と5条は農地を他の用途に変える(=農地が減る)話なので、より広域的な視点を持つ知事等が判断する、というイメージです。
<メモ>
指定市町村とは、農林水産大臣が指定した、権限が移譲されている市町村のことです。
無許可の場合どうなる?契約の効力と罰則
もし、これらの許可を受けずに権利移動や転用をしてしまったら、どうなるのでしょうか?農地法の規制は非常に厳しく、重いペナルティが科せられます。
【無許可行為の結果】
- 3条許可を取らずに権利移動した場合 ⇒ その契約(売買、賃貸借など)は無効となります。
- 4条許可を取らずに転用した場合 ⇒ 都道府県知事等から、工事の中止や原状回復(元の農地に戻すこと)を命じられることがあります。契約自体は関係ないので無効にはなりません。
- 5条許可を取らずに転用目的権利移動をした場合 ⇒ 契約は無効となり、かつ、知事等から原状回復を命じられることがあります。

5条違反が一番厳しいんですね!契約も無効にされて、元に戻せって言われるなんて…。
【罰則】
さらに、無許可でこれらの行為を行った場合や、虚偽の申請をした場合には、厳しい罰則も定められています。これは3条・4条・5条すべて共通です。
- 3年以下の懲役 または 300万円以下の罰金
- (違反者が法人の場合は、行為者を罰するほか、その法人に対して1億円以下の罰金が科されることもあります)
無許可での農地の取引や転用は、絶対にしてはいけません!非常にリスクが高い行為です。
【国土利用計画法との比較】
ここで、前回学習した国土利用計画法を思い出してください。国土利用計画法の届出をしなくても、契約自体は有効でしたよね?しかし、農地法(3条・5条)の許可を得ないと、契約そのものが無効になってしまうという点が、非常に大きな違いです。農地を守るという目的のために、より強い効力を持たせているんですね。
【特例】市街化区域内なら手続きが簡単に?
都市計画法で定められている「市街化区域」は、すでに市街地を形成している区域、またはおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域でしたね。つまり、積極的に建物を建てて市街地にしていくべきエリアです。
このような市街化区域内にある農地については、農地法の規制が一部緩和される特例があります。
- 対象となるのは? ⇒ 4条(転用)と5条(転用目的権利移動)のケースです。農地を宅地などに変える行為が対象です。
- どんな特例? ⇒ 都道府県知事等の許可は不要となり、代わりに、あらかじめ農業委員会に届け出ればよいことになっています。
- 手続きは? ⇒ 事前に農業委員会に届け出ます。「事後」ではなく「事前」届出なので注意!
市街化区域では、農地を他の用途に転用しやすくするために、許可制ではなく、より簡単な事前届出制になっている、と理解しましょう。
3条(権利移動のみ)には、この市街化区域の特例はありません! なぜなら、3条は農地を農地のまま使うためのルールであり、市街化を促進する(=転用しやすくする)という特例の趣旨とは関係ないからです。市街化区域内の農地を農地のまま売買したり貸借したりする場合は、原則通り3条許可(農業委員会の許可)が必要です。
【例外】許可や届出が不要になるケース
最後に、農地法の許可や届出が、そもそも不要となる例外的なケースを見ていきましょう。これも試験でよく問われます。
【許可・届出が不要となる主な例外ケース】
- 【3条・5条関連】相続(遺産分割含む)、法人の合併・分割、時効取得など ⇒ これらは契約によらない権利の移転なので、3条許可も5条許可も不要です。ただし、相続などで農地の権利を取得した場合は、遅滞なく農業委員会への届出は必要です(許可とは別)。離婚による財産分与も許可不要とされています。
- 【4条・5条関連】国または都道府県等が転用する場合 ⇒ 学校、病院、庁舎などを建設するために国や都道府県が転用する場合は、知事との協議が成立すれば許可不要です。(市町村の場合は許可が必要)
- 【4条・5条関連】市町村が道路、河川、堤防などの公共施設にするために転用する場合 ⇒ 許可は不要です。
- 【4条関連】自己所有の農地を、農業経営に必要な農業用施設(例:農業用倉庫、温室など)にする場合で、その面積が2アール(200㎡)未満の場合 ⇒ 4条許可は不要です。
- 【共通】土地収用法などにより収用または使用される場合 ⇒ 強制的な権利取得なので許可は不要です。
特に、相続や国・都道府県等が関わる場合、2アール未満の農業用施設への転用は、試験で狙われやすい例外なので、しっかり覚えておきましょう!
【完全版】農地法3条・4条・5条 比較まとめ表
それでは、これまでの内容をすべてまとめた比較表で、最終確認をしましょう!
<農地法3条・4条・5条 比較まとめ表>
| 項目 | 3条許可(権利移動) | 4条許可(転用) | 5条許可(転用目的権利移動) |
|---|---|---|---|
| 適用場面 | ・農地→農地 ・採草→採草 ・採草→農地 (利用権の設定・移転) | ・農地→農地以外 (自己転用) ※採草の転用は対象外 | ・農地→農地以外 ・採草→農地以外・採草以外 (転用を伴う利用権の設定・移転) |
| 許可権者 | 農業委員会 | 原則:都道府県知事等 (指定市町村長の場合あり) | |
| 無許可の場合の 契約の効力 | 無効 | - (契約関係なし) | 無効 |
| 無許可の場合の 行政措置 | - | 原状回復命令等 | 原状回復命令等 |
| 無許可の場合の 罰則 | 3年以下の懲役 or 300万円以下の罰金 (法人は1億円以下) ※共通 | ||
| 市街化区域内の 特例 | なし | 農業委員会へ事前届出でOK (許可不要) | |
| 許可が不要な 主な例外 | ・相続、遺産分割、離婚 ・時効取得 ・国、都道府県等の取得 ・土地収用 など | ・国、都道府県等の転用(協議) ・市町村等の公共転用 ・2a未満の農業用施設 ・土地収用 など | ・相続、遺産分割、離婚 ・時効取得 ・国、都道府県等の取得/転用(協議) ・市町村等の公共転用 ・土地収用 など |
| 抵当権設定 | 許可不要 | - | - |

この表が頭に入っていれば、農地法の問題はかなり解けるはずです!何度も見返して完璧にしましょう!
まとめ
今回は、宅建試験の超重要科目である「農地法」、特に3条・4条・5条の許可制度について、その違いやポイントを詳しく解説しました。
農地を守るための大切な法律であり、それゆえに規制も厳しいですが、ルールをしっかり理解すれば、試験で確実に得点できる分野でもあります。
最後に、今回の最重要ポイントをまとめておきましょう!
- 農地かどうかは現況主義で判断。地目は関係ない。
- 3条許可:農地等を農地等のまま使うための権利移動。許可権者は農業委員会。抵当権設定は不要。無許可は契約無効。
- 4条許可:農地を農地以外にする転用(自己転用)。許可権者は知事等。採草放牧地の転用は不要。無許可は原状回復命令。
- 5条許可:農地等を農地等以外にするための転用目的権利移動。許可権者は知事等。無許可は契約無効+原状回復命令。
- 無許可の罰則は共通で重い(3年懲役or300万罰金等)。
- 市街化区域内では、4条・5条は許可不要で農業委員会への事前届出でOK(3条は特例なし)。
- 相続や国・都道府県等が関わる場合、2アール未満の農業用施設への転用などは許可不要の例外がある。
3条・4条・5条の違い、許可権者、無許可の場合の効力、市街化区域の特例、例外規定。これらをしっかり押さえることが農地法攻略のカギです!

農地法は、最初はとっつきにくいかもしれませんが、一度理解してしまえば安定した得点源になります。諦めずに繰り返し学習して、自信を持って試験に臨んでくださいね!