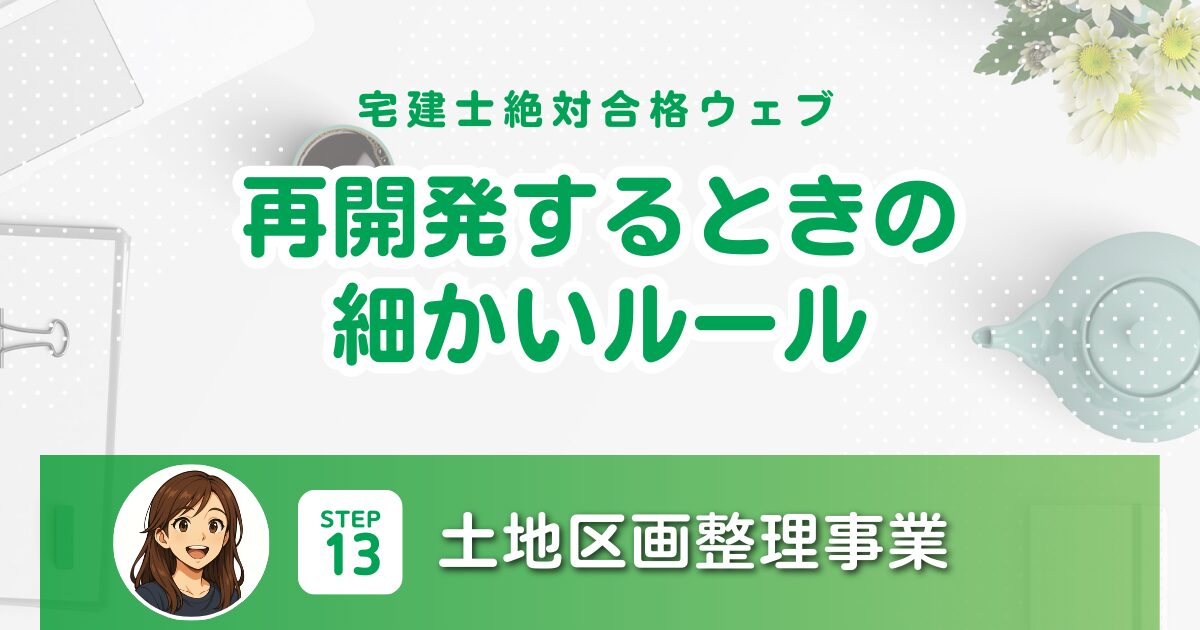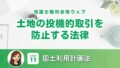法令上の制限の中でも、「土地区画整理法」って、なんだか規模が大きくて、手続きも複雑そうで、ちょっと苦手意識を持っている方もいるかもしれませんね。「施行者って誰のこと?」「換地?仮換地?何が違うの?」「権利関係はどうなるの?」など、疑問がいっぱい浮かんでくる分野だと思います。特に、事業の長い期間の中で、土地の権利がどう変化していくのか、その流れを掴むのが難しいですよね。
でも、この土地区画整理事業は、私たちが普段暮らしている街を、より安全で、より便利で、より快適にするために、とっても重要な役割を果たしているんです。曲がりくねって狭かった道路がまっすぐ広くなったり、使いにくかった形の土地がきれいな四角になったり、公園や広場ができたり…これらは土地区画整理事業の成果なんですよ。
この記事では、そんな「土地区画整理法」について、事業の目的や流れといった基本から、試験で特に狙われやすい「換地計画」「仮換地」「換地処分」といった専門的な内容まで、図や表を使いながら、順を追って丁寧に解説していきます。この記事を読めば、複雑に見える土地区画整理事業の全体像が掴め、難しい用語や権利関係の変化もスッキリ理解できるようになりますよ!

ちょっと複雑ですが、街づくりの基本となる大切な法律です。一緒に頑張りましょう!
<この記事でわかること>
- 土地区画整理法の目的と事業の具体的な内容について理解できる
- 誰が事業を行うのか(施行者の種類と要件)が明確になる
- 土地区画整理事業の全体の流れと、事業中の建築制限がわかる
- 換地計画、仮換地、換地処分のそれぞれの意味と手続きのポイントが整理できる
- 仮換地指定や換地処分によって権利関係がどう変わるのかが明確になる
土地区画整理法の基本 | 事業の目的・施行者・全体の流れを知ろう
まずは、土地区画整理法がどんな法律で、どんな目的を持っているのか、そして誰がどのように事業を進めていくのか、基本的なことから確認していきましょう。全体像を掴むことが大切です。
土地区画整理法ってどんな法律?目的は?
土地区画整理法は、主に都市計画区域内の土地について、道路が狭かったり、土地の形がいびつだったりして、そのままでは利用しにくい市街地や、これから市街地として開発しようとする地域を、計画的に整備し、健全で住みやすい街にするためのルールを定めた法律です。
この法律に基づく「土地区画整理事業」の大きな目的は、主に以下の2つです。
- 宅地利用の増進:
土地の区画(境界)や形をきれいに整えて、家などを建てやすく、より利用価値の高い宅地にすることを目指します。例えば、旗竿地や三角形の土地を整形な四角形にしたり、狭小な土地をまとめて適度な広さにしたりします。 - 公共施設の整備改善:
道路、公園、広場、河川、下水道などの公共施設を、計画的に新しく設置したり、既存のものを拡幅・改良したりします。これにより、交通の便が良くなったり、安全性が向上したり、快適な生活環境が生まれたりします。
これを実現するために、土地区画整理事業では、区域内の土地の所有者などから、その権利に応じて少しずつ土地を提供してもらい(これを「減歩(げんぶ)」といいます)、その土地を使って道路や公園などの公共施設用地を生み出したり、事業費を捻出するための土地(保留地)としたりします。
そして、残りの土地を、元の土地の条件などを考慮しながら、新しく区画された土地として権利者に割り当て直します(これを「換地(かんち)」といいます)。つまり、土地の所有権などを交換・分合することで、街全体の再編を図るわけです。

みんなで少しずつ土地を出し合って(減歩)、新しい土地をもらう(換地)ことで、街全体を良くしていくための法律なんですね。
土地区画整理事業って具体的に何をするの?
では、具体的に土地区画整理事業ではどんなことが行われるのでしょうか?イメージをつかむために、事業前と事業後の変化を見てみましょう。
【事業前の状態】
- 道路が狭く、曲がりくねっていて、車のすれ違いが困難だったり、緊急車両が入りにくかったりする。
- 歩道がなく、歩行者の安全が確保されていない。
- 公園や広場などのオープンスペースが不足している。
- 個々の土地の形がいびつ(不整形)で、家を建てにくかったり、有効活用できなかったりする。
- 土地の境界が不明確な場合がある。
- 上下水道やガスなどのライフラインが未整備、または老朽化している。
【事業後の状態】
- 道路が拡幅され、まっすぐになり、交通の利便性や安全性が向上する。
- 歩道が整備され、安全に歩けるようになる。
- 公園や広場が計画的に配置され、憩いの場や防災空間が生まれる。
- 土地が整形化され、利用価値が高まり、住宅なども建てやすくなる。
- 土地の境界が明確になる。
- ライフラインが整備され、生活の利便性や安全性が向上する。
このように、土地区画整理事業は、単に土地の区画を整理するだけでなく、道路や公園などの公共施設を一体的に整備することで、都市の基盤そのものを改善し、土地の利用価値を高めることを目指す、非常に総合的な街づくり事業なんです。
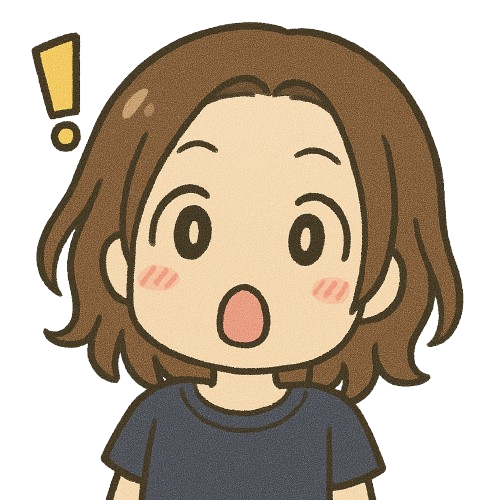
わぁ、全然違いますね!整理後はすごくスッキリして、安全で住みやすそうです!これが区画整理の効果なんですね。
誰が事業を進めるの?施行者の種類とポイント
この土地区画整理事業は、誰が主体となって進めるのでしょうか?事業を行う人や組織を「施行者(しこうしゃ)」と呼びます。施行者には様々な種類があり、誰が施行するかによって、手続きや必要な同意要件などが異なります。ここは試験でもよく問われるポイントです!
施行者は、大きく分けて「民間施行者」と「公的施行者」に分類されます。
【民間施行者】
民間施行者は、主に土地の権利者自身が主体となって事業を進めるケースです。
- 個人施行者:
- 施行地区内の宅地の所有者や借地権者(地上権者または賃借権者)が1人、または数人が共同して行う場合です。
- 施行するには、施行地区内の宅地の所有者および借地権者の全員の同意を得て、都道府県知事の認可が必要です。
- 全員同意というハードルが高いため、比較的小規模な事業や、権利者が少ない場合に用いられることが多いです。
- 土地区画整理組合:
- 施行地区内の宅地の所有者や借地権者が7人以上共同して設立する「組合」が施行する場合です。最も一般的な施行形態の一つです。
- 組合を設立するには、まず7人以上の発起人が集まり、定款(組合のルール)と事業計画を作成します。
- そして、設立について、施行地区内の宅地の所有者および借地権者のそれぞれの3分の2以上(人数だけでなく、所有する土地の地積(面積)についても3分の2以上)の同意を得て、都道府県知事の認可を受ける必要があります。
- 認可されると組合は法人となり、施行地区内の宅地の所有者・借地権者は、設立に同意しなかった人も含めて全員が組合員になります(強制加入)。
【超重要】組合設立の要件:「7人以上」「所有者・借地権者それぞれ」「人数・地積ともに」「3分の2以上の同意」「知事の認可」。これは絶対に覚えましょう!
- 区画整理会社:
- 土地区画整理事業を行うことを目的として設立された株式会社が施行する場合です。
- 施行するには、その会社の株主のうち、施行地区内の宅地の所有者または借地権者である者が、総株主の議決権の過半数を有している必要があります。
- さらに、事業計画について、施行地区内の宅地の所有者および借地権者のそれぞれの3分の2以上(人数・地積の両方)の同意を得て、都道府県知事の認可が必要です。(同意要件は組合と同じですね)
組合と似ていますが、株式会社という形態をとる点、株主構成に要件がある点が異なります。
【公的施行者】
公的施行者は、国や地方公共団体などが、公共的な目的のために主体となって事業を進めるケースです。
- 都道府県または市町村:
- 地方公共団体が主体となって行う場合です。都市計画事業として行われることが多いです。
- 施行するには、原則として議会の議決などを経て、国土交通大臣の認可(市町村施行の場合は都道府県知事の認可の場合もある)が必要です。
- 国土交通大臣:
- 国の重要な事業として、国土交通大臣自らが施行する場合です。大規模な災害復興事業などで見られます。
- 独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)や地方住宅供給公社など:
- 法律に基づいて設立された公的な機関が施行する場合です。大都市圏での大規模な宅地開発などで多く見られます。
- 施行するには、国土交通大臣の認可等が必要です。
【公的施行の重要ルール:土地区画整理審議会】
公的施行者(都道府県、市町村、UR、公社など)が土地区画整理事業を行う場合、事業の計画や運営について、権利者の意見を反映し、事業の公正性・透明性を確保するために、「土地区画整理審議会」を設置しなければならないと定められています(ただし、国土交通大臣が施行する場合は設置義務はありません)。
この審議会は、学識経験者や、区域内の土地所有者・借地権者から選挙で選ばれた委員などで構成され、換地計画や仮換地の指定、保留地の決定などについて意見を述べたり、同意を与えたりする重要な役割を担います。
<施行者の種類と設立・認可要件 比較表>
| 施行者の種類 | 主な要件 | 必要な同意 | 認可権者 | 審議会設置義務 |
|---|---|---|---|---|
| 個人施行者 | 所有者・借地権者(1人 or 数人) | 所有者・借地権者の全員同意 | 都道府県知事 | 不要 |
| 土地区画整理組合 | 所有者・借地権者7人以上 | 所有者・借地権者の各2/3以上同意(人数・地積) | 都道府県知事 | 不要 |
| 区画整理会社 | 株式会社(株主の過半数が権利者) | 所有者・借地権者の各2/3以上同意(人数・地積) | 都道府県知事 | 不要 |
| 都道府県・市町村 | 地方公共団体 | (議会の議決等) | 国土交通大臣 or 都道府県知事 | 必要 |
| 国土交通大臣 | 国 | - | - | 不要 |
| UR・地方住宅供給公社等 | 公的法人 | - | 国土交通大臣等 | 必要 |
特に土地区画整理組合の設立要件(7人以上、各2/3同意)と、公的施行者の審議会設置義務(国土交通大臣を除く)は頻出なので、必ず押さえてください!
事業はどう進む?全体の流れと建築等の制限
土地区画整理事業は、計画の決定から工事の完了、そして権利関係の最終的な整理まで、一般的に長い期間をかけて段階的に進められます。ここでは、その大まかな流れと、事業期間中にかかる重要な制限について見ていきましょう。
【事業の大まかな流れ】
土地区画整理事業は、以下のようなステップで進んでいきます。
- 事業計画・施行規程等の決定:施行者が、事業を行う区域、設計の概要(道路や公園の配置など)、事業期間、資金計画などを定めた「事業計画」や、事業の進め方のルールを定めた「施行規程」(組合の場合は定款)を作成・決定します。
- 事業計画等の認可・公告:作成した事業計画について、都道府県知事等から認可を受けます。認可されると、その旨が公告(広く一般に知らせること)されます。この認可公告の日から、正式に土地区画整理事業が開始され、後述する建築等の制限がかかります。
- 換地計画の作成:事業区域内のどの土地(従前の宅地)に対して、どの場所に、どれくらいの広さの新しい土地(換地)を割り当てるか、清算金はどうするか、保留地はどこに設けるかなどを具体的に定めた「換地計画」を作成します。(詳細は後述)
- 換地計画の認可:作成した換地計画について、都道府県知事等の認可を受けます。(公的施行の場合は審議会の同意も必要)
- 仮換地の指定(順次):換地計画の認可後、工事の進捗に合わせて、権利者に対して一時的に使用できる土地として「仮換地」を指定していきます。これにより、工事中でも生活や事業を継続しやすくなります。(詳細は後述)
- 工事の施行:換地計画に基づき、道路、公園、宅地盤(宅地の土台となる造成工事)などの整備工事を行います。仮換地が指定された場所から順次行われることが多いです。
- 換地処分の通知・公告:原則として事業区域内の全ての工事が完了した後、最終的な換地を確定させる「換地処分」を行います。施行者は、換地計画で定められた内容を関係権利者に通知し、その後、都道府県知事等が換地処分があった旨を公告します。この公告によって、法的な権利関係が確定します。(詳細は後述)
- 登記:換地処分の公告後、施行者は権利者に代わって、土地や建物の登記手続きを一括して行います。これにより、登記簿上も新しい権利関係が反映されます。この登記が完了すると、土地区画整理事業は実質的に完了となります。
- 清算金の徴収・交付:換地処分の公告によって確定した清算金について、徴収または交付の手続きが行われます。

認可や公告がたくさん出てきますね…。事業開始の「事業計画認可公告」、権利確定の「換地処分公告」が特に重要です。全体の流れをイメージできるようにしておきましょう。
【事業施行中の建築等の制限】
土地区画整理事業をスムーズに進めるためには、工事の妨げになったり、換地計画の実現を困難にしたりするような行為を、事業期間中は制限する必要があります。
【制限がかかる期間】
事業計画の認可の公告があった日 から 換地処分の公告がある日 まで
【制限される行為】
施行地区内において、以下の行為をしようとする者は、原則として都道府県知事等(※)の許可を受けなければなりません。
- 土地の形質の変更(切り土、盛り土、掘削など)
- 建築物その他の工作物(建物、擁壁、広告塔など)の新築、改築、増築
- 移動の容易でない物件(重量が5トンを超えるもの。ただし、分割すれば5トン以下になるものは除く)の設置または堆積
(※)許可権者は、国土交通大臣が施行する場合は国土交通大臣、それ以外の施行者(個人、組合、会社、都道府県、市町村、UR等)の場合は都道府県知事です。市町村長ではない点に注意!
つまり、事業中は、勝手に土地を掘ったり、建物を建てたり修理したり、重い機械や資材などを置いたりすることが原則できなくなる、ということです。もしこれらの行為をしたい場合は、必ず事前に許可を得る必要があります。施行者は、許可申請があった場合、事業の施行に支障があると判断すれば、許可しないことができます。
【違反した場合】
もし、この制限に違反して許可なくこれらの行為を行った場合、都道府県知事等は、その行為者(またはその後の権利承継人)に対して、相当の期限を定めて、原状回復(元の状態に戻すこと)や、建築物等の移転・除去を命じることができます。命令に従わない場合は、行政代執行される可能性もあります。
この建築等の制限は、都市計画法における「都市計画事業地内の制限」と非常によく似ています。期間(認可公告~完了公告)や制限される行為(土地形質変更、建築物新築等、移動困難物件設置)、許可権者(原則知事等)などをセットで覚えておくと効率的です。
【重要ポイント】換地計画・仮換地・換地処分を徹底解説
ここからは、土地区画整理事業の核心部分であり、宅建試験でも最重要ポイントとなる「換地」に関するルールを詳しく見ていきます。「換地計画」「仮換地」「換地処分」という3つのキーワードが軸になります。それぞれの意味と手続き、そして権利関係にどのような影響を与えるのかをしっかり理解しましょう。
換地計画とは?換地のルールと清算金・保留地
換地とは?
「換地(かんち)」とは、区画整理事業前の土地(これを「従前の宅地」といいます)の代わりに、事業完了後に新しく割り当てられる土地のことを指します。土地区画整理事業では、原則として、従前の宅地にあった所有権や借地権などの権利は、この換地へと移ることになります。
換地計画の作成と認可
施行者は、事業を進めるにあたって、「換地計画」というものを定めなければなりません。これは、事業区域内のどの従前の宅地に対して、どの場所に、どれくらいの広さの換地を割り当てるか、そしてそれに伴う清算金の額や、事業費に充てるための保留地の位置・面積などを具体的に定めた、事業の設計図とも言える重要な計画です。
この換地計画は、施行者が作成した後、原則として都道府県知事等の認可を受けなければなりません。(民間施行の場合は認可、公的施行(都道府県・市町村・UR等)の場合は、まず土地区画整理審議会の同意を得た上で、知事等の認可を受ける、という流れになります。)
換地照応の原則
換地計画を定める際には、非常に重要な基本原則があります。それは、「換地」と「従前の宅地」とが、以下の点について照応(しょうおう)するように、つまり、できるだけつり合いがとれているように定めなければならないという原則です。これを「換地照応の原則」といいます。
【照応させるべき事項】
- 位置(元の場所からの距離、方位、道路への接道状況など)
- 地積(面積。ただし、減歩があるので通常は元の面積より小さくなります)
- 土質(土地の質、地盤の良し悪しなど)
- 水利(水の便、排水状況など)
- 利用状況(住宅地、商業地、工場地などの現在の使われ方)
- 環境(日照、通風、騒音、眺望、周辺の状況など)
もちろん、区画整理によって街全体が変わるので、これらの要素全てを従前の宅地と全く同じにすることは不可能です。しかし、換地計画では、これらの要素を総合的に考慮して、できるだけ公平になるように、不利益が生じないように換地を割り当てることが求められます。
清算金
換地照応の原則に基づいて換地を定めても、完全に公平な割り当てを行うのは非常に困難です。どうしても、従前の宅地の価値と、割り当てられた換地の価値の間に、多少の差(不均衡)が生じてしまうことがあります。
この価値の不均衡を金銭によって調整するための仕組みが「清算金(せいさんきん)」です。
- 従前の宅地の価値に比べて、割り当てられた換地の価値が低くなった権利者に対しては、その差額に相当する清算金が施行者から交付されます(お金をもらえます)。
- 逆に、従前の宅地の価値に比べて、割り当てられた換地の価値が高くなった権利者からは、その差額に相当する清算金が施行者へ徴収されます(お金を支払います)。
この清算金の額は、換地計画において、個々の換地ごとに定められます。そして、後述する換地処分の公告の翌日にその額が確定し、その後、実際に徴収・交付の手続きが行われます。
保留地
換地計画では、区域内の土地の一部を、特定の権利者に換地として割り当てずに、「保留地(ほりゅうち)」として定めることができます。
保留地は、主に以下のような目的で設けられます。
- 事業費への充当:施行者が保留地を売却し、その売却代金を道路工事や事務費など、土地区画整理事業に必要な費用に充てるため。
- 特定の目的のための用地:定款や事業計画で定められた特定の目的(例えば、集会所の建設用地など)のために確保しておくため。
【保留地に関する注意点】
公的施行者(都道府県、市町村、UR等)が保留地を定めようとする場合は、事前に土地区画整理審議会の同意を得なければなりません。これは、保留地を定めることが権利者の減歩率(土地が減る割合)に影響を与える可能性があるため、権利者の代表等で構成される審議会のチェックを受ける必要があるからです。
一方、民間施行者(個人、組合、会社)には土地区画整理審議会が設置されないため、審議会の同意は不要です。(組合の場合は総会の議決など、内部での意思決定手続きは必要です)
仮換地の指定とは?手続きと効果を理解しよう
土地区画整理事業は、計画決定から工事完了、換地処分まで、数年、場合によっては十数年以上かかることもあります。その間、工事のために自分の土地(従前の宅地)が使えなくなってしまっては、そこに住んでいる人や事業を営んでいる人は非常に困りますよね。
そこで、工事がある程度進んだ区域から順次、最終的な換地処分が行われるまでの間、一時的に従前の宅地の代わりに使用収益できる土地として割り当てられるのが「仮換地(かりかんち)」です。この仮換地を指定する手続きを「仮換地の指定」といいます。
仮換地指定の手続き
施行者が仮換地を指定する際には、一定の手続きが必要です。これは施行者の種類によって異なります。
- 個人施行者:関係権利者(仮換地となる土地の権利者と、指定を受ける従前の宅地の権利者)の同意が必要。
- 土地区画整理組合:総会等の議決(同意)が必要。
- 区画整理会社:施行地区内の宅地の所有者および借地権者のそれぞれの3分の2以上(人数・地積)の同意が必要。(設立時の同意要件と同じですね)
- 公的施行者(都道府県・市町村・UR等):あらかじめ土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。
【公的施行の場合の注意点】
公的施行者が仮換地を指定する場合に必要なのは、審議会の「意見聴取」であり、「同意」までは求められていません。保留地を定める場合は「同意」が必要だったので、この違いをしっかり区別しましょう!
これらの手続きを経た上で、施行者は、仮換地を指定する旨を、仮換地となる土地(またはその一部)の権利者と、指定を受ける従前の宅地の権利者の双方に、仮換地の位置や地積、そして仮換地の指定の効力発生日を通知して行います。
仮換地指定の効果
仮換地が指定され、その効力発生日が到来すると、権利関係に非常に重要な変化が生じます。ここが宅建試験で最も狙われやすいポイントの一つなので、しっかり理解してください!
【仮換地指定の効力発生日 から 換地処分の公告がある日 まで】の間、以下の効果が発生します。
- 使用収益権の変化:
- 従前の宅地の権利者(所有者や借地権者)は、指定された「仮換地」について、従前の宅地が持っていた権利(所有権に基づく使用収益、借地権など)と同じ内容の使用収益権を取得します。 つまり、仮換地を自分の土地のように使うことができるようになります。
- 同時に、その権利者は、元々持っていた「従前の宅地」については、使用収益することができなくなります。 工事の邪魔にならないようにするためですね。
- 所有権等の所在:
- 使用収益権は仮換地に移りますが、土地の「所有権」そのものや、その土地に設定されていた「抵当権」などの権利は、依然として「従前の宅地」に残ったままです。
- そのため、権利者は、仮換地の効力期間中であっても、従前の宅地を売却(所有権移転)したり、従前の宅地に抵当権を設定したりすることは可能です。ただし、買った人や抵当権者も、使用収益できるのは仮換地の方になります。
- 第三者の使用収益権:
- 仮換地として指定された土地に、元々別の権利者(例えば、仮換地指定を受けた人とは違う所有者や借地権者)がいた場合、その元々の権利者は、仮換地の効力発生日以降、その仮換地を使用収益することができなくなります。(その代わり、その人には別の仮換地が指定されるか、損失補償がされることになります)
- 建築行為:
- 従前の宅地は使用収益できなくなるので、そこに新しく建物を建てることはできません。
- 一方、権利者は、自分に割り当てられた「仮換地」の上であれば、建物を建築することができます。
- ただし、前述した事業施行中の建築等の制限(知事等の許可)は、仮換地上での建築にも適用されるので、原則として許可を得る必要があります。
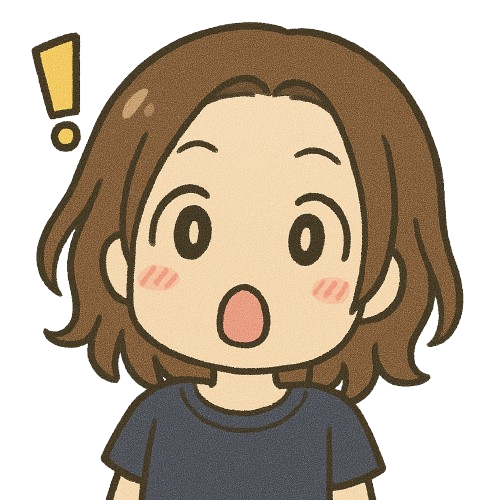
使う権利(使用収益権)と、持っている権利(所有権や抵当権)が、仮換地の期間中は一時的にズレるんですね!しっかり整理する必要がありますね!
その他の関連ルール
- 仮換地に指定されなかった土地の管理:仮換地の指定が行われた結果、一時的に誰も使用収益する権利者がいなくなった従前の宅地(例えば、Aさんの従前の宅地の一部がBさんの仮換地になり、Aさん自身は別の場所に仮換地を指定された場合など)は、換地処分の公告がある日まで、施行者が管理します。
- 使用収益開始日を別に定める場合:仮換地が指定されても、まだ造成工事などが終わっておらず、すぐに使用収益を開始できない場合があります。そのような場合、施行者は、仮換地の指定の効力発生日とは別に、「使用収益を開始できる日」を定めることができます。この場合、本来効力発生日から使えたはずなのに使えなかった期間については、施行者は権利者に対して損失を補償しなければなりません。
- 換地を定めない宅地の使用収益停止:換地計画において、特定の従前の宅地について「換地を定めない」とされた場合(例えば、道路や公園などの公共施設用地になる場合や、清算金交付で対応する場合など)、施行者は、その宅地の権利者に対し、期日を定めて使用収益を停止させることができます。これも工事等を円滑に進めるための措置です。
換地処分とは?事業完了の手続きと効果
仮換地の指定を経て工事が進み、原則として事業に関する全ての工事が完了すると、いよいよ最終的な権利の確定手続きである「換地処分(かんちしょぶん)」が行われます。これが土地区画整理事業の最終ゴールであり、権利関係が法的に確定する重要な瞬間です。
換地処分の手続き
- 通知:施行者は、換地計画において定められた換地や清算金などの事項を、関係する権利者(換地を受け取る人、清算金を支払う人・受け取る人など)に通知して、換地処分を行います。
- 時期:換地処分は、原則として区域内の全ての工事が完了した後、遅滞なく行わなければなりません。ただし、例外的に、規約、定款または施行規程に特別な定めがある場合は、全ての工事が完了する前でも換地処分を行うことが可能です。
- 届出・公告:施行者は、換地処分を行った後、遅滞なくその旨(換地処分の内容や日付)を都道府県知事等に届け出なければなりません。届出を受けた都道府県知事等は、換地処分があった旨を公告します。
【超重要!】換地処分の効力発生は、この都道府県知事等による「公告」が基準となります! 通知があった日や、届出があった日ではありません!
換地処分の効果
換地処分の公告があった日の翌日から、法律上、様々な効果が一斉に発生します。これにより、仮換地によって一時的に複雑になっていた権利関係が最終的に整理され、新しい街の権利関係が法的に確定します。
【換地処分公告の”翌日”に生じる主な効果】
- 換地が従前の宅地とみなされる:
換地計画において定められた換地は、法律上、従前の宅地とみなされます。また、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地(公共施設用地になったり、金銭清算されたりした土地)に存在していた権利は、この公告があった日が終了した時に消滅します。 - 権利の移行・確定:
- 従前の宅地の所有権や借地権(地上権・賃借権)などは、原則として、換地計画で定められた換地の上にそのまま移行し、確定します。
- 仮換地の指定によって生じていた「使用収益権は仮換地に、所有権は従前地に」という権利のズレは解消され、所有権も使用収益権も換地の上にある状態になります。
- 従前の宅地に存在した権利の移行(例外あり):
- 従前の宅地に設定されていた抵当権、質権、先取特権などの担保物権や、買戻しの特約なども、原則として、対応する換地の上に移転します。つまり、従前の土地を担保にお金を借りていた場合、その担保権は新しい換地の上に引き継がれるということです。
- 【例外:地役権】
ただし、地役権(他人の土地を通行する権利、水を引く権利など)は、原則として換地には移転せず、従前の宅地にそのまま残ります。なぜなら、地役権は特定の土地(要役地)の便益のために、別の特定の土地(承役地)の上に設定される権利であり、土地の場所が変わると意味がなくなってしまうことが多いからです。
ただし、区画整理によって地役権を設定している意味(行使する利益)がなくなった場合は、その地役権は換地処分の公告があった日が終了した時に消滅します。
- 清算金の確定:
換地計画で定められていた清算金の額が確定します。この確定した金額に基づいて、今後、徴収・交付の手続きが進められます。(清算金は、分割徴収・分割交付も可能です) - 保留地の帰属:
換地計画において定められた保留地は、公告があった日が終了した時において、原則として施行者が取得します。(定款等で別に定めがある場合は、その定められた者が取得します)。 - 公共施設の帰属:
- 土地区画整理事業によって新しく設置された道路や公園などの公共施設は、原則として、換地処分の公告の翌日に、その公共施設が所在する市町村に帰属し、管理されることになります。
- 従前の公共施設に代わって新しい公共施設が設置された場合、従前の公共施設は原則として廃止され、その土地は、換地として割り当てられたり、保留地になったりします。(ただし、従前の公共施設がそのまま使われる場合は、市町村等に帰属します)

公告の”翌日”に、こんなにたくさんのことが一気に確定するんですね!複雑だった権利関係がこれでスッキリ整理されますね。
換地処分の公告後の登記
換地処分の公告によって権利関係は法的に確定しますが、それを登記簿に反映させる必要があります。
土地区画整理事業の施行地区内の土地や建物についての登記は、換地処分の公告の日から登記がされるまでの間は、原則として行うことができません。(ただし、確定日付のある証書によって公告前に登記原因が生じたことが証明される場合は例外的に可能です)。これは、権利関係が変動する時期に混乱を防ぐためです。
そして、換地処分の公告があった後、施行者は遅滞なく、区域内の土地・建物に関する登記を申請しなければなりません。 これは、個々の権利者が行うのではなく、施行者がまとめて行うことになっています(代位登記)。この登記によって、登記簿上も新しい権利関係が公示され、土地区画整理事業に関する一連の手続きが完了します。
まとめ
今回は、都市計画区域内の街づくりにおいて非常に重要な役割を果たす「土地区画整理法」について、事業の目的や施行者、全体の流れ、そして宅建試験で特に重要となる換地計画・仮換地・換地処分のルールを中心に解説しました。
専門用語が多く、権利関係の変化が複雑で、とっつきにくいと感じるかもしれませんが、一つ一つのステップや用語の意味、そして「誰が」「いつ」「何をするのか」「権利はどうなるのか」という点を意識して整理すれば、必ず理解できるようになります。
最後に、今回の超重要ポイントをしっかりおさらいしておきましょう!
- 土地区画整理法は、都市計画区域内で、宅地利用の増進と公共施設の整備改善を目的とする街づくり事業の法律。
- 施行者には民間(個人:全員同意、組合:7人以上・各2/3同意、会社:各2/3同意)と公的(都道府県・市町村・国・UR等:原則審議会設置)がある。
- 事業期間中の制限:事業計画認可公告~換地処分公告まで、土地形質変更、建築物新築等、5トン超物件設置には原則知事等の許可が必要。
- 換地計画:換地・清算金・保留地を定める計画。換地照応の原則(位置、地積、土質、水利、利用状況、環境)が基本。知事等の認可が必要。
- 保留地:事業費充当等のための土地。公的施行者が定める場合は審議会の同意が必要。
- 仮換地の指定:工事期間中に一時的に使用できる土地。効力発生日に使用収益権は仮換地へ移るが、所有権・抵当権は従前の宅地に残る。公的施行者が指定する場合は審議会の意見聴取が必要。
- 換地処分:原則、全工事完了後に行う最終的な権利確定手続き。
- 換地処分の効果:公告の”翌日”に発生。
- 換地が従前の宅地とみなされる。
- 所有権・借地権・抵当権等は換地へ移転。
- 地役権は原則として従前の宅地に残る(消滅する場合あり)。
- 清算金が確定する。
- 保留地は施行者等に帰属する。
- 新設公共施設は原則市町村に帰属する。
- 登記:換地処分公告後、施行者が一括して申請する。

仮換地指定の効果(使用収益権と所有権のズレ)と、換地処分の効果(公告”翌日”に権利確定、特に地役権の扱い!)は、比較しながら確実に区別して理解しておきましょう!