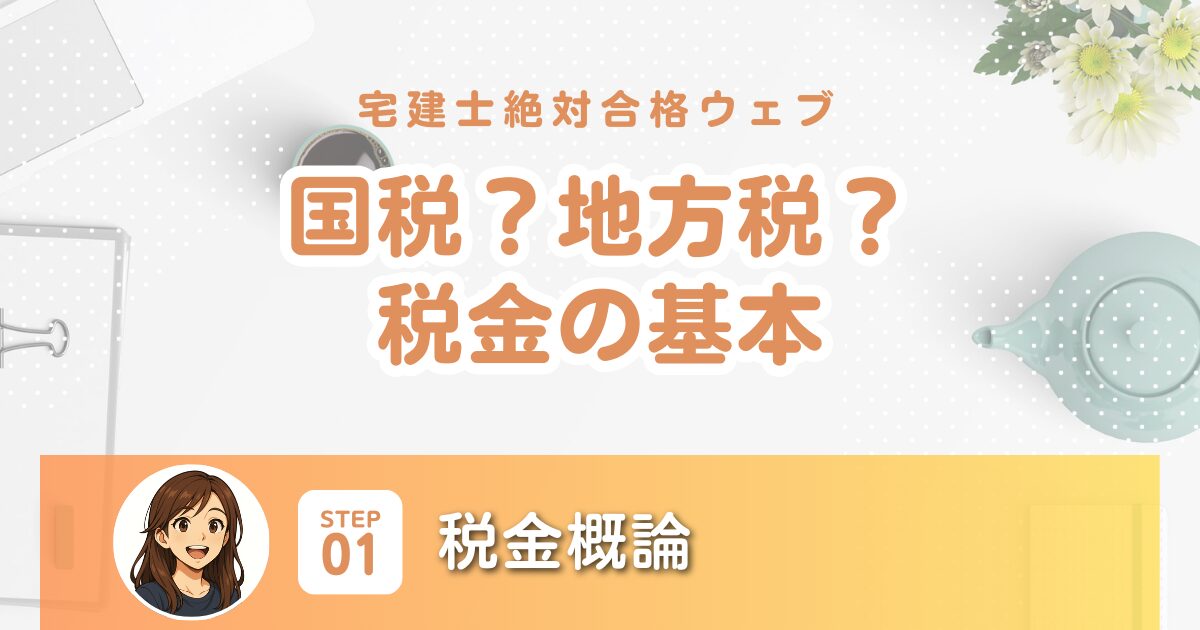意外とボリュームがあって、しかも数字や細かいルールが多くて苦手意識を持ちやすいのが「税金・その他」の分野ですよね。「所得税?不動産取得税?固定資産税?似たような名前が多くて混乱する!」「計算問題は苦手…」「どこまで深く勉強すればいいの?」なんて、悩んでしまう方も多いのではないでしょうか。私も受験生の時は、たくさんの税金の種類とルールを覚えるのに苦労しました…
不動産取引には様々な税金が関わってきます。宅建士として活躍するためには、これらの税金の知識は必須です。そしてもちろん、宅建試験でも毎年必ず複数問出題される重要分野!ここでしっかり得点できるかどうかは、合格を左右する大きなポイントになります。でも、安心してください!税金分野は、出題される範囲やポイントがある程度決まっているので、効率よく学習すれば、確実に得点源にできる分野でもあるんです。
この記事では、そんな宅建試験の「税金」分野について、まずは全体像を掴むために、どんな種類の税金が出題されるのか、そして税額計算の基本的な仕組みはどうなっているのか、といった基礎の基礎をわかりやすく解説していきます。

この記事を読めば、複雑に見える税金分野の全体像がスッキリ整理でき、これから各税金を個別に学習していく上での土台をしっかり作ることができますよ!
<この記事でわかること>
- 国税と地方税の違いと、宅建試験で重要な税金の分類
- 宅建試験で出題される5つの主要な税金の概要と学習ポイント
- 税額計算の基本的な仕組み(課税標準・税率・税額)
- 税金が安くなる特例や控除の種類とその違い
- 税金分野の効率的な学習の進め方
国税と地方税の種類をマスターしよう
まずは、世の中にあるたくさんの税金の中から、宅建試験で特に出題されやすい税金の種類とその分類について見ていきましょう。
税金のキホン:国税と地方税って何が違うの?
税金は、大きく分けて「どこに納めるか」によって2種類に分類されます。
- 国税(こくぜい):
- 文字通り、国に対して納める税金のことです。
- 国の予算として、国の様々な活動(社会保障、公共事業、教育、防衛など)に使われます。
- <例>所得税、法人税、消費税、相続税、贈与税、印紙税、登録免許税など
- 地方税(ちほうぜい):
- 都道府県や市区町村といった地方公共団体に納める税金のことです。
- その地域の住民サービス(教育、福祉、消防、ゴミ処理など)のために使われます。
- 地方税はさらに「道府県税(都税含む)」と「市町村税(特別区税含む)」に分けられます。
- <例>住民税、事業税、自動車税、不動産取得税(道府県税)、固定資産税(市町村税)など
私たちが普段何気なく払っている消費税は国税ですが、一部は地方にも配分されています。住民税は都道府県と市町村の両方に納めていますね。このように、税金には色々な種類と納め先があるんです。

国に納めるか、都道府県・市町村に納めるかで分かれるんですね。
宅建試験で問われる5つの重要税金リスト
では、宅建試験では、これらの税金のうち、どれが重要なのでしょうか?宅建試験の「税金・その他」分野で主に出題されるのは、以下の5つの税金です。まずはこの5つをしっかり覚えましょう!
【宅建試験で重要な5つの税金】
- 国税
- 所得税(譲渡所得):個人が不動産などを売って得た利益(譲渡所得)にかかる税金。
- 印紙税:不動産の売買契約書など、特定の文書を作成した時にかかる税金。
- 登録免許税:不動産の所有権移転登記や抵当権設定登記など、登記をする時にかかる税金。
- 地方税(道府県税)
- 不動産取得税:不動産(土地・建物)を取得した時にかかる税金。
- 地方税(市町村税)
- 固定資産税:不動産(土地・建物)などを所有していることに対して、毎年かかる税金。
<宅建試験に出る税金 分類表>
| 分類 | 税金の種類 | 納税先 | どんな時にかかる?(主な例) |
|---|---|---|---|
| 国税 | 所得税(譲渡所得) | 国 | 不動産を売却して利益が出た時 |
| 印紙税 | 国 | 売買契約書などを作成した時 | |
| 登録免許税 | 国 | 不動産登記をする時 | |
| 地方税(道府県税) | 不動産取得税 | 都道府県 | 不動産を購入・贈与・新築した時 |
| 地方税(市町村税) | 固定資産税 | 市町村 | 不動産を所有している間(毎年1月1日時点) |
各税金のポイントと学習のコツ
それでは、上記5つの税金について、それぞれの簡単な特徴と、宅建試験対策としてどこを重点的に学習すればよいかのポイントを見ていきましょう。各税金の詳しい内容は、それぞれ別の記事で解説しますので、ここではまず全体像を掴んでくださいね。
所得税(譲渡所得)
個人の所得にかかる税金が所得税です。所得には給料や事業収入など10種類ありますが、宅建試験で問われるのは、ほぼ不動産などを売却した際の利益(=譲渡所得)に関する部分です。
【特徴】
- 暦年課税:1月1日から12月31日までの1年間の所得を計算します。
- 申告納税方式:納税者自身が所得と税額を計算して、税務署に申告し納税します。(確定申告ですね!)
【宅建でのポイント】
- 居住用財産(マイホーム)を売却した場合の様々な特例(3,000万円特別控除、軽減税率の特例、買換え特例など)が最重要です。
- 所有期間(長期譲渡か短期譲渡か)によって税率が変わる点もポイントです。
- 不動産賃貸による所得(不動産所得)は、宅建試験ではほとんど出題されません。譲渡所得に絞って学習しましょう。
印紙税
不動産の売買契約書や建物の建築請負契約書など、法律で定められた特定の文書(課税文書といいます)を作成した際に、その文書に収入印紙を貼って消印することで納める税金です。
【特徴】
- 文書の種類と、そこに記載された金額(契約金額など)に応じて税額が決まります。
- 印紙を貼り忘れても契約自体の効力には影響しませんが、ペナルティ(過怠税)が課せられます。
【宅建でのポイント】
- どの文書が課税文書にあたるのか、あたらないのかの区別(例:売買契約書は課税、賃貸借契約書は原則非課税、領収書は金額により課税など)。
- 契約金額がいくらの場合に、いくらの印紙税額になるか(具体的な税額を覚える必要はほぼありませんが、記載金額によって税額が変わることは理解しておく)。
- 契約書を複数作成した場合や、契約金額の記載がない場合の扱い。
登録免許税
不動産の権利に関する登記(例えば、所有権の移転登記、保存登記、抵当権の設定登記など)を法務局に申請する際に納める国税です。
【特徴】
- 登記の種類や、登記の原因(売買、相続、新築など)、不動産の価額によって税率や計算方法が異なります。
- 登記申請時に、収入印紙または現金で納付します。
【宅建でのポイント】
- 住宅用家屋の所有権保存登記・移転登記、抵当権設定登記に関する税率の軽減措置の要件が最も重要です。どんな建物が対象になるのか、床面積や築年数などの要件をしっかり覚えましょう。
- 誰が納税義務者になるのか(原則として登記を受ける人)。
- その他の細かい論点は、過去問で問われた知識を個別に押さえていくのが効率的です。
不動産取得税
土地や建物を取得したことに対して、一度だけ課税される道府県税です(東京都の場合は都税)。取得の原因は、売買、交換、贈与、新築、増改築など問いません。
【特徴】
- 不動産を取得した人が納税義務者となります。
- 相続による取得の場合は、原則として課税されません。
- 税額は、不動産の価格(原則として固定資産税評価額)に税率を掛けて計算されます。
【宅建でのポイント】
- 課税標準の特例(宅地や住宅に関する価格の軽減措置)。
- 税率の軽減。
- 免税点(一定額未満の不動産取得には課税されない)。
- 非課税となるケース(相続、法人の合併、公共用の道路用地の取得など)。
- 固定資産税と内容が似ている部分が多く、混同しやすいので注意! それぞれの違いを意識して学習することが大切です。
固定資産税
毎年1月1日(賦課期日といいます)時点で、土地、家屋、償却資産(事業用の機械など)を所有している人に対して課税される市町村税です(東京23区の場合は都税)。
【特徴】
- その年の1月1日時点の所有者が、その年度分の納税義務者となります(年の途中で売買しても納税義務者は変わりません)。
- 税額は、固定資産税評価額(課税標準)に標準税率(通常1.4%)を掛けて計算されます。
- 市町村が税額を計算して通知してくる賦課課税方式です。
【宅建でのポイント】
- 宅建試験では、主に土地と家屋に関する固定資産税が出題されます。
- 課税標準の特例(特に住宅用地に対する軽減措置は超重要!)。
- 新築住宅に対する税額の減額措置。
- 納税義務者(1月1日時点の所有者、共有の場合、質権・地上権設定時など)。
- 免税点(課税標準が一定額未満の場合は課税されない)。
- 固定資産課税台帳の閲覧や、審査の申出(不服申し立て)に関するルール。
- 不動産取得税との混同に注意!(課税主体、課税されるタイミング、特例の内容などを比較して覚えましょう)。

それぞれの税金で覚えるべきポイントが見えてきましたね!個別記事でしっかり深掘りしていきましょう!
税額計算の仕組み | 課税標準・税率・控除を理解しよう
次に、税金の額(税額)がどのように計算されるのか、基本的な仕組みを見ていきましょう。これは、どの税金にも共通する考え方なので、しっかり理解しておくと、個別の税金の学習がスムーズになりますよ。
税額はどう決まる?基本の計算式
ほとんどの税金の税額は、以下の基本的な計算式で求められます。
課税標準(かぜいひょうじゅん) × 税率(ぜいりつ) = 税額(ぜいがく)
それぞれの用語の意味を確認しましょう。
- 課税標準:税額を計算するための基礎となる金額や数量のことです。不動産関連の税金では、多くの場合、不動産の価格(固定資産税評価額など)が課税標準になります。所得税なら所得金額、印紙税なら契約書の記載金額などがこれにあたります。
- 税率:課税標準に対して税金を課す割合のことです。「〇〇%」や「〇〇円」といった形で定められています。税率は、税金の種類や課税対象によって異なります。
- 税額:実際に納めるべき税金の金額のことです。

なるほど、税金の計算って、基本はこのシンプルな掛け算なんですね!
税金が安くなる?特例・軽減措置の種類
ただし、実際の税金計算では、様々な特例や軽減措置が設けられていて、納税者の負担が軽くなるようになっています。この特例や軽減措置が、どの段階で適用されるかによって、大きく3つの種類に分けられます。この違いを理解することが非常に重要です!
- 課税標準の特例(課税標準の軽減)
これは、税率を掛ける前の「課税標準」そのものを減額する措置です。
<例>固定資産税の住宅用地の特例:住宅が建っている土地(住宅用地)は、その面積に応じて課税標準が1/3や1/6に減額されます。
計算式でいうと、(課税標準 - 控除額) × 税率 = 税額 というイメージです。
(実際には減額割合で計算することが多いですが) - 軽減税率(けいげんぜいりつ)
これは、通常適用される税率よりも低い税率を適用する措置です。
登録免許税の住宅用家屋の軽減税率:一定の要件を満たすマイホームの登記については、通常の税率よりも低い税率が適用されます。
計算式でいうと、課税標準 × (低い税率) = 税額 となります。
「税率から控除する」のではなく、「適用される税率そのものが低くなる」という点に注意してください。 - 税額控除(ぜいがくこうじょ)
これは、課税標準に税率を掛けて計算された「税額」から、直接一定の金額を差し引く措置です。
<例>所得税の住宅ローン控除:年末のローン残高に応じて計算された金額が、所得税額から直接差し引かれます。
計算式でいうと、(課税標準 × 税率)- 控除額 = 税額 となります。
<ポイント>
「課税標準から引かれるのか(課税標準の特例)」、「税率自体が低くなるのか(軽減税率)」、「計算された税額から引かれるのか(税額控除)」によって、最終的に納める税額は大きく変わってきます!
特に、「課税標準の特例」と「税額控除」を混同しないように注意してください。どっちから引かれるかで効果が全然違いますからね!

どこで安くなるかで、意味合いが全く違うんですね!これはしっかり区別して覚えないと!
まとめ
今回は、宅建試験の「税金」分野の学習を始めるにあたって、まずは知っておきたい全体像と基本的な考え方について解説しました。
たくさんの税金の種類があって難しく感じるかもしれませんが、宅建試験で問われるのは主に5つの税金であり、それぞれのポイントを押さえて学習すれば、決して攻略できない分野ではありません。
最後に、今日の重要ポイントをまとめておきましょう!
- 税金は国税(国に納める)と地方税(都道府県・市町村に納める)に大別されます。
- 宅建試験で重要なのは、所得税(譲渡所得)、印紙税、登録免許税(以上、国税)、不動産取得税(道府県税)、固定資産税(市町村税)の5つです。
- 各税金にはそれぞれ特徴があり、譲渡所得の特例(所得税)、課税文書の区別(印紙税)、住宅用家屋の軽減措置(登録免許税)、課税標準の特例(不動産取得税・固定資産税)などが重要な学習ポイントです。
- 税額計算の基本式は 課税標準 × 税率 = 税額 です。
- 税負担を軽減する措置には、課税標準の特例(課税標準から控除)、軽減税率(低い税率を適用)、税額控除(税額から直接控除)の3種類があり、その違いを理解することが重要です。

税金の全体像が見えてきましたか?まずはこの基本を押さえて、これから各税金の詳細な学習に進んでいきましょう!