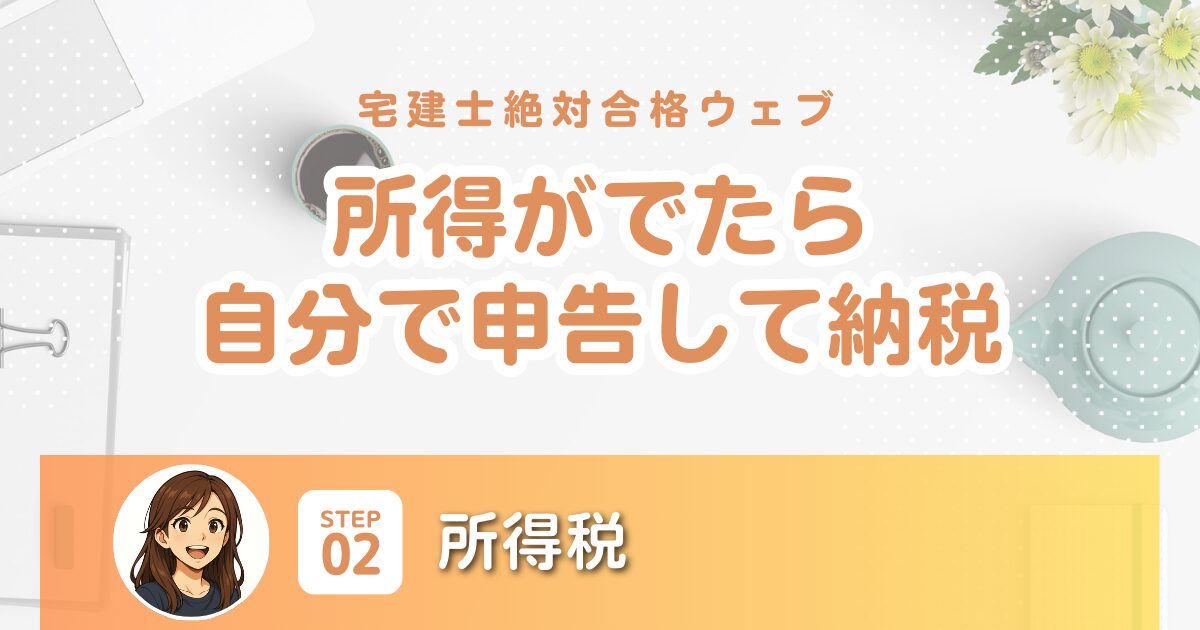宅建試験の「税金」分野、中でも「所得税」と聞くと、「なんだか難しそう…」「確定申告とかよくわからないし…」と、ちょっと身構えてしまう方も多いのではないでしょうか?普段、会社員の方だと給与から天引きされていることが多いので、自分で計算する機会は少ないかもしれませんね。特に不動産を売ったときの税金(譲渡所得)となると、特例がたくさんあって、「3000万円控除?買換え特例?軽減税率?どれが使えるの?」「一緒に使える特例はあるの?」と、頭がこんがらがってしまいがちですよね。
不動産を売却して利益が出た場合にかかるのが「譲渡所得」に対する所得税ですが、マイホーム(居住用財産)の売却など、特定のケースでは税金の負担を軽くするための様々な特例制度が用意されています。これらの特例を知っているかどうかで、納める税金の額が大きく変わることも!宅建試験でも毎年必ずと言っていいほど、これらの特例の適用要件や、複数の特例を併用(重複適用)できるかどうかが問われます。ここは絶対に落とせない重要ポイントです!
この記事では、そんな複雑に見える所得税(譲渡所得)の特例について、特に宅建試験で重要な「3000万円特別控除」「買換え特例」「軽減税率」、そして関連性の高い「住宅ローン控除」などを中心に、それぞれの内容、適用されるための条件(要件)、そしてどの特例が一緒に使えるのか(重複適用)などを、わかりやすく整理して解説していきます。

この記事を読めば、ややこしい譲渡所得の特例がスッキリ理解でき、試験で問われるポイントをしっかり押さえることができますよ!
<この記事でわかること>
- 不動産を売った時の所得税(譲渡所得)の基本的な考え方
- 居住用財産(マイホーム)売却時の主な特例(3000万円控除、買換え特例、軽減税率)の内容と適用要件
- 収用された場合の5000万円特別控除のポイント
- 各特例を一緒に使えるか(重複適用)のルール
- 住宅ローン控除の概要と、譲渡所得の特例との関係
所得税(譲渡所得)の基本 | 分離課税と計算方法、学習のポイント
まずは、不動産を売ったときの所得税(譲渡所得)の基本的な考え方から押さえましょう。
給与所得とは別モノ?譲渡所得の「分離課税」
皆さんがお給料としてもらう所得は「給与所得」ですが、不動産を売って得た利益は「譲渡所得」という、また別の種類の所得になります。
所得税の計算では、通常、給与所得や事業所得など様々な所得を合計して税額を計算するのですが(これを総合課税といいます)、土地や建物の譲渡所得は、これらの他の所得とは分けて(分離して)税額を計算するルールになっています。これを「分離課税」といいます。
なぜ分離課税かというと、不動産の売却益は一時的に大きな金額になることが多く、他の所得と合算するとその年だけ税率が極端に高くなってしまう可能性があるため、特別な計算方法をとっているんですね。

分離課税にして、給料とは別に計算するんですね。
譲渡所得の計算方法と税率の基本
譲渡所得にかかる所得税額も、基本的には「課税標準 × 税率」で計算されます。
譲渡所得の場合の「課税標準」にあたるのが「課税譲渡所得金額」で、これは以下のように計算されます。
収入金額(=売った値段) - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除額 = 課税譲渡所得金額
- 取得費:その不動産を買った時の代金や手数料など。
- 譲渡費用:売るためにかかった仲介手数料や印紙代など。
- 特別控除額:後で説明する3000万円特別控除などの特例による控除額。
そして、この課税譲渡所得金額に掛ける「税率」は、売った不動産の所有期間によって大きく異なります。
- 長期譲渡所得:譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超える場合。所得税率は原則15%。
- 短期譲渡所得:譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年以下の場合。所得税率は原則30%。
所有期間の判定日は「譲渡した年の1月1日時点」という点に注意!年の途中で5年を超えても、その年の1月1日時点で5年以下なら短期譲渡になります。短期の方が税率が高いのは、投機的な短期売買を抑制するためです。
(※上記の税率は所得税のみの税率です。実際にはこれに加えて住民税がかかります。)
最重要!特例・軽減税率の理解と重複適用
譲渡所得の計算は上記の通りですが、宅建試験で最も重要なのは、特定のケースで税負担が軽減される様々な特例や軽減税率です。
特に重要なのは以下の2点です。
- それぞれの特例の内容と、それを受けるための適用要件を正確に覚えること。
- 複数の特例の適用要件を満たす場合に、それらを一緒に使うことができるか(重複適用できるか)を判断できること。
どの特例が適用できるのか?そして、その組み合わせはOKなのか?ここが譲渡所得の問題を解く上での最大のカギになります!
【頻出特例】控除・買換え・軽減税率を徹底解説! | 適用要件と注意点
それでは、宅建試験で頻出の譲渡所得に関する特例を見ていきましょう。
マイホーム売却の強い味方!居住用財産の3000万円特別控除
これは、自分が住んでいた家(居住用財産)を売却した場合に、譲渡所得から最高3000万円まで控除できる、非常に有利な特例です(課税標準の特例)。
【概要】
譲渡所得の計算式で見た「特別控除額」の部分で、最大3000万円を差し引くことができます。つまり、譲渡益が3000万円以下であれば、この特例を使えば所得税はかからなくなる、ということです。
【主な適用要件】
- 自分が住んでいた家屋、または家屋とその敷地の譲渡であること。
- 家屋に住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の年末までに譲渡すること。(転勤などで引っ越した後でも、一定期間内なら適用可能です!)
- 売った相手が、配偶者や直系血族(親子、祖父母、孫など)、生計を一にする親族など、特別な関係のある人でないこと。
- その年の前年または前々年に、この3000万円特別控除や、後述する買換え特例など特定の特例を受けていないこと。(原則として3年に1回しか使えません)
- 所有期間や居住期間の長さは問われません! たとえ買って半年で売ったとしても、要件を満たせば適用できます。
【重複適用について】
- 特定の居住用財産の買換え特例とは併用できません。どちらか一方を選択適用します。
- 住宅ローン控除とは、原則として併用できません。(3000万円控除を適用する年、その前年、前々年に居住した家については、住宅ローン控除は受けられません。逆も同様です。)
- 後述する居住用財産の軽減税率とは併用可能です!

所有期間に関係なく3000万円も控除されるなんて、すごい特例ですね!
公共事業に協力したら?収用交換等の5000万円特別控除
自分の土地などが、道路建設などの公共事業のために国や地方公共団体などに買い取られた場合(収用交換等といいます)にも、譲渡所得から最高5000万円まで控除できる特別控除があります。
【概要】
これも課税標準の特例で、譲渡所得から最高5000万円を控除できます。
【重複適用について】
- 居住用財産の3000万円特別控除とは選択適用です。両方は使えません。通常は控除額の大きい5000万円控除を選択します。
- 居住用財産の軽減税率とは併用可能です。
- 後述する優良住宅地等のための軽減税率とは併用できません。
<ポイント>
宅建試験では、3000万円控除の方が圧倒的に重要ですが、5000万円控除も存在し、特に重複適用のルールは問われる可能性があります。
住み替えを応援!特定の居住用財産の買換え特例
マイホームを売って、新しいマイホームに買い換える場合に使える特例です。これは控除ではなく、譲渡益に対する課税を、買い換えたマイホームを将来売却する時まで繰り延べる(先送りにする)という制度です。
【概要】
例えば、家Aを5000万円で売り(取得費等は無視)、家Bを7000万円で買った場合、本来なら家Aの売却益に課税されますが、この特例を使えば、その課税は行われず、将来家Bを売却した時に、家Aの利益も含めて課税される、という仕組みです。もし、家Aを5000万円で売り、家Bを4000万円で買った場合は、差額の1000万円部分については、売却した年に課税されます。
<注意>
指示内容に「譲渡益の部分に課税する」とありましたが、正確には「課税を繰り延べる」制度です。非課税になるわけではありません。
【主な適用要件】
この特例は、適用要件が非常に厳しいのが特徴です!
- 【売った資産について】
- 居住用財産であること(3年ルールあり)、譲渡先制限は3000万円控除と同様。
- 家屋・敷地ともに、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えていること。
- その家屋に居住していた期間が10年以上であること。
- 売った代金(譲渡対価)が1億円以下であること。
- 【買った資産(買換資産)について】
- 床面積が50㎡以上、敷地面積が500㎡以下であること。
- 中古の場合は、一定の築年数要件(耐火建築物は築25年以内など)を満たすか、新耐震基準に適合していること。
- 売った年の前年から、売った年の翌年末までの3年間に取得すること。
- 取得した年の翌年末までに居住すること。
【重複適用について】
- 居住用財産の3000万円特別控除、軽減税率とは併用できません。
- 住宅ローン控除とも併用できません。

うーん、要件がすごく細かいですね…。10年以上の所有・居住、1億円以下、買った家の面積や築年数まで…。覚えるのが大変そう…
税率が低くなる!2つの軽減税率
譲渡所得にかかる税率が、通常よりも低くなる特例もあります。
長く住んだマイホームなら!居住用財産の軽減税率
【概要】
自分が住んでいた家(居住用財産)で、所有期間が10年を超えているものを売却した場合に、長期譲渡所得の税率がさらに軽減される制度です。
【適用要件】
- 譲渡した年の1月1日時点で所有期間が10年を超える居住用財産であること。(3年ルール、譲渡先制限などは3000万円控除と同様)
【軽減税率】
課税長期譲渡所得金額のうち、
- 6000万円以下の部分 ⇒ 所得税率 10% (通常15%)
- 6000万円を超える部分 ⇒ 所得税率 15% (通常通り)
<注意>
例えば、課税長期譲渡所得が7000万円の場合、6000万円部分が10%、残りの1000万円部分が15%となります。全額が15%になるわけではありません。
【重複適用について】
- 居住用財産の3000万円特別控除、収用等の5000万円特別控除と併用可能です! 併用する場合、特別控除を差し引いた後の金額で、6000万円以下かどうかを判断します。
- 買換え特例とは併用できません。
<チェック>
所有期間10年超がポイント!3000万円控除とセットで使えるのが大きい!
公共目的の土地譲渡なら!優良住宅地等のための土地譲渡の軽減税率
【概要】
所有期間が5年を超える土地などを、国や地方公共団体、UR都市機構などに、優良な住宅地の供給などの目的のために買い取られた場合に、長期譲渡所得の税率が軽減される制度です。
【適用要件】
- 譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超える土地等であること。
- 譲渡先が国、地方公共団体、UR都市機構など一定の公共的な主体であること。
【軽減税率】
課税長期譲渡所得金額のうち、
- 2000万円以下の部分 ⇒ 所得税率 10% (通常15%)
- 2000万円を超える部分 ⇒ 所得税率 15% (通常通り)
【重複適用について】
- 居住用財産の3000万円特別控除、収用等の5000万円特別控除とは併用できません!
<ポイント>
こちらは所有期間5年超が要件ですが、適用される場面が限定的で、特別控除との併用ができない点が特徴です。
<軽減税率の比較表>
| 種類 | 対象 | 所有期間要件 | 軽減税率(所得税) | 特別控除との併用 |
|---|---|---|---|---|
| 居住用財産の軽減税率 | 居住用財産 | 10年超 | 6000万円以下:10% 6000万円超 :15% | 3000万/5000万控除と併用可 |
| 優良住宅地等の軽減税率 | 土地等(譲渡先限定) | 5年超 | 2000万円以下:10% 2000万円超 :15% | 特別控除と併用不可 |
【重要】特例の重複適用(併用)まとめ
これまで見てきた特例の重複適用(併用)の可否は、試験で頻繁に問われます。ここでしっかり整理しておきましょう!
<特例の重複適用 可否一覧表>
| \ | 3000万円控除 | 5000万円控除 | 買換え特例 | 居住用軽減税率 | 優良住宅地軽減税率 | 住宅ローン控除 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000万円控除 | - | × (選択) | × | 〇 | × | × (原則) |
| 5000万円控除 | × (選択) | - | -※ | 〇 | × | 〇 |
| 買換え特例 | × | -※ | - | × | -※ | × |
| 居住用軽減税率 | 〇 | 〇 | × | - | -※ | × (原則) |
| 優良住宅地軽減税率 | × | × | -※ | -※ | - | 〇 |
| 住宅ローン控除 | × (原則) | 〇 | × | × (原則) | 〇 | - |
※併用する場面が通常想定されない組み合わせは「-」としています。

この表は便利!どの組み合わせがOKで、どれがNGなのか、しっかり覚えよう!
住宅ローン控除も忘れずに! | マイホーム取得・リフォームの税額控除
最後に、譲渡所得の特例と関連が深い「住宅ローン控除」についても触れておきましょう。これは家を買ったりリフォームしたりする際の特例ですが、譲渡所得の特例との併用関係が試験で問われることがあります。
定番!住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)
【概要】
個人が住宅ローン等を利用してマイホームを新築、取得、または増改築等した場合に、年末のローン残高に応じて計算された金額が、所得税額から直接控除される(税額控除)制度です。所得税から控除しきれない場合は、翌年の住民税からも一部控除されます。
【主な適用要件】
適用要件は非常に細かく、また税制改正で変更されることが多いので、常に最新情報の確認が必要ですが、主なポイントは以下の通りです(2025年4月13日現在の一般的な情報として)。
- 住宅を取得してから6ヶ月以内に入居し、控除を受ける年の年末まで引き続き住んでいること。
- ローンの償還期間(返済期間)が10年以上であること。
- 家屋の床面積が原則50㎡以上であること(合計所得金額1000万円以下の場合は40㎡以上に緩和)。
- 床面積の2分の1以上が自己の居住用であること。
- 中古住宅の場合は、一定の築年数要件(耐火25年以内、非耐火20年以内など)を満たすか、新耐震基準適合証明などがあること。
- 控除を受ける年の合計所得金額が2000万円以下であること(床面積40㎡台の場合は1000万円以下)。
【重複適用について】
- 居住用財産の譲渡所得の特例(3000万円控除、買換え特例、軽減税率)とは、原則として併用できません。具体的には、自分が住んでいる家(またはその敷地)についてこれらの譲渡所得の特例の適用を受ける場合、その居住年はもちろん、その前2年、後2年の計5年間は、住宅ローン控除の適用は受けられません。(逆も同様)
- ただし、収用交換等の5000万円特別控除や、譲渡損失の繰越控除などとは併用可能です。
<ポイント>
マイホームの売却特例と購入時のローン控除は、基本的には同時期には使えない、と覚えておきましょう。
特定の改修工事も対象!バリアフリー改修等の住宅ローン控除
【概要】
高齢者や要介護者などがいる世帯が、自宅に一定のバリアフリー改修工事や省エネ改修工事などをローンを組んで行った場合に、年末ローン残高に応じて所得税額から控除される制度もあります(特定増改築等住宅借入金等特別控除)。
【主な適用要件】
これも要件が細かいですが、主なものは以下の通りです(2025年4月13日現在の一般的な情報として)。
- 居住者の要件:50歳以上の人、要介護・要支援認定を受けている人、障害のある人、またはこれらの人と同居している親族など。
- 工事内容:手すりの設置、段差解消、浴室・トイレの改良などのバリアフリー改修、窓の断熱改修などの省エネ改修など、対象工事が定められています。一定の工事費要件もあります。
- 家屋の要件:床面積50㎡以上など。
- ローン要件:償還期間が5年以上など(※通常の住宅ローン控除と異なる場合があるので注意)。
- 所得要件:合計所得金額が3000万円以下など。
【重複適用について】
これも、通常の住宅ローン控除と同様に、居住用財産の譲渡所得の特例(3000万円控除等)とは原則併用できませんが、収用等の5000万円控除等とは併用可能です。

リフォームローンでも税金が戻ってくる場合があるんですね!対象工事や要件はしっかり確認が必要ですね。
(※税制は頻繁に改正されます。特に住宅ローン控除やリフォーム減税に関する要件(床面積、所得制限、対象工事、控除額、適用期限など)は、常に最新の情報を国税庁のウェブサイトなどで確認するようにしてください。)
まとめ
今回は、宅建試験の所得税(譲渡所得)分野で最も重要な、各種特例について詳しく解説しました。多くの特例があり、適用要件も複雑ですが、マイホームの売買など身近なケースに関わるものも多く、しっかり理解しておきたい内容です。
最後に、今回の重要ポイントをしっかり復習しましょう!
- 不動産の譲渡所得は、他の所得と分けて計算する分離課税です。
- 居住用財産の3000万円特別控除は、所有期間に関係なく適用でき、譲渡益から最大3000万円を控除できますが、買換え特例や住宅ローン控除とは併用できません。
- 特定の居住用財産の買換え特例は、所有期間10年超・居住期間10年以上などの厳しい要件がありますが、譲渡益への課税を繰り延べできます。他の多くの特例と併用できません。
- 居住用財産の軽減税率は、所有期間10年超の場合に適用でき、税率が低くなります。3000万円・5000万円特別控除と併用可能です。
- 収用交換等の5000万円特別控除は、公共事業による収用などの場合に適用でき、居住用軽減税率と併用できます。
- 住宅ローン控除は、マイホーム取得等の際に税額控除を受けられる制度ですが、居住用財産の譲渡所得の主要な特例とは原則として併用できません。
- 各特例の適用要件(期間、金額、面積、譲渡先など)と、重複適用の可否を正確に覚えることが、宅建試験対策の鍵です。

複雑な特例も、一つ一つの要件と重複適用のルールを整理すれば、きっと理解できます!過去問演習で知識を定着させましょう!