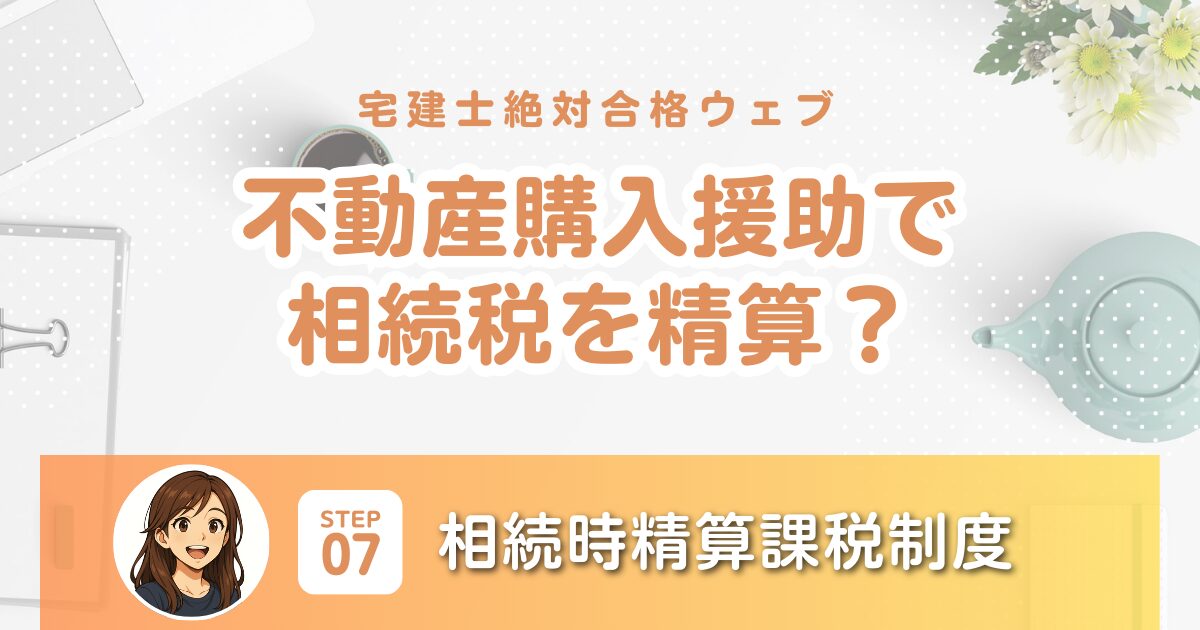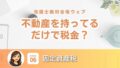今回は「相続時精算課税制度」について解説しますね。「なんだか難しそう…」「贈与税とか相続税とか、税金の話はややこしくて…」って感じていませんか? そうですよね、税金の制度って専門用語も多いし、仕組みが複雑だったりして、とっつきにくいイメージがあるかもしれません。
特に、大きな金額が動くマイホーム購入の際には、贈与税がどれくらいかかるのか、節税する方法はないのか、すごく気になりますよね。せっかく親御さんが「家を買うなら援助するよ」と言ってくれても、その援助に多額の贈与税がかかってしまうと、実際に手元に残るお金が想像よりずっと少なくなってしまって、計画が狂ってしまう…なんてこともあり得ます。
そこで役立つのが、今回ご紹介する「相続時精算課税制度」や「住宅取得等資金の贈与に関する特例」なんです。これらの制度を上手に活用すれば、贈与税の負担を大きく減らしたり、場合によってはゼロにできたりする可能性もあるんですよ!知っているのと知らないのとでは大違いなんです。
この記事では、相続時精算課税制度の基本的な仕組みから、具体的なメリット・デメリット、そして特にマイホーム購入を考えている方に関係の深い「住宅取得等資金の贈与」に関するお得な特例について、できるだけ専門用語をかみ砕いて、わかりやすく解説していきます。この記事を読み終える頃には、ご自身の状況に合わせてどの制度が利用できそうか、どんな点に注意すればいいのかが、きっとクリアになっているはずですよ。

税金の制度は毎年のように改正があります。特に相続・贈与関連は大きな変更が多いので、常に最新の情報をチェックすることが大切ですよ!
<この記事でわかること>
- 相続時精算課税制度の基本的な仕組みと2024年改正のポイントについて理解できる
- 相続時精算課税制度のメリット・デメリットの対策がわかる
- 具体的なケースで、どれくらい税金が変わるかのシミュレーションのポイントが整理できる
- 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例との違いがわかる
- 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度が明確になる
相続時精算課税制度とは?|仕組み・メリット・デメリットを徹底解説!
まずは、相続時精算課税制度がどんな制度なのか、基本的な仕組みからメリット・デメリット、そしてもう一つの代表的な贈与税の制度である「暦年課税」との違いまで、じっくり見ていきましょう!
相続時精算課税制度の基本的な仕組み
相続時精算課税制度は、原則として60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫(贈与を受けた年の1月1日時点での年齢です)に対して財産を贈与した場合に、贈与を受けた側(子や孫)が選択できる贈与税の制度です。

「選択できる」というのがポイントですね。自動的に適用されるわけではなく、贈与を受けた人が自分で「この制度を使います!」と選んで、税務署に手続きをする必要があります。
この制度を選択すると、どうなるかというと…
- 贈与者(あげる人、例えばお父さん)ごとに、累計で2,500万円までの贈与については「特別控除」として、贈与税がかかりません。
- 累計で2,500万円を超えた部分については、その超えた金額に対して一律20%の税率で贈与税が課税されます。
「えっ、じゃあお父さんから2,500万円、お母さんから2,500万円、合計5,000万円まで非課税で貰えるってこと?」って思いますよね。贈与の時点では、確かにその通りです。でも、この制度の名前をもう一度見てください。「相続時」に「精算」する、とありますよね。
これがこの制度の最大の特徴なんです。
どういうことかというと、この制度を使って贈与された財産(の価額)は、贈与した人(お父さんやお母さん)が将来亡くなった時に、その人の相続財産に「持ち戻して」相続税として計算し直されるんです。
つまり、贈与の時点では税負担が軽くなる(またはゼロになる)けれど、それはあくまで「先送り」であって、最終的には相続の時に、もともとあった相続財産とその贈与された財産を合算して相続税を計算しますよ、という制度なんです。もし贈与時に20%の贈与税を支払っていた場合は、その支払った贈与税額は、計算された相続税額から差し引かれます(二重課税にならないようになっています)。
<ポイント>2024年1月1日以降の贈与から新ルール! 年間110万円の基礎控除が創設!
実は、この相続時精算課税制度、2024年1月1日から大きな改正があって、ぐっと使いやすくなりました!
それは、これまで説明した特別控除2,500万円の枠とは「別枠」で、年間110万円までの「基礎控除」が新たに設けられたことです!
この年間110万円以下の贈与については、なんと…
- 贈与税の申告が不要に!
- 将来の相続財産に加算する必要もなくなったんです!
これは本当に大きなメリットです! 以前の制度では、相続時精算課税制度を選択すると、たとえ年間10万円とかの少額の贈与であっても、毎年必ず申告が必要でしたし、その全額が将来の相続財産に加算されていました。それが、今回の改正で年間110万円までなら、申告も将来の相続への影響も気にせずに贈与できるようになったんです。

年間110万円までなら、申告も将来の相続財産への加算も気にせず贈与できるようになったのは、本当に嬉しい改正ですよね! これで、お小遣い感覚での支援もしやすくなりました。
相続時精算課税制度のメリット
では、この制度を利用するメリットを改めて整理してみましょう。
- 一度にまとまった金額を贈与しやすい: なんといっても、特別控除2,500万円(+新たにできた年間110万円の基礎控除)という大きな非課税枠があるのが魅力です。例えば、住宅購入の頭金など、大きな金額を生前に、贈与税の負担なく(または少なく)子や孫に移すことができます。通常の暦年課税(後述します)の基礎控除は年間110万円なので、例えば2,000万円を贈与しようとすると約18年もかかってしまいますからね。
- 将来値上がりしそうな財産を早めに贈与できる: 相続時に加算される贈与財産の価額は、原則として「贈与した時の価額」で評価されます。そのため、将来価値が上がりそうな株式や、開発予定のある地域の土地などを早めにこの制度で贈与しておけば、相続時の評価額を低く抑えられ、結果的に相続税の節税につながる可能性があります。
- 贈与者の年齢要件がない場合がある(住宅取得等資金): 後で詳しく説明しますが、マイホームの購入資金(住宅取得等資金)として贈与を受ける場合にこの制度を選択するときは、特例により、贈与者である親や祖父母が60歳未満でもOKになります。
- 収益物件の早期移転で収益を子・孫に移せる: 賃貸アパートや駐車場など、収益を生む不動産を早めに子や孫に贈与すれば、その後の家賃収入などを子や孫自身の所得にすることができます。所得の分散効果も期待できますね。
- 年間110万円の基礎控除で少額贈与が手軽に: 2024年の改正により、年間110万円までなら申告不要・相続財産への加算不要で贈与できるようになったため、制度全体の使い勝手が格段に向上しました。これまでは少額贈与でも申告が必要だったため敬遠していた人も、利用しやすくなったと言えます。
相続時精算課税制度のデメリット・注意点
メリットがたくさんある一方で、デメリットや注意点もしっかり理解しておく必要があります。特に、一度選択すると後戻りできない点には要注意です!
- 一度選択すると暦年課税に戻れない: これが最大の注意点であり、デメリットとも言えます。例えば、お父さんからの贈与について一度「相続時精算課税制度」を選択すると、その後、お父さんからの贈与については、もう一つの制度である「暦年課税」(年間110万円まで非課税)の基礎控除を使うことは二度とできません。 制度を選択する際は、将来のこともよく考えて、本当にこの制度で良いのか慎重に判断する必要があります。(※ただし、2024年改正で新設された「年間110万円の基礎控除」は、暦年課税の基礎控除とは別物なので、相続時精算課税を選択した後も利用できます。ややこしいですが、区別してくださいね。)
- 年間110万円超の贈与は毎年申告が必要: 新設された基礎控除110万円を超えて、特別控除2,500万円以下の贈与を受けた場合、たとえ贈与税額が計算上ゼロ円であっても、贈与を受けた年の翌年に贈与税の申告が必要です。これを忘れると、特別控除が使えなくなってしまう可能性があるので注意が必要です。
- 相続時に手続きが必要: 贈与した人が亡くなった際には、この制度で贈与された財産(基礎控除110万円分を除く)を相続財産にきちんと加えて相続税の申告をする必要があります。 どの財産をいつ、いくらで贈与されたのか、記録や贈与契約書などをしっかり保管しておくことが大切になります。
- 小規模宅地等の特例が使えない可能性: 相続税には、亡くなった人が住んでいた土地などの評価額を最大80%も減額できる「小規模宅地等の特例」という非常に有利な制度があります。しかし、相続時精算課税制度を使って贈与された土地については、原則としてこの特例の適用を受けることができません。 自宅の敷地などをこの制度で生前贈与する場合は、このデメリットを十分に考慮する必要があります。
- 将来値下がりした場合は不利になることも: メリットの裏返しですが、贈与した時よりも相続が発生した時の方が財産の価値が下がってしまった場合でも、原則として「贈与時の価額」で相続財産に加算されるため、結果的に相続税が高くなってしまう可能性があります。(※ただし、贈与された土地や建物が災害によって一定以上の被害を受けた場合には、相続時に価額を再計算できる場合があります。)
- 贈与税の納税が必要になる場合がある: 累計の贈与額が特別控除2,500万円(+基礎控除110万円)を超えると、その超えた部分に20%の贈与税がかかります。将来、相続税から差し引かれるとはいえ、贈与の時点で一時的に納税資金を用意する必要が出てきます。

メリット・デメリットをしっかり比較して、ご自身の状況や将来の見通しに合った制度かどうか、じっくり見極めることが本当に重要ですね。
暦年課税との比較
ここで、もう一つの代表的な贈与税の課税方法である「暦年課税(れきねんかぜい)」と比較してみましょう。一般的に「贈与税」というと、こちらの暦年課税を指すことが多いです。
暦年課税は、1年間(1月1日から12月31日まで)に贈与を受けた財産の合計額が、基礎控除額である110万円を超えた場合に、その超えた部分に対して贈与税がかかる制度です。税率は、金額に応じて10%から最大55%までの超過累進税率となっています。
相続時精算課税制度との主な違いを表にまとめました。
<暦年課税と相続時精算課税制度の比較表>
| 項目 | 暦年課税 | 相続時精算課税制度 |
|---|---|---|
| 基礎控除額 | 年間110万円 | 年間110万円(2024年1月1日以降の贈与) |
| 特別控除額 | なし | 累計2,500万円 |
| 税率 | 超過累進税率(10%~55%) | 特別控除超は一律20% |
| 対象者(贈与者) | 制限なし | 原則60歳以上の父母・祖父母(※住宅取得等資金贈与などは例外あり) |
| 対象者(受贈者) | 制限なし | 18歳以上の子・孫 |
| 申告 | 年間110万円超の場合に必要 | 年間110万円超の場合に必要(贈与税額0円でも必要) |
| 相続時の扱い | 死亡前7年以内の贈与は相続財産に加算(※注) | 贈与財産(基礎控除分を除く)は全額相続財産に加算 |
| 制度変更 | (相続時精算課税を選択したら戻れない) | 暦年課税には戻れない |
| 小規模宅地等の特例 | 対象(相続開始前7年以内の贈与は除くなど要件あり) | 原則対象外 |
スクロールできます
(※注)暦年課税の相続財産への加算期間について
以前は、暦年課税で贈与された財産のうち、相続開始前「3年以内」のものが相続財産への加算対象でした。しかし、税制改正により、この期間が段階的に「7年以内」に延長されることになりました。具体的には、2024年1月1日以降の贈与から適用され、2027年1月1日から段階的に期間が延びていき、最終的に2031年1月1日以降は、相続開始前7年以内の贈与が加算対象となります。この点も、どちらの制度を選択するか判断する上で重要になりますね。
どちらの制度が有利かは、一概には言えません。贈与したい金額の大きさ、贈与する財産の種類(現金、不動産、株式など)、贈与を受ける人の状況、そして将来の相続がどうなりそうか(相続財産の額や相続人の数)など、様々な要因によって変わってきます。
相続時精算課税制度の具体例|どれくらい税金が変わる?

具体例で見てみると、違いが分かりやすいですよ!ちょっと計算してみましょう。
では、具体的に相続時精算課税制度を使うと、税金の負担がどのように変わる可能性があるのか、簡単なケースでシミュレーションしてみましょう。
ケース1:父から子へ2,000万円の現金を贈与する場合(父の相続財産が他に5,000万円ある場合)
【前提】
- 贈与を受ける子:18歳以上
- 贈与する父:60歳以上
- 贈与日:2024年1月1日以降
- 父が亡くなった時の相続財産(今回の贈与分を除く):5,000万円
- 相続人:子1人のみ
【暦年課税の場合】
- 贈与税の計算
- 基礎控除:110万円
- 課税価格:2,000万円 – 110万円 = 1,890万円
- 贈与税額:1,890万円 × 45% – 265万円 = 約585.5万円 (※特例税率(直系尊属からの贈与)を使用)
- 相続税の計算(父死亡時)
- 相続財産:5,000万円
- 暦年贈与加算:今回の贈与が死亡前7年以内であれば、1,890万円が加算されます。ここでは加算されると仮定します。
- 課税対象の遺産総額:5,000万円 + 1,890万円 = 6,890万円
- 相続税の基礎控除:3,000万円 + 600万円 × 1人 = 3,600万円
- 課税遺産総額:6,890万円 – 3,600万円 = 3,290万円
- 相続税額:3,290万円 × 15% – 50万円 = 443.5万円
- 合計税負担(贈与税+相続税)
- 約585.5万円 + 443.5万円 = 約1,029万円

2,000万円もらっても、贈与税だけで約585万円も!最終的な税負担もかなり大きいですね…
【相続時精算課税制度を選択した場合】
- 贈与税の計算
- 基礎控除:110万円
- 特別控除:2,500万円
- 贈与額2,000万円から基礎控除110万円を引くと1,890万円。これは特別控除2,500万円の範囲内です。
- 贈与税額:0円 (ただし、贈与税の申告は必要です)
- 相続税の計算(父死亡時)
- 相続財産:5,000万円
- 相続時精算課税での贈与加算額:1,890万円(基礎控除110万円を差し引いた額)
- 課税対象となる遺産総額:5,000万円 + 1,890万円 = 6,890万円
- 相続税の基礎控除:3,600万円
- 課税遺産総額:6,890万円 – 3,600万円 = 3,290万円
- 相続税額:3,290万円 × 15% – 50万円 = 443.5万円
- 合計税負担(贈与税+相続税)
- 0円 + 443.5万円 = 443.5万円
このケースでは、贈与時点での税負担は相続時精算課税制度の方が圧倒的に軽いですね!そして、最終的な合計税負担で見ても、相続時精算課税制度の方が有利になりました。
以前の回答では相続税が高くなる結果でしたが、暦年課税の贈与税計算と相続税率の適用を修正した結果、このケースでは相続時精算課税制度が有利という結論に変わりました。このように、前提条件や税率の適用一つで結果が大きく変わるのが税金計算の難しいところです。

なるほど! 贈与税の負担をなくして早く資金を渡せるメリットが大きいですね。相続税の加算も、基礎控除分はされないのがポイントですね。
ケース2:父から子へ2,000万円の現金を贈与。父死亡時の相続財産が0円の場合
では、先ほどの例で、もしお父さんが亡くなった時の相続財産が、今回の贈与以外に全くなかったらどうなるでしょうか?
【暦年課税の場合】
- 贈与税:約585.5万円 (ケース1と同じ)
- 相続税:
- 相続財産:0円
- 暦年贈与加算:1,890万円(死亡前7年以内と仮定)
- 課税対象の遺産総額:0円 + 1,890万円 = 1,890万円
- 基礎控除:3,600万円
- 課税遺産総額:1,890万円 – 3,600万円 = 0円(マイナスなので0円)
- 相続税額:0円
- 合計税負担:約585.5万円 + 0円 = 約585.5万円
【相続時精算課税制度を選択した場合】
- 贈与税:0円 (ケース1と同じ)
- 相続税:
- 相続財産:0円
- 相続時精算課税での贈与加算額:1,890万円
- 課税対象となる遺産総額:0円 + 1,890万円 = 1,890万円
- 基礎控除:3,600万円
- 課税遺産総額:1,890万円 – 3,600万円 = 0円(マイナスなので0円)
- 相続税額:0円
- 合計税負担:0円 + 0円 = 0円

このケースだと、相続時精算課税制度を選べば、贈与税も相続税も全くかからずに2,000万円を受け取れるんですね!これは大きい!
このように、将来の相続税があまりかからない(相続財産が基礎控除以下である)と予想される場合には、相続時精算課税制度は非常に有効な選択肢になります。生前にまとまった財産を非課税(または低税率)で移転できるメリットが最大限に活かせるからです。
シミュレーションの注意点
ただし、これらのシミュレーションはあくまで非常に簡略化されたモデルケースです。実際には、相続人の数、他の相続財産の内容(不動産や有価証券など)、生命保険金の有無、債務の有無など、様々な要素が絡み合って税額が決まります。
また、将来の税制改正によって、制度内容や税率が変わる可能性も常にあります。
したがって、これらの例はあくまで参考程度にとどめ、実際に制度を利用する前には、必ず税理士などの専門家に相談し、ご自身の状況に合わせた詳細なシミュレーションとアドバイスを受けるようにしてください。
【マイホーム購入者必見】住宅取得等資金贈与の特例を使いこなそう!
さて、ここからは宅建士試験の受験者の方や、まさにこれからマイホームの購入を考えている、あるいは親御さんからの資金援助を検討している方にとって、特に重要な特例について詳しく解説していきます!
親や祖父母からマイホームの購入資金を援助してもらう場合に使える、贈与税が軽くなる(またはゼロになる)とってもお得な制度が、実は2つもあるんです。これらをうまく組み合わせることで、大きな節税効果が期待できますよ!
① 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例
一つ目は、これまで説明してきた「相続時精算課税制度」の、いわば「住宅購入バージョン」とも言える特例です。
通常の相続時精算課税制度では、贈与者(あげる人)は原則として60歳以上でないとダメ、という年齢要件がありましたよね。
しかし、贈与する目的が「住宅取得等資金(マイホームの購入や新築、増改築のためのお金)」である場合には、この特例を使うことで、贈与者(親や祖父母)の年齢に関わらず、相続時精算課税制度を選択できるんです!
【特例の主な要件】
この特例を使うためには、いくつかの要件を満たす必要があります。主なものを挙げてみますね。
- 資金の使い道:贈与されたお金を、自分が住むための住宅用家屋の新築、取得(購入)、または増改築等の対価に充てること。(土地を先に購入して、その後家を建てる場合の、その土地の購入資金も対象になります)
- 贈与者:直系尊属(父母、祖父母など)であること。年齢は問いません。
- 受贈者(もらう人):贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の子または孫であること。そして、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。(※ただし、取得する住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は、合計所得金額が1,000万円以下である必要があります)
- 家屋の要件:取得する住宅の床面積(登記簿面積)が40㎡以上240㎡以下であること。また、床面積の2分の1以上が自分の居住用であること。中古住宅の場合は、建築後の年数や耐震基準に関する要件もあります(例:木造なら築20年以内、または新耐震基準に適合していること等)。
- 期限の要件:贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その資金の全額を住宅の取得等の対価に充てて、かつ、その家屋に居住すること(または、同日後遅滞なく居住することが確実であると見込まれること)。
ここに挙げたのは主な要件です。実際にはもっと細かい規定がありますので、利用を検討する際は、必ず国税庁のホームページで最新の情報を確認するか、税務署や税理士さんに相談してくださいね!
この「住宅取得等資金の贈与に関する相続時精算課税の特例」を使った場合も、適用される控除や税金の計算方法は、通常の相続時精算課税制度と同じです。
- 特別控除:累計2,500万円
- 基礎控除:年間110万円(2024年1月1日以降の贈与)
が適用されます。
例えば、お父さん(55歳)から住宅取得資金として2,000万円、お母さん(53歳)からも同じ目的で1,000万円の贈与を受けたとします。この場合、お父さんからの贈与について、お母さんからの贈与について、それぞれでこの特例を使って相続時精算課税制度を選択すれば、どちらの贈与も基礎控除・特別控除の範囲内に収まるため、贈与税はかからずに合計3,000万円の援助を受けることができます(ただし、それぞれ申告は必要です)。
ただし、もちろん注意点も通常の相続時精算課税制度と同じです。特に、一度選択すると、その贈与者(この例では父、母それぞれ)からの将来の贈与について暦年課税の基礎控除は使えなくなること、そして、贈与された資金で購入した土地や建物については、原則として相続税の小規模宅地等の特例が使えなくなることは、しっかり覚えておきましょう。
② 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
そして、もう一つ!マイホーム購入を考えている方にとって、非常に強力で嬉しい制度がこちらの「非課税措置」です!
これは、先ほど説明した相続時精算課税制度(の特例)とは全く別の制度です。
一定の要件を満たせば、親や祖父母から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、一定の金額まで、贈与税が完全に「非課税」になるという、夢のような制度なんです!
「精算課税」ではないので、将来、相続財産に加算される心配もありません! まさに、もらい得(というと語弊があるかもしれませんが…)な制度と言えます。

これはすごいですよね! 相続時に精算されるわけじゃなく、本当に非課税になるなんて!
【非課税限度額】(令和4年1月1日から令和8年12月31日までの贈与)
非課税になる限度額は、取得する住宅の種類によって異なります。
- 省エネ等住宅の場合:1,000万円
- 上記以外の住宅の場合:500万円
「省エネ等住宅」とは?
以下のいずれかの基準を満たす住宅のことです。
① 断熱等性能等級4以上 または 一次エネルギー消費量等級4以上
② 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上 または 免震建築物
③ 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上
これらの基準を満たしていることを証明する書類(住宅性能証明書など)を、贈与税の申告時に提出する必要があります。
【主な適用要件】
この非課税措置を受けるための主な要件は、先ほどの「相続時精算課税の特例」の要件とほとんど同じです。
- 資金の使い道:自分が住むための住宅用家屋の新築、取得、増改築等の資金。
- 贈与者:直系尊属(父母、祖父母など)。年齢は問いません。
- 受贈者:贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の子・孫など。贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下。(床面積40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下)
- 家屋の要件:床面積40㎡以上240㎡以下、居住用部分が1/2以上、中古の場合は耐震基準適合など。
- 期限の要件:贈与を受けた年の翌年3月15日までに資金を充てて取得し、同日までに居住すること(または居住見込み)。
こちらも要件が細かく定められています。特に、取得する住宅が「省エネ等住宅」に該当するかどうかで非課税になる金額が大きく変わるので、住宅の性能に関する証明書類などをしっかり確認することが重要です。
【最大のポイント】他の制度との併用が可能!
この「住宅取得等資金の非課税措置」の本当にすごいところは、他の贈与税の制度と組み合わせて使える点なんです!
具体的には、以下の2つのパターンで併用が可能です。
<併用パターン1:暦年課税と併用>
暦年課税には、誰からの贈与であっても年間110万円まで非課税になる「基礎控除」がありますよね。この基礎控除と、住宅取得等資金の非課税措置を組み合わせることができます。
住宅取得等資金の非課税枠(最大1,000万円) + 暦年課税の基礎控除(110万円)
= 合計 最大1,110万円 まで贈与税ゼロ!
例えば、お父さんから「省エネ等住宅」の購入資金として1,110万円の贈与を受けた場合、この組み合わせを使えば、贈与税は一切かかりません。もちろん、将来の相続財産に加算されることもありません。
<併用パターン2:相続時精算課税制度と併用>
なんと、相続時精算課税制度とも併用できるんです!
住宅取得等資金の非課税枠(最大1,000万円)
+ 相続時精算課税の基礎控除(110万円)
+ 相続時精算課税の特別控除(累計2,500万円)
= 合計 最大3,610万円 まで贈与税ゼロ!
(※ただし、非課税枠1,000万円と基礎控除110万円を超える部分(最大2,500万円)は、相続時精算課税制度の特別控除を使ったことになるので、将来の相続税の計算対象にはなります。)
そうなんです! 具体例で見てみましょう。
【設例】
父から子へ、省エネ等住宅の購入資金として3,000万円の贈与があり、子は相続時精算課税制度を選択し、かつ住宅取得等資金の非課税措置も併用する場合。
- まず、住宅取得等資金の非課税措置が適用され、1,000万円が完全に非課税になります。(相続財産にも加算されません)
- 次に、相続時精算課税制度の基礎控除として、110万円が控除されます。(これも相続財産には加算されません)
- 残りの贈与額は、3,000万円 – 1,000万円 – 110万円 = 1,890万円 です。
- この1,890万円は、相続時精算課税制度の特別控除(累計2,500万円)の枠内に収まります。
- したがって、贈与税額は0円となります。
- ただし、将来、父が亡くなった時には、特別控除を使った1,890万円分が、父の相続財産に加算されて相続税が計算されます。
マイホーム購入時に親や祖父母から資金援助を受ける場合、まず検討すべきなのは、この「住宅取得等資金の非課税措置」が使えないか、ということです。要件を満たせば、将来の相続にも影響なく非課税で贈与を受けられる、最も有利な制度だからです。
その上で、非課税枠(最大1,000万円)を超える援助を受ける場合に、その超える部分について「暦年課税の基礎控除(110万円)」を使うか、それとも「相続時精算課税制度(基礎控除110万円+特別控除2,500万円)」を使うか、どちらが自分の状況にとって有利かを検討する、という流れが良いでしょう。
【重要】申告を忘れずに!
これらの特例(相続時精算課税の特例、住宅取得等資金の非課税措置)の適用を受けるためには、たとえ計算の結果、贈与税額がゼロになったとしても、必ず贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、税務署へ贈与税の申告書を提出する必要があります。
申告の際には、戸籍謄本や源泉徴収票、登記事項証明書、工事請負契約書や売買契約書の写し、省エネ等住宅の場合はそれを証明する書類など、多くの添付書類が必要になります。手続きを忘れたり、書類が不足していたりすると、せっかくの特例が受けられなくなってしまいますので、十分に注意してください!
まとめ
今回は、贈与税の「相続時精算課税制度」と、特にマイホーム購入に関連する「住宅取得等資金の贈与」に関する2つの特例について、詳しく解説してきました。少し複雑な内容でしたが、それぞれの制度のポイントや違い、注意点などを掴んでいただけましたでしょうか?
特に、2024年の税制改正で相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が新設されたこと、そして、住宅取得等資金の非課税措置(最大1,000万円)が非常に強力で、他の制度とも併用できるという点は、これから宅建の勉強を始める方や、実際にマイホームの購入や資金計画を考えている方にとって、非常に重要な知識だと思います。
最後に、この記事でお伝えした重要なポイントを、箇条書きでまとめておきますね。頭の整理や復習に役立ててください。
- 相続時精算課税制度:原則60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与で選択可。累計2,500万円の特別控除に加え、年間110万円の基礎控除(2024年~、申告不要・相続加算なし)がある。
- 相続時精算の仕組み:基礎控除を除く贈与額は、贈与者の相続時に相続財産に加算して相続税を計算する(支払った贈与税は控除)。
- 相続時精算課税の注意点:一度選択すると暦年課税に戻れない。年間110万円超は申告必要。小規模宅地等の特例が原則使えない。
- 住宅取得資金の相続時精算課税特例:住宅資金贈与の場合、贈与者の年齢に関わらず相続時精算課税を選択できる。
- 住宅取得資金の非課税措置:相続時精算課税とは別制度。住宅資金贈与について、最大1,000万円(省エネ等住宅)または500万円(その他)まで完全に非課税(相続財産にも加算されない)。
- 非課税措置の併用:この非課税措置は、暦年課税(基礎控除110万円)とも、相続時精算課税制度(基礎控除110万円+特別控除2,500万円)とも併用可能!
- 申告義務:これらの特例を利用して贈与税がゼロになる場合でも、期限内(翌年3月15日まで)に必ず贈与税の申告が必要。

税金の制度は一見すると複雑で難しいですが、仕組みを理解して上手に活用すれば、大きなメリットがあります。特にマイホームのような人生の大きな買い物では、使える制度を知っているのと知らないのとでは大違いです。賢く計画を進めたいですね!