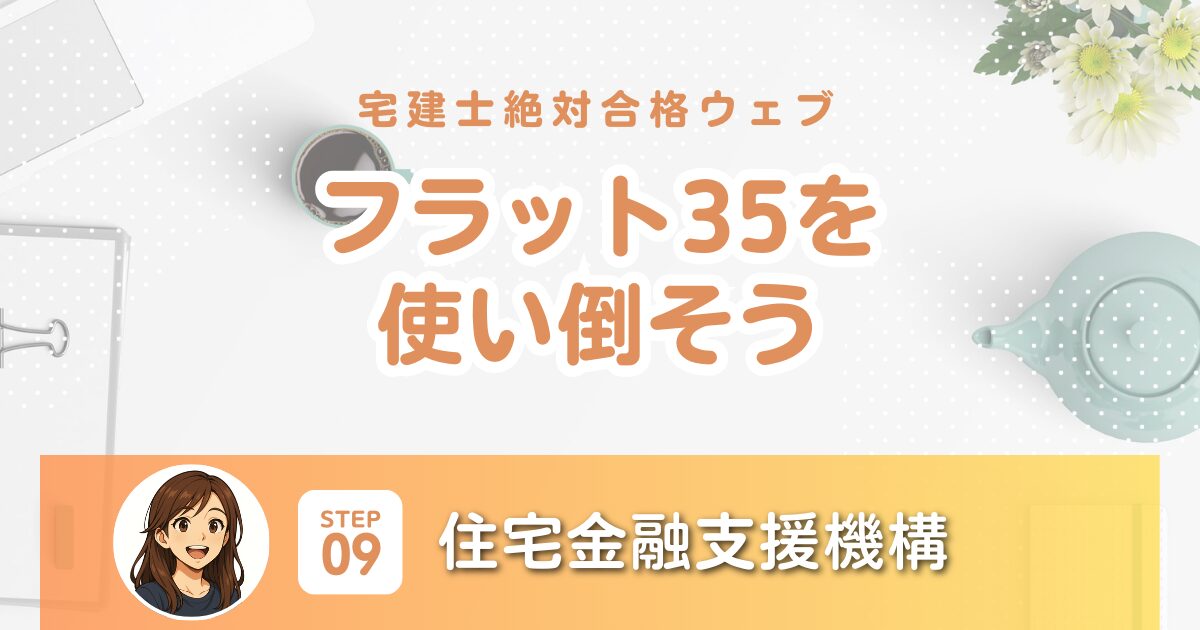皆さんは「住宅金融支援機構」って、名前は聞いたことありますか? もしかしたら、「フラット35」という住宅ローンなら知っている!という方も多いかもしれませんね。実は、そのフラット35を提供しているのが、この住宅金融支援機構なんです。
でも、「具体的にどんな組織なの?」「なんで国が住宅ローンに関わってるの?」「試験ではどんなことが聞かれるの?」って、疑問に思うことも多いのではないでしょうか。特に、業務内容がたくさんあって、どれが重要なのか分かりにくい…と感じている方もいるかもしれません。
住宅金融支援機構は、昔の「住宅金融公庫」の役割を引き継ぎ、国民の住生活の安定と向上をサポートする、とても大切な役割を担っています。その業務内容は多岐にわたりますが、宅建試験で問われるポイントはある程度決まっているんですよ。
この記事では、住宅金融支援機構がどんな目的で設立され、具体的にどんな業務を行っているのか、そして宅建試験で特に押さえておくべきポイントはどこなのかを、一つひとつ丁寧に解説していきます。この記事を読めば、住宅金融支援機構の全体像がしっかりと理解でき、試験対策もバッチリ進められるはずです!

「公庫」から「機構」へ。名前が変わっただけでなく、その役割も少し変化したんですね。
<この記事でわかること>
- 住宅金融支援機構が設立された背景と目的について理解できる
- 主要業務である「証券化支援業務(フラット35など)」の仕組みの対策がわかる
- 融資保険業務や団体信用生命保険(団信)業務の内容のポイントが整理できる
- 機構が直接融資を行うケース(災害時、高齢者向けなど)との違いがわかる
- 宅建試験で問われる業務委託や検査に関するルールが明確になる
住宅金融支援機構ってどんな組織?|設立の背景と目的を知ろう
まずは、住宅金融支援機構がどのような組織なのか、その基本から見ていきましょう。設立された背景や目的を知ることで、具体的な業務内容の理解もグッと深まりますよ。
住宅金融公庫から住宅金融支援機構へ
現在の「独立行政法人 住宅金融支援機構」は、もともと「住宅金融公庫」という名前の国の機関(特殊法人)でした。もしかしたら、親御さんの世代の方には「公庫」という名前のほうが馴染み深いかもしれませんね。
住宅金融公庫は、第二次世界大戦後の住宅不足を解消したり、国民がマイホームを持ちやすくしたりするために、長期・固定金利の住宅ローンを直接、国民に融資するという重要な役割を担っていました。「公庫融資で家を建てた」という話を聞いたことがある方もいるかもしれません。
しかし、時代が進むにつれて、民間の銀行などでも様々な住宅ローン商品が提供されるようになり、金融市場も大きく変化しました。そこで、国の役割を見直し、「官(国)から民(民間)へ」という流れの中で、住宅金融の分野でも民間の活力をより活かしていこう、ということになったんです。
その結果、2007年(平成19年)4月1日に「独立行政法人 住宅金融支援機構法」という法律が施行され、住宅金融公庫はその役割を終えて解散しました。そして、その業務の多くを引き継ぐ形で、「独立行政法人 住宅金融支援機構」が新たに設立されたのです。
つまり、単に名前が変わっただけではなく、その役割や業務の重心が変化した、というのが大きなポイントです。
住宅金融公庫との最も大きな違いは、機構は原則として、住宅ローンを利用する人に直接お金を貸す(直接融資)のではなく、民間の金融機関(銀行など)が提供する住宅ローンを「支援」する役割に重点を置くようになったことです。「支援」って具体的にどういうこと?というのは、次の業務内容で詳しく見ていきますね。
ただし、どんな状況でも民間金融機関だけで対応できるわけではありません。そのため、例外的に、特定の目的のためには機構が今でも直接融資を行うケースもあります。これも後ほど詳しく説明します。
住宅金融支援機構の3つの主な目的
では、新しく設立された住宅金融支援機構は、具体的に何を目指しているのでしょうか? 法律(独立行政法人 住宅金融支援機構法)には、その目的が明確に定められています。大きく分けて、以下の3つの柱があるんです。
- 一般の金融機関による住宅の建設等に必要な資金の融通を「支援」すること
これが機構の最も中心的な目的です。民間の金融機関だけでは提供が難しいとされる、長期・固定金利の住宅ローンなどを、金融機関がもっと提供しやすくなるように、様々な形でサポートします。これにより、消費者が安心して利用できる住宅ローンの選択肢を増やすことを目指しています。 - 住宅の建設等に関する必要な「情報提供」を行うこと
住宅ローン選びや、住宅の建設・購入、リフォームなどに関する様々な情報を収集・分析し、広く一般に提供します。金利の情報、税金や補助金の制度、住宅の品質に関する知識など、専門的で分かりにくい情報を、消費者が理解しやすく、適切な判断ができるように手助けする役割です。 - 災害からの復興や特別な配慮が必要な分野で「直接融資」を行うこと
大規模な自然災害からの復興、高齢者や子育て世帯向けの住宅確保、耐震性の向上など、国の政策として特に支援が必要であり、かつ、民間の金融機関だけでは対応が難しい分野については、機構がセーフティネットとして直接、資金の貸付(融資)を行います。
これらの目的を達成するために、住宅金融支援機構は、次に説明するような様々な業務を行っているんですね。
ポイントは、国の役割が「直接お金を貸す」ことから、「民間の金融機関をサポートする」ことにシフトした点です。ただし、災害時などのセーフティネット機能は、引き続き国(機構)が担っている、というバランスになっています。
証券化支援・融資保険・団信|主要な業務内容を徹底解説
それでは、住宅金融支援機構が具体的にどんな業務を行っているのか、特に重要なものを中心に詳しく見ていきましょう。ここは宅建試験でも頻繁に出題される分野なので、しっかり理解してくださいね!

なるほど!銀行は貸したお金をすぐに機構から回収できるから、長期のローンでも安心して貸せるんですね!
① 証券化支援業務(買取型・保証型)|フラット35の仕組み
これが、住宅金融支援機構の業務の中で最も重要で、中心的なものです。皆さんがよくご存じの「フラット35」も、この証券化支援業務という仕組みがあるからこそ成り立っているんです。
「証券化」って聞くと、なんだか難しそう…と感じるかもしれませんが、基本的な仕組みを理解すれば大丈夫ですよ! 証券化支援業務には、大きく分けて「買取型」と「保証型」の2つのタイプがあります。
【買取型(フラット35など)の仕組み】
「フラット35」はこの買取型の代表例です。仕組みは以下のようになっています。
- 住宅ローンの実行:まず、私たち(住宅購入者)が、マイホームを買うために、銀行などの民間金融機関の窓口で「フラット35」などの住宅ローンを申し込み、契約して、お金を借ります。
- 債権の買取:次に、ローンを実行した金融機関は、私たちに対して持っている「貸したお金を返してもらう権利(=住宅ローン債権)」を、住宅金融支援機構に売却します。金融機関は、これにより、貸したお金を早期に回収できるわけです。
- 証券の発行:機構は、全国の金融機関から買い取ったたくさんの住宅ローン債権をまとめて、それを担保(裏付け)にして「MBS(Mortgage Backed Securities:資産担保証券)」という名前の証券を発行します。
- 証券の販売:機構は、発行したMBSを、国内外の年金基金や生命保険会社などの機関投資家に向けて販売します。投資家は、これを購入することで資金を提供します。
- 資金の流れ:機構は、投資家からMBSの販売代金として得た資金を使って、金融機関から住宅ローン債権を買い取るための代金を支払います。
- ローン返済:私たち住宅ローン利用者は、毎月、ローンを借りた金融機関(または、返済金の回収業務を機構から委託された会社)に対して、ローンの返済を続けます。
- 投資家への支払い:機構は、私たちから回収した返済金をもとに、MBSを購入した投資家に対して、証券の利息の支払いや元本の償還(返済)を行います。
この仕組みの最大のメリットは、金融機関にとって、長期・固定金利の住宅ローンを提供することに伴うリスク(将来の金利上昇リスクや、貸したお金が返ってこない貸し倒れリスクなど)を、機構にスムーズに移転できる点です。貸したお金(債権)をすぐに機構に売却できるので、資金が固定化される心配もありません。
その結果、私たち消費者は、将来の金利上昇の心配がなく、返済額が長期間変わらない「長期・固定金利」の住宅ローンを、比較的利用しやすい金利水準で借りることができるようになるのです。これが、フラット35が多くの人に利用されている大きな理由なんですね。
【保証型】
もう一つ、「保証型」という仕組みもあります。こちらは少しマイナーですが、覚えておきましょう。
保証型では、金融機関が貸し出した住宅ローン債権を、機構が直接買い取るわけではありません。代わりに、金融機関がその住宅ローン債権を担保として発行する債券(証券化商品)について、機構がその元本や利息の支払いを「保証」します。
もし金融機関に何か問題が起きて、債券の支払いができなくなったとしても、機構が代わりに支払ってくれるという保証が付くわけです。これにより、その債券の信用力が高まり、金融機関は住宅ローンを証券化して、市場から資金を調達しやすくなります。
買取型も保証型も、最終的には、金融機関が長期の住宅ローンを提供しやすくするための「支援」である、という点が共通しています。宅建試験では、まず「証券化支援業務が機構の主要業務である」こと、そして「買取型(フラット35の仕組み)」をしっかり押さえておくことが重要です。
② 融資保険業務
これは、民間の金融機関が独自に提供する住宅ローン(フラット35以外のローン)に対して、住宅金融支援機構が「保険」をかける業務です。
具体的には、もし、その住宅ローンを借りた人(債務者)が、失業や病気、倒産などの理由で、ローンの返済が困難になってしまった場合、機構が、保険契約を結んでいる金融機関に対して、ローンの未返済額の一部を保険金として支払う、という仕組みです。
この保険は、あくまで機構と金融機関との間で結ばれる契約です。私たちローン利用者が、直接、機構に保険料を支払うわけではありません(通常は、金融機関が支払う保険料が、ローンの金利に上乗せされる形で含まれています)。
Q. この保険があると、金融機関にはどんなメリットがあるの?
A. もし貸した相手がローンを返せなくなっても、機構から保険金が支払われるので、金融機関は貸し倒れのリスクを減らすことができます。そのため、例えば、自己資金(頭金)が少ない人や、収入が不安定な個人事業主、特定の条件(例:子育て世帯向け優遇など)を満たす人向けの住宅ローンなど、通常よりも少しリスクが高いと判断されるようなローンでも、より積極的に提供しやすくなる、という効果があります。
つまり、融資保険業務も、間接的に住宅ローンの供給を促進し、国民の住宅取得を支援する役割を果たしているんですね。
③ 団体信用生命保険(団信)業務
「団信(だんしん)」という言葉、住宅ローンを検討したことがある方なら、一度は耳にしたことがあるかもしれませんね。これは「団体信用生命保険」の略称です。
団信は、住宅ローンを借りた人(被保険者)が、ローンの返済期間中に死亡してしまったり、所定の高度障害状態になってしまったりした場合に、生命保険会社が、その時点でのローン残高に相当する保険金を、住宅金融支援機構(またはローンを提供した金融機関)に支払う、という仕組みの生命保険です。
保険金が支払われると、それで残りの住宅ローンが全額完済されるため、残されたご家族にローンの返済負担が残らない、というメリットがあります。
住宅金融支援機構は、フラット35の利用者などを対象として、この団体信用生命保険への加入手続きや契約管理に関する業務を行っています。
フラット35を利用する場合、基本的に団信への加入が融資の条件となっています(ただし、健康上の理由などで加入できない場合や、既に同等の生命保険に加入している場合などは、加入が免除されることもあります)。
団信に加入する場合、その保険料に相当する額は、通常、フラット35の借入金利に上乗せされる形で支払うことになります。
最近では、死亡・高度障害だけでなく、がん・脳卒中・急性心筋梗塞の三大疾病にかかった場合や、その他の病気・ケガによって長期間働けなくなった(就業不能状態)場合に、ローン残高がゼロになる、より保障範囲が広いタイプの団信も登場しています。もちろん、その分、金利の上乗せ幅は大きくなります。
④ 住宅関連情報の提供業務
機構の目的の一つに「情報提供」がありましたが、これも重要な業務です。
機構は、住宅ローンや住宅の建設・購入、リフォームなどに関する様々な情報を収集・分析し、それを機構のウェブサイトやパンフレット、電話相談、セミナーなどを通じて、広く一般の消費者や住宅事業者に向けて提供しています。
具体的には、以下のような情報です。
- 最新の住宅ローン金利動向(フラット35の金利など)
- 住宅取得やリフォームに関する税制の優遇措置や補助金制度
- 省エネ住宅や耐震性の高い住宅など、良質な住宅を選ぶためのポイント
- 中古住宅の選び方、インスペクション(建物状況調査)の重要性
- 耐震診断や耐震改修、バリアフリーリフォームに関する技術情報や費用
- 住宅ローンの返済計画の立て方、資金計画シミュレーションツール
これらの情報を提供することで、消費者が住宅に関する様々な選択をする際に、十分な情報に基づいて適切な判断ができるようにサポートしています。
機構のウェブサイトは、住宅に関する情報が非常に充実していて、信頼性も高いです。これから住宅購入を考えている方はもちろん、宅建の勉強をしている方も、関連知識を深めるために一度覗いてみると、とても参考になりますよ!
⑤ 既往債権(きおうさいけん)の管理・回収業務
これは、機構が設立される前の旧住宅金融公庫時代に貸し出された住宅ローン(=既往債権)について、その管理や返済金の回収を行う業務です。
住宅金融公庫は解散しましたが、公庫から融資を受けて、現在も返済を続けている人はまだたくさんいます。これらのローン債権は、機構が引き継いでいます。
そのため、機構は、これらの既往債権について、返済状況を管理したり、滞納者への督促を行ったり、契約条件の変更(リスケジュール)の相談に応じたりといった、債権管理・回収業務も引き続き行っているのです。
機構の業務の中心は「支援」にシフトしましたが、過去の「直接融資」の後始末(というと語弊があるかもしれませんが)もしっかり行っている、ということですね。
機構の直接融資とその他の業務|災害時・高齢者向けなど
これまで見てきたように、住宅金融支援機構の主な役割は、民間金融機関が行う住宅ローンを「支援」することです。しかし、それだけでは対応できない、特別な状況や政策的に重要な分野については、機構自身が直接、お金を貸し出す「直接融資業務」も行っています。これは、国民生活の安定を守るためのセーフティネットとしての役割と言えますね。

災害で家を失ったり、壊れたりした方々にとっては、本当に頼りになる制度ですね。
直接融資業務が認められるケース
機構が直接融資を行えるのは、法律で定められた、一般の金融機関だけでは融資の提供が難しいと考えられる、限定的な分野に限られています。宅建試験では、どのような場合に直接融資が可能か、その種類を問われることがあります。
災害関連の貸付
これは、大規模な自然災害(地震、台風、豪雨など)によって住宅に被害を受けた方々を支援するための融資です。具体的には、以下のような資金の貸付があります。
- 災害復興建築物の建設・購入資金:被災した住宅に代わる新しい住宅を建てる、または購入するための資金。
- 被災建築物の補修資金:被災した住宅を修理するための資金。
- 災害予防のための代替建築物の建設・購入資金、移転資金:災害の危険性が高い区域(土砂災害特別警戒区域など)から安全な場所へ移転するための、新しい住宅の建設・購入費用や移転費用。
- 災害予防関連工事資金:擁壁の設置など、住宅の災害への備えを強化するための工事費用。
- 地震に対する安全性向上を目的とする住宅改良(耐震改修)資金:既存住宅の耐震性を高めるための改修工事費用。
- (特例として)阪神・淡路大震災の被災者向けの、特別の融資制度。

これらの災害関連融資は、被災者の生活再建を支える上で、非常に重要な役割を果たしています。金利も低めに設定されていることが多いです。
都市居住再生機構関連の貸付
都市部における居住環境の改善や、特定のニーズに応える住宅供給を支援するための融資です。
- 合理的土地利用建築物に関する資金:
- 老朽化したマンションの建替えに必要な建設資金。
- 細かく分かれた土地(狭小な敷地など)をまとめて、耐火性能の高い共同住宅などを建てる場合の建設・購入資金。
- マンションの共用部分(廊下、階段、エレベーターなど)を維持・修繕・改良するための資金。
- 子育て世帯・高齢者世帯向けの優良な賃貸住宅の建設・改良資金。
- 高齢者の住宅のバリアフリー改修や耐震改修工事に関する資金。(次の「高齢者向け返済特例制度」と関連します)
財形住宅貸付業務
財形貯蓄(勤労者財産形成貯蓄)を行っている勤労者(会社員など)が、住宅を取得したりリフォームしたりするための資金を借りる制度です。
通常、財形住宅融資は、勤務先の会社などを通じて(転貸融資)受けることが多いのですが、勤務先がその制度を扱っていないなどの理由で転貸融資を受けられない人に対しては、機構が直接、住宅資金の貸付を行います。
注意点として、機構の直接融資は、これら法律で定められた特定のケースに限られる、ということです。例えば、「一般的な新築住宅の購入資金」や「一般的なリフォーム資金」については、機構が直接融資を行うことは原則ありません(フラット35などの民間支援を利用することになります)。
高齢者向けの返済特例制度
機構が行う直接融資の中でも、特に高齢者の住宅改良(バリアフリー工事や耐震改修工事)に関する資金の貸付については、ユニークな返済方法が用意されています。これは「高齢者向け返済特例制度」と呼ばれます。
この制度の特徴は、
- 毎月の返済は、利息の支払いのみでOK。
- 借りたお金の元本については、借りた人(債務者)が亡くなった時に、
- 相続人が一括して返済する
- または、担保として提供していた住宅とその敷地を処分(売却など)して、その代金から返済する
という仕組みになっている点です。(一定の要件を満たす必要があります)
この仕組みは、将来の相続財産(自宅)を活用して、現在の生活の質を高める「リバースモーゲージ」という考え方に近いものです。
この制度を利用することで、年金収入が中心で、月々の返済負担を増やしたくない高齢者の方でも、安心して自宅のバリアフリー化や耐震化といった必要なリフォームを行うことができるようになります。高齢化社会に対応した、重要な制度と言えますね。
貸付条件の変更(リスケジュール)
機構から直接融資を受けている人が、予期せぬ事情、例えば、失業、転職による収入減、病気やケガによる長期療養、災害による被害などによって、経済状況が著しく悪化し、ローンの返済(元金や利息の支払い)を続けることが著しく困難になった場合には、救済措置が用意されています。
その人が機構に申し出ることによって、返済期間を延長したり、一定期間は元金の返済を据え置いたりするなど、貸付条件の変更(リスケジュール)や支払方法の変更をしてもらえる場合があります。(もちろん、一定の審査や要件があります)
万が一、返済が苦しくなった場合に、すぐに担保物件を取り上げられるのではなく、返済計画を見直す相談ができる窓口があるというのは、利用者にとって大きな安心材料になりますね。
住宅の質の向上を図るための措置
住宅金融支援機構は、単にお金を融通するだけでなく、市場に供給される住宅の質を高めるための取り組みも行っています。これも間接的な「支援」と言えるかもしれません。
その代表例が、フラット35を利用するための「技術基準」です。
フラット35の融資を受けるためには、その対象となる住宅が、機構が定めた一定の技術基準(耐震性、耐久性・可変性、省エネルギー性、バリアフリー性など)に適合している必要があります。
住宅の購入者は、建築中や完成後に、第三者の検査機関による物件検査を受け、その基準に適合していることの「適合証明書」を取得して、金融機関に提出しなければなりません。

また、機構は、特に質の高い住宅の取得を促進するために、「フラット35S」という制度を設けています。
これは、フラット35の技術基準に加えて、さらに高いレベルの省エネルギー性、耐震性、バリアフリー性、耐久性・可変性のいずれかの基準を満たす住宅を取得する場合に、当初の一定期間(5年間または10年間)、フラット35の借入金利を一定率引き下げるという優遇制度です。
このように、機構の融資制度を利用するための条件として、一定の住宅性能を求めることや、より高性能な住宅に対して金利優遇を行うことで、結果的に、市場全体の住宅の質の向上を誘導するという役割も果たしているんですね。
業務委託・検査などのルールを押さえよう!
最後に、宅建試験で細かい知識として問われる可能性のある、住宅金融支援機構の運営に関するルール、特に「業務の委託」と「検査」について確認しておきましょう。ここは少し地味な内容ですが、試験直前に見直しておくと役立つかもしれません。
業務の委託
住宅金融支援機構は、その業務を効率的かつ効果的に行うために、業務の一部を他の機関に委託することができます。フラット35の申し込みや審査、返済金の受け取りなどを、皆さんが銀行の窓口で行えるのは、この業務委託の仕組みがあるからです。
ただし、どんな業務でも委託できるわけではありません。法律により、「住宅に関する情報の提供業務」(先ほど説明した④の業務ですね)については、機構自身が行うべき業務とされており、委託することはできません。
また、委託できる相手も、誰でも良いわけではなく、以下の3つの種類に限定されています。
- 主務省令で定める金融機関:銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、生命保険会社、損害保険会社など、住宅ローン業務に関連する多くの金融機関が含まれます。
- 債権回収会社(サービサー):「債権管理回収業に関する特別措置法」という法律に基づいて法務大臣の許可を受けた、債権の管理や回収を専門に行う会社です。主に、既往債権の管理・回収業務などが委託されることがあります。
- 地方公共団体その他政令で定める法人:都道府県や市町村などの地方公共団体や、その他、政令で特別に定められた法人も委託先となり得ます。

試験対策としては、「住情報の提供業務は委託できない」ことと、「委託できる相手の種類(金融機関、サービサー、地方公共団体等)」を正確に覚えておくことが重要です。「不動産会社」や「コンサルティング会社」などに委託できる、といった選択肢は誤りになります。
委託先への報告徴収・立入検査
機構から業務の委託を受けた金融機関などが、ちゃんと契約通りに、そして法令やルールを守って業務を行っているか、国(主務大臣)がチェックする仕組みも定められています。
住宅金融支援機構の主務大臣は、国土交通大臣と財務大臣の二人です。
この主務大臣は、機構の業務が適正に行われているか監督するために、必要があると認めるときは、機構から業務の委託を受けた金融機関、債権回収会社、地方公共団体などに対して、以下の権限を持っています。
- 委託された業務の状況に関して、報告を求めること(報告徴収)
- その省庁の職員を、委託を受けた機関の事務所などに立ち入らせ、委託業務の状況や帳簿、書類、その他の物件を検査させること(立入検査)
国が、機構だけでなく、その委託先に対しても、直接、報告を求めたり、検査に入ったりできる、という点がポイントです。これにより、機構の業務全体の適正な運営を確保しようとしているわけですね。
試験では、「主務大臣が誰か(国土交通大臣及び財務大臣)」、そして主務大臣が「委託先に対して報告徴収や立入検査ができる」という点を押さえておきましょう。
まとめ
今回は、独立行政法人 住宅金融支援機構について、その設立の経緯から具体的な業務内容、そして宅建試験で押さえるべきポイントまで、かなり詳しく見てきました。少し専門的な話もあって難しかったかもしれませんが、機構がどんな役割を果たしているのか、全体像を掴んでいただけたでしょうか?
住宅金融支援機構は、単に住宅ローンを提供したり支援したりするだけでなく、国の住宅政策を実現し、私たちの住生活の安定と向上に貢献するという、非常に重要な役割を担う組織です。特に、長期・固定金利の代表であるフラット35の仕組みを支える「証券化支援業務」は、機構の業務の中でも最も中心的なものと言えますね。
最後に、この記事で学んだ重要ポイントをもう一度おさらいしましょう。
- 住宅金融支援機構は、旧住宅金融公庫の業務を引き継ぎ、2007年に設立された独立行政法人である。
- 主な目的は、①民間金融機関の住宅ローン支援、②住宅情報の提供、③特定の分野での直接融資の3つ。
- 中心業務は「証券化支援業務(買取型・保証型)」であり、これにより長期・固定金利のフラット35などが実現している。
- その他、民間ローンへの「融資保険業務」、ローン利用者のための「団体信用生命保険(団信)業務」、幅広い「住情報の提供」、旧公庫からの「既往債権管理」なども行う。
- 民間では対応困難な、災害時(復興、予防、耐震)や高齢者向け住宅改良、マンション建替え、財形(転貸不可の場合)など、限定的なケースでは「直接融資」も行う。
- 高齢者向け直接融資には、利息のみ毎月返済し、元本は死亡時に一括返済等する特例制度がある。
- 業務の一部(住情報提供を除く)は、金融機関、債権回収会社、地方公共団体等に委託できる。
- 主務大臣(国土交通大臣・財務大臣)は、機構だけでなく、その委託先に対しても報告徴収・立入検査ができる。

宅建試験では、機構の各業務の内容や目的、特に証券化支援や直接融資の種類、そして委託や検査に関する細かいルールが問われることが多いです。過去問などを通じて、どの部分が狙われやすいかを確認しながら、知識を定着させていきましょう!