宅建業法の様々なルールを学んできましたが、今回は「もし、そのルールを破ってしまったら…?」という、ちょっと背筋が伸びるお話、「監督処分」と「罰則」についてです。
「指示処分」「業務停止」「免許取消」「事務禁止」「登録消除」…なんだか物々しい言葉が並びますよね。「罰金〇〇万円以下」「懲役〇年以下」なんて聞くと、ますます「怖い!」と感じるかもしれません。
でも、これらの処分や罰則は、決して怖がらせるためだけにあるわけではありません。ルール違反を防ぎ、公正な取引を守ることで、私たち消費者や、真面目に業務を行っている他の業者さんを守り、不動産業界全体の信頼を維持するために、なくてはならないものなんです。
そして、宅建士を目指す皆さんにとっては、どんな行為がどんなペナルティにつながるのかを正確に理解しておくことが、将来トラブルに巻き込まれないため、そして試験で確実に得点するために、非常に重要になってきます!
この記事では、そんな「監督処分」と「罰則」について、
- まず、「監督処分」と「罰則」って何が違うの?
- 宅建業者さんが受ける監督処分の種類と内容は?
- 宅建士さんが受ける監督処分の種類と内容は?
- 具体的な違反行為に対する罰則(懲役・罰金・過料)の重さは?
という点を中心に、分かりやすく整理して解説していきます。これを読めば、「この違反をしたら、どうなっちゃうんだろう?」というモヤモヤが解消され、宅建業法のペナルティに関する知識がバッチリ身につきますよ!

さあ、監督処分と罰則のルールをしっかり理解して、コンプライアンス意識を高め、試験に自信を持って臨みましょう!
この記事でわかること
- 「監督処分」と「罰則」の根本的な違い
- 宅建業者が受ける3つの監督処分(指示・業務停止・免許取消)の内容とポイント
- 宅建士が受ける3つの監督処分(指示・事務禁止・登録消除)の内容とポイント
- 取引士証の提出・返還・返納が必要になるケース
- 具体的な違反行為に対する罰則(懲役・罰金・過料)の重さ
【違いを理解!】監督処分と罰則、それぞれの意味と目的
まず最初に、よく混同されがちな「監督処分」と「罰則」の違いを、具体的な例をもとにはっきりさせておきましょう!
- 例:飲酒運転で死亡事故を起こしてしまった場合…
- 運転免許を取り消される → これが「監督処分」(行政上の措置)にあたります。
- 懲役刑で刑務所に行く → これが「罰則」(刑事罰)にあたります。
つまり、
- 監督処分:
- 宅建業や取引士としての業務の適正化を図るために、行政庁(国土交通大臣や都道府県知事)が行う、業務に関する指示や制限、資格の剥奪などの行政上の措置のこと。
- 例:指示処分、業務停止処分、免許取消処分、事務禁止処分、登録消除処分
- 罰則:
- 法律違反に対して科される制裁のこと。刑事手続きによって科される刑事罰(懲役、罰金)と、行政上の義務違反に対して科される行政罰(過料)があります。
- 例:懲役刑、罰金刑、過料
【宅建業者への処分】指示・業務停止・免許取消!処分の種類と内容を徹底解説
では、まず宅建業者が受ける可能性のある監督処分を、軽いものから順に見ていきましょう。
① 指示処分
一番軽い処分が「指示処分」です。
- 内容: 業務運営の改善のために、必要な指示を与える処分。「ここを直しなさい」「こういうやり方に変えなさい」といった命令です。
- 処分権者:
- その業者に免許を与えた免許権者(国土交通大臣または都道府県知事)
- その業者が業務を行っている区域の都道府県知事(免許権者でなくても、自分の県内で違反があれば指示できる)
- 主な処分事由:
- 業務に関してお客さんなどに損害を与えた、または与えるおそれが大きいとき。
- 宅建業法や、その他の法律(建築基準法など)に違反し、宅建業者としてふさわしくないと認められるとき。
- 契約内容について、ちゃんと説明しなかったとき(重要事項説明義務違反など)。
- 不当な履行遅延(理由なく物件の引渡しを遅らせるなど)をしたとき。
② 業務停止処分
指示処分に従わなかったり、より重い違反をしたりすると、「業務停止処分」が科されることがあります。
- 内容: 期間を定めて(1年以内)、業務の全部または一部の停止を命じる処分。処分を受けたことは公告されます(世間に公表される)。
- 処分権者: 指示処分と同じ(免許権者 または 業務地の知事)
- 主な処分事由:
- 指示処分に違反したとき。
- 宅建業法や他の法令に違反し、宅建業者として不適当と認められるとき(指示処分事由と重なる部分もありますが、より悪質な場合など)。
- 誇大広告をしたとき。
- 自分が雇っている宅建士が事務禁止処分や登録消除処分を受け、そのことについて業者にも責任があると認められるとき。
- 営業保証金が不足したのに、定められた期間内に供託しなかったとき。
- 1年以内に事業を開始しない、または1年以上事業を休止している場合(※これは免許取消事由にも該当)。
- 重要事項説明義務違反(35条書面)、契約書面交付義務違反(37条書面)など、宅建業法の重要なルールに違反したとき。

業務停止になると、その期間は営業ができなくなってしまうので、業者にとってはかなり厳しい処分ですね…。
③ 免許取消処分
最も重い処分が「免許取消処分」です。これを受けると、宅建業を営むことができなくなります。免許取消には、必ず取り消さなければならない「必要的取消」と、取り消すかどうかを行政庁が判断する「任意的取消」があります。
- 内容: 宅建業の免許を取り消す処分。処分を受けたことは公告されます。
- 処分権者: その業者に免許を与えた免許権者(国土交通大臣または都道府県知事)のみ! (業務地の知事は免許取消はできません)
- 主な【必要的】免許取消事由: (これに該当したら必ず取り消される!)
- 不正な手段で免許を取得したとき。
- 業務停止処分に違反して営業したとき。
- 業務停止処分の事由に該当し、特に情状が重いとき。(悪質性が極めて高い場合など)
- 免許を受けてから1年以内に事業を開始しない、または引き続き1年以上事業を休止したとき。
- 役員や政令で定める使用人などが欠格要件に該当してしまったとき。
- 営業保証金を供託せず、催告を受けても一定期間内に供託しないとき(保証協会加入の場合も同様)。
- 主な【任意的】免許取消事由: (取り消される可能性がある)
- 宅建業者の事務所の所在地が確認できないとき。
- 免許に付された条件に違反したとき。

免許取消処分を下せるのは、免許を与えた免許権者だけ、という点はしっかり覚えておきましょう!
【取引士への処分】指示・事務禁止・登録消除!取引士が受ける処分の重さとは?
次に、宅建業者ではなく、個人の「宅地建物取引士」が受ける可能性のある監督処分を見ていきましょう。こちらも3段階あります。業者への処分と名前が似ていますが、少し違うので注意してくださいね。
① 指示処分
取引士に対する一番軽い処分です。
- 内容: 取引士として行うべき事務について、適正な運営を確保するために必要な指示を与える処分。(任意処分)
- 処分権者: 都道府県知事 (登録をしている知事、または業務地の知事)
- 主な処分事由:
- 取引士が、自分が勤めていない宅建業者の専任取引士であるかのように表示することを許し、その業者が表示した場合。
- 取引士が名義貸し(自分の名前を他人に使わせること)を許し、他人がその名前を使った場合。
- 取引士として行うべき事務に関して、不正または著しく不当な行為をしたとき。
② 事務禁止処分
指示に従わない場合や、より重い不正行為などがあった場合に科される可能性があります。
- 内容: 期間を定めて(1年以内)、取引士としてすべき事務(重要事項説明など)を行うことを禁止する処分。(任意処分)
- 処分権者: 都道府県知事 (指示処分と同じ)
- 主な処分事由:
- 指示処分に違反したとき。
- 指示処分の事由(名義貸し、不正・不当な行為など)に該当するとき。
- 備考(取引士証の扱い):
- 事務禁止処分を受けたら、速やかに取引士証をその処分をした知事に提出しなければなりません。
- 事務禁止期間が満了したら、本人が返還を請求すれば、取引士証は返還されます。

事務禁止期間中は、取引士としての仕事ができなくなるんですね。取引士証も一時的に取り上げられてしまいます。
③ 登録消除処分
取引士にとって最も重い処分です。これを受けると、取引士としての登録自体が抹消されます。これは必要的処分、つまり該当したら必ず消除されます。
- 内容: 都道府県知事の登録を消除する処分。(必要的処分)
- 処分権者: 都道府県知事 (登録をしている知事)
- 主な処分事由: (これに該当したら必ず消除される!)
- 取引士が、登録の欠格要件(破産者、禁錮以上の刑、暴力団員など)のいずれかに該当してしまったとき。
- 不正な手段で取引士の登録を受けたとき。
- 不正な手段で取引士証の交付を受けたとき。
- 事務禁止処分の事由に該当し、特に情状が重いとき。
- 事務禁止処分に違反して、取引士としての事務を行ったとき。
- 備考(取引士証の扱い):
- 登録を消除されたら、取引士証を返納しなければなりません。(事務禁止の「提出」とは違い、返してもらえません)
事務禁止は提出 → 期間満了後に返還
登録消除は返納 → 返ってこない
この取引士証の扱いの違いは、試験でも問われやすいのでしっかり区別しましょう!
【罰則一覧】懲役・罰金・過料!違反行為とペナルティの重さをチェック
最後に、具体的な違反行為に対して、どのような罰則(懲役・罰金・過料)が科されるのかを見ていきましょう。すべてを完璧に覚えるのは大変ですが、特に重い罰則が科されるケースや、身近な義務違反に対する罰則は押さえておきたいところです。
以下に、主な違反行為と罰則を重い順にまとめます。
- 【3年以下の懲役 または 300万円以下の罰金 (または併科)】 ← 最も重い!
- 不正な手段で宅建業の免許を取得する行為
- 名義貸し(自己の名義で他人に宅建業を営ませる)行為
- 業務停止処分に違反して営業する行為
- 無免許で宅建業を営む行為
- 【2年以下の懲役 または 300万円以下の罰金 (または併科)】
- 重要な事項について、故意に事実を告げなかったり、不実のことを告げたりする行為(事実不告知・不実告知)
- 【1年以下の懲役 または 100万円以下の罰金 (または併科)】
- 不当に高額な報酬を要求する行為
- 【6ヶ月以下の懲役 または 100万円以下の罰金 (または併科)】
- 営業保証金を供託せずに事業を開始する行為(※保証協会加入の場合も同様)
- 誇大広告等の禁止に違反する行為
- 不当な履行遅延(物件の引渡し等を不当に遅らせる)行為
- 手付の貸付け等による契約締結の誘引行為
- 【100万円以下の罰金】
- 免許申請書などに虚偽の記載をする行為
- 他人に自己の名義で営業表示や広告をさせる行為
- 専任の取引士の設置義務に違反する行為
- 法定の上限額を超える報酬を受領する行為(※要求は懲役刑もありうる)
- 【50万円以下の罰金】
- 契約書面(37条書面)の交付義務に違反する行為
- 従業者名簿を備え付けない、または虚偽記載する行為
- 帳簿を備え付けない、または虚偽記載する行為
- 守秘義務に違反する行為
- 【10万円以下の過料】 ← 罰金ではなく「過料」(行政罰)
- 登録消除処分を受けたのに取引士証を返納しない行為
- 事務禁止処分を受けたのに取引士証を提出しない行為
- 重要事項説明の際に取引士証を提示しない行為

無免許営業や名義貸し、業務停止命令違反など、根本的なルール違反や悪質な行為には重い罰則が科されますね。一方で、書類の不備や取引士証の不携帯などは「過料」という比較的軽いペナルティになっています。
まとめ
お疲れ様でした! 今回は、宅建業法の「監督処分」と「罰則」について、その違いから具体的な内容まで詳しく見てきました。
ルール違反に対するペナルティを知ることは、気を引き締めて業務にあたる上でとても大切です。最後にポイントをまとめます。
- 監督処分は行政庁による行政措置(指示、業務停止、免許取消、事務禁止、登録消除)、罰則は制裁(懲役、罰金、過料)。
- 業者への処分は重い順に「指示処分」→「業務停止処分(1年以内)」→「免許取消処分(必要的・任意的)」。免許取消は免許権者のみ可能。
- 取引士への処分は重い順に「指示処分」→「事務禁止処分(1年以内、取引士証提出)」→「登録消除処分(必要的、取引士証返納)」。処分権者は主に知事。
- 罰則は違反行為によって重さが異なり、無免許営業や名義貸し等は特に重い。懲役と罰金が併科されることもある。過料は行政罰。
試験では、処分の種類と事由の組み合わせ、処分権者、取引士証の扱い、罰則の重さなどが問われます。特に業者と取引士の処分の違い、免許取消・登録消除の必要的/任意的、取引士証の提出/返納の違いなどは頻出ポイントなので、しっかり区別して覚えてくださいね。

これで宅建業法のルールとそのペナルティについて、一通り学ぶことができましたね! 知識をしっかり定着させて、自信を持って試験に臨んでください!

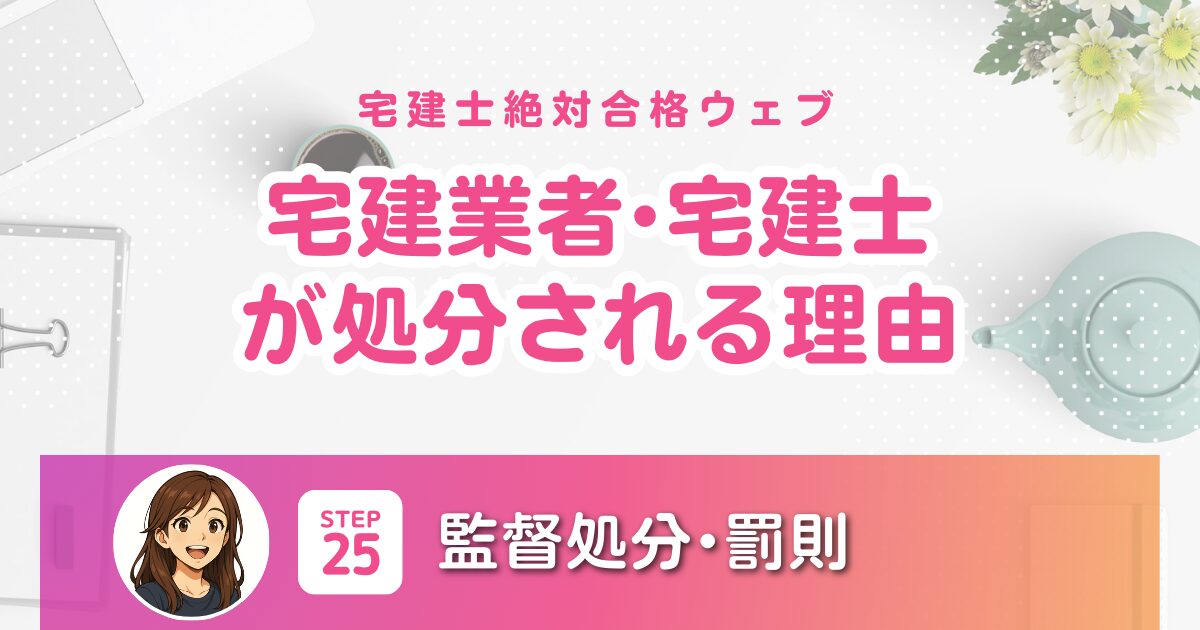


一つの違反行為に対して、監督処分と罰則の両方が科されることもあります。例えば、無免許で宅建業を営んだ場合、免許がないので免許取消処分は受けませんが、懲役や罰金といった「罰則」が科されます。また、業務停止処分を受けたのに営業を続けた場合、免許取消という「監督処分」を受け、さらに懲役や罰金といった「罰則」も科される可能性があります。