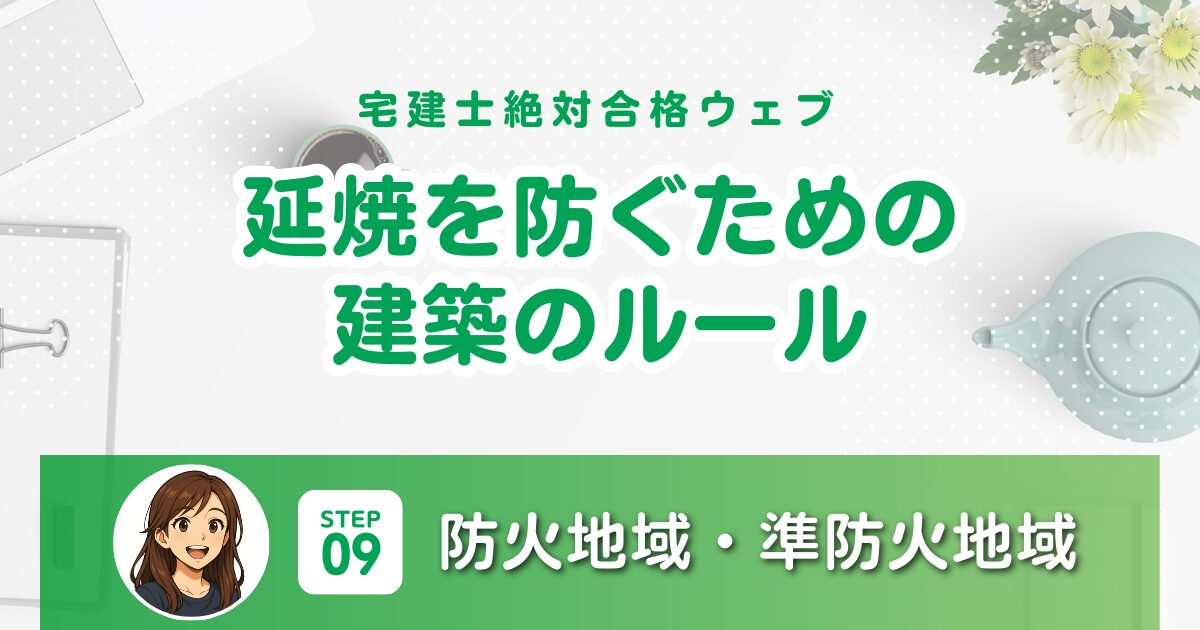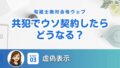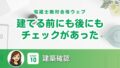建築基準法の中には、似たような用語や細かい数字がたくさん出てきて、「防火地域?準防火地域?何が違うの?」「耐火建築物とか準耐火建築物とか、もうわけがわからない!」って混乱してしまうこと、ありますよね。特に防火地域と準防火地域は、建物の制限に関わる重要なルールなのに、違いや具体的な基準がなかなか頭に入ってこない…なんて方も多いのではないでしょうか?
市街地で火災が起きたときの被害を最小限にするために、とっても大切なルールなんですけど、覚えることが多くて大変ですよね。私も受験生の時は、このあたりの数字や条件を覚えるのに苦労しました…
でも、大丈夫です!この記事では、そんな防火地域と準防火地域について、基本的なことから、試験で狙われやすいポイントまで、わかりやすく解説していきます。それぞれの地域でどんな建物が建てられて、どんな制限があるのか、そして、もし建物が2つの地域にまたがっていたらどうなるのか…など、皆さんがつまずきやすい点をしっかりカバーします。

この記事を読めば、防火地域・準防火地域のモヤモヤがスッキリ解消されて、自信を持って問題に取り組めるようになりますよ!
<この記事でわかること>
- 防火地域・準防火地域がどんな目的で指定されるのか
- 防火地域と準防火地域の制限の違い
- それぞれの地域で建物を建てる際の具体的なルール(階数・面積・構造)
- 建物が防火地域と準防火地域にまたがる場合の重要なルール
- 試験で特に注意すべきポイント
防火地域・準防火地域のキホン | 目的と指定、違いを知ろう
まずは、防火地域と準防火地域がどんなものなのか、基本的なところから押さえていきましょう!
防火地域・準防火地域ってどんな地域?指定の目的は?
防火地域(ぼうかちいき)と準防火地域(じゅんぼうかちいき)は、都市計画法という法律に基づいて、「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」として指定されるエリアのことです。
簡単に言うと、「ここは火事が燃え広がりやすいから、特に気を付けて建物を建ててね!」と指定されている地域なんですね。

都市計画法で「地域」を定めるんですね。
例えば、駅前の商店街や、建物がぎゅっと密集しているような場所をイメージしてみてください。もし1軒の建物で火災が発生したら、あっという間に隣の建物、そのまた隣の建物へと燃え移って、大きな火災になってしまう可能性がありますよね。

そういった市街地での火災の延焼(燃え広がること)を防いで、被害を最小限に食い止めるために、防火地域や準防火地域が指定されます。そして、これらの地域内では、建物を燃えにくい構造にするためのルール(建築制限)が定められているんです。
防火地域・準防火地域の目的は、市街地での火災の延焼防止! これ、基本中の基本なのでしっかり覚えておきましょう。
防火地域と準防火地域、どっちが厳しい?
防火地域と準防火地域、名前は似ていますが、火災防止のための規制の厳しさには違いがあります。
結論から言うと、防火地域の方が、準防火地域よりも規制が厳しいです。

「準」がつくと、少し制限が緩やかになるイメージですね!
一般的に、より火災の危険性が高いと考えられる地域(例:特に建物が密集している商業地域など)が防火地域に指定され、その周辺の地域が準防火地域に指定されることが多いです。
規制が厳しいということは、それだけ燃えにくい、しっかりとした構造の建物を建てなければならない、ということになります。具体的にどんな違いがあるのかは、次の章で詳しく見ていきましょう。
<防火地域 vs 準防火地域 規制の厳しさ比較表>
| 地域 | 規制の厳しさ | 主な指定場所(イメージ) |
|---|---|---|
| 防火地域 | 厳しい | 駅前商業地、幹線道路沿いなど、特に建物が密集し、火災時の危険性が高いエリア |
| 準防火地域 | やや厳しい(防火地域よりは緩やか) | 防火地域の周辺、住宅密集地など |
どちらの地域にも指定されていない場所もあります。その場合は、これらの厳しい建築制限はかかりません。(ただし、建築基準法上の他の耐火性能に関する規定がかかる場合はあります。)
【重要ポイント】防火地域・準防火地域内の建築制限 | 耐火建築物・準耐火建築物
さて、ここからが本番です!防火地域と準防火地域では、具体的にどのような建物を建てなければならないのか、そのルール(建築制限)を見ていきましょう。階数や延べ面積によって、求められる建物の種類が変わってくるので、しっかり整理して覚える必要がありますよ。
ここで出てくる重要なキーワードが「耐火建築物(たいかけんちくぶつ)」と「準耐火建築物(じゅんたいかけんちくぶつ)」です。
- 耐火建築物:主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)が耐火構造であるもの+延焼のおそれのある部分にある開口部(窓やドアなど)に防火設備(防火戸など)を有する建築物。火災が起きても、一定時間、倒壊したり延焼したりしない、非常に燃えにくい構造です。鉄筋コンクリート造などが代表例です。
- 準耐火建築物:耐火建築物に準ずる耐火性能を持つ建築物。耐火建築物ほどではないけれど、通常の建物よりは燃えにくい構造になっています。
ざっくり言うと、耐火建築物の方が準耐火建築物よりも、さらに火に強い建物、というイメージでOKです!
防火地域の建築制限 | 階数・延べ面積の基準を覚えよう
まずは、規制が厳しい防火地域のルールからです。
防火地域内では、建物の階数や延べ面積によって、次の2つのルールが適用されます。
【ルール1】
次のいずれかに該当する建築物は、必ず耐火建築物等としなければなりません。
- 地階を含む階数が3以上 の建築物
- 延べ面積が100㎡を超える 建築物
防火地域の最重要ポイント!「階数3以上」または「延べ面積100㎡超」は絶対に耐火建築物等!ここは数字と条件を正確に暗記してくださいね!
「地階を含む」という点も見落としがちなので注意です!地上2階建てでも、地下1階があれば階数は3になります。
【ルール2】
上記【ルール1】に該当しない建築物(つまり、地階を含まない階数が2以下で、かつ延べ面積が100㎡以下の建築物)は、耐火建築物または準耐火建築物としなければなりません。
防火地域では、どんなに小さな建物でも、最低でも準耐火建築物にしないといけないんですね!厳しい!
「耐火建築物等」って何?
先ほどの【ルール1】で「耐火建築物等」という言葉が出てきましたね。これは、厳密には以下のいずれかを指します。
- 耐火建築物
- 延焼防止性能について、耐火建築物と同等の安全性を確保できるものとして政令で定める技術的基準に適合する建築物(特定避難時間倒壊等防止建築物など、難しい名前がついていますが、宅建試験レベルでは「耐火建築物と同等の性能を持つもの」と理解しておけば十分です)
試験対策上は、「耐火建築物等 ≒ 耐火建築物」と考えてしまって、まずは大丈夫です。ただし、選択肢で正確な表現が問われる可能性もあるので、頭の片隅には置いておきましょう。
<防火地域の建築制限まとめ表>
| 建築物の条件 | 求められる建築物の種類 |
|---|---|
| 地階を含む階数3以上 または 延べ面積が100㎡を超える | 耐火建築物等 |
| 上記以外(階数2以下 かつ 延べ面積100㎡以下) | 耐火建築物 または 準耐火建築物 |
【忘れがち注意】防火地域の看板・広告塔のルール
防火地域では、建物本体だけでなく、看板などにも防火上のルールがあります。うっかり見落としやすいポイントなので、しっかり確認しましょう。
防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、以下のいずれかに該当するものは、その主要な部分を不燃材料で造り、または覆わなければなりません。
- 建築物の屋上に設けるもの
- 高さが3mを超えるもの
不燃材料(ふねんざいりょう)とは、コンクリート、れんが、瓦、鉄鋼、アルミニウム、ガラスなど、建築材料のうち、燃えにくい性能を持つものとして国土交通大臣が定めたもの、または認定したものを指します。

屋上にある看板や、背の高い看板は、燃えにくい材料で作ってね、ということですね。
看板のルールは、「屋上」または「高さ3m超」がキーワードです!これもセットで覚えておきましょう。
準防火地域の建築制限 | 防火地域との違いを比較
次に、準防火地域の建築制限を見ていきましょう。防火地域よりは規制が少し緩やかになりますが、それでも一定の基準を満たす必要があります。
準防火地域内では、建物の階数や延べ面積によって、主に次の3つのルールが適用されます。
【ルール1】
次のいずれかに該当する建築物は、必ず耐火建築物等としなければなりません。
- 地階を除く階数が4階以上 の建築物
- 延べ面積が1,500㎡を超える 建築物
準防火地域の最重要ポイント!「地階を除く階数4階以上」または「延べ面積1,500㎡超」は耐火建築物等!防火地域との数字の違いをしっかり区別してください!
防火地域では「地階を含む階数3以上」でしたが、準防火地域では「地階を除く階数4階以上」です。この違い、ひっかけ問題でよく出ますよ!
【ルール2】
次のいずれかに該当する建築物は、耐火建築物等 または 準耐火建築物等としなければなりません。
- 地階を除く階数が3 の建築物
- 延べ面積が500㎡を超え、1,500㎡以下 の建築物
準防火地域の3階建てや、中規模の建物(延べ面積500㎡超~1,500㎡以下)は、耐火建築物等か準耐火建築物等にする必要がある、と覚えましょう。
ここでも「耐火建築物等」「準耐火建築物等」となっていますが、これも先ほどの防火地域の場合と同様に、「耐火建築物または準耐火建築物とその同等以上の性能を持つもの」という意味合いです。
【ルール3】
上記【ルール1】【ルール2】に該当しない建築物(例:木造2階建て、延べ面積500㎡以下など)については、一定の技術的基準(外壁や軒裏の防火構造など)を満たす必要がありますが、原則として耐火建築物や準耐火建築物にしなくてもよい場合があります。(ただし、一定の条件を満たす木造建築物等は、準耐火建築物等と同等の防火性能が求められることもあります。)
準防火地域では、比較的小さな建物なら、必ずしも耐火・準耐火にしなくても良い場合があるんですね。防火地域より少し柔軟性があります。
防火地域と準防火地域の建築制限比較まとめ
<防火地域と準防火地域の建築制限比較表>
| 地域 | 条件 | 求められる建築物 |
|---|---|---|
| 防火地域 | 階数3以上 (地階含む) または 延べ面積 100㎡超 | 耐火建築物等 |
| 上記以外 | 耐火建築物 または 準耐火建築物 | |
| 準防火地域 | 階数4階以上 (地階除く) または 延べ面積 1,500㎡超 | 耐火建築物等 |
| 階数3階 (地階除く) または 延べ面積 500㎡超 1,500㎡以下 | 耐火建築物等 または 準耐火建築物等 | |
| 上記以外 | 原則として耐火・準耐火でなくてもよい(ただし一定の防火措置は必要) |
こうして並べてみると、違いが分かりやすいですね!特に階数と延べ面積の数字はしっかり区別して覚えましょう!
建物が地域をまたがる場合のルール
宅建試験で非常によく狙われるのが、建築物が防火地域と準防火地域にまたがって建っている場合のルールです。
例えば、敷地の一部が防火地域で、残りが準防火地域というケースです。この場合、建物全体にどちらの地域のルールが適用されるのでしょうか?
答えは、
建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合は、その全部について、防火地域内の建築物に関する規定が適用される
です!
つまり、建物の一部でも防火地域にかかっていれば、建物全体が防火地域の厳しい規制を受けるということになります。
ここで、非常に重要な注意点があります!
このルールの主語は「建築物」であって、「敷地」ではありません!
どういうことかと言うと、たとえ敷地が防火地域と準防火地域にまたがっていても、建物自体が完全に準防火地域内に収まっていれば、その建物には準防火地域の規定しか適用されない、ということです。
あくまで建物が防火地域にかかっているかどうかで判断します。敷地が防火地域にかかっていても、建物がセーフならセーフ!ここは本当に間違えやすいので、しっかり区別してくださいね!
まとめ
今回は、宅建試験の建築基準法から「防火地域」と「準防火地域」について詳しく解説しました。市街地の火災延焼を防ぐための重要なルールでしたね。
最後に、今回の重要ポイントをまとめておきましょう!
- 防火地域・準防火地域は、都市計画法に基づき、市街地の火災延焼を防ぐために指定される地域です。
- 規制の厳しさは、防火地域 > 準防火地域 です。
- 防火地域では、原則として階数3以上(地階含む) or 延べ面積100㎡超の建物は耐火建築物等に、それ以外の建物も耐火建築物 or 準耐火建築物にする必要があります。
- 防火地域の看板等は、屋上設置 or 高さ3m超なら不燃材料で造る必要があります。
- 準防火地域では、原則として階数4階以上(地階除く) or 延べ面積1,500㎡超の建物は耐火建築物等に、階数3階(地階除く) or 延べ面積500㎡超1,500㎡以下の建物は耐火建築物等 or 準耐火建築物等にする必要があります。
- 建物が防火地域と準防火地域にまたがる場合は、建物全体に厳しい方の防火地域の規定が適用されます。
- またがる場合の判断基準は、建物です!敷地ではありません。

防火地域・準防火地域は、建築基準法の中でも頻出のテーマです。特に、階数や延べ面積の数字、そして地域をまたがる場合のルールは、ひっかけ問題も作りやすいので、試験で確実に得点できるように、何度も復習して完璧にマスターしておきましょう!