さあ、権利関係の山場、借地借家法に突入です!特に、土地を借りて建物を建てるための権利、「借地権(しゃくちけん)」のルール、なんだかややこしくて、どこから手をつけていいか分からない…なんて思っていませんか?「普通借地権」と「定期借地権」って何が違うの?契約期間って最低何年?更新はどうなるの?もし地主さんが土地を売っちゃったら、借りてる権利はどうなるの…?など、疑問がいっぱいで頭が混乱しちゃいますよね。
借地権は、私たちの住まいや事業に関わる大切な権利ですが、民法のルールだけでは借りている人(借地権者)の立場が弱くなってしまうことがあります。そこで、借地人を手厚く保護するために作られたのが「借地借家法」なんです。この法律には、民法の原則を変更する特別なルールがたくさん定められています。
この記事では、宅建試験で避けては通れない超重要分野である「借地権」について、借地借家法の基本ルールを中心に、普通借地権の存続期間や更新の仕組み、第三者に対する対抗力、契約期間中に建物が壊れた場合のルール、借地権を譲渡したり転貸したりする場合の手続き、そして契約終了時の建物買取請求権まで、しっかり解説します。さらに、契約の更新がない定期借地権についても、3つの種類(一般定期借地権、建物譲渡特約付借地権、事業用定期借地権等)それぞれの特徴と違いを、比較しながら分かりやすく説明していきます!

この記事を読めば、普通借地権と定期借地権の根本的な違い、契約更新の具体的な手続きや要件、登記がなくても権利を主張できる「対抗要件」の特則など確実にマスターできますよ。
<この記事でわかること>
- 借地権の定義と借地借家法による保護の必要性
- 借地権を第三者に対抗するための要件(建物登記、滅失時の掲示)
- 普通借地権の存続期間(最低期間、更新後の期間)
- 普通借地権の更新方法(合意・請求・法定)と地主が拒絶できる「正当事由」
- 契約期間中に建物が滅失した場合の再築ルール
- 借地権の譲渡・転貸に必要な手続きと裁判所の許可制度
- 契約終了時に建物を買い取ってもらえる「建物買取請求権」
- 更新がない「定期借地権」3種類の違い(期間、目的、契約方法など)
借地権のキホン:土地を借りて建物を建てる権利【借地借家法】
まずは、「借地権」とは何か、そしてなぜ「借地借家法」という特別な法律で保護されているのか、基本から確認しましょう。
借地権とは?建物を建てるための土地利用権
借地権とは、建物の所有を目的とする「地上権」または「土地の賃借権」のことを指します(借地借家法 第2条1号)。
ポイントは「建物の所有を目的とする」という部分です。単に駐車場として使うため、資材置き場として使うために土地を借りる場合は、原則として借地借家法の対象となる「借地権」にはあたりません(その場合は主に民法の賃貸借のルールが適用されます)。
借地権には「地上権」と「土地の賃借権」の2種類がありますが、覚えていますか?
- 地上権: 設定契約と登記により発生する「物権」。譲渡や転貸が自由。
- 土地の賃借権: 賃貸借契約により発生する「債権」。譲渡や転貸には原則として賃貸人の承諾が必要。
実際には、地主さんにとって制約の大きい地上権が設定されることは稀で、ほとんどの借地権は「土地の賃借権」です。賃借権は本来、契約相手(賃貸人)にしか主張できない弱い権利(債権)ですが、このままだと、土地を借りて建物を建てた人の立場が不安定になってしまいますよね。
弱い立場?いいえ!借地人を守る借地借家法のルール
そこで登場するのが「借地借家法」です。この法律は、民法の原則を修正し、建物の所有を目的として土地を借りる人(借地権者)の権利を手厚く保護することを目的としています。
なぜなら、借地権者は土地の上に建物を建てて生活や事業の基盤としていることが多く、簡単に土地を取り上げられてしまうと、非常に大きな損害を被ってしまうからです。地主さんと比べて立場が弱くなりがちな借地権者を守るために、様々な特別ルールが設けられているのです。
その一つが「片面的強行規定(へんめんてききょうこうきてい)」という考え方です。借地借家法の多くの規定は、これに反する特約(契約での特別な約束)を結んでも、それが借地権者にとって不利なものであれば無効になる、という効力を持っています(借地借家法 第16条、第21条など)。つまり、法律が定めた最低限の保護ラインを下回るような契約は許されない、ということです。
超重要!借地権の対抗力:地主が変わっても大丈夫?
借地権が保護される重要なルールの筆頭が「対抗力」です。
前回の賃貸借の記事でも触れましたが、土地の賃借権(借地権)は、本来「登記」をしなければ、土地の所有者が変わった場合(例えば、地主さんが土地を第三者に売却した場合)に、新しい所有者に対して「私はこの土地を借りる権利がある!」と主張できませんでしたよね。そして、賃貸人には登記協力義務がないため、登記は難しいのが現実でした。
しかし、借地借家法は、借地権者が土地の上に建てた建物の登記があれば、借地権自体の登記がなくても対抗力を認める、という画期的なルールを定めました!
ここでのポイントは2つ!
- 借地権者自身の名義で登記されていること。(例えば、同居している息子の名義ではダメ、という判例があります)
- 登記されている建物であること。(建物の種類を示す「表示の登記」でも、所有権を示す「所有権保存登記」や「所有権移転登記」でもOKです)
この2つの要件を満たす建物を土地の上に持っていれば、たとえ借地権自体の登記がなくても、後から土地の所有権を取得した新しい地主さんに対しても、堂々と借地権を主張できるのです!
【建物滅失時の対抗力維持(掲示)】
では、もしその登記された建物が火事や地震で滅失してしまったら、対抗力も失われてしまうのでしょうか?それでは、建物を再築しようと考えている借地権者は不安ですよね。
そこで、借地借家法は、登記された建物を所有していた借地権者が、建物滅失後、一定の事項(滅失があった日、建物を特定するために必要な事項、新たに建物を築造する旨)を、その土地の見やすい場所に掲示すれば、建物が滅失した日から2年間は、建物の登記がなくても第三者に対抗できる、というルールも設けています(借地借家法 第10条2項)。

建物がなくなっても、すぐに権利を失うわけじゃないんですね!再築のための猶予期間が与えられるのは安心です。
普通借地権のルール:期間・更新・建物はどうなる?
借地借家法が定める借地権には、大きく分けて「普通借地権」と「定期借地権」があります。まずは、原則となる「普通借地権」のルールについて詳しく見ていきましょう。普通借地権は、契約の更新があるのが特徴です。
契約期間は最低30年!普通借地権の存続期間
普通借地権の契約期間(存続期間)は、民法の賃貸借ルールよりもかなり長く設定されています。
- 最初の契約期間:
- 契約で期間を定める場合、最低でも30年以上としなければなりません(借地借家法 第3条)。もし、契約で「20年」と定めても、自動的に「30年」になります。
- 契約で期間を定めなかった場合も、存続期間は30年となります(借地借家法 第9条)。
- 最長期間については特に制限はありません。50年でも100年でも設定可能です。
- 更新後の契約期間:
- 契約が更新された場合、最初の更新後の存続期間は最低でも20年以上、2回目以降の更新後の存続期間は最低でも10年以上としなければなりません(借地借家法 第4条、第9条)。
- 当事者がこれより長い期間(例えば、最初の更新で30年)を定めることは自由です。期間を定めなかった場合は、法定の最低期間(初回20年、以降10年)となります。
<存続期間の比較表(最低期間)>
| 権利の種類 | 最初の契約期間 | 更新後(1回目) | 更新後(2回目以降) | 備考 |
| 民法の土地賃貸借 | 定めなし | 定めなし | 定めなし | 最長50年の制限あり |
| 普通借地権 (借地借家法) | 30年以上 | 20年以上 | 10年以上 | 最長制限なし |
| 普通借家権 (借地借家法) | 制限なし | (期間定めなし) | (期間定めなし) | 1年未満は期間定めなし |
<チェック>
普通借地権の「30年」「20年」「10年」という最低期間は、試験で頻出です!しっかり暗記しましょう。
契約は続く?終わる?普通借地権の更新ルール
普通借地権の大きな特徴は、原則として契約が更新されることです。借地人の生活基盤を守るためですね。更新の方法には3つのパターンがあります。
- 合意更新: 借地権者と地主が話し合って合意し、契約を更新する方法です。更新後の期間は、法定の最低期間(初回20年、以降10年)以上であれば、自由に定めることができます。
- 請求による更新: 契約期間が満了する際に、土地の上に建物が存在する場合、借地権者が地主に対して「更新してください!」と請求すれば、原則として前の契約と同じ条件で契約が更新されます(借地借家法 第5条1項)。
更新後の期間は、定めがなければ法定期間(初回20年、以降10年)となります。この更新請求に対して、地主が拒絶するには、後述する「正当事由」が必要です。 - 法定更新(使用継続による更新): 土地の上に建物が存在する場合で、契約期間が満了した後も、借地権者が土地の使用を継続しているのに、地主が遅滞なく異議を述べなかったときも、前の契約と同じ条件で契約が更新されたものとみなされます(借地借家法 第5条2項)。
これも法定更新の一種で、更新後の期間は定めがなければ法定期間となります。この場合も、地主が更新を阻止するには「正当事由」のある異議が必要です。
【地主の更新拒絶と「正当事由」】
上記の「請求による更新」や「法定更新」に対して、地主が「更新したくない!」と拒絶するためには、ただ「嫌だ」と言うだけではダメで、遅滞なく異議を述べ、かつ、その異議に「正当な事由」があると認められる必要があります(借地借家法 第6条)。
「正当事由」があるかどうかは、以下の要素などを総合的に考慮して、裁判所が最終的に判断します。
- 土地の使用者(地主及び借地権者)が土地の使用を必要とする事情(例:地主が自分で家を建てて住む必要性 vs 借地権者がそこで生活・営業している必要性)
- 借地に関する従前の経緯(権利金支払いの有無、契約期間、これまでの信頼関係など)
- 土地の利用状況(建物の種類、老朽化の程度、周辺の土地利用など)
- 地主が借地権者に対して財産上の給付(いわゆる立退料)を提供する旨の申出
立退料の提供は、正当事由を補強する一要素にすぎません。立退料を払えば必ず正当事由が認められるわけではありませんし、逆に立退料がなくても他の事情から正当事由が認められることもあります。

借地上に建物がある限り、借地権はかなり強く保護されていて、地主さんが更新を拒むのは結構ハードルが高いんですね!
契約期間中に建物が燃えちゃったら?【建物滅失と再築】
契約期間中に、借地上の建物が火事や災害で滅失してしまった場合、借地権者はその土地に建物を再築することができるのでしょうか?これも、最初の契約期間中か、更新後の期間中かでルールが異なります。
(1) 最初の契約期間中の滅失・再築(借地借家法 第7条)
- 地主の承諾がある場合: 当然、再築できます。この場合、借地権の存続期間は、承諾があった日または建物が再築された日のうち、いずれか早い方から20年間延長されます。
- 地主の承諾がない場合: なんと、承諾がなくても再築は可能です!ただし、この場合、借地権の存続期間は延長されません。当初の契約期間満了で原則終了しますが、満了時に建物がちゃんと存在していれば、更新請求権や法定更新の適用はあり得ます。
- 地主に承諾を求めたが、2ヶ月以内に返事がない場合: この場合は、地主が承諾したものとみなされ、存続期間は上記と同様に20年間延長されます。
(2) 更新後の契約期間中の滅失・再築(借地借家法 第8条)
- 地主の承諾がある場合: 再築できます。存続期間も、承諾があった日または建物が再築された日のうち、いずれか早い方から20年間延長されます。(これは最初の期間中と同じ)
- 地主の承諾がない場合: ここが違います!最初の期間中と異なり、更新後の期間中に地主の承諾なく、残存期間を超えて長持ちするような建物を再築した場合、地主は借地権の消滅請求や賃貸借契約の解約申入れをすることができます。この申入れがあると、3ヶ月後に借地権は消滅してしまいます!
- ただし、借地権者としては、どうしても再築したいやむを得ない事情がある場合には、裁判所に申し立てて、地主の承諾に代わる許可を得る道があります。
- 地主に承諾を求めたが、2ヶ月以内に返事がない場合: 最初の期間中とは異なり、みなし承諾の規定はありません。したがって、承諾が得られない限り、勝手に再築すると解約されるリスクがあります。裁判所の許可を得る必要があります。
最初の期間中は比較的自由に再築できますが、更新後の期間中は地主の意向がより尊重される(承諾なしの再築にリスクがある)という違いがあります。しっかり区別しましょう!
借地権を売りたい!又貸ししたい!【譲渡・転貸の承諾と裁判所の許可】
土地の賃借権である借地権を、第三者に譲渡したり、土地を転貸(又貸し)したりするには、原則として地主の承諾が必要でしたよね(民法612条)。
しかし、借地権者が借地上の建物を売りたい場合、建物だけ売っても土地の借地権が一緒に付いてこなければ、買い手は困ってしまいます。だから通常、建物の譲渡と借地権の譲渡はセットで行われます。
このとき、もし地主さんが、特に不利になるわけでもないのに、借地権の譲渡や転貸の承諾をしてくれない場合はどうすればいいのでしょうか?
ここでも借地借家法が借地権者を助けてくれます!
借地権者は、裁判所に申し立てて、地主の承諾に代わる許可を求めることができるのです(借地借家法 第19条)。
裁判所は、地主の不利益にならないかなど諸事情を考慮し、許可を与えるかどうかを判断します。許可が出れば、地主の承諾がなくても、借地権を譲渡したり、土地を転貸したりすることが可能になります。
地主さんの横暴(不当な承諾拒否)から借地権者を守るための制度ですね!ただし、あくまで「地主に不利にならないのに」という条件付きです。
契約終了!でも建物が…【建物買取請求権】
普通借地権の存続期間が満了し、契約が更新されない場合、借地権者は土地を更地にして返還するのが原則ですが、それでは土地の上に建てた建物が無駄になってしまいます。
そこで、借地借家法は、借地権者を保護するため、「建物買取請求権(たてものかいとりせいきゅうけん)」という強力な権利を認めています(借地借家法 第13条)。
これは、借地権の存続期間が満了し、契約の更新がない場合に、借地権者が地主に対して、借地上にある建物を時価で買い取るように請求できる権利です。この請求権が行使されると、地主の意思に関わらず、建物の売買契約が成立したのと同じ効果が生じ、地主は建物を時価で買い取らなければなりません。
この権利は、借地権者の賃料不払いなどの債務不履行によって契約が解除された場合には行使できません。あくまで、契約が円満に(?)更新されずに終了する場合の保護措置です。
【第三者の建物買取請求権】
建物買取請求権は、期間満了時だけでなく、別の場面でも登場します。
それは、借地上の建物を取得した第三者が、地主から賃借権の譲渡・転貸について承諾を得られなかった場合です。
先ほど、譲渡・転貸の承諾が得られない場合、元の借地権者は「裁判所の許可」を求められると説明しましたね。しかし、もし許可を得ずに建物が譲渡され、建物を買った第三者が後から地主に承諾を求めても拒否された場合、どうなるでしょうか?
この場合、建物を取得した第三者は、地主に対して「この建物を時価で買い取ってください!」と請求することができるのです(借地借家法 第14条)。建物を買ったのに土地が使えない、という最悪の事態を避けるためのセーフティネットですね。
<譲渡・転貸に関する保護規定 まとめ>
| タイミング | 保護される者 | 保護の方法(行使できる権利) | 根拠条文 |
| 譲渡・転貸前(承諾拒否時) | 借地権者(元の借り主) | 裁判所の許可の申立て | 借地借家法19条 |
| 譲渡・転貸後(承諾拒否時) | 建物を取得した第三者 | 建物買取請求権の行使 | 借地借家法14条 |
更新がない借地権!?定期借地権の種類と特徴を知ろう
これまで見てきた普通借地権は、更新があることで借地権者が長期間安定して土地を利用できるメリットがありました。しかし、地主さん側からすると、「一度貸したらなかなか土地が返ってこない」というデメリットにもなります。
そこで、一定期間が経過したら確実に土地が返還されることを目的として創設されたのが、「定期借地権(ていきしゃくちけん)」です。定期借地権は、契約の更新がないことが最大の特徴です。
定期借地権には、以下の3つの種類があります。
定期借地権とは?3つのタイプを比較!
- 一般定期借地権(借地借家法 第22条)
- 建物譲渡特約付借地権(借地借家法 第24条)
- 事業用定期借地権等(借地借家法 第23条)
それぞれの特徴を見ていきましょう。
【タイプ①】一般定期借地権:最もスタンダードな定期借地権
- 存続期間: 50年以上で定めなければなりません。
- 目的: 建物の種類に制限はありません(居住用でも事業用でもOK)。
- 必須の特約: 以下の3つの特約を必ず定めなければなりません。
- 契約の更新をしないこと
- 期間の延長(建物の再築などによる)をしないこと
- 期間満了時の建物買取請求権を認めないこと
- 契約方法: 上記の特約を定める場合は、必ず書面(契約書)によってしなければなりません。公正証書である必要はありませんが、口頭ではダメです。
⇒ 期間が満了したら、借地権者は建物を収去して土地を更地にして地主に返還する必要があります。
【タイプ②】建物譲渡特約付借地権:期間満了時に建物を売る約束
- 存続期間: 30年以上で定めます。
- 目的: 建物の種類に制限はありません。
- 必須の特約: 「借地権設定後30年以上を経過した日に、借地上の建物を地主に相当の対価で譲渡する」旨の特約を結びます。この建物の譲渡によって借地権は消滅します。
- 契約方法: この特約は、書面でする必要はありません。口頭での合意でも有効です。
- <メモ>期間満了と同時に地主が建物を買い取る(借地権者からみれば売却する)ことで、スムーズに借地関係を終了させるタイプの契約ですね。
【タイプ③】事業用定期借地権等:事業用建物のための借地権
- 存続期間: 10年以上50年未満の範囲で定めます。(※法改正があり、以前は10年以上20年以下でした。現行法では10年以上50年未満です。より使いやすくなりました。)
- 目的: 専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする場合に限られます。居住用の建物(店舗兼住宅なども含む)は対象外です。
- 必須の特約: 一般定期借地権と同様に、①更新しない、②期間延長しない、③建物買取請求権を認めない、という内容の特約(借地借家法23条2項で規定される借地権の場合)を定めます。
- 契約方法: 必ず公正証書によって契約しなければなりません。普通の契約書や口頭では設定できません。
例えば、賃貸マンションやアパート経営のために土地を借りる場合、建物は事業用ですが「居住用」でもあるため、この事業用定期借地権等は利用できません。その場合は、普通借地権や一般定期借地権などを利用することになります。
<定期借地権3タイプの比較表>
| 種類 | 存続期間 | 目的 | 必須特約 | 契約方式 |
| 一般定期借地権 | 50年以上 | 制限なし | 更新なし・延長なし・建物買取請求権なし | 書面 |
| 建物譲渡特約付借地権 | 30年以上 | 制限なし | 建物譲渡特約(設定後30年以上経過日) | 口頭でも可 |
| 事業用定期借地権等 | 10~50年未満 | 事業用のみ | 更新なし・延長なし・建物買取請求権なし(23条2項の場合) | 公正証書 |

定期借地権は種類によって期間や契約方法が全然違いますね!それぞれの特徴をしっかり区別して覚えましょう!
まとめ
お疲れ様でした!今回は、借地借家法の「借地権」について、普通借地権の基本ルールから定期借地権の種類まで、盛りだくさんの内容を解説しました。
借地権は、建物の所有を目的とする土地利用権であり、弱い立場になりがちな借地人を保護するために、借地借家法によって民法の原則が大きく修正されています。対抗力、存続期間、更新、建物滅失、譲渡・転貸、建物買取請求権といった普通借地権のルール、そして更新のない定期借地権の3つのタイプ、それぞれのポイントをしっかり掴むことができましたか?
- 借地権は建物所有目的の土地利用権。借地借家法で手厚く保護される。
- 対抗力は原則登記だが、借地権者名義の建物登記でOK。滅失後も掲示で2年間維持可能。
- 普通借地権の期間は最低30年、更新後は初回20年、以降10年。建物があれば原則更新(地主拒絶には正当事由必要)。
- 賃借権譲渡・転貸は承諾必要だが、不承諾でも裁判所の許可の道あり。
- 契約更新がない場合、借地権者は地主に建物買取請求ができる。譲渡不承諾時に建物を取得した第三者も同様。
- 定期借地権は更新がないタイプで、①一般(50年以上/書面/買取請求権なし)、②建物譲渡特約付(30年以上/口頭可/建物譲渡)、③事業用(10~50年未満/公正証書/事業用のみ)の3種類。

借地借家法の分野は、数字や要件が多くて覚えるのが大変ですが、それぞれの制度趣旨(なぜこのようなルールになっているのか)を考えながら学習すると、より深く理解でき、忘れにくくなりますよ。

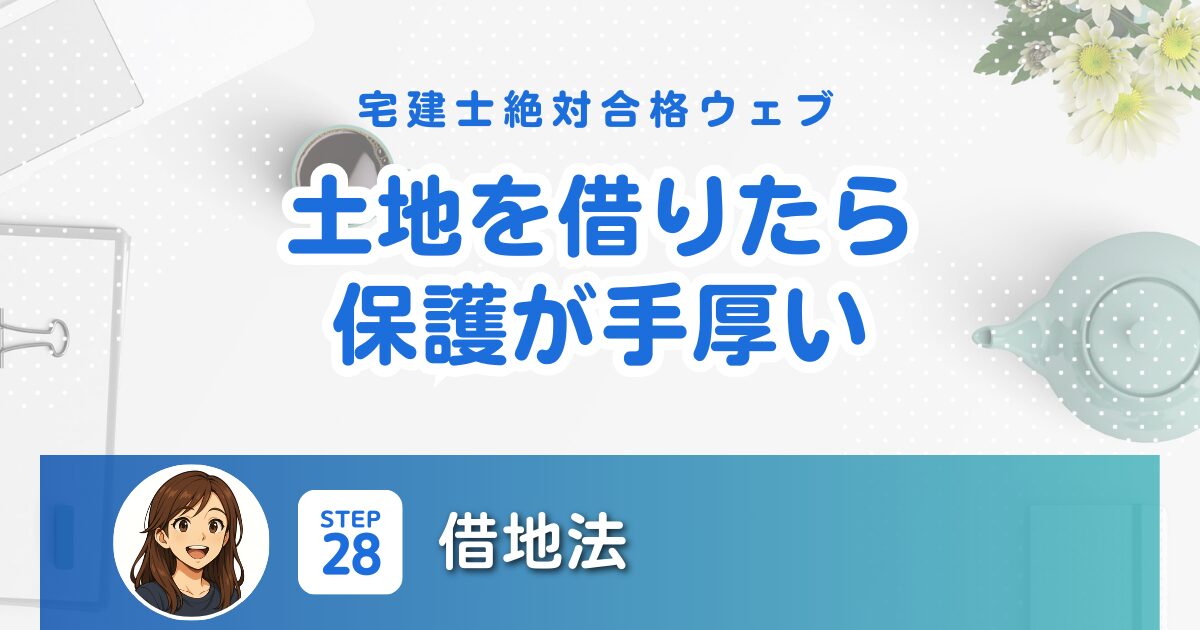


【借地権の対抗要件(借地借家法 第10条1項)】
借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。