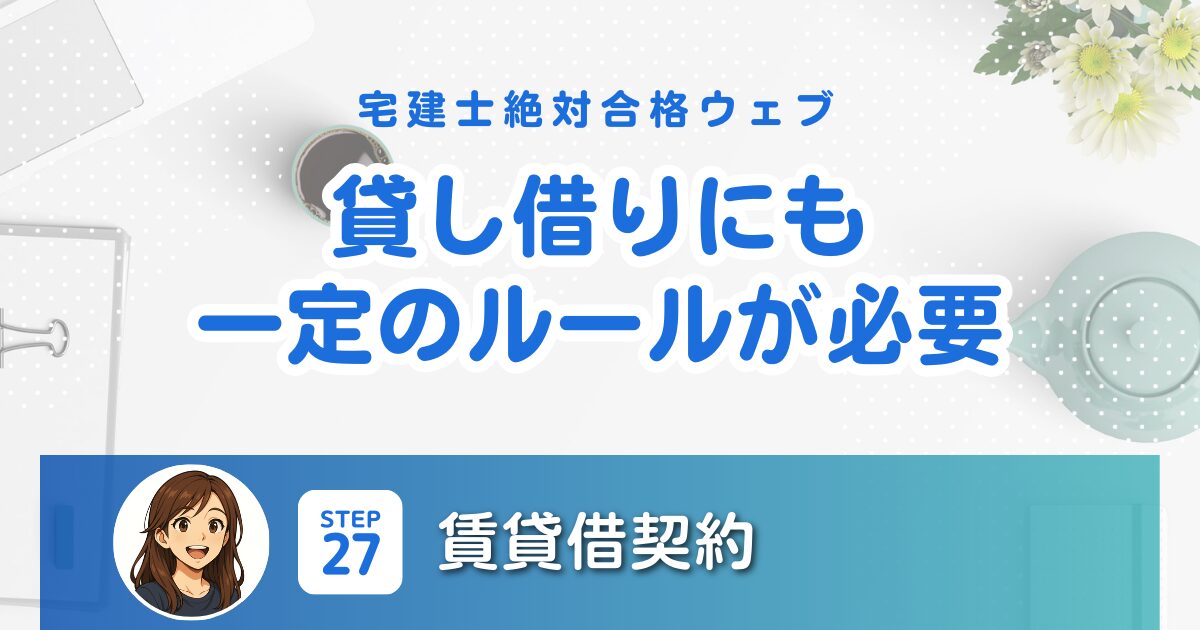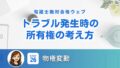さて、宅建の権利関係、学習は進んでいますか?今回は、私たちの生活にもとっても身近な「賃貸借契約(ちんたいしゃくけいやく)」についてです。アパートやマンションを借りたり、土地を借りて家を建てたり…こうした契約、日常的によく聞きますよね。
例えば、「借りているアパートの大家さんが変わったら、新しい大家さんに家賃を払えばいいの?追い出されたりしない?」「部屋の雨漏りがひどいんだけど、誰が直す責任があるの?自分で勝手に直しちゃダメ?」「退去するとき、敷金って全額返ってくるの?いつ返してもらえるの?」「友達に無料で部屋を貸す『使用貸借』って、普通の賃貸借と何が違うの?」…などなど、基本的なルールが意外とあやふやだったりしませんか?
賃貸借契約は、民法だけでなく、借地借家法という特別な法律も関わってくる、奥が深い分野なんです。
この記事では、そんな「賃貸借契約」について、基本となる権利(賃借権)を第三者に主張できるかという「対抗力」の問題から、借りている物の修繕は誰がすべきか、もし壊れたり使えなくなったりしたらどうなるのか(滅失)、借りた権利を人に譲ったり又貸ししたりできるのか(譲渡・転貸)、入居時に預ける敷金のルール、そしてよく似ているけど実は違う「使用貸借」との比較まで、受験生が混乱しやすいポイントを中心に一つ一つ丁寧に解説していきます!

この記事を読めば、賃貸借に関する幅広い知識が頭の中でスッキリ整理できます!
<この記事でわかること>
- 賃貸借契約の基本的な内容と賃借権の性質
- 賃借権を第三者に対抗するための要件(登記、建物登記、引渡し)
- 賃貸物件の修繕義務は誰にあるのか、賃借人が修繕できるケース
- 賃借物が滅失・損傷した場合の賃料減額や契約解除のルール
- 賃借権の譲渡や転貸(又貸し)のルールと無断で行った場合の効果
- 敷金の法的な意味、返還時期、当事者が変わった場合の扱い
- 無償の貸し借り「使用貸借」と賃貸借の重要な違い
賃貸借の基本ルールと対抗力:借りた権利を守る方法【借地借家法】
まずは、賃貸借契約の基本と、借りた権利(賃借権)を第三者にも主張できるか、という「対抗力」の問題から見ていきましょう。
まずは基本!賃貸借契約ってどんな契約?
賃貸借契約とは、当事者の一方(賃貸人、大家さんやオーナーのことですね)が、ある物の使用及び収益を相手方(賃借人、借り主のこと)にさせることを約束し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約束することによって、その効力を生じる契約です(民法601条)。
- 目的物: 不動産(土地、建物)だけでなく、動産(DVD、車など)も対象になりますが、宅建試験では主に不動産の賃貸借が問われます。
- 賃借権: この契約に基づいて、賃借人が賃貸人に対して「目的物を使わせて!」と要求できる権利のことです。これは、特定の人(賃貸人)に対して特定の行為(使わせること)を請求できる権利なので、「債権」に分類されます。物を直接支配する「物権」とは違うんですね。
借りた物件が売られたら?賃借権の対抗力とは
賃借権が「債権」であるということは、原則として、契約した相手(賃貸人)に対してしか主張できない、ということです。
では、もし借りているアパートのオーナー(賃貸人Aさん)が、そのアパートを別の人(Bさん)に売却してしまったらどうなるでしょう?賃借人であるあなたは、新しいオーナーBさんに対して「私はこの部屋を借りる権利(賃借権)があるんだから、引き続き住まわせてください!」と主張できるのでしょうか?
ここで重要になるのが「対抗力(たいこうりょく)」です。対抗力とは、契約当事者以外の第三者に対しても、自分の権利を主張できる法的な力のことです。
不動産の賃借権について、民法は、「登記」をすれば、その後にその不動産の権利を取得した第三者に対しても効力を生じる(対抗できる)と定めています(民法605条)。つまり、賃借権の登記があれば、新しいオーナーBさんに対しても賃借権を主張できるわけです。
しかし、現実には、賃貸借契約で賃借権の登記まですることはほとんどありません。なぜなら、賃貸人(オーナー)には、賃借権の登記に協力する義務が法律上ないからです。
そこで登場するのが、賃借人を保護するための特別な法律、「借地借家法(しゃくちしゃっかほう)」です!
借地借家法は、不動産賃借権の登記がなくても、一定の要件を満たせば第三者に対抗できる、という特則を設けて、賃借人の地位を強化しています。これは絶対に覚えてください!
【借地借家法による対抗力の特則】
- 土地の賃借権(借地権)の場合借地権(建物を所有する目的で土地を借りる権利)の登記がなくても、その土地の上に、借地権者(賃借人)自身の名義で登記された建物を所有していれば、第三者に対抗できます(借地借家法 第10条)。つまり、土地の賃借権自体の登記はなくても、その上に建てた自分の家の登記があればOK!ということです。
- 建物の賃借権の場合建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡し(鍵をもらって住み始めること)があったときは、その後にその建物について物権(所有権など)を取得した第三者に対抗できます(借地借家法 第31条)。つまり、アパートやマンションを借りて、実際に住んでいれば(引渡しを受けていれば)、後からオーナーが変わっても、新しいオーナーに対抗できるのです!
これは超重要ポイントです! 土地の賃借権は「建物登記」、建物の賃借権は「引渡し」 が対抗要件になる!と、しっかり区別して覚えましょう。これで、登記がなくても安心して借りていられますね。
<賃借権の対抗要件 まとめ表>
| 権利の種類 | 原則(民法) | 特則(借地借家法) |
| 土地賃借権 | 登記 | 借地上の賃借人名義の建物登記 (借地借家法10条) |
| 建物賃借権 | 登記 | 建物の引渡し (借地借家法31条) |
トラブル発生!賃貸物件の修繕・滅失と費用負担のルール
賃貸物件に住んでいると、雨漏りがしたり、設備が壊れたり、といったトラブルはつきものです。そんな時、修理は誰がしてくれるのか、費用は誰が負担するのか、もし建物の一部や全部が使えなくなったらどうなるのか、といったルールを見ていきましょう。
雨漏り!エアコン故障!修理は誰がする?【賃貸人の修繕義務】
賃貸人(大家さん)の基本的な義務は、賃借人(借り主)に目的物を使わせ、収益をさせることです。そのため、賃貸人は、賃借物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負っています(民法606条1項)。
例えば、アパートの部屋で雨漏りがした場合や、備え付けのエアコンが故障した場合などは、基本的に賃貸人が修理する義務を負います。
ただし、その修繕が必要になった原因が、賃借人のせい(故意や過失)である場合(例えば、賃借人が壁を殴って穴を開けてしまった場合など)は、賃貸人は修繕義務を負いません。この場合は、賃借人が自分の責任で直す必要があります。
また、賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為(例えば、マンション全体の大規模修繕工事など)をしようとするときは、賃借人はそれを拒むことはできません(忍容義務、民法606条2項)。多少不便でも我慢しなければならない、ということですね。
大家さんが直してくれない!自分で修理してもいい?【賃借人の修繕権】
賃貸人に修繕義務があるといっても、なかなか対応してくれなかったり、緊急で修理が必要だったりする場合もありますよね。そんな時、賃借人はどうすればいいのでしょうか?
2020年4月施行の改正民法で、賃借人が自ら修繕できる権利(修繕権)が明確に規定されました(民法607条の2)。以下のいずれかの場合には、賃借人は自分で修繕することができます。
- 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知したか、または賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
- 急迫の事情があるとき。(例:台風で窓ガラスが割れて雨風が吹き込んでいる、など)
これで、「大家さんに何度もお願いしてるのに全然直してくれない…」という場合や、待ったなしの状況でも、賃借人が自分で業者を手配して修理することが法的に認められるようになりました!これは大きな進歩ですね。
修理代や改良費は請求できる?【費用償還請求権】
賃借人が賃貸借契約に関連して費用を支出した場合、その費用を賃貸人に請求できる場合があります。これを費用償還請求権(ひようしょうかんせいきゅうけん)といい、「必要費」と「有益費」の2種類があります(民法608条)。
- 必要費(ひつようひ):賃借物の保存・維持に必要な費用のことです。
例えば、雨漏りの修理費用、壊れた給湯器の交換費用、水道管の修繕費用などがこれにあたります。賃借人がこれを支出した場合、賃貸人に対して直ちにその全額を請求することができます(民法608条1項)。 - 有益費(ゆうえきひ):賃借物の価値を客観的に高めるために支出した費用のことです。
例えば、賃借人が自己負担で和式トイレを洋式トイレに交換した場合や、性能の良いエアコンを設置した場合などが考えられます。
賃借人が有益費を支出した場合、賃貸借契約が終了した時点で、その価値の増加が現存している場合に限り、賃貸人は賃借人に対して、「実際に支出した金額」または「価値が増加した額」のいずれか賃貸人が選択した方を償還しなければなりません(民法608条2項)。
なお、裁判所は、賃貸人の請求によって、有益費の償還について相当の期限を与える(支払いを猶予する)ことができます。
<必要費と有益費の違い まとめ表>
| 種類 | 内容 | 具体例 | 請求時期 | 請求できる額 |
| 必要費 | 維持・保存に必要な費用 | 雨漏り修理、給湯器交換 | 支出後直ちに | 支出した全額 |
| 有益費 | 物の価値を高める費用 | トイレの洋式化、エアコン設置 | 契約終了時 | 支出額 or 価値増加額 のうち賃貸人が選択 |
台風で一部損壊!地震で住めない!賃料や契約はどうなる?【賃借物の滅失】
もし、借りている建物の一部または全部が、地震や台風などの自然災害(賃借人のせいではない理由)によって壊れたり、使えなくなったりした場合、賃料や契約関係はどうなるのでしょうか?これも民法にルールがあります(民法611条、616条の2)。
- 一部が滅失・使用不能になった場合例えば、借りている2階建ての一軒家が台風で被害を受け、2階部分が全く使えなくなってしまったような場合です。
この場合、それが賃借人のせいでないのであれば、使用できなくなった部分の割合に応じて、賃料はその時点から当然に減額されます(民法611条1項)。賃借人が「減額して!」と請求しなくても、法律上自動的に減額されるんです。
上の例なら、建物の半分が使えないので、賃料も半額になる、というイメージですね。さらに、残った部分だけでは、賃借人が契約した目的(例えば、居住すること)を達成できない場合には、賃借人は契約自体を解除することもできます(民法611条2項)。 - 全部が滅失・使用不能になった場合例えば、建物が火事で全焼してしまったり、地震で倒壊してしまったりして、全く使用できなくなった場合です。この場合、賃貸借契約の目的を達することができなくなるので、賃貸借契約はその時点で当然に終了します(民法616条の2)。特別な手続きは不要です。

賃料が自動的に減額されるのは助かりますね!全部使えなくなったら契約も自動終了、というのも分かりやすいルールです。
又貸しはOK?敷金はいつ返ってくる?【権利譲渡・転貸・敷金・使用貸借】
賃貸借契約には、権利の譲渡や又貸し(転貸)、そして入居時に預ける敷金など、他にも知っておくべき重要なルールがあります。また、賃貸借とよく似た「使用貸借」との違いも見ていきましょう。
友達に部屋を貸したい!勝手にできる?【賃借権の譲渡・転貸】
借りている部屋(賃借物)を、さらに他の人に貸すこと(転貸 、又貸しとも言います)や、借りている権利(賃借権)そのものを他の人に譲り渡すこと(譲渡 )は、原則として賃貸人(大家さん)の承諾がなければできません(民法612条1項)。
もし、賃借人が賃貸人に無断で賃借権を譲渡したり、賃借物を転貸したりした場合、賃貸人は原則として賃貸借契約を解除することができます(民法612条2項)。この解除には、事前に「やめなさい」と催告する必要はありません(無催告解除)。
ただし、ここにも重要な例外(判例)があります!
無断譲渡や無断転貸があったとしても、その行為が賃貸人に対する裏切り行為(背信的行為)とはいえないような特別な事情がある場合には、賃貸人は解除権を行使できない、とされています。これを「信頼関係破壊の法理」といいます。
例えば、
- 賃借人が個人で経営していた事業を法人化し、その法人に賃借権を譲渡した場合
- 賃借人が、同居していた配偶者や親子に部屋を使わせる(転貸する)場合
などは、実質的に利用者が変わらない、あるいは賃貸人が予測できる範囲内の変化であるため、信頼関係を破壊したとは言えず、解除が認められない可能性が高いです。
単に「無断でやった」という事実だけでは解除できず、「賃貸人との信頼関係を壊すほどの裏切り行為だ」と評価できる場合に限って解除できる、という点がポイントです。試験でもよく問われますよ!
なお、賃貸人が譲渡や転貸を承諾する場合、その意思表示は、元の賃借人に対してだけでなく、新しい賃借人や転借人(又借りする人)に対して直接行っても有効です。そして、一度有効に承諾したら、後から「やっぱりやめた」と撤回することはできません。
入居時に払った敷金、どうなるの?【敷金のルール】
アパートなどを借りる際に、「敷金(しききん)」を預けるのが一般的ですよね。この敷金についても、民法にルールが定められています(民法622条の2)。
敷金の定義と目的: 敷金とは、いかなる名目であっても、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭のことです。
簡単に言うと、家賃の滞納があったり、退去時に部屋を汚したり壊したりした場合の修理費用(原状回復費用)などに備えて、あらかじめ預けておく担保金、ということですね。
- 敷金の充当: 賃料の滞納があった場合、賃貸人は敷金をその支払いに充てることができます。しかし、賃借人の方から「滞納した家賃は敷金から引いておいてください!」と請求することはできません。敷金はあくまで契約終了・明渡し時まで賃貸人が確保しておくべきものだからです。
- 賃貸人(オーナー)が変わった場合: 賃貸借の期間中に、賃貸物件が売買されるなどして賃貸人の地位が新しいオーナーに移転した場合、敷金に関する権利義務(預かった敷金を返す義務など)も、当然に新しい賃貸人に承継されます。したがって、賃借人は、契約終了・明渡し時には、新しいオーナーに対して敷金の返還を請求することになります。元の(旧)オーナーは敷金返還義務を免れます。
- 賃借人(借り主)が変わった場合: 賃借人が、賃貸人の承諾を得て適法に賃借権を第三者に譲渡した場合、敷金に関する権利義務は、原則として新しい賃借人には承継されません。敷金に関する契約はあくまで元の賃借人と賃貸人の間のものだからです。したがって、敷金は、譲渡の時点で(または契約終了・明渡し時に)元の(旧)賃借人に返還されるべきものとなります。新しい賃借人は、必要であれば新たに賃貸人に敷金を差し入れることになります。
- 敷金返還の時期: 敷金は、①賃貸借契約が終了し、かつ、②賃借人が賃借物を返還(明け渡し)した時に、賃借人に返還されます。ただし、それまでに生じた未払いの賃料や損害賠償(通常の使用による損耗や経年劣化を除く原状回復費用など)があれば、その額が敷金から差し引かれた(控除された)残額が返還されます。
オーナーチェンジの時と、借り主が変わる時(賃借権譲渡)で、敷金の扱いが異なる点は要注意です!オーナーチェンジなら新オーナーに引き継がれ、賃借権譲渡なら元の借り主に返還(新借り主には引き継がれない)、と覚えましょう。
タダで貸し借りする「使用貸借」って?賃貸借との違いは?
最後に、賃貸借とよく似た契約として「使用貸借(しようたいしゃく)」があります。これは、無償(タダ)で物の貸し借りをする契約のことです(民法593条)。友達からゲームを借りたり、親から車を借りたりするのが典型例ですね。
賃貸借(有償)と使用貸借(無償)は、似ているようで重要な違いがいくつもあります。
- 契約の性質: 賃貸借は有償契約、使用貸借は無償契約です。これが最大の違いです。※2020年の民法改正で、使用貸借も口約束だけで成立する諾成契約になりました(それまでは実際に物を受け取らないと成立しない要物契約でした)。
- 貸主の義務: 無償であるため、使用貸借の貸主は、賃貸借の貸主ほど重い義務を負いません。
- 修繕義務: 原則として負いません。借主が自分で直すか、そのまま使うことになります。
- 担保責任: 目的物に欠陥があっても、原則として責任を負いません。ただし、欠陥を知りながら借主に告げなかった場合は責任を負います(民法596条)。
- 費用負担: 借りた物の通常の必要費(例:借りたカメラの電池代、車のガソリン代など)は、借主が負担しなければなりません(民法595条1項)。
- 契約の終了原因: 使用貸借は、借主が死亡すると、その時点で契約が終了します(民法597条3項)。貸主と借主個人の信頼関係に基づく契約だからです。一方、賃貸借は、賃借人が死亡しても契約は終了せず、相続人に権利義務が引き継がれます。
- 対抗力: 使用貸借権は、賃借権のように登記したり、引渡しによって第三者に対抗したりすることは原則としてできません。非常に弱い権利と言えます。
- 解除: 使用貸借の解除ルールは少し複雑ですが、基本的には、借主はいつでも解除できます。貸主は、期間や目的の定めの有無によって解除できるタイミングが異なります(民法598条)。
<賃貸借と使用貸借の主な違い まとめ表>
| 項目 | 賃貸借 | 使用貸借 |
| 対価 | 有償(賃料あり) | 無償(タダ) |
| 貸主の義務 | 修繕義務あり、担保責任あり | 原則なし |
| 対抗力 | あり(登記、建物登記、引渡し) | 原則なし |
| 終了原因 | 期間満了、解除、目的物滅失等 | 上記に加え、借主の死亡でも終了 |
| 費用負担 | 通常の必要費は賃貸人負担 | 通常の必要費は借主負担 |
無償だから貸主の責任は軽く、借主の権利も弱い、とイメージすると分かりやすいかもしれませんね。
まとめ
お疲れ様でした!今回は、身近な契約である「賃貸借」について、対抗力、修繕、滅失、譲渡・転貸、敷金といった重要論点と、関連する「使用貸借」との違いを詳しく見てきました。
賃貸借は、民法だけでなく借地借家法も関わるため、覚えるべきルールが多い分野ですが、一つ一つのルールを丁寧に確認し、具体的な場面を想像しながら学習すれば、必ず理解が深まります。
- 不動産賃借権の対抗要件は、原則「登記」ですが、土地なら「借地上の建物登記」、建物なら「引渡し」があればOK(借地借家法)。
- 修繕は基本的に賃貸人の義務ですが、賃借人のせいなら不要。賃借人も一定の場合には自ら修繕でき、立て替えた必要費・有益費は請求できます。
- 賃借人のせいでなく一部滅失すれば賃料は当然減額、目的達成不可なら解除も可。全部滅失なら契約は当然終了。
- 賃借権の譲渡・転貸には原則賃貸人の承諾が必要。無断で行っても、背信性がなければ解除できない場合もあります(信頼関係破壊の法理)。
- 敷金は、賃貸人変更(オーナーチェンジ)では新賃貸人に承継されますが、賃借人変更(賃借権譲渡)では新賃借人には承継されません。返還は契約終了・明渡し時です。
- 使用貸借は無償の契約で、借主死亡で終了、対抗力なし、貸主の義務も軽いなど、賃貸借とは多くの違いがあります。

これらのポイントをしっかり押さえて、賃貸借に関する問題を確実に得点できるようにしましょう!権利関係は難しいですが、一つ一つ積み重ねていけば必ず力になります!