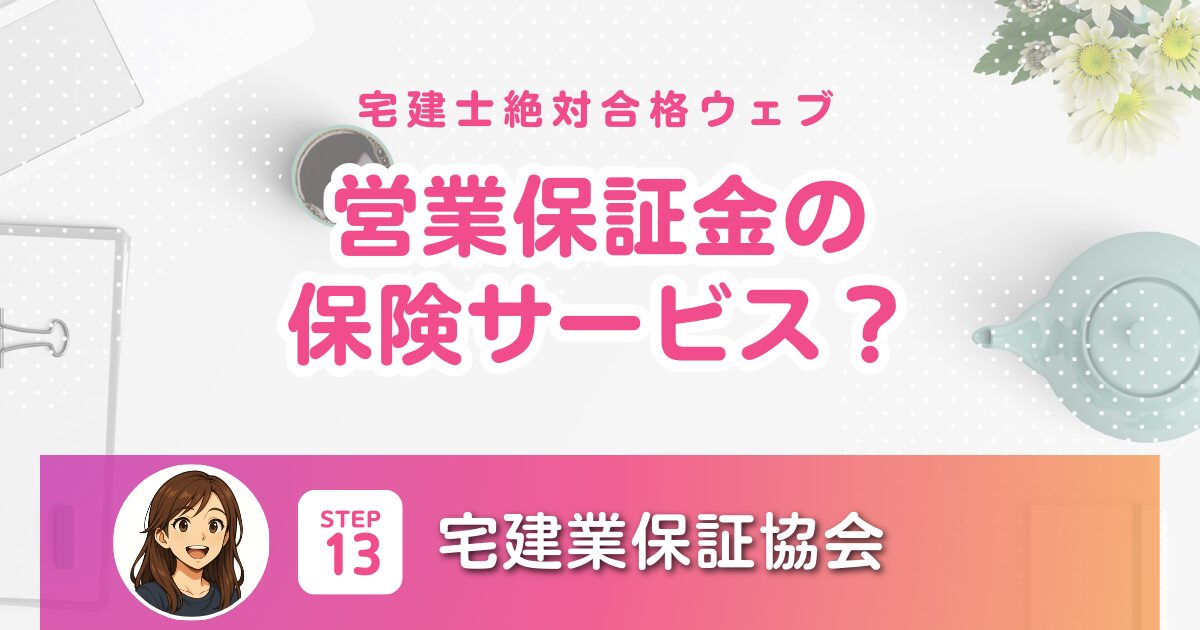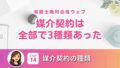宅建業を始めたいけど、営業保証金1,000万円は正直キツイ…初期費用を抑える方法はないの?って思っていませんか? 実は、そんなあなたに朗報! もっと少ない負担で宅建業をスタートできる、もう一つの制度があるんです! それが「弁済業務保証金制度」、通称「保証協会」を利用する仕組みです!
今回は、この保証協会の制度について、営業保証金との違いから、加入手続き、万が一の際の還付や取戻しのルール、さらには保証協会がどんなお仕事をしているのかまで、しっかり解説していきますよ! これを読めば、あなたに合った開業方法が見つかるかも!?

保証協会ってよく聞くけど、実際どんな制度なの? って方も多いはず。今日はその謎をスッキリ解き明かしましょう!
この記事でわかること
- 保証協会(弁済業務保証金制度)の基本的な仕組みとメリット
- 営業保証金制度との具体的な違い(初期費用、手続きなど)
- 保証協会への加入、還付、取戻しに関する手続きの流れと注意点
- 消費者保護だけじゃない!保証協会の様々な業務内容
- 自分にはどっちの制度が合っているかの判断材料
保証協会って何?営業保証金との違いとメリット
開業のハードルを下げる!保証協会の役割
前回解説したように、宅建業を始めるには、原則として「営業保証金」を供託所に預ける必要がありました。でも、本店だけで1,000万円、支店が増えればさらに500万円ずつ…となると、特に新規で開業する方にとっては、かなりの負担ですよね。
「もっと少ない資金で、安心して宅建業を始められるようにできないか?」
そんな声に応えて作られたのが、「宅地建物取引業保証協会(保証協会)」と、そこが運営する「弁済業務保証金制度」なんです!
この制度を使えば、宅建業者は保証協会に比較的少額のお金(弁済業務保証金分担金)を納めるだけで、営業保証金を直接供託する代わりとすることができるんです。つまり、開業時の初期費用をぐっと抑えられるのが最大のメリット!
保証協会は、国土交通大臣から指定を受けた公益法人で、現在「公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会(全宅保証)」と「公益社団法人 不動産保証協会(全日保証)」の2つがあります。宅建業者はどちらか(または両方)に加入することができますよ。
お金の流れを図で理解!制度の全体像
じゃあ、保証協会を使うと、お金の流れはどうなるんでしょうか? 営業保証金の場合と比較しながら見てみましょう。
【営業保証金の場合】
(宅建業者) → [営業保証金(本店1000万+支店500万/箇所)を供託] → (供託所)
【保証協会(弁済業務保証金制度)の場合】
(宅建業者) → [①弁済業務保証金分担金(本店60万+支店30万/箇所)を納付] → (保証協会) → [②弁済業務保証金をまとめて供託] → (供託所)
ポイントは、宅建業者が直接供託所に大金を預けるのではなく、まず保証協会に「分担金」という形で少額を納め、その分担金などを元に、保証協会がまとめて「弁済業務保証金」として供託所に供託する、という二段階になっている点です。
そして、万が一、損害を受けた消費者が弁済を受ける(還付)際も、この保証協会が供託した弁済業務保証金から支払われる、という仕組みになっています。
- 弁済業務保証金分担金: 宅建業者が保証協会に納めるお金(少額)
- 弁済業務保証金: 保証協会が供託所に供託するお金(高額)
この二つの「金」の違い、しっかり区別してくださいね!
どっちを選ぶ?営業保証金と保証協会の比較
ここで、営業保証金制度と保証協会(弁済業務保証金制度)の主な違いを表で整理してみましょう!
<営業保証金と保証協会(弁済業務保証金)の比較表>
| 項目 | 営業保証金制度 | 保証協会(弁済業務保証金制度) | ポイント |
| 初期費用(目安) | 高い(本店1,000万~) | 安い(本店60万~) ※別途加入金等あり | 開業時の資金負担が大きく違う! |
| お金を預ける相手 | 供託所 | 保証協会 | 業者は協会に分担金を納付する |
| 供託する主体 | 宅建業者 | 保証協会 | 供託手続きは協会が代行してくれる |
| 供託物 | 金銭 または 有価証券 | 分担金は金銭のみ! | 保証協会への分担金は現金のみ! |
| 還付限度額 | 供託額(本店1000万ベース) | 営業保証金と同額(本店1000万ベース) | 消費者保護のレベルは同じ! |
| 還付手続き | 被害者 → 供託所 | 被害者 → 協会認証 → 供託所 | 保証協会の「認証」が必要になる |
| 還付後の不足額補充 | 業者 → 供託所 (通知から2週間以内) | 協会 → 供託所、業者 → 協会 (各2週間以内) | 関係者が増え、手続きが少し複雑に |
| 取戻し主体 | 宅建業者 | 保証協会 | 取り戻せるのは供託した保証協会 |
| 取戻し時の公告 | 原則必要(例外あり) | 地位喪失時:必要、事務所廃止時:不要 | 事務所廃止時のルールが違う! |
※保証協会への加入には、分担金の他に別途入会金や年会費等がかかる場合があります。
メリット・デメリット
- 営業保証金:
- メリット:手続きが比較的シンプル。協会の年会費などがかからない。
- デメリット:初期費用が非常に高額。
- 保証協会:
- メリット:初期費用を大幅に抑えられる。協会の研修や情報提供を受けられる。
- デメリット:年会費等がかかる。還付などの手続きに関係者が増える。

どっちが良いかは一概には言えませんが、やっぱり初期費用を抑えたいなら保証協会が魅力的ですよね! でも、手続きの違いもしっかり理解しておくのが大事です!
加入から還付・取戻しまで!保証協会の手続きをマスター
保証協会制度のメリット・デメリットが分かったところで、具体的な手続きの流れを見ていきましょう! 営業保証金とは違う点がたくさんあるので、しっかりチェックしてくださいね!
まずは加入!分担金の納付ルール
保証協会を利用するには、まず協会に加入し、「弁済業務保証金分担金」を納付する必要があります。
- いつ納付する?(新規加入時)
- 保証協会に加入しようとする日(加入前)までに納付します。
- いくら納付する?
- 主たる事務所(本店):60万円
- 従たる事務所(支店):1か所につき 30万円
- 何で納付する?
- 金銭(現金)のみです! ここ、超重要!
- <NG> 営業保証金は有価証券でもOKでしたが、保証協会への分担金は現金払いオンリー! 有価証券は使えません! 試験でよく狙われますよ!
- 事務所を増やしたら?(事務所増設時)
- 支店を増やした場合は、その増設の日から2週間以内に、増やす支店1か所につき30万円の分担金を追加で保証協会に納付する必要があります。期限が「2週間以内」というのもポイントです!
供託は誰がいつ?保証協会の供託義務
宅建業者が保証協会に分担金を納付したら、次は保証協会が動きます。
- 誰が供託する?
- 保証協会です。宅建業者(社員)ではありません。
- いつ供託する?
- 保証協会は、社員(業者)から分担金の納付を受けたら、その日から1週間以内に、その分担金を基にした弁済業務保証金を供託所に供託しなければなりません。
宅建業者としては、保証協会に分担金を払いさえすれば、あとは保証協会が供託手続きをやってくれる、というわけですね。これは楽ちん!
もしもの時の還付!手続きと注意点
保証協会に加入している業者(社員)との取引で損害を受けた場合、被害者は弁済業務保証金から還付を受けることができます。
- 誰が還付を受けられる?
- 保証協会の社員である宅建業者との宅地建物取引に関して損害を受けた人です。
- 注意点①: その業者が保証協会に加入する前の取引によって生じた損害でも、還付の対象になります!
- 注意点②: 営業保証金と同じく、宅建業者は還付請求できません(業者間取引は対象外)。
- いくらまで還付される?(還付限度額)
- ここがビックリポイント! 還付される限度額は、業者が実際に納めた分担金(本店60万、支店30万)の額ではありません!
- なんと、営業保証金制度の場合と同額、つまり、本店なら1,000万円、支店なら500万円/箇所を基準とした額が限度になります!
- <計算例>
- 本店のみの業者(分担金60万円納付)→ 還付限度額 1,000万円
- 本店+支店1つの業者(分担金90万円納付)→ 還付限度額 1,500万円
- 少ない分担金で、万が一の際の補償額は営業保証金と同じレベルが確保されている、ということですね。これも保証協会制度の大きなメリット!
- 還付を受けるための手続きは?
- 営業保証金の場合は、被害者が直接供託所に請求できましたが、保証協会の場合はワンクッション入ります。
- ① まず、還付を受けようとする被害者は、保証協会の認証を受ける必要があります。「確かにこの損害は、この社員との取引で生じたものですね」というお墨付きをもらうイメージです。
- ② その認証書を持って、供託所に還付を請求します。
- <チェック> 営業保証金と違い、保証協会の場合は、まず協会の「認証」が必要になる、という点をしっかり覚えておきましょう!
還付後の流れが複雑!不足額補充の連鎖
さて、無事に還付が行われた後、減ってしまった弁済業務保証金を元に戻す手続きが始まります。ここ、関係者が多くてちょっと複雑なので、流れをしっかり追いましょう!
- 供託所 → 国土交通大臣: 供託所は還付した旨を国土交通大臣に通知します。
- 国土交通大臣 → 保証協会: 国土交通大臣は、その通知内容を保証協会に伝えます。
- 保証協会 → 供託所: 保証協会は、国土交通大臣から通知を受けた日から2週間以内に、還付された額と同じ額の弁済業務保証金を供託所に供託して、穴埋めをしなければなりません。
- 保証協会 → 社員(宅建業者): 同時に、保証協会は、実際に還付に使われたお金(これを「還付充当金」といいます)を、「あなたが原因で還付があったので、この分を協会に納めてください」と、原因となった社員(業者)に通知します。
- 社員(宅建業者) → 保証協会: 通知を受けた社員(業者)は、その通知を受けた日から2週間以内に、指定された還付充当金を保証協会に納付しなければなりません。
もし社員(業者)が還付充当金を納付しなかったら…?
これが大変なことに! 期限(通知から2週間以内)までに還付充当金を納付しないと、その業者は保証協会の社員としての地位を失ってしまいます!
社員の地位を失うということは、保証協会の保護を受けられなくなる、ということ。そうなると、その業者は原則通り、地位を失った日から1週間以内に、自力で営業保証金(本店1,000万円+支店分)を供託所に供託しなければならなくなります! もしこれもできなければ、免許取消しにつながる可能性も…。
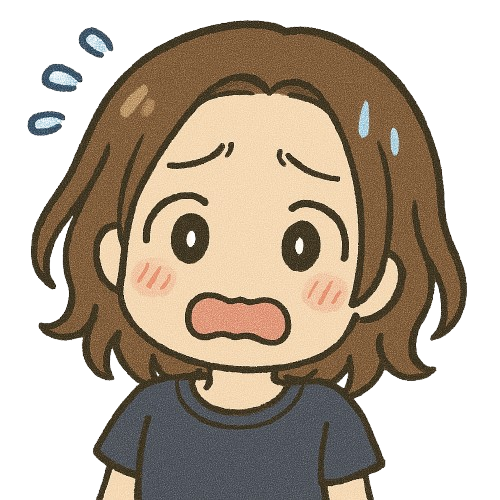
還付があった後の手続き、特に還付充当金の納付は絶対に忘れないようにしないと! 2週間ってあっという間ですからね!
ちなみに、社員が地位を失った場合、保証協会はすぐにその旨を、その業者の免許権者に報告する義務もあります。
お金は戻る?弁済業務保証金の取戻し
次に、保証協会が供託した弁済業務保証金を取り戻すケースです。営業保証金と似ているようで、違う点がありますよ!
- 誰が取り戻す?
- 供託しているのは保証協会なので、取り戻すことができるのも保証協会です。社員(宅建業者)が直接取り戻すことはできません。
- どんな時に取り戻せる?
- 社員(宅建業者)が保証協会の社員としての地位を失ったとき。(例:廃業、除名、還付充当金の未納など)
- 社員(宅建業者)が一部の事務所(支店)を廃止したとき。(その支店分の分担金に対応する保証金を取り戻します)
- 取戻しの手続き(公告ルール)は?
- 社員の地位を失った場合: 保証協会は、6ヶ月以上の期間を定めて公告し、他に還付請求権者がいないか確認してから取り戻します。(営業保証金の原則と同じ)
- 一部の事務所(支店)を廃止した場合: この場合は、公告は不要です! 保証協会は直ちに該当する分を取り戻すことができます。
事務所廃止時の公告ルールが、営業保証金と保証協会で違う点に注意しましょう! 保証協会の方が手続きが早いですね。
説明義務もちょっと違う!
保証協会に加入している社員(業者)が、お客さんに説明しなければいけない内容も、少しだけ増えます。
- 何を説明する?
- ① 加入している保証協会の名称、住所、事務所の所在地
- ② その保証協会が弁済業務保証金を供託している供託所の名称とその所在地
- 営業保証金の場合は②だけでよかったのですが、保証協会の場合は、①の協会の情報もプラスして説明する必要があります。
- いつ、誰に?
- 契約が成立するまでの間に、取引の相手方に説明します。
- 例外は?
- 相手方が宅建業者の場合は、説明を省略できます。(これは営業保証金と同じ)
縁の下の力持ち!保証協会のいろんなお仕事
保証協会は、弁済業務(お金の保証)以外にも、宅建業界の健全な発展のために、いろいろな業務を行っているんですよ。最後に、その主な業務内容を見てみましょう。業務には「必ずやらなければならないこと」と「任意でできること」があります。
これは必須!保証協会の必要的業務
以下の3つは、保証協会が必ず行わなければならない業務です。
- 苦情の解決: 社員(業者)が行った宅建業の取引に関する、お客さんからの苦情(クレーム)の相談に乗り、解決を図ります。
- 研修業務: 宅建士や、宅建業の仕事をしている人・これからしようとする人に対して、必要な知識や能力向上のための研修を行います。
- 弁済業務: これまで見てきた、万が一の際の損害に対する弁済(還付)を行う業務です。
やってくれると助かる!保証協会の任意的業務
こちらは、法律で義務付けられてはいませんが、保証協会が行うことができる業務です。
- 一般保証業務: 手付金の返還保証など、弁済業務とは別の保証を行うことがあります。
- 手付金等の保管業務: 高額になりがちな手付金などを、一時的に安全に預かる業務です。
- 宅地建物取引業の健全な発達を図るために必要な業務: 例えば、一般消費者を対象とした不動産の無料相談所を開設したり、情報提供を行ったりします。
- 研修費用の助成: 社員(業者)が行う研修にかかる費用の一部を助成することもあります。(H29改正で追加)
これらの任意業務があるおかげで、私たちはより安心して不動産取引ができたり、業界全体のレベルアップが図られたりしているんですね。保証協会って、本当に縁の下の力持ち!
まとめ
今回は、保証協会と弁済業務保証金制度について、詳しく見てきました! 営業保証金制度との違いを中心に、理解を深めていただけたでしょうか?
保証協会制度は、初期費用を抑えて宅建業を始められる大きなメリットがある一方、手続きに関わる人が増えたり、独自のルールがあったりします。特に、分担金は金銭のみ、還付には協会の認証が必要、還付後の不足額補充の流れ、取戻しは協会が行い、事務所廃止時は公告不要、説明義務に協会情報が加わる、といった点は、営業保証金との違いとしてしっかり押さえておきたいポイントです。
- 保証協会とは?:少ない初期費用(分担金)で開業できる制度。業者は協会に分担金納付、協会が供託所に供託。
- 分担金ルール:本店60万、支店30万。金銭のみ! 新規加入は加入前、増設は2週間以内。
- 供託ルール:協会が分担金納付から1週間以内に行う。
- 還付ルール:限度額は営業保証金と同じ! 被害者は協会認証→供託所へ請求。還付後は協会・業者ともに2週間以内に不足額補充手続きが必要。怠ると地位喪失→1週間以内に営業保証金供託義務!
- 取戻しルール:協会が取り戻す。地位喪失時は6ヶ月公告、事務所廃止時は公告不要!
- 保証協会の業務:弁済業務のほか、苦情解決、研修(必須業務)、手付金保管など(任意業務)も行う。
どちらの制度を選ぶかは、皆さんの資金状況や事業計画によって変わってくると思います。今回の記事を参考に、ご自身にとって最適な方法を選んで、宅建士としての第一歩を踏み出してくださいね!

保証協会の仕組み、バッチリ理解できましたか? 営業保証金との違いを意識して覚えるのがポイントですよ! 応援しています!