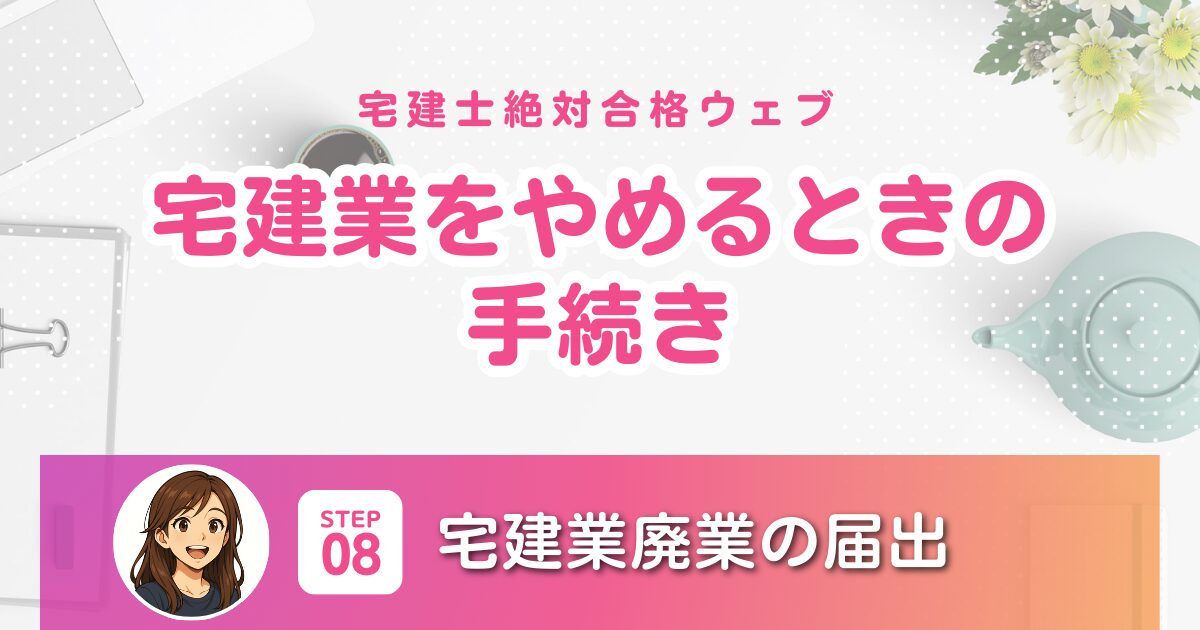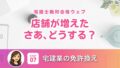宅建業を始めるには、免許申請や事務所の設置など、たくさんの手続きが必要でしたよね。でも、実は事業を「辞める」ときにも、ちゃんとルールに沿った手続きが必要だってご存知でしたか?「もうやーめた!」で終わり、というわけにはいかないんです。
会社がなくなったり、個人事業主の方が亡くなったり、あるいは自ら事業をやめる決断をしたり…様々な理由で宅建業を続けられなくなることがあります。そんな時に必要になるのが「廃業等の届出」です。
また、もし宅建業者さんが亡くなってしまった場合、残された契約はどうなるの?とか、そもそも免許がないのに宅建業をやったり、名前だけ貸したりするのは許されるの?といった疑問も出てきますよね。
この記事では、宅建業を廃業する際などの届出手続きや、特別なルールである「みなし業者」、そして絶対にやってはいけない「無免許営業」や「名義貸し」について、詳しく解説していきます!
この記事でわかること
- 宅建業を辞める際に必要な「廃業等の届出」のルール(いつ・誰が・何を)
- どんな場合に免許が効力を失うのか(失効タイミング)
- 特例ルール「みなし業者」とは何か、何ができるのか
- 絶対にNGな「無免許営業」や「名義貸し」とその重い罰則
宅建業を辞めるとき・辞めざるを得ないときの手続き「廃業等の届出」
宅建業を営んでいた個人や法人が、様々な事情で事業を続けられなくなった場合、その旨を免許を与えてくれた免許権者(都道府県知事または国土交通大臣)に届け出る必要があります。これを「廃業等の届出」と言います。
なぜ届出が必要?廃業等のパターンと手続きのポイント
この届出は、免許権者が「どの業者が、いつ、どんな理由で宅建業を営まなくなったのか」を正確に把握するために、とっても重要なんです。届け出をしないと、もう営業していないはずの業者の情報が残り続けてしまい、混乱の元になりますからね。
届出が必要になる主なケース(事由)と、その際に押さえておくべきポイントは以下の4つです。
- どういった事情で(届出事由)
- いつまでに届け出るか(届出時期)
- 誰が届け出る義務を負うのか(届出義務者)
- いつ免許が効力を失うのか(免許の失効時期)

特に「届出義務者」と「免許の失効時期」は、事由によって異なるので、しっかり区別して覚えるのが重要ですよ!試験でもよく狙われるポイントです!
【一覧表】いつ・誰が・何を届け出る?廃業等の事由別まとめ
では、具体的にどんなケースで、誰が、いつまでに届け出て、いつ免許が失効するのか、一覧表で見てみましょう!
| 届出が必要になる事情 (届出事由) | いつまでに届け出る? (届出時期) | 誰が届け出る義務がある? (届出義務者) | いつ免許が効力を失う? (失効時期) |
|---|---|---|---|
| 死亡 (個人業者の場合) | 死亡の事実を知った日から30日以内 | 相続人 | 死亡した時 |
| 合併 により法人が消滅した場合 | 合併の日から30日以内 | 消滅した法人の元代表役員 | 合併した時 |
| 破産手続開始の決定 を受けた場合 | 破産手続開始決定の日から30日以内 | 破産管財人 | 届出があった時 |
| 法人が解散 した場合 (合併・破産除く) | 解散の日から30日以内 | 清算人 | 届出があった時 |
| 宅建業を廃止 した場合 | 廃業の日から30日以内 | 廃業した個人 または 法人の代表役員 | 届出があった時 |
※注意: 届出期間はすべて「30日以内」です!これは共通なので覚えやすいですね!

届出義務者が、事由によって「相続人」「元代表役員」「破産管財人」「清算人」と変わるのがポイントですね。それぞれの立場の人に届出の義務がある、ということです。
いつ免許は効力を失う?失効タイミングの違いに注意!
もう一つの重要な違いが、「免許がいつ効力を失うか」です。
- 死亡 や 合併消滅 の場合は、その事実が発生した「死亡時」「合併時」に、免許は自動的に効力を失います。届出をする前に、もう免許はなくなっているんですね。
- 一方で、破産、解散、廃業 の場合は、届出義務者が「届出をした時」に、初めて免許が効力を失います。届出がされるまでは、形式上はまだ免許が有効な状態、ということです。
この失効タイミングの違い、すごく大事です!特に「死亡」と「合併」は、届出を待たずに即失効!と覚えておきましょう!
失効タイミングのまとめ
- 即時失効グループ: 死亡、合併消滅 → 事実発生時に失効
- 届出時失効グループ: 破産、解散、廃業 → 届出時に失効
もし届出を忘れたらどうなる?(注意喚起)
この廃業等の届出は、法律で定められた義務です。もし、正当な理由なく届出を怠った場合、過料(罰金のようなもの)などのペナルティが科される可能性があります。
うっかり忘れてた!じゃ済まされないんですね…。関係者の方は、責任をもって期限内に手続きを行う必要がありますね。
また、届出がされないと、行政側もその業者が営業を続けているのか判断できず、適切な管理ができなくなってしまいます。業界全体の信頼性にも関わることなので、ルールはしっかり守りましょう!
特例ルール「みなし業者」と絶対NGな禁止行為
さて、宅建業者が事業を続けられなくなった場合の手続きを見てきましたが、ここからは、それに関連する特別なルールや、絶対にやってはいけない禁止行為について解説します。
免許は引き継げない!でも相続人はどうなる?「みなし業者」とは
まず大前提として、宅建業の免許は、その免許を受けた特定の個人や法人に対して与えられるものなので、他人に譲渡したり、相続したりすることはできません。
例えば、お父さんが個人で営んでいた宅建業を、息子さんがそのまま引き継ぐ、ということは原則できないんですね。息子さんが宅建業をやりたいなら、自分で新しく免許を取得する必要があります。
でも、ここで一つ問題が…。もし、個人事業主の宅建業者さんが、契約を結んだ後、物件の引き渡しや登記手続きが終わる前に亡くなってしまったら、契約相手(買主さんなど)は困ってしまいますよね?「契約したのに、手続きが進まない!」なんてことになったら大変です。
そこで登場するのが「みなし業者」という特別なルールです!
宅建業者が死亡した場合、その相続人は、「亡くなった業者が生前に結んだ契約に基づく取引を結了(けつりょう)させる目的の範囲内」においては、宅建業者とみなされて、必要な業務を行うことができるんです。
「みなし業者」のポイント
- 対象者: 死亡した宅建業者の相続人
- 目的: 生前に結ばれた契約の後始末(取引の結了)のためだけ
- 効果: その目的の範囲内で、宅建業者とみなされる
みなし業者ができること・できないこと
「宅建業者とみなされる」と言っても、何でもできるわけではありません。あくまで「取引を結了させる目的の範囲内」に限られます。
みなし業者(相続人)ができること
- 亡くなった業者が売買契約を結んでいた物件の引き渡しを行う。
- 契約に基づく登記手続き(所有権移転など)を行う。
- 契約に必要な残代金の受領などを行う。
みなし業者(相続人)ができないこと
- 新しく不動産の売買契約や賃貸借契約の仲介をする。
- 新しく自らが売主となる契約を結ぶ。
- 亡くなった業者の名義で広告を出す。
つまり、あくまで「やりかけの仕事の後片付け」をするための特例なんですね!新しい営業活動は一切できません。ここ、しっかり区別しておきましょう!
法人が合併で消滅した場合や、破産・解散した場合も、同様の考え方で、消滅法人の元代表役員や破産管財人、清算人などが、取引を結了させる目的の範囲内で業務を行うことがあります。これも広い意味での「みなし業者」と言えるかもしれませんね。
絶対ダメ!「無免許営業」とその重い罰則
これはもう、当たり前のことですが、宅建業の免許を受けずに宅建業を営むこと(=無免許営業)は、絶対に禁止されています!
宅建業は、高額な取引を扱い、専門的な知識も必要とされるため、免許制度によって一定の質と信頼性を担保しているわけです。無免許で勝手に営業されたら、消費者の保護も何もあったもんじゃありませんよね。
もし、このルールを破って無免許営業をした場合、非常に重い罰則が待っています!
- 罰則: 3年以下の懲役 または 300万円以下の罰金 (場合によっては両方が科されることも!)

懲役刑もあるなんて…!本当に厳しい罰則ですね。軽い気持ちで手を出していいものでは絶対にありません!
無免許での表示や広告も禁止!
さらに、無免許の人は、実際に営業活動をしなくても、「自分は宅建業を営んでいる」かのような表示をしたり、宅建業を営む目的で広告を出したりすることも禁止されています。
例えば、免許がないのに名刺に「○○不動産」と書いたり、ウェブサイトで「不動産売買の仲介します!」と宣伝したりするような行為ですね。
これに違反した場合も、罰則があります。
- 罰則: 100万円以下の罰金
無免許は、営業するのもダメ!それっぽい表示や広告をするのもダメ!ってことですね。
自分の名前を貸すのもNG!「名義貸し」の禁止と罰則
免許を持っている宅建業者さんにも、絶対に守らなければならないルールがあります。それが「名義貸しの禁止」です。
宅建業者は、自分の名義(会社名や個人事業主としての名前)を使って、他人に宅建業を営ませてはいけません。
- 例: 宅建業者Aさんが、免許を持っていない友人Bさんに「俺の名前(A)を使って、不動産の仕事していいよ」と言って、Bさんが実際にAさん名義で取引をするようなケース。

これも、無免許営業を助長する行為であり、免許制度の根幹を揺るがす悪質な行為とみなされます。だから、厳しく禁止されているんですね。
名義貸しをした場合も、無免許営業と同じく、非常に重い罰則が科せられます。
- 罰則: 3年以下の懲役 または 300万円以下の罰金 (場合によっては両方が科されることも!)
名義を貸した側(宅建業者)も、無免許で営業した側と同じくらい重い罪になるんですね!
名義貸しによる表示・広告も罰則対象!
さらに、宅建業者は、自分の名義を使って、他人に「宅建業を営む旨の表示」をさせたり、「宅建業を営む目的の広告」をさせたりすることも禁止されています。
- 例: 宅建業者Aさんが、無免許のBさんに「A社の名前でチラシ作って、お客さん集めていいよ」と許可するようなケース。
これに違反した場合も、罰則があります。
- 罰則: 100万円以下の罰金
名義貸しも、実際に営業させるのもダメ!表示や広告をさせるのもダメ!ということですね。どちらも厳しい罰則があるので、絶対にやめましょう。
まとめ
今回は、宅建業を辞める際の「廃業等の届出」や、特別なルールである「みなし業者」、そして絶対にやってはいけない「無免許営業」と「名義貸し」について解説しました!事業の終わり方や、禁止されている行為について、しっかり理解していただけたでしょうか?
宅建業は、始める時も、そして終わる時も、きちんとルールに則った手続きが必要です。そして、免許制度の信頼を守るためにも、無免許営業や名義貸しといった不正行為は絶対に許されません。コンプライアンス意識を高く持って、健全な業界を目指していきたいですね!
最後に、今日のポイントをまとめておきましょう!
- 廃業等の届出:
- 死亡、合併、破産、解散、廃業などの場合に、30日以内に届出が必要(義務)。
- 届出義務者や免許の失効時期は事由によって異なるので注意!
- 死亡・合併 → 事実発生時に失効
- 破産・解散・廃業 → 届出時に失効
- みなし業者:
- 宅建業者が死亡した場合など、相続人が取引結了目的の範囲内で宅建業者とみなされる特例。
- 新しい契約や営業活動はできない!
- 無免許営業の禁止:
- 免許なく宅建業を営むことは絶対禁止!
- 罰則:3年以下の懲役 or 300万円以下の罰金。
- 無免許での表示・広告も禁止(罰則:100万円以下の罰金)。
- 名義貸しの禁止:
- 宅建業者が他人に自分の名義を使わせて宅建業を営ませることは禁止!
- 罰則:3年以下の懲役 or 300万円以下の罰金。
- 名義を使わせて表示・広告させることも禁止(罰則:100万円以下の罰金)。

これらのルールは、宅建試験でも頻出の重要項目です。しっかり復習して、知識を定着させてくださいね!応援しています!