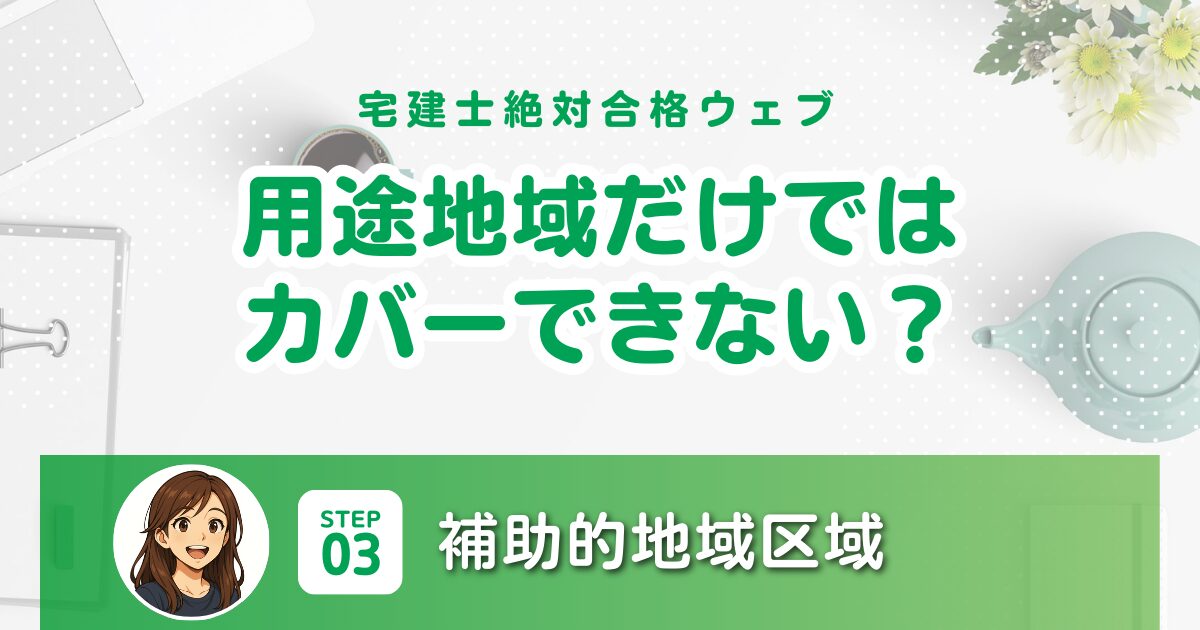こんにちは! 不動産会社勤務の宅建士です。前回は用途地域について学びましたが、今回はその用途地域をさらに補完する役割を持つ「補助的地域地区」について解説していきますね!
「高度地区」と「高度利用地区」って名前が似てるけど何が違うの? 「特別用途地区」と「特定用途制限地域」もややこしい…。「高層住居誘導地区」ってどこに指定されるの? などなど、補助的地域地区も種類が多くて、それぞれの違いやルールを覚えるのが大変!と感じていませんか?
たしかに、これらの地域地区は、用途地域ほどメジャーではないかもしれませんが、街づくりにおいて重要な役割を果たしており、宅建試験でもしっかり出題されるポイントなんです。用途地域だけでは対応しきれない、より細かな土地利用のコントロールや、特定の目的(景観保護、再開発促進、高層住宅誘導など)を達成するために定められています。
この記事では、そんな補助的地域地区の中から、特に試験で問われやすい「高度地区」「高度利用地区」「高層住居誘導地区」「特定街区」「特別用途地区」「特定用途制限地域」「風致地区」をピックアップし、それぞれの目的、指定される場所、主なルールなどを分かりやすく解説していきます。

この記事を読めば、各地区の違いが明確になり、複雑なルールもスッキリ整理できるはずです!
この記事でわかること
- 補助的地域地区とは何か、その役割
- 高度地区と高度利用地区の違い(高さ制限 vs 容積率・建ぺい率等)
- 特別用途地区と特定用途制限地域の違い(用途地域内 vs 用途地域外)
- 高層住居誘導地区が定められる用途地域と容積率のルール
- 特定街区や風致地区の目的と特徴
高さ・利用度・用途をコントロール!高度地区・高度利用地区・特別用途地区・特定用途制限地域
まずは、建物の高さや土地の利用度、そして用途地域のルールを補完・調整する役割を持つ4つの地域地区を見ていきましょう。名前が似ているものもあるので、違いをしっかり意識してくださいね。

まずは基本の4つから!それぞれの役割の違いがポイントですよ。
【高さのルール】高度地区とは?最高限度と最低限度のポイント
高度地区とは、用途地域内において、市街地の環境を維持したり、土地利用を増進したりするために、建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区のことです。
<目的>
- 最高限度を定める場合:例えば、低層住宅が建ち並ぶエリアで、その良好な住環境を守るために「これ以上高い建物は建てないでね」と制限する場合(日照や通風の確保など)。
- 最低限度を定める場合:例えば、駅前などの商業地で、土地の有効活用を促すために「ある程度の高さの建物を建ててね」と誘導する場合。
<ポイント>
・あくまで用途地域が定められている場所に追加で指定されるルールです。
・制限するのは「高さ」です。
・高さの「最高限度」または「最低限度」のどちらか一方、あるいは両方を定めることができます。「両方定めなければならない」わけではありません!
<NG ひっかけ注意!>
・「高度地区では容積率を定める」→ × (高さを定める地区です)
・「高度地区では高さの最高限度と最低限度を定めなければならない」→ × (どちらか一方でもOK)

高さの上限だけじゃなく、下限を決めることもあるんですね!
【土地のポテンシャルを引き出す】高度利用地区とは?再開発を促進する仕組み
高度利用地区とは、用途地域内において、市街地の土地を合理的かつ健全に高度利用し、都市機能を更新(リニューアル)するために定められる地区です。
現状はあまり有効活用されていないけれど、ポテンシャルの高いエリア(駅前など)で、細分化された土地をまとめて、大きなビルや商業施設などを建てて再開発を進めたい!というような場合に指定されます。
<目的&制限内容>
土地の高度利用を図るため、以下のような制限を定めます。
- 容積率の最高限度および最低限度:単に上限だけでなく、ある程度の規模の建物を建てるように下限も定めます。
- 建ぺい率の最高限度:敷地いっぱいに建物を建てられるように、建ぺい率の制限が緩和されることが多いです。(※建築基準法の前面道路幅員による容積率・建ぺい率制限は適用されません)
- 建築面積の最低限度:小さすぎる建物が建つのを防ぎ、土地の共同化・大規模化を促します。
- 壁面の位置の制限:建物の壁を道路境界線から後退させるなどして、歩行者空間や空地を確保します。
<ポイント>
・これも用途地域が定められている場所に追加で指定されます。
・目的は「土地の高度利用」と「都市機能の更新」です。
・制限するのは「容積率(最高・最低)」「建ぺい率(最高)」「建築面積(最低)」「壁面の位置」などです。
「高さ」の最高限度や最低限度を直接定める地区ではありません。(容積率の制限によって、結果的に高さがコントロールされることはあります)。さきほどの「高度地区」と混同しないようにしましょう!

高度地区は「高さ」、高度利用地区は「土地利用の密度や効率」をコントロールするんです!
【用途地域のルールを微調整】特別用途地区とは?用途地域との関係性がカギ
特別用途地区とは、用途地域内において、その地区の特性(例えば、文教地区、観光地区、研究開発地区など)にふさわしい土地利用を進めたり、環境を保護したりするために、ベースとなる用途地域の建築制限(用途制限)を、地方公共団体の条例によって、さらに強化したり、緩和したりする地区のことです。
・必ず「用途地域内」に定められます。用途地域が指定されていない場所に、特別用途地区だけが単独で指定されることは絶対にありません!これが最大のポイントです。
・役割は、用途地域のルールを、地域の実情に合わせて「カスタマイズ(微調整)」することです。
<具体例>
・例えば、「第二種住居地域」だけど、ここは特に教育施設が多いから、風俗店やパチンコ店などは条例で禁止しよう(制限を強化)。
・例えば、「準工業地域」だけど、ここはアニメ関連の企業を集積させたいから、スタジオや展示場などを建てやすくしよう(制限を緩和)。
「特別用途地区」と「特別用途地域」、似ていますが正しくは「地区」です。ただ、もし試験で間違えて覚えていても、意味が通じれば得点できることが多いので、そこまで神経質にならなくても大丈夫ですよ(笑)。正確に覚えるに越したことはないですけどね!
【用途地域がない場所のルール】特定用途制限地域とは?特別用途地区との違い
特定用途制限地域とは、用途地域が定められていない土地(非線引都市計画区域または準都市計画区域)において、その地域の良好な環境を守るために、特定の好ましくない建築物(例:騒音や集客が大きい施設など)の建築を、地方公共団体の条例によって制限する地域のことです。
<ポイント>
・「用途地域が定められていない」場所に指定されるのが、特別用途地区との決定的な違いです!
・役割は、用途地域という網羅的なルールがない場所で、ピンポイントで問題となりそうな特定の建物の建築だけを「制限」することです。特別用途地区のように制限を「緩和」する機能はありません。
<具体例>
・用途地域が定められていない郊外の集落で、良好な住環境を守るために、パチンコ店や大規模な工場などの建築を条例で制限する。
<チェック>
・特別用途地区 → 用途地域内で、制限を強化または緩和
・特定用途制限地域 → 用途地域外(非線引・準都市計画区域)で、特定の用途を制限
この違いをしっかり区別しましょう!こちらも「地域」と「地区」を間違えやすいですが、意味を理解していれば大丈夫です。

場所(用途地域内か外か)と機能(緩和もあるか、制限だけか)が違うんですよ。
特定の目的で街を誘導・保全!高層住居誘導地区・特定街区・風致地区
次に、特定の目的、例えば高層住宅の建設を促したり、大規模な再開発を行ったり、あるいは自然景観を守ったりするために定められる3つの地域地区を見ていきましょう。
【タワマンを呼び込む?】高層住居誘導地区とは?定められる場所の限定ルール
高層住居誘導地区とは、住居と住居以外の用途(商業・業務機能など)を適切にミックスさせ、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するために定められる地区です。
・バブル崩壊後などに都心から郊外へ移った人々を呼び戻し、職住近接(職場と住まいが近いこと)を実現する。
・都心部などの利便性の高い地域で、土地の有効活用を図りつつ、良好な高層住宅の供給を促進する。
この地区では、容積率の最高限度や建ぺい率の最高限度、敷地面積の最低限度などが定められます。また、高層住宅の建設を促すために、容積率制限や斜線制限などが緩和される特例があります。
<試験最重要ポイント!指定できる場所>
高層住居誘導地区は、どこにでも指定できるわけではありません。以下の用途地域のうち、都市計画で定められた容積率が400%または500%の区域内に限られます。
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 準工業地域
逆に、以下の用途地域には定めることができません。
- 第一種・第二種低層住居専用地域
- 第一種・第二種中高層住居専用地域
- 田園住居地域
- 商業地域
- 工業地域
- 工業専用地域

えっ、中高層住居専用地域にも定められないんですね!これは要注意!
低層・中高層の「専用」地域や、商業・工業系の制限の強い地域には定められない、と覚えましょう。特に「中高層住居専用地域」は引っかかりやすいので注意が必要です!
【超高層ビル街の特別ルール】特定街区とは?一般的な規制が適用されない?
特定街区とは、市街地の整備改善を図るために、街区(道路などで囲まれた一区画)単位で、建築物の容積率、高さの最高限度、壁面の位置を一体的に定める制度です。
新宿副都心や、横浜のみなとみらい21地区のような、超高層ビルが建ち並ぶエリアを想像してください。ああいった大規模な再開発プロジェクトなどで活用されることが多いです。
特定街区内では、建築基準法で定められている一般的な形態規制(建ぺい率、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限など)は適用されません!
その代わりに、個別の街区ごとに定められる容積率、高さ、壁面の位置の制限に従うことになります。これにより、画一的な規制にとらわれず、自由度の高い、まとまりのある都市空間を創り出すことが可能になります。
特定街区=超高層ビル街=一般的な高さ制限などのルールは適用除外、と覚えましょう!
【街の自然美を守る】風致地区とは?京都嵐山をイメージ!
風致地区とは、都市の中にある自然の景観や趣のある場所(これを「風致」といいます)を維持・保全するために定められる地区です。
歴史的な庭園、由緒ある神社仏閣の境内地、水辺や樹林地など、自然の美しさや趣を大切にしたいエリアです。ユーザー提供情報にもあった京都の嵐山などが代表例ですね。
都市の貴重な自然景観を守るため、風致地区内では、地方公共団体(都道府県または市町村)が定める条例によって、以下のような行為が制限されます。
- 建築物の建築(高さ、デザイン、色彩などが規制されることも)
- 宅地の造成、土地の形質の変更
- 木竹の伐採
- 土石類の採取
- 屋外での物の堆積 など
<ポイント>
・目的は「都市の風致(自然景観・趣)の維持」です。
・具体的な規制内容は、個別の地方公共団体の条例で定められます。
指定権者は地方公共団体ですが、条例制定の主体が都道府県か市町村かは、区域の規模等によって決まる場合がありますが、宅建試験レベルでは「地方公共団体の条例で規制される」と覚えておけば十分でしょう。
まとめ
今回は、用途地域を補完する様々な「補助的地域地区」について解説しました。高度地区、高度利用地区、特別用途地区、特定用途制限地域、高層住居誘導地区、特定街区、風致地区と、たくさんの種類がありましたが、それぞれの目的と特徴、そして特に注意すべきポイント(指定場所や制限内容の違いなど)は掴めたでしょうか?
これらの地域地区は、用途地域だけでは実現できない、よりきめ細やかな街づくりや、特定の政策目的(再開発、高層化、景観保護など)を達成するために重要な役割を担っています。宅建試験でも、それぞれの地区の定義やルールが問われますので、しっかり復習しておきましょう。
最後に、今回学んだ補助的地域地区のポイントをまとめます。
- 高度地区:用途地域内で、高さの最高限度または最低限度を定める。
- 高度利用地区:用途地域内で、容積率(最高・最低)、建ぺい率(最高)、建築面積(最低)、壁面位置等を定め、土地の高度利用を促進。高さ制限は直接定めない。
- 特別用途地区:用途地域内で、条例により用途制限を強化または緩和。地域の特性に合わせたカスタマイズ。
- 特定用途制限地域:用途地域が定められていない土地で、条例により特定の用途を制限。環境保全が目的。
- 高層住居誘導地区:特定の用途地域(住居系・近隣商業・準工業)で容積率400/500%の区域に定め、高層住宅建設を誘導。容積率・斜線制限緩和あり。
- 特定街区:街区単位で容積率・高さ最高限度・壁面位置を定め、大規模再開発を促進。一般的な形態規制は適用除外。
- 風致地区:都市の自然景観・趣(風致)を維持するため、地方公共団体の条例で建築等を制限。

似たような名前の地区の違いや、指定できる場所のルールなどを中心に、繰り返し確認して知識を定着させてくださいね。頑張りましょう!