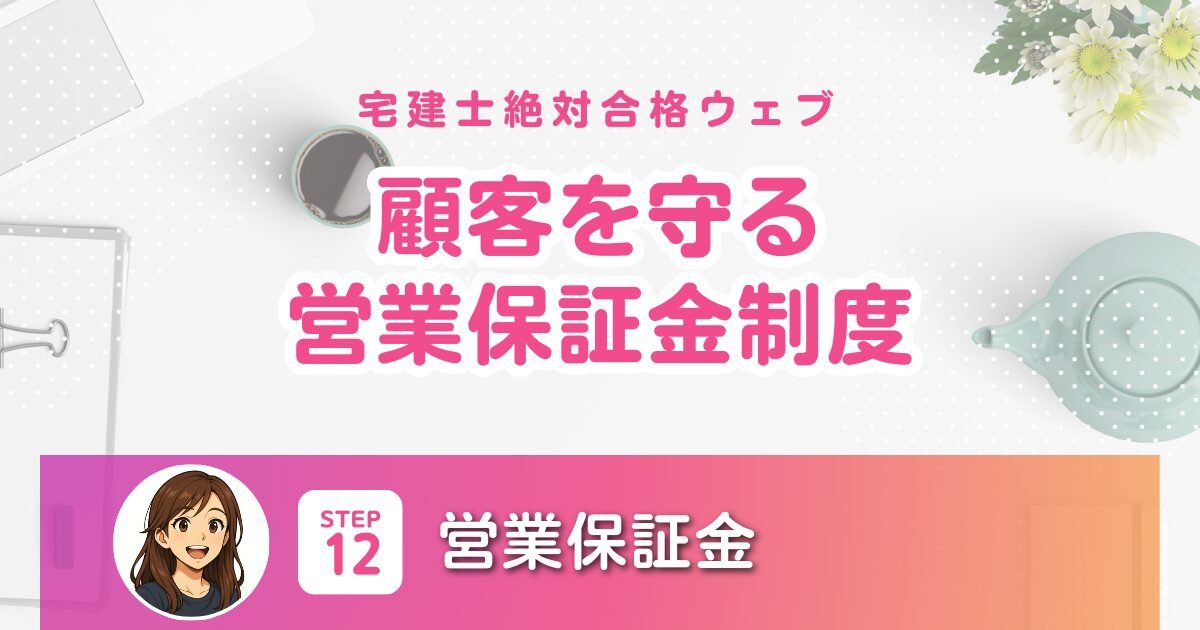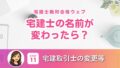宅建業を始めるには『営業保証金』が必要って聞くけど、それって一体何なの? いくら必要なの? どんな手続きがいるの?って疑問だらけですよね? 宅建業法の中でも、この営業保証金は絶対に避けて通れない、超・重要テーマなんです! しっかり理解しておかないと、そもそも業務を開始できなかったり、後々トラブルになったりすることも…。
そこで今回は、宅建業の運営に不可欠な「営業保証金」について、その目的から具体的な供託ルール、さらには事務所が増えたり移転したりした場合の手続き、万が一の際の還付や取戻しまで、まるっと分かりやすく解説していきますよ!

営業保証金って、言葉は聞くけど中身は複雑…って思われがち。でも大丈夫! ポイントを押さえれば、しっかり理解できますからね!
この記事でわかること
- 営業保証金がなぜ必要なのか、その目的と仕組み
- 営業保証金の供託に関する基本ルール(金額、場所、方法など)
- 事務所の新設・移転、供託物の変更など、ケース別の手続き方法
- 消費者保護の要! 営業保証金の還付手続きの流れと注意点
- 営業保証金を取り戻せるケースとその手続きについて
万が一に備える!営業保証金制度の基本をマスターしよう
なんで必要?営業保証金制度の目的と仕組み
まず、そもそも「営業保証金」って、なんで必要なのでしょうか?
不動産取引って、扱う金額がとっても大きいですよね。もし、宅建業者のミス(過失)やルール違反でお客さん(一般消費者)が高額な損害を被ってしまった場合、当然、その損害を補償してもらわないといけません。
でも、もしその宅建業者が「ごめん、お金ないんだ…」ってなったら、被害を受けたお客さんは泣き寝入りするしかない…なんてことになりかねません! それじゃあ、安心して取引なんてできませんよね。
そこで登場するのが「営業保証金制度」です!
これは、宅建業者が業務を開始する前に、あらかじめ「供託所」という国の機関にお金を預けておく(これを「供託」と言います)制度なんです。
この仕組みがあることで、万が一、宅建業者との取引で損害を受けた消費者は、業者がお金を払えなくても、この供託所から一定の範囲内でお金の支払い(弁済)を受けることができるんです。まさに、消費者を守るためのセーフティーネット、というわけですね!
供託所は、法務局やその支局、出張所などにあることが多いです。皆さんの街にもきっとありますよ!
いくら、どこに、何で?供託の基本ルールをチェック!
じゃあ、具体的にどんなルールで供託するのか、基本をしっかり押さえましょう!
- 誰が供託するの?(供託義務者)
- 宅地建物取引業者です。これから宅建業を営もうとする会社や個人事業主ですね。
- どこに供託するの?(供託場所)
- 主たる事務所(本店)の最も近くにある供託所です。
※ここ、すごく大事! 支店がどこにあろうと、供託するのは必ず「本店」の最寄りの供託所なんです! 試験でもよく問われますよ!
- 主たる事務所(本店)の最も近くにある供託所です。
- いくら供託するの?(供託金の額)
- 主たる事務所(本店):1,000万円
- 従たる事務所(支店):1か所につき 500万円
<計算例>- 本店のみの場合 → 1,000万円
- 本店+支店1つの場合 → 1,000万円 + 500万円 = 1,500万円
- 本店+支店3つの場合 → 1,000万円 + (500万円 × 3) = 2,500万円
- 何で供託するの?(供託方法)
- 金銭(現金)はもちろんOK!
- または、一定の有価証券でも供託できます。ただし、有価証券の種類によって評価額が変わるので注意が必要です!
有価証券の種類と評価割合の比較表
| 有価証券の種類 | 評価割合 (額面金額に対して) | 例 |
| 国債証券 | 100% | 額面1,000万円の国債 → 1,000万円として評価 |
| 地方債証券、政府保証債券 | 90% | 額面1,000万円の地方債 → 900万円として評価 |
| 国土交通省令で定める有価証券(※) | 80% | 額面1,000万円の鉄道債券 → 800万円として評価 |
| ※株券や手形、 小切手などは認められません! | – | 不動産投資信託(REIT)の 投資証券なども対象外です。 |
(※)国土交通省令で定める有価証券には、鉄道債券や電信電話債券、道路債券など、公共性の高いものが多いですね。ちょっとマニアックですが、過去問で見かけることもあります。

有価証券だと、額面通りに評価されないものがあるのがミソですね! 特に地方債や政府保証債が90%っていうのは覚えておきたい数字です!
もし供託を忘れたら…?免許が危ない!
この営業保証金の供託は、宅建業を始めるための必須条件! もし、免許を受けたのに供託を怠っていたら、どうなるんでしょうか?
- まず、免許を受けた日から3ヶ月以内に、「ちゃんと供託しましたよ!」っていう届出を免許権者(都道府県知事 or 国土交通大臣)にしないといけません。
- もし、3ヶ月経っても届出がない場合、免許権者は「早く届け出なさい!」と催告(注意喚起)をしなければなりません。(これは義務!)
- その催告が届いてから、さらに1ヶ月以内にやっぱり届出がない場合…免許権者は、その業者の免許を取り消すことができます。
注意! 免許の取消しは「任意」!
催告は「しなければならない」義務ですが、その後の免許取消しは「することができる」任意なんです。つまり、必ず取り消されるわけではないけれど、取り消される可能性がある、ということですね。この「義務」と「任意」の違い、しっかり区別してください!
ケース別!営業保証金の手続きいろいろ
さて、基本ルールを押さえたところで、次は具体的なケースごとに必要な手続きを見ていきましょう! 業務を続けていると、いろんな変化がありますからね。
支店が増えた!事務所新設・増設時の手続き
事業が順調で、新たに支店を出すことになった! おめでとうございます! でも、手続きを忘れちゃいけません。
- 追加供託: 新しい支店1つにつき、500万円の営業保証金を追加で供託する必要があります。
- 供託場所: これも大事! 追加の供託も、本店(主たる事務所)の最寄りの供託所にします。新しくできた支店の最寄りじゃないですよ!
- 届出: 追加で供託したら、遅滞なく、その旨を免許権者に届け出る必要があります。この時、供託したことを証明する「供託書正本の写し」を添付するのを忘れずに!
本店お引越し!営業保証金の保管替えって?
今度は、本店(主たる事務所)が引っ越して、最寄りの供託所が変わってしまった場合です。この場合は、営業保証金を移し替える手続きが必要になります。これを「保管替え」と言います。
手続きの方法は、もともと何を供託していたかによって、2パターンに分かれます。
- パターン①:金銭のみで供託していた場合
- この場合はシンプル! 今までの供託所に対して、「新しい本店最寄りの供託所に、預けてあるお金を移してください」と保管替えの請求をします。
- パターン②:「有価証券のみ」または「有価証券+金銭」で供託していた場合
- こっちがちょっと複雑! 有価証券が含まれている場合は、保管替えの請求はできません。
- 代わりに、まず移転後の新しい本店最寄りの供託所に、必要な額(本店分1,000万円+支店分)を新たに供託し直します。これを「二重供託」と言います。一時的に、古い供託所と新しい供託所の両方にお金がある状態になるわけですね。
- そして、新しい供託所に供託した後で、古い供託所に預けてあった営業保証金を取り戻します。(取戻しの手続きは後で詳しく説明しますね!)
有価証券が含まれていると「二重供託」になる! ここ、しっかり覚えておきましょう! 金銭だけなら簡単な保管替え、有価証券が絡むと二重供託が必要、と覚えてくださいね。
- 届出: 保管替えの手続き(金銭のみの場合)や、二重供託の手続き(有価証券含む場合で新たに供託した後)が完了したら、遅滞なく、その旨を免許権者に届け出る必要があります。これも供託書正本の写しを忘れずに!
供託物をチェンジ!営業保証金の変換とは
「今は現金で1,000万円供託しているけど、会社の資金繰りのために一部を国債に変えたいな…」なんてこともあるかもしれません。このように、供託している営業保証金の種類を変更することを「営業保証金の変換」と言います。
これも可能なんですが、一つだけ重要な注意点があります! それは…
変換前と変換後の「評価額」を同じか、それ以上にしなければならないということです!
例えば、現金1,000万円(評価額1,000万円)を供託している業者が、これを額面1,000万円の地方債に変えたい、と考えたとします。
でも、地方債の評価割合は90%でしたよね? つまり、額面1,000万円の地方債の評価額は900万円にしかなりません。これだと、必要な1,000万円に100万円足りない!
なので、この場合は、
「額面1,000万円の地方債(評価額900万円)」+「現金100万円(評価額100万円)」
という組み合わせで新たに供託し、もともと供託していた現金1,000万円を取り戻す、という形になります。
<計算例>
現金1,000万円(評価額1,000万円)
↓ 変換
額面1,000万円の地方債(評価額900万円)+ 現金100万円(評価額100万円)= 合計評価額1,000万円
- 届出: 変換のために新たに供託をしたら、これも遅滞なく、免許権者に届け出る必要があります。供託書正本の写しを忘れずに!
被害者を救済!営業保証金の還付手続きの流れ
さて、営業保証金制度の最も重要な役割、消費者保護についてです。もし、宅建業者との取引で損害を受けた消費者が、供託所から弁済を受ける場合、これを「営業保証金の還付」と言います。
どんな人が還付を受けられて、どんな手続きになるのか見ていきましょう。
- 還付を受けられる人:
- 宅地建物取引に関して、宅建業者のせいで損害を受けた人(一般消費者など)です。
- 注意! 広告業者への広告代金の未払いや、内装業者のリフォーム代金未払い、従業員への給料未払いなどは、「宅地建物取引」に関する損害ではないので、還付の対象にはなりません。
- さらに重要! 平成29年の法改正で、宅建業者は還付請求できなくなりました! つまり、業者間の取引で損害を受けても、相手の営業保証金からは弁済を受けられない、ということです。これも試験で狙われやすいポイント!
- 還付される金額:
- あくまで、その業者が供託している営業保証金の総額の範囲内です。
- 例えば、業者が1,500万円(本店+1支店)供託していて、あなたの損害額が2,000万円だったとしても、供託所から還付されるのは1,500万円まで。残りの500万円は、別途、業者自身の財産から回収する必要があります。
- 還付の手続きと、その後の流れ:
<~を説明した図> 還付手続きフロー図
- 被害者 → 供託所: 被害者が供託所に還付を請求します。
- 供託所 → 免許権者: 供託所が実際に還付を行ったら、その旨を免許権者に通知します。
- 免許権者 → 宅建業者: 免許権者は、「あなたの営業保証金から〇〇円還付されたので、不足分を補充してくださいね」と業者に通知します。
- 宅建業者 → 供託所: 通知を受け取った宅建業者は、通知を受けた日から2週間以内に、還付されて減ってしまった分のお金(不足額)を供託所に供託しなければなりません。
- 宅建業者 → 免許権者: 不足額を供託したら、供託した日から2週間以内に、「ちゃんと供託しましたよ」という届出を免許権者に提出しなければなりません。

2週間! 2週間! って、還付された後の業者の対応期限はすごく短いんです! ここ、数字をしっかり覚えてくださいね!
- 不足額の供託を怠ったら?
- もし、通知から2週間以内に不足額を供託しないと、免許権者はその業者に対して業務停止処分をすることができます。これも「任意」ですが、厳しいペナルティですよね。
- さらに、供託した後も、2週間以内に免許権者に届け出ないと、やはり業務停止処分などの対象になる可能性があります。
これも義務!供託所等の説明
営業保証金を供託している宅建業者は、お客さんと取引する際に、ちゃんと説明しなければいけないことがあります。
- いつ説明する?: 契約が成立するまでの間(重要事項説明と同じタイミングが多いですね)
- 何を説明する?: 自分が営業保証金を供託している「供託所の名称」と「その所在地」
- 誰に説明する?: 取引の相手方
- 例外は?: 取引の相手方が宅建業者である場合は、説明を省略できます。これも平成29年の法改正で追加されたルールです!
これも消費者保護の一環ですね。「万が一の時は、ここの供託所に言えば補償を受けられますよ」と、あらかじめ伝えておくわけです。
お金が戻ってくる?営業保証金の取戻しについて
最後に、供託した営業保証金が戻ってくるケース、「取戻し」についてです。どんな場合に、どうやって取り戻せるのでしょうか?
どんな時に取り戻せるの?取戻し事由いろいろ
営業保証金は、以下のような場合に、供託していた宅建業者(またはその承継人、例えば合併後の会社など)が取り戻すことができます。
- 免許が効力を失ったとき:
- 免許の有効期間が満了した(更新しなかった)
- 個人の業者が死亡した
- 法人が合併して消滅した
- 業者が破産した
- 宅建業を廃止した(廃業届を出した)
- 免許が取り消されたとき: (不正な手段で免許を取った、法律違反で刑罰を受けた、などの理由で)
- 一部の事務所(支店)を廃止したとき:
- 支店を1つ廃止したら、その支店分の500万円を取り戻せます。(供託額が本来必要な額を超えた場合)
- 二重供託をしたとき:
- さっき出てきましたね! 本店移転で有価証券が含まれていて、新しい供託所に供託し直した場合、古い方の供託所に預けてあった分を取り戻せます。
取戻しの手続きと「公告」のルール
じゃあ、取り戻せる理由ができたら、すぐに全額返してもらえるのでしょうか? ここに一つ、原則的なルールがあります。
【原則】6ヶ月以上の公告が必要!
取り戻しをする前に、「この業者は営業保証金を取り戻そうとしていますが、この業者との取引で損害を受けた方は、〇ヶ月以内に申し出てくださいね」という内容の公告(お知らせ)を、6ヶ月以上の期間を定めて行わなければなりません。
これは、まだ損害賠償を請求するかもしれない権利者(還付請求権者)がいないかを確認するためです。この公告期間中に申し出がなければ、晴れて営業保証金を取り戻せる、というわけです。
【例外】公告が不要なケースもある!
ただし、この面倒な公告をしなくても、すぐに取り戻せる例外的なケースが2つあります! ここ、試験で超頻出です!
- 取戻し事由が発生してから10年が経過したとき
- 例えば、廃業してから10年も経てば、さすがにもう還付を請求する人もいないだろう、ということで公告は不要になります。(還付請求権の時効も考慮されています)
- 二重供託をしたことにより、移転前の供託分を取り戻すとき
- 本店移転で新しい供託所にちゃんと供託し直した場合は、古い方の供託所にはもう誰も還付請求しないはずなので、公告なしで速やかに取り戻せます。
公告不要の例外は「10年経過」と「二重供託」! これは絶対に覚えてくださいね!

原則は公告が必要だけど、例外的に不要なケースもある。この『原則と例外』をセットで覚えるのが、宅建業法攻略のコツですよ!
まとめ
ふぅ~、営業保証金について、かなり詳しく見てきましたね! お疲れ様でした!
営業保証金は、宅建業を営む上で、そして消費者を保護する上で、なくてはならない重要な制度です。その仕組みやルールは少し複雑ですが、ポイントを押さえれば必ず理解できます!
- 目的: 消費者保護のためのセーフティーネット
- 基本: 本店1,000万、支店500万を「本店最寄り」の供託所に金銭or有価証券で供託。
- 手続き: 事務所増設、本店移転(保管替え/二重供託)、供託物変更(変換)など、ケースに応じた手続きと届出が必要。
- 還付: 消費者が損害を受けた場合の弁済手続き。業者は還付後2週間以内に不足額供託&届出!
- 取戻し: 免許失効や支店廃止などで可能。原則6ヶ月公告が必要だが、「10年経過」と「二重供託」は公告不要!
これらのポイントをしっかり復習して、営業保証金の項目を得点源にしちゃいましょう!

営業保証金、マスターできましたか? 覚える数字や期間も多いですが、一つ一つ丁寧に確認すれば大丈夫! 次のステップに向けて、一緒に頑張りましょうね!