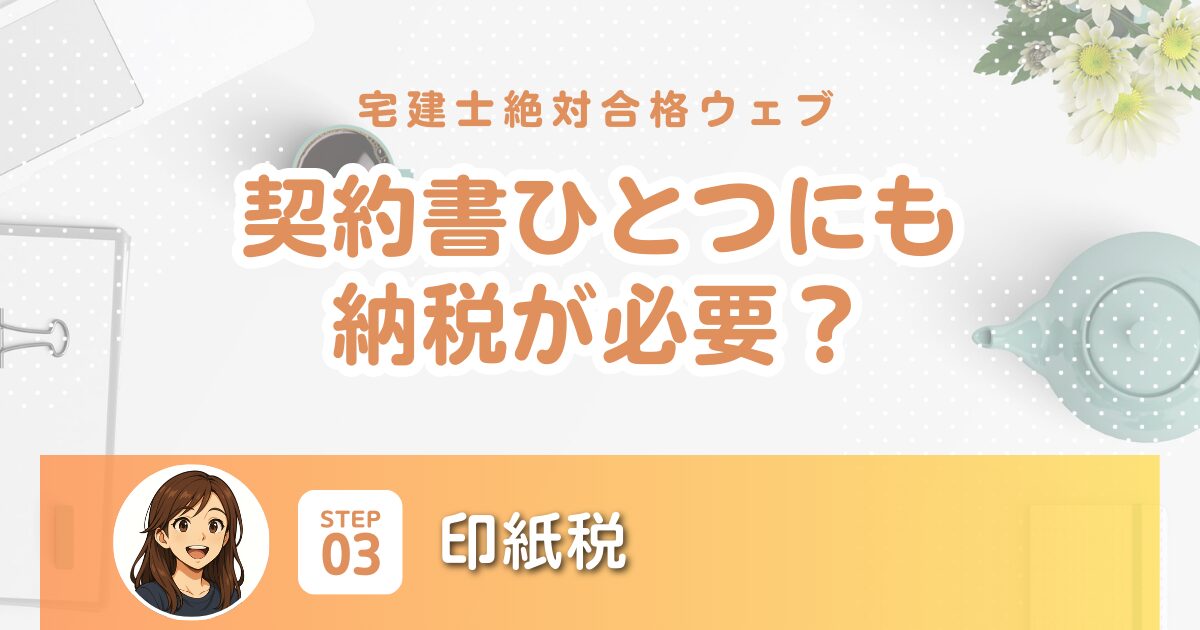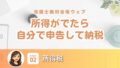今回は「印紙税(いんしぜい)」についてです。「契約書に貼る収入印紙のこと?」となんとなく知っている方も多いと思いますが、「どんな契約書に貼る必要があるの?」「金額はどうやって決まるの?」「貼り忘れたらどうなるの?」など、いざ詳しく聞かれると意外と知らないことが多いのではないでしょうか?
特に、どの文書が課税対象で、どの文書が対象外なのか、その見極めが試験ではよく問われます。「建物の賃貸借契約書は要らないけど、土地の賃貸借契約書は必要…?」「売買契約書はいるけど、委任状は…?」など、混乱しやすいポイントもいくつかありますよね。でも大丈夫!印紙税は、ルールさえしっかり押さえれば、決して難しい税金ではありません。
この記事では、そんな印紙税の基本から、宅建試験で特に重要な「課税文書と非課税文書の見分け方」「税額の基準となる記載金額のルール」「正しい納付方法」、そして「もし納付しなかった場合のペナルティ」まで、わかりやすく丁寧に解説していきます。

この記事を読めば、印紙税に関するモヤモヤが解消し、どんな文書に印紙が必要なのか自信を持って判断できるようになりますよ!
<この記事でわかること>
- 印紙税がどんな税金で、なぜ必要なのか
- 宅建試験で重要な課税文書と非課税文書の具体例
- 印紙税の納税義務者と納付時期
- 税額の基準となる「記載金額」の決め方(ケース別)
- 正しい印紙の貼り方・消印の方法と、納付しなかった場合のペナルティ
印紙税の基本 | どんな税金?なぜ契約書に印紙が必要?
まずは、印紙税の基本的な性格やルールについて見ていきましょう。
印紙税ってどんな税金?
印紙税とは、経済的な取引などに関連して作成される特定の「文書」(契約書や領収書など)に対して課税される国税です。皆さんも、不動産の売買契約書や、少し高額な買い物をした時の領収書などで「収入印紙」が貼られているのを見たことがあるかもしれませんね。
この税金は、経済取引を行う際に様々な文書が作成され、それによって法律関係が明確になったり、取引の証拠が残ったりすることに着目し、そうした文書を作成する能力(担税力)のある人に広く公平に負担を求める、という考え方に基づいています。
納付方法は少し特殊で、原則として、課税対象となる文書に、定められた金額の収入印紙を貼り付け、それに消印をすることで納税したことになります。

税務署に直接お金を納めるんじゃなくて、印紙を貼ることで納税になるんですね。
納税義務者は誰?いつまでに納める?
では、印紙税を納める義務があるのは誰でしょうか?
- 納税義務者:印紙税の納税義務者は、その課税文書を作成した人(または法人)です(印紙税法第3条)。契約の相手方ではなく、あくまで文書の「作成者」が納税義務を負います。
- 共同作成の場合:例えば、不動産売買契約書を売主と買主が共同で作成した場合、売主と買主の両方が、連帯して納税義務を負うことになります。(連帯納税義務)
<ポイント>実務上は、契約書を2通作成して各自が保管する場合、それぞれが自分の保管する契約書に貼る印紙代を負担することが多いですが、法律上は連帯して納付する義務がある、とされています。 - 正本・副本(写し)の扱い:契約書などを複数作成し、一方が「正本」、もう一方が「副本」や「写し」といった名称であっても、契約の当事者間で契約の成立を証明する目的で作成されたものであれば、その副本や写しも課税文書として扱われ、それぞれに印紙税が必要になります。単なるコピー(複写)で、契約の証明用でないものは課税されません。
- 納付時期:印紙税は、課税文書を作成した時までに納付しなければなりません。つまり、契約書に署名・押印するタイミングまでには、印紙を貼って消印しておく必要があるということです。
【重要】課税?非課税?印紙税がかかる文書・かからない文書をマスター!
印紙税の学習で最も重要なのが、どんな文書に印紙税がかかり(=課税文書)、どんな文書にはかからないのか、その区別をしっかりつけることです。
宅建試験でよく出る!課税対象となる主な文書(課税文書)
印紙税法では、課税対象となる文書(課税文書)が20種類定められていますが、宅建試験で特に重要なのは以下のものです。
- 不動産売買契約書(土地・建物の売買契約書)
- 不動産交換契約書
- 不動産贈与契約書 (※ただし、税額の扱いは後述)
- 土地賃借権設定契約書、地上権設定契約書 (土地の貸し借りに関する権利設定の契約書)
- 工事請負契約書 (建物の新築・増改築などの工事契約書)
- 金銭または有価証券の受取書(領収書)
- ただし、営業に関わるもので、かつ記載された受取金額が5万円以上のものに限ります。(※金額は2024年4月現在。今後変更の可能性あり)
- 「営業に関わる」とは、会社などの法人はもちろん、個人事業主が行う事業に関するものも含みます。
<注意>
後日、正式な契約書を作成する約束で交わされる仮契約書や、すでに存在する契約の内容を変更するための変更契約書・覚書なども、その内容によっては課税文書となる場合があります。
これは非課税!印紙税がかからない主な文書
次に、印紙税がかからない文書です。これには2つのパターンがあります。
- 不課税文書:そもそも印紙税法で定められた課税文書の種類に該当しないため、印紙税がかからない文書。
- 非課税文書:課税文書の種類には該当するけれど、法律や政策的な理由から、特別に印紙税を課さない(非課税)とされている文書。
宅建試験で重要な「印紙税がかからない文書」の例を挙げます。
【不課税文書の主な例】
- 委任状 (例:不動産売買の代理権を与える委任状)
- 建物の賃貸借契約書 (アパートやマンション、店舗などの賃貸借契約書)
- 抵当権設定契約書、質権設定契約書 (お金を借りる際の担保設定の契約書)
- 使用貸借契約書 (タダで物を貸し借りする契約書)
<超重要!>
建物の賃貸借契約書は不課税ですが、上で見たように土地の賃貸借契約書は課税文書です。この違いは絶対覚えてください!
【非課税文書の主な例】
- 国、地方公共団体、または印紙税法別表第二に掲げる者(UR都市機構など特定の公共法人)が作成した文書
<ポイント>国や自治体が作成者の一方であれば、相手方が民間でもその文書は非課税になります。 - 記載された契約金額等が一定額未満の文書
- 不動産売買契約書、交換契約書、土地賃借権設定契約書など ⇒ 記載金額1万円未満は非課税
- 工事請負契約書 ⇒ 記載金額1万円未満は非課税
- 金銭または有価証券の受取書(領収書) ⇒ 記載金額5万円未満は非課税
- 営業に関しない受取書(領収書)
<例>個人間でお金の貸し借りをして、返済を受けた際の領収書など。会社や事業者が発行するものではない領収書は、たとえ5万円以上でも非課税です。
<比較表:課税文書と非課税文書の主な例>
| 課税文書(印紙が必要な主な例) | 非課税・不課税文書(印紙が不要な主な例) |
|---|---|
| 不動産売買契約書 | 建物の賃貸借契約書 |
| 土地賃借権設定契約書 | 抵当権設定契約書 |
| 工事請負契約書 | 委任状 |
| 領収書(営業に関するもの5万円以上) | 領収書(5万円未満 or 営業に関しないもの) |
| 不動産交換契約書 | 国・地方公共団体等が作成した文書 |
| 不動産贈与契約書 | 記載金額1万円未満の売買契約書等 |

こうやって比較すると分かりやすいですね!特に「建物賃貸借は非課税」はしっかり覚えよう!
いくら貼るの?課税標準(記載金額)のルールと納付・罰則
課税文書に該当する場合、次に問題になるのが「いくらの収入印紙を貼ればいいのか?」ですよね。印紙税額は、原則としてその文書に書かれている金額、つまり「記載金額」に応じて決まります。
税額の基準「記載金額」はどう決まる?ケース別解説
印紙税額を決めるもとになる「記載金額」が、文書の種類によってどう判断されるのか、主なケースを見ていきましょう。
- 不動産売買契約書:その文書に記載された売買代金(契約金額)が記載金額となります。
<注意>もし、契約書に売買代金全体の記載がなく、手付金の額しか書かれていない場合は、「記載金額のない文書」として扱われます。
- 不動産交換契約書:交換する両方の不動産の価額が記載されている場合は、そのうち高い方の金額が記載金額となります。もし、交換差金のみが記載されている場合は、その交換差金の額が記載金額となります。
- 不動産贈与契約書:贈与は対価の授受がないため、価額の記載があっても「記載金額のない文書」として扱われます。
- 土地賃借権設定契約書・地上権設定契約書:後日返還される予定のない権利金、礼金などの金額が記載金額となります。賃料(月額家賃など)や保証金(敷金など、後で返還されるもの)は記載金額には含まれません。
- 変更契約書:
- 元の契約金額を増額する変更契約書の場合 ⇒ その増加した金額が記載金額となります。
- 元の契約金額を減額する変更契約書の場合 ⇒ 「記載金額のない文書」として扱われます。
<ポイント>
「記載金額のない文書」と判断された場合、印紙税額は原則として一律200円となります(一部例外あり)。贈与契約書や、売買代金の記載がない契約書、減額の変更契約書などがこれに該当します。
税率はどうなる?
印紙税の具体的な税額(いくらの印紙を貼るか)は、上記で決まった記載金額に応じて、段階的に定められています。(例:売買契約書なら、記載金額100万円超500万円以下は◯◯円、500万円超1000万円以下は◯◯円…のように)
しかし、宅建試験でこの具体的な税額テーブルを暗記する必要はまずありません。 「記載金額によって税額が変わるんだな」ということと、「記載金額なしなら原則200円だな」ということを理解しておけば十分です。
正しい納付方法:印紙の貼り方と消印
印紙税の納付は、文書に収入印紙を貼り、消印(けしいん)をすることで完了します。
- 収入印紙の貼付:定められた税額分の収入印紙(郵便局やコンビニなどで購入できます)を、課税文書の所定の場所(なければ任意の場所)に貼り付けます。
- 消印:貼った収入印紙と文書の紙面にまたがるように、文書の作成者(またはその代理人、従業員など)の印章(ハンコ)または署名(サイン)ではっきりと印をします。これにより、その印紙が使用済みであることが示され、再利用を防ぎます。
印紙を貼るだけではダメ!必ず消印が必要です。消印を忘れた場合も、印紙税を納付しなかったものとして扱われ、後述するペナルティ(過怠税)の対象になるので注意してください!
印紙を貼り忘れたらどうなる?過怠税について
もし、課税文書に収入印紙を貼らなかったり、貼り忘れたり、貼ったけど消印をしなかったりした場合、どうなるのでしょうか?
税務調査などでその事実が発覚した場合、ペナルティとして「過怠税(かたいぜい)」が徴収されます。
過怠税の額は、原則として、納付すべきだった印紙税額とその2倍に相当する金額との合計額、つまり、本来納めるべきだった印紙税額の3倍にもなります!
<例>
本来1万円の印紙を貼るべき契約書に貼り忘れていた場合、1万円+(1万円×2)=3万円の過怠税が徴収されることになります。
ただし、税務調査を受ける前に、自主的に「印紙を貼り忘れていました」と申し出た場合は、過怠税が「本来の税額+その10%(=1.1倍)」に軽減される措置があります。それでも、本来より多く払うことには変わりありません。

うっかりミスでも3倍は厳しいですね…。契約書を作成したら、印紙の要否と金額をしっかり確認して、忘れずに貼って消印しないと!
まとめ
今回は、契約書や領収書など身近な文書に関わる「印紙税」について、その基本から宅建試験で重要なポイントまで解説しました。
地味に見えても、取引の基本に関わる重要な税金です。特に課税文書と非課税文書の区別はしっかりマスターしておきましょう。
最後に、今回の重要ポイントをまとめておきます。
- 印紙税は、特定の課税文書の作成時に課税される国税で、収入印紙を貼付し消印して納付します。
- 宅建試験では、不動産売買契約書、土地賃借権設定契約書、請負契約書、領収書(営業・5万円以上)などが主な課税文書です。
- 建物の賃貸借契約書や抵当権設定契約書、委任状などは不課税・非課税です。
- 納税義務者は文書作成者(共同作成なら連帯)。納付時期は作成時。
- 税額は原則として記載金額に応じて決まります。売買代金、交換価額(高い方)、権利金などが記載金額になります。
- 贈与契約書や減額の変更契約書などは「記載金額なし」として扱われ、税額は原則200円です。
- 印紙を貼らなかったり消印を忘れたりすると、原則として本来の税額の3倍の過怠税が課せられます。

課税・非課税の区別と、記載金額のルール、そして過怠税。このあたりをしっかり押さえれば、印紙税の問題は怖くありませんね!