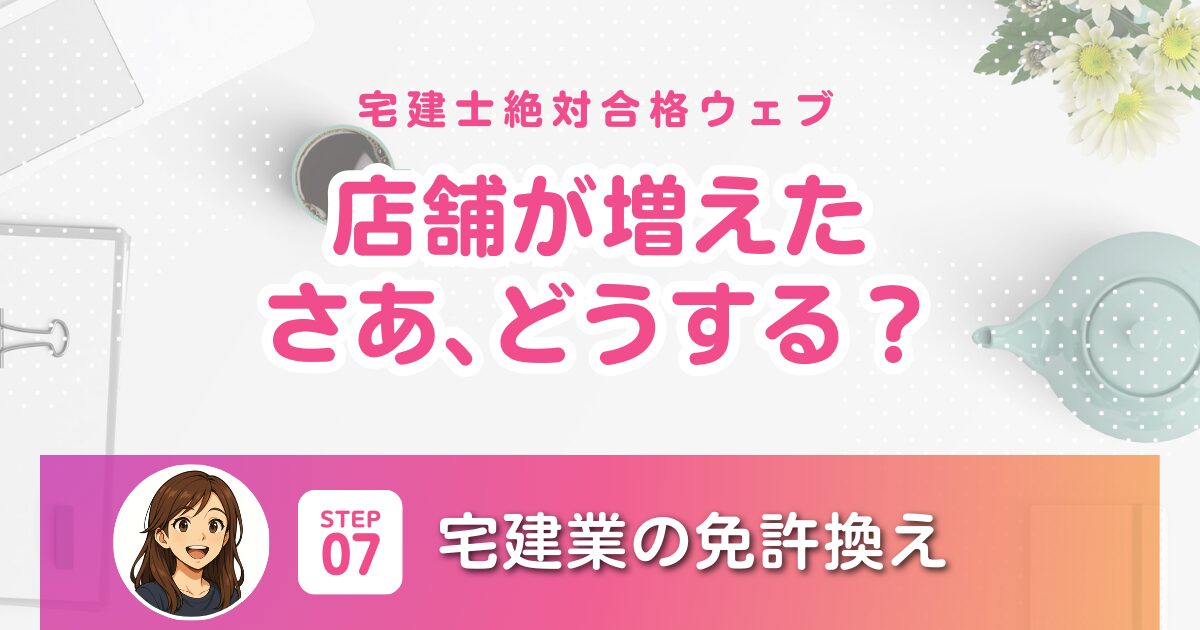会社の事務所を引っ越したり、新しく支店を出したり、逆に支店を閉鎖したり…宅建業を営んでいると、事務所の状況が変わることってありますよね。そんな時、「あれ?今持ってる宅建業の免許って、そのままで大丈夫なんだっけ?」って疑問に思ったことはありませんか?
実は、事務所の場所が変わったことによって、免許を発行してくれた「免許権者」が変わる場合には、「免許換え(めんきょがえ)」という手続きが必要になるんです!「え、免許を取り直すってこと?」「どんな時に必要なの?」って、ちょっと戸惑ってしまいますよね。
でも大丈夫!この「免許換え」、ルール自体は意外とシンプルなんです。この記事では、どんな時に免許換えが必要になるのか、どうやって申請するのか、そして免許換えをしたらどうなるのか、といった点を、具体例を交えながら分かりやすく解説していきます!
この記事でわかること
- 「免許換え」とは何か、どんな時に必要になる手続きなのか
- 免許換えの申請先(知事免許と大臣免許で違う!)
- 免許換えをした後の、新しい免許の有効期間について
- 免許換えに伴う、古い免許の扱いや免許権者間の通知ルール
- 免許換えとセットで必要になる他の手続きについて
事務所が変わったら要注意!「免許換え」ってどんな手続き?
まずは、「免許換え」がどんな手続きなのか、基本的なところから押さえていきましょう!これを理解しておけば、事務所の変更があったときも慌てず対応できますよ。
「免許換え」が必要になるのはどんな時?
「免許換え」とは、簡単に言うと、今持っている宅建業の免許を発行してくれた免許権者(都道府県知事 or 国土交通大臣)とは別の免許権者に、新しく免許を発行してもらう手続きのことです。
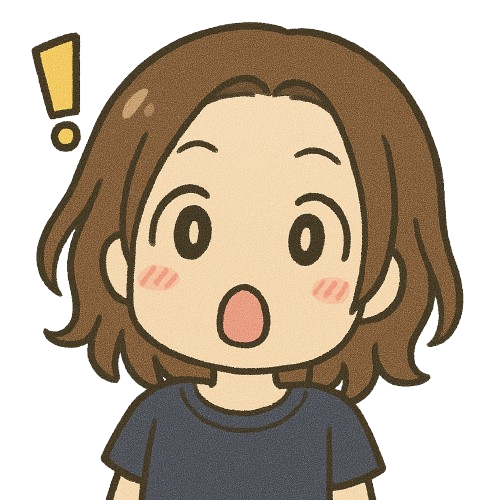
つまり、免許の種類が変わる(例:知事免許→大臣免許)とか、同じ知事免許でも管轄する都道府県が変わる(例:東京都知事免許→神奈川県知事免許)場合に必要になるんですね!
じゃあ、どんな時に免許権者が変わる可能性があるのでしょうか?それは主に、事務所の設置状況に変化があったときです。
思い出してください、免許の種類(知事免許か大臣免許か)は、「いくつの都道府県に事務所があるか」で決まるんでしたよね?
- 1つの都道府県にしか事務所がない → その都道府県の知事免許
- 2つ以上の都道府県に事務所がある → 国土交通大臣免許
このルールに基づいて、以下のようなケースで免許換えが必要になります。
- ケース1:知事免許 → 大臣免許
- 例:東京都内にしか事務所がなかった(東京都知事免許)けど、新たに神奈川県にも支店を設置した。
- → 2つの都道府県に事務所を持つことになるので、国土交通大臣免許への免許換えが必要!
- ケース2:大臣免許 → 知事免許
- 例:東京都と神奈川県に事務所があった(国土交通大臣免許)けど、神奈川県の支店を廃止して、東京都内の事務所だけになった。
- → 1つの都道府県にしか事務所がなくなるので、東京都知事免許への免許換えが必要!
- ケース3:知事免許 → 別の知事免許
- 例:東京都内にしか事務所がなかった(東京都知事免許)けど、その事務所を廃止して、新たに神奈川県にだけ事務所を設置した。
- → 管轄する都道府県が変わるので、神奈川県知事免許への免許換えが必要!
ポイントは「最終的に、どの都道府県に、いくつ事務所がある状態になるか」です! 事務所の増減や移転の結果、免許権者が変わるかどうかを判断しましょう。
同じ都道府県内での本店移転や支店増設は? 例えば、東京都知事免許を持っている業者が、東京都内で本店を移転したり、東京都内に新たに支店を増やしたりする場合はどうでしょうか?
この場合、事務所があるのは依然として東京都内だけ(1つの都道府県のみ)なので、免許権者は東京都知事のまま変わりません。
ですから、免許換えは不要です!ただし、本店所在地や事務所の名称・所在地が変わるので、「宅建業者名簿の変更届出」と「免許証の書換え交付申請」は必要になりますよ。
申請先はどこ?知事免許と大臣免許で違う申請ルート
免許換えが必要になったら、どこに申請すればいいのでしょうか?これは、「新しくどの免許権者の免許を受けることになるか」によって、申請ルートが異なります。
- 新しく「都道府県知事免許」を受ける場合:
- 新たに免許権者となる都道府県知事に対して、直接、免許換えの申請をします。
- 例:大臣免許から千葉県知事免許に換えるなら、千葉県知事に直接申請!
- 例:東京都知事免許から千葉県知事免許に換えるなら、千葉県知事に直接申請!
- 新しく「国土交通大臣免許」を受ける場合:
- 主たる事務所(本店)の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、国土交通大臣に申請します。(※新規申請の時と同じルートですね!)
- 例:東京都知事免許から大臣免許に換える(本店は東京都のまま)なら、東京都知事を経由して申請!

ここも大事なポイントです!大臣免許への申請は、新規でも免許換えでも、必ず「本店所在地の知事を経由する」んですね!しっかり覚えておきましょう!
具体例で見る!免許換えの申請パターン
ちょっとややこしいので、具体例で申請先を確認してみましょう!
- パターン1:
- 変更前: 本店:東京都、支店:千葉県(国土交通大臣免許)
- 変更後: 本店:千葉県(旧東京本店は廃止)
- 結果: 千葉県内にしか事務所がない状態になるので、「千葉県知事免許」への免許換えが必要。
- 申請先: 新たな免許権者である千葉県知事に直接申請。
- パターン2:
- 変更前: 本店:東京都(東京都知事免許)
- 変更後: 本店:東京都、支店:千葉県に増設
- 結果: 2つの都道府県に事務所がある状態になるので、「国土交通大臣免許」への免許換えが必要。
- 申請先: 主たる事務所(本店)がある東京都の知事を経由して申請。
- パターン3:
- 変更前: 本店:東京都(東京都知事免許)
- 変更後: 千葉県に事務所を移転(旧東京本店は廃止)
- 結果: 千葉県内にしか事務所がない状態になるので、「千葉県知事免許」への免許換えが必要。
- 申請先: 新たな免許権者である千葉県知事に直接申請。

どうでしょう?具体例で見るとイメージしやすいですよね!「最終的にどの免許になるか」と「本店はどこにあるか」を確認すれば、申請先が判断できますね。
免許換えしたら免許証番号はどうなる?
免許換えをすると、新しい免許権者から新しい免許証が交付されます。そうなると、もちろん免許証番号も新しくなります!
例えば、東京都知事(2)第12345号の免許を持っていた業者が、大臣免許に免許換えをしたら、「国土交通大臣(1)第67890号」のように、全く新しい番号が付与されます。
そして注目は、更新回数を表すカッコの中の数字!免許換えをすると、更新回数はリセットされて、(1)から再スタートになるんです!だから、免許換えをしたばかりの業者さんは、たとえ長年営業していても、番号上は新規業者さんと同じ(1)になるんですね。ちょっとした豆知識です!
免許換え後のルールとポイントをしっかり押さえよう!
無事に免許換えの申請が受理され、新しい免許が交付された!これで一安心…ですが、免許換えに伴って知っておくべきルールがいくつかあります。これも試験で問われやすいポイントなので、しっかり確認しましょう!
新しい免許の有効期間はいつからスタート?(更新との違い)
免許換えによって新しく交付された免許、その有効期間はいつから始まるのでしょうか?
これは、免許の更新の時とは扱いが異なります!
- 免許の更新の場合: 更新前の免許の有効期間満了日の翌日から5年間
- 免許換えの場合: 新しい免許を受けたその時から新たに5年間

そうなんです!免許換えの場合は、前の免許の有効期間が残っていたとしても、それは関係なく、免許換えが完了した日から、新しい5年間のカウントがスタートするんです!これは大きな違いなので、しっかり区別してくださいね!
免許換え後の有効期間 = 新免許を受けた時から5年間!
古い免許はどうなるの?効力がなくなるタイミング
免許換えをして、新しい免許権者から新しい免許を受けたら、それまで持っていた古い免許(従前の免許)はどうなるのでしょうか?
これは、新しい免許を受けた時点で、古い免許はその効力を失います。 自動的に無効になる、ということですね。
- 例: もともと東京都知事免許を持っていた業者が、本店を大阪府に移して大阪府知事免許を受けた(免許換えした)場合、その大阪府知事免許を受けた瞬間に、古い東京都知事免許は効力を失います。

一つの宅建業者が、同時に複数の有効な免許を持つことはない、ということですね。免許換えによって、古いものから新しいものへ、スムーズにバトンタッチされるイメージです。
古い免許が効力を失うということは、その古い免許証はもう使えないということ。どうするんでしたっけ…? そうです!「免許証の返納」が必要でしたね!免許換えによって効力を失った従前の免許証は、遅滞なく、従前の免許権者に返納しなければなりません(義務です!)。これも忘れずに行いましょう!
免許権者同士の連携プレー!通知のルール
免許換えが行われると、免許を与える行政機関(免許権者)の間でも、ちゃんと情報連携が行われます。
宅建業者が免許換えをして、新しく免許を与えた免許権者(国土交通大臣または都道府県知事)は、その業者に免許を交付したら、遅滞なく、その旨を「従前の(古い方の)免許を与えていた免許権者」に通知しなければならない、というルールがあるんです。
- 例: 宅建業者A社が、東京都知事免許から大阪府知事免許へ免許換えをした場合。新しく免許を与えた大阪府知事は、古い方の免許を与えていた東京都知事に対して、「A社さんに、うちが新しく免許を出しましたよー!」と、遅滞なく通知しなければなりません。
行政同士でもちゃんと連絡を取り合っているんですね!これによって、「あの業者はもううちの管轄じゃなくて、○○知事(大臣)の管轄になったんだな」って、古い免許権者も把握できるわけですね。スムーズな情報管理のための大切なルールです。
免許換えとセットで必要な手続きは?(名簿変更・書換え交付などへの言及)
さて、「免許換え」は免許権者が変わる場合の大元の手続きですが、これに伴って、他にもやらなければならない手続きがあることを忘れてはいけません。
事務所の移転や増設・廃止が免許換えの原因になることが多いわけですから、当然、宅建業者名簿の記載事項(事務所の所在地や名称、場合によっては商号や代表者、専任宅建士など)にも変更が生じているはずですよね?
ですから、免許換えの申請と併せて、あるいは前後して、以下の手続きも必要になるケースがほとんどです。
- 宅建業者名簿の変更届出: 変更があった日から30日以内に!(義務)
- 免許証の書換え交付申請: 免許証記載事項に変更があれば、変更届出と同時に!(義務)
- 従前の免許証の返納: 新しい免許を受けたら遅滞なく!(義務)
免許換えは、これらの関連手続きと一連の流れで行われることが多い、と理解しておくと良いですね!どの手続きが、いつまでに、どこに対して必要なのか、しっかり整理しておくことが大切です。
免許換えの手続き自体、新規免許申請と同じように、申請書の作成や様々な添付書類(会社の定款や登記簿謄本、役員や専任宅建士の証明書類、事務所の写真や図面など)の準備が必要です。
手数料も新規申請と同額(33,000円 ※2025年4月現在)かかります。時間も手間もかかる手続きなので、免許換えが必要になりそうな場合は、早めに準備を進めることをお勧めします!
まとめ
今回は、宅建業の「免許換え」について、どんな時に必要で、どうやって手続きするのか、そして免許換え後の注意点などを解説しました!事務所の状況が変わったときに必要になる重要な手続き、理解していただけましたでしょうか?
免許換えは、免許の更新とは違うルール(特に有効期間!)があったり、申請先がケースによって異なったりと、少しややこしい部分もありますが、基本を押さえれば大丈夫!試験でも実務でも役立つ知識なので、しっかり復習しておきましょうね!
最後に、免許換えの重要ポイントをおさらいです!
- 免許換えとは: 事務所の設置状況変更により、免許権者(知事⇔大臣、知事→別の知事)が変わる場合に、新しい免許権者から免許を受け直す手続き。
- 申請先:
- 新しく知事免許になる場合 → その知事に直接申請。
- 新しく大臣免許になる場合 → 本店所在地の知事を経由して申請。
- 有効期間: 新しい免許を受けたその時から新たに5年間!(更新とは違う!)
- 従前の免許: 新しい免許を受けた時点で効力を失う。古い免許証は遅滞なく返納(義務)。
- 免許権者間の通知: 新免許権者は、旧免許権者に遅滞なく免許交付の旨を通知(義務)。
- 関連手続き: 名簿変更届出(30日以内)、免許証書換え交付(必要な場合、変更届出と同時)、旧免許証返納(遅滞なく)なども忘れずに!

宅建業者として活動していく上で、事務所の変更は起こりうることです。その際に慌てないためにも、免許換えのルールをしっかり理解しておくことが大切ですね!