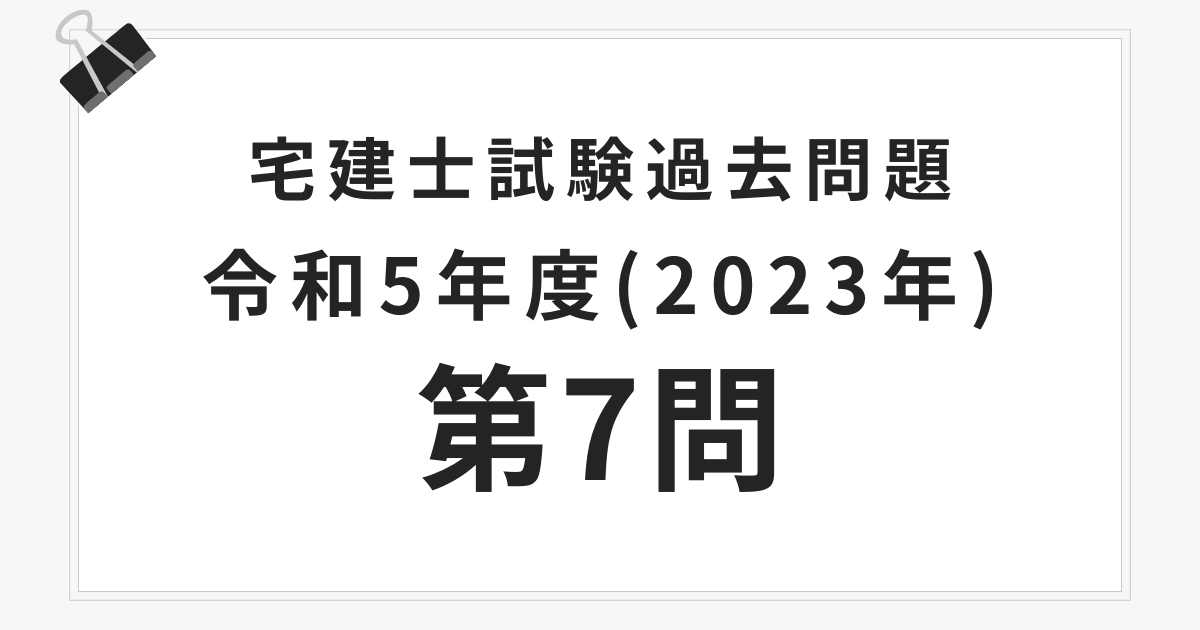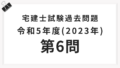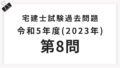問題:宅建士試験 過去問題 令和5年(2023年)問7
甲建物を所有するAが死亡し、Aの配偶者Bが甲建物の配偶者居住権を、Aの子Cが甲建物の所有権をそれぞれ取得する旨の遺産分割協議が成立した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 遺産分割協議において、Bの配偶者居住権の存続期間が定められなかった場合、配偶者居住権の存続期間は20年となる。
- Bが高齢となり、バリアフリーのマンションに転居するための資金が必要になった場合、Bは、Cの承諾を得ずに甲建物を第三者Dに賃貸することができる。
- Cには、Bに対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務がある。
- Cは、甲建物の通常の必要費を負担しなければならない。
正解を見る
正解
3
解説
選択肢1:誤り。
配偶者居住権の存続期間は、原則として「配偶者が死亡するまで」です(民法第1030条)。期間の定めがなかった場合に自動的に20年とされるわけではありません。
選択肢2:誤り。
配偶者は、配偶者居住権に基づいて居住する権利を持ちますが、その使用範囲を超えて第三者に賃貸する場合は、建物所有者(C)の承諾が必要です(民法第1032条第2項)。
選択肢3:正しい。
配偶者居住権は対抗要件として登記が必要であり、その登記は建物の所有者によってなされなければならないため、CにはBに対して登記を備えさせる義務があります(民法第602条の2、第1032条第3項)。
選択肢4:誤り。
配偶者居住権が設定された建物について、通常の必要費は配偶者(B)が負担します。所有者(C)は特別の事情がない限り負担義務を負いません。
よって、正解は 3 です。