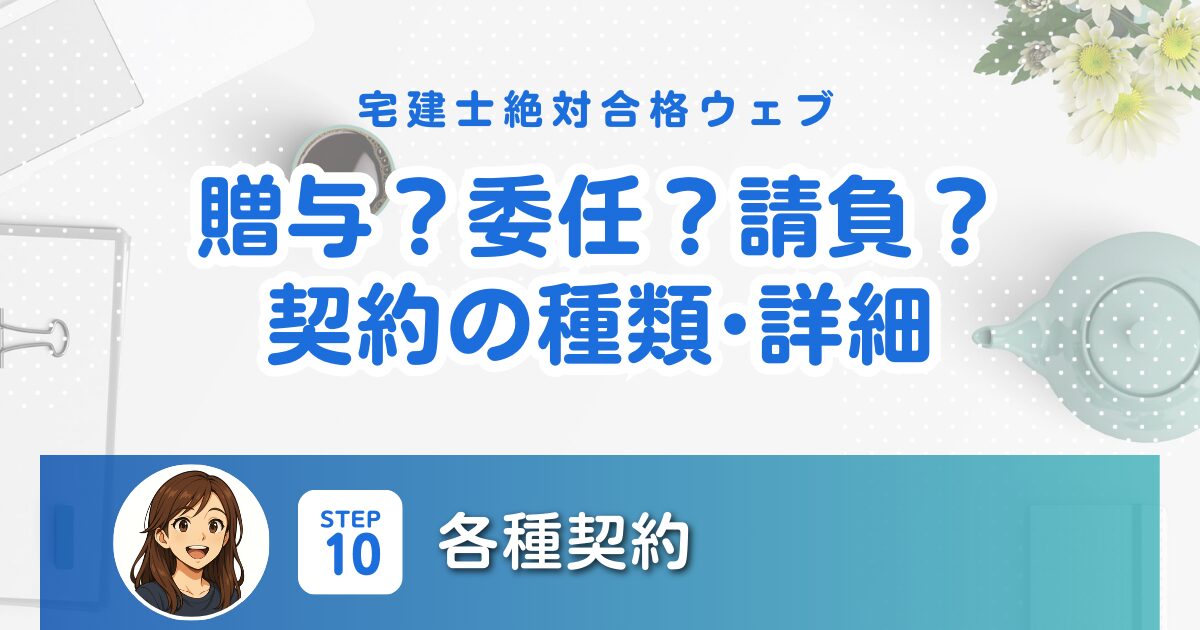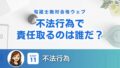こんにちは!不動産会社で働きながら宅建士としても奮闘中の私です。宅建の権利関係の勉強、進捗はいかがですか?民法には色々な「契約」の種類が出てきますよね。「贈与」「委任」「請負」…名前は聞いたことあるけど、それぞれ何がどう違うのか、正確に説明するとなると、意外と難しいと感じていませんか?「委任と請負って、どっちも仕事を頼む契約じゃないの?」「事務管理って、契約じゃないのにどうして民法に出てくるの?」など、混乱しやすいポイントも多いですよね…。私も勉強中はよく頭がごちゃごちゃになっていました!
でも、これらの契約に関するルールは、宅建試験でも頻出ですし、特に委任(媒介契約など)や請負(建物の建築など)は不動産取引の実務でも深く関わってきます。それぞれの契約の性質や当事者の権利・義務の違いをしっかり理解しておくことが、合格への近道ですし、将来きっと役立ちますよ!
この記事では、「贈与」「委任」「請負」「事務管理」そして契約の効力に関わる「停止条件」という、宅建試験で特に重要な契約関連のテーマについて、それぞれの特徴や違い、注意すべきポイントを、具体例や比較表を使いながら、一つ一つ丁寧に解説していきます。この記事を読み終える頃には、これらの契約に関する知識がスッキリ整理されて、「なるほど、そういうことか!」と自信を持てるようになっているはずです。一緒に学んでいきましょう!

契約の種類が多くて大変ですけど、ポイントを押さえれば大丈夫!一緒に頑張りましょうね!
この記事でわかること
- モノをタダであげる「贈与契約」の基本ルールと注意点(解除の可否、贈与者の責任など)について理解できる
- 仕事を頼む契約「委任」と「請負」の決定的な違いとそれぞれの報酬・義務・解除に関するポイントが整理できる
- 頼まれてないけど助ける「事務管理」とは何か、その要件や効果、委任との違いがわかる
- 条件が成就したら効力が発生する「停止条件」付き契約の仕組みと注意点の対策がわかる
- 各契約における当事者の権利、義務、責任(契約不適合責任含む)の違いが明確になる
無償?有償?タダであげる「贈与契約」のルールと注意点
まずは、一番シンプルで身近かもしれない「あげる・もらう」の契約、「贈与契約」から見ていきましょう。「タダなんだから簡単でしょ?」と思いきや、意外と注意点があるんですよ。

プレゼントにも法律ルールがあるんですね!
贈与契約ってどんな契約?身近なプレゼントも実は贈与!
贈与契約(ぞうよけいやく)とは、当事者の一方(贈与者:ぞうよしゃ、あげる人)が無償で(タダで)自分の財産(お金や物、権利など)を相手方(受贈者:じゅぞうしゃ、もらう人)に与える意思を表示し、相手方がこれを受諾(じゅだく:承諾すること)することによって成立する契約です(民法第549条)。
ポイントは2つです。
- 無償契約: 対価(見返り)がない、タダの契約であること。
- 諾成契約(だくせいけいやく): 当事者の「あげます」「もらいます」という意思表示の合致(合意)だけで成立し、実際に物を渡したりする必要はないこと。(口約束でも成立します)
私たちの日常生活でも、意識していなくても贈与契約はたくさんあります。
- 友人への誕生日プレゼント
- 親から子への仕送りやお小遣い
- お中元やお歳暮のやり取り
- チャリティーへの寄付
これらも法律的に見れば、贈与契約なんですね。
口約束の贈与は取り消せる?書面にした場合は?【解除のルール】
贈与契約は口約束でも有効に成立しますが、「やっぱりあげるのやめた!」とか「もらうのやめた!」と後から取り消し(法律上は「解除」といいます)ができるかどうかについては、契約が書面でされたかどうかで扱いが大きく異なります。これは試験でもよく問われる重要な違いです!
① 書面によらない贈与(口約束など)の場合
口約束など、契約内容が書面になっていない贈与契約は、各当事者(贈与者・受贈者どちらからでも)が原則として自由に解除できます(民法第550条本文)。
なぜなら、口約束は軽い気持ちでされることも多く、後で気が変わることもあり得るため、履行(実際に物を渡すなど)が終わるまでは、その意思を尊重しようという考え方だからです。
<注意!履行済み部分は解除不可!>
ただし、いくら口約束の贈与でも、すでに履行が終わった部分(例えば、もうプレゼントを渡してしまった、お金を振り込んでしまったなど)については、解除することはできません(民法第550条ただし書)。「あげたものを返せ!」とは言えないわけですね。
例:
Aさんが友人のBさんに「今度、使っていないゲーム機をあげるよ」と口約束しました。その後、Aさんが実際にゲーム機をBさんに渡す前に「ごめん、やっぱりあれ使うことにしたから、あげるのやめるね」と言うのはOKです(履行前の解除)。しかし、AさんがBさんにゲーム機を渡した後で「やっぱり返して!」と言うことは原則できません(履行後の解除は不可)。
② 書面による贈与の場合
契約書を作成するなど、贈与の意思が書面で明確に表示されている場合は、原則として、一方的に解除することはできません。
書面にするということは、贈与者の意思が慎重かつ確実であると考えられるため、口約束よりも契約の拘束力が強まります。解除するためには、相手方の債務不履行(例えば、後述する負担付贈与で負担を履行しない場合)など、特別な理由がない限り、相手方の合意が必要になります。
【贈与の解除ルール まとめ】
- 書面によらない贈与: 履行前ならいつでも自由に解除可能(贈与者・受贈者どちらからでも)。履行後は解除不可。
- 書面による贈与: 原則として一方的な解除は不可。
この違いはしっかり区別しておきましょう!
あげた物に欠陥があったら?贈与者の責任は軽い?【契約不適合責任】
もし、贈与で「あげた」物(贈与の目的物)に、後から欠陥や不具合(例えば、あげた中古車がすぐに故障した、あげた土地に埋設物があったなど)が見つかった場合、贈与者はその責任を負うのでしょうか? 売買契約なら「契約不適合責任」を負うのが原則ですが、タダであげた贈与の場合はどうなるのでしょう?
贈与は無償(タダ)の契約なので、売買契約のような有償契約に比べて、贈与者の責任は原則として軽くなっています。
民法では、贈与者は、贈与の目的物を「特定した時の状態で引き渡せば足りる」とされています(民法第551条第1項)。
つまり、物を特定した時点(「この絵をあげるよ」と決めた時など)で、その物にキズや汚れがあったとしても、贈与者は基本的にそのまま引き渡せば義務を果たしたことになり、後から修理したり、損害賠償したりする責任(=契約不適合責任)は原則として負わない、ということです。「タダでもらうんだから、文句は言えないよね」というバランス感覚ですね。
ただし、例外的に贈与者が責任を負うケースもあります。
- 贈与者が欠陥を知りながら受贈者に告げなかった場合:
これは不誠実ですよね。わざと欠陥を隠してあげたような場合には、信義に反するので、贈与者も契約不適合責任を負います(民法第551条第1項ただし書)。 - 贈与者が品質などを保証した場合:
「この中古車、ちゃんと動くことを保証するよ!」などと、贈与者が目的物の品質や性能を保証した場合は、その保証した内容については責任を負います。もし保証内容と違っていたら、債務不履行責任を問われる可能性があります。 - 負担付贈与の場合(後述):
見返り(負担)がある贈与の場合は、責任が重くなります。
【贈与者の責任 まとめ】
- 原則: 責任は負わない(特定時の状態で引き渡せばOK)。
- 例外: 欠陥を知ってて黙っていた場合、品質を保証した場合、負担付贈与の場合は責任を負う。
【応用編】負担付贈与・定期贈与・死因贈与とは?
贈与契約には、通常の単純な贈与以外にも、少し特殊なタイプがあります。宅建試験でも問われる可能性があるので、それぞれの特徴を押さえておきましょう。
① 負担付贈与:タダじゃない贈与?責任は売買と同じ?
負担付贈与(ふたんつきぞうよ)とは、受贈者(もらう人)に一定の負担(何らかの義務)を負わせることを条件として行われる贈与契約のことです(民法第553条)。完全にタダではなく、「これをあげる代わりに、〇〇してね」というタイプの贈与ですね。
例:
- 「この家をあげるから、私が生きている間は毎月5万円の生活費を援助してね」
- 「この土地をあげる代わりに、隣接する私の土地の草刈りを毎年やってね」
この場合、受贈者は財産をもらう権利を得ると同時に、約束した負担を履行する義務を負います。もし受贈者がその負担を履行しない場合は、贈与者は相当の期間を定めて催告し、それでも履行されなければ、贈与契約自体を解除することができます。
また、負担付贈与は、その「負担」がある分、完全に無償の契約とは言えません。そのため、贈与者の責任も通常の贈与より重くなります。
<重要!負担付贈与の責任>
負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売買契約の売主と同じ担保責任(契約不適合責任)を負います(民法第551条第2項が553条で読み替え)。
つまり、上記の例で、受贈者がちゃんと生活費援助や草刈りをしているのに、もらった家や土地に重大な欠陥(契約不適合)があった場合、贈与者は「タダであげたから」と言って責任を免れることはできず、修補や損害賠償などの責任を負う可能性がある、ということです。
② 定期贈与:毎月の仕送りなど。死亡で効力を失う!
定期贈与(ていきぞうよ)とは、定期的に(例えば、毎年、毎月、毎週など)決まった額の財産を給付することを目的とする贈与契約のことです(民法第552条)。
例:「大学を卒業するまで、毎月10万円を仕送りする」という親から子への約束など。
定期贈与の最も大きな特徴は、その終了事由にあります。
<定期贈与の終了>
定期贈与は、贈与者 または 受贈者 のどちらか一方が死亡すると、その時点で効力を失います(消滅します)。
これは、定期贈与が当事者間の個人的な信頼関係に基づく、一身専属的(いっしんせんぞくてき:その人でなければ意味がない)な性質が強い契約と考えられるためです。例えば、親が亡くなったら、その相続人が仕送りを続ける義務はない、ということですね。
③ 死因贈与:「私が死んだらあげる」契約。遺言と同じで撤回可能?
死因贈与(しいんぞうよ)とは、贈与者の死亡によって効力が生じると定められた贈与契約のことです(民法第554条)。「私が死んだら、あなたに〇〇をあげます」という内容の契約ですね。
これは、贈与者が生きている間に結ぶ「契約」ですが、効力が発生するのが死亡時であり、財産を無償で与えるという点で、「遺言(いごん)」による「遺贈(いぞう)」と非常によく似ています。
そのため、民法では、死因贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する、と定めています。
<重要!死因贈与と遺贈規定の準用>
死因贈与には遺贈のルールが適用されます。その結果、最も重要な効果として、遺言が原則としていつでも自由に撤回できるように、死因贈与契約も、原則として贈与者は(たとえ書面で契約していたとしても)いつでも自由に撤回することができる、と考えられています。
通常の書面による贈与は原則撤回(解除)できないのと比べて、大きな違いですね。ただし、負担付の死因贈与で、受贈者がすでに負担を履行した場合などは、例外的に撤回が制限されることもあります。
※遺言の方式(自筆証書遺言や公正証書遺言など)に関する規定は、死因贈与には準用されません。死因贈与契約自体は、特に方式は定められていません。
仕事を頼む・頼まれる契約!「委任契約」と「請負契約」の違いを徹底比較!
次に、宅建試験で非常によく比較対象として問われる「委任契約」と「請負契約」を見ていきましょう。どちらも誰かに仕事を頼む契約ですが、その目的や当事者の義務・責任には大きな違いがあります。この違いを理解することが、得点の鍵になります!

委任と請負、どっちがどっちか分からなくなりがちですよね。ここでしっかり整理しましょう!
誰かに何かを頼む契約【委任・請負・事務管理】の違いを整理!
本題に入る前に、仕事を頼む・頼まれる関係として、委任、請負、そして後で詳しく見る「事務管理」の基本的な違いを表で簡単に整理しておきましょう。全体像を掴むのに役立ちます。
<委任・請負・事務管理の基本的な違い>
| 項目 | 委任契約 | 請負契約 | 事務管理 |
|---|---|---|---|
| 契約の有無 | あり | あり | なし(法律上の義務なく行う) |
| 目的 | 事務の処理(プロセス重視) (法律行為が多い) | 仕事の完成(結果重視) | 他人の事務処理 (本人の利益のため) |
| 報酬 | 原則無報酬(特約必要) | 原則有償 | なし |
| 受任者/請負人/管理者の主な義務 | 善管注意義務 | 仕事完成義務 契約不適合責任 | 善管注意義務(緊急時は軽減) |
| 解除 | いつでも可能 (損害賠償の場合あり) | 仕事完成前なら可能 (注文者は損害賠償要) | ‐(契約ではない) |
(※表が見にくい場合はスクロールしてください)
この表からもわかるように、特に委任と請負は、「目的(プロセスか結果か)」と「報酬(原則無償か有償か)」、そして「義務・責任(善管注意義務か仕事完成・契約不適合責任か)」が大きく異なります。では、それぞれ詳しく見ていきましょう。
法律行為を任せる「委任契約」のポイント【報酬・義務・解除】
委任契約とは?どんな場面で使われる?
委任契約(いにんけいやく)とは、当事者の一方(委任者:いにんしゃ、頼む人)が法律行為をすること(または事務処理)を相手方(受任者:じゅにんしゃ、頼まれる人)に委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約です(民法第643条)。
委任契約のポイントは、目的が「事務の処理」そのものにあり、必ずしも「結果の達成」までを約束するものではない、という点です。プロセスをきちんと行うことが重視されます。
委任契約の例:
- 弁護士に「裁判で代理人として活動してもらう」ことを依頼する。(勝訴という結果を保証するものではない)
- 税理士に「確定申告の手続きをしてもらう」ことを依頼する。
- 医師に「病気の診察や治療をしてもらう」ことを依頼する。(病気が治るという結果を保証するものではない)
- 不動産会社(宅建業者)に「不動産の売却や賃貸の媒介(仲介)活動をしてもらう」ことを依頼する(媒介契約)。(必ず売れる、借り手が見つかるという結果を保証するものではない)
宅建業者が依頼者(売主や貸主など)と結ぶ「媒介契約」は、法律上、この委任契約(またはそれに準ずる準委任契約)の性質を持つとされています。そのため、委任契約のルールを理解することは、宅建業法を理解する上でも非常に重要になります。
※法律行為でない事務の委託(例:「犬の散歩をお願いする」)は、厳密には「準委任契約」といいますが、基本的なルールは委任契約と同じです。
報酬はもらえるの?原則はタダ?【報酬ルール】
委任契約の報酬については、ちょっと意外かもしれませんが、重要なルールがあります。
<委任の原則=無報酬!>
委任契約は、特約(とくやく:特別な約束)がなければ、原則として無報酬(タダ)です!(民法第648条第1項)。
「えっ、弁護士さんとかタダじゃないでしょ?」と思いますよね。それは、通常、弁護士さんとの間では契約時に「報酬は〇〇円とします」という報酬に関する特約を結んでいるからです。もし特約がなければ、法律上は報酬を請求できないのです。
報酬に関する主なルールは以下の通りです。
- 報酬請求の時期: 原則として、委任事務の処理が完了した後でなければ請求できません(後払い)。(民法第648条第2項)
- 履行割合に応じた報酬: 委任者の責任でない理由で、委任事務の履行が途中でできなくなったり、契約が途中で終了したりした場合は、受任者は、すでにした履行の割合に応じて報酬を請求できます。(民法第648条第3項) (例:裁判の途中で和解した場合など)
- 成果に対して報酬を支払う約束の場合(成果報酬型): 「契約が成立したら報酬〇〇円」のように、成果に対して報酬が支払われる約束の場合は、その成果が引き渡されるのと同時に報酬を支払う必要があります(同時履行)。(民法第648条の2第1項)
宅建業者の媒介報酬も、通常は「売買契約が成立したら成功報酬として〇〇円」という成果報酬型の特約になっていることが多いですね。
受任者の大切な義務【善管注意義務・報告義務】
仕事を任された受任者(例:宅建業者)には、委任者(例:依頼者)に対して、主に次のような大切な義務があります。
- 善管注意義務(ぜんかんちゅういぎむ): 受任者は、委任契約の本旨に従い、善良な管理者としての注意をもって、委任事務を処理する義務を負います(民法第644条)。これは、受任者の職業や専門家としての能力、社会的地位などから考えて、通常期待されるレベルの注意を払って、誠実に仕事をしなさい、という意味です。報酬の有無にかかわらず、この義務は発生します。委任契約における最も基本的で重要な義務の一つです!
- 報告義務: 受任者は、委任者から請求があったときはいつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は遅滞なくその経過及び結果を報告しなければなりません(民法第645条)。
- 受取物等の引渡し・権利移転義務: 受任者は、委任事務を処理する中で受け取った金銭その他の物や、収集した果実(利益)、自己の名で取得した権利などを、委任者に引き渡し、移転しなければなりません(民法第646条)。
かかった費用はどうなる?【費用の前払・償還請求】
委任事務を処理するために必要となった費用(例えば、交通費、通信費、登記費用など)は、基本的には委任者が負担すべきものです。受任者は以下の請求ができます。
- 費用前払請求: 委任事務の処理に費用が必要な場合、受任者は委任者に対して、その費用の前払いを請求できます(民法第649条)。
- 費用償還請求: 受任者が委任事務処理のために必要と認められる費用を立て替えて支出した場合は、後でその費用と支出日以降の利息を委任者に請求(償還請求)できます(民法第650条第1項)。
- 債務弁済請求・担保供与請求: 受任者が委任事務処理のために必要と認められる債務を負担した場合(例:委任者の代わりに何かを購入する契約をした)、委任者に対して自己に代わってその弁済をすることを請求でき、まだ弁済期にないときは相当の担保を供させることができます(民法第650条第2項)。
委任契約をやめたいときは?【解除の自由と注意点・終了事由】
委任契約は、当事者間の個人的な信頼関係を基礎とする契約であるため、その解除(契約の終了)に関しては、他の契約とは異なる特徴的なルールがあります。
- 各当事者からの自由な解除: 委任契約は、委任者・受任者のどちらからでも、いつでも理由なく自由に解除することができます(民法第651条第1項)。「やっぱり頼むのやめた」「もう引き受けられない」が、原則としていつでも言えるのです。
- 損害賠償の可能性: ただし、自由な解除が認められるとはいえ、相手方にとって不利な時期に解除した場合や、委任者が受任者の利益をも目的とする委任(例:成果報酬型の媒介契約など)を解除した場合は、やむを得ない事由がない限り、相手方が被った損害を賠償しなければならない場合があります(民法第651条第2項、第651条の2第3項により読み替え)。
- 当然の終了事由: 以下の事由が発生すると、契約は解除の意思表示がなくても当然に終了します(民法第653条)。
- 委任者 または 受任者 の 死亡
- 委任者 または 受任者 の 破産手続開始の決定
- 受任者 が 後見開始の審判 を受けたこと
<超注意!終了事由のひっかけ>
委任契約の終了事由で特に注意が必要なのは、「後見開始の審判」です。終了するのは「受任者」が後見開始の審判を受けた場合だけであり、「委任者」が後見開始の審判を受けても、委任契約は当然には終了しません!ここは、代理権の消滅事由(本人の死亡・破産・後見開始、代理人の死亡・破産・後見開始で消滅)とも異なる点なので、混同しないようにしっかり区別してください!
仕事の完成を約束する「請負契約」のポイント【報酬・契約不適合責任】
次に、もう一つの「仕事依頼」の契約である「請負契約」です。委任契約との違いを意識しながら見ていきましょう。
請負契約とは?委任との違いは「仕事の完成」!
請負契約(うけおいけいやく)とは、当事者の一方(請負人:うけおいにん、仕事を引き受ける人)がある仕事を完成させることを約束し、相手方(注文者:ちゅうもんしゃ、仕事を頼む人)がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束することによって成立する契約です(民法第632条)。
委任契約が「事務の処理プロセス」を目的としていたのに対し、請負契約は「仕事の完成」という「結果」を目的としている点が決定的な違いです。
請負契約の例:
- 大工さん(請負人)に「家を建てる」ことを依頼する(注文者)。(家という結果の完成が目的)
- クリーニング屋さん(請負人)に「スーツをクリーニングする」ことを依頼する(注文者)。(きれいになったスーツという結果が目的)
- プログラマー(請負人)に「会社のウェブサイトを制作する」ことを依頼する(注文者)。(ウェブサイトという結果の完成が目的)
注文者と請負人の義務は?【報酬支払と仕事完成・引渡し】
- 注文者の主な義務: 約束した仕事の結果(完成した物など)に対して、報酬を支払う義務があります。
- 請負人の主な義務: 約束した仕事を完成させ、もし目的物がある場合はそれを注文者に引き渡す義務があります。そして、完成した仕事や目的物に契約不適合があれば、その責任を負う義務があります。
報酬の支払い時期については、以下のルールがあります。
- 目的物の引渡しが必要な場合: 報酬は、目的物の引渡しと同時に支払わなければなりません(同時履行)。(民法第633条本文)
- 目的物の引渡しが不要な場合: 仕事が完了した後、遅滞なく報酬を支払わなければなりません。(民法第633条ただし書)
仕事の完成・引渡しと報酬支払いは、基本的には同時履行の関係にある、と考えると分かりやすいですね。(ただし、仕事の完成自体は報酬支払いより先です)。
完成した建物に欠陥が!請負人の責任は?【契約不適合責任】
請負契約は、仕事の完成という結果に対して報酬が支払われる有償契約です。そのため、売買契約と同様に、完成した仕事の目的物(例えば、建築された建物)が、種類、品質、数量に関して契約の内容に適合しない場合(=契約不適合)には、請負人は注文者に対して契約不適合責任を負います(民法第559条が売買の規定を準用)。
<請負人の契約不適合責任>
注文者は、請負人に対して以下の権利を追及できます(内容は売買契約の場合と同じです)。
- 追完請求(修補請求): 「欠陥があるから直してください!」(民法562条)
- 報酬減額請求: 「欠陥がある分、代金をまけてください!」(民法563条)
- 損害賠償請求: 「欠陥のせいで損害が出たので賠償してください!」(民法564条で415条など準用)
- 契約の解除: 「こんな欠陥があるなら、もうこの契約はやめます!」(民法564条で541条など準用)
これらの権利を行使できる期間には制限があります。原則として、注文者は、不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しなければ、権利を失ってしまいます(民法第566条)。ただし、請負人が不適合について悪意・重過失の場合は別です。
【例外】請負人が責任を負わないケースとは?(注文者原因)
ただし、完成した仕事の目的物に契約不適合があったとしても、その原因がもっぱら注文者側にある場合には、請負人は責任を負いません。
具体的には、以下のケースでは、注文者は契約不適合責任を追及できません(民法第636条)。
- 注文者が提供した材料の性質によって不適合が生じた場合
- 注文者の与えた指図(指示)によって不適合が生じた場合
例:
注文者が特殊な安い材料を指定して提供し、それを使って建築したら雨漏りが発生した場合や、注文者が無理な設計変更を強く指示し、その通りに施工したら構造的な問題が生じた場合などです。
ただし、ここにも例外の例外があります。
もし、請負人が、注文者から提供された材料や与えられた指図が不適当であることを知りながら、それを注文者に告げなかった場合は、信義則に反するため、請負人は責任を免れることができず、通常通り契約不適合責任を負います。「プロなら、まずいと思ったらちゃんと言ってよ!」ということですね。
頼まれてないけど助けちゃう?「事務管理」と条件付き契約「停止条件」
最後に、契約関係ではないけれど民法で定められている「事務管理」と、契約の効力発生のタイミングに関わる「停止条件」について見ていきましょう。これらも宅建試験で問われることのある知識です。

あともう少し!契約とはちょっと違うけど、大事なルールですよ。
おせっかいも法律行為?「事務管理」とは?【委任との違い】
事務管理(じむかんり)とは、法律上の義務がないにもかかわらず、他人のためにその事務(仕事)を処理することを言います(民法第697条第1項)。
ポイントは「義務がないのに」「他人のために」という点です。つまり、契約(委任など)で頼まれたわけでもなく、法律でそうする義務が定められているわけでもないのに、いわば親切心や義侠心から、他人の用事をやってあげるような状況を指します。「おせっかい」を法律的に扱ったもの、と考えるとイメージしやすいかもしれません。
事務管理の例:
- 長期旅行中で留守にしている隣人の家の屋根が、台風で一部壊れているのを見つけ、頼まれていないけど雨漏りを防ぐために応急処置をしてあげた。
- 道端で倒れている人を見つけ、頼まれていないけど救急車を呼び、応急手当をして介抱した。
- 友人が入院中、頼まれていないけど友人のペットの世話をしてあげた。
事務管理を行う人を「管理者」、助けられる(事務を処理してもらう)人を「本人」と呼びます。
委任契約との最大の違いは、管理者と本人の間に契約関係がないことです。そのため、委任とは異なるルールが適用されます。
緊急時の責任は軽くなる?【緊急事務管理】
頼まれてもいないのに他人の事務に手出しをするわけですから、もし失敗して本人に損害を与えてしまった場合、管理者の責任はどうなるのでしょうか?
原則として、管理者は、委任契約の受任者と同じく、善良な管理者としての注意義務(善管注意義務)をもって事務管理を行わなければなりません(民法第697条など)。
しかし、特に緊急性が高い状況で、本人の生命や財産を守るために行った事務管理については、管理者の責任が軽減されます。
<緊急事務管理の責任軽減>
本人の身体、名誉、または財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をした場合、管理者は、悪意(わざと損害を与えようとした)または重大な過失(著しい不注意)がない限り、その行為によって本人に生じた損害を賠償する責任を負いません(民法第698条)。
つまり、善意で急いで助けようとした結果、多少の失敗(軽過失)があったとしても、悪質でなければ大目に見てあげましょう、というルールです。これにより、困っている人を見たときに、人々がためらわずに助け合いやすくなるように配慮されているんですね。
管理者の義務と権利【通知義務・善管注意義務・費用償還請求】
事務管理を行う管理者には、以下のような義務と権利があります。
- 通知義務: 管理者は、事務管理を始めたことを、原則として遅滞なく本人に通知しなければなりません(ただし、本人が既に知っている場合は不要です)。(民法第700条)
- 善管注意義務: 事務管理は、本人の意思(もし分かれば)に適合し、かつ、本人にとって最も有利な方法で行うように努めなければなりません(これも善管注意義務の一環と考えられます)。(民法第697条)
- 継続義務: 管理者は、本人またはその相続人・法定代理人が管理できるようになるまで、事務管理を継続する義務があります(ただし、継続が本人の意思に反するか、本人に不利なことが明らかな場合は別)。(民法第700条)
- 費用償還請求権: 管理者が本人のために有益な費用(必要費や有益費)を支出した場合(例:壊れた屋根の修理材料費など)、本人に対してその費用の償還(返還)を請求できます(民法第702条第1項、第2項)。
報酬はもらえない!費用前払いもNG!
事務管理はあくまで他人のために無償で行う行為が前提なので、委任契約とは異なり、以下の点が重要です。
- 管理者は、本人に対して報酬を請求することはできません(民法第702条関連)。特約を結ぶこともできません(そもそも契約ではないので)。
- 管理者は、本人に対して費用の前払いを請求することもできません(立て替えた後の償還請求のみ可能です)。
報酬や費用の前払いが認められない点は、委任との明確な違いとして押さえておきましょう。
条件が叶ったら効力発生!「停止条件」付き契約とは?
最後に、契約の効力が発生するタイミングに関わる「停止条件」について見ていきましょう。これも契約の分類とは少し違いますが、契約の効力に関する重要な概念です。
停止条件ってどんなもの?具体例で理解しよう!
停止条件(ていしじょうけん)とは、将来発生するかどうかが不確実な事実(=条件)が成就(じょうじゅ:現実に発生すること)することによって、契約の効力が「発生」する、というタイプの条件のことです(民法第127条第1項)。
つまり、条件が成就するまでは、契約の効力は停止(ストップ)しているけれど、条件がクリアされれば、その時点から契約が有効になる、という仕組みですね。「〇〇したら、△△しますよ」という約束がこれにあたります。
停止条件の例:
- 「次の宅建試験に合格したら、お祝いに10万円あげる」(停止条件付贈与契約)
条件:「宅建試験に合格すること」
効果:合格した時に、「10万円あげる」という贈与契約の効力が発生する。 - (不動産売買でよくある)「買主が銀行から住宅ローンの承認を得られたら、この土地の売買契約は効力を生じる」(いわゆるローン特約)
条件:「住宅ローンの承認が得られること」
効果:承認が得られた時に、「土地の売買契約」の効力が発生する。
契約はいつから有効?条件成就までの効力は?
- 効力発生時期: 停止条件付きの契約は、原則として、条件が成就した時からその効力が生じます(民法第127条1項)。(※当事者の合意で遡及させることも可能ですが、原則は成就時からです)
- 条件成就前の状態: 条件が成就するまでの間は、契約の効力(例:代金を支払う義務や物を引き渡す義務)は発生していません。しかし、契約自体は有効に成立しています。そのため、当事者は、条件が成就した場合に発生するであろう相手方の利益を、不当に害することはできません(民法第128条)。
停止条件付き契約の注意点【解除・妨害・相続】
- 契約の拘束力と解除: 条件成就前で契約の効力が発生していなくても、契約自体は有効に成立しているので、当事者は正当な理由なく一方的に契約を破棄(解除)することはできません。
- 条件成就の妨害: 当事者の一方がわざと(故意に)条件の成就を妨げた場合、相手方は「その条件は成就したものとみなす」ことができます(民法第130条第1項)。(例:ローン特約付き売買で、売主が買主のローン審査に必要な書類の提出に協力せず、わざとローンを不成立にさせた場合、買主は「ローンは承認されたものとして契約は有効だ」と主張できる可能性があります。)
- 条件成就による利益の享受: 逆に、条件が成就することによって不利益を受ける当事者が、わざと条件を成就させた場合は、相手方は「条件は成就しなかったもの」とみなすことができます(民法第130条第2項)。
- 相続: 停止条件付き契約における当事者の権利や義務(条件が成就した場合に発生するであろう期待権など)も、財産権の一種として相続の対象になります。
【宅建業法】停止条件と「8種規制」の関係性
宅建業法には、消費者保護の観点から、宅建業者が自ら売主となる場合に様々な制限(通称:8種規制)が設けられています。その中に、この停止条件と関連するものがあります。
自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限(宅建業法第33条の2):
宅建業者は、原則として、自分が所有していない(または確実に取得できる見込みがない)宅地や建物を、自ら売主となって(宅建業者ではない)買主に売る契約を締結することは禁止されています。
もし、宅建業者が、ある土地を「〇〇の条件が成就したら取得できる」という停止条件付きの契約で購入する予定だったとしても、その条件がまだ成就しておらず、確実に所有権を取得できるかどうかが不確定な段階では、その土地を一般の買主に転売する契約(自ら売主となる場合)は、原則として結んではいけないのです。(※例外として、手付金等の保全措置を講じた未完成物件の売買などは認められる場合がありますが、原則禁止です)。
これは、もし条件が成就せずに宅建業者が土地を取得できなかった場合に、買主に物件を引き渡せなくなるリスクから買主を保護するための重要なルールです。
まとめ
今回は、宅建試験で重要な契約関連のテーマ、「贈与」「委任」「請負」「事務管理」、そして「停止条件」について、それぞれの特徴や違い、重要なルールを詳しく解説しました。
これらのテーマは、単独で問われることもありますが、互いの違いを比較させたり、他の分野(例えば契約不適合責任や宅建業法)と絡めて出題されたりすることも多いです。それぞれのキーワードと内容を正確に結びつけ、違いを明確に理解しておくことが大切ですね。
この記事のポイントまとめ
- 贈与: 無償・諾成契約。書面によらない贈与は履行前なら解除自由、書面なら原則不可。責任は原則軽いが例外あり。負担付贈与は責任重く、死因贈与は撤回可能。
- 委任: 事務処理が目的(プロセス重視)。原則無報酬。善管注意義務が中心。いつでも自由解除可能(損害賠償注意)。死亡・破産・受任者の後見開始で終了。
- 請負: 仕事の完成が目的(結果重視)。原則有償。仕事完成義務と契約不適合責任を負う。仕事完成前なら解除可能(注文者は損害賠償要)。
- 事務管理: 契約なしで他人の事務処理。報酬なし、費用前払いなし。善管注意義務(緊急時は軽減)。費用償還請求は可能。
- 停止条件: 条件成就で効力発生。成就前も契約は有効(拘束力あり)。成就妨害はみなし成就。宅建業法の自己所有に属しない物件の売買制限とも関連。
特に委任と請負の違い(目的、報酬、義務・責任、解除)は頻出なので、何度も比較して頭に叩き込みましょう。贈与の特殊形態や事務管理、停止条件も、基本的な考え方と重要なポイントを押さえておけば、十分対応できるはずです。

今回の記事が、皆さんの宅建合格への道のりを少しでも明るく照らすことができれば、とても嬉しいです。繰り返し学習して、自信を持って本番に臨んでくださいね!