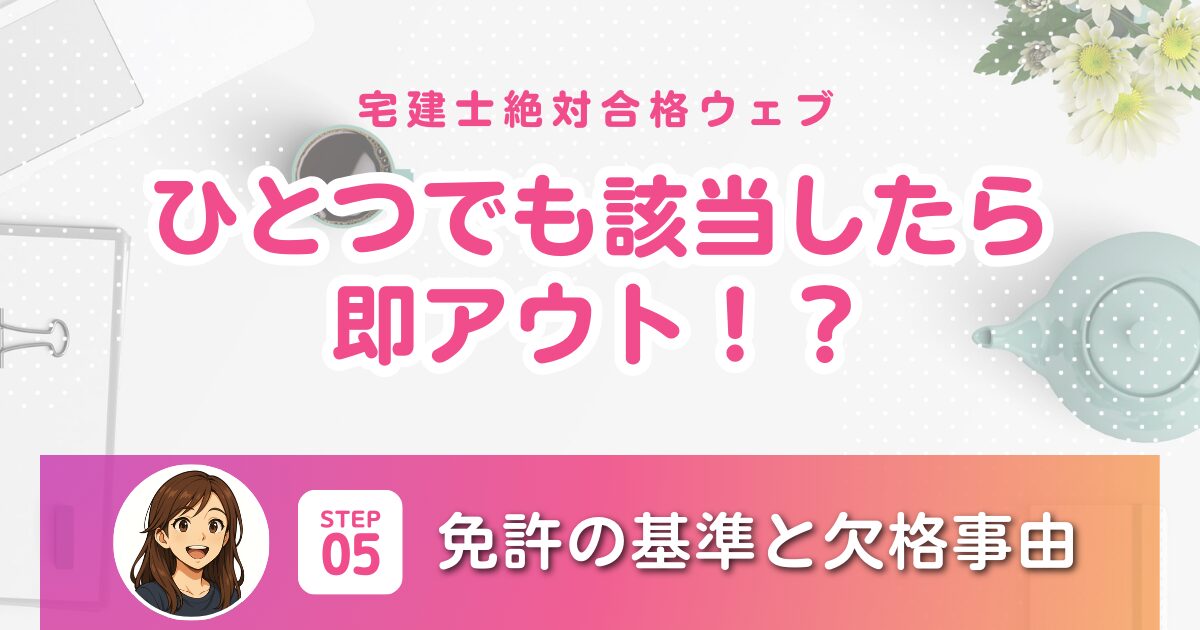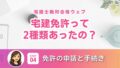宅建業の免許って、申請すれば誰でももらえるわけじゃないって、ご存知でしたか?実は、宅建業を営むのにふさわしくないと判断される一定の基準があって、それに当てはまってしまうと、残念ながら免許を受け取ることができないんです。この基準のことを「欠格事由(けっかくじゆう)」って言うんですよ。
「え、自分は大丈夫かな…」「どんな場合に免許がもらえなくなっちゃうの?」って、ちょっと不安になりますよね。でも大丈夫!どんなことが欠格事由にあたるのか、しっかり理解しておけば、無用な心配も減りますし、試験対策としてもバッチリです!
この記事では、宅建業免許の「欠格事由」について、どんな種類があるのか、そして特に注意したいポイントはどこなのか、詳しく、そして分かりやすく解説していきますね!
この記事でわかること
- 「欠格事由」ってそもそも何なのか
- 宅建業免許が受けられない具体的なケース(欠格事由リスト)
- 特に間違いやすい、重要な欠格事由のポイント解説
- 役員や使用人が欠格事由に該当する場合の影響
- もし免許申請が拒否されたらどうなるのか
そもそも「欠格事由」って何?免許がもらえないケースとは
まずは、「欠格」とか「欠格事由」っていう言葉の意味から確認していきましょう!なんとなく怖いイメージがあるかもしれないけど、正しく理解すれば大丈夫ですよ。
「欠格」の意味をしっかり理解しよう
「欠格(けっかく)」っていうのは、文字通り「必要な資格がないこと」を意味します。シンプルですよね!
これを宅建業の世界に当てはめてみると…
- 宅建業の免許欠格: 宅建業の免許を受ける資格がない(=免許がもらえない)こと。
- 宅建士の登録欠格: 宅建士として登録を受ける資格がない(=試験に受かっても宅建士になれない)こと。

今回は「免許」の欠格事由がテーマですけど、「宅建士登録」にも別の欠格事由があるんですよ。似ている部分も多いですが、少し違う点もあるので、混同しないように注意が必要ですね!
つまり、宅建業を営むための「免許」をもらうためには、この「免許の欠格事由」に当てはまらないことが大前提になる、ということです。
免許の基準=欠格事由!これに当てはまるとNG
宅建業っていうのは、高額な財産である不動産を扱って、たくさんの人の権利関係に関わる、とっても重要な仕事ですよね。だから、誰でも簡単になれるわけじゃなくて、一定の信頼性や適格性が求められるんです。
その信頼性や適格性を判断するための「基準」が設けられていて、この基準を満たさない状態のことを「欠格事由」と呼んでいます。
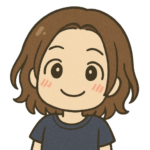
言い換えると、「こういう人は、宅建業を適正に営むのが難しいかもしれないから、免許はあげられませんよ」っていうルールのことですね。
免許を申請する人(個人事業主の場合)や、申請する会社(法人の場合)の役員さん、それから「政令で定める使用人」さん(支店長さんなど、重要なポジションの人です)が、この欠格事由のどれか一つでも当てはまってしまうと、免許を受けることができなくなってしまいます。
ポイントは「一つでも該当したらアウト」という点です! たくさんの項目がありますが、全部クリアしていないと免許はもらえません。自分自身はもちろん、法人の場合は役員などの関係者についても確認が必要になるんですね。
要注意!宅建業免許の欠格事由リストと重要ポイント解説
では、具体的にどんなことが欠格事由になるのか、見ていきましょう!リストアップすると結構な数になりますが、一つずつ丁寧に確認していけば大丈夫ですよ。
まずは全体像をチェック!欠格事由一覧
ここに挙げる項目のどれか一つでも該当すると、宅建業の免許は受けられません。
- 心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができないと判断された者
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 特定の悪いこと(※後述)をして免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(法人の場合、聴聞公示日前60日以内の役員だった者も含む)
- 上記3の免許取消し処分を受けるべきだったのに、その前に廃業の届出をし、その届出の日から5年を経過しない者
- 禁錮以上の刑(死刑、懲役、禁錮)に処せられ、その刑の執行が終わった日(または執行猶予期間が終わった日など)から5年を経過しない者
- 特定の法律違反による罰金刑(※後述)に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者
- 免許の申請前5年以内に、宅地建物取引業に関して不正または著しく不当な行為をした者
- 宅地建物取引業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者
- 暴力団員である、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(いわゆる暴排条項です)
- 暴力団員等がその事業活動を支配している者(会社)
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人(親権者など)が上記1~9、11のいずれかに該当する場合
- 事務所ごとに、専任の宅地建物取引士を規定の人数(従業員の5人に1人以上)設置していない者(会社)

うわぁ…たくさんありますね…。でも、一つ一つ見ていくと、ちゃんと理由があるものばかりです。落ち着いて確認していきましょう!
ここからは、特に試験でも狙われやすく、理解が少し難しいかもしれないポイントをピックアップして、詳しく解説していきますね!
【重要ポイント①】心身の故障ってどんな場合?
最初の欠格事由は「心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない一定の者」です。
これは、例えば、認知症や精神的な障がいなどによって、宅建業を適切に行うために必要な認知、判断、意思疎通をスムーズに行うことが難しいと個別に判断された場合に該当します。
以前は、「成年被後見人」や「被保佐人」に該当すると、それだけで一律に欠格とされていました。でも、法改正があって、今は肩書きだけで判断するのではなく、個々の能力をちゃんと見て、実質的に判断されることになったんです!これは大きな変更点なので、しっかり覚えておいてくださいね。 <
つまり、成年被後見人や被保佐人だからといって、必ずしも欠格になるわけではない、ということですね。個別の審査の結果、大丈夫だと判断されれば免許を受けられる可能性もあるんです。
【重要ポイント②】破産したらもうダメ?復権って?
「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」も欠格事由です。
自己破産などの手続きが始まると、「破産者」という状態になり、一時的に宅建業の免許は受けられなくなります。
でも、ここで重要なのが「復権(ふっけん)」というキーワード!
破産手続きが無事に終わって、裁判所などから「もう大丈夫ですよ」とお墨付き(=復権)をもらえれば、すぐに免許を受けられるようになるんです!

これは朗報ですよね!他の欠格事由みたいに「5年間待たないとダメ」っていうルールは適用されません。復権さえ得れば、すぐにOK!なんです。試験でもよくひっかけ問題で出ますよ!
破産=即5年欠格、ではない! 「復権を得ていない間」が欠格期間です。復権すれば欠格事由は解消されます!
【重要ポイント③】過去の免許取消しや違反の影響は?(役員の連帯責任も!)
過去に悪いことをして免許を取り消された場合なども、一定期間、免許が受けられなくなります。ここ、ちょっと複雑なので、整理して理解しましょう!
以下の理由で免許を取り消された場合、取消しの日から5年間は新たに免許を受けられません。
- 不正の手段で免許を取得した(例:嘘の申請をした)
- 業務停止処分に違反した(例:営業しちゃダメって言われてたのに営業した)
- 業務停止処分に該当するような悪いことをして、その内容が特に悪質だった(情状が特に重い)
これらは、宅建業者としての信頼を大きく損なう行為ですから、ペナルティとして5年間は再チャレンジできない、ということですね。
さらに、法人の場合に注意が必要なのが、役員の連帯責任です。
上記の理由で法人が免許を取り消される際、その「聴聞(ちょうもん)」(=処分を下す前に、言い分を聞く手続きのことです)の公示日(=聴聞やるよ!ってお知らせが出た日)の前60日以内に、その法人の役員だった人も、個人として5年間、免許が受けられなくなってしまうんです!

ええっ!会社がやったことなのに、役員だった人も!?って思いますよね。でも、それだけ役員の責任は重い、ということなんです。
また、ズル賢いことを考える人がいるかもしれません。「免許取消し処分を受けそうだから、その前に会社を畳んじゃえ(廃業しちゃえ)!」と。でも、そんな「処分逃れ」は許されません!
上記の免許取消し事由に該当して、処分決定前に自ら廃業の届出をした場合も、その届出の日から5年間は免許を受けられません。
役員の欠格期間の起算点について 法人の免許が取り消された場合、その当時の役員の欠格期間(5年間)がいつからスタートするかというと、「免許取消処分の日」と、もしその前に廃業していれば「廃業届出日」の、どちらか早い方からカウントします。
役員ってどこまでの範囲?
ここでいう「役員」って、どこまでの人を指すのでしょうか?
基本的には、株式会社の取締役などが該当します。常勤か非常勤かは問いません。
さらに、肩書は取締役じゃなくても、相談役、顧問、執行役などで、実質的に会社に対して強い影響力を持っている人も「役員」とみなされることがあります。

単に「専任の宅地建物取引士」であるだけとか、「政令で定める使用人(支店長など)」であるだけでは、通常はこの「役員」には含まれません。ただし、取締役などを兼任している場合は別ですよ!
【重要ポイント④】刑罰を受けたらどうなる?禁錮刑・罰金刑の違い
過去に犯罪を犯して刑罰を受けた場合も、欠格事由になることがあります。ただし、刑罰の種類によって扱いが違うので注意が必要です。
- 禁錮(きんこ)以上の刑(死刑、懲役、禁錮)の場合:
- どんな罪であっても(例えば、窃盗でも傷害でも詐欺でも)、刑の執行が終わった日、または執行を受けることがなくなった日(時効の完成や執行猶予期間の満了など)から5年間は免許を受けられません。
- 罰金刑の場合:
- こちらは全ての罰金刑が対象ではありません! 以下の特定の法律違反による罰金刑に限られます。
- 宅地建物取引業法違反
- 暴力的な犯罪(傷害罪、現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪など)
- 背任罪(会社などに対して損害を与える裏切り行為)
- これらの罪で罰金刑を受け、その刑の執行が終わった日などから5年間は免許を受けられません。
- こちらは全ての罰金刑が対象ではありません! 以下の特定の法律違反による罰金刑に限られます。

禁錮以上は罪名問わずアウト、罰金刑は特定の罪だけアウト、って覚えるといいですね!ここも試験でよく問われる違いです!
どんな罪で罰金刑だとアウト?暴力的な犯罪の範囲は?
罰金刑の対象になる「暴力的な犯罪」には、具体的にどんなものがあるでしょうか?
宅建業法では、傷害罪、現場助勢罪(ケンカの加勢など)、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪などが挙げられています。
一方で、以下の罪で罰金刑を受けても、それだけでは宅建業免許の欠格事由にはなりません。
- 過失傷害罪(うっかり人にケガをさせた)
- 私文書偽造罪
- 道路交通法違反(スピード違反とか)
- 過失運転致死傷罪
傷害罪はアウトだけど、過失傷害罪はセーフ、というあたりがポイントですね!故意(わざと)か過失(うっかり)かで扱いが変わる罪もあるということです。
【重要ポイント⑤】暴力団関係は絶対NG!
社会的に問題となっている暴力団を排除するため、宅建業法でも厳しい規定が置かれています。
- 暴力団員であること
- 暴力団員でなくなった日から5年を経過しないこと
- 法人の場合、暴力団員等がその事業活動を支配していること(役員に暴力団員がいる、暴力団に資金提供しているなど)
これらに該当する場合は、当然、免許は受けられません。コンプライアンス(法令遵守)の観点からも非常に重要視されている点ですね。

これはもう、絶対にダメ!ってことですね。クリーンな業界であるために、厳しいルールが設けられています。
【重要ポイント⑥】未成年者や専任宅建士不足も欠格事由に
最後に、個人の能力や過去の行為とは少し違うタイプの欠格事由も見ておきましょう。
- 未成年者の場合:
- 原則として、未成年者は単独で有効な法律行為ができないため、そのままでは免許を受けられません。
- ただし、「営業に関して成年者と同一の行為能力を有する未成年者」(例えば、親から宅建業を営むことの許可を得ている場合など)であれば、免許を受けられる可能性があります。
- しかし! その未成年者の法定代理人(親権者など)が、これまで見てきた欠格事由(破産、刑罰、暴力団関係など)のどれかに該当してしまうと、いくら本人の能力があっても、やっぱり免許は受けられなくなってしまいます。
- 専任の宅地建物取引士の不足:
- 宅建業を営む事務所には、法律で定められた数(業務に従事する者5人につき1人以上)の専任の宅建士を置かなければなりません。
- この人数を満たしていない状態では、事務所としての体制が整っていないとみなされ、免許を受けることができません。

未成年者のケースは、本人だけでなく法定代理人のチェックも必要なんですね。専任宅建士の設置義務も、宅建業の適正な運営のための重要なルールです!
もし免許申請が拒否されたら…?
万が一、免許申請をしたけれど、審査の結果、欠格事由に該当するなどの理由で免許が与えられない、という判断(=拒否処分)がされた場合、どうなるのでしょうか?
その場合は、免許権者(国土交通大臣または都道府県知事)は、必ず理由を付けて、書面で申請者に通知しなければならないことになっています。
いきなり「ダメです!」だけじゃなくて、ちゃんと「こういう理由で今回は免許を交付できません」と説明してくれるんですね。納得できない場合は、不服申し立てなどの手続きに進むことも考えられます。
まとめ
今回は、宅建業免許の「欠格事由」について、詳しく見てきました。覚えることが多くて大変だったかもしれませんが、これでどんな場合に免許が受けられないのか、全体像がつかめたのではないでしょうか?
欠格事由は、宅建業の信頼を守るための大切なルールです。試験でも頻出ですし、実務においてもコンプライアンス上、非常に重要になりますので、この機会にしっかりマスターしておきましょう!
最後に、今日の重要ポイントをまとめますね!
- 欠格事由とは: 宅建業免許を受けるための基準を満たさない状態のこと。一つでも該当すると免許は受けられない。
- 主な欠格事由:
- 心身の故障: 個別判断(成年被後見人等でも即アウトではない)
- 破産者: 復権を得ればすぐにOK!(5年待つ必要なし)
- 免許取消し等: 不正手段・業務停止違反・情状重い場合は取消しor廃業から5年。法人の元役員も連帯責任あり!
- 刑罰:
- 禁錮以上は罪名問わず、執行終了等から5年。
- 罰金刑は宅建業法違反・暴力的犯罪・背任罪に限り、執行終了等から5年。
- 暴力団関係: 現役はもちろん、辞めても5年はNG。支配関係もアウト。
- 未成年者: 法定代理人が欠格だとNG。
- 専任宅建士不足: 事務所ごとに規定人数(5人に1人以上)が必要。
- 拒否処分: 免許が不交付の場合は、理由付きの書面で通知される。
宅建業免許の欠格事由は、細かいルールが多いですが、一つ一つ理由を考えながら覚えると理解が深まりますよ。頑張ってくださいね!