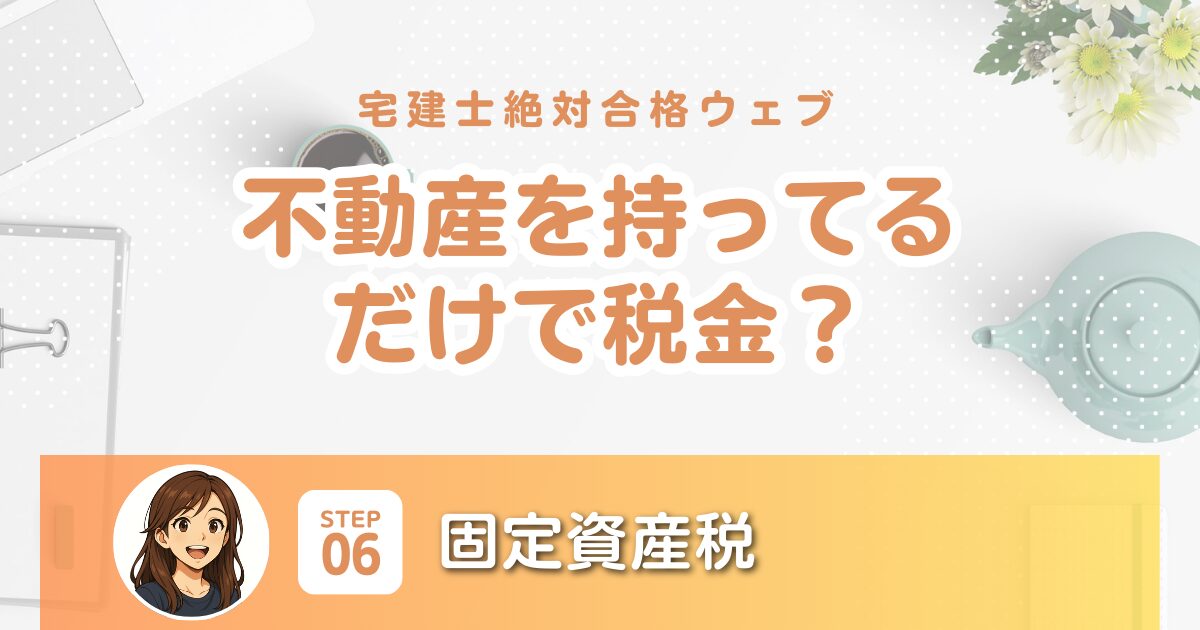宅建の勉強、進んでいますか?税金分野って、数字や専門用語が多くてちょっととっつきにくいですよね…。特に「固定資産税」は、不動産を持っている限り毎年関わってくる身近な税金なのに、いざ勉強するとなると「課税標準って何?」「特例がたくさんあって覚えられない!」なんて声もよく聞きます。
固定資産税は、宅建試験の「税・その他」分野で頻出のテーマです。配点はそれほど多くないかもしれませんが、不動産取引の実務では、お客様への説明で必ずと言っていいほど登場する超重要知識なんです。仕組みが複雑に感じるかもしれませんが、ポイントを押さえてしまえば、決して難しいものではありません。むしろ、仕組みがわかると「なるほど!」と思える部分も多いんですよ。
この記事では、宅建試験で特に問われやすい固定資産税の重要ポイントを、初心者の方にも「そういうことだったのか!」とスッキリ理解していただけるように、計算方法からお得な特例、関連する制度まで、図解や具体例を交えながら丁寧に解説していきます。この記事を読み終える頃には、固定資産税の全体像がしっかりと掴め、苦手意識もなくなっているはずです。しっかり学んで、本試験での貴重な得点源にしちゃいましょう!

固定資産税は、仕組みさえ理解すれば怖くありませんよ!一緒に頑張りましょう!
<この記事でわかること>
- 固定資産税が「誰に」「何に」「いつ」課税されるのか理解できる
- 固定資産税の税額計算のキホン(課税標準と税率)の対策がわかる
- お得な特例措置(住宅用地の特例、新築住宅の減額)の内容と要件のポイントが整理できる
- 固定資産税に関連する制度(縦覧、閲覧、不服申し立て)との違いがわかる
- 固定資産税がかからない「免税点」が明確になる
【基本】固定資産税ってどんな税金?誰がいつ、何に納めるの?
まずは、固定資産税がどんな税金なのか、基本的な仕組みから見ていきましょう。「誰が」「いつの時点の」「何に対して」税金を納めるのか、この3つのポイントをしっかり押さえることが、理解への第一歩です。
固定資産税とは? – 毎年かかる地方税
固定資産税とは、土地、家屋、償却資産(これらをまとめて「固定資産」といいます)を持っている人(所有者)に対して、その固定資産がある市町村(東京23区の場合は都)が課税する地方税です。
不動産の税金というと、家を買った時にかかる「不動産取得税」を思い浮かべる方もいるかもしれませんね。不動産取得税は、不動産を「取得した時」に一度だけかかる税金です。一方、固定資産税は、その固定資産を「所有している限り」毎年課税される、という点が大きな特徴です。持っているだけでコストがかかる、ということですね。
納税義務者は誰? – 1月1日時点の所有者
では、誰が固定資産税を納める義務があるのでしょうか?
固定資産税を納める義務がある人(これを納税義務者といいます)は、毎年1月1日(賦課期日といいます)現在で、固定資産課税台帳という帳簿に「この不動産の所有者はこの人ですよ」と登録されている人です。
原則:その年の1月1日時点の所有者
例外1:土地に質権が設定されている場合 → その質権者(お金を貸していて、土地を担保にとっている人など、実質的に管理している人)
例外2:所有者が不明な場合 → 色々調査しても所有者が誰だか分からない…という場合は、その固定資産を使用者(実際に使っている人)を所有者とみなして課税することができます。ただし、この場合は事前に使用者へ通知が必要です。
ここで宅建試験頻出のひっかけポイント!
もし、年の途中で不動産を売買したら、その年の固定資産税は誰が納めることになると思いますか? 例えば、2025年の5月1日にAさんからBさんに土地が売却されたケースを考えてみましょう。
答えは、Aさん(売主)です!
固定資産税の納税義務者は、あくまでその年の1月1日時点での所有者で判断されます。たとえ5月に所有権がBさんに移ったとしても、2025年度分の固定資産税の納税義務者は、1月1日時点で所有者だったAさんのままなんです。

実際の不動産取引では、売買契約の際に、引渡し日を基準に固定資産税の金額を日割り計算して、買主さんが売主さんに支払う(精算する)ことが慣習として広く行われています。でも、これはあくまで当事者間の取り決め。法律上の納税義務者は、1月1日時点の所有者である売主さんのまま、という点はしっかり区別して覚えてくださいね。
共有名義の場合はどうなるの?
一つの不動産を複数人で所有している状態、いわゆる共有名義の場合はどうなるのでしょうか?
この場合、共有者全員が連帯して納税義務を負います。つまり、「私たちは共有者だから、自分の持ち分だけ払えばいいんでしょ?」とはならず、全員が全額に対して責任を負う、ということです。
市町村からの納税通知書は、代表者一人に送られてくることが多いですが、もし代表者が納税しなかった場合、他の共有者にも納税の義務が生じます。
課税対象は何? – 土地・家屋・償却資産
次に、何に対して固定資産税がかかるのか、課税対象(課税客体)を見ていきましょう。固定資産税の対象となるのは、以下の3種類です。
- 土地:田んぼ、畑、宅地(建物が建っている敷地)、池沼、山林、牧場、原野など、すべての土地が対象です。登記簿に登記されているかどうかは関係ありません。
- 家屋:住家(マイホーム)、店舗、工場、倉庫といった建物全般です。土地に定着していて、屋根と壁があって、独立して使える状態のものが該当します。
もちろん、別荘やセカンドハウス、賃貸アパートなども家屋として課税対象になりますよ。
- 償却資産:ちょっと聞き慣れない言葉かもしれませんね。これは、土地や家屋以外で、事業のために使うことができる有形の資産のことです。
具体例としては、会社やお店で使っているパソコン、コピー機、応接セット、工場の機械、お店の商品陳列棚、看板などが挙げられます。
注意点:個人が家庭で使っている家具や家電(テレビ、冷蔵庫など)は、事業用ではないので償却資産には含まれません。また、自動車は自動車税の対象なので、固定資産税の対象外です。
宅建試験では、償却資産の細かい内容まで問われることは少ないですが、固定資産税の課税対象が「土地・家屋・償却資産」の3つであることは、基本知識としてしっかり覚えておきましょう。
どうやって納付するの? – 普通徴収
固定資産税は、どうやって納めるのでしょうか? 納付方法は「普通徴収」という方式です。
これは、市町村(または都)から送られてくる納税通知書を使って、納税者自身が金融機関の窓口やコンビニエンスストア、口座振替などで納付する方法を指します。
納税通知書は、遅くとも納期限の10日前までに納税義務者に交付されなければならない、と定められています。
通常、固定資産税は年4回の納期(例えば、4月、7月、12月、翌年2月など、市町村によって異なります)に分けて納付することになりますが、希望すれば第1期の納期限までに全額を一括で納付することも可能です。

会社員の方だと、所得税や住民税が給料から天引きされる「特別徴収」に馴染みがあるかもしれませんが、固定資産税は自分で納付する「普通徴収」なんですね。
固定資産税の計算方法|課税標準・税率・特例を理解しよう!
ここからは、実際に固定資産税の税額がどのように決まるのか、計算の仕組みを詳しく見ていきましょう。「課税標準」「税率」「特例」というキーワードが出てきますが、一つずつ丁寧に解説していきますので、安心してくださいね。
税額計算の基本式
固定資産税の税額は、とてもシンプルな計算式で求められます。
固定資産税額 = 課税標準 × 税率
この式に出てくる「課税標準」と「税率」が何なのかを理解することが、税額計算のキモになります。
課税標準とは? – 固定資産課税台帳の登録価格
課税標準とは、簡単に言うと「税額を計算するための基になる価格」のことです。
固定資産税の場合、この課税標準は、原則として固定資産課税台帳に登録された価格となります。この価格のことを一般的に「固定資産税評価額」と呼びます。
じゃあ、この価格は誰がどうやって決めているの?と思いますよね。これは、国(総務大臣)が定めた全国共通のルールである「固定資産評価基準」に基づいて、各市町村長(東京23区の場合は都知事)が、一つ一つの土地や家屋の状況を評価して決定しています。
ここで注意!固定資産税評価額は、実際に市場で売買される価格(時価)とは異なります。一般的には、時価よりも低い価格(目安としては時価の7割程度)になることが多いと言われています。あくまで税金を計算するための評価額、と捉えてくださいね。
価格の見直し(評価替え)は3年に1度
土地や家屋の状況、そして経済状況は常に変化していますよね。そのため、固定資産税評価額もずっと同じではありません。
土地と家屋の固定資産税評価額は、原則として3年ごとに見直しが行われます。この見直しのことを「評価替え」といいます。
評価替えが行われる年度を基準年度といい、次の基準年度までの3年間(第2年度、第3年度)は、原則として基準年度の評価額がそのまま据え置かれます。
据え置き期間中の例外:
土地:地価が大きく下落した場合など、評価額を据え置くことが適当でないと市町村長が認めるときは、評価替えの年度以外でも価格の修正(下落修正)が行われることがあります。(上がる方向への修正はありません)
家屋:増改築や一部取り壊しなど、物理的な変化があった場合は、その翌年度に評価額が見直されます。
税率 – 標準税率は1.4%
次に税率です。固定資産税の税率は、標準税率として1.4%(1.4/100)と定められています。
「標準」という言葉がついているのは、これはあくまで国が「このくらいの税率が標準ですよ」と示しているもので、市町村は、それぞれの財政状況などに応じて、条例によってこれとは異なる税率を定めることも可能だからです(ただし、上限はあります)。とはいえ、実際には多くの市町村がこの標準税率である1.4%を採用しています。
注意!都市計画税との混同に注意!
固定資産税とよく似た税金に「都市計画税」があります。都市計画税は、市街化区域内の土地・家屋に課される税金で、固定資産税とあわせて徴収されることが多いです。都市計画税の税率は、上限(制限税率)が0.3%と定められています。固定資産税の1.4%と混同しないように、しっかり区別して覚えましょう!
ここで、固定資産税と都市計画税の主な違いを表にまとめておきますね。
<固定資産税と都市計画税の比較表>
| 税の種類 | 課税主体 | 納税義務者 | 課税対象 | 課税標準 | 標準税率/制限税率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資産税 | 市町村(23区は都) | 1月1日時点の所有者 | 土地、家屋、償却資産 | 固定資産税評価額 | 標準税率 1.4% | 毎年課税 |
| 都市計画税 | 市町村(23区は都) | 1月1日時点の所有者 | 市街化区域内の土地、家屋 | 固定資産税評価額 | 制限税率 0.3% | 固定資産税とあわせて徴収されることが多い |
【重要】住宅用地の課税標準の特例 – 税負担を軽減!
さあ、ここが固定資産税の学習における最重要ポイントの一つです!しっかり集中して聞いてくださいね。
私たちが生活する上で欠かせない「住宅」。その住宅が建っている土地(これを住宅用地といいます)については、税金の負担を軽くしてあげよう、という特別な措置(特例)が設けられています。
具体的にどうなるかというと、税額計算の基になる「課税標準」の額が、通常の評価額よりも大幅に減額されるんです!
減額の内容は、土地の面積によって2段階になっています。
- 小規模住宅用地(住宅1戸あたり200㎡までの部分):
課税標準 = 価格(評価額) × 1/6 - 一般住宅用地(住宅1戸あたり200㎡を超える部分):
課税標準 = 価格(評価額) × 1/3
(ただし、この特例が適用される土地の面積には上限があり、家屋の床面積の10倍までとされています。)

課税標準が6分の1とか3分の1になるなんて、かなり大きな軽減措置ですよね! 例えば、評価額が3,000万円の土地(面積180㎡)にマイホームが建っていれば、課税標準はなんと 3,000万円 × 1/6 = 500万円 になるんです。税額もぐっと抑えられますね!
計算例を見てみよう!
言葉だけだと分かりにくいので、具体例で計算してみましょう。
【設例】
土地の評価額:4,800万円
土地の面積:300㎡
上記土地の上に、住宅が1戸建っている
この土地の固定資産税の課税標準と税額はいくらになるでしょうか?
- 小規模住宅用地部分(200㎡までの部分)を計算
- 土地全体の評価額は4,800万円なので、1㎡あたりの評価額は 4,800万円 ÷ 300㎡ = 16万円/㎡
- 200㎡分の評価額は 16万円/㎡ × 200㎡ = 3,200万円
- 小規模住宅用地なので、課税標準は 3,200万円 × 1/6 = 約533.3万円
- 一般住宅用地部分(200㎡を超え300㎡までの部分)を計算
- 200㎡を超える部分は 300㎡ – 200㎡ = 100㎡
- 残りの100㎡分の評価額は 16万円/㎡ × 100㎡ = 1,600万円
- 一般住宅用地なので、課税標準は 1,600万円 × 1/3 = 約533.3万円
- 土地全体の課税標準額を合計
- 約533.3万円 + 約533.3万円 = 約1,066.6万円
- 土地の固定資産税額を計算
- 課税標準 × 税率(1.4%) なので、約1,066.6万円 × 1.4% = 約14.9万円
もしこの特例がなかったら、課税標準は4,800万円のままなので、税額は 4,800万円 × 1.4% = 67.2万円 にもなってしまいます。特例があることで、税負担が大きく軽減されているのがわかりますね。
重要チェック!
この住宅用地の特例は、あくまで「住宅」が建っている土地に適用されるものです。建物が建っていない更地や、駐車場として利用されている土地、店舗や事務所のみが建っている土地には、この特例は適用されませんので注意してくださいね。
アパートやマンションのような共同住宅(貸家)が建っている土地の場合は、「住宅の戸数 × 200㎡まで」の部分が小規模住宅用地(1/6)となり、それを超える部分が一般住宅用地(1/3)として計算されます。戸数が多いほど、1/6が適用される面積が広くなるんですね。
【重要】新築住宅の税額減額特例 – 一定期間、税金が半分に!
住宅に関するもう一つの大きな優遇措置が、新築住宅に対する税額の減額特例です。マイホームを新築したり、新築のマンションを購入したりした場合に関係してくる、とっても嬉しい制度ですよ!
これは、一定の要件を満たす新築の住宅について、新たに固定資産税が課税されることになった年度から一定期間、家屋(建物)にかかる固定資産税の税額が1/2に減額されるというものです。
適用要件
この特例を受けるためには、新築された住宅が以下の要件を満たす必要があります。
- 床面積要件:居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下であること。
注意! 一戸建て以外の貸家住宅(アパートなど)の場合は、床面積要件が少し異なり、40㎡以上280㎡以下となります。
- 用途要件:店舗併用住宅のように、住居以外の部分がある場合は、居住部分の床面積が建物全体の床面積の1/2以上であること。
減額される範囲と期間
減額される税金の範囲と、減額が適用される期間も決まっています。
- 減額される範囲:家屋全体ではなく、居住部分の床面積120㎡に相当する部分までの固定資産税額が1/2になります。つまり、すごく広い豪邸(例えば居住部分が200㎡)の場合、120㎡分までの税額は半分になりますが、残りの80㎡分は通常の税額がかかる、ということです。
- 減額される期間:
- 一般の住宅(下記以外):新築後3年度分
- 3階建て以上の中高層耐火住宅・準耐火住宅(マンションなど):新築後5年度分

新築マンションを買うと、最初の5年間は固定資産税が安くなる、なんて話を聞いたことがあるかもしれませんが、それはこの特例のおかげなんですね!
計算例を見てみよう!
ここでも具体例で確認してみましょう。
【設例】
2025年中に新築された木造2階建ての一戸建て住宅
居住部分の床面積:100㎡
家屋の固定資産税評価額(課税標準):1,000万円
税率:1.4%
- 減額前の家屋の固定資産税額を計算
- 1,000万円(課税標準) × 1.4% = 14万円
- 減額される税額を計算
- 床面積100㎡は、減額対象の上限である120㎡以下なので、家屋全体の税額が減額対象になります。
- 減額割合は1/2なので、14万円 × 1/2 = 7万円
- 減額後の固定資産税額(最初の3年間)を計算
- 減額前の税額 – 減額される税額 = 14万円 – 7万円 = 7万円
- ※この住宅は木造2階建て(一般の住宅)なので、減額期間は3年度分です。
- 4年目以降の固定資産税額
- 減額期間が終了するため、原則として減額前の税額である14万円に戻ります。(※ただし、3年ごとの評価替えで評価額自体が変わる可能性はあります)
ポイント! この新築住宅の税額減額特例は、あくまで「家屋(建物)」に対する減額措置です。土地の固定資産税には適用されません。土地については、先ほど説明した「住宅用地の課税標準の特例」が適用されることになります。セットで覚えておきましょう。
【関連知識】固定資産税と一緒に押さえておきたい制度と免税点
固定資産税の計算方法や特例を理解したら、あと少し!関連する制度や、税金がかからない「免税点」についても確認しておきましょう。これらも宅建試験で問われることがある知識です。
縦覧制度 – 他の土地・家屋の価格と比較できる
「うちの土地(家)の固定資産税評価額って、周りと比べて高すぎないかな?」と疑問に思うこともあるかもしれません。そんな時に役立つのが「縦覧(じゅうらん)制度」です。
これは、自分が所有している土地や家屋の評価額が適正かどうかを判断するために、同じ区市町村内にある他の土地や家屋の評価額を見ることができる制度です。
縦覧できる人:
その区市町村の固定資産税の納税者(土地の納税者は土地の価格を、家屋の納税者は家屋の価格を縦覧できます)
縦覧できるもの:
- 土地価格等縦覧帳簿:土地の所在、地番、地目、地積(面積)、価格(評価額)が記載されています。
- 家屋価格等縦覧帳簿:家屋の所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格(評価額)が記載されています。
注意:縦覧帳簿には、プライバシー保護のため、他の土地や家屋の所有者の氏名などは記載されていません。あくまで価格を比較するための情報が載っています。
縦覧期間:原則として、毎年4月1日から、20日またはその年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日までの間です。(市町村によって具体的な期間は異なります)
固定資産課税台帳の閲覧 – 自分の資産情報を確認
縦覧制度と似ているようで少し違うのが「閲覧(えつらん)制度」です。
こちらは、納税義務者が、自分自身が所有する固定資産に関する固定資産課税台帳の記載事項を確認(閲覧)できる制度です。
また、納税義務者だけでなく、その土地を借りている借地人や、その家を借りている借家人なども、権利の対象となっている土地や家屋に関する部分について、固定資産課税台帳を閲覧することが可能です(賃料などの対価を支払っている場合に限ります)。
縦覧と閲覧の違い:
縦覧 → 他人の土地・家屋の「価格」を比較するために見る制度
閲覧 → 自分の(または借りている)固定資産の「詳細情報(価格含む)」を確認する制度
この違いをしっかり押さえておきましょう。
閲覧は、基本的に年間を通じていつでも可能です(手数料がかかる場合があります)。また、固定資産課税台帳の記載事項について、証明書(評価証明書や公課証明書など)の交付を受けることもできます。これは、不動産登記や融資の手続きなどで必要になることがあります。
審査の申出(不服申し立て) – 評価額に納得がいかない場合
固定資産課税台帳に登録された自分の土地や家屋の価格(評価額)について、「どう考えてもこの評価額はおかしい!高すぎる!」と不服がある場合、納税者は諦める必要はありません。
その価格を決定した市町村長(または都知事)に対して直接文句を言うのではなく、中立的な第三者機関である「固定資産評価審査委員会」に対して、「審査の申出(しんさのもうしで)」という形で不服を申し立てることができます。
申出ができる期間:
固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までです。
法改正に注意! 以前はこの期間が「納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して60日以内」でしたが、法改正により「3か月」に延長されました。宅建試験では最新の情報が問われるので、ここはしっかり「3か月」で覚えてください!
固定資産評価審査委員会は、納税者からの申出を受けて、評価額が適正かどうかを審査します。審査の結果、評価額が不当であると認められれば、固定資産課税台帳に登録された価格が修正されることになります。
免税点 – この金額未満なら課税されない!
最後に、固定資産税がかからないケースについてです。
実は、固定資産税には「免税点」という制度があります。これは、課税標準となるべき額が、ある一定の金額に満たない場合(未満の場合)には、固定資産税は課税しませんよ、というボーダーラインのことです。
少額の資産にまで課税するのは、徴税コストの面からも効率的ではない、という考え方に基づいています。
免税点となる金額は、資産の種類ごとに以下のように定められています。
<固定資産税の免税点の表>
| 資産の種類 | 免税点(課税標準額がこの金額未満の場合) |
|---|---|
| 土地 | 30万円 |
| 家屋 | 20万円 |
| 償却資産 | 150万円 |
スクロールできます
重要ポイント! この免税点の判定は、同一人が同一の区市町村内に所有する、それぞれの資産の課税標準額の「合計額」で判断します。
例えば、AさんがB市内に、課税標準額20万円の土地(甲土地)と、課税標準額15万円の土地(乙土地)の2つを持っている場合を考えてみましょう。
甲土地(20万円)も乙土地(15万円)も、それぞれ単独で見れば土地の免税点である30万円未満です。しかし、免税点の判定は合計額で行うため、20万円 + 15万円 = 35万円 となり、30万円以上になります。したがって、この場合、Aさんは甲土地と乙土地の両方について固定資産税が課税されることになります。「土地は土地で合計」「家屋は家屋で合計」して判断する、という点をしっかり覚えておきましょう。
不動産取得税にも免税点がありましたが、金額が異なりますよね!不動産取得税の免税点は、土地は10万円、家屋(新築・増改築)は23万円、家屋(その他売買など)は12万円でした。固定資産税の免税点(土地30万、家屋20万)としっかり区別して覚えてくださいね!
まとめ
今回は、宅建試験の「税・その他」分野の中でも特に重要な「固定資産税」について、基本的な仕組みから計算方法、お得な特例、関連制度、免税点まで、幅広く解説してきました。いかがでしたでしょうか?
覚える項目が多くて「やっぱり税金は大変…」と感じた方もいるかもしれませんが、一つ一つのルールを見ていくと、そこまで複雑怪奇なものではない、と思っていただけたら嬉しいです。
特に、納税義務者(毎年1月1日時点の所有者)、課税標準(原則は固定資産税評価額)、標準税率(1.4%)といった基本事項、そして何よりも2つの大きな特例(住宅用地の課税標準の特例、新築住宅の税額減額特例)は、宅建試験で繰り返し問われる超頻出ポイントです。それぞれの要件や内容を正確に理解し、いつでも引き出せるようにしておくことが合格へのカギとなります。
最後に、今回の記事でお伝えした固定資産税の重要ポイントを、箇条書きで簡潔にまとめておきます。復習に役立ててくださいね。
- 固定資産税とは:毎年1月1日時点の土地・家屋・償却資産の所有者に対し、その資産がある市町村(23区は都)が課税する地方税。
- 納税義務者:原則として、1月1日現在の固定資産課税台帳上の所有者。共有の場合は連帯納税義務あり。
- 納付方法:市町村から送付される納税通知書により納付する普通徴収。
- 課税標準:原則として固定資産課税台帳に登録された価格(固定資産税評価額)。価格は3年に1度評価替えされる。
- 税率:標準税率は1.4%。市町村は条例で異なる税率を定めることも可能。
- 住宅用地の特例:住宅が建つ土地は、面積に応じて課税標準が1/6(200㎡まで)または1/3(200㎡超)に減額される。
- 新築住宅の特例:一定要件を満たす新築住宅は、一定期間(一般3年、中高層耐火等5年)、家屋の税額(120㎡相当分まで)が1/2に減額される。
- 縦覧制度:納税者が、他の土地・家屋の価格を比較できる制度。
- 閲覧制度:納税義務者や借地借家人が、自己の(または借りている)資産情報を確認できる制度。
- 審査の申出:評価額に不服がある場合、納税者は固定資産評価審査委員会に審査の申出ができる(納税通知書交付後3か月以内)。
- 免税点:同一市区町村内の課税標準額の合計が一定額未満(土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円)の場合、課税されない。
固定資産税を学習する際は、不動産取得税との違い(課税タイミング、免税点など)や、都市計画税との関連(課税対象、税率など)も意識すると、知識が整理され、より理解が深まりますよ。

税金分野は暗記要素も多いですが、しっかり対策すれば安定した得点源になります。この記事が、皆さんの宅建試験合格の一助となれば幸いです。頑張ってくださいね!