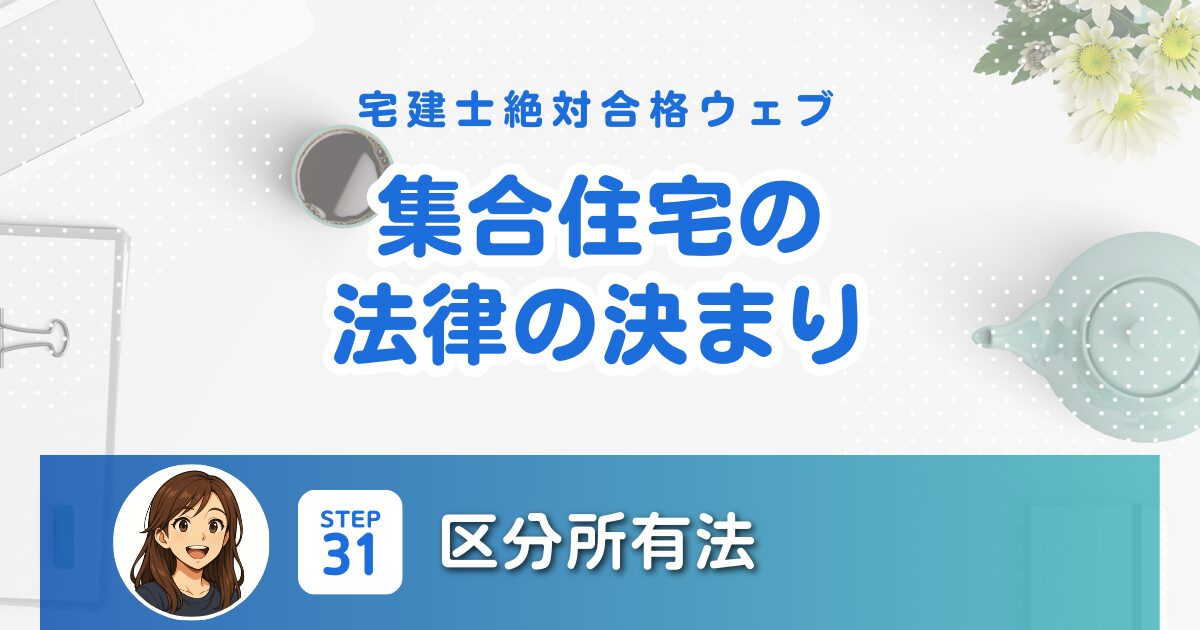マンションに住んでいる方や、これから購入を考えている方にとっては身近なルールですが、いざ法律の言葉で「専有部分」「共用部分」「敷地利用権」なんて言われると、「え、何だっけ?」ってなりがちですよね? 特に、管理組合や集会のルールは、細かい数字も多くて覚えるのが大変!と感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、そんな区分所有法の基本的な考え方、特に「専有部分と共用部分の違い」「敷地に関する権利」「マンションの管理体制」「集会のルール」について、宅建試験で問われやすいポイントを押さえながら、しっかり解説していきます。「どこまでが自分のもの?」「廊下やエレベーターの扱いは?」「土地の権利はどうなってるの?」「マンションの運営って誰がどうやって決めているの?」といった疑問がスッキリ解消されるはずです。

この記事を読めば、区分所有法の全体像がつかめて、複雑に見えるルールも整理しやすくなりますよ。試験対策はもちろん、不動産に関する知識を深めるためにも、ぜひ最後まで読んでみてくださいね!
この記事でわかること
- 専有部分と共用部分の具体的な範囲と違い
- 共用部分の種類(法定・規約)と管理方法
- 敷地利用権と敷地権の意味、分離処分のルール
- 管理組合、管理組合法人、管理者の役割と違い
- 集会の招集方法、決議要件(普通決議・特別決議)
マンションの基本ルール!専有部分と共用部分の違いと管理方法を理解しよう
マンションのような集合住宅のルールを定めているのが「区分所有法」です。まずは、その基本となる「専有部分」と「共用部分」について見ていきましょう。

まずは基本のキ、専有部分と共用部分の違いから押さえましょう!
専有部分ってどこまで?
専有部分とは、簡単に言うと、区分所有権の目的となる建物の部分のことです。マンションで言えば、「301号室」や「405号室」といった、独立した住戸として使えるお部屋の部分を指します。
「独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができる」というのが法律上の定義です。構造上・利用上の独立性が必要なんですね。
壁で区切られていて、他の部分を通らなくても直接外部へ出入りできるような構造がイメージしやすいですね。この専有部分を所有する権利が「区分所有権」です。
共用部分の範囲と種類、持分割合のルール
一方、共用部分とは、専有部分以外の建物の部分、つまり、マンションに住んでいる人みんなで使う部分のことです。具体的には、廊下、階段、エレベーター、エントランスホール、建物の基礎や柱、壁、屋根などがこれにあたります。
電気・ガス・水道の配線や配管なども、専有部分の中を通っている部分以外は共用部分になりますよ。
共用部分の具体例と持分の考え方
共用部分は、原則として区分所有者全員の共有となります。
そして、それぞれの区分所有者が持つ共用部分の持分割合は、規約で特に定めがなければ、その人が持っている専有部分の床面積の割合によって決まります。広い部屋を持っている人ほど、共用部分の持分割合も大きくなる、というイメージですね。
この持分割合は、管理費や修繕積立金の負担割合、そして後で説明する集会での議決権の割合にも影響してくることが多いので、重要なポイントです。
法定共用部分と規約共用部分の違いは?
共用部分には、法律上当然に共用部分とされる「法定共用部分」と、本来は専有部分にできるような部分や付属の建物を、規約によって共用部分とした「規約共用部分」の2種類があります。
- 法定共用部分:廊下、階段、エレベーター室、エントランス、建物の構造上重要な部分(壁、柱、床、屋根など)、専有部分に属さない建物の附属物(電気配線、給排水管など)など、構造上・性質上、当然に共用とされる部分です。これらは、登記をしなくても共用部分として扱われます。
- 規約共用部分:本来は専有部分として独立して使えるような部分(例:管理人室、集会室)や、マンションとは別の付属建物(例:駐車場棟、倉庫)などを、マンションの管理規約で「みんなで使う共用部分にしましょう」と定めたものです。
規約共用部分は、その旨を登記することができます。登記しておけば、「ここは規約によって共用部分とされているんですよ」ということを、マンションの区分所有者以外の人(第三者)にも主張できるようになります。

規約で共用部分にする場合は登記が必要なんですね!
【重要】専有部分と共用部分の持分はセット!分離できない理由
ここが非常に大切なポイントです!
区分所有法の別段の定めがある場合を除き、専有部分とその専有部分に係る共用部分の持分は、原則として分離して処分することができません。
どういうことかと言うと、「301号室の所有権だけ売却して、共用部分(廊下やエレベーターなど)の持分は手元に残しておく」とか、「共用部分の持分だけを、マンションを持っていない第三者に売却する」といったことは、原則できないということです。
考えてみれば当たり前ですよね。マンションの一室(専有部分)を買ったのに、そこに行くための廊下や階段(共用部分)を使う権利がなかったら困ります。逆に、マンションの部屋を持っていない人が、そのマンションの廊下の権利だけ持っていても意味がありません。
専有部分を売却すれば、共用部分の持分も一緒に移転する、ということです。常に一体として扱われるんですね。
【どうやって管理する?】共用部分の管理方法と決議要件
みんなで使う共用部分は、適切に維持管理していく必要があります。その管理方法は、内容によって区分所有者の関与の度合い(必要な賛成数)が変わってきます。
<共用部分の管理行為の比較表>
| 管理行為の種類 | 具体例 | 決議要件 | 規約による定め |
|---|---|---|---|
| 保存行為 | 共用部分の損傷箇所の修理、不法占拠者に対する明渡し請求など、現状を維持するための行為 | 各区分所有者が単独で行える | 規約で別段の定めをすることも可能 |
| 管理行為 | 共用部分の利用方法を定める、共用部分に火災保険をかけるなど、保存行為と変更行為以外の利用・改良行為 | 規約に別段の定めがない限り、集会の普通決議(区分所有者および議決権の各過半数)で決定 | 規約で決議要件を変更可能 |
| 変更行為(軽微変更) | 共用部分の形状や効用の著しい変更を伴わない変更。(例:手すりの設置、防犯カメラの設置、集会室のカーペット張替えなど) | 原則、集会の普通決議(区分所有者および議決権の各過半数)で決定 | 規約で決議要件を変更可能 |
| 変更行為(重大変更) | 共用部分の形状や効用の著しい変更を伴う変更。(例:エレベーターの新設、駐車場の増設、階段室をスロープに変更するなど) | 集会の特別決議(区分所有者および議決権の各3/4以上)で決定 | 規約で「区分所有者の定数」のみ過半数まで減らすことが可能(議決権の3/4以上は変更不可) |
特に変更行為は、その内容が「軽微」なのか「重大」なのかによって、必要な決議要件が大きく異なるので注意が必要です。「形状または効用の著しい変更を伴うか否か」が判断基準になります。

修理くらいなら一人でできるけど、大きな変更にはたくさんの賛成が必要なんですね。
重大変更の特別決議では、区分所有者の「頭数」の要件(3/4以上)は規約で過半数まで下げられますが、「議決権」の要件(3/4以上)は規約でも変えられない、という点も細かいですが重要です。
土地の権利はどうなる?敷地利用権と敷地権の違いとポイント
マンションの建物(専有部分・共用部分)については分かりましたね。では、そのマンションが建っている「土地」に関する権利はどうなっているのでしょうか?ここで登場するのが「敷地利用権」と「敷地権」です。

建物だけじゃなく、土地の権利も大事ですよね。しっかり確認しましょう!
【マンションと土地の関係】敷地利用権ってなに?
敷地利用権とは、区分所有者が、そのマンション(専有部分)を所有するために、マンションの敷地を利用する権利のことです。
多くの場合、マンションの敷地は区分所有者全員の共有になっています(所有権の場合が多いですが、地上権や賃借権の場合もあります)。この敷地に対する共有持分が、実質的に敷地利用権と呼ばれるものになります。
<イメージ>
建物(ハコ)の権利 → 区分所有権(専有部分)+共用部分の持分
土地(地面)の権利 → 敷地利用権
この敷地利用権の割合も、共用部分の持分割合と同じように、規約に別段の定めがない限り、専有部分の床面積の割合によって決まります。
【登記で明確化】敷地権とは?分離処分の禁止ルール
ここでも重要な「分離処分の禁止」のルールが出てきます。
建物(専有部分)を利用するためには、当然その下の土地を利用する権利が必要です。そのため、専有部分と敷地利用権も、原則として分離して処分することはできません。(規約で別段の定めをすれば分離処分も可能ですが、一般的ではありません。)
「301号室の所有権だけ売却して、土地の権利(敷地利用権)は売らない」とか、「土地の権利(敷地利用権)だけを第三者に売却する」ということは原則できません。
そして、このように建物(専有部分)と一体化して、分離処分が原則として禁止されている敷地利用権で、かつ、その旨が登記されたものを特に「敷地権」と呼びます。
つまり、「敷地利用権」のうち、規約で分離処分が認められておらず、登記によって建物と一体化されたものが「敷地権」になる、という関係です。もし規約で分離処分が認められている場合は、「敷地権」としての登記はできません。
敷地権はどこに記録される?登記の仕組み
敷地権の登記は、不動産登記簿のどこに記録されるのでしょうか?
敷地権である旨の登記は、まずマンションの建物全体の情報を記録する「一棟の建物の表題部」に記録されます。ここには、敷地となっている土地の情報(所在、地番、地目、地積)と、敷地権の種類(所有権なのか、地上権なのか等)が記録されます。
さらに、各部屋(専有部分)の情報を記録する「専有部分の建物の表題部」にも、敷地権の種類と、その専有部分が持つ敷地権の割合(持分割合)が記録されます。
敷地権の登記がされると、土地の登記簿には「敷地権である旨の登記」がされ、基本的には土地だけの権利変動(売買や抵当権設定など)の登記はできなくなります。建物(専有部分)の登記をすれば、自動的に敷地権も移転したり、抵当権が設定されたりする仕組みになるのです。

登記を見るだけで、建物と土地の権利関係がセットになっていることがわかるんですね。
マンション運営の要!管理組合・管理者・集会の役割とルール
マンションという共同生活の場を円滑に運営していくためには、しっかりとした管理体制が必要です。その中心となるのが「管理組合」と、そこで行われる「集会」です。
【マンションの自治組織】管理組合ってどんな組織?法人化できる?
管理組合は当然に存在する!
マンションの区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体(管理組合)を構成します。
これは、区分所有関係が成立すると、法律上当然に成立する団体です。「管理組合を結成するための特別な手続き」は不要で、区分所有者になった時点で自動的にそのマンションの管理組合の構成員になります。脱退することもできません。
管理組合法人になるための手続き
管理組合は、一定の手続きを踏むことで「管理組合法人」という法人格を取得することができます。法人になると、組合名義で契約を結んだり、財産を所有したりできるようになります。
管理組合法人になるための要件は以下の通りです。
- 区分所有者および議決権の各3/4以上の多数による集会の決議(特別決議)で、法人となる旨、その名称、事務所の所在地を定めること。
- その主たる事務所の所在地で登記をすること。
管理組合法人になると、必ず「理事」と「監事」を置かなければなりません。理事が法人を代表し、業務を行います。監事は理事の業務執行や法人の財産状況を監査する役割を担います。
【運営のリーダー】管理者って誰がなる?どんな役割?
管理組合法人になっていない、いわゆる「権利能力なき社団」としての管理組合では、その代表者・業務執行者として「管理者」を置くことができます(必ず置かなければならないわけではありません)。
一方、管理組合法人の場合は、先ほど説明した「理事」が法律上当然に管理者としての役割を担います。
管理者は、以下のような人がなることができます。
- 区分所有者の中から選ばれる(理事長など)
- 区分所有者以外の人(例えば、管理業務を委託している管理会社の担当者など)
- 法人(管理会社など)
つまり、管理者は区分所有者でなくても、法人でもなれる、という点がポイントです。
管理者は、規約や集会の決議に従って、共用部分の保存行為を行ったり、集会を招集したり、管理組合の代表として必要な業務を行います。
【みんなで決める場】集会のキホン!招集方法と手続き
集会とは、マンションの管理に関する重要な事項(規約の変更、大規模な修繕、管理者の選任・解任など)を決定するために、区分所有者全員が集まって行う会議のことです。

マンションの意思決定を行う、一番重要な場ですね!
誰がいつ集会を開くの?
- 原則:管理者(または管理組合法人の理事)が、少なくとも年に1回、集会を招集しなければなりません。
- 請求による招集:区分所有者や議決権が一定数に満たないなどの理由で管理者が集会を招集しない場合、区分所有者および議決権の各1/5以上を持つ区分所有者は、管理者(または理事)に対し、会議の目的(議題)を示して集会の招集を請求することができます。
- 管理者がいない場合:管理者が置かれていないマンションでは、区分所有者および議決権の各1/5以上を持つ区分所有者が、直接集会を招集することができます。
この「1/5以上」という割合は、規約で減らすことができます(ゼロにはできません)。
招集通知のルール
集会を招集するには、原則として以下の手続きが必要です。
- 時期:会日(集会の開催日)の少なくとも1週間前までに、招集通知を発する必要があります。
- 内容:通知には、会議の目的となる事項(議題)を示さなければなりません。特に、後述する特別決議が必要な事項については、その議案の要領も通知する必要があります。
- 方法:通知は、各区分所有者に対して行います(通常は郵送など)。
<チェック>
・「1週間前まで」という期間は、規約で伸ばしたり縮めたり(伸縮)することが可能です。
・規約で定めれば、マンション内の見やすい場所に掲示することで、招集通知に代えることも認められています。
・区分所有者全員の同意があれば、これらの招集手続きを省略して集会を開くことも可能です。
集会の決議事項と必要な賛成数(普通決議・特別決議)
集会で何かを決める(決議する)には、原則として、あらかじめ招集通知で示された議題についてのみ決議することができます(普通決議事項については、招集手続きを省略した集会や、規約で別段の定めがあれば、通知外の事項も決議できる場合があります)。
議決権は、原則として共用部分の持分割合(=専有部分の床面積割合)によりますが、規約で別段の定め(例えば、1住戸1議決権など)をすることも可能です。
区分所有者は、書面や代理人(他の区分所有者や同居の親族など)によって議決権を行使することもできます。
決議に必要な賛成数は、その内容の重要度によって異なります。大きく分けて「普通決議」と「特別決議」があります。
<集会の決議要件の比較表>
| 決議に必要な数 | 主な決議事項 | 規約による軽減・加重 |
|---|---|---|
| 普通決議 (区分所有者および議決権の各過半数) |
| 規約で別段の定め(過半数より厳しくも緩くも)が可能 |
| 特別決議 (区分所有者および議決権の各3/4以上) |
| 規約で「区分所有者の定数」のみ過半数まで軽減可能。 (議決権の3/4以上は軽減不可) |
| 特別決議 (区分所有者および議決権の各4/5以上) |
| 規約による軽減・加重は一切不可 |
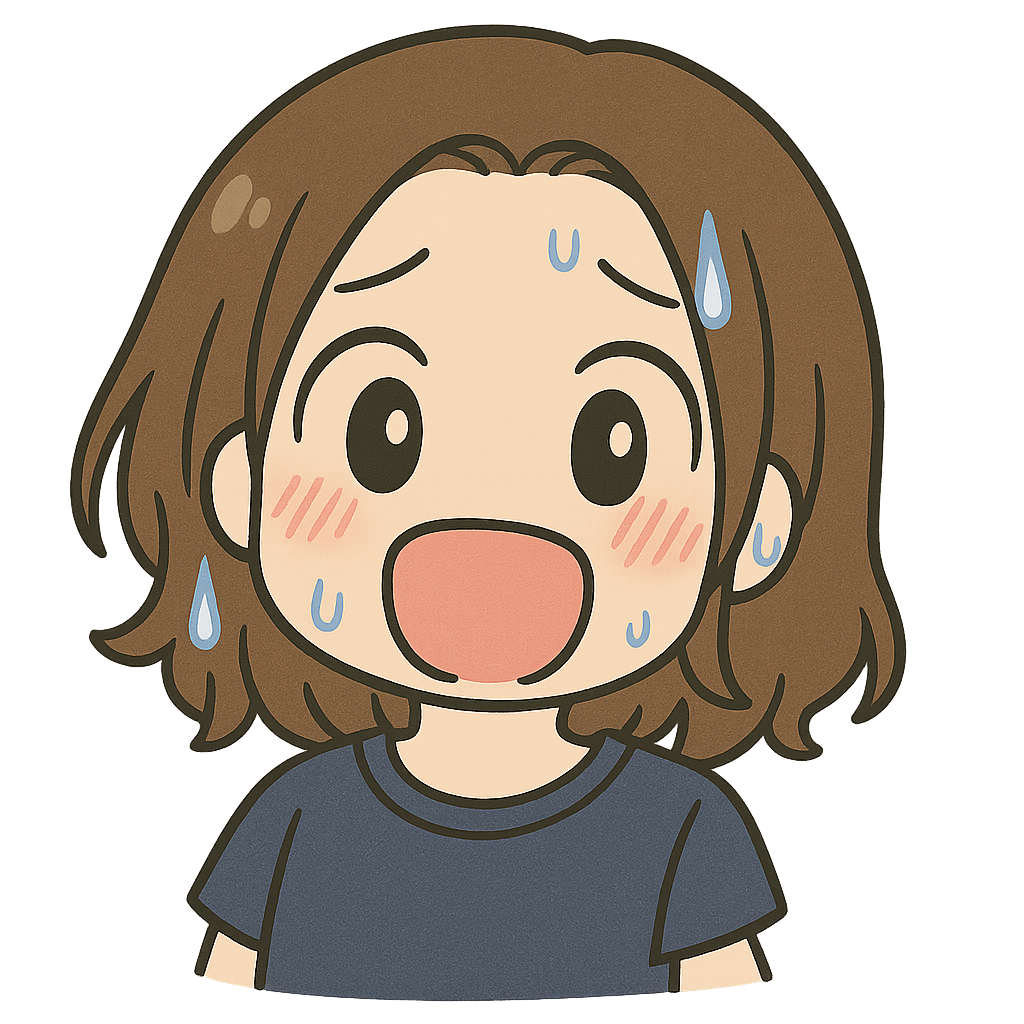
うわー、数字がいっぱい!でも、内容の重大さで必要な賛成数が違うのは理にかなってますね。特に建替えは大変だから、一番厳しいんですね!
<重要>
普通決議は「区分所有者数」と「議決権」の両方で過半数、特別決議は原則として両方で3/4以上(建替えは4/5以上)が必要です。「および」の部分をしっかり意識してくださいね!
賃借人など占有者の意見も聞こう!意見陳述権
マンションには、区分所有者だけでなく、賃貸で住んでいる人(賃借人など)もいますよね。このような専有部分を占有している人(占有者)で、建物またはその敷地・附属施設の使用方法について利害関係を持つ議題がある場合、その占有者は集会に出席して意見を述べることができます。
意見を述べる権利(意見陳述権)はありますが、議決権はありません。しかし、マンション運営においては、実際に住んでいる占有者の意見を聞くことも大切ですよね。
まとめ
今回は、宅建試験でも重要な「区分所有法」の基本について、専有部分・共用部分、敷地利用権・敷地権、管理組合・管理者、そして集会のルールを中心に解説してきました。
覚えることは多いですが、一つ一つのルールには理由があります。マンションという共同生活の場を円滑に維持・運営していくための知恵が詰まっているんですね。
特に、共用部分の管理や集会の決議要件などは、数字が多くて混同しやすい部分ですが、表などを活用しながら、それぞれの違いをしっかり区別して覚えるようにしましょう。
この記事で解説したポイントをまとめると、以下のようになります。
- 専有部分:独立して使用できる住戸部分。所有権の対象。
- 共用部分:廊下やエレベーターなど皆で使う部分。原則、区分所有者全員の共有で、持分は専有部分の床面積割合。法定共用部分と規約共用部分がある。専有部分と分離処分は原則不可。
- 共用部分の管理:保存行為(単独可)、管理行為(普通決議)、変更行為(軽微:普通決議、重大:特別決議[3/4以上])。
- 敷地利用権:専有部分を所有するために敷地を利用する権利。これも専有部分と分離処分は原則不可。
- 敷地権:分離処分できない敷地利用権が登記されたもの。
- 管理組合:区分所有者全員で構成される団体(当然設立)。法人化も可能(特別決議[3/4以上]と登記が必要)。
- 管理者:管理組合(法人化されていない場合)の代表者。区分所有者以外や法人もなれる。
- 集会:マンション管理の意思決定の場。管理者が年1回以上招集。区分所有者の1/5以上で招集請求も可能。
- 集会決議:普通決議(過半数)、特別決議(原則3/4以上、建替えは4/5以上)。占有者には意見陳述権あり。

区分所有法は、マンションに関する様々なルールの基礎となります。試験合格はもちろん、不動産取引の実務においても非常に重要な知識ですので、繰り返し復習して確実にマスターしてくださいね!