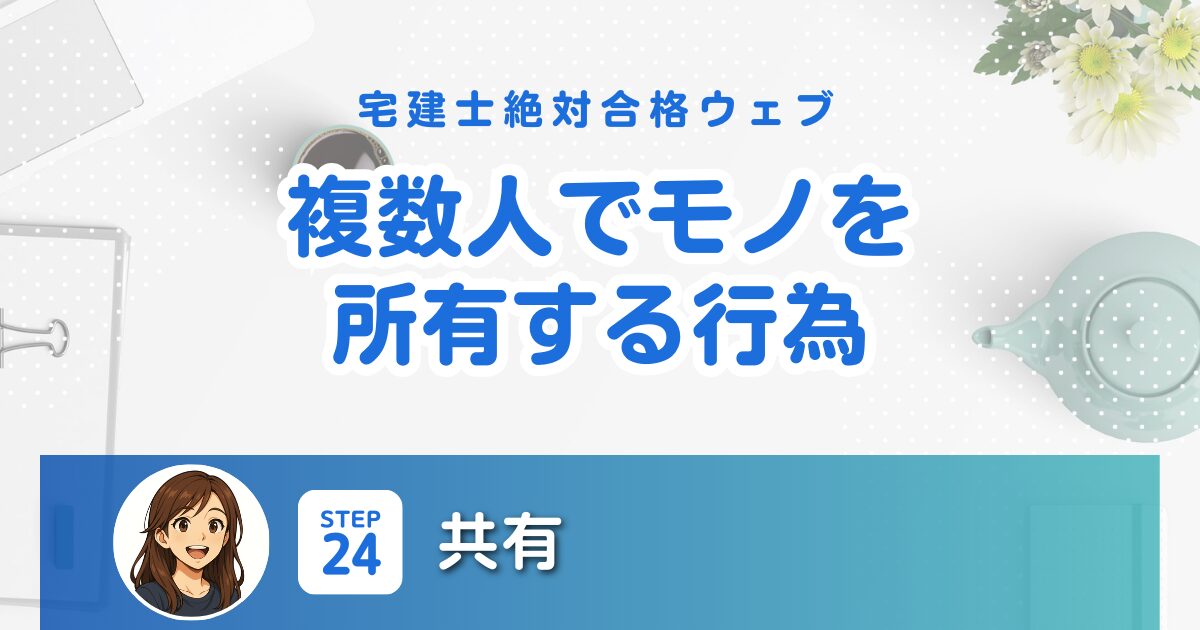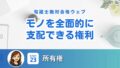宅建の権利関係でたくさんある権利の中でも、「共有」って、なんだか言葉は聞くけど、実際のルールとなると複雑そうで、ちょっと苦手意識を持っている方もいらっしゃるかもしれません。「一つの不動産を複数人で持つなんて、意見が分かれたらどうするんだろう?」「修理したいだけなのに、全員のハンコが必要なの?」「もし共有者の一人が亡くなったら、その権利ってどうなるの?」…考え出すと、色々な疑問が浮かんできますよね。特に相続がきっかけで、急に自分自身が共有者になる、なんて可能性もあるのに、いまいちルールがピンとこない、という方もいるのではないでしょうか。
この記事では、そんな「共有」について、基本となる「持分」の考え方から、共有している物の使い方や維持管理に関するルール(保存・管理・変更という3つの分類がカギ!)、共有関係をやめたいときの「分割」の方法、そしてもしもの時、共有者が亡くなってしまった場合の持分の行方まで、具体的な例をたくさん交えながら、順を追って丁寧に、そして分かりやすく解説していきます!
この記事を最後まで読んでいただければ、複雑に見える共有のルールが頭の中でスッキリ整理されて、試験でどんな角度から問われても「あ、これはあの話だな!」と自信を持って解答できる力が身につきます。特に、ちょっと間違えやすい管理行為と変更行為の違いの区別や、共有者が死亡した場合の持分の帰属先に関するルールをマスターしちゃいましょう!

共有は頻出テーマなので、しっかり学んで得点源にしちゃいましょう!
<この記事でわかること>
- 「共有」とは具体的にどのような状態なのか、そのイメージが掴める
- 共有関係の基礎となる権利の割合「持分」の意味と、その決まり方について理解できる
- 共有物を修理・賃貸・売却するなど、具体的な行為ごとに必要な手続き(誰の同意がどの程度必要か)のルール(保存・管理・変更行為)が明確になる
- 共有関係を解消したい場合の「共有物分割」の方法と、分割を制限するルールについて理解できる
- 共有者の一人が亡くなった場合、その持分が最終的に誰に帰属するのか、その順序とルールがわかる
「共有」の基本と「持分」の考え方をマスターしよう
まずは、「共有」ってそもそもどんな状態を指すのか、そして共有関係を理解する上で絶対に欠かせない基礎知識である「持分」について、しっかりとその意味と考え方を固めていきましょう!ここが全てのスタートラインです。

共有のキホン、「持分」を理解することが最初のステップですよ!
「共有」ってどんな状態?具体例でイメージをつかもう!
共有(きょうゆう)とは、とてもシンプルに言うと、「一つの物(物や権利)を、複数の人が共同で所有している状態」のことです。ポイントは「一つの物」を「複数人」で持っている、という点ですね。
宅建試験で主に問題となるのは、土地や建物といった「不動産」の共有ですが、例えば自動車や絵画のような「動産」を共有することも、もちろんあり得ます。
具体的な例を挙げてみましょう。
例1:共同購入
Aさん、Bさん、Cさんの3人が、お金を出し合って、共同で別荘地にある一戸建ての建物を購入したとします。この場合、この建物はAさん、Bさん、Cさんの3人による「共有物(きょうゆうぶつ)」となり、Aさん、Bさん、Cさんはそれぞれ「共有者(きょうゆうしゃ)」となります。
例2:共同相続
亡くなったお父さん(被相続人)が遺した自宅の土地と建物を、長男Dさんと長女Eさんが共同で相続したとします。この場合、この土地と建物はDさんとEさんの「共有物」となり、DさんとEさんは「共有者」となります。
特に、相続が発生した場合、遺産分割協議がまとまるまでの間や、協議の結果として不動産を複数人で分け合う(共有する)という結論になるケースは少なくありません。ですから、共有は意外と身近な法律問題でもあるんですよ。
「持分」とは?どうやって決まるの?
共有関係において、絶対に理解しておかなければならない、最も基本的な概念が「持分(もちぶん)」です。これは、共有関係のあらゆるルールの基礎となります。
持分とは、共有物全体に対して、各共有者が持っている所有権の割合のことを指します。共有者それぞれが、その共有物に対してどれくらいの権利を持っているかを示すパーセンテージや分数、と考えてください。
先ほどの共同購入の例で考えてみましょう。
別荘の購入価格が4,000万円で、Aさんが2,000万円、Bさんが1,000万円、Cさんが1,000万円をそれぞれ出資したとします。
この場合、それぞれの持分割合は、出資額の割合に応じて以下のようになります。
- Aさんの持分: 2,000万円 / 4,000万円 = 1/2 (または50%)
- Bさんの持分: 1,000万円 / 4,000万円 = 1/4 (または25%)
- Cさんの持分: 1,000万円 / 4,000万円 = 1/4 (または25%)
このように、持分の割合は、原則として共有関係が発生した原因(例えば、共同購入時の出資額の割合、共同相続の場合の法定相続分の割合など)に基づいて決まります。当事者間でこれと異なる割合を合意することも可能です。
では、もし何らかの理由で、各共有者の持分がはっきりしない場合や、特に持分割合を決めずに共有関係が始まった場合はどうなるのでしょうか?
この場合、民法では、各共有者の持分は相等しい(=均等である)ものと推定されます。(民法第250条)
例えば、3人で共有していて持分が不明なら、各自の持分は1/3ずつと推定されるわけです。
【ポイント】
「推定される」という点が重要です。これは、「とりあえず均等だと仮定しましょう」という意味合いです。もし後から、「実はAさんが多く出資していた」という証拠(契約書など)が出てくれば、その証拠に基づいて実際の持分割合が決まることになります。しかし、そうした証拠がない限りは、法律上は平等に扱われる、というルールですね。そして当然ですが、持分はあくまで全体に対する「割合」なので、全ての共有者の持分を合計すると、必ず「1」(または100%)になります。
共有者の権利:自分の「持分」は自由に処分できる!
共有というのは、法的な見方をすると、一つの所有権を、複数の共有者が量的に分割して持ち合っているような状態です。ですから、共有者であるAさん、Bさん、Cさんは、それぞれがその建物の所有権の一部(これを共有持分権といいます)を持っていることになります。
そして、各共有者は、自分が持っている「持分」については、他の共有者の同意を得なくても、原則として自由に処分することができるとされています。(民法には直接的な規定はありませんが、所有権の内容として当然に認められています。ただし、組合財産など一部例外はあります。)
例えば、先ほどの例で、持分1/2を持つAさんは、自分のこの「持分1/2」という権利を、全くの第三者であるDさんに売却したり、お金を借りる際の担保として抵当権を設定したりすることが、BさんやCさんの許可なく、原則として自由にできるのです。
【注意点!】
ここで絶対に混同してはいけないのは、あくまで自由に処分できるのは、自分の「持分」という権利(割合)だけであって、共有物である建物そのものを、Aさんが勝手に全部売却したり、取り壊したりすることはできない、ということです。
共有物全体に関する行為(つまり、建物自体をどうするか)については、これから説明する別のルール(保存・管理・変更)が適用されますからね!ここをしっかり区別しましょう。
どうやって使う?どうやって管理する?共有物の利用ルール【保存・管理・変更】
一つの物を複数人で共有している場合、その物を実際にどうやって使っていくのか、あるいは壊れた時にどうやって修理するのか、誰かに貸す場合はどうやって決めるのか…など、具体的な利用や管理に関するルールを決めておかないと、間違いなくトラブルの元になりますよね。
そこで民法では、共有物に関する共有者の行為を、その内容や影響の度合いによって大きく3つのカテゴリーに分類し、それぞれについて意思決定の方法(誰の同意がどの程度必要か)を定めています。この3つの分類を理解することが、共有のルールをマスターする上で最重要ポイントと言っても過言ではありません!

この3分類をしっかり区別できるようにしましょうね!
共有物に関する行為を3つに分類!
共有物に対する共有者の行為は、その内容によって以下の3つに分けられます。それぞれの行為にどんな具体例が当てはまるのか、そして決定には何が必要なのかを見ていきましょう。
- 保存行為(ほぞんこうい)
- 管理行為(かんりこうい)
- 変更行為(へんこうこうい)(処分行為を含むこともあります)
なぜこの3つに分ける必要があるのか? それは、どの行為に該当するかによって、「共有者の一人が単独でできるのか」、「持分の過半数で決められるのか」、それとも「共有者全員の同意が必要なのか」という、意思決定のルールが変わってくるからです。さあ、一つずつ詳しく見ていきましょう!
【保存行為】共有物を維持するための行為は「単独」でOK!
保存行為とは、文字通り、共有物の価値や現状を維持するための行為、つまり、共有物が壊れたり価値が下がったりするのを防いだり、共有者の権利を守ったりするための行為を指します。「現状維持」や「権利保全」がキーワードです。
具体例としては、以下のようなものが挙げられます。
- 共有している建物の屋根が雨漏りしているので、その修理をすること。
- 共有している土地に、誰かが勝手にゴミを捨てていった場合に、その撤去を求めること(不法投棄の排除)。
- 共有している不動産に、権利がないのに勝手に住み着いている不法占拠者がいる場合に、その人に対して「出ていってください!」と明け渡しを請求すること。
- 共有不動産の登記名義が事実と異なっている場合に、それを正しい状態に直す更正登記を申請すること。
- 共有物について発生した損害賠償請求権などの債権の時効を中断(更新)させるための手続きをすること。
これらの保存行為は、基本的には共有物の現状を維持するものであり、他の共有者にとっても不利益になることは通常ありません。むしろ、放置すると共有者全員にとってマイナスになることが多いですよね。
そのため、民法では、これらの保存行為は、各共有者が単独で(つまり、他の共有者の同意を得ずに一人で)行うことができると定めています。(民法第252条第5項)
確かに、雨漏りを修理するのに、いちいち遠方に住んでいる他の共有者全員のハンコを集めていたら、建物がどんどん傷んでしまいますもんね。緊急性が高い場合もあるので、単独でできるというのは合理的です。
【管理行為】利用や改良に関する行為は「持分の価格の過半数」で決定!
管理行為とは、共有物の性質を変更しない範囲で、共有物を利用したり、改良したりする行為のことです。保存行為(現状維持)よりも一歩進んで、共有物を積極的に活用したり、その価値を高めたりするような行為をイメージすると分かりやすいでしょう。「活用・改良」がキーワードです。
具体例としては、以下のようなものが挙げられます。
- 共有している建物を、第三者に賃貸する契約を結ぶこと、またはその賃貸借契約を解除すること。
- 賃貸する場合の賃料(家賃)の額を決定したり、変更したりすること。
- 共有している空き地を、駐車場として貸し出すこと。
- 共有している通路(私道)が砂利道で使いにくいので、アスファルト舗装にすること。(ただし、あまりに大規模なものや性質を変えるようなものは、次の「変更行為」にあたる可能性もあります。)
- 持分の過半数を持っている共有者が、自分の判断で、少数持分者(その共有物の利用について特に取り決めがない場合)に対して、共有物を使用させること。
- 共有物の管理に関する委任契約などを結ぶこと。
これらの管理行為を行うためには、どうすればいいのでしょうか? 全員の同意が必要なのでしょうか?
民法では、管理行為は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決定する必要がある、と定めています。(民法第252条第1項本文)
【超・超・重要ポイント!】
ここ、宅建試験で本当に、本当によく問われる点です! 意思決定の基準となるのは、「共有者の頭数(人数)」の過半数ではなく、「持分の価格(=持分割合)」の過半数である、という点です! 絶対に間違えないでください!
再び、Aさん(持分1/2)、Bさん(持分1/4)、Cさん(持分1/4)が建物を共有している例で考えてみましょう。この建物を第三者Xさんに貸す(賃貸借契約を結ぶ)という管理行為を決定したい場合、誰の賛成が必要でしょうか?
- Aさん(1/2)だけが賛成しても、持分はちょうど半分(1/2)であり、「過半数(1/2を超える)」には達していません。したがって、Aさん一人だけでは賃貸借契約を結ぶことはできません。
- Aさん(1/2)とBさん(1/4)の二人が賛成すれば、合計持分は 1/2 + 1/4 = 3/4 となり、これは過半数(1/2)を超えています。したがって、AさんとBさんの賛成があれば、Cさんが反対していても、この建物をXさんに賃貸することができます。
- 同様に、Aさん(1/2)とCさん(1/4)の賛成でも、合計持分3/4で決定できます。
- Bさん(1/4)とCさん(1/4)の二人だけが賛成しても、合計持分は 1/4 + 1/4 = 1/2 であり、過半数には達していません。したがって、BさんとCさんだけでは決定できません。(Aさんの賛成が必要になります。)

持分が多い人の意見が通りやすい仕組みになっています。でも、「過半数」だから、ちょうど半分(50%)ぴったりではダメで、50%を少しでも超える必要がある、という点も要注意ですね!
ちなみに、2023年4月施行の民法改正により、以前は解釈が分かれることもあった、期間の短い賃貸借(例えば、建物なら3年以内、土地なら5年以内の賃貸借)や、使用貸借(タダで貸すこと)なども、この「管理行為」として、持分価格の過半数で決定できることが明確化されました。これも改正点として押さえておくと良いでしょう。
【変更・処分行為】重大な変更や売却は「全員の同意」が必要!
変更行為とは、共有物の物理的な形状や性質を大きく変えてしまう行為を指します。また、「処分行為」も、共有物に対する権利そのものを失わせたり、他人に移転させたりする重大な行為として、変更行為と同様に扱われることが多いです。「根本的な変更・権利処分」がキーワードです。
具体例としては、以下のようなものが挙げられます。
- 共有している建物を増築したり、大規模なリフォーム(間取り変更など)をしたりすること。
- 共有している土地の種類(地目)を変えて、例えば畑だった土地を宅地として造成すること。
- 共有している建物や土地そのものを全部、第三者に売却すること。
- 共有している不動産全体に、抵当権を設定すること(つまり、共有物全体を借金の担保に入れること)。
- 共有している更地(建物がない土地)の上に、新たに建物を建てること。
これらの変更・処分行為は、共有物の状態や権利関係を根本的に変えてしまう、非常に影響の大きい行為です。そのため、これらの行為を行うためには、どうすれば良いでしょうか?
民法では、変更・処分行為を行うためには、共有者全員の同意が必要である、と定めています。(民法第251条第1項)
【絶対条件!】
これは非常に厳しい要件です。たとえ、ある共有者が共有物の持分の99%を持っていたとしても、残りのたった1%の持分を持つ共有者が一人でも反対すれば、原則としてその共有物全体を売却したり、大規模な変更を加えたりすることはできません。全員一致が原則なんです。

それはそうですよね。自分が共有者になっている家が、自分の知らない間に勝手に売られてしまったり、全く違う用途の土地に変えられてしまったりしたら、たまったもんじゃないですもんね。全員の同意が必要なのは当然かもしれません。
最後に、これら3つの行為類型と決定要件を表にまとめておきましょう。この表は何度も見返して、頭に叩き込んでください!
<保存・管理・変更(処分)行為のまとめ>
| 行為の種類 | 内容のイメージ | 具体例 | 意思決定の要件 | 根拠条文 |
|---|---|---|---|---|
| 保存行為 | 共有物の現状維持・権利保全 | ・雨漏り修理 ・不法占拠者への明渡請求 ・時効中断(更新)措置 | 各共有者が単独で可能 | 民法第252条第5項 |
| 管理行為 | 性質を変えない範囲での利用・改良 | ・賃貸借契約(締結・解除) ・短期賃貸借、使用貸借 ・駐車場としての利用 | 持分の価格の過半数で決定 (共有者の頭数ではない!) | 民法第252条第1項 |
| 変更(処分)行為 | 物理的・法律的な重大な変更、権利処分 | ・増改築、宅地造成 ・共有物全体の売却 ・共有物全体への抵当権設定 ・土地への新規建築 | 共有者全員の同意が必要 | 民法第251条第1項 |
共有関係を解消したい!「共有物分割」と「共有者の死亡」のルール
共有関係は、複数人で協力して物を管理・利用できるというメリットがある一方で、意見がまとまらなかったり、管理や費用の負担が複雑になったりするというデメリットもあります。「もういっそのこと、この共有関係を解消したい!」と考える共有者が出てくることも、当然あり得ますよね。
ここでは、共有関係を終了させるための「共有物分割」という手続きと、共有関係に変化が生じるもう一つの重要な場面、「共有者の一人が亡くなった場合」の持分の行方について、そのルールを詳しく見ていきましょう。

共有って、続けるのも大変なんです。やめたい時や、もしもの時のルールも知っておかないと!
いつでも解消できる?「共有物分割請求権」とは
共有者としては、「いつまでも他の人と一緒に物を持ち続けるのは煩わしい」「自分の権利分をはっきりさせて、単独で自由に使えるようにしたい!」と思うことがありますよね。
民法では、そのような共有者の意思を尊重し、原則として、各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができると定めています。(民法第256条第1項本文)
この権利を「共有物分割請求権(きょうゆうぶつぶんかつせいきゅうけん)」といいます。
【強力な権利!】
この請求権は、非常に強力な権利とされています。なぜなら、他の共有者が「分割には反対だ!」と言っていても、共有者の一人が「分割したい!」と請求すれば、最終的には必ず分割の手続きが進められることになるからです。他の共有者の同意は不要で、共有者の一人から一方的に請求できる点がポイントです。これは、共有状態が継続することによる不都合を解消するための、共有者の基本的な権利として認められているんですね。
では、実際に分割請求がされた場合、どのようにして共有物を分けるのでしょうか? 分割の方法には、大きく分けて「協議による分割」と「裁判による分割」があります。
① 協議による分割:まずは話し合いで
分割請求があった場合、まずは共有者全員で話し合って、どのように分割するかを決めるのが基本です。(協議分割)
話し合いで決めることができる分割方法としては、主に以下の3つがあります。
- 現物分割(げんぶつぶんかつ):
共有物を物理的に分けて、それぞれの部分を各共有者が単独で所有する方法です。例えば、広い土地であれば、持分割合に応じて土地を測量して分け(分筆し)、それぞれの土地を単独所有にする、といった方法です。 - 代金分割(だいきんぶんかつ):
共有物を全体として第三者に売却し、その売却代金を持分割合に応じて分配する方法です。建物のように物理的に分けるのが難しい場合や、分けると価値が下がってしまう場合などによく用いられます。 - 価格賠償(かかくばいしょう):
共有者の一人が他の共有者の持分を買い取って、その共有物を単独で所有する方法です。持分を失う共有者には、その対価として適正な価格(代償金)が支払われます。これも「全面的価格賠償」と呼ばれ、協議で合意できれば可能です。(※裁判分割でも認められる場合があります。)
② 裁判による分割:話し合いがまとまらない場合
もし、共有者間での話し合い(協議)がまとまらない場合(例えば、分割方法で意見が対立する、そもそも話し合いに応じてくれない共有者がいるなど)は、共有者は裁判所に共有物分割の訴えを起こすことができます。(民法第258条)
裁判所は、当事者の主張を聞いた上で、どのように分割するのが最も公平で適切かを判断し、分割方法を命じることになります。
裁判所が命じる分割方法としては、
- まずは現物分割ができるかどうかを検討します。
- 現物分割が不可能(物理的に分けられない、分けると著しく価値が下がるなど)な場合や、現物分割が可能でも価格賠償が相当と認められる場合には、価格賠償(特定の共有者に取得させ、他の共有者には賠償金を支払わせる)を命じることがあります。
- 現物分割も価格賠償も適切でないと判断された場合には、最終的に代金分割、つまり共有物を競売にかけて、その売却代金を持分割合に応じて分配するよう命じることが多いです。(競売による代金分割)
裁判になると、どの分割方法になるかは最終的に裁判所の判断に委ねられることになります。競売になると市場価格より安くなる可能性もあるので、できれば当事者間の話し合いで円満に解決するのが理想的ですね。
分割しない約束もできる?「不分割特約」
原則として「いつでも分割請求できる」のが共有物のルールですが、「いや、この共有物はみんなで大事に維持していきたいから、しばらくは分割しないでいようよ」といった約束をすることも、もちろん可能です。
このように、共有者間で、共有物を分割しない旨の契約(合意)をすることを「不分割特約(ふぶんかつとくやく)」といいます。(民法第256条第1項ただし書)
この特約を結んでおけば、その期間中は、たとえ共有者の一人が「やっぱり分割したい!」と言い出しても、分割請求をすることができません。
ただし、この不分割特約を結べる期間には、上限が定められています。その期間は、5年を超えることができません。もし、契約で「10年間は分割しない」と定めたとしても、その特約は5年間だけ有効とされ、5年経過後はいつでも分割請求ができるようになります。
また、この不分割特約は、期間が満了した後に更新することも可能です。ただし、更新する場合も、その更新の時から5年を超える期間を定めることはできません。(民法第256条第2項)
【数字を覚えよう!】
「分割しない」という約束(不分割特約)もできるけど、その有効期間は最長で5年まで! 更新する場合も、その更新時から最長で5年! この「5年」という数字は、宅建試験の選択肢でひっかけ問題としてよく使われますので、確実に覚えておきましょう!
もし共有者の一人が亡くなったら…持分はどうなる?
最後に、共有関係において避けて通れない問題、共有者の一人が亡くなってしまった場合、その人が持っていた「持分」は一体どうなるのか、というルールについて見ていきましょう。これは実務でも非常によく遭遇するケースであり、試験でも重要なポイントです。
共有持分も、個人の財産権(所有権の一部)ですから、その人が亡くなった場合(法律用語で「被相続人」と言います)、基本的には相続の対象になるのが大原則です。
では、具体的に誰に持分がいくのか、順を追って見ていきましょう。
① まずは相続人が承継する
亡くなった共有者に、配偶者やお子さん、親、兄弟姉妹といった法律上の相続人がいる場合は、その共有者の持分は、原則として相続人に承継(相続)されます。(民法第896条)
もし相続人が複数いる場合は、遺産分割協議によって特定の相続人が持分を取得するか、あるいは相続人全員でその持分をさらに共有する(相続人間の共有関係が新たに発生する)ことになります。
② 相続人がいない場合は? → 特別縁故者へ?
では、亡くなった共有者に、法律上の相続人が一人もいなかった場合はどうなるのでしょうか?
この場合、すぐに他の共有者のものになるわけではありません。まず、亡くなった方(被相続人)と特別な関係にあった人がいれば、その人が持分を取得できる可能性があります。そのような特別な関係にあった人のことを「特別縁故者(とくべつえんこしゃ)」と言います。
具体的には、
- 被相続人と生計を同じくしていた者(内縁の妻・夫など)
- 被相続人の療養看護に努めた者(長年介護してくれた人など)
- その他、被相続人と特別の縁故があった者(親密な友人など)
これらの「特別縁故者」と認められる人が、相続人がいないことが確定した後、一定期間内に家庭裁判所に「財産をください」と申し立てて、それが家庭裁判所に認められれば、共有持分を含む相続財産の全部または一部を取得することができます。(民法第958条の2)
特別縁故者として財産をもらうためには、家庭裁判所への申し立てと、裁判所の審判が必要です。自動的にもらえるわけではない点に注意してくださいね。
③ 相続人も特別縁故者もいない場合 → 他の共有者へ!
亡くなった方に相続人もおらず、かつ、特別縁故者もいない場合、または特別縁故者への財産分与が行われてもなお共有持分が残った場合、その残った持分は、最終的にどうなるのでしょうか?
通常の相続財産であれば、最終的には国のもの(国庫)に帰属するのが原則です。
しかし! 共有持分に限っては、特別なルールがあります!
この場合、その亡くなった(相続人不存在等の)共有者の持分は、国のものになるのではなく、他の共有者に、それぞれの持分割合に応じて帰属することになるんです!(民法第255条)
例:A(持分1/2)、B(持分1/4)、C(持分1/4)の3人で不動産を共有していて、Aさんが亡くなり、Aさんには相続人も特別縁故者もいなかったとします。
この場合、Aさんの持分1/2が、残りの共有者であるBさんとCさんに、彼らの現在の持分割合(B:C = 1/4 : 1/4 = 1:1)に応じて、分け与えられます。
つまり、Aさんの持分1/2を、BさんとCさんが半分ずつ(それぞれ1/4ずつ)取得することになります。
結果として、Bさんの持分は、元の1/4 + 新たに取得した1/4 = 1/2 になり、
Cさんの持分も、元の1/4 + 新たに取得した1/4 = 1/2 になります。
したがって、共有者が死亡した場合の持分の行方は、以下の優先順位で決まることになります。
① 相続人 → ② 特別縁故者 → ③ 他の共有者

相続人がいない場合の相続財産は、普通は最終的に国庫にいく流れをイメージしがちですが、共有持分だけは特別扱いで、最終的には他の共有者にいく、というルールになっているんですね。
まとめ
お疲れ様でした! 今回は、宅建試験の権利関係の中でも特に重要で、頻出テーマである「共有」について、その基本概念から、具体的な利用・管理のルール、そして共有関係の解消や共有者の死亡といった少し応用的な内容まで、詳しく見てきました。
「共有」とは一つの物を複数人で所有する状態であり、各共有者はその権利の割合である「持分」を持っているんでしたね。そして、共有物をどう扱うかについては、「保存行為」「管理行為」「変更・処分行為」という3つの分類があり、それぞれ意思決定のルール(単独、持分過半数、全員同意)が異なることが非常に重要でした。
また、共有関係を解消したい場合には、原則としていつでも「分割請求」ができ、その方法(現物分割、代金分割、価格賠償)や、分割しない約束(不分割特約、最長5年)のルールもありました。最後に、共有者の一人が亡くなった場合の持分の行方には、「相続人 → 特別縁故者 → 他の共有者」という、通常の相続とは異なる特別な帰属順位があることも学びました。
最初は少しとっつきにくいと感じたかもしれませんが、この記事を通して、具体的な例やルールを一つ一つ確認していくことで、共有に関する知識が整理され、だいぶ理解が深まったのではないでしょうか。
最後に、今回の重要ポイントをまとめます。
- 共有とは一つの物を複数人で所有すること。各人は原則として出資額等に応じた持分を持つ(持分不明なら均等と推定)。
- 共有物の保存行為(修理、不法占拠者への明渡請求など)は、各共有者が単独で可能。
- 共有物の管理行為(賃貸借契約、駐車場利用など)は、持分の価格の過半数で決定(頭数ではない!)。
- 共有物の変更・処分行為(増改築、共有物全体の売却、全体への抵当権設定など)は、共有者全員の同意が必要。
- 各共有者は原則としていつでも共有物の分割を請求できる(共有物分割請求権)。
- 分割しない契約(不分割特約)も可能だが、期間は最長5年(更新も更新時から最長5年)。
- 共有者が死亡した場合、その持分は ①相続人 → ②特別縁故者 → ③他の共有者 の順で帰属する(国庫にはいかない!)。
共有は、権利関係の中でも特に具体的な事例問題として出題されやすく、また、不動産実務においても非常に関わりの深い分野です。今回の内容をしっかりと復習し、過去問演習などを通して知識を定着させ、試験本番での確実な得点源にしてくださいね!

繰り返し問題を解いて、ルールの違いを正確に理解することが合格へのカギですよ!