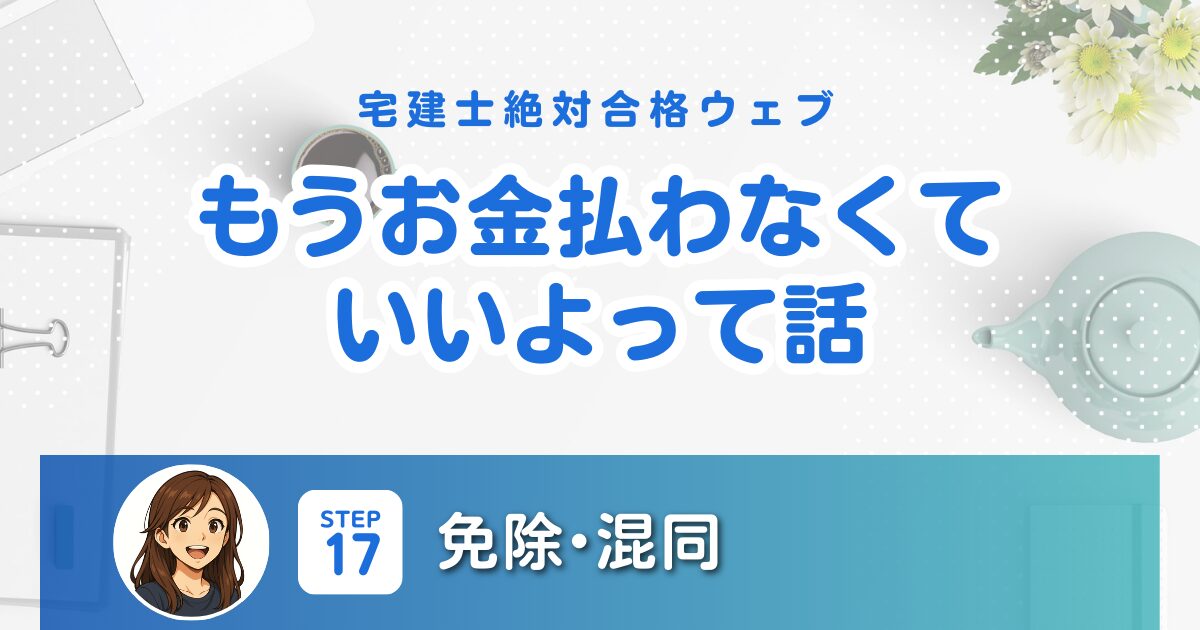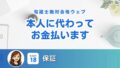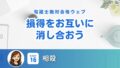民法の債権とか物権を勉強していると、「免除(めんじょ)」とか「混同(こんどう)」っていう言葉、出てきますよね。「免除」は、まあなんとなく「借金チャラにしてもらうことかな?」って想像つくけど、「混同」って…なにそれ?ってなりませんか?どっちも権利とか義務が消えちゃう話っぽいけど、何がどう違うの?って。特に、連帯債務とか保証人が絡んでくると、誰の借金がどうなるのか、ますます「???」ってなっちゃうこと、ありませんか?
今回は、債権(お金を請求する権利とか)や物権(物を直接支配する権利とか)が消滅する原因になる「免除」と「混同」について、それぞれの意味と効果、そして宅建試験で特に気をつけたいポイントを、できるだけわかりやすく解説していきますね!
簡単に言うと、「免除」は、お金を貸してる人(債権者)の「もう返さなくていいよ」っていう意思で債務がなくなること。一方、「混同」は、権利を持つ人と義務を負う人がたまたま同じ人になっちゃって、「自分で自分に請求しても意味ないよね」ってことで権利や義務が消えちゃうこと、という違いがあります。どちらも権利関係が変わる大事なルールで、特に複数の人が関わる連帯債務とか、保証人がいるケースでどう扱われるのかは、しっかり理解しておく必要があるんですよ。
この記事では、「免除」と「混同」それぞれの基本的な考え方から、具体的にどんな場面で使われるのか(借地権と所有権、抵当権と所有権、借金とか)、そして、連帯債務者や連帯保証人がいる場合に、一人の人に起こったことが他の人にも影響するのかどうか(相対効・絶対効)の違いなどを丁寧に説明していきます。

ちょっとややこしい部分もあるけど、一緒にマスターしましょう!
<この記事でわかること>
- 債務の「免除」とは何か、その基本的な効果について理解できる
- 連帯債務や連帯保証で一人が免除された場合、他の人にどう影響するのか(相対効)がわかる
- 「混同」によって権利や債務が消滅する仕組みがわかる
- 物権(借地権・抵当権など)や債権が混同する具体例がイメージできる
- 免除と混同の違い、特に連帯債務・保証との関係(相対効・絶対効)のポイントが整理できる
債務がチャラに?「免除」の基本と連帯債務・連帯保証への影響(相対効)
まずは、「免除(めんじょ)」から見ていきましょう。これは、言葉のイメージ通りなので、比較的わかりやすいかもしれませんね。
免除とは? – 債権者が一方的に債務をなくすこと
免除っていうのは、債権者(お金を貸してる人など、何かを請求する権利がある人)が、債務者(お金を借りてる人など、何かをする義務がある人)に対して、「あなたが負っている債務(借金とか)は、もう履行しなくていいですよ(返さなくていいですよ)」という一方的な意思表示をすることによって、その債権(請求する権利)を消滅させることを言います(民法第519条)。
【例で見てみよう!】
Bさん(債権者)がAさん(債務者)に100万円を貸していました。でもある日、BさんがAさんに「Aさんには昔すごくお世話になったからね。今回の100万円の借金は、特別に免除してあげるよ!」と伝えました。
【ポイント】
免除は、債権者Bさんからの「免除します!」っていう一方的な意思表示だけで効果が発生します。債務者Aさんの「ありがとうございます!」っていう承諾は必要ないんです。だって、借金がなくなるのはAさんにとって嬉しいこと(有利なこと)だから、それでOKとされているんですね。こういう、一方的な意思表示だけで法律効果を生じさせる権利のことを「形成権(けいせいけん)」って言いますね。
連帯債務者の一人が免除されたらどうなる? – 原則「相対効」!
じゃあ、もし複数人が同じ借金を一緒に負っている「連帯債務」のケースで、その連帯債務者のうちの一人だけが、債権者から「あなただけは免除してあげるよ」って言われたら、他の連帯債務者たちの借金はどうなるんでしょうか?ここ、試験でもよく問われるところです!
【例で見てみよう!】
連帯債務者のAさんとBさんは、債権者のCさんに対して、連帯して1,000万円の借金を負っています(二人の間の負担割合は、公平にA:500万円、B:500万円とします)。その後、CさんがBさんに対してだけ「あなたの1,000万円の債務は特別に免除します」と伝えました。
相対効とは? – 免除された人だけに効果がある
この場合、今の民法では、連帯債務者の一人に対する免除の効果は、原則として「相対効(そうたいこう)」である、とされています(民法第441条、第440条)。
相対効っていうのは、その法律行為の効果が、特定の当事者の間(この例だと、免除をしたCさんと、免除されたBさんの間)だけで生じて、他の当事者(つまりAさん)には直接の影響を及ぼさない、っていう意味です。
つまり、CさんがBさんの債務を免除しても、その「免除された」っていう効果は、原則としてBさんにしか及ばない。だから、Aさんが負っているCさんへの債務(1,000万円)には、直接的な影響はない、っていうのが基本ルールなんです。
他の連帯債務者の債務はどうなる? – 原則、影響なし
相対効の原則から考えると、Bさんが免除されても、Aさんは依然としてCさんに対して1,000万円全額の支払い義務を負っている、ということになります。
「えっ!?ちょっと待って!Bさんは借金チャラになったのに、Aさんは相変わらず1,000万円全部払わなきゃいけないの?それって、なんだかAさんがかわいそうじゃない?不公平じゃない?」
…って思いますよね!私もそう思います!
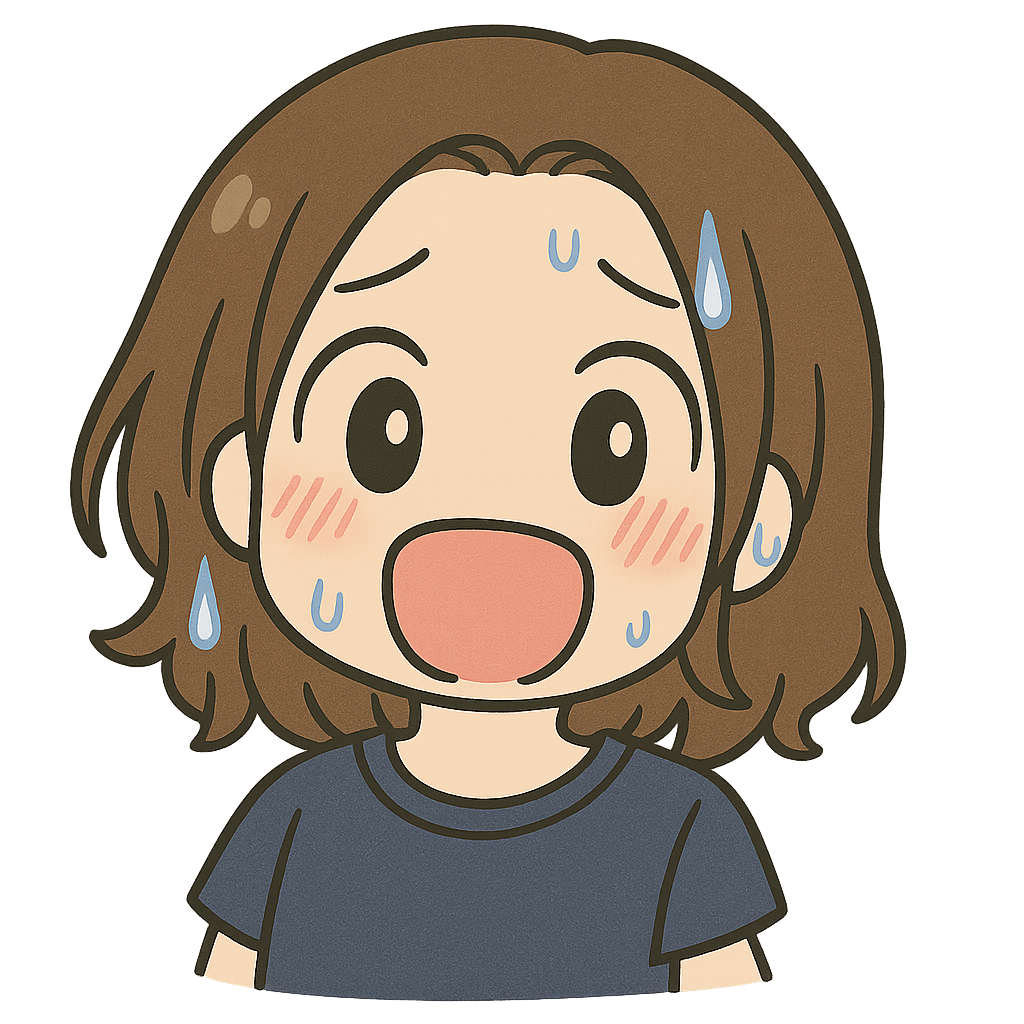
たしかに!Bさんがラッキーなのはわかるけど、その分、Aさんが損するみたいになるのはおかしい気がしますよね…。
【補足】負担部分と求償権の関係はどう調整される?
そうなんです。単純に「相対効だからAさんは全額負担ね!」ってしちゃうと、明らかに不公平ですよね。だから、民法はちゃんと調整するためのルールを用意してくれています。
それは、連帯債務者の一人であるBさんが免除された場合でも、他の連帯債務者であるAさんは、免除されたBさんの「負担部分」(この例だと500万円)の限度で、債権者Cさんに対して債務の履行を拒むことができる、とされているんです(民法第445条)。
つまり、Aさんは、Cさんから「1,000万円払って!」って請求されても、「いやいや、Bさんの負担部分である500万円については、Bさんがあなた(Cさん)から免除されたんだから、私は払いませんよ!」って主張できるんです。その結果、Aさんが実際にCさんに支払わなければならないのは、自分の本来の負担部分である残りの500万円だけ、ということになるんですね。これで公平性が保たれます!
【結論!】
連帯債務の一人への免除は相対効(Aさんの債務は原則消えない)だけど、Aさんは免除されたBさんの負担部分の範囲で支払いを拒める!
ちなみに、もしAさんがこのルールを知らずに(または主張せずに)、先にCさんに1,000万円全額を払っちゃった場合、後からBさんに対して「あなたの負担部分の500万円を返して!」って求償することはできない、とされています。注意が必要ですね。
連帯保証人が免除された場合は? – これも原則「相対効」!
次に、借金の保証人の中でも特に責任が重い「連帯保証人」が、債権者から免除された場合はどうなるでしょうか?
これも、さっきの連帯債務の場合と考え方は基本的に同じで、原則として「相対効」です。
【例で見てみよう!】
主たる債務者のAさんが、債権者のCさんから1,000万円を借りました。そして、Bさんがその借金の連帯保証人になりました。その後、Cさんが連帯保証人のBさんに対してだけ「あなたの保証債務は特別に免除します」と伝えました。
この場合、免除の効果は、免除された連帯保証人のBさんにしか及びません。だから、Bさんの保証債務は消滅しますが、もともとお金を借りた本人である主たる債務者Aさんの債務(1,000万円)には、全く何の影響もなく、そのまま残ります。
【しっかり区別!】
連帯保証人が免除されても、主たる債務者は全然影響を受けない、って覚えておきましょう!これは、保証債務の基本的な性質である「付従性(ふじゅうせい)」(主たる債務が消えれば、保証債務も消える)とは、逆方向の話なので、ごっちゃにしないように気をつけてくださいね!
ちなみに、逆のケース、つまり主たる債務者AさんがCさんから債務を免除された場合は、保証債務の付従性によって、連帯保証人Bさんの保証債務も原則として消滅します。
この辺りの、連帯債務や保証の場面で、ある出来事が他の人にも影響するのか(絶対効)、しないのか(相対効)っていう区別は、本当にややこしいけど、すごく大事なところなので、しっかり整理して理解していきましょうね!
権利が一つにまとまると消える?「混同」の仕組みと具体例
続いては、「混同(こんどう)」について見ていきましょう。これは「免除」と比べると、ちょっとイメージしにくい言葉かもしれません。でも、具体例を見ると「あ、そういうことね!」ってわかりやすいですよ。
混同とは? – 権利と義務などが同じ人に属すること
混同っていうのは、ある権利(例えば、土地の所有権とか、お金を請求する債権とか)と、その権利とは本来別々にあるべき、または対立する関係にある別の権利(例えば、その土地の抵当権とか地上権とか)や義務(借金を返す債務とか)が、何らかの理由(相続とか、売買とか)で、たまたま同じ一人の人にくっついちゃった(帰属した)場合に、そのまま両方を持ち続けることに意味がない方の権利や債権が、原則として消滅しますよ、っていう制度のことです(物権については民法第179条、債権については民法第520条)。
うーん、やっぱりちょっと難しいですね…。もっと簡単に言うと、「自分で自分に対して権利を主張したり、自分で自分に対して義務を負ったりするのって、意味ないし、変だよね?だから、そういう意味がなくなっちゃった方の権利とか義務は、消えちゃうことにしましょう」っていう考え方なんです。
混同には、土地や建物に関する権利(物権)についての混同と、お金の貸し借りとかの権利(債権)についての混同があります。それぞれ見ていきましょう。
【物権の混同①】借地権者が土地の所有権も手に入れたら?
【例で見てみよう!】
Aさんは、Bさんが持っている土地を借りて(借地権や地上権を設定して)、そこに自分の家を建てて住んでいました。その後、AさんがBさんからその土地自体を買い取った場合、または、Bさんが亡くなって、Aさんが唯一の相続人としてその土地を相続した場合。
この場合、Aさんはその土地の完全な持ち主(所有者)になりましたよね。土地を自由に使える所有権を持っているのに、わざわざ制限のある権利である借地権(や地上権)を、同じ土地に対して持ち続ける意味って、ありますか?…ないですよね!
だから、このような場合は、原則として、Aさんが持っていた借地権(または地上権)は、混同によって消滅するんです(民法第179条1項)。所有権という強い権利の中に、吸収されちゃうイメージですね。
【物権の混同②】抵当権者が抵当不動産の所有権も手に入れたら?
【例で見てみよう!】
AさんはBさんにお金を貸していて、その借金の担保として、Bさんが持っている土地に抵当権を設定していました(Aさんは抵当権者です)。その後、AさんがBさんから、その抵当権が付いている土地自体を買い取った場合、または、借金の代わりにその土地を受け取った(代物弁済)場合。
この場合も、Aさんは自分で自分の土地に抵当権を持っている、っていう変な状態になります。自分で自分にお金を払えなかったら、自分で自分の土地を競売にかける…なんて意味ないですよね。
だから、原則として、Aさんが持っていた抵当権は、混同によって消滅するんです(民法第179条1項)。
【債権の混同】借金した相手を相続したら?
【例で見てみよう!】
Bさん(お父さん)がAさん(息子)に100万円を貸していました(BさんはAさんに対して100万円の貸金債権を持っています)。その後、お父さんのBさんが亡くなり、息子AさんがBさんの唯一の相続人として、Bさんの財産(もちろん、Aさんに対する貸金債権も含まれます)を全て相続した場合。
この場合、Aさんは、自分自身に対して「100万円返せ!」って請求する権利を持つことになります。これも、自分で自分に請求するなんて、全く意味がないですよね。
だから、原則として、その債権(Bさんから相続した、Aさん自身に対する貸金債権)は、混同によって消滅するんです(民法第520条本文)。結果的に、Aさんは借金を返さなくてよくなるわけですね。

混同って、なんかパズルみたい!権利と義務が同じ人にピタッとはまっちゃって、意味がなくなると、その権利がポロッと消えちゃう感じなんですね!
【重要】混同の例外ってあるの?
ここまで、「原則として」混同によって権利が消滅する、ってお話ししてきましたが、混同にも大事な例外があるんです!消滅しないケースもあるんですね。
それは、混同によって消滅するはずの権利(例えば、抵当権とか地上権とか債権)が、第三者の権利の目的になっている場合です(民法第179条1項ただし書、民法第520条ただし書)。
「第三者の権利の目的になっている」って、ちょっとわかりにくいですよね。具体例で見てみましょう。
【混同の例外ケース①:後順位の抵当権者がいる場合】
Aさんが持っている土地に、Bさんが1番抵当権、Cさんが2番抵当権を持っていました。その後、1番抵当権者のBさんが、Aさんからその土地の所有権を取得しました。
もし、ここで原則通りBさんの1番抵当権が混同で消滅しちゃうとどうなるでしょう? 本来2番だったCさんが、繰り上がって1番抵当権者になってしまいますよね。これは、Cさんにとっては予期せぬラッキー(不当な利益)になってしまいます。これを防ぐために、この場合は、Bさんの1番抵当権は混同によって消滅しないんです。
【混同の例外ケース②:権利にさらに権利が付いている場合】
Aさん所有の土地の地上権者であるBさんが、その持っている地上権を担保にして、Cさんのためにお金を借りて抵当権を設定していました(地上権に抵当権が設定されている状態)。その後、地上権者のBさんが、Aさんからその土地の所有権を取得しました。
もし、ここで原則通りBさんの地上権が混同で消滅しちゃうと、Cさんが設定していた抵当権の目的物(地上権)自体がなくなってしまいますよね。これではCさんが困ってしまいます。Cさんを保護するために、この場合も、Bさんの地上権は混同によって消滅しないんです。
【例外のポイント】
原則通り混同で権利を消滅させちゃうと、損をしてしまう第三者がいる場合は、その第三者を守るために、例外的に混同は起こらない(権利は消滅しない)!って覚えておきましょう!
混同と連帯債務・連帯保証の関係 – 債権混同は「絶対効」
最後に、この「混同」が、連帯債務や連帯保証の場面で起こったらどうなるかを見てみましょう。ここが、さっき見た「免除」との大きな違いが出てくるところです!
先ほど、債権の混同(債権と債務が同じ人にくっつくこと)が起こると、その債権は原則として消滅する、って説明しましたよね。
では、もし、連帯債務者の一人と、債権者との間で混同が起こったらどうなるでしょうか?
【例で見てみよう!】
連帯債務者のAさんとBさんが、債権者のCさんに連帯して1,000万円の借金を負っています。その後、AさんがCさんを単独で相続して、Cさんが持っていたAさん・Bさんに対する1,000万円の債権を、Aさん自身が相続しました。
この場合、Aさんについて見ると、自分自身に対する債権を持つことになり、債権と債務が混同します。だから、Aさんの債務は、原則どおり混同によって消滅しますよね。
じゃあ、もう一人の連帯債務者Bさんの債務はどうなると思いますか?
実は、この債権混同の効果は、連帯債務においては「絶対効(ぜったいこう)」とされているんです!(民法第441条、第440条)。
絶対効っていうのは、その効果が、連帯債務者の一人(この場合はAさん)について生じると、他の全ての連帯債務者(Bさん)にも影響を及ぼす、っていう意味でしたよね。
つまり、Aさんについて混同が起こって債権が消滅すると、その効果はBさんのためにも生じて、Bさんも原則として1,000万円の債務全額を免れることになるんです!Aさんの負担部分だけじゃなくて、全部です!
【超重要!免除との違い!】
さっき見た「免除」は原則「相対効」(他の人に影響しない、ただし負担部分の調整あり)でしたよね?
それに対して、「混同」は原則「絶対効」(他の人にも影響して、他の人も債務を免れる)なんです!
この「免除は相対効、混同は絶対効」という違いは、連帯債務や保証の問題を解く上で、めちゃくちゃ大事なポイントなので、絶対に覚えてくださいね!
ちなみに、連帯保証の場合も同じように考えます。主たる債務者と債権者の間で混同が起これば、その効果は絶対効として保証人にも及ぶので、保証人も原則として保証債務を免れることになります。
このように、連帯債務や保証の場面では、ある出来事(免除、混同、弁済、相殺、更改など)が、他の人に影響する「絶対効」なのか、影響しない「相対効」なのかを正確に区別することが、正解へのカギになります。「混同」は絶対効の代表選手として、しっかりインプットしておきましょう!
まとめ
今回は、債権や物権が消えちゃう原因になる「免除」と「混同」について、その基本的なルールや具体例、そして連帯債務・保証との関係を中心に解説してきました!
どっちも権利が消えるっていう結果は似ているけど、どうして消えるのかっていう原因(債権者の意思なのか、権利と義務がくっついたからなのか)と、その効果、特に他の人が関わる場合にどう影響するのか(相対効?絶対効?)に大きな違いがありましたね。この区別、しっかりできましたか?
【今日のポイントをギュッと凝縮!】
- 免除:債権者が一方的に債務を消す意思表示。債務者の承諾はいらない。
- 連帯債務・保証と免除:原則相対効。免除された人だけに効果あり。他の人は原則影響受けない(ただし、連帯債務では負担部分の調整ルールあり)。
- 混同:権利と義務(または対立する権利)が同じ人にくっついて、意味がなくなった方の権利・債権が消えること。
- 物権の混同:借地権・地上権や抵当権が、所有権と同じ人にくっつくと原則消える。
- 債権の混同:債権と債務が同じ人にくっつくと原則消える。
- 混同の例外:第三者の権利の目的になっている場合は、その第三者を守るために消滅しない。
- 連帯債務・保証と混同:債権の混同は原則絶対効。他の連帯債務者や保証人も原則として債務を免れる!
「免除」と「混同」、それぞれの意味と効果、そして特に連帯債務や保証が絡んだときの「相対効」と「絶対効」の違いは、しっかりマスターしておきたいですね。これらの知識は、単独の問題として出ることもありますし、連帯債務、保証、相続、抵当権といった他の分野の問題の中で、複合的に問われることもすごく多いです。
それぞれの制度がどうしてそうなっているのか、っていう理由や背景を考えながら、他の知識と関連付けて勉強していくと、より深く、そして忘れにくく理解できると思いますよ。

宅建合格に向けて、一歩一歩、着実に知識を積み重ねていきましょう!応援しています!ファイトです!