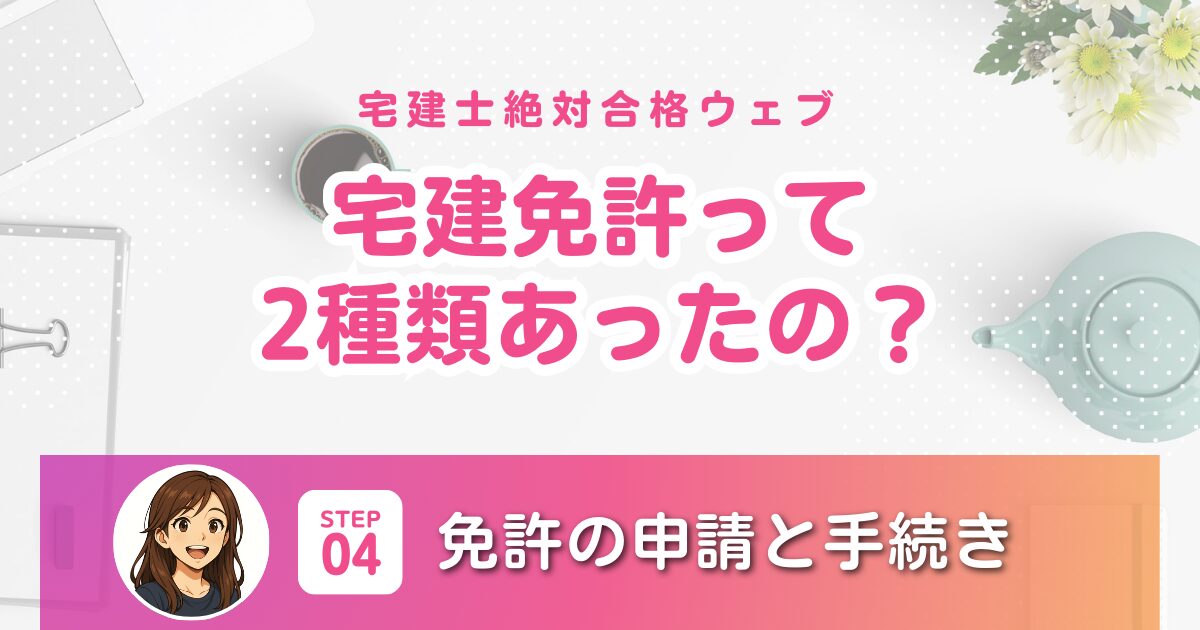宅建業の免許、「都道府県知事免許」と「国土交通大臣免許」…どっちがどっちだっけ?って、ちょっとわかりにくいですよね。事務所の数とか場所とか、いろいろ条件があって頭がこんがらがっちゃう!なんて人もいるんじゃないでしょうか?
宅建業を始めるには、この「免許」が絶対に必要なんです。試験に合格して宅建士になった!だけじゃ、まだ宅建業はできないんですよね。会社として、あるいは個人事業主として宅建業をやるには、ちゃんとルールに沿って免許を取得しないといけないんです。
この記事では、宅建業の免許について、基本的なところから申請方法、更新まで、できるだけわかりやすく解説していきます!これを読めば、免許の種類の違いや、どうやって申請すればいいのかがスッキリわかるはず!
この記事でわかること
- 都道府県知事免許と国土交通大臣免許の違い
- 免許申請の具体的な手続きや必要な書類
- 免許にかかる手数料や条件について
- 免許がもらえるまでの期間(標準処理期間)
- 免許の更新手続きについて
宅建業免許のキホン!知事免許と大臣免許の違いって?
まず、宅建業の免許には大きく分けて2つの種類があるってことを押さえましょう!それが「都道府県知事免許」と「国土交通大臣免許」です。

この2つの違い、宅建試験でもよく問われる超重要ポイントです!しっかり区別できるようにしましょう。
じゃあ、どうやってこの2つが使い分けられるのか、見ていきましょう!
事務所の場所がカギ!知事免許と大臣免許の分け方
この2つの免許、どっちが必要になるかは、ズバリ「事務所をどこに設置するか」で決まります。ポイントは「いくつの都道府県に事務所があるか」です。
- 都道府県知事免許:
- 1つの都道府県内にだけ事務所を設置する場合
- 本店も支店もぜーんぶ埼玉県内! → 埼玉県知事免許
- 事務所は東京都内に1つだけ! → 東京都知事免許
- 1つの都道府県内にだけ事務所を設置する場合
- 国土交通大臣免許:
- 2つ以上の都道府県にまたがって事務所を設置する場合
- 本店は東京都、支店は埼玉県にある! → 国土交通大臣免許
- 本店は大阪府、支店は東京都と埼玉県と京都府にある! → 国土交通大臣免許
- 2つ以上の都道府県にまたがって事務所を設置する場合

極端な話、東京都内に100個事務所があっても、全部東京都内なら東京都知事免許でOK。逆に、東京都に本店、埼玉県に支店が1つずつ、合計2つの事務所でも、都道府県をまたいでいるから国土交通大臣免許が必要になります。
免許の種類を決めるのは「事務所が設置されている都道府県の数」!
- 1つの都道府県のみ → 都道府県知事免許
- 2つ以上の都道府県にまたがる → 国土交通大臣免許
免許があればどこでもOK?業務範囲について
じゃあ、例えば埼玉県知事免許を持っていたら、埼玉県内の物件しか扱えないの?って思うかもしれませんが、そんなことはないんです!
宅建業の免許を持っていれば、原則として、全国どこの物件でも取引の対象にできます。
つまり、神奈川県知事免許を持っている宅建業者が、北海道にある土地の売買や、沖縄にあるマンションの賃貸の仲介をすることも可能なんです。すごいですよね!

これは結構意外ですよね?免許の種類は事務所の場所で決まるけど、業務ができるエリアは全国!って覚えておくといいですね!
ただし、注意点もあって、新たに別の都道府県に事務所を設置したい場合は、免許の種類が変わる可能性があります。
例えば、もともと東京都知事免許を持っていた業者が、新たに神奈川県にも支店を出したい!となったら、これは「2つ以上の都道府県に事務所を設置する」ことになるので、国土交通大臣免許への「免許換え」という手続きが必要になります。
免許申請から更新までの流れ
免許の種類がわかったところで、次は実際にどうやって免許を取得するのか、その流れを見ていきましょう!申請から更新まで、一つずつ解説していきますね。
まずは申請!どこに何を提出する?
宅建業の免許を取得するには、「免許申請書」に必要な書類を添えて、「免許権者」に提出する必要があります。免許権者っていうのは、免許を与える権限を持っている人のこと。つまり、知事免許なら都道府県知事、大臣免許なら国土交通大臣ですね。
申請先はどっち?知事?それとも大臣?
申請書の提出先は、取得したい免許の種類によって少し異なります。
- 都道府県知事免許を受けたい場合:
- 事務所を設置する都道府県の知事に直接、免許申請書を提出します。シンプル!
- 国土交通大臣免許を受けたい場合:
- ここがちょっとポイント!直接、国土交通大臣に提出するのではなく、主たる事務所(本店)がある都道府県の知事を経由して、免許申請書を提出するんです。

大臣免許なのに、いきなり国に提出じゃないんです!まずは本店の住所がある都道府県の窓口(知事)を通すって流れ、しっかり覚えておこう!ワンクッション挟むイメージかな?
免許申請書に書くことリスト
免許申請書には、主に以下のような情報を記載する必要があります。
- 商号または名称: 会社の名前や、個人事業主としての屋号など。
- 役員の氏名(法人の場合): 取締役などの役員全員の氏名。もし「政令で定める使用人」(例えば、支店長さんとか、重要なポジションの使用人さんのことだよ!)がいる場合は、その人の氏名も必要です。
- 申請者の氏名(個人の場合): 個人事業主本人の氏名。法人と同じく、「政令で定める使用人」がいる場合はその人の氏名も。
- 事務所の名称及び所在地: 本店や支店の名前と住所を全部書きます。
- 専任の宅地建物取引士の氏名: 各事務所に必ず置かなければいけない「専任の宅建士」の氏名。
- 他に事業を行っているときは、その事業の種類: 例えば、不動産賃貸業や建設業、管理業など、宅建業以外にも事業をやっている場合に記載します。
記載事項は、法人の場合と個人の場合で少し違う部分もあるから、自分がどっちで申請するのか確認してね!
添付書類一覧
免許申請書だけじゃなく、一緒に提出しなきゃいけない書類もたくさんあります。主なものをリストアップしてみますね!
- 宅地建物取引業経歴書(更新の場合): これまでにどんな取引(売買、賃貸など)をどれくらいやってきたか、その金額や報酬額などを記載します。(※新規申請の場合は不要なことが多いけど、自治体によって扱いが違う場合もあるので確認してね!)
- 欠格要件に該当しないことを誓約する書面: 「私は法律で定められた欠格要件(例えば、破産者じゃないとか、過去に悪いことして懲役刑を受けてないとか、特定の罪で罰金刑を受けてないとか)には当てはまりません!」ってお約束する書類です。
- 相談役及び顧問に関する書類(該当する場合): もし会社に相談役や顧問がいる場合は、その人の情報も必要になります。
- 株主又は出資者に関する書類(法人の場合): 会社の株主構成などがわかる書類です。
- 事務所について要件を備えていることを証する書面:
- 従業員名簿: どんな人が働いているかのリスト。
- 専任の宅地建物取引士設置証明書: ちゃんと専任の宅建士を置いてますよ、っていう証明。
- 専任の宅建士が成年被後見人、被保佐人でない旨の証明書: 専任の宅建士が、判断能力に問題がない状態であることを証明する書類。これは法務局で発行してもらいます。(※「登記されていないことの証明書」という名前の書類だよ!)
- その他国土交通省令で定める書面:
- 身分証明書(市区町村発行): 破産者でないことなどを証明する書類。(※これは専任の宅建士だけでなく、役員や政令で定める使用人も必要だよ!)
- 事務所を使用する権原に関する書面: 事務所がちゃんと使える場所であることを証明する書類。例えば、賃貸オフィスなら賃貸借契約書のコピーとか、自社ビルなら登記事項証明書(登記簿謄本)とか。
- 事務所付近の地図及び事務所の写真: 事務所の場所がわかる地図と、事務所の内外の写真。ちゃんと営業できる状態か確認するためですね。

結構たくさんあります!書類集め、大変そう…。でも、免許をもらうためには避けて通れない道!
添付書類、めちゃくちゃ多い! 不備があると申請がスムーズに進まないので、申請先の都道府県庁や地方整備局のウェブサイトなどで、最新の必要書類リストを必ず確認するようにしましょう!自治体によって少しずつ書式や必要なものが違うこともあるから要注意!
免許申請の手数料
免許を申請するには、手数料がかかります。金額は、新規申請でも更新申請でも、一律で3万3,000円です。
(※2025年4月時点の情報です。今後、法改正などで金額が変わる可能性もあるので、申請時には必ず最新情報を確認してくださいね!)
この手数料は、収入印紙で納付します。免許申請書に、3万3,000円分の収入印紙を貼って提出する、という形です。
免許に条件が付くこともあるの?
実は、免許を与えるときや、免許を更新するときに、国土交通大臣や都道府県知事が「条件」を付けることができるんです。
これは、何か特別な事情がある場合に、「こういうルールは守ってくださいね」と念を押すようなイメージです。例えば、
- 例1: 免許を申請した会社の役員Aさんが、すごく昔に暴力団に関わっていた過去があった場合(今はもちろん関係ないけど)。念のため、「今後、暴力団の構成員になったり、暴力団の影響を受けたりしないこと」という条件が付く、みたいなケース。
- 例2: 免許を更新する際に、「免許を取ってから最初の1年間、宅建業の取引状況をちゃんと報告してくださいね」という条件が付く、みたいなケース。ちゃんと事業を運営しているかを確認するためですね。
免許の条件は最小限
この免許の条件は、むやみやたらに付けられるわけではありません。ちゃんとルールがあります。
- 目的: 「宅建業の適正な運営」と「取引の公正」を確保するため。
- 程度: 必要最小限度のものにしなければならない。
- 義務: 免許を受ける人に不当な義務を課すものであってはならない。
つまり、免許を与える側が好き勝手に厳しい条件を付けちゃダメってことですね。あくまでも、健全な宅建業の運営に必要な範囲内で、かつ、業者にとって不公平にならないように、慎重に判断されるべきものなんです。
申請から免許がもらえるまでの標準処理期間
免許申請書を提出してから、実際に「免許ゲット!」となるまで、どれくらいの時間がかかるのか、気になりますよね。この期間の目安のことを「標準処理期間」と言います。
目安としては、以下のようになっています。
- 国土交通大臣免許の場合:
- 申請書を都道府県知事に提出してから、それが国の担当部署(地方整備局長等 ※後で説明するね!)に届くまで:約10日
- 国の担当部署に申請書が届いた日の翌日から、免許の処分(OKかNGか)が出るまで:約90日
- 合計すると、だいたい100日くらいが目安になります。
- 都道府県知事免許の場合:
- これは都道府県によって処理期間が異なりますが、一般的には30日~60日くらいが目安と言われています。大臣免許よりは短いことが多いですね。
「地方整備局長等」っていうのは、国土交通大臣から「宅建業の免許に関する事務処理、お願いね!」って委任されている機関のこと。全国をブロックに分けて担当していて、例えば関東地方なら「関東地方整備局長」が担当するんです。
標準処理期間はあくまでも目安! 次のような場合は、この期間に含まれないので、もっと時間がかかることがあります。
- 申請書の記載に不備があった場合: 書類に間違いや漏れがあって、それを直すのにかかった時間はカウントされません。
- 追加の資料提出などを求められた場合: 審査のために、申請者に追加で資料の提出をお願いすることがあります。その場合、申請者が対応してくれるまでの時間はカウントされません。

だから、申請書類は完璧な状態で提出するのが、早く免許をもらうためのコツなんですね!不備があると、それだけ時間がかかっちゃうから…。
5年に一度の免許の更新について
宅建業の免許、一度取ったら永久に有効!…というわけではありません。有効期間は5年間なんです。
だから、5年経つ前に「免許の更新」の手続きをしないと、免許が失効してしまいます。免許がない状態で宅建業を続けると、もちろん法律違反になっちゃうから大変!
更新の申請ができる期間も決まっています。
- 免許の有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間
この60日間の間に、更新のための免許申請書を提出する必要があります。
更新申請の期間は「満了日の90日前~30日前」! 早すぎてもダメ、遅すぎてもダメなんです。更新時期が近づいてきたら、早めに準備を始めるのが吉ですね!更新の時も、新規申請と同じように手数料(3万3,000円 ※2025年4月時点)がかかりますよ。
まとめ
今回は、宅建業の免許について、種類や申請方法、更新まで一通り解説してみました!結構ボリュームがあったけど、ついてこれたかな?
最後に、今日の内容をもう一度おさらいしておきましょう!
- 免許の種類は2つ!
- 都道府県知事免許: 1つの都道府県内にだけ事務所がある場合。
- 国土交通大臣免許: 2つ以上の都道府県に事務所がある場合。
- 業務範囲は、どちらの免許でも全国!
- 免許申請の流れ
- 申請先: 知事免許は知事へ直接。大臣免許は本店所在地の知事を経由して国へ。
- 必要書類: 免許申請書+たくさんの添付書類(経歴書、誓約書、身分証明書、事務所の資料など)。不備がないように注意!
- 手数料: 3万3,000円(収入印紙で納付 ※2025年4月時点)。
- 免許の条件
- 免許の付与時や更新時に、必要最小限度の範囲で条件が付されることがある。
- 標準処理期間
- 申請から免許交付までの目安。大臣免許は約100日、知事免許は30日~60日程度(都道府県による)。書類不備などがあると延びる!
- 免許の更新
- 有効期間は5年間。
- 更新申請は、有効期間満了日の90日前から30日前までに行うこと!
宅建業の免許制度は、ルールが細かくて覚えるのが大変かもしれないけど、宅建業の信頼性を支える大切な仕組みです。一つ一つのルールをしっかり理解して、試験対策にも、そして将来の実務にも役立ててくださいね!

基本事項の積み重ねが、宅建合格への一番の近道!頑張っていきましょう!