宅建の勉強を始めたけど、民法の用語ってなんだか難しくて、テキストを読んでいても「???」ってなっちゃうこと、ありませんか? 特に「善意」「悪意」とか、「無効」「取消し」とか、普段使う言葉と意味が違ったりして、混乱しちゃいますよね。
「善意って、良いことじゃないの?」「対抗するって、ケンカすること?」「停止条件って、何を停止するの?」…なんて、疑問がたくさん浮かんできませんか? 民法は宅建試験の中でも重要な科目なのに、最初の法律用語でつまずいてしまうと、なんだかやる気もなくなっちゃいますよね…。
でも、安心してください! この記事では、そんな宅建受験生のみなさんが民法アレルギーにならないように、特に重要で、かつ、つまずきやすい基本的な法律用語をピックアップして、一つひとつ丁寧に、具体例を交えながら解説していきます。まるで隣で私が説明しているような感覚で、スラスラ読めるように工夫しました!
この記事を読めば、難解な法律用語も「なるほど、そういうことか!」ってスッキリ理解できるようになりますよ。民法の条文やテキストが、前よりもずっと読みやすくなるはずです。最初に基本をしっかり押さえておけば、その後の民法の学習がぐっと楽になりますし、得点アップにも繋がります。

さあ、私と一緒に民法の基本用語をマスターして、宅建合格への大きな一歩を踏み出しましょう!
- 日常会話とは違う!民法独特の「善意」「悪意」「対抗する」の本当の意味
- うっかり度合いで変わる?「過失」の種類(重過失・軽過失・無過失)とその違い
- 契約がどうなるかが決まる!「無効」と「取消し」の決定的な違いと「追認」とは何か
- “もし~なら”を契約に盛り込む!「停止条件」と「解除条件」の具体例と効力の違い
- いつか必ずやってくる!契約の効力に関わる「期限」の種類と「期限の利益」
民法特有の言葉遣いに慣れよう!「善意・悪意」「過失」「対抗する」をマスター
民法の勉強を始めると、まず最初に「えっ?」ってなるのが、普段私たちが使っている言葉と意味が違う用語が出てくるところですよね。でも、これは法律の世界の”お約束”みたいなものなんです。
最初にしっかり意味を押さえておけば、後がすごく楽になりますよ! ここでは、特に基本的な「善意・悪意」「過失」「対抗する」について見ていきましょう。
【超基本】「善意」「悪意」は良い・悪いじゃない?その意味とは
まず、絶対に押さえておきたいのが「善意(ぜんい)」と「悪意(あくい)」です。
日常生活で「あの人は善意の人だね」とか「悪意を感じる」なんて使いますよね。この場合、「善意=親切、良い心」「悪意=悪い心、害意」みたいな意味で使っていると思います。
法律用語の「善意」「悪意」は、道徳的な良し悪しとは全く関係ありません!
じゃあ、法律用語としての意味は何なのでしょうか?
- 善意 (ぜんい):ある事実を知らないこと
- 悪意 (あくい):ある事実を知っていること
たったこれだけなんです! シンプルですよね?
【具体例を見てみよう!】
例えば、私があなたに中古のパソコンを売る契約をしたとします。でも、実はそのパソコン、私が友人から借りていたものだった…!なんて場合。
- あなたが、そのパソコンが私の所有物ではないこと(借り物であること)を知らなかった場合 → あなたはパソコンの所有権について「善意」である、となります。
- あなたが、そのパソコンが私の所有物ではないこと(借り物であること)を知っていた場合 → あなたはパソコンの所有権について「悪意」である、となります。

良い・悪いじゃなくて、単に「知ってるか」「知らないか」だけなんですね!最初は私も戸惑いましたよ~。
この「善意」「悪意」は、後で出てくる「無効」や「取消し」、「対抗する」などの場面で、「善意の第三者には対抗できない」とか「悪意の買主は保護されない」みたいに、権利関係を判断する上でめちゃくちゃ重要になってくるんです。
だから、まずこの「知っているか・知らないか」という意味をしっかり頭に入れてくださいね!
うっかり?わざと?「過失」の種類(重過失・軽過失・無過失)を知ろう
次に出てくるのが「過失(かしつ)」です。これは比較的、日常で使う意味と近いかもしれません。
- 過失 (かしつ):「注意を怠った」こと、「不注意」や「落ち度」があったこと
例えば、「不注意でコップを割っちゃった」とか「運転中の不注意で事故を起こした」のような場面で使う「不注意」が、法律用語の「過失」に近いイメージです。
そして、この「過失」には、その不注意の度合いによって3つのレベルがあるんです。
- 重過失 (じゅうかしつ):著しい不注意があったこと。「ちょっと考えれば分かるでしょ!」レベルの、かなり大きな落ち度です。
- イメージ:「ほとんどわざとじゃない?」ってくらい、注意義務を怠った状態。
- 軽過失 (けいかしつ):軽い不注意があったこと。「あ、うっかりしてた!」くらいの、少しの落ち度です。単に「過失」という場合は、通常この軽過失を指すことが多いです。
- イメージ:普通に注意していれば防げたかもしれないけど、ちょっと注意が足りなかった状態。
- 無過失 (むかしつ):まったく落ち度がないこと。「十分注意していたけど、それでも防げなかった」という状態です。
- イメージ:どれだけ注意していても避けられなかったような状況。
どこからどこまでが重過失で、どこからが軽過失なのか、その境界線を厳密に考える必要はありません。宅建試験対策としては、「重い不注意」「軽い不注意」「落ち度なし」の3つのレベルがあるんだな、とイメージできればOKです!
この過失の有無や程度も、後々の権利関係に影響してきます。例えば、損害賠償請求ができるかどうか、契約を取り消せるかどうか、といった場面で重要になります。
セットで覚えたい!「善意無過失」「善意有過失」「善意無重過失」
さっき勉強した「善意・悪意」と、今やった「過失」。この2つが組み合わさって使われることも非常に多いんです。特に「善意」とセットで使われるパターンをしっかり理解しておきましょう。
- 善意無過失 (ぜんいむかしつ)
- 意味:ある事実を知らなかったし、知らないことについて落ち度もなかった。
- 言い換えると:「まったく落ち度なく、知らなかった」「十分注意したけど、知ることができなかった」
- 法律上、一番保護されることが多い立場です。
- 善意有過失 (ぜんいゆうかしつ)
- 意味:ある事実を知らなかったけど、知らないことについて落ち度があった。
- 言い換えると:「知らなかったけど、ちょっと注意すれば気づけたはず(=軽過失があった)」
- 単に「有過失」と書かれている場合も、通常は「善意有過失(軽過失あり)」を指します。
- 善意無重過失 (ぜんいむじゅうかしつ)
- 意味:ある事実を知らなかったし、重大な落ち度はなかった。(軽い落ち度はあったかもしれない)
- 言い換えると:「知らなかったけど、重大な不注意(重過失)まではなかった」「少し注意不足だったかもしれないけど、そこまでひどい落ち度じゃない」
- 「善意有過失」との違いが少し分かりにくいですが、「無重過失」は「重過失がない」という意味です。つまり、軽過失はあってもOKというニュアンスが含まれます。

セットになると少し複雑に感じますか? 「善意=知らない」「無過失=落ち度なし」「有過失=落ち度あり」「無重過失=重い落ち度なし」って分解して考えると分かりやすいですよ!
主張できる?できない?「対抗する」の意味を理解しよう
これもまた、日常会話とはちょっと違う意味で使われる言葉ですね。「対抗する」と聞くと、「ライバル会社に対抗する」みたいに、張り合ったり競争したりするイメージがありませんか?
法律用語、特に民法で使う「対抗する(たいこうする)」は、そういう意味ではありません。
- 対抗する (たいこうする):自分の権利を主張すること
すごくシンプルに言うと、「これは私のものだ!」とか「私にはこういう権利がある!」と他の人に対して言い張ること、これが「対抗する」なんです。
例えば、私が持っている土地を、AさんにもBさんにも売ってしまった(二重譲渡と言います)とします。
(私が土地を持っていて、矢印がAさんとBさん両方に向かって伸びている図)
この場合、AさんとBさんは、どっちが本当の所有者になれるんでしょうか? 不動産の場合、原則として先に登記(とうき:不動産の権利関係を記録するもの)を備えた方が、所有権を確定的に取得できます。
もしAさんが先に登記をしたら…
- Aさんは、Bさんに対して「この土地は私のものだ!」と主張できます。 → これを法律用語で「AはBに所有権を対抗することができる」と言います。
- 逆に、BさんはAさんに対して所有権を主張できません。 → 「BはAに所有権を対抗することができない」となります。

誰に対して、自分の権利を正当に主張できるか、ってことなんですね。「対抗=主張」と覚えるといいかも!
この「対抗する」という言葉は、特に不動産取引(物権変動)や債権譲渡などの場面で頻繁に出てきます。「対抗要件(たいこうようけん)」という言葉もセットで重要になりますが、これは「自分の権利を第三者に対抗(主張)するために必要な条件」のことです。不動産の場合は、さっき言った「登記」が対抗要件になります。
契約はどうなる?「無効」「取消し」「追認」の違いを徹底解説
契約に関するトラブルも、民法では重要なテーマです。契約したはいいけど、その契約、本当に有効なの? 後から「やっぱりやめたい!」って言えるの? そんな疑問に答えるのが、「無効」「取消し」「追認」という考え方です。
この3つ、似ているようで全然違うので、しっかり区別できるようにしましょう!
最初からなかったことに!「無効」とは?具体例と特徴
まず、「無効(むこう)」です。
- 無効 (むこう):法律行為(契約など)が、初めから全く効力を持たないこと。
「無効」な契約は、契約した時点から、ずーっと効力が生じていない、いわば”存在しない契約”のようなイメージです。
- 公序良俗(こうじょりょうぞく)に反する契約
- 社会の一般的な秩序や道徳に反する内容の契約です。
- 例:「人を殺してくれたら1000万円払う」という殺人請負契約、愛人契約など。
- こんな契約、絶対ダメですよね。法律も認めてくれません。
- 強行法規(きょうこうほうき)に違反する契約の一部
- 当事者の意思に関わらず、法律が強制的に適用するルールのことです。これに反する契約内容は無効になることがあります。(全てが無効になるわけではないのがポイント)
- 意思無能力者(いしむのうりょくしゃ)が行った契約
- 例えば、泥酔していて自分の言動の意味が全く分からない状態の人や、重度の認知症などで判断能力が全くない人が結んだ契約。
- 自分のしていることの結果を判断できない状態での契約は、そもそも有効に成立しません。
- 誰でも主張できる:契約の当事者だけでなく、関係のない第三者でも「この契約は無効だ!」と主張できます。
- いつでも主張できる:主張できる期間に制限はありません。10年後でも20年後でも、「あの契約は無効だった」と言えます。
- 追認できない:「やっぱりこの無効な契約を有効にしたい」と思っても、原則として有効なものとして認める(追認する)ことはできません。(一部例外はありますが、基本はできないと覚えましょう)
後から取り消せる?「取消し」とは?遡及効と期間制限に注意
次に「取消し(とりけし)」です。無効とよく似ていますが、大きな違いがあります。
- 取消し (とりけし):いったん有効に成立した法律行為(契約など)の効力を、後から意思表示によって、契約時にさかのぼって消滅させること。
ここがポイント! 無効は「初めから効力がない」のに対し、取消しは「取り消されるまでは一応有効」なんです。そして、取り消されると、契約した時にさかのぼって効力がなくなるんです。
この、さかのぼって効力がなくなることを「遡及効(そきゅうこう)」と言います。
民法で取消しが認められているのは、主に次のような場合です。
- 制限行為能力者(せいげんこういのうりょくしゃ)が行った契約
- 未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人といった、判断能力が不十分な人を保護するための制度です。これらの人が、法定代理人(親権者など)や保佐人、補助人の同意を得ずに行った契約は、原則として取り消すことができます。
- 例: 未成年者が親に内緒で高額なバイクを買っちゃった!みたいなケースですね。後から親が取り消せます。
- 詐欺(さぎ)によって結んだ契約
- 騙されて、本当は買うつもりのないものを買わされた場合など。騙された人は契約を取り消せます。
- 強迫(きょうはく)によって結んだ契約
- 脅されて、無理やり契約させられた場合など。脅された人は契約を取り消せます。
- 錯誤(さくご)によって結んだ契約(一定の場合)
- 契約の重要な部分について、勘違い(錯誤)があった場合、一定の要件を満たせば取り消せる可能性があります。(※錯誤については少し複雑なので、ここでは取消しの一例として挙げるにとどめます)
無効と比べながら、取消しの特徴を見てみましょう。
- 主張できる人が限定されている:誰でも主張できる無効と違って、取消しができるのは、法律で定められた特定の人(取消権者:とりけしけんじゃ)だけです。例えば、制限行為能力者本人やその法定代理人、騙された人、脅された人などです。
- 主張できる期間に制限がある:いつでも主張できる無効と違い、取消権は一定期間内に行使しないと消滅してしまいます(時効)。
- 追認できる時から5年間
- 契約などの行為の時から20年間
- このどちらか早い方が経過すると、もう取り消せなくなります。
- 追認できる:取消しができる契約は、「やっぱりこの契約でいいや」と有効なものとして確定させること(追認)ができます。追認すると、もうその契約を取り消すことはできなくなります。

無効と取消し、全然違いますね! 特に「誰が」「いつまで」主張できるかが大きな違いです!
無効と取消しの比較表
| 項目 | 無効 | 取消し |
| 効力 | 初めから効力がない | 取り消されるまでは一応有効、取り消されると初めから無効に |
| 主張できる人 | 誰でも | 特定の人(取消権者)のみ |
| 主張できる期間 | 制限なし(いつでも) | 制限あり(追認できる時から5年、行為の時から20年) |
| 追認 | 原則できない | できる(追認すると、もう取り消せなくなる) |
やっぱり有効にしたい!「追認」とは?追認できるタイミング
最後に「追認(ついにん)」です。これは「取消し」とセットで出てくることが多い言葉です。
- 追認 (ついにん):取り消すことができる法律行為(契約など)を、後から有効なものとして確定させる意思表示のこと。
「追って認める」という字の通りですね。取消しができるということは、契約の効力がまだ不安定な状態です。その不安定な状態を、「やっぱりこの契約、有効にします!」と確定させるのが追認です。
さっきの「騙されてモノを買わされた」例で考えてみましょう。
騙された買主は、契約を取り消すことができますよね。でも、もし「騙されたのは悔しいけど、この商品自体は欲しかったんだよな…」と思った場合。
買主は「取消し」をしないで、「追認」することを選べます。
追認をすれば、その契約は完全に有効なものとして確定し、以後、取り消すことはできなくなります。
<ポイント>
- 追認は、取消権の放棄を意味します。
- 追認ができるのは、取消しができる人(取消権者)だけです。相手方(例でいう売主)は追認できません。
ここ、大事なポイントです! いつでも追認できるわけではありません。
追認は、「取消しの原因となっていた状況が消滅した『後』」でなければ、原則として有効な追認とはなりません。
- 制限行為能力者の場合:
- 未成年者が成年に達した後。
- 成年被後見人が、判断能力を回復して後見開始の審判が取り消された後。
- 詐欺の場合:
- 騙されていたことに気づいた後。
- 強迫の場合:
- 脅迫されている状態が終わった後。

冷静に判断できる状態になってからじゃないと、本当に有効な追認とは言えない、ということですね。ただし、法定代理人や保佐人、補助人が追認する場合は、本人の状況に関わらず、いつでも行うことができます。
条件?期限?契約の効力発生・消滅のタイミングを左右する「条件」と「期限」
契約を結ぶときに、「もし〇〇だったら、この契約を有効にしよう」とか、「〇月〇日から効力が発生するようにしよう」みたいに、契約の効力が発生したり消滅したりするタイミングを、将来の出来事に結びつけることがあります。これが「条件(じょうけん)」と「期限(きげん)」です。これも民法の重要ワードですよ!
合格したら家をあげる!「停止条件」とは?宅建業法との関係もチェック
まずは「停止条件(ていしじょうけん)」から見ていきましょう。
- 停止条件 (ていしじょうけん):ある条件が成就(じょうじゅ:実現すること)するまで、法律行為(契約など)の効力の発生を停止させておく条件のこと。
「停止」という言葉がついていますが、何を停止させるかというと、「契約の効力」が発生するのを、条件が整うまで「待った!」をかけているイメージです。
「もし君が独学で宅建試験に合格したら、この家を君にあげよう」という約束(贈与契約)をしたとします。
- 「もし君が独学で宅建試験に合格したら」 → これが停止条件
- 「この家を君にあげよう」 → これが贈与契約
この場合、契約自体は成立していますが、「宅建に合格する」という条件が成就するまでは、「家をあげる」という契約の効力は発生しません(停止している)。そして、見事!宅建に合格したその時から、家をもらえる権利が発生する、というわけです。
- 契約自体は有効に成立: 条件付きでも契約は契約。正当な理由なく一方的に解除はできません(効力は発生してなくても)。
- 故意の妨害はNG: 条件が成就しないようにわざと邪魔をしたら、その条件は成就したものとみなされます。例えば、上の例で、家をあげる約束をした人が、合格しそうになったら勉強道具を隠すとか! そういう妨害をしたら、合格したものとして家をあげないといけなくなる可能性があります。
- 相続の対象: 条件付き契約の当事者が亡くなった場合、その「条件が成就したら権利を得られる(または義務を負う)かもしれない」という地位も相続されます。
- 条件成就の効果は原則、将来に向かって発生: 停止条件の場合、条件が成就した時から効力が発生するのが原則です。(ただし、当事者の合意でさかのぼらせる(遡及させる)ことも可能です。)
【宅建業法との関係:ここが超重要!】
宅建試験では、この停止条件が宅建業法と絡めて出題されることが多いんです! 特に「8種規制」の一つである「自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限」との関係が重要です。
8種規制とは?
売主が宅建業者で、買主が宅建業者以外(一般消費者など)の場合に、買主を保護するために宅建業者に課せられる8つの制限のことです。
この制限の中に、「宅建業者は、自己の所有に属しない宅地建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む)を締結してはならない」というルールがあります。例外的にOKな場合もあるのですが、その一つが停止条件付契約なんです。
…と言いたいところですが、実は原則として停止条件付契約でもダメなんです!
停止条件付で「将来、自分が手に入れるかもしれない」という不確実な状態の物件を、宅建業者が一般消費者に売る契約を結ぶことは、原則として禁止されている、と理解しておきましょう。

宅建業法では、買主さんが不利益を被らないように、より厳しいルールが定められているんですね!民法と宅建業法のルールの違いに注意です!
試験に落ちたら仕送りストップ!「解除条件」とは?既成条件・不能条件も解説
次に「解除条件(かいじょじょうけん)」です。停止条件とセットで覚えましょう。
- 解除条件 (かいじょじょうけん):ある条件が成就(実現すること)したら、それまで有効だった法律行為(契約など)の効力が消滅する条件のこと。
停止条件が「効力の発生」に関する条件だったのに対し、解除条件は「効力の消滅」に関する条件です。「解除」という言葉通り、条件が成就すると契約の効力がなくなるイメージですね。
「もし君が次の宅建試験に落ちたら、毎月5万円の仕送りをやめる」という約束(贈与契約)をしたとします。
- 「もし君が次の宅建試験に落ちたら」 → これが解除条件
- 「毎月5万円の仕送りをやめる(=もらう権利がなくなる)」 → 贈与契約の効力が消滅
この場合、契約によって、まず毎月5万円の仕送りをもらう権利が発生しています(効力が生じている状態)。しかし、「宅建試験に落ちる」という条件が成就してしまったら、その成就した時から、仕送りをもらう権利が消滅する(契約の効力がなくなる)わけです。
- 条件成就までは有効: 停止条件とは逆に、解除条件付きの契約は、条件が成就するまでは完全に有効です。
- 条件成就の効果は原則、将来に向かって消滅: 解除条件の場合、条件が成就した時から効力が消滅するのが原則です。
- 遡及効も可能: 停止条件と同じく、当事者の合意があれば、条件成就の効果を契約時にさかのぼらせる(遡及させる)ことも可能です(民法127条3項)。例えば、「試験に落ちたら仕送りを止めると共に、これまで送った分も全額返してもらう」という合意があれば、過去にさかのぼって効力が覆ることになります。
条件には、ちょっと特殊なケースもあります。
- 既成条件 (きせいじょうけん):契約を結んだ時点で、すでに条件が成就している、または成就しないことが確定している場合。
- 解除条件が契約時にすでに成就していた場合(例:「令和6年の試験に落ちたら仕送り終了」という契約を、すでに落ちた後に結んだ場合)→ その契約は無効になります (民法131条1項)。
- 解除条件が契約時にすでに成就しないことが確定していた場合(例:「もし太陽が西から昇ったら仕送り終了」という契約)→ 条件が成就することはありえないので、条件がないのと同じ=無条件の契約となり、仕送りは続くことになります (民法131条2項)。
- 不能条件 (ふのうじょうけん):条件の内容が、そもそも実現不可能な場合。
- 不能な解除条件を付けた契約(例:「東京から大阪まで瞬間移動できるようになったら仕送り終了」という契約)→ 条件が成就することは不可能なので、効力が消滅することもありません。これも無条件の契約となり、仕送りは続くことになります (民法133条2項)。

既成条件や不能条件は少しややこしいですが、理屈で考えると「そりゃそうだよね」ってなりますよ! 無効になるのか、無条件になるのかを区別できるようにしましょう。
いつか必ずやってくる!「期限」とは?始期・終期・確定期限・不確定期限
「条件」と似ているけれど、決定的に違うのが「期限(きげん)」です。
- 期限 (きげん):法律行為(契約など)の効力の発生または消滅を、将来発生することが「確実」な事実にかからせること。
「条件」との一番の違いは、発生するかどうかが「不確実」(例:試験に合格するかどうか)なのか、「確実」(例:来年の5月1日が来ること)なのか、という点です!
期限には、いくつか分類の仕方があります。
- 効力の発生か消滅かで分類
- 始期 (しき):その期限が到来したら、効力が発生するもの。「始まりの時期」ですね。
- 例:「来年の4月1日から、あなたを正社員として雇います」→ 4月1日が来たら雇用契約の効力が発生します。
- 終期 (しゅうき):その期限が到来したら、効力が消滅するもの。「終わりの時期」です。
- 例:「この賃貸契約は、再来年の3月31日まで有効です」→ 3月31日が過ぎたら契約の効力が消滅します。
- 始期 (しき):その期限が到来したら、効力が発生するもの。「始まりの時期」ですね。
- 到来する時期が確定しているかで分類
- 確定期限 (かくていきげん):いつ到来するかが確定している期限。
- 例:「来年の5月1日」「2030年12月31日」など、日付が決まっているもの。
- 不確定期限 (ふかくていきげん):到来すること自体は確実だけど、それがいつになるかは確定していない期限。
- 例:「私が死んだら、この土地をあなたにあげます」→ 人はいつか必ず死ぬので到来は確実ですが、それがいつかは分かりませんよね。
- 例:「次の冬が来たら、暖房器具を納品します」→ 冬は必ず来ますが、具体的に何月何日かは決まっていません。
- 確定期限 (かくていきげん):いつ到来するかが確定している期限。
| 項目 | 条件 | 期限 |
| 将来の事実 | 発生が不確実 | 発生が確実 |
| 例 | 「試験に合格したら」「雨が降ったら」 | 「来年の4月1日」「私が死んだら」 |
| 効力 | 成就/不成就により、発生・消滅・確定など | 到来により、発生または消滅 |
| 遡及効 | 当事者の意思で可能 | なし (期限はさかのぼれません!) |
期限には、条件と違って遡及効がありません。「来年の4月1日から」という始期を、「去年の4月1日から」にさかのぼらせることはできないですよね。時間は戻せませんから!
待ってもらえるメリット?「期限の利益」とは
最後に、「期限」に関連して「期限の利益(きげんのりえき)」という言葉も押さえておきましょう。
- 期限の利益 (きげんのりえき):期限が到来するまでの間、債務(義務)を履行しなくてもよいという、主に債務者(義務を負う側)が受ける利益のこと。
あなたが銀行から100万円を借りて、「返済期限は1年後」という契約(金銭消費貸借契約)を結んだとします。
この場合、あなたは「1年間、100万円を返さなくてもいい」という利益を得ていますよね? この「返済期限まで待ってもらえる」というメリットが、期限の利益なんです。この間、借りたお金を自由に使うことができます。
誰のための利益?
この「期限の利益」は、通常は債務者のためにあると考えられています。
ただし、契約の内容によっては、債権者(権利を持つ側)のため、あるいは双方のためにある場合もあります。
- 無利息の消費貸借:主に債務者のため(借りた側は返済を待ってもらえる)
- 利息付きの消費貸借:債務者と債権者双方のため(借りた側は返済を待ってもらえ、貸した側は期限まで利息を受け取れる)
- 無償の寄託契約(物を預かる契約):主に債権者(預けた側)のため(期限まで預かってもらえる)
期限の利益は放棄できる?
原則として、期限の利益は放棄できます。
さっきの借金の例で、あなたが「1年後じゃなくて、半年後に繰り上げ返済したい!」と思えば、それは可能です。
ただし、その放棄によって相手方の利益を害することはできません。
例えば、利息付きの借金の場合、あなたが繰り上げ返済すると、貸した側(銀行)は本来もらえたはずの残りの期間の利息を受け取れなくなってしまいますよね。この場合、あなたは残りの期間の利息分などを損害として賠償した上でないと、繰り上げ返済(期限の利益の放棄)が認められないことがあります。
【期限の利益を失う場合(期限の利益の喪失)】
債務者が一定の状況になると、この「待ってもらえる」という期限の利益を失ってしまうことがあります。これを期限の利益の喪失(そうしつ)と言います。
民法では、次のような場合に期限の利益を喪失すると定められています。
- 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき
- 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき(例:借金の担保に入れていた家を燃やしてしまった)
- 債務者が担保を提供する義務を負っている場合に、これを提供しないとき
これらの状況になると、債権者は「もう待てない!今すぐ返せ!」と請求できるようになります。

期限の利益、なんとなくイメージできましたか? 借金やローンに関わる身近な話でもありますね!
まとめ
今回は、宅建試験の民法で最初につまずきやすい基本的な法律用語について、詳しく解説してきました。いかがでしたか?
最初はとっつきにくく感じるかもしれませんが、一つひとつの意味と使い方を、具体例とセットで理解していくことが大切です。
- 善意・悪意は「知らない・知っている」、過失は「不注意の度合い」、対抗するは「権利を主張する」。日常用語との違いに注意しましょう。
- 無効は「初めから効力なし」、取消しは「いったん有効だけど後から取り消せる(遡及効あり)」。誰が、いつまで主張できるかの違いも重要でしたね。追認は取消権の放棄です。
- 条件は「不確実な事実」で効力が左右され、期限は「確実な事実」で効力が左右されます。停止条件と解除条件、始期と終期、確定期限と不確定期限、それぞれの違いをしっかり区別しましょう。
- 期限の利益は「待ってもらえるメリット」のことでした。
これらの基本用語は、民法の様々な場面で繰り返し登場します。ここでしっかりと土台を固めておけば、今後の学習がスムーズに進むこと間違いなしです!
- 法律用語は日常の意味と違うことがあるので注意!
- 「善意=知らない」「悪意=知っている」は超基本!
- 「無効」と「取消し」は効力、主張者、期間、追認可否が違う!
- 「条件(不確実)」と「期限(確実)」の違いを意識しよう!
- 具体例をイメージしながら覚えるのが効果的!

民法の学習は覚えることが多くて大変ですが、基本を一つひとつクリアしていけば、必ず理解が深まっていきます。焦らず、諦めずに、一緒に頑張っていきましょうね!

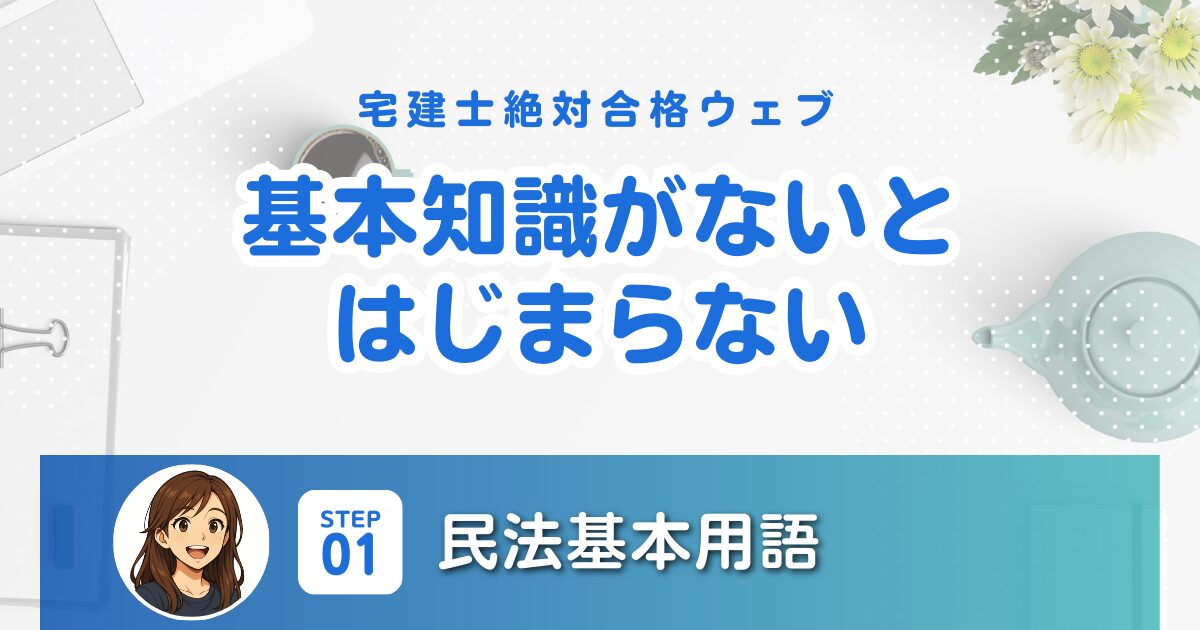


以前は「手付金等の保全措置を講じればOK」という例外があったりしましたが、法改正などを経て、現在は、宅建業者が他人物(まだ自分の所有物になっていない物件)を売る場合、原則として契約自体が禁止されています。
ただし、例外的に契約が許されるのは、「確実に物件を取得できることが担保されている場合」、例えば、取得に関する契約が既に成立している場合や予約が成立している場合(停止条件付などを除く) などに限られます。