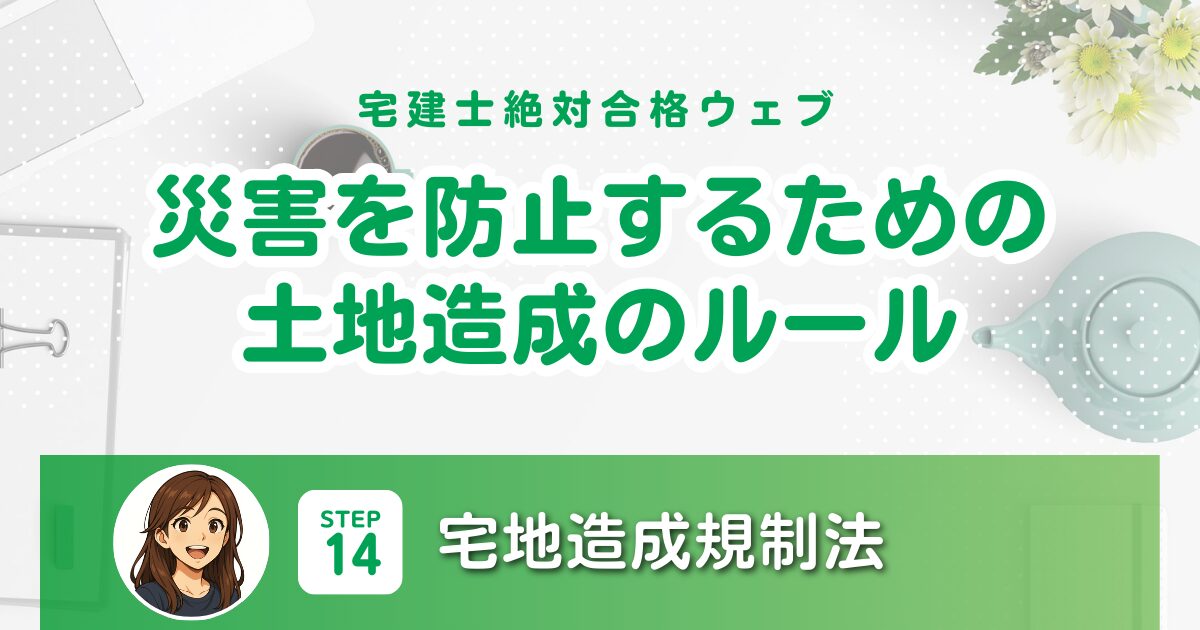「法令上の制限」の分野は、たくさんの法律を覚えなくてはいけなくて、ちょっと大変ですよね…。その中でも、比較的新しく、そして私たちの安全に直結する重要な法律が「宅地造成及び特定盛土等規制法」、通称「盛土規制法(もりどきせいほう)」です。「盛土」っていう言葉、最近ニュースでよく耳にするけど、この法律って何?前の「宅地造成等規制法」とどう違うの?なんだか規制される区域が2つもあるみたいで、ややこしそう…なんて思っていませんか?
実はこの法律、近年、全国各地で問題になっている危険な盛土や、宅地を造成する際の崖崩れ、土砂の流出といった災害を未然に防ぐために、これまでの「宅地造成等規制法」という法律を大幅にパワーアップさせて作られたものなんです。私たちの命や大切な財産を守るための重要なルールが定められているのですが、規制の内容が細かかったり、専門用語が出てきたりして、少しとっつきにくいイメージがあるかもしれません。
そんな「盛土規制法」について、そもそもなぜこの法律ができたのかという背景や目的、基本的な考え方から、特に重要な2種類の規制区域(「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」)の違い、それぞれの区域でどんな工事をするときに許可や届出が必要になるのか、そしてルールを守らなかった場合の罰則まで、わかりやすく解説していきます。

法令上の制限は覚えることが多いですが、一つ一つ丁寧に見ていけば大丈夫ですよ!一緒に頑張りましょう!
<この記事でわかること>
- 盛土規制法が制定された目的と、従来の法律からの変更点が理解できる
- 「宅地」「宅地造成」「特定盛土等」など、重要な用語の定義がわかる
- 「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」という2つの規制区域の違いと、それぞれの指定方法が整理できる
- 各区域でどのような工事を行う場合に、許可や届出が必要になるのか、具体的な規模の違いがわかる
- 土地の所有者などに課せられる安全確保の義務や、違反した場合の罰則の内容が明確になる
盛土規制法の基本 | 目的・用語の定義・規制区域の全体像
まずは、盛土規制法がどんな法律なのか、その骨格となる基本的な部分から押さえていきましょう。ここをしっかり理解することが、複雑な規制内容を読み解くための第一歩になりますよ。
なぜできた?盛土規制法の目的と背景
盛土規制法の正式名称は「宅地造成及び特定盛土等規制法」といいます。ちょっと長いですが、この名前自体が法律の内容を表していますね。
この法律の目的は、シンプルに言うと「宅地造成や、特定の危険な盛土、土石の堆積(物を積み上げること)によって起こる崖崩れや土砂の流出による災害を防ぐこと」です(法第1条)。私たちの安全な暮らしを守るための法律なんですね。
この法律が作られた大きなきっかけの一つに、2021年に静岡県熱海市で発生し、多くの方が犠牲になった大規模な土石流災害があります。この災害では、谷に不安定な状態で盛られた大量の土砂(盛土)が崩れ、被害を拡大させたと指摘されています。
このような災害を受けて、これまでの「宅地造成等規制法」では十分に対応しきれていなかった、宅地以外の土地(森林や農地など)で行われる盛土や、建設現場から出る土(残土)などを単に積み上げておく行為(土石の堆積)についても、危険なものはしっかりと規制する必要がある、という社会的な要請が高まりました。
そこで、従来の法律を抜本的に見直し、規制の対象を広げ、より包括的に危険な盛土等を規制するために、この「盛土規制法」が制定され、2023年5月26日から施行されたという経緯があるんです。
つまり、従来の法律の「宅地造成」に関する規制を引き継ぎつつ、新たに「特定盛土等」と「土石の堆積」も規制対象に加えたのが、この盛土規制法の大きな特徴と言えます。
盛土規制法の用語の定義
盛土規制法を理解する上で、いくつか重要なキーワード(用語)の意味を正確に押さえておく必要があります。試験でも、これらの用語の定義が問われる可能性がありますので、一つ一つしっかり確認していきましょう。
宅地
この法律でいう「宅地」とは、「農地、採草放牧地、森林」ならびに「道路、公園、河川、港湾、飛行場などの公共施設の用に供されている土地」以外の土地を指します(法第2条1号)。
注意点! 宅建業法でいう「宅地」の定義とは少し異なります。宅建業法では、用途地域内であれば原則として全ての土地が宅地ですし、用途地域外でも建物の敷地や、建物を建てる目的で取引される土地は宅地とされますよね。
しかし、盛土規制法では、現況が農地や森林であれば、たとえ将来家を建てる予定があったとしても、この法律上は「宅地」には該当しません。この違いはしっかり区別しておきましょう!
工事主
宅地造成等に関する工事を行う人(主体)のことです。具体的には、「①その工事の請負契約の注文者」または「②請負契約によらずに自らその工事をする者」を指します(法第2条7号)。
例えば、マイホームを建てるために、土地の造成工事を工務店にお願いしたAさんがいるとします。この場合、工事を依頼した(注文した)Aさんが「工事主」になります。一方、不動産会社Bが、自社で所有している土地を分譲するために、自社の従業員を使って造成工事を行う場合は、自ら工事をするB社が「工事主」となります。
実際に工事を行う業者さん(施工業者)のことではない、という点に注意してくださいね。
宅地造成
この法律における「宅地造成」とは、「宅地以外の土地(農地、森林など)」を「宅地」にするために行う、盛土や切土など土地の形質を変更する工事で、一定の規模以上のものをいいます(法第2条2号)。
ここでのポイントは、「宅地以外 → 宅地」という土地の利用目的の変更が伴う点です。例えば、もともと宅地だった土地を駐車場や資材置場(これらは宅地以外の土地)にするために行う造成工事は、土地の形質変更には該当しますが、「宅地造成」には当たりません。
また、単に「宅地」から「宅地」への形質変更(例えば、庭を平らにするなど)も、原則として「宅地造成」には該当しません。ただし、後述する「特定盛土等」や「土石の堆積」に該当すれば、規制の対象になる可能性はあります。
特定盛土等
宅地、農地、採草放牧地、または森林において行われる「盛土」(傾斜地に盛土する場合は、地盤の締固めや擁壁の設置などが不十分なものに限る)その他の土地の形質の変更で、これによって人家等に危害を及ぼすおそれが大きいものとして政令で定めるものをいいます(法第2条3号)。
簡単に言うと、宅地造成には該当しないけれど、危険性が高いと判断される盛土などの工事のことですね。例えば、森林や農地での大規模な盛土などがこれに該当する可能性があります。
土石の堆積
宅地、農地、採草放牧地、または森林において行う、土や石などを一定規模以上積み上げること(土地の形質変更を伴わないもの)を指します(法第2条4号)。
これは、例えば建設現場から出た残土を一時的に(あるいは継続的に)特定の場所に積み上げておくような行為をイメージすると分かりやすいでしょう。これも、やり方によっては崩落などの危険があるため、規制の対象に加えられました。
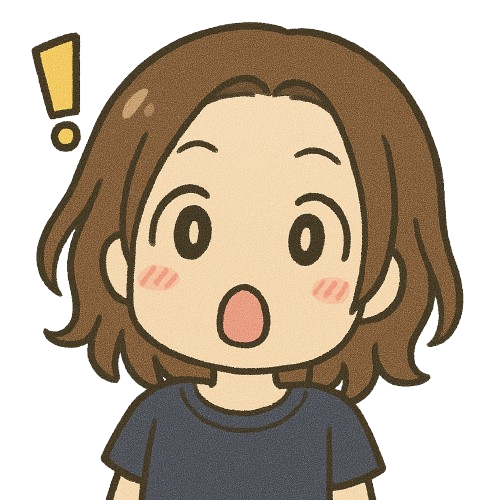
「宅地造成」だけじゃなくて、「特定盛土等」と「土石の堆積」も新たに規制対象になったんですね!これで規制の網の目が細かくなったわけですね。
規制区域は2種類!全体像を掴もう
盛土規制法では、崖崩れや土砂流出による災害を防止するために、特に規制を及ぼす必要がある区域として、2種類の規制区域を都道府県知事等が指定することができます。この2つの区域の違いをしっかり理解することが、盛土規制法の全体像をつかむ上で非常に重要です!
- 宅地造成等工事規制区域(たくちぞうせいとうこうじきせいくいき)
- 特定盛土等規制区域(とくていもりどとうきせいくいき)
それぞれの区域がどんな場所を対象とし、どんな目的で指定されるのか、大まかなイメージをつかみましょう。
1. 宅地造成等工事規制区域
- 主な目的:主に「宅地造成」に伴う崖崩れや土砂流出の災害を防止すること。
- 対象となる場所:市街地や、これから市街地になろうとしている土地(集落を含む)など、人家が集まっている、または集まる可能性のあるエリアが中心です。
- イメージ:従来の「宅地造成工事規制区域」の考え方を基本的に引き継ぎつつ、規制対象となる工事の範囲を広げたもの、と考えると理解しやすいかもしれません。
2. 特定盛土等規制区域
- 主な目的:主に「特定盛土等」や「土石の堆積」によって人家等に危害を及ぼす災害を防止すること。
- 対象となる場所:上記の宅地造成等工事規制区域「以外」の土地で、地形や土地利用の状況から見て、危険な盛土等が行われた場合に、周辺の人家などに被害が及ぶおそれが特に大きいと判断されるエリアです。例えば、山間部や農地などで、不適切な盛土や残土処分が行われるリスクがある場所などが想定されます。
- イメージ:宅地造成が行われにくい場所であっても、危険な盛土等が行われる可能性がある場所をピンポイントで規制するイメージです。
重要なポイント! この2つの規制区域は、互いに重複して指定されることはありません。つまり、ある土地が「宅地造成等工事規制区域」であり、かつ「特定盛土等規制区域」である、ということはないのです。どちらか一方の区域に指定されることになります。
どうでしょう?まずは、この2つの区域の基本的な性格の違いを押さえておきましょう。次の章からは、それぞれの区域について、より具体的な規制の内容、つまり「どんな工事をする時に」「どんな手続きが必要なのか」といった点を詳しく見ていきます。
宅地造成等工事規制区域 | 許可制・届出・保全義務を徹底解説
ここからは、まず「宅地造成等工事規制区域」について詳しく見ていきましょう。市街地など、私たちの生活に身近なエリアが対象となることが多い区域です。従来の宅地造成等規制法の内容を踏襲しつつ、規制が強化されている点がポイントです。

まずは一つ目の区域、宅地造成等工事規制区域からですね。ここは許可が必要な工事の規模をしっかり覚えるのが大切ですよ!
区域の指定と許可が必要な工事(宅地造成)
区域の指定
都道府県知事(または政令指定都市・中核市の市長。以下「都道府県知事等」とします)は、宅地造成に伴う災害の発生状況などを把握するための基礎調査の結果に基づき、関係市町村長の意見を聞いた上で、「宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の土地の区域」を「宅地造成等工事規制区域」として指定することができます(法第10条)。
簡単に言うと、「ここで宅地造成が行われると、崖崩れなどで多くの人に被害が出るかもしれないな」と判断されるエリアを指定する、ということです。区域が指定されると、その旨が公示(広く一般に知らせること)されます。
許可が必要な工事
この「宅地造成等工事規制区域」内で、「宅地造成等に関する工事」を行う場合には、その工事主は、工事に着手する前に、あらかじめ都道府県知事等の許可を受けなければなりません(法第12条)。勝手に工事を始めてはいけない、ということですね。
では、許可が必要となる「宅地造成等に関する工事」とは、具体的にどのような規模の工事なのでしょうか? ここが試験でも非常に狙われやすいポイントです!以下の基準は必ず暗記しましょう。
Q. 宅地造成等工事規制区域で「許可」が必要な工事の規模は?
以下のいずれかに該当する「宅地造成」(宅地以外→宅地への変更)または「特定盛土等・土石の堆積」に関する工事です。
| 工事の種類 | 許可が必要となる規模 | 覚え方のヒント |
|---|---|---|
| 切土(きりど:土地を削り取ること) | 切土をする部分に高さが2mを超える崖(がけ)ができる場合 | キリ(切)が良い「2m」 |
| 盛土(もりど:土を盛ること) | 盛土をする部分に高さが1mを超える崖ができる場合 | 盛り(盛)上がるのは「1m」から |
| 切土と盛土を同時に行う | 盛土をする部分に高さ1m以下の崖ができ、かつ、切土と盛土を合わせて高さが2mを超える崖ができる場合 | 合わせて「2m」 |
| 上記①~③の崖ができない場合でも… | 切土または盛土をする土地の面積が500㎡を超える場合 | 面積はゴーゴー「500㎡」 |
| (参考)特定盛土等・土石の堆積 | 上記と同様の規模(盛土1m超崖、切土2m超崖、面積500㎡超など)に該当する場合 | 宅地造成と同じ基準 |
※「崖」とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。
ポイント整理!
- 崖ができるかどうかがまず重要。「崖」の定義(角度30度超)も意識しましょう。
- 崖ができる場合、切土は2m超、盛土は1m超で許可が必要。盛土の方が基準が厳しい!と覚えましょう。
- 切土と盛土を同時にやる場合も、合計で2m超の崖ができれば許可対象です。
- たとえ崖ができなくても、工事面積が500㎡を超えれば許可が必要になります。
- この基準は、「宅地造成」だけでなく、区域内で行われる同規模の「特定盛土等」や「土石の堆積」にも適用されます。
許可手続きの流れ
許可が必要な工事を行う場合、大まかな手続きの流れは以下のようになります。
- 工事主が都道府県知事等に許可申請書を提出。
- 知事等が申請内容を審査。(技術的基準に適合しているかなどをチェック)
- 審査の結果、問題なければ許可。
- 工事主が工事に着手。
- 工事が完了。
- 工事主が知事等に完了検査を申請。(完了日から4日以内とされることが多いですが、運用は確認要)
- 知事等が工事結果を検査。(許可内容通りか、基準に適合しているか)
- 検査に合格すれば検査済証が交付される。(法第17条)
この検査済証が交付されて、初めてその造成地を使うことができるようになります。
技術的基準と有資格者による設計
許可を受けるためには、その工事計画が、擁壁(ようへき:土砂崩れを防ぐ壁)、排水施設、地盤の締め固めなど、災害防止のために必要な技術的基準(政令で定められています)に適合している必要があります(法第13条)。
さらに、特に危険性が高いと考えられる一定の工事については、専門的な知識や技術を持つ有資格者(例:技術士、一級建築士、RCCMなど)によって設計されなければならない、というルールもあります(法第14条)。
例えば、高さが5mを超える擁壁を設置する工事や、切土または盛土をする土地の面積が1,500㎡を超える土地における排水施設の設置工事などが該当します。
開発許可との関係
都市計画法で定められている「開発許可」を受けた開発行為の中で行われる宅地造成に関する工事については、盛土規制法の許可を受ける必要はありません(法第15条)。
開発許可の手続きの中で、すでに盛土規制法と同等以上の安全基準がチェックされているため、二重の手続きを避ける趣旨です。この場合、盛土規制法の許可があったものとみなされます。
計画の変更
一度受けた許可の内容(工事計画)を変更しようとする場合も、原則として、再度、変更についての許可を受けなければなりません(法第16条)。
ただし、工事の完了予定年月日を延期したり、工事主の氏名や住所が変わったりといった軽微な変更については、変更の許可までは不要で、遅滞なくその旨を届け出ればよいとされています。
許可までは不要でも「届出」が必要なケース
宅地造成等工事規制区域内では、上記の「許可」が必要な規模の工事に該当しない場合でも、以下の特定の行為を行う際には、都道府県知事等への「届出」が必要になります(法第21条)。許可と届出の違い、そしてそれぞれのタイミングをしっかり区別しましょう。
- 区域指定の際に、すでに行われている工事がある場合
- 対象:区域として指定された時に、その区域内ですでに宅地造成等に関する工事(許可が必要な規模のものも含む)を行っている工事主。
- 届出時期:指定があった日から21日以内に届け出る必要があります。
- 擁壁などの除却工事を行う場合
- 対象:区域内で、高さが2mを超える擁壁、排水施設、または地すべり抑止ぐい等の全部または一部を除却(取り壊すこと)する工事を行う者。
- 届出時期:工事に着手する日の14日前までに届け出る必要があります。
- 宅地以外の土地への転用があった場合
- 対象:区域内の土地で、宅地以外の土地(例:公共施設用地である道路や水路など)を宅地、農地、採草放牧地または森林に転用した者。
- 届出時期:転用した日から14日以内に届け出る必要があります。(転用後の用途が規制対象となるため)
届出は許可と違って、事前に審査を受けるものではありませんが、行政が区域内の状況を把握するために必要な手続きです。届出の対象となる行為と、それぞれの届出期限(「指定から21日以内」「着手14日前まで」「転用から14日以内」)をセットで覚えておきましょう!
土地の安全を守る!保全義務・勧告・改善命令
宅地造成等工事規制区域内の土地については、工事を行う時だけでなく、その後の維持管理においても、安全を確保するための責任が課せられています。
土地の保全義務
区域内の宅地の所有者、管理者、または占有者は、その宅地について、宅地造成等に伴う災害が生じないように、常時安全な状態に維持するように努めなければならないとされています(法第22条)。これは「努力義務」ですが、自分の土地だからといって危険な状態を放置してはいけない、という考え方を示しています。この義務は、区域が指定される前から存在していた造成地(既存の造成地)などにも適用されます。
勧告
都道府県知事等は、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要があると認める場合には、その土地の所有者、管理者、占有者、工事主、または工事施行者(実際に工事を行う業者)に対して、擁壁の設置や改造、盛土の改良など、災害防止のために必要な措置をとることを勧告することができます。
改善命令
さらに、擁壁などの安全性が十分でなく、そのまま放置しておくと重大な災害を引き起こすおそれが大きいと認められる場合には、都道府県知事等は、その土地の所有者、管理者、または占有者に対して、相当の猶予期間を設けて、擁壁の設置や改造、あるいは盛土の改良といった災害防止のための工事を行うことを命じることができます(法第23条)。これを改善命令といいます。勧告に従わない場合や、緊急性が高い場合などに出される、より強制力の強い措置です。
報告徴収・監督処分
都道府県知事等は、法律の施行に必要な限度で、土地の所有者や工事主などに対して、工事の状況などについて報告を求めることができます(報告徴収)。また、不正な手段で許可を受けたり、許可の条件に違反したり、法律の規定に違反した場合には、その許可を取り消したり、工事の停止を命じたり、改善命令と同様の措置を命じたりすることができます(監督処分)。
罰則は重い!違反した場合のペナルティ
宅地造成等工事規制区域内でのルール違反に対しては、非常に重い罰則が定められています。これは、違反行為が人命に関わる重大な災害につながる可能性があるためです。
主な罰則の例(法第55条など)
- 無許可で宅地造成等の工事(許可が必要な規模のもの)を行った者
- 不正な手段(虚偽の申請など)によって許可を受けた者
- 都道府県知事等からの改善命令や工事停止命令に違反した者
- 技術的基準に適合しない違反設計を行った設計者
- 設計図書通りに施工せず、技術的基準に適合しない違反施工を行った工事施行者(元請・下請を含む)
これらの違反行為に対しては、「3年以下の懲役 または 1000万円以下の罰金」という重い罰則が科せられます。さらに、法人がこれらの違反行為を行った場合には、行為者を罰するだけでなく、その法人に対しても「3億円以下の罰金」が科される可能性があります(両罰規定)。
届出義務違反や報告義務違反などに対しても、別途罰金刑などが定められています。ルールを守ることの重要性が、これらの罰則の重さからもわかりますね。
特定盛土等規制区域 | より危険な盛土等を規制!許可と届出
次に、もう一つの規制区域である「特定盛土等規制区域」について見ていきましょう。こちらは、宅地造成等工事規制区域「以外」の場所、例えば山林や農地などで、特に危険性が高いと判断される盛土や土石の堆積をピンポイントで規制するための区域です。
どんな区域?指定の要件と目的
区域の指定
都道府県知事等は、基礎調査の結果などを踏まえ、関係市町村長の意見を聞いて、「宅地造成等工事規制区域以外の土地」の区域であって、その区域内の土地の地形や土地利用の状況などからみて、その区域内で「特定盛土等」または「土石の堆積」が行われた場合に、これに伴う崖崩れや土砂の流出によって、人家等に危害を及ぼすおそれが特に大きいと認められる区域を、「特定盛土等規制区域」として指定することができます(法第26条)。
ここでのポイントは、あくまで「宅地造成等工事規制区域以外の土地」が対象であること、そして規制の主眼が「特定盛土等」と「土石の堆積」にあることです。
目的
この区域が設けられた主な目的は、宅地造成には当たらないものの、例えば森林を伐採して大規模な盛土を行ったり、あるいは建設現場から出た残土を農地に不適切に長期間積み上げたりするような行為によって、下流の人家などに被害が及ぶのを未然に防ぐことです。熱海市の土石流災害の教訓を踏まえ、こうしたリスクに対応するために新設された規制区域と言えます。
繰り返しになりますが、重要なのでもう一度!
特定盛土等規制区域は、宅地造成等工事規制区域と重複して指定されることはありません。ある土地がどちらの区域に属するかは、都道府県等が公表する情報(指定区域図など)で確認する必要があります。
ここでも許可・届出が必要!規模の違いに注意
特定盛土等規制区域内においても、一定の工事を行う場合には、都道府県知事等への「届出」または「許可」が必要になります。ここで注意したいのは、届出や許可が必要となる工事の「規模」が、宅地造成等工事規制区域の場合と一部異なる点です。しっかり比較して覚えましょう。
1. 届出が必要な工事
- 対象となる行為:区域内で行われる「特定盛土等」または「土石の堆積」に関する工事(ただし、後述する「許可」が必要な規模には満たないもの)。
- 手続き:工事主は、工事に着手する日の30日前までに、工事計画を知事等に届け出る必要があります(法第27条)。
- 届出が必要となる規模:実は、この届出が必要となる規模は、先ほど見た「宅地造成等工事規制区域」で『許可』が必要となる規模と同じです!
【特定盛土等規制区域で『届出』が必要な規模】(宅造区域の許可規模と同じ)
- 切土で高さ2m超の崖ができる
- 盛土で高さ1m超の崖ができる
- 切土と盛土を合わせて高さ2m超の崖ができる
- 上記に該当しなくても、切土または盛土をする土地の面積が500㎡を超える
- (土石の堆積の場合も、盛土の基準に準じて判断されることが多いですが、詳細は要確認)
あれ?と思いましたか?そうなんです。宅地造成等工事規制区域であれば「許可」が必要な規模の工事でも、特定盛土等規制区域で行う場合は、まずは「届出」(しかも着手30日前まで)でよい、ということになります。ただし、届出内容が不適切な場合は、知事等が計画変更を命じることもできます(法第29条)。
また、区域が指定された時にすでに行われている工事(許可が必要な規模を含む)については、指定があった日から起算して21日以内に届け出る必要があります(法第40条)。これは宅造区域の場合と同じですね。

区域によって同じ規模でも手続きが違うんですね。特定盛土等規制区域の方が、まずは届出でOKな範囲が広い、と。これは引っかかりやすいポイントかも!
2. 許可が必要な工事
特定盛土等規制区域内でも、特に大規模な「特定盛土等」または「土石の堆積」に関する工事を行う場合には、都道府県知事等の「許可」が必要になります(法第30条)。
- 対象となる行為:区域内で行われる「特定盛土等」または「土石の堆積」に関する工事で、特に大規模なもの。
- 手続き:工事主は、工事に着手する前に、あらかじめ知事等の許可を受けなければなりません。許可申請、審査、技術基準への適合、完了検査、検査済証の交付といった手続きの流れは、宅地造成等工事規制区域の許可の場合とほぼ同様です(法第31条~第35条)。
- 許可が必要となる規模(大規模):ここが重要です!届出で済む規模よりも、さらに大きな規模の工事が許可の対象となります。
Q. 特定盛土等規制区域で「許可」が必要な工事の規模は?
以下のいずれかに該当する、特に大規模な工事です。
【特定盛土等(盛土・切土)の場合】(法第30条1項)
- 盛土をする部分に高さが2mを超える崖ができるもの
- 切土をする部分に高さが5mを超える崖ができるもの
- 盛土と切土を合わせて高さが5mを超える崖ができるもの
- 上記①~③の崖が生じない場合でも、盛土をする部分の高さが5mを超えるもの
- 上記①~④に該当しなくても、盛土または切土をする土地の面積が3000㎡を超えるもの
【土石の堆積の場合】(法第30条2項)
- 堆積する部分の高さが5mを超え、かつ、堆積を行う土地の面積が1500㎡を超えるもの
- 堆積する部分の高さが5m以下であっても、堆積を行う土地の面積が3000㎡を超えるもの
規模要件の比較ポイント!
宅地造成等工事規制区域の許可基準(切土2m崖、盛土1m崖、面積500㎡超)と比べて、特定盛土等規制区域の許可基準は、かなり大規模な工事が対象になっていることがわかりますね。(切土5m崖、盛土2m崖、面積3000㎡超など)。
規模要件のまとめ比較表
| 区域 | 手続き | 主な規模要件(例:崖ができる場合) | 主な規模要件(例:面積) | 対象となる主な行為 |
|---|---|---|---|---|
| 宅地造成等工事規制区域 | 許可 | 切土2m超崖 盛土1m超崖 | 500㎡超 | 宅地造成等 |
| 届出 | (擁壁除却、区域指定時工事、転用) | 特定行為 | ||
| 特定盛土等規制区域 | 届出 (着手30日前) | 切土2m超崖 盛土1m超崖 | 500㎡超 | 特定盛土等 土石の堆積 |
| 許可 | 切土5m超崖 盛土2m超崖 | 3000㎡超 (土石堆積は別途基準あり) | 特定盛土等 土石の堆積(大規模) | |
ここが大きな違い! 特定盛土等規制区域では、宅地造成等工事規制区域とは異なり、規制対象となる行為に「宅地造成」(宅地以外→宅地)が含まれていません。その代わり、「特定盛土等」や「土石の堆積」が規制の中心であり、これらは農地や森林における行為も対象となる点が非常に重要です。宅地造成等工事規制区域は主に「宅地」が舞台でしたが、こちらは「農地」や「森林」も舞台になり得る、という違いがあります。
罰則
特定盛土等規制区域内において、無許可で大規模な工事を行ったり、届出を怠ったり、あるいは都道府県知事等からの命令(計画変更命令や改善命令など)に違反した場合の罰則も、宅地造成等工事規制区域の場合と同様に厳しいものが定められています。
無許可工事や改善命令違反など、重大な違反に対しては、「3年以下の懲役 または 1000万円以下の罰金」(法人の場合は3億円以下の罰金)が科せられます(法第55条など)。
やはり、こちらの区域でもルールをしっかりと守ることが求められます。
まとめ
今回は、2023年5月から新しく施行された「盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)」について、その目的や背景、重要な用語の定義、そして宅建試験対策として特に重要な2種類の規制区域(宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域)における許可・届出制度や罰則などを中心に解説してきました。
少し複雑に感じられたかもしれませんが、この法律は、危険な盛土などによる悲しい災害を繰り返さないために作られた、私たちの安全を守るための大切なルールです。規制の対象となる場所(区域)や行為(宅地造成、特定盛土等、土石堆積)、そして手続きが必要となる「規模」をきちんと整理して理解すれば、きっと攻略できるはずです!
最後に、今回の重要ポイントを箇条書きでまとめておさらいしましょう。
- 盛土規制法は、宅地造成、特定盛土等、土石の堆積に伴う崖崩れや土砂流出による災害を防止することを目的とした法律です。
- 規制区域には、主に市街地などを対象とし宅地造成等を規制する「宅地造成等工事規制区域」と、それ以外の場所で特定盛土等・土石の堆積を規制する「特定盛土等規制区域」の2種類があり、重複して指定されることはありません。
- 宅地造成等工事規制区域では、一定規模(例:切土2m超崖、盛土1m超崖、面積500㎡超)の宅地造成等工事を行う場合に、都道府県知事等の許可が必要です。また、擁壁の除却など特定の行為には届出が必要です。
- 特定盛土等規制区域では、一定規模(宅造区域の許可規模と同じ)の特定盛土等・土石の堆積工事を行う場合に、着手30日前までの届出が必要です。さらに大規模(例:切土5m超崖、盛土2m超崖、面積3000㎡超)な工事を行う場合には、都道府県知事等の許可が必要です。この区域では農地や森林における行為も対象となります。
- どちらの区域内の土地についても、所有者等には安全確保の努力義務があり、知事等は危険な状態に対して勧告や改善命令を出すことができます。
- 無許可工事や改善命令違反などの重大な違反行為には、「3年以下の懲役または1000万円以下の罰金」(法人には最大3億円の罰金)という重い罰則が科せられます。

2つの区域の違い、特に許可・届出が必要になる「規模」の数字の違いをしっかり区別して覚えることが、盛土規制法をマスターする一番の近道ですよ!頑張ってくださいね!