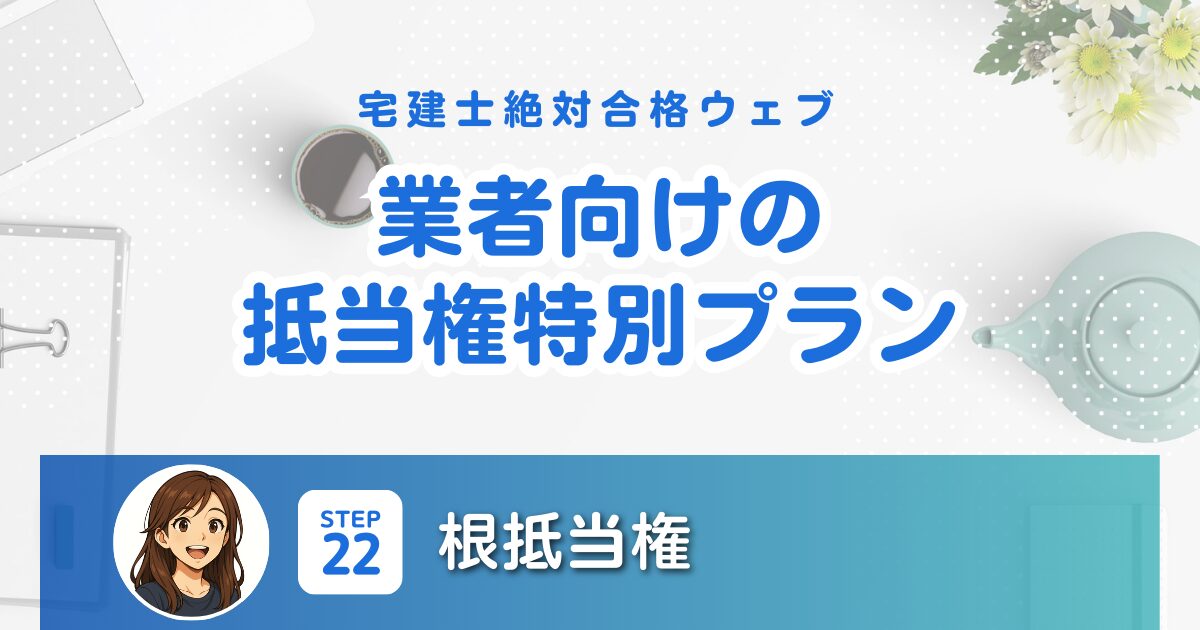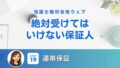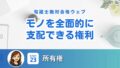権利関係の中でも、「抵当権」と名前が似ている「根抵当権(ねていとうけん)」って、違いがよくわからなくて混乱しやすいポイントですよね。「どっちも不動産を担保にするんでしょ?」くらいのイメージの方もいらっしゃるかもしれません。普通の抵当権と根抵当権、その違いをしっかり説明できますか?
実は、根抵当権は、特に会社経営や個人事業主の方など、継続的にお金のやり取りがある場合に、とっても便利な仕組みなんです。ただ、普通の抵当権とは違う独特のルールがたくさんあります。
この記事では、そんなちょっととっつきにくい根抵当権について、まずは基本から、そして一番大事な普通の抵当権との違いを比べながら、詳しく解説していきますね。どんな仕組みなのか、どんな時に使われるのか、根抵当権ならではのちょっと変わった特徴(付従性がない、とか)まで、できるだけイメージしやすいように説明していきますので、安心してくださいね!
この記事を最後まで読んでいただければ、「根抵当権って結局なに?」というモヤモヤがスッキリ解消されて、抵当権との違いもバッチリ区別できるようになります。

根抵当権、ちょっと複雑ですけど、ポイントを押さえれば大丈夫ですよ!
<この記事でわかること>
- 根抵当権の基本的な仕組みと、抵当権との明確な違いについて理解できる
- 根抵当権がどんな場面で利用され、なぜ便利なのかがわかる
- 根抵当権を理解する上で最も重要なキーワード「元本確定」の意味とタイミングが明確になる
- 根抵当権の独特な特徴(付従性・随伴性の否定、効力範囲など)のポイントが整理できる
- 根抵当権の内容変更に関するルール(できること・できないこと、注意点)がわかる
根抵当権ってなに?抵当権との違いは?
まずは、「根抵当権ってそもそも何なの?」という基本のキから見ていきましょう。普通の抵当権とどこが違うのかを常に意識しながら読むと、理解がぐっと深まりますよ。

抵当権との違いがわかれば、根抵当権の輪郭が見えてきますよ!
根抵当権のキホン:上限額まで繰り返し使える便利な担保!
根抵当権(ねていとうけん)とは、すごく簡単に言うと、「持っている不動産(土地や建物)を担保にして、あらかじめ『ここまでならOKですよ』と決めた上限額(これを極度額:きょくどがくと言います)の範囲内であれば、特定の種類の取引に関して、将来にわたって何度でもお金を借りたり返したりできる権利」のことなんです。
普通の抵当権を思い出してください。あれは、「A銀行から住宅ローンとして3,000万円を借りました」というような、特定の1つの借金(債権)を担保するためのものでしたよね。家を買う時にローンを組んで、そのローン返済のために自宅に抵当権が設定される、というのが典型的な例です。
それに対して根抵当権は、個別の具体的な借金を一つ一つ担保するのではなく、「これから発生するかもしれない、まだ特定されていない複数の借金(不特定の債権)」を、いわば「枠」でまとめて担保するイメージなんです。
<根抵当権のイメージ>
ちょっと具体例でイメージしてみましょう。
【登場人物】
Aさん:会社の社長。自社の土地を持っている。(根抵当権設定者であり、お金を借りる債務者)
B銀行:Aさんの会社に運転資金を融資する銀行。(根抵当権者であり、お金を貸す債権者)
【根抵当権の設定内容】
担保物件:Aさん所有の工場とその土地
極度額:5,000万円(この上限までは担保しますよ、という保証枠)
被担保債権の範囲:「銀行取引によって生じる一切の債権」(例:手形貸付、当座貸越など、銀行との間で発生する借金全般)
このような根抵当権を設定しておけば、AさんはB銀行との間で「銀行取引」に関する借入れであれば、極度額である5,000万円の範囲内で、①借りて → ②返して → ③また借りて…ということを、契約期間中なら自由に繰り返せるわけです。その都度、面倒な抵当権設定の登記手続きをする必要がありません。
極度額(きょくどがく)は、根抵当権で担保される債権の最大限度額のことです。実際に借りている額ではなく、「この範囲までなら担保しますよ」という上限の枠を示す金額です。根抵当権を設定する際には、この極度額を必ず定めなければなりません。
具体例で理解!どんな時に根抵当権が使われるの?
根抵当権は、このように継続的な取引関係がある場合に特にその真価を発揮します。ですから、個人の住宅ローンなど一回きりの大きな借入れよりも、事業者間の取引や、会社が銀行から運転資金を継続的に借り入れるようなケースでよく利用されるんです。
例:部品メーカーA社と取引銀行B銀行のケース
- 部品メーカーのA社は、材料の仕入れ代金の支払いや、従業員の給料支払いなどのために、取引先のB銀行から頻繁に運転資金を借りたり、返済したりを繰り返しています。
- もしこれが普通の抵当権だったら、A社がB銀行からお金を借りるたびに、毎回、抵当権設定契約を結び、法務局で登記手続きをしなければなりません。これでは、手間も時間も、そして登記費用(登録免許税や司法書士報酬)もかかって、すごく大変ですよね。
- そこで、A社は自社工場(不動産)に、B銀行を根抵当権者とする根抵当権を設定することにしました。
- 極度額:8,000万円
- 被担保債権の範囲:「銀行取引」
- こうしておけば、A社はB銀行から、「銀行取引」に関する借入れ(例えば、手形割引や短期の貸付など)であれば、その合計額が8,000万円を超えない限り、必要な時にスムーズに融資を受けられるようになります。B銀行にとっても、一度設定しておけば、8,000万円までは確実に担保が確保されている状態になるので、安心して融資を実行しやすくなります。
まさに、取引のたびに登記手続きをしなくて済むので、貸す側(銀行)も借りる側(会社)も、お互いにとって効率的で便利な仕組みなんですね。
抵当権と根抵当権の決定的な違い【特定 vs 不特定】
さて、ここで一度、普通の抵当権と根抵当権の最も根本的で重要な違いを、しっかりと頭に入れておきましょう。それは、「担保される借金(被担保債権:ひたんぽさいけん)が、設定時点で特定されているかどうか」という点です。
- 抵当権:
「〇年〇月〇日にA銀行から借りた住宅ローン3,000万円」のように、特定の、具体的な1つの債権を担保します。
その特定の借金が返済されれば、抵当権も原則としてその役目を終えて消滅します(これを付従性:ふじゅうせい と言います)。 - 根抵当権:
「これからA社とB銀行の間で発生する『銀行取引』に関する債権」のように、まだ発生していないものも含めた、不特定の複数の債権を、あらかじめ決めた極度額という「枠」の中でまとめて担保します。
そのため、一時的に借金の残高がゼロになったとしても、取引関係が続く限り、根抵当権は原則として消滅しません(つまり、付従性がないのです)。
抵当権は、特定の借金をピンポイントで狙い撃ちするイメージ。
根抵当権は、将来発生するかもしれない借金をまとめてキャッチする「網」や「枠」のようなイメージ、と言うと分かりやすいでしょうか?
この「特定か、不特定か」という違いが、これから説明していく根抵当権の様々な独特な特徴(付従性がない、随伴性がない、元本確定が必要、など)の根源になっています。ここをしっかり理解しておくと、他の論点もスムーズに頭に入ってきますよ。
<比較表>抵当権と根抵当権の違いまとめ
ここで、抵当権と根抵当権の主な違いを表にまとめて整理しておきましょう。試験前にもサッと確認できるようにしておくと便利です。
| 項目 | 抵当権 | 根抵当権 |
|---|---|---|
| 担保される債権 | 特定の債権(例:住宅ローン) | 不特定の債権(一定の範囲内のもの) |
| 付従性(ふじゅうせい) (債権が消滅したら担保権も消滅するか) | あり (借金を完済すれば原則消滅) | なし(元本確定前は、債権が一時的にゼロでも消滅しない) |
| 随伴性(ずいはんせい) (債権が譲渡されたら担保権も移転するか) | あり (債権譲渡で抵当権も一緒に移転) | なし(元本確定前は、特定の債権が譲渡されても根抵当権は原則移転しない) |
| 極度額(きょくどがく) | なし (借りた債権額がそのまま担保額) | あり(必ず定める必要あり) (担保される上限額) |
| 利息・損害金の担保範囲 | 元本 + 利息・損害金 (ただし利息等は最後の2年分に限られる場合あり) | 元本 + 利息・損害金 (極度額の範囲内なら全額担保、期間制限なし) |
| 主な利用場面 | 住宅ローン、事業用の一括融資など個別の貸付 | 継続的な取引(企業の運転資金融資、手形割引など) |
※付従性・随伴性の否定は、主に元本確定前の特徴です。
どうでしょうか?こうして比べてみると、名前は似ていても、性質がかなり違うことがわかりますよね。
根抵当権のポイント!特徴と元本確定、変更ルールについて
根抵当権の基本的な仕組みと、抵当権との大きな違いがイメージできたところで、次は宅建試験で特に重要となる根抵当権ならではのルールや特徴について、さらに詳しく掘り下げていきましょう。何度も出てくる「元本確定」というキーワードが、ここでも主役になりますよ!

ここからが本番!試験で問われやすいポイントをしっかり押さえましょう!
いつ借金が確定する?「元本確定」とは?
根抵当権は、「極度額」という上限の枠の中で、将来発生する不特定の借金を担保するものでした。つまり、設定した時点では「最終的にいくらの借金を担保することになるのか」は、まだ決まっていない、フワフワした状態なんです。
でも、いつまでもその状態だと、いざ根抵当権を実行して不動産を競売にかける時や、権利関係を整理したい時に、「結局、この根抵当権はいくらの借金を担保してるの?」がハッキリせず、困ってしまいますよね。
そこで、「ある特定のタイミングで、それ以降は新たな借金を担保対象から外し、その時点で存在している借金の総額(元本)をカチッと確定させる」という手続きが必要になります。この、担保される借金の元本をフィックスさせることを「元本確定(がんぽんかくてい)」と言うんです。
元本確定 = 根抵当権が担保する借金の金額(元本)を最終決定し、それ以降の新たな借入は担保しないようにすること。
元本確定のタイミングは?(元本確定事由)
では、具体的にどんな時に元本は確定するのでしょうか? 民法で定められている主なケース(これを元本確定事由:がんぽんかくていじゆう と言います)を見てみましょう。
- ① 確定期日の到来:
根抵当権を設定する際に、「〇年〇月〇日に元本を確定する」というように、あらかじめ元本を確定させる期日(確定期日)を決めていた場合、その日が来れば自動的に元本が確定します。(ただし、この確定期日は、根抵当権の設定時から5年以内の日で定めなければなりません。) - ② 元本確定請求:
当事者(根抵当権者や設定者)が、「元本を確定させてください!」と請求した場合。(これについては後で詳しく説明しますね。) - ③ 根抵当権者または債務者の破産等:
お金を貸している根抵当権者、またはお金を借りている債務者(もしくは根抵当権設定者)が破産手続開始の決定を受けた場合、元本は確定します。(他にも、会社更生や民事再生の手続開始なども確定事由になります。) - ④ 根抵当権の実行(競売申立て等):
根抵当権者が、担保不動産の競売を申し立てた場合、または、その不動産が他の債権者によって差し押さえられた場合などにも、元本は確定します。 - ⑤ 当事者間の合意:
根抵当権者と設定者が話し合って、「今日で元本を確定させましょう」と合意した場合も、元本は確定します。
これらの事由が発生すると、それ以降に発生した新たな債権は、もうその根抵当権では担保されなくなります。
誰がいつ「元本確定請求」できるの?
上記の確定事由のうち、「② 元本確定請求」について、もう少し詳しく見てみましょう。確定期日を特に定めていない場合でも、当事者は一定の条件を満たせば、元本の確定を一方的に請求することができます。
- 根抵当権設定者(不動産の所有者など)からの請求:
- 請求できる時期:根抵当権の設定時から3年が経過した後であれば、いつでも請求できます。
- 確定する時期:請求してから2週間が経過した時に元本が確定します。
- 根抵当権者(お金を貸している側)からの請求:
- 請求できる時期:いつでも請求できます。(設定後すぐでもOK)
- 確定する時期:請求した時に直ちに元本が確定します。
【ここがポイント!】
確定期日の定めがない場合…
・設定者は「設定後3年経過」したら請求でき、「2週間後」に確定。
・根抵当権者は「いつでも」請求でき、「直ちに」確定。
この違いは試験で問われやすいので、しっかり覚えましょう!
元本が確定したらどうなるの? → 普通の抵当権に変身!
さて、元本が確定すると、その時点で実際に存在している借金の額(+利息など)が、その根抵当権によって最終的に担保される金額となります。
そして、ここが非常に重要なポイントなのですが、元本が確定した後の根抵当権は、その性質が大きく変わり、普通の抵当権とほぼ同じように扱われるようになるんです!
具体的には、以下のような変化が起こります。
- ① 新たな借金は担保されない:
元本確定後に新たに発生した借金は、もうその根抵当権の担保対象にはなりません。(枠が閉じられたイメージ) - ② 付従性が復活する:
確定した元本とその利息などを全額返済すれば、根抵当権も消滅するようになります。(普通の抵当権と同じ!) - ③ 随伴性が復活する:
確定した債権(元本)を第三者に譲渡すれば、根抵当権も一緒にその第三者に移転するようになります。(これも普通の抵当権と同じ!)

元本確定は、根抵当権が普通の抵当権に「変身」するスイッチみたいなものなんですね!
この「元本確定前」と「元本確定後」で根抵当権の性質が変わる、という点をしっかり理解しておくことが、根抵当権マスターへの鍵となります。
根抵当権の4つの大きな特徴【付従性なし・随伴性なし・範囲限定・効力範囲】
元本確定前の根抵当権には、普通の抵当権にはない(または大きく異なる)特徴がいくつかあります。これらは宅建試験でも頻出の論点ですので、一つ一つ確実に押さえていきましょう。
特徴①:全額返済しても消えない!?【付従性の否定】
先ほども少し触れましたが、これは根抵当権の最も基本的な特徴の一つです。
普通の抵当権なら、担保している借金を全額返済すれば、その借金(主債務)に従って、抵当権(従たる権利)も原則として消滅しますよね。これを「付従性(ふじゅうせい)」と言いました。
しかし、元本確定前の根抵当権には、この付従性がありません。どういうことかと言うと、例えば、根抵当権を設定している会社が、一時的に業績が良くなって借入金の残高がゼロになったとしても、それだけでは根抵当権は自動的には消滅しないんです。
なぜなら、根抵当権は特定の借金ではなく、「継続的な取引の枠」を担保しているからです。一時的に残高がゼロでも、また将来借り入れる可能性がある限り、枠自体は有効なまま残り、いつでもまた借りられる状態が続くわけですね。
根抵当権を消滅させるには、借金をゼロにした上で、さらに当事者(根抵当権者と設定者)が「もうこの根抵当権は使いません」と合意して、法務局で抹消登記の手続きをする必要があります。完済しただけではダメ、という点をしっかり覚えておきましょう!
特徴②:どんな借金もOKじゃない!【被担保債権の範囲の限定】
根抵当権は「不特定の債権」を担保すると言いましたが、だからといって「どんな種類の借金でも、とにかく全部まとめて担保できる」というわけではありません。
根抵当権を設定する際には、債務者との間で「一定の範囲に属する不特定の債権」を担保するものとして、その範囲を特定しなければならない、と決められています。
例えば、
- 「銀行取引によって生じる債権」
- 「手形上または小切手上の債権」
- 「A社とB社の間の継続的な商品売買取引によって生じる債権」
のように、取引の種類を具体的に特定する必要があるんです。
逆に、「債務者との間に生じる一切の債権」とか「将来発生する全ての債権」のような、範囲を全く限定しない包括的な根抵当権(これを包括根抵当権:ほうかつねていとうけん と言います)は、原則として認められていません。あまりに範囲が広すぎると、債務者や他の債権者にとって不測の損害を与える可能性があるからです。
ちゃんと、「どんな種類の取引から発生する借金を担保するのか」を限定しないといけないんですね。
特徴③:債権を譲渡してもついていかない!【随伴性の否定】
これも重要な特徴です。普通の抵当権の場合、担保している特定の債権(例えば、住宅ローン債権)が、銀行Aから債権回収会社Bに譲渡されると、その債権にくっついている抵当権も一緒にBに移転しますよね。これを「随伴性(ずいはんせい)」と言いました。
しかし、元本確定前の根抵当権には、原則としてこの随伴性がありません。どういうことかというと、例えば、根抵当権者B銀行が、被担保債権の範囲に含まれる個々の債権(例えば、A社に貸した運転資金1,000万円の債権)だけを、第三者Cに譲渡したとしても、根抵当権そのものは原則としてCには移転せず、B銀行のもとに留まるんです。
なぜでしょうか?
それは、根抵当権が個々の独立した債権ではなく、根抵当権者と債務者との間の「継続的な取引関係から生じる債権全体」を一体として担保するもの、という性格が強いからです。もし、個別の債権が譲渡されるたびに根抵当権までバラバラに移転してしまうと、元の根抵当権者(B銀行)はまだ残っている他の債権が無担保になってしまって困りますし、債務者(A社)も取引関係が複雑になって不利益を受ける可能性があるため、このようなルールになっています。
ただし、例外的に、元本確定前に根抵当権そのものを譲渡する方法(全部譲渡、分割譲渡、一部譲渡)も定められていますが、少し複雑なので、宅建試験対策としてはまず「原則として随伴性はない」と覚えておけば大丈夫でしょう。
特徴④:利息も全額カバー!抵当権より広い効力範囲
最後に、担保される範囲、特に利息や遅延損害金の扱いについての違いです。
普通の抵当権の場合、競売になった際に、その売却代金から優先的に弁済を受けられる利息や遅延損害金は、原則として「満期となった最後の2年分」に限られていましたよね。(これは、後順位の抵当権者などを保護するためのルールでした。)
しかし、根抵当権の場合は、もっとパワフルです! 元本が確定した後、その確定した元本に対する利息や遅延損害金については、極度額の範囲内であれば、期間の制限なく(最後の2年分という縛りなく)全額が担保されるんです!

へぇ~!根抵当権の方が、利息や損害金についても、より手厚く保護されるんですね!これは債権者にとっては嬉しいポイントですね。
例:極度額5,000万円の根抵当権で、元本確定時の元本が4,000万円だったとします。
その後、返済が滞ってしまい、利息や遅延損害金がどんどん増えて、例えば3年分で合計500万円、4年分で合計700万円…となったとしても、その元本(4,000万円)と利息・損害金(700万円)の合計額(4,700万円)が、設定された極度額(5,000万円)の範囲内であれば、その全額(4,700万円)が根抵当権によって担保され、競売代金から優先的に弁済を受けられる、ということです。
根抵当権の内容は変更できる?【極度額・債権範囲・債務者・確定期日】
根抵当権を設定した後で、「やっぱり極度額を増やしたいな」とか、「取引の種類を追加したいな」とか、内容を変更したい場合が出てくるかもしれません。このような根抵当権の内容変更は、いつでも自由にできるのでしょうか? ここでも「元本確定前」か「元本確定後」かで扱いが変わること、そして「他の利害関係者に影響があるかどうか」がポイントになります。
<比較表>根抵当権の変更ルールまとめ【元本確定前 vs 元本確定後】
主な変更内容について、いつ変更できるか、そして変更する際に他の利害関係者(例えば、後順位の抵当権者など、変更によって不利になるかもしれない人)の承諾が必要かどうかをまとめました。
| 変更する内容 | 変更可能な時期 | 利害関係人の承諾は必要? | 主な注意点 |
|---|---|---|---|
| ① 極度額の変更 (増額または減額) | 確定前・後ともに可能 | 必要 | 後順位者等の利害に直接影響するため |
| ② 被担保債権の範囲の変更 (例:「銀行取引」→「銀行取引及び手形取引」) | 確定前のみ可能 | 原則不要 | 確定後は性質が変わるため変更不可 |
| ③ 債務者の変更 (例:個人事業主→法人成りした会社へ) | 確定前のみ可能 | 原則不要 | 確定後は性質が変わるため変更不可 ※合意と登記が必要。実務上は複雑な場合も。 |
| ④ 元本確定期日の変更 (例:期日を2年延長する) | 確定前のみ可能 | 原則不要 | 確定後はそもそも期日の意味がないため変更不可 |
※上記の表は基本的なルールを示したものです。変更には当事者間の合意と登記が必要です。
極度額の変更:利害関係人の承諾が必須!
担保の上限額である極度額を変更する場合(増やす場合も減らす場合も)、これは元本確定前でも確定後でも行うことができます。
ただし、考えてみてください。極度額が増えれば、その分、後から担保を取った人(後順位抵当権者など)が、競売になった時に回収できるお金が減ってしまう可能性がありますよね。逆に極度額が減れば、根抵当権者が回収できる上限が下がることになります。
このように、極度額の変更は、他の利害関係人の利害に直接的に影響を与える可能性が高いです。そのため、極度額を変更するには、その変更によって不利益を受ける可能性のある利害関係者全員の承諾を得なければならない、とされています。
極度額の変更は、時期を問わずできるけど、影響が大きいから利害関係人の承諾が絶対に必要!と覚えましょう。
被担保債権の範囲・債務者・確定期日の変更:確定前なら原則承諾不要!
一方で、以下の変更については、扱いが異なります。
- 被担保債権の範囲の変更(例:「銀行取引」に「保証契約」を追加する)
- 債務者の変更(※元の債務者との関係が完全に切れる「免責的債務引受」などは少し複雑ですが、基本的な変更は可能)
- 元本確定期日の変更(例:2025年3月末だった期日を2027年3月末に延期する)
これらの変更は、元本が確定する前であれば、利害関係人の承諾なしに行うことができます(もちろん、根抵当権者と設定者の合意は必要ですよ)。なぜなら、これらの変更は、極度額の変更ほど直接的に後順位抵当権者などの回収見込み額に影響を与えるとは考えられていないためです。
ただし、重要なのは、これらの変更は元本確定後には、もはや行うことができないという点です。なぜなら、元本が確定すると、根抵当権は特定の元本を担保する普通の抵当権と同じような性質になるため、もはや「不特定の債権の範囲」や「確定期日」といった根抵当権特有の要素を変更する意味がなくなるからです。
考え方のヒントとしては、「①他の人の不利益に直結する変更(=極度額変更)は、承諾が必要」「②根抵当権の性質が変わる『元本確定後』は、根抵当権特有の要素(債権範囲、確定期日など)はもう変更できない」という2つの視点で整理すると、承諾の要否や変更できる時期を判断しやすくなりますよ。
まとめ
今回は、宅建試験の権利関係の中でも、特に抵当権との違いが分かりにくい「根抵当権」について、その基本的な仕組みから、重要な特徴、そして試験でよく問われるルールまで、詳しく解説してきました。少しボリュームがありましたが、最後までお読みいただきありがとうございます!
根抵当権は、特に継続的な取引がある場合に、当事者双方にとってメリットのある便利な担保制度ですが、普通の抵当権とは違う「元本確定」という重要な概念や、「付従性・随伴性がない(元本確定前)」といった独特の性質を持っていることが、大きなポイントでしたね。この違いをしっかり理解しておくことが、宅建試験を攻略する上で非常に大切になります。
最後に、今回の記事で学んだ根抵当権の重要ポイントを、箇条書きで振り返っておきましょう。
- 根抵当権とは: 不動産を担保に、極度額の範囲内で、一定の範囲の不特定の債権について、繰り返し借り入れできる権利。継続的取引に便利。
- 抵当権との最大の違い: 担保する債権が特定されていない点。これにより、付従性・随伴性がない(元本確定前)という特徴が生じる。
- 元本確定: 担保される借金の元本総額をフィックスさせること。確定事由(期日到来、請求、破産、競売等)により確定し、確定後は普通の抵当権に近い性質に変化する(付従性・随伴性が復活)。
- 元本確定請求: 確定期日の定めがない場合、設定者は設定後3年経過で請求可(2週間後確定)、根抵当権者はいつでも請求可(直ちに確定)。
- 根抵当権の特徴(元本確定前):
- 付従性なし: 借金残高ゼロでも自動消滅しない(抹消登記が必要)。
- 被担保債権の範囲限定: 取引の種類等で範囲を定める必要あり(包括根抵当権はNG)。
- 随伴性なし: 個別の債権譲渡で根抵当権は原則移転しない。
- 効力範囲: 利息・損害金は極度額内なら全額担保(最後の2年縛りなし)。
- 根抵当権の変更:
- 極度額: 確定前後問わず変更可だが、利害関係人の承諾が必要。
- 債権範囲・債務者・確定期日: 確定前のみ変更可で、原則利害関係人の承諾は不要。
根抵当権の学習は、ぜひ普通の抵当権と比較しながら進めてみてください。共通点と相違点を意識することで、それぞれの特徴がより鮮明になり、記憶にも残りやすくなりますよ。

根抵当権、最初はとっつきにくいかもしれませんが、仕組みを理解すれば得点源になります!頑張ってくださいね!応援しています!