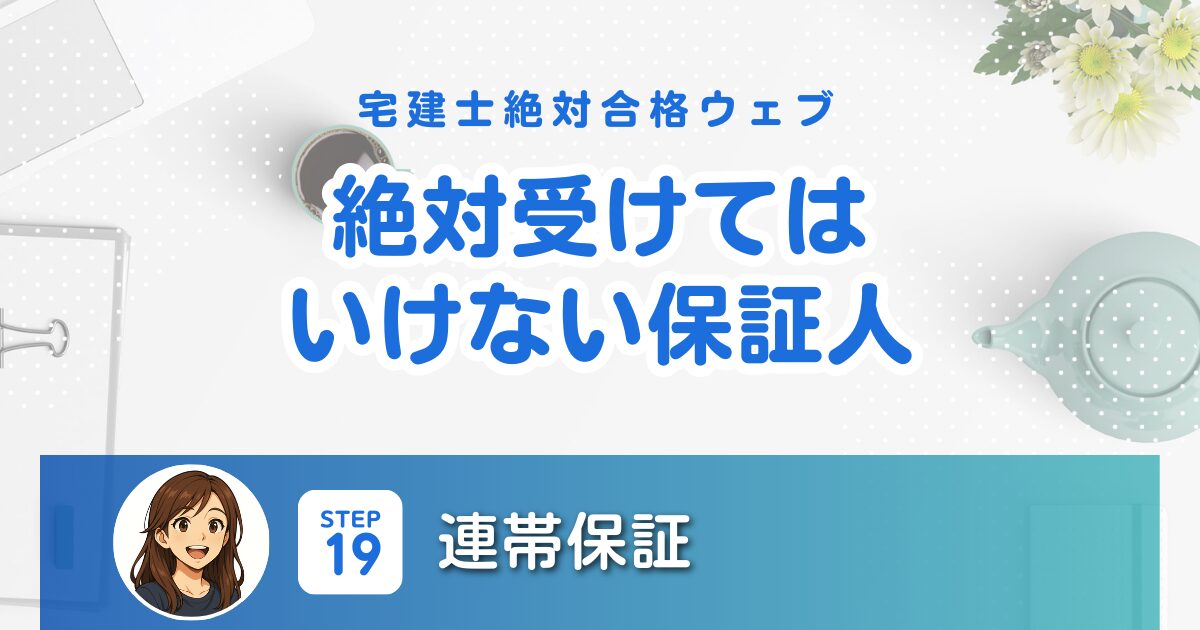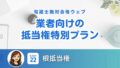民法の債権分野、特に「保証」や「連帯債務」あたりは、言葉も似ているし、登場人物も多くて、関係性がこんがらがってしまいがちですよね。「連帯保証」と「連帯債務」って、どっちも「連帯」って付くけど、何がどう違うの?とか、「絶対効」「相対効」って言われてもピンとこない…、「求償権」の計算なんて、もう考えたくない!なんて方もいらっしゃるかもしれません。
今回は、そんな苦手意識を持ちやすい「連帯保証」と「連帯債務」について、その違いを中心に、それぞれの仕組みや重要なルール(絶対効・相対効、求償権など)を、できるだけ分かりやすく解説していきますね!
連帯保証も連帯債務も、複数の人が関わって債務を負担する点で共通していますが、その責任の重さや、当事者間で起こった出来事が他の人にどう影響するか(絶対効・相対効)、そして誰かが代わりに支払った場合に他の人に請求できる権利(求償権)のルールが異なるんです。
この記事では、まず連帯保証人の責任の重さや絶対効・相対効のルールを解説し、次に連帯債務の仕組みと絶対効・相対効について説明します。そして最後に、両者の最も重要な違いである「求償権」のルールを比較しながら、知識を整理していきます。具体例もたくさん使いますので、ぜひ最後まで読んで、苦手を得意に変えていきましょう!

こんにちは!今回はちょっと複雑な「連帯保証」と「連帯債務」ですけど、一緒に頑張りましょう。
<この記事でわかること>
- 連帯保証人と普通の保証人の違い(3つの権利がない!)について理解できる
- 連帯保証と連帯債務における「絶対効」と「相対効」の区別がわかる
- 連帯債務の基本的な仕組みと債権者の権利について理解できる
- 連帯保証と連帯債務の最も重要な違いである「求償権」のルールが明確になる
- 宅建試験で問われやすいポイントが整理できる
超重要!連帯保証人の重い責任と絶対効・相対効のルール
まずは「連帯保証人」について見ていきましょう。よく耳にする「保証人」と似ているようで、実は責任の重さが全然違うんです。しっかり区別できるようにしましょうね。
連帯保証人って普通の保証人と何が違うの?3つの「ない」!
連帯保証人も保証人の仲間ではあるのですが、普通の保証人が持っている3つの大事な権利(抗弁権)が、連帯保証人には認められていません。これが、普通の保証人との最大の違いであり、連帯保証人の責任が「重い!」と言われる理由なんです。
特徴①:「催告の抗弁権」がない!
普通の保証人だったら、もし債権者さんから「お金を払ってください!」といきなり請求されても、「いやいや、まずは主たる債務者さん(お金を借りた本人)に請求してくださいよ!」って言えましたよね。これを「催告の抗弁権(さいこくのこうべんけん)」と言います。
でも、連帯保証人にはこの「待った!」をかける権利がないんです。債権者さんは、主たる債務者に請求する前に、いきなり連帯保証人に「全額払ってください!」と請求できます。そして、連帯保証人は「先に本人に請求して」とは言えず、支払いを拒否できないんですね。
連帯保証人は、債権者から請求されたら、主たる債務者より先に支払わなければならない可能性がある、ということです。
特徴②:「検索の抗弁権」がない!
普通の保証人には、もう一つ強力な盾があります。「検索の抗弁権(けんさくのこうべんけん)」です。これは、もし債権者から請求されても、「主たる債務者には十分な支払い能力があって、しかも差し押さえできる財産(例えば不動産とか預金とか)も簡単に見つかるんですよ!だから、まずはそっちから取り立ててください!」と主張できる権利でした。
しかし、残念ながら連帯保証人にはこの権利もありません。たとえ主たる債務者がお金持ちで、すぐに差し押さえできる財産を持っていたとしても、債権者さんから「あなたが払ってください」と言われれば、連帯保証人は「本人の財産から取ってよ」とは言えず、支払いを拒否できないのです。
特徴③:「分別の利益」がない!
保証人が一人ではなく、複数いる場合を考えてみましょう。普通の保証人であれば、「分別の利益(ぶんべつのりえき)」というものがありました。これは、保証人が何人かいれば、借金の全額を保証人の人数で割った金額(按分額)についてだけ責任を負えばよく、他の保証人の分まで責任を負う必要はない、というルールです。
ところが、連帯保証人にはこの「分別の利益」がありません。連帯保証人が何人いようと関係なく、各連帯保証人は、それぞれが主たる債務の全額について責任を負うことになります。
<分別の利益の有無による負担額の違いの例>
例えば、AさんがBさんから1,000万円を借りて、その保証人としてCさん、Dさん、Eさん、Fさんの4人がいたとします。
- 普通の保証人(C, D, E, F)の場合(分別の利益あり):
債権者Bさんは、各保証人に対して、1,000万円 ÷ 4人 = 250万円までしか請求できません。 - 連帯保証人(C, D, E, F)の場合(分別の利益なし):
債権者Bさんは、Cさん、Dさん、Eさん、Fさんのそれぞれに対して、1,000万円全額を請求できます。(もちろん、合計で1,000万円を超えて回収することはできませんが、誰か一人に全額請求することも可能ということです。)

ひえぇ…!連帯保証人には、普通の保証人にある言い分が全然通じないんですね…。これは本当に責任重大ですね…。
つまり連帯保証人は主債務者とほぼ同等の責任!
これらの「3つのない」(催告の抗弁権なし、検索の抗弁権なし、分別の利益なし)によって、連帯保証人は、実質的に主たる債務者とほとんど同じ立場で、債権者に対して借金の全額を支払う義務を負うことになります。ただ「連帯」という言葉が付くだけで、これほどまでに責任の重さが違うんですね。
連帯保証人間の求償権 – 負担を超えた分は請求できる
連帯保証人には分別の利益がないので、債権者から請求されると、自分が本来負担すべき割合(連帯保証人の間で特に取り決めがなければ、人数で割った均等割合になります)を超えて支払わなければならないことがあります。
もし、連帯保証人の一人が、自分の負担すべき部分を超えて弁済(支払い)をした場合は、その超えて支払った金額について、他の連帯保証人に対して「私の代わりに払ってくれた分、返してください」と請求することができます。これを「求償権(きゅうしょうけん)」と言います(民法第465条1項)。
例: Aさんの借金1,000万円について、BさんとCさんが連帯保証人になったとします。BさんとCさんの間の負担部分は、特に決め事がなければ半分ずつ、つまり各500万円です。
もし、Bさんが債権者に800万円を支払った場合、Bさんは自分の負担部分500万円を300万円超えて支払っていますよね。この超えた300万円について、Bさんはもう一人の連帯保証人であるCさんに「払ってください」と求償できるわけです。(ただし、Cさんの負担部分である500万円が上限になります。)
もしBさんが300万円しか支払わなかった場合は、自分の負担部分500万円を超えていないので、Cさんには求償できません。
(ちなみに、弁済した連帯保証人は、主たる債務者Aさんに対しては、自分の負担部分に関係なく、支払った全額(+利息や費用など)を求償することができますよ。)
絶対効と相対効 – 連帯保証人に起きたことは他の人に影響する?
次に、ちょっとややこしい「絶対効(ぜったいこう)」と「相対効(そうたいこう)」の話です。これは、連帯保証人の一人に何か出来事(例えば、借金を払ったとか、時効が更新されたとか)があった場合に、それが主たる債務者や他の連帯保証人に影響するのかどうか、というルールです。
- 絶対効: 他の人にも影響が及ぶこと
- 相対効: その当事者間だけで効果が生じ、他の人には影響が及ばないこと
原則は「相対効」 – 自分だけに影響
連帯保証人に生じた事由は、原則として「相対効」です。つまり、その出来事が起こった連帯保証人と債権者の間だけで効果があり、基本的には主たる債務者には影響しません。
相対効となる主な例:
- 承認: 連帯保証人の一人が「確かに借金があります」と認めても(承認)、その連帯保証人の保証債務の時効がリセット(更新)されるだけで、主たる債務者の借金の時効には影響しません。
- 請求: 債権者が連帯保証人の一人に「払ってください」と請求しても、主たる債務の時効の完成がストップしたりリセットされたり(完成猶予・更新)はしません。
- 時効完成: 連帯保証人の保証債務だけ時効で消滅しても、主たる債務は消えません。
- 免除: 債権者が連帯保証人の一人だけ「あなたの保証債務は免除します」と言っても、主たる債務は消えません。
民法の改正(2020年4月施行)で、以前は絶対効とされていた事由の多くが相対効になりました。特に、連帯保証人の承認や、連帯保証人への請求が相対効である点は重要です。
例外の「絶対効」 – 主債務者にも影響(弁済・相殺など)
ただし、例外的に「絶対効」となる事由もあります。これらの事由が連帯保証人に生じた場合は、主たる債務者の債務にも良い影響(債務が減るなど)が及びます。
絶対効となる主な例:
- 履行(弁済): 連帯保証人が借金を支払えば、その分だけ主たる債務も当然消滅します。全額払えば、主たる債務も全額消えます。これは当たり前ですよね。
- 相殺: 連帯保証人が、たまたま債権者に対して何か別の債権(例えば、売掛金など)を持っていた場合に、それを借金と「相殺(そうさい)」すれば、その分だけ主たる債務も消滅します。
(少し細かい話ですが) 以前は「更改」や「混同」も絶対効とされていましたが、改正民法下では、これらが連帯保証人に生じても、主たる債務を直接消滅させる効果はないため、相対効と整理されるのが一般的です。ただし、連帯保証人がいなくなる(混同)とか、保証契約の内容が変わる(更改)という間接的な影響はあります。
<連帯保証人に生じた事由における絶対効・相対効の表>
| 連帯保証人に生じた事由 | 主たる債務への影響 | 効力 |
|---|---|---|
| 弁済 | 消滅する | 絶対効 |
| 相殺 | 消滅する | 絶対効 |
| 更改 | 影響なし(※) | 相対効 |
| 混同 | 影響なし(※) | 相対効 |
| 請求 | 影響なし | 相対効 |
| 承認 | 影響なし | 相対効 |
| 時効完成 | 影響なし | 相対効 |
| 免除 | 影響なし | 相対効 |
※更改・混同は保証債務自体は消滅しますが、主たる債務を直接消滅させる効果はないため、相対効と整理するのが一般的です。ただし、保証人がいなくなるなどの間接的な影響はあります。
【要チェック】主たる債務者に起きたことは全て絶対効!
ここがすごく大事なポイントです! 連帯保証人に起こったことは原則「相対効」でしたが、逆に、主たる債務者について生じた事由は、原則としてすべて保証人(連帯保証人を含む)に対しても効力が生じます(絶対効)! これは、保証債務が主たる債務に従属する性質(付従性:ふじゅうせい)を持っているからです。
- 主たる債務者が弁済すれば、保証債務もその分減ります。
- 主たる債務について時効が完成すれば、保証人もそれを主張して支払いを拒否できます。
- 主たる債務者に有利な事由(例:契約の無効・取消し)があれば、保証人もそれを主張できます。
この「主たる債務者→保証人」は絶対効、「保証人→主たる債務者」は原則相対効、という非対称な関係をしっかり理解しておきましょう。
みんなで全額責任?連帯債務の仕組みと絶対効・相対効
さて、次はもう一つの「連帯」がつく言葉、「連帯債務」について見ていきましょう。これも複数の人が債務を負う点は同じですが、連帯保証とは仕組みが異なります。

こっちは「保証人」じゃなくて、「債務者」が連帯するんですね!どう違うんだろう?
連帯債務とは? – 各自が全額の支払い義務を負う
連帯債務とは、数人の債務者(連帯債務者)が、同じ内容の借金や支払い義務について、各自が独立して、債権者に対して「全額」を支払う義務を負う債務のことです(民法第436条)。
連帯保証のような「主たる債務者」と「保証人」という主従関係はありません。参加している債務者全員が、いわば「主役」として、それぞれが全額について責任を負う、という関係です。
例:Aさん、Bさん、Cさんの3人が、共同で売主Dさんから3,000万円の土地を購入し、代金の支払いについて「連帯して支払います」と約束した場合、Aさん、Bさん、Cさんは連帯債務者となります。
<連帯債務の関係図>
債権者: D (売主) ← 3,000万円の請求権
↑↓
連帯債務者: A --- B --- C (買主)
(それぞれがDに対して3,000万円全額の支払義務を負う)
(内部的な負担部分は例えば各1,000万円など)
この場合、Aさん、Bさん、Cさんは、それぞれがDさんに対して「私一人で3,000万円全部払います」という義務を負っている状態になります。
債権者は誰にでも全額請求できる!
連帯債務の大きな特徴は、債権者さんの権利が非常に強いことです。上の例で言うと、債権者Dさんは、
- 連帯債務者Aさん、Bさん、Cさんの誰か一人に対して、債務の全額(3,000万円)を請求することができる。
- 連帯債務者の数人(例えばAさんとBさん)に対して、同時に債務の全額(3,000万円)を請求することができる。
- 連帯債務者全員(Aさん、Bさん、Cさん)に対して同時に、債務の全額(3,000万円)を請求することができる。
つまり、債権者さんは、一番お金を持っていそうな人を選んで全額請求することも、全員に同時に請求することも自由にできるわけですね。これは、債権を回収しやすくするための仕組みです。
連帯債務も原則「相対効」 – 一人に起きたことは他の人に影響しない
さて、絶対効・相対効の話ですが、連帯債務においても、連帯保証と同じく、連帯債務者の一人について生じた事由は、原則として「相対効」です。つまり、他の連帯債務者には影響を及ぼしません(民法第441条)。これも民法改正で明確になった重要なポイントです。
相対効となる主な例:
- 承認: 連帯債務者Aさんが債務を承認しても、BさんやCさんの債務の時効は更新されません。
- 請求: 債権者がAさんに請求(裁判上の請求など)しても、BさんやCさんの時効の完成猶予・更新の効果は生じません。
- 時効完成: Aさんの債務だけ時効で消滅しても、BさんやCさんの債務は当然には消滅しません。
- 免除: 債権者がAさんの債務だけ免除しても、BさんやCさんの債務は当然には消滅しません。
【補足:時効完成・免除の場合の調整】
時効完成や免除が相対効ということは、Aさんの債務が時効や免除で消えても、BさんやCさんは依然として全額の債務を負うの?というと、少し調整が入ります。
他の連帯債務者(BさんやCさん)は、時効が完成したり免除されたりしたAさんの「負担部分」の限度で、債権者に対して支払いを拒むことができる、とされています(民法第439条、第445条)。
例えば、A, B, Cの負担部分が均等(各1/3)の場合、Aの債務が時効で消滅したら、BとCはそれぞれ、全額ではなく、Aの負担部分1/3を除いた2/3の限度で支払義務を負う、というイメージです。(これは連帯保証の場合も似たような考え方があります。)
例外の「絶対効」 – 他の債務者にも影響が及ぶケース
連帯債務においても、もちろん例外的に「絶対効」となる事由があります。これらが生じた場合は、他の連帯債務者全員に影響が及び、債務が消滅するなどの効果が生じます。
絶対効となる主な例:
- 弁済(および代物弁済、供託): 連帯債務者の一人が弁済などを行えば、その分だけ他の連帯債務者の債務も共通して消滅します。全額払えば、全員の債務が消えます。
- 相殺: 連帯債務者の一人が債権者に対して持つ債権で相殺すれば、その分だけ他の連帯債務者の債務も共通して消滅します。(なお、他の連帯債務者は、相殺できる権利を持っている人の「負担部分」の限度で、支払いを拒むこともできます。)
- 混同: 連帯債務者の一人が、たまたま相続などで債権者の地位も引き継いでしまい、債権と債務が同じ人に帰属した場合(混同)、その連帯債務者の債務は消滅します。そして、他の連帯債務者は、混同によって債務が消滅した人の「負担部分」の限度で、支払いを拒むことができます。(以前は混同も債務全体が消滅する絶対効と広く解釈されていましたが、改正民法では上記のような効果になりました。)
- 更改: 連帯債務者の一人と債権者の間で、元の債務を消滅させて新しい債務を成立させる契約(更改)をした場合、他の連帯債務者も含めて、元の債務は全て消滅します。これは強力な絶対効ですね!
<重要ポイント>
連帯債務で絶対効となるのは主に「弁済・相殺・更改」と覚えましょう!(混同は少し効果が特殊です)。これら以外は原則相対効、と整理するとスッキリします。
連帯保証の場合と比較すると、「更改」が連帯債務では明確に絶対効とされている点が異なりますね(連帯保証では相対効と整理されるのが一般的でした)。
絶対効と相対効の区別は、宅建試験で狙われやすいポイントです。どちらの制度(連帯保証か連帯債務か)の話なのか、誰に何が起こったのかを正確に把握して、効果を判断できるように練習しましょう!
【比較】連帯保証と連帯債務の決定的な違いは「求償権」!
ここまで、連帯保証と連帯債務のそれぞれの仕組みや絶対効・相対効について見てきました。どちらも複数の人が関わる点で似ていますが、責任の根拠や効果に違いがありましたね。
そして、この二つの制度を比較したときに、最も重要で決定的な違いが現れるのが、誰かが代わりに支払った場合の「求償権」のルールなんです! ここは絶対にマスターしましょう!

いよいよ核心の違いですね!求償権、しっかり整理しましょう!
求償権の違いが最大のポイント!
なぜ求償権のルールが違うのか? それは、二つの制度の基本的な構造の違いから来ています。
- 連帯保証: あくまで「主たる債務者」がメインで、「保証人」はバックアップ役。主従関係がある。
- 連帯債務: 全員が対等な立場で、それぞれが独立して全額の責任を負う「主役」。
この構造の違いが、お金を払った後に他の人に請求できるかどうかのルール(求償権)に大きく影響してくるんです。
連帯保証人間の求償 – 「負担部分を超えたら」求償できる
連帯保証人が複数いる場合に、一人が債権者に支払いをしたとしても、自分の負担部分(連帯保証人間での取り決めがなければ頭割り)を超えて支払わない限り、他の連帯保証人には求償できませんでしたよね。
あくまで「自分の担当分を超えて肩代わりした分」についてのみ、他の連帯保証人に請求できる、というルールです(民法第465条1項)。
<連帯保証人間の求償計算例>
状況:主債務者Aの債務1,000万円をBさんとCさんが連帯保証(負担部分は特に決めず、均等で各500万円とします)。
- ケース1:Bさんが債権者に800万円を弁済した場合
- Bさんは自己の負担部分500万円を300万円超えて弁済しました。
- したがって、Bさんは他の連帯保証人Cさんに対して、この超過分300万円を求償できます。(Cさんの負担部分500万円が上限です。)
- ケース2:Bさんが債権者に300万円を弁済した場合
- Bさんは自己の負担部分500万円を超えていません。
- したがって、Bさんは他の連帯保証人Cさんに対して求償できません。(ただし、主たる債務者Aさんには300万円全額を求償できます。)

なるほど!連帯保証人同士だと、まず自分の分を払って、それを超えないと他の保証人には請求できないんですね。
連帯債務者間の求償 – 「負担部分を超えなくても」求償できる
一方、連帯債務の場合はどうでしょうか? 連帯債務者は全員が対等な立場で、それぞれが全額の責任を負っていました。
そのため、連帯債務者の一人が弁済した場合、たとえ自己の負担部分を超えていなくても、弁済した額について、他の連帯債務者に対して、それぞれの負担部分の割合に応じて求償することができるんです!(民法第442条)
これが連帯保証との決定的な違いです!
<連帯債務者間の求償計算例>
状況:Aさん、Bさん、Cさんの3人が連帯債務者として、Dさんに対して1,200万円の債務を負っている(負担部分は特に決めず、均等で各400万円とします)。
- ケース:Aさんが債権者Dさんに300万円を弁済した場合
- Aさんは自己の負担部分400万円を超えていません。
- しかし、連帯債務なので、負担部分超過は関係ありません! Aさんは弁済した300万円について、他の連帯債務者Bさん・Cさんに対し、それぞれの負担割合(各1/3)に応じて求償できます。
- → AさんはBさんに 300万円 × (1/3) = 100万円 を求償できます。
- → AさんはCさんに 300万円 × (1/3) = 100万円 を求償できます。
- (残りの100万円はAさん自身の負担分となります。)
<超重要!>
連帯債務では、負担部分を超えなくても、少しでも弁済すれば、他の連帯債務者にその負担割合に応じて求償できる! この点を絶対に押さえてください!
連帯保証人と連帯債務者の違いまとめ
最後に、これまで見てきた連帯保証人と連帯債務者の主な違いを表で整理しておきましょう。頭の中をスッキリさせるのに役立ててくださいね。
<連帯保証人と連帯債務者の主な違いの比較表>
| 項目 | 連帯保証人 | 連帯債務者 |
|---|---|---|
| 基本構造 | 主従関係(主債務者⇔保証人) | 対等関係(全員が主たる債務者) |
| 催告・検索の抗弁権 | なし | (概念自体なし) |
| 分別の利益 | なし | (概念自体なし、各自全額責任) |
| 一人に生じた事由の効力 | 原則:相対効 例外:絶対効(弁済・相殺など) | 原則:相対効 例外:絶対効(弁済・相殺・更改など) |
| 他の連帯者への求償要件 | 自己の負担部分を超えて弁済した場合 | 弁済すれば(負担部分超過不要) |
| 他の連帯者への求償範囲 | 超過額について | 弁済額 × 他の連帯者の負担割合 |
まとめ
今回は、「連帯保証」と「連帯債務」という、宅建試験の民法分野で避けては通れない、そして多くの受験生が混同しやすい二つの重要な制度について、その違いを中心に詳しく解説してきました。
どちらも「連帯」がつくのでややこしいですが、構造、責任、絶対効・相対効、そして求償権の違い、しっかり区別できましたか?
ポイントをもう一度整理しましょう。
- 連帯保証人は、普通の保証人が持つ「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」という3つの権利がなく、主たる債務者とほぼ同じ重い責任を負います。
- 連帯債務者は、主従関係はなく、全員が対等な立場で、各自が独立して債務全額について責任を負います。
- 一人に生じた事由の効力(絶対効・相対効)は、民法改正により、どちらの制度でも原則「相対効」となりました。ただし、「弁済」「相殺」などは共通して絶対効、「更改」は連帯債務で特に重要な絶対効事由です。
- 逆に、主たる債務者に生じた事由は、保証人(連帯保証人含む)に対して全て絶対効となる付従性を忘れないでください。
- そして、最も重要な違いである求償権のルール!
- 連帯保証人間の求償は、自己の負担部分を超えて弁済した場合に、その超過額についてのみ可能です。
- 連帯債務者間の求償は、自己の負担部分を超えていなくても、弁済すればその額に応じて(負担割合に応じて)可能です。
これらの違い、特に絶対効・相対効の区別や求償権のルールの違いは、宅建試験で頻出の論点です。この記事で基本をしっかり押さえたら、ぜひ過去問や問題集で具体的な事例にあたって、知識を定着させていってくださいね。

最初は複雑に感じるかもしれませんが、一つ一つのルールを丁寧に理解し、違いを意識して整理すれば、必ず得意分野にできるはずです!皆さんの合格を心から応援しています!