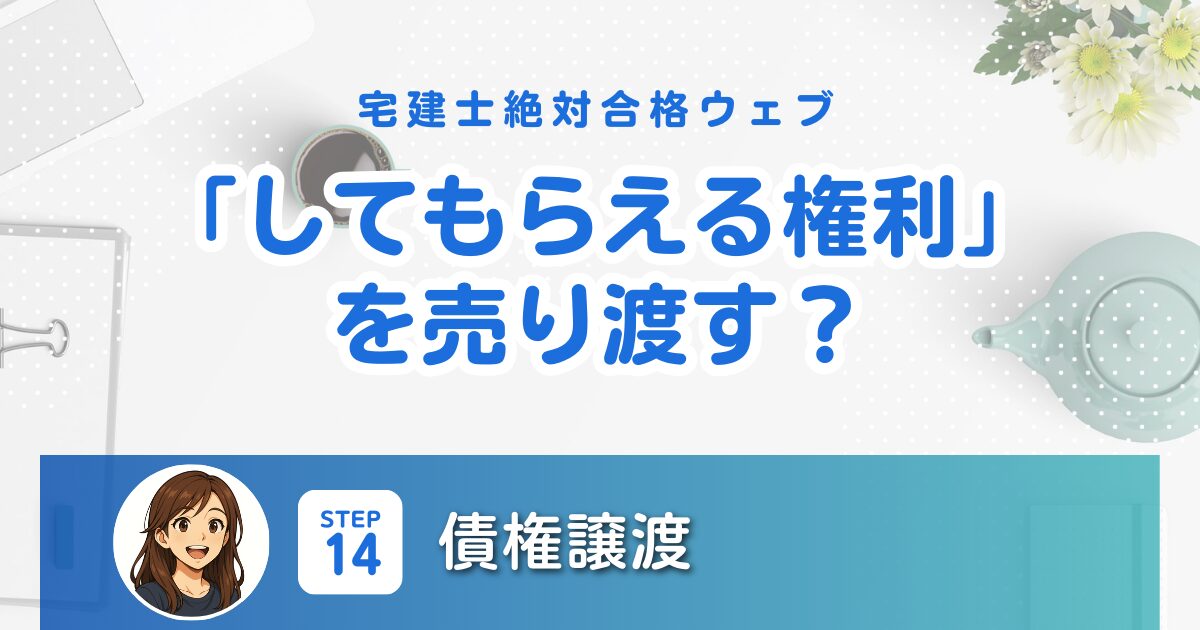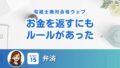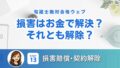権利関係って、ほんと色々なルールがあって頭がパンクしそう…なんて思ってませんか?特に「債権譲渡」とかって、言葉は聞いたことあるけど、「対抗要件」?「確定日付」?「相殺」?って、もう何がなんだか…ってなりがちですよね。

登場人物も多くなりがちだし、誰が誰に何を主張できるのか、ゴチャゴチャになりやすいんですよね…。私も最初はチンプンカンプンでした…。
でも、この債権譲渡のルールって、お金の貸し借りとか、不動産取引の代金支払いとか、実は身近な場面でも関わってくる可能性がある、とっても大事な知識なんです!宅建試験でも頻出論点なので、ここでしっかり理解しておけば、権利関係の得点アップに繋がりますよ!苦手なまま放置しておくのはもったいない!
この記事では、そんなちょっと複雑に見える「債権譲渡」について、基本的な考え方から、民法改正で変わった譲渡禁止特約の扱い、債務者や第三者に対抗するための要件、もし債権が二重に譲渡されちゃったらどうなるの?、譲渡されたけど相殺したい場合は?といった応用論点まで、図を使いながらステップバイステップで分かりやすく解説していきます!
この記事でわかること
- 債権譲渡の基本的な意味と成立要件について理解できる
- 民法改正後の「譲渡禁止特約」の扱いのポイントが整理できる
- 債権譲渡を債務者や第三者に対抗するための要件(通知・承諾・確定日付)の対策がわかる
- 債権が二重譲渡された場合の優先順位の決め方との違いがわかる
- 債権譲渡された場合に、債務者が相殺できるケースとできないケースが明確になる
債権譲渡のキホン!譲渡禁止特約があっても有効ってホント?対抗要件も解説
まずは、債権譲渡の基本中の基本から見ていきましょう!ここをしっかり押さえることが、複雑な応用論点を理解するための第一歩ですよ。

基本がわかれば、応用もグッと楽になりますからね!
そもそも債権譲渡ってなに? – 権利を他の人に譲り渡すこと
債権譲渡(さいけんじょうと)とは、その名の通り、「債権」、つまり「特定の人に対して、特定のこと(お金を払ってもらう、物を引き渡してもらうなど)をしてもらう権利」を、他の人に譲り渡すことを言います。
民法では、原則として、債権はその性質が許す限り、自由に譲渡できる、とされています(民法第466条1項)。お金のように、誰に請求できるかが変わっても本質が変わらない権利は、基本的に売り買いしたり、あげたりできる、ということですね。
例えば、こんな状況を考えてみましょう。
- Bさん(貸主)がAさん(借主)に100万円を貸しました。
→ この時点で、BさんはAさんに対して「100万円を返してもらう権利(貸金債権)」を持っています。 - その後、Bさんは急にお金が必要になりました。でも、Aさんからの返済期日はまだ先です。
- そこで、Bさんはお金に余裕のある友人Cさんに、「私がAさんに持っている100万円の債権を、80万円であなたに譲ります(買い取ってください)!」と持ちかけ、Cさんはこれを承諾しました。
- → この結果、Bさんが持っていたAさんに対する100万円の貸金債権が、Cさんに譲渡されました。
<債権譲渡の基本的な関係>
(譲渡前)
[貸主 B (元の債権者)] — 100万円返せ! —> [借主 A (債務者)]
(譲渡後)
[譲渡人 B] — 債権を譲渡 —> [譲受人 C (新しい債権者)]
[譲受人 C] — 100万円返せ! —> [借主 A (債務者)]
この債権譲渡によって、これからはCさんが正当な債権者として、Aさんに対して「100万円を返してください!」と請求できる権利を持つことになります。BさんはもうAさんに請求できません。
このように、債権譲渡は、債権を資金化したり(Bさんが早期にお金を手に入れる)、担保に入れたり(債権を担保にお金を借りる)と、経済活動において重要な役割を果たしているんです。
債権譲渡はどうやって成立するの? – 譲渡人 と譲受人の合意だけ!
じゃあ、どうすれば債権譲渡は法的に有効に成立するのでしょうか? 誰かの許可が必要だったり、特別な手続きが必要だったりするのでしょうか?
実は、債権譲渡の契約自体は、とってもシンプルなんです。
債権譲渡は、債権を譲り渡す人(譲渡人 Bさん)と、譲り受ける人(譲受人 Cさん)の間の「合意」だけで成立します。
<超重要ポイント!>
債権譲渡の契約を成立させるためには、債務者Aさんの承諾や同意は必要ありません!
BさんとCさんの間で「この債権を譲ります!」「はい、譲り受けます!」という意思表示が合致すれば、その時点で債権譲渡契約は有効に成立するのです。Aさんがその事実を知らなくても、です。
「え、債務者に黙って勝手に債権者を変えちゃっていいの?」って思いますよね。この点が、後で出てくる「対抗要件」の話につながってきます。
【民法改正】譲渡禁止特約があっても債権譲渡は原則有効に!
ここで、ちょっとややこしいけれど、宅建試験では避けて通れない超重要ポイントが登場します。それが「譲渡禁止特約(じょうときんしとくやく)」の扱いです。これは2020年4月施行の民法改正でルールが変わった点なので、特に注意が必要です!
譲渡禁止特約とは?
譲渡禁止特約とは、債権者(例:Bさん)と債務者(例:Aさん)が契約を結ぶ際に、「この契約から生じる債権(例えば、BさんのAさんに対する貸金債権)は、第三者に譲渡してはいけませんよ」という特別な約束(特約)をすることです。
債務者Aさんの立場からすると、「お金を返す相手は、顔見知りで信頼しているBさんだけにしてほしい。いきなり知らないCさんとか、ましてや怖い取り立て業者とかから請求されるのは困るな…」って思う場合がありますよね。そういった債務者の意向を反映するために、この特約が付けられることがあります。(あるいは、債権者が自社の都合でつけることもあります)
【改正後ルール】特約があっても譲渡は有効!でも債務者も保護される!
じゃあ、もしこの譲渡禁止特約があるにもかかわらず、債権者Bさんが約束を破って、勝手にCさんに債権を譲渡しちゃったら、その譲渡はどうなるんでしょうか?
【民法改正後のルール(現行法)】
なんと、譲渡禁止特約が付いている債権であっても、それを譲渡すること自体は、原則として有効なんです!(民法第466条2項)。
民法第466条(債権の譲渡性)
2. 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(次条において「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
「えっ!?特約で禁止したのに、譲渡できちゃうの!? じゃあ特約って何の意味があるの?」って思いますよね。私も最初に聞いたときはビックリしました!
これは、債権を譲渡して資金調達しやすくするなど、債権の流通性を高めるという経済的な要請から、譲渡そのものは有効とされたんです。でも、それだと特約を結んだ債務者Aさんがかわいそうですよね。
そこで、民法は債務者を保護する仕組みも用意しています。譲渡は有効だけれども、一定の場合には、債務者Aさんは新しい債権者Cさんからの請求を拒否したり、元の債権者Bさんに支払ったりできる、というバランスを取っているんです。
譲受人が悪意・重過失の場合、債務者はどうできる?
債務者Aさんが保護されるのは、譲受人Cさんが、債権に譲渡禁止特約が付いていることについて「悪意(あくい)」または「重大な過失(じゅうだいなかしつ)」の場合です。
- 悪意:譲渡禁止特約の存在を知っていたこと。
- 重過失:通常求められる程度の簡単な注意をすれば特約の存在を知ることができたはずなのに、著しい不注意によって知らなかったこと。
もし、譲受人Cさんが悪意または重過失だったら、債務者Aさんは以下のことができます(民法第466条3項)。
- 履行の拒絶: 譲受人Cさんから「お金を払ってください!」と請求されても、「いや、あなたには払いませんよ!」と支払いを拒否することができます。
- 譲渡人Bへの弁済等による免責: Cさんへの支払いを拒否した上で、元の債権者である譲渡人Bさんに対して弁済(お金を返すこと)すれば、それで有効な弁済となり、債務は消滅します。つまり、Bさんに返しちゃえば、もうCさんに払う必要はなくなる、ということです。(お金を法務局に預ける「供託」という方法でもOKです)
<ポイント>
譲渡は有効だけど、譲受人が悪意・重過失なら、債務者はCさんを無視してBさんに返済すればOK! これで債務者は完全に義務を果たしたことになります。
ただし、もし譲受人Cさんが譲渡禁止特約について善意(ぜんい:知らなかった)かつ無過失(むかしつ:知らないことについて落ち度がない)だったら、債務者AさんはCさんからの請求を拒否できません。原則通り、新しい債権者であるCさんに支払う必要があります。この場合は、債権の流通性が優先されるわけですね。
【さらに注意!】
たとえ譲受人Cが悪意・重過失であっても、債務者Aが自ら進んでCに支払ってしまった場合は、後から「やっぱりBに払うべきだった!」とは言えず、その支払いは有効な弁済となります(民法466条の3)。
新しい債権者から「払って!」と言われたら?債務者への対抗要件
さて、債権譲渡の契約はBさんとCさんの合意だけで成立する、という話に戻りましょう。
でも、債務者Aさんの立場からすると、これでは困りますよね。ある日突然、見ず知らずのCさんから「私が新しい債権者になったから、私にお金を払って!」と言われても、「え?誰?本当にBさんから権利を譲り受けたの? Bさんにはもう払わなくていいの?」って不安になります。もしかしたら、Cさんは嘘をついているだけかもしれません。
なぜ対抗要件が必要なの?
そこで、譲り受けた債権(「お金返して!」と言う権利)を、債務者Aさんに対して有効に主張(対抗)するためには、一定の要件が必要とされています。これを「債務者対抗要件」と言います。この要件を満たして初めて、譲受人Cさんは「私が正当な債権者ですよ!だから私に払ってください!」とAさんに堂々と主張できるわけです。逆に、この要件がない限り、AさんはCさんからの請求を拒否できます。
対抗要件は2つ!「譲渡人からの通知」or「債務者の承諾」
債務者対抗要件として認められるのは、以下のどちらかが必要です(民法第467条1項)。
- 譲渡人から債務者への「通知」:
元の債権者である譲渡人Bさんが、債務者Aさんに対して「私があなたに対して持っていた債権を、Cさんに譲渡しましたよ」と通知すること。 - 債務者の「承諾」:
債務者Aさんが、債権譲渡の事実を知って、「わかりました、Cさんに譲渡されたことを了解しました」と承諾すること。
このどちらか一方があれば、譲受人Cさんは債務者Aさんに対して「私が新しい債権者です」と法的に主張(対抗)できます。Aさんは、原則としてCさんに支払う義務を負うことになります。
【超重要!】通知は「譲渡人」から!譲受人からではダメ!
ここで、すっっっごく大事な注意点があります!
債務者への通知は、必ず「譲渡人(元の債権者)B」から行われなければなりません。
譲受人(新しい債権者)CからAさんに「私がBさんから債権を譲り受けましたよ!」と通知しても、それは有効な対抗要件としては認められません。
<絶対ダメ!>
譲受人C → 債務者A への通知 = 対抗要件にならない!
考えてみれば当たり前ですよね。もし譲受人からの通知でOKなら、「私がBさんから債権を譲り受けた者でーす!」って、全く関係ない第三者が嘘をついて通知を送ってきたとしても、債務者Aさんにはそれが本当かどうか確かめようがありません。元の債権者であるBさんからの通知だからこそ、Aさんは「ああ、本当に譲渡されたんだな」と信用できるわけです。
異議をとどめない承諾とは?その効果
債務者Aさんが債権譲渡を「承諾」する場合、特に何も文句(反論や条件など)を言わずに承諾することを「異議をとどめない承諾(いぎをとどめないしょうだく)」と言います。
もしAさんがこの「異議をとどめない承諾」をしてしまうと、ちょっと怖い効果が発生します。それは、本来なら元の債権者Bさんに対して主張できたはずの事柄(例えば、「Bさん、その借金はもう半分返済済みですよ!」とか、「そもそもBさんとの間の契約は無効ですよ!」といった抗弁(反論))を、新しい債権者Cさんに対しては主張できなくなってしまう、という効果です(民法第468条1項)。
つまり、うっかり何も言わずに「はい、承知しました」と承諾してしまうと、後から「実は…」と反論することができなくなり、Cさんに全額支払わなければならなくなる可能性があるのです。

承諾する時は、何か反論があればちゃんと言わないとダメなんですね!
ですので、債務者の立場としては、承諾する場合には、譲渡人に対して主張できることがあれば、ちゃんとその旨を留保して(言い残して)承諾する(異議をとどめた承諾)ことが重要になります。
ピンチ!債権が二人に譲渡されたら?二重譲渡のルール
世の中、うっかりミスや、時には悪い考えから、同じ債権を複数の人に譲渡してしまうケースもあります。これを「二重譲渡(にじゅうじょうと)」、あるいは三重譲渡、四重譲渡…とまとめて「債権の多重譲渡」と言います。
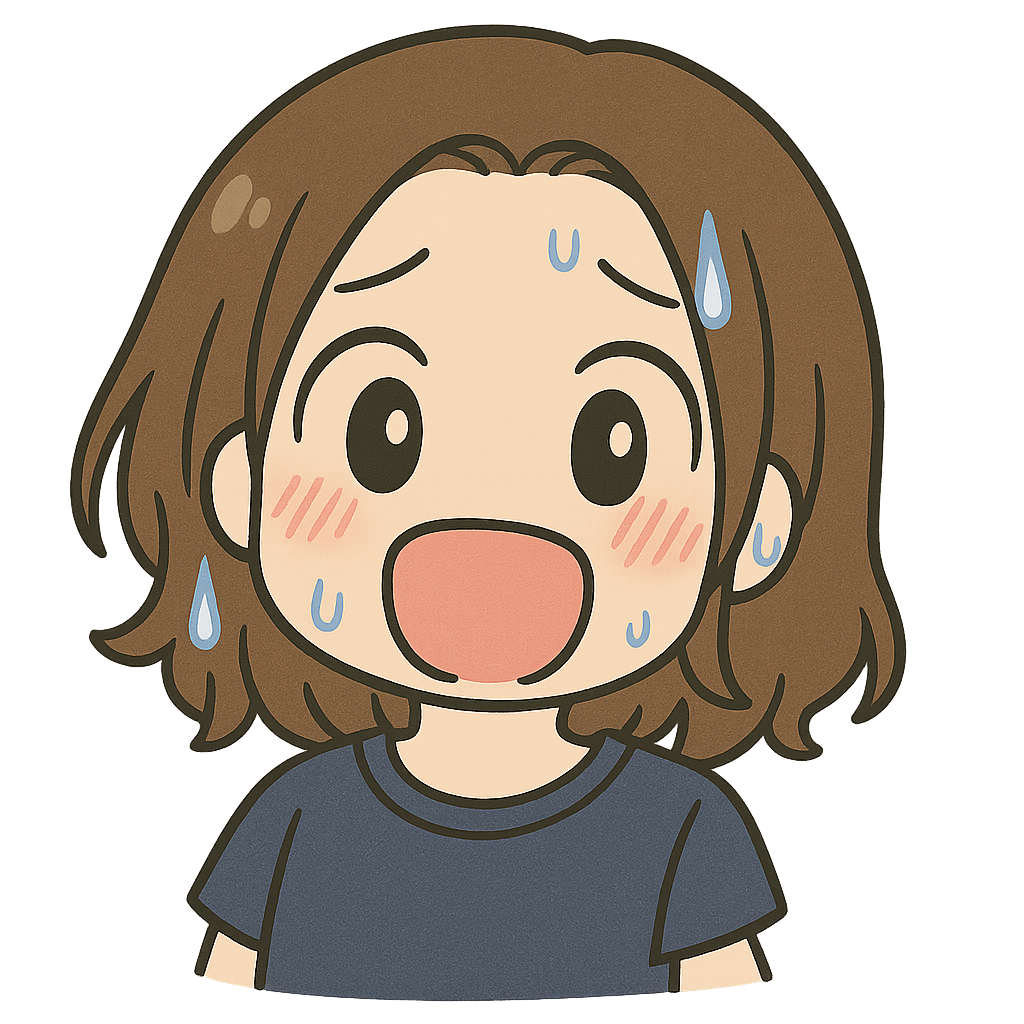
えー!同じ権利を二人に売っちゃうなんてことあるんですね!?
債権は目に見えない権利なので、物理的な物と違って、複数の人に譲渡する契約を結ぶこと自体はできてしまうんですね。では、そんな場合、誰が本当の債権者になるのでしょうか?
同じ債権が二人に… 二重譲渡の問題点
例えば、先ほどの例で、元の債権者Bさんが、Aさんに対する100万円の貸金債権を、まずCさんに譲渡しました。しかし、その後、お金に困ったBさんが、同じ債権をさらにDさんにも譲渡しちゃった、という場合を考えてみましょう。
この場合、第一譲受人のCさんと、第二譲受人のDさん、どちらがAさんに対して「私こそが正当な債権者だ!100万円を返せ!」と主張できるのでしょうか?
契約した順番でCさんが優先? それとも、何か別のルールがあるのでしょうか? このままだと、CさんとDさんの間で争いになってしまいますし、債務者Aさんも誰に返せばいいのか分からず困ってしまいますよね。
どっちが優先?第三者への対抗要件は「確定日付」!
この債権の二重譲渡(多重譲渡)の場合、複数の譲受人(CさんとDさん)のうち、どちらが優先するかを決めるためのルールがあります。
それは、債務者Aさん以外の第三者(この場合は他の譲受人であるCまたはD)に対して、自分が債権を譲り受けたことを法的に主張(対抗)できるかどうか、で決まります。そして、この「第三者対抗要件」として要求されるのが、「確定日付(かくていひづけ)のある証書」による通知または承諾なんです(民法第467条2項)。
民法第467条(債権譲渡の対抗要件)
2. 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
確定日付のある証書とは?(内容証明郵便など)
確定日付っていうのは、「その日付の時点で、その文書(証書)が確かに存在していた」ということを、法律上、公の機関が証明してくれる日付のことです。普通の口頭での通知や承諾、あるいは普通の手紙(郵便)による通知などには、この確定日付がありません。
確定日付を得られる証書の代表的なものは以下の2つです。
- 内容証明郵便: 郵便局が、「いつ、どんな内容の文書を、誰から誰あてに差し出したか」を証明してくれる郵便です。配達証明を付ければ、相手に届いた日付も証明できます。
- 公正証書: 全国の公証役場で、公証人という法律の専門家が作成してくれる公的な文書です。
このどちらかの方法で、債務者Aさんに通知を送るか、債務者Aさんから承諾をもらう必要があるわけです。
確定日付のある通知・承諾が決め手!
二重譲渡の場合、複数の譲受人(例:CさんとDさん)のうち、
- 確定日付のある証書による「通知」が債務者Aに到達した
- または、確定日付のある証書による債務者Aの「承諾」があった
という、第三者対抗要件を先に備えた方が、他方の譲受人に対して優先します。
つまり、契約した順番が早いかどうかは関係ありません。例えば、
- BがCに債権譲渡(契約)
- BがDに同じ債権を二重譲渡(契約)
- BがDへの譲渡について、内容証明郵便でAに通知し、それがAに到達した。
- その後、BがCへの譲渡について、普通郵便でAに通知した。
この場合、契約自体はCさんの方が先ですが、第三者対抗要件である「確定日付のある証書による通知」を先に備えたのはDさんなので、DさんがCさんに優先します。AさんはDさんに支払うべき、ということになります。
確定日付のある通知が複数届いたら? – 到達した順番で勝負!
じゃあ、もしCさんもDさんも、両方とも頑張って「確定日付のある証書」(例えば、両方とも内容証明郵便)で通知を送った場合は、どうやって優劣を決めるのでしょうか?
この場合は、非常にシンプルです。
確定日付のある通知が債務者Aさんに「到達した日時」の早い方が勝ちです!
<超重要ポイント!>
優劣を決めるのは、内容証明郵便に記載されている「確定日付の日付」の先後ではありません!
あくまで、その通知が債務者Aさんのところに「到達した日時」の先後で決まります。
例えば、Cさんの通知の確定日付が10月1日で、Dさんの通知の確定日付が10月2日でも、Dさんの通知が先にAさんに到達(例:10月3日到達)し、Cさんの通知が後で到達(例:10月4日到達)したら、Dさんが優先します。
これは、債務者Aさんが「どちらの譲渡が先に有効になったか」を知る基準は、通知の到達時だから、という理由に基づいています。
もし、CさんとDさんの確定日付のある通知が、まったく同時にAさんに到達した場合はどうなるのでしょうか? この場合は、どちらの譲受人もお互いに対して優先権を主張できません。そのため、CさんもDさんも、それぞれが債務者Aさんに対して「全額払え!」と請求できる、と考えられています。ただし、Aさんはどちらか一方に全額支払えば、それで債務は消滅します(二重に払う必要はありません)。
債権譲渡されたけど相殺したい!債務者ができること・できないこと
最後に、債権譲渡と「相殺(そうさい)」が絡んでくるケースを見ていきましょう。相殺は、お互いに持っている同種の債権(金銭債権どうしなど)を、対当額で帳消しにする、という便利な制度でしたね。

債権譲渡と相殺…なんだか難しそうだけど、これも試験でよく問われるんですよね!
状況設定:債権譲渡と相殺の問題
例えば、こんな状況を考えてみましょう。
- Aさん(債務者)は、Bさん(元の債権者)から100万円を借りています(B→A 貸金債権)。
- 一方で、Aさんも以前にBさんに対して、別の取引で50万円の売掛金を持っていました(A→B 売掛金債権)。つまり、AさんはBさんに50万円請求できる権利(反対債権)を持っています。
- その後、Bさんが、Aさんに対する100万円の貸金債権を、Cさん(譲受人)に譲渡しました。
- そして、元の債権者Bさんから債務者Aさんへ、債権譲渡の通知がありました(対抗要件具備)。
この状況で、新しい債権者CさんがAさんに対して「100万円払ってください!」と請求してきました。このとき、債務者Aさんは、自分が元の債権者Bさんに対して持っている50万円の売掛金債権(反対債権)を使って、Cさんからの請求額と相殺できるのでしょうか? つまり、「Bさんに持ってる50万円の権利と相殺して、残り50万円だけ払います!」と主張できるのでしょうか?
【原則】通知を受ける前に持っていた反対債権なら相殺できる!
結論から言うと、これは可能です!
債務者Aさんが、債権譲渡の対抗要件(この場合はBからの通知)を備えるよりも前に、元の債権者Bさんに対する反対債権(A→Bの50万円売掛金債権)を取得していた場合は、その反対債権をもって、新しい譲受人Cさんに対しても相殺を主張(対抗)できます(民法第469条1項)。
民法第469条(債権の譲渡における相殺)
1. 債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。
(※この「譲渡人に対して生じた事由」には、反対債権の取得が含まれます)
上の例で言うと、もし②のAさんがBさんに対して50万円の売掛金債権を持ったのが、④のBさんからAさんへの譲渡通知が来るよりも前だったら、AさんはCさんに対して「私がBに持ってる50万円の債権と相殺します!」と主張して、差額の50万円だけをCさんに支払えばOK、ということになります。
これはなぜかというと、債務者Aさんの立場からすれば、譲渡される前にすでに反対債権を持っていた場合、「まあ、いざとなったらBさんへの支払いと相殺できるだろう」と期待しているのが普通ですよね。その債務者の相殺に対する合理的な期待を保護する必要があるからです。債権が勝手に譲渡されたからといって、その期待が奪われてしまうのは酷だ、という考え方です。
通知を受けた後に取得した反対債権では相殺できないのが原則
では逆に、債務者Aさんが、債権譲渡の通知を受けた後に、元の債権者Bさんに対する反対債権を取得した場合はどうでしょうか?
例えば、上記の例で、④の譲渡通知がAさんに届いた後(10月1日)に、別の取引でAさんがBさんに50万円の売掛金債権を取得した(10月10日)ようなケースです。
この場合、原則として、その反対債権(通知後に取得したもの)で譲受人Cさんに対して相殺を主張することはできません(民法第469条2項1号)。
なぜなら、譲渡通知を受けた時点で、債務者Aさんは「あ、これからはBさんじゃなくてCさんに返済しないといけないんだな」と認識しているはずです。それにもかかわらず、その後で元の債権者Bさんに対して取得した債権を使って、Cさんへの支払いを免れようとするのは、新しい債権者Cさんにとっては予測できない不利益(不意打ち)になってしまうからです。この場合は、債権を譲り受けたCさんの利益が優先されるわけですね。
(※ただし、少し細かい話になりますが、通知を受けた後に取得した反対債権でも、その発生原因(例えば契約)が通知前に既に存在していた場合や、譲渡された債権(C→A)と同一の原因に基づく場合などは、例外的に相殺できるケースもあります(民法469条2項2号、3号)。宅建試験では、まずは上記の原則をしっかり押さえることが重要です。)
相殺できるかどうかのポイントまとめ
債権譲渡と相殺の関係をまとめると、以下のようになります。
債務者が譲受人に対抗(相殺を主張)できるかどうかの判断基準は、「債務者が、元の譲渡人に対する反対債権を取得したタイミング」と「債権譲渡の対抗要件(通知・承諾)が具備されたタイミング」の前後関係で決まります。
【相殺できるか?の判断】
- 反対債権の取得が、対抗要件具備(通知の到達 or 承諾)よりも前 → 相殺できる! (民法469条1項)
- 反対債権の取得が、対抗要件具備(通知の到達 or 承諾)よりも後 → 原則、相殺できない! (民法469条2項1号)

相殺できるかどうかは、反対債権を取得したタイミングと、譲渡通知が来たタイミングのどっちが早いかで決まるんですね!
まとめ
今回は、「債権譲渡」について、基本的な仕組みから、民法改正で注目される譲渡禁止特約の扱い、対抗要件(債務者・第三者)、二重譲渡のルール、そして相殺との関係まで、詳しく見てきました!
登場人物が多くて少し複雑に感じたかもしれませんが、誰の立場から見て、どんなルールが適用されるのか、図などを使いながら一つずつ整理していくと、意外と理解できるものですよね!
債権譲渡は、私たちの経済社会を円滑に回すための重要な制度ですが、それに関わる債務者、譲渡人、譲受人、さらには他の第三者の利害を公平に調整するために、民法では「対抗要件」というルールを中心に、様々な規定を置いています。
特に、
- 譲渡禁止特約があっても譲渡は原則有効であること、そしてその場合の債務者保護の仕組み
- 債務者対抗要件(譲渡人からの通知 or 承諾)と第三者対抗要件(確定日付ある証書)の違いと、それぞれの役割
- 二重譲渡の場合の優劣は「確定日付」ではなく「到達日」の先後で決まること
- 相殺できるかは、反対債権の取得時期と対抗要件具備時の前後関係で決まること
これらのポイントは、宅建試験でも頻出であり、正確な理解が求められます。
<この記事のポイント 再確認!>
- 債権譲渡: 権利を譲渡人から譲受人へ移転する契約。両者の合意のみで成立(債務者の同意不要)。
- 譲渡禁止特約: 特約があっても譲渡自体は原則有効(民法改正)。ただし譲受人が悪意・重過失なら債務者は履行拒絶・譲渡人への弁済等で対抗可能。
- 債務者対抗要件: 譲受人が債務者に権利主張するため。「譲渡人からの通知」or「債務者の承諾」が必要。譲受人からの通知は×。
- 第三者対抗要件: 二重譲渡などで譲受人間の優劣を決めるため。「確定日付のある証書」による通知・承諾が必要。
- 二重譲渡の優劣: 確定日付のある通知・承諾が債務者に「到達した日時」の先後で決まる(確定日付の日付ではない!)。
- 債権譲渡と相殺: 債務者は、対抗要件具備時より「前」に取得した譲渡人への反対債権なら、譲受人に相殺可能。具備時より「後」なら原則不可。
債権譲渡のルールは、一見すると細かくて難しく感じるかもしれません。でも、それぞれのルールが「なぜそうなっているのか?(債務者を保護するため? 譲受人を保護するため? 取引の安全を守るため?)」という理由や背景を考えながら学習すると、ただ暗記するよりもずっと理解が深まり、記憶にも残りやすくなりますよ。関係者が複数出てくるので、簡単な図を自分で書いて関係性を整理するのもおすすめです!

今回学んだ債権譲渡の知識をしっかり自分のものにして、自信を持って試験に臨めるように、繰り返し復習頑張りましょうね!