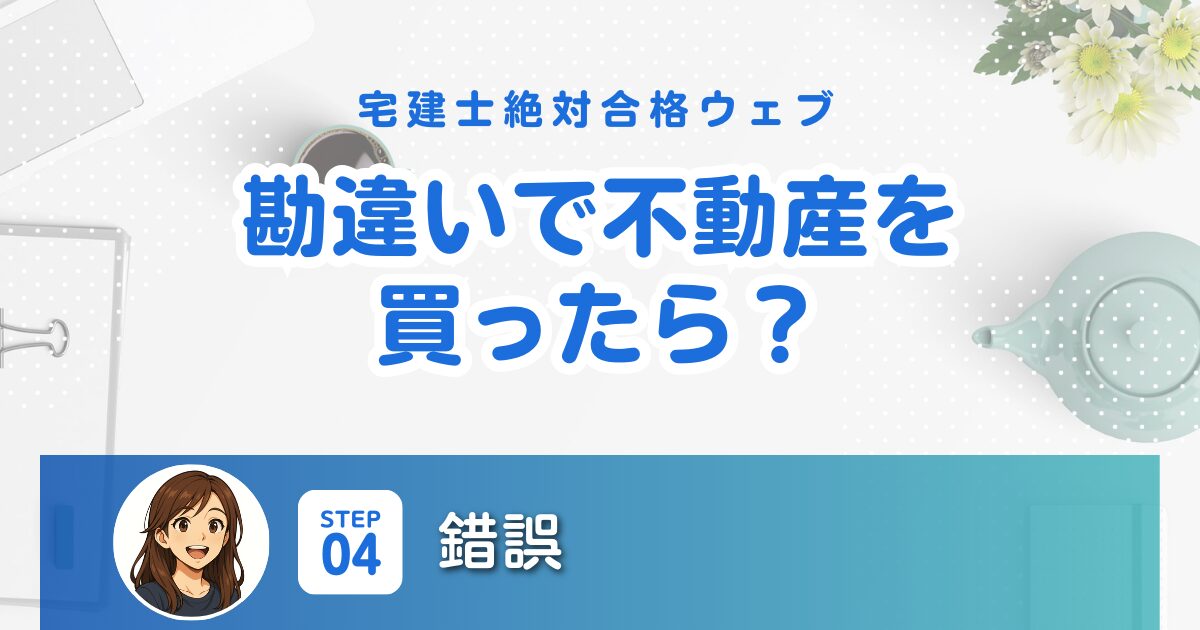今回は、民法の「錯誤」についてです。「錯誤って、なんだか言葉が難しそう…」「契約でうっかりミスしちゃった時って、どうなるの?」なんて疑問に思ったこと、ありませんか?宅建の権利関係の問題では、この「錯誤」がよく登場します。契約の効力に関わる大事なルールなので、避けては通れないんですよね。
でも、「どんな場合に契約を取り消せて、どんな時はダメなのか」「表示の錯誤?動機の錯誤?何が違うの?」「第三者が出てきたらどうなるの?」など、混乱しやすいポイントが多いのも事実です…。
そこでこの記事では、錯誤の基本的な意味から、具体的な種類、「表示の錯誤」と「動機の錯誤」の違い、契約を取り消せるための条件(要件)、そして例外的に取り消せるケース、さらには第三者が関わってきた場合のルールまで、具体例をたくさん交えながら、一つひとつ丁寧に解説していきます。

この記事を最後まで読めば、錯誤に関するややこしいルールがスッキリ整理できて、自信を持って問題に取り組めるようになりますよ! 苦手意識がある方も、これを機に得意分野に変えちゃいましょう!
- 「錯誤」の基本的な意味と2つの種類(表示の錯誤・動機の錯誤)
- どんな「勘違い」なら契約を取り消せるのか(錯誤の成立要件)
- うっかりミス(重過失)があっても取り消せる例外的なケース
- 「動機の錯誤」で特に気を付けたいポイント
- 錯誤があった契約に第三者が登場した場合のルール(誰が保護される?)
「錯誤」ってどんな意味?種類と効果(取消し)を知ろう!宅建民法解説
まずは、「錯誤」という言葉自体の意味と、どんな種類があるのか、そして錯誤があった場合に契約がどうなるのか、基本から押さえていきましょう!
そもそも「錯誤」とは?~日常でいう「勘違い」のこと~
「錯誤」というと難しく聞こえますが、簡単に言えば、「勘違い」や「意図しない間違い」のことなんです。
私たちが日常生活で「あっ、間違えちゃった!」「こうだと思ってたのに違った!」なんて言う、あの感覚に近いですね。
民法では、契約などの法律行為をする際に、この「錯誤」があった場合のルールを定めています。
錯誤の2つのタイプ:「表示の錯誤」と「動機の錯誤」
民法上の錯誤は、大きく分けて2つのタイプがあります。この違いを理解するのが、錯誤を攻略する第一歩ですよ!
錯誤のタイプ分け
- 表示の錯誤: 自分の意思と、実際に表示(相手に伝えたこと)が食い違っているケース。
- 動機の錯誤: 意思表示そのものは食い違っていないけど、その意思表示をするに至ったキッカケ(動機)に勘違いがあるケース。
それぞれの具体例を見てみましょう。
表示の錯誤:思ってたことと違うことを言っちゃった!
これは、「心の中で思っていたこと(意思)」と、「実際に口にしたことや書いたこと(表示)」がズレている状態です。
- 例: Aさんは「甲土地を買いたい」と思っていたのに、うっかり契約書に「乙土地を買います」と書いてサインしてしまった。
- この場合、Aさんの内心の意思(甲土地を買う)と、表示された内容(乙土地を買う)が一致していませんよね。これが「表示の錯誤」です。
- 「100万円で売る」つもりが、ゼロを一つ多く書いて「1000万円で売る」と契約書に書いてしまった、なんていうのも表示の錯誤にあたります。

いわゆる「言い間違い」や「書き間違い」がこれですね!
動機の錯誤:そう思ったキッカケが勘違いだった!
こちらは、「意思」と「表示」自体は一致しているんですが、その意思を持つに至った「動機」の部分に勘違いがあったというケースです。
- 例: Bさんは、「この土地の近くに新しい駅ができるらしい!便利になるから買おう!」と思って、「この土地を買います」と意思表示しました。しかし、実際には新駅の計画は存在しませんでした。
- この場合、Bさんの「この土地を買う」という意思と、「この土地を買います」という表示は一致しています。
- でも、「新駅ができるから」という、土地を買おうと思ったそもそものキッカケ(動機)が勘違いだったわけですね。これが「動機の錯誤」です。
- 他にも、「この絵は有名な画家が描いた本物だ」と信じて購入したけど、実は贋作だった、というようなケースも動機の錯誤にあたります。
表示の錯誤 → 意思と表示が不一致
動機の錯誤 → 意思と表示は一致、でもその動機に勘違いあり
この2つの区別、しっかり覚えておきましょうね!
錯誤があった契約はどうなる?~原則有効だけど「取消し」できる~
さて、契約の際に錯誤があった場合、その契約はどうなるのでしょうか?
民法では、錯誤による意思表示は、原則として有効ですが、一定の要件を満たせば、後から「取り消す」ことができるとされています(民法95条1項)。
無効じゃなくて「取消し」なのがミソ!
「無効」と「取消し」は似ているようで違うんです。
- 無効: 最初から効力がなかったものとして扱われます。基本的に誰でも主張できます。
- 取消し: 一応有効に成立したものを、後から効力を失わせることです。取消権を持つ人(錯誤の場合は基本的に勘違いした本人=表意者)だけが主張できます。
なぜ錯誤は「無効」ではなく「取消し」なのでしょうか?
それは、錯誤の制度が、勘違いをしてしまった人(表意者)を保護するためのものだからです。表意者自身が「やっぱりこの契約はなかったことにしたい」と思った場合に、その意思を尊重して取り消せるようにしているんですね。相手方からは取り消せません。

表意者のための救済措置、というイメージですね。
(錯誤)
民法第95条1項 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤(=表示の錯誤)
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤(=動機の錯誤)
どんな「勘違い」なら取り消せる?錯誤の成立要件と例外
錯誤があれば何でもかんでも取り消せるわけではありません。
「ちょっとした勘違い」で契約が簡単に取り消せてしまうと、取引の安全が害されてしまいますよね。
そこで、民法は錯誤による取消しができるための「要件」を定めています。ここが宅建試験でもよく問われるポイントです!
原則として、錯誤による取消しを主張するためには、以下の2つの要件を両方満たす必要があります。
- その錯誤が、法律行為の目的や取引上の社会通念に照らして「重要」であること。
- 錯誤をした人(表意者)に「重大な過失」がないこと。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
取り消せるのは「重要な勘違い」だけ!
まず、その勘違いが「重要」なものでなければなりません(民法95条1項)。
「重要」かどうかは、契約の目的や、世間一般の常識(取引上の社会通念)から見て判断されます。
- 例(重要とは言えない場合):
- 心の中では3,000万円で土地を買うつもりだったのに、計算ミスでうっかり「3,000万100円で買います」と言ってしまった。
- この100円の差は、通常、土地取引においては「重要」な錯誤とは言えないでしょう。こんな場合にまで取消しを認める必要はない、と考えられます。
- 心の中では3,000万円で土地を買うつもりだったのに、計算ミスでうっかり「3,000万100円で買います」と言ってしまった。
つまり、「その勘違いがなかったら、普通はその契約を結ばなかっただろう」と言えるくらいの、契約の根幹に関わるような重大な勘違いである必要がある、ということです。
うっかりミスにも程度がある?「重大な過失」があると原則取り消せない!
次に、勘違いをした本人(表意者)に「重大な過失」がないことが原則的な要件となります(民法95条3項)。
「過失」とは、不注意のことです。「重大な過失(重過失)」とは、普通の人なら当然払うべき注意を、著しく怠っていたような場合を指します。
- 例(重大な過失があり得る場合):
- 不動産取引のプロである宅建士が、部下に作成させた重要事項説明書の内容を全く確認せずに署名・押印し、後でその内容に重大な勘違いがあったことが判明した。
- これは、プロとしてあまりにも不注意であり、「重大な過失」があったと判断される可能性が高いです。
- 不動産取引のプロである宅建士が、部下に作成させた重要事項説明書の内容を全く確認せずに署名・押印し、後でその内容に重大な勘違いがあったことが判明した。

ちょっとしたうっかりミス(軽過失)」なら取り消せるけど、「普通ありえないでしょ!」っていうレベルの不注意(重過失)があったら、自己責任の部分も大きいので、原則として取り消せませんよ、ということです。
(錯誤)
民法第95条3項 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
原則として錯誤取消しができる場合
上記の 1. 重要な錯誤であること と 2. 表意者に重過失がないこと の両方を満たす場合です。
【重要】表意者に重大な過失があっても取り消せる「例外」パターン!
ここからが少しややこしいですが、とても重要です!
原則として、表意者に「重大な過失」があると錯誤取消しはできません。しかし、例外的に、表意者に重大な過失があっても取り消しが認められるケースが2つあります(民法95条3項柱書かっこ内、同項1号、2号)。
例外的に取り消せるのはどんな時?
- 相手方が、表意者が錯誤していることを知っていた(悪意)、または、知らなかったことに重大な過失があった(重過失)場合 (民法95条3項1号)
- 相手方も、表意者と同じ錯誤に陥っていた場合(共通錯誤) (民法95条3項2号)
それぞれ見ていきましょう。
例外①:相手が表意者の勘違いを知っていたり、知らなかったことに重過失がある場合
表意者(Aさん)に重大な過失があったとしても、相手方(Bさん)が「あ、Aさん勘違いしてるな」と知っていた(悪意)場合や、「普通なら気づくでしょ!」という状況なのに重大な不注意で気づかなかった(重過失)場合には、もはや相手方Bさんを保護する必要性は低いですよね。
このような場合は、たとえAさんに重大な過失があっても、Aさんは錯誤による取消しを主張できます。

相手方が悪質だったり、相当不注意だったりする場合は、重過失のある表意者でも保護されるんですね!
例外②:お互いに同じ勘違いをしていた場合(共通錯誤)
表意者(Aさん)だけでなく、相手方(Bさん)も、全く同じ内容の勘違いをしていた場合です。これを「共通錯誤」といいます。
この場合も、お互い様というか、勘違いを前提に契約が進んでいたわけですから、表意者Aさんに重大な過失があったとしても、取消しを認めても不都合はないだろう、と考えられます。
- 例: AさんもBさんも、ある土地に高価な美術品が埋まっていると信じ込んで売買契約をしたが、実際には何も埋まっていなかった。この場合、たとえAさんがその情報を鵜呑みにしたことに重大な過失があったとしても、Bさんも同じ勘違いをしていたなら、Aさんは取消しを主張できる可能性があります。
例外的に取消しができる場合(表意者に重過失があってもOK)
- 相手方が悪意 or 重過失
- 共通錯誤
この例外パターンは試験でも狙われやすいので、しっかり押さえてくださいね!
ちょっとややこしい?「動機の錯誤」の特別ルール
最初に説明した錯誤の2つのタイプのうち、「動機の錯誤」については、もう一つ注意点があります。
思い出してください。「動機の錯誤」は、意思表示そのものではなく、そのキッカケとなった「動機」に勘違いがある場合でしたね。
<動機の錯誤の例>
「新駅ができる」と思って土地を買ったが、計画はなかった。
この動機の錯誤の場合、原則として、その勘違いしている「動機」が、相手方に表示されて、法律行為の基礎とされていることが、錯誤として認められるための追加の要件となります(民法95条2項、判例の考え方)。
意思表示までの流れ
人が意思表示をするまでには、通常、以下のような段階があります。
- 動機: (例:この土地の近くに新駅ができるらしいぞ!)
- 内心的な意思: (例:よし、便利になるからこの土地を買おう!)
- 表示: (例:「この土地を買います」と相手に伝える)
動機の錯誤は、この①の段階での勘違いです。
でも、心の中でどういう動機で買おうと思ったかなんて、普通は相手には分かりませんよね。

確かに、相手はエスパーじゃないですもんね…。
そこで、動機の錯誤が問題となる場合は、その動機が相手に伝わっていて、契約の前提となっている必要がある、と考えられているんです。
<ポイント> 動機が表示されていることが必要!
この「表示」は、必ずしも「私がこの土地を買うのは、新駅ができるからです!」とはっきり言葉で伝えること(明示)だけを意味するわけではありません。
契約の状況などから、暗黙のうちに(黙示的に)その動機が相手に示され、契約の基礎となっていると認められればOKです。
<動機が全く表示されていない場合>
例えば、内心で「隣に有名人が引っ越してくるらしいから、この家を買おう」と思っていただけで、そのことを相手に全く伝えておらず、客観的な状況からも推測できないような場合は、たとえ後でそれが勘違いだとわかっても、動機の錯誤として取り消すのは難しいでしょう。
明示と黙示って?判例もチェック!
- 明示: 言葉や書面などで、はっきりと動機を相手に伝えること。
- 例:「将来値上がりすると聞いたので、この土地を買います」と契約時に伝える。
- 黙示: 言葉には出さないけれど、契約の経緯や状況などから、その動機が契約の基礎となっていることが客観的に推測できる形で示されていること。
- 判例の例①: 歴史的価値があると思って高価な絵画を購入したが、実は贋作だったケース。購入者は「本物だから買う」と明示していなくても、価格や取引の状況から、本物であることが取引の当然の前提(黙示の表示)であったとして、錯誤取消しが認められた例があります (東京高裁 H10.9.28)。
- 判例の例②: 会社の借金のために連帯保証人になったが、実は保証契約の時点で会社がすでに破綻状態だったケース。「健全な会社だと思っていた」という動機は、通常、保証契約を結ぶ際の黙示の前提となっているとして、錯誤取消しが認められた例があります (東京高裁 H17.8.10)。
動機の錯誤は、その動機が明示または黙示に表示され、契約の基礎となっている場合に、初めて錯誤取消しの土俵に乗る、と覚えておきましょう。その上で、先ほど説明した「重要性」や「重過失の有無(+例外)」の要件を検討することになります。
勘違いした人 vs 事情を知らない第三者!錯誤と第三者の関係はどうなる?
最後に、錯誤による取消しと「第三者」との関係について見ていきましょう。これも宅建試験では頻出のテーマです。
例えば、こんなケースを考えてみてください。
【ケース】
Aさんは勘違い(錯誤)によって、自分の土地(甲土地)をBさんに売却してしまいました。
その後、Bさんはその甲土地を、Aさんが錯誤していたことを知らないCさんに転売しました。
この状況で、Aさんが「あの契約は錯誤だったから取り消す!」と言った場合、AさんとCさん、どちらが甲土地の所有権を主張できるでしょうか?
<~錯誤と第三者の関係を図で説明~>
A(表意者・錯誤あり) → B(相手方) → C(第三者)
AがBとの契約を錯誤取消し。Cは甲土地を取得できる?
このような場合、誰を保護すべきかという問題が生じます。
民法は、取引の安全を図る観点から、一定の条件を満たす第三者を保護する規定を置いています。
基本ルール:善意無過失の第三者は保護される!
錯誤による取消しは、「善意」でかつ「過失がない」第三者には対抗(主張)することができません(民法95条4項)。
第三者保護のキーワード
- 善意: ある事実を知らないこと。この場合は、「Aさんが錯誤によって契約したこと」を知らない、という意味です。
- 無過失: 過失がないこと。つまり、「Aさんが錯誤していたことを知らなかったこと」について、不注意がなかった、という意味です。
つまり、第三者Cさんが、Aさんの錯誤について全く知らず、かつ、知らなかったことについて落ち度がない(善意無過失)場合には、たとえAさんがBとの契約を錯誤で取り消したとしても、AさんはCさんに対して「土地を返して!」とは言えない、ということです。この場合、Cさんが保護され、甲土地の所有権を取得します。
逆に、第三者Cさんが、Aさんの錯誤について知っていた(悪意)場合や、知らなかったとしても不注意があった(有過失)場合には、Cさんは保護されません。この場合は、Aさんが保護され、AさんはCさんに対して錯誤取消しを主張し、土地の返還を求めることができます。
(錯誤)
民法第95条4項 第一項の規定による意思表示の取消し(=錯誤取消し)は、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
錯誤のケースでは、善意「かつ」無過失の両方が揃って初めて第三者が保護される、という点をしっかり押さえてくださいね!善意なだけではダメ、無過失なだけでもダメです。
具体例で確認!誰が保護されるか判断してみよう
先のケースで考えてみましょう。
- パターン1: 第三者Cが善意無過失の場合
- Cさんは、AさんがBに土地を売った経緯(錯誤があったこと)を全く知らず、知らないことにも落ち度がなかった。
- → Cさんが保護される。 AはCに土地の返還を主張できない。甲土地はCさんのものになります。
- パターン2: 第三者Cが悪意の場合
- Cさんは、「Aさんは勘違いしてBに土地を売っちゃったらしいよ」ということを知っていた。
- → Aさんが保護される。 AはCに土地の返還を主張できる。
- パターン3: 第三者Cが善意だが有過失の場合
- Cさんは、Aさんの錯誤を知らなかった(善意)けれど、ちょっと調べれば分かりそうな状況だったのに、それを怠っていた(有過失)。
- → Aさんが保護される。 AはCに土地の返還を主張できる。(善意無過失ではないため)
<<錯誤の表意者 vs 第三者の比較表>>
| 第三者の状態 | 保護されるのは? | AはCに対抗できる? |
| 善意 かつ 無過失 | 第三者C | できない |
| 悪意 | 表意者A | できる |
| 善意だが有過失 | 表意者A | できる |
| (重過失も含む) | 表意者A | できる |
この第三者との関係は、他の民法の論点(詐欺や強迫など)と比較しながら覚えると、より理解が深まりますよ!
まとめ
今回は、宅建試験の頻出テーマである「錯誤」について、基本的な意味から取消しの要件、例外、そして第三者との関係まで詳しく見てきました。
ちょっと複雑な部分もありましたが、ポイントを押さえれば必ず理解できます!
最後に、今回の内容を簡単にまとめておきましょう。
- 錯誤とは?: いわゆる「勘違い」のこと。表示の錯誤(意思と表示の不一致)と動機の錯誤(動機の勘違い)がある。
- 錯誤の効果: 原則有効だが、一定の要件を満たせば「取消し」が可能。
- 取消しの要件(原則):
- 錯誤が「重要」であること。
- 表意者に「重大な過失」がないこと。
- 取消しの要件(例外): 表意者に重過失があっても、以下の場合は取消し可能。
- 相手方が悪意または重過失の場合。
- 共通錯誤の場合。
- 動機の錯誤の注意点: 原則として、その動機が明示または黙示に表示されている必要がある。
- 第三者との関係: 錯誤による取消しは、善意無過失の第三者には対抗できない(第三者が保護される)。悪意または有過失の第三者には対抗できる(表意者が保護される)。

錯誤は、具体例をイメージしながら、要件や例外を一つひとつ丁寧に整理していくことが大切です。この記事が、あなたの宅建合格への一助となれば嬉しいです!諦めずに頑張りましょうね!