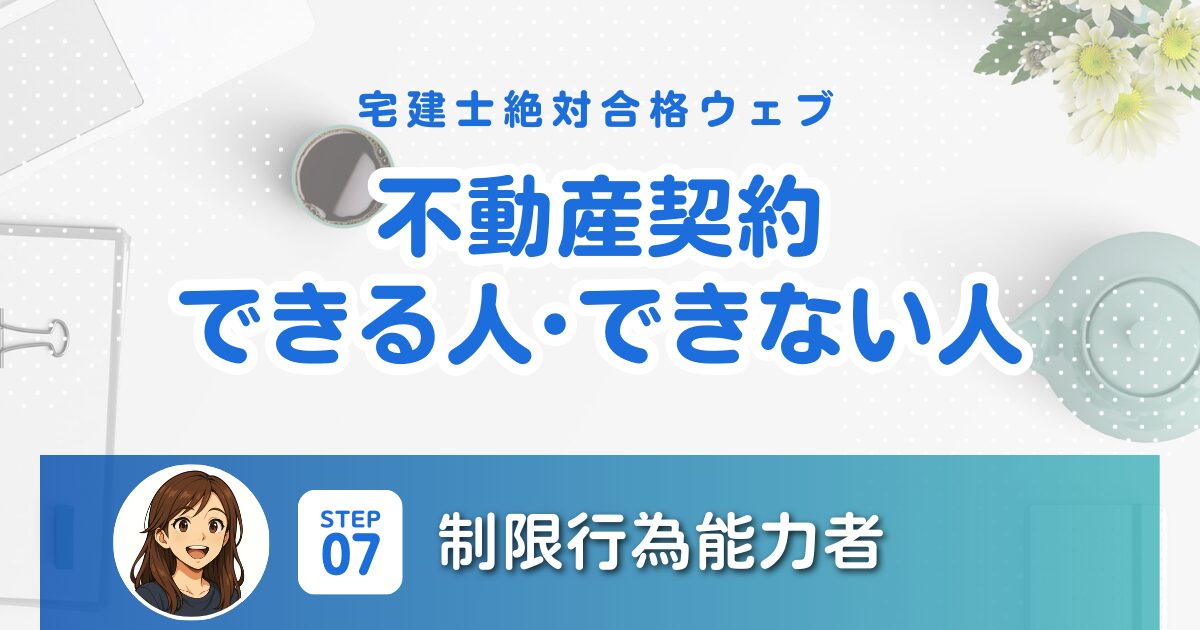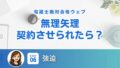権利関係って、普段聞き慣れない言葉が多くて、特に「制限行為能力者」のあたりは、種類も多いし、それぞれ何ができて何ができないのか、混乱しやすいポイントですよね。「成年被後見人?被保佐人?被補助人?何が違うのー!」って頭を抱えている方もいらっしゃるんじゃないでしょうか?
でも、安心してください。この制限行為能力者の分野は、宅建試験では頻出ですし、実務でもお客様の状況によっては関わってくる大切な知識なんです。しっかり理解しておけば、権利関係の得点アップに繋がりますよ!
この記事では、制限行為能力者とは何か、どんな種類があるのか、それぞれの人ができること・できないこと、そしてもし制限行為能力者と契約してしまった場合のルールについて、わかりやすく、かみ砕いて解説していきます。

この記事を読めば、今までごちゃごちゃになっていた知識がスッキリ整理されて、「なるほど!」と思えるはずです。一緒に頑張ってマスターしましょう!
この記事でわかること
- 制限行為能力者とは何か、なぜ保護が必要なのか
- 未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人の4つの違いと特徴
- それぞれの制限行為能力者が単独でできること、できないこと(契約の取消しなど)
- 保護者(法定代理人、後見人、保佐人、補助人)の役割と権限
- 制限行為能力者と契約した相手方を保護するためのルール(催告権、詐術)
そもそも制限行為能力者って?重要なポイントを理解しよう!
まず、「制限行為能力者」って言葉自体がちょっと硬いですよね。どんな人のことを指すのか、ピンと来ない方もいるかもしれません。宅建試験でしっかり得点するためにも、まずは基本から押さえていきましょう!
制限行為能力者とは?わかりやすく解説!
制限行為能力者とは、簡単に言うと、一人で完全に有効な法律行為(契約など)をすることができない人のことです。
法律行為っていうのは、例えば、家を買ったり売ったり、部屋を借りたり貸したりする「契約」を結ぶことなどを指します。普通、私たち大人は自分の意思で自由に契約を結べますよね?これを「行為能力がある」と言います。
でも、世の中には、年齢が若かったり、病気や障害などで判断能力が十分でなかったりするために、自分一人だけで契約などの重要な判断をすると、不利な契約を結んでしまったり、後で困ったことになってしまう可能性がある方たちがいます。

そういった方たちを保護するために、民法では「この人たちが一人でした契約は、後から取り消せるようにしよう」とか、「契約するときは保護者の同意を得るようにしよう」といったルールを定めているんです。
そうやって法律で行為能力が制限されている人たちのことを、「制限行為能力者」と呼ぶんですね。
なぜ保護が必要なの?契約は取り消せる?
じゃあ、なぜわざわざ法律で「制限」する必要があるんでしょうか?
それは、判断能力が不十分な人が、よくわからないまま不利な契約を結んでしまって、財産を失ったり、不利益を被ったりするのを防ぐためです。
例えば、まだ社会経験の少ない未成年者が、高額な商品をよく考えずに契約してしまったり、認知症の方が悪質な業者に騙されて不要なリフォーム契約をしてしまったり…といったケースが考えられますよね。
制限行為能力者を保護するため、彼らが単独で行った法律行為(契約など)は、原則として後から取り消すことができるようになっています。
取り消されると、その契約は最初からなかったことになります。これが制限行為能力者制度の大きなポイントです。
ただし、例外的に取り消せない場合もあるので、そこはしっかり区別して覚える必要がありますよ!後で詳しく説明しますね。
制限行為能力者の4つのタイプ【未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人】
制限行為能力者には、その判断能力の程度などに応じて、次の4つの種類があります。
- 未成年者(みせいねんしゃ)
- 成年被後見人(せいねんひこうけんにん)
- 被保佐人(ひほさにん)
- 被補助人(ひほじょにん)
「被」がついているのは、「~される人」という意味です。成年被後見人なら「後見人に保護される人」ということですね。
それぞれの人がどんな状態なのか、そしてどんな保護者がつくのかを表にまとめると、こんな感じです。
<制限行為能力者の種類と保護者の比較表>
| 種類 | 判断能力の状態 | 保護者 | 保護者の選任 | 備考 |
| 未成年者 | 年齢的に未熟 | 法定代理人(親権者等) | 自動的に決定 | 18歳未満 |
| 成年被後見人 | 常に判断能力を欠く状況 | 成年後見人 | 家庭裁判所 | 精神上の障害等が最も重い |
| 被保佐人 | 判断能力が著しく不十分 | 保佐人 | 家庭裁判所 | 成年被後見人よりは軽いが、不十分 |
| 被補助人 | 判断能力が不十分 | 補助人 | 家庭裁判所 | 最も軽いが、特定の行為には援助が必要 |
このように、判断能力のレベルによって、保護の内容や保護者の権限が変わってくるんです。宅建試験では、この4つの違いを正確に理解しておくことがとても重要ですよ!
【例外】胎児にも権利が認められるケースとは?相続・遺贈・損害賠償
ここで少し例外的なお話です。
原則として、人は生まれてこないと権利を持つことができません。お母さんのお腹の中にいる「胎児」の段階では、まだ権利能力(権利を持ったり義務を負ったりできる資格)は認められていないんです。
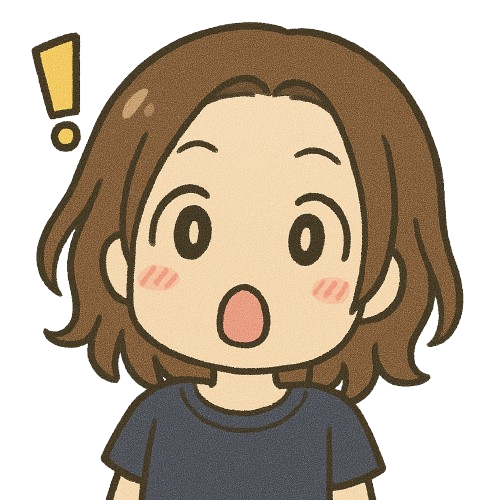
たしかに、まだ生まれていない赤ちゃんが自分で契約とかはできませんもんね。
しかし、生まれてくることを条件に、特別に権利能力が認められるケースが3つあります。これも宅建試験で問われることがあるので、覚えておきましょう。
胎児に権利能力が認められる3つの例外
- 不法行為に基づく損害賠償請求:例えば、お父さんが交通事故で亡くなってしまった場合、胎児も加害者に対して損害賠償を請求できます。
- 相続:お父さんが亡くなった時に胎児だった場合、生まれたら相続人になることができます。
- 遺贈:遺言によって財産を受け取ること(遺贈)も、胎児の段階で指定されていれば、生まれた後に受け取ることができます。
あくまで例外ですが、重要なポイントなので押さえておきましょう。
【種類別】制限行為能力者の特徴と注意点をマスター!未成年者から被補助人まで
ここからは、制限行為能力者の4つのタイプ、「未成年者」「成年被後見人」「被保佐人」「被補助人」について、それぞれの特徴やできること・できないこと、保護者の役割などを詳しく見ていきましょう!違いをしっかり意識しながら読み進めてくださいね。
【18歳未満】未成年者の契約と取り消し – 親の同意は必要?例外は?
まずは一番身近かもしれない「未成年者」です。
未成年者の定義と法定代理人(親権者)
未成年者とは、18歳未満の人を指します。
以前は20歳未満でしたが、2022年4月1日の民法改正で18歳に引き下げられました。結婚できる年齢(婚姻適齢)も男女ともに18歳に統一されています。
未成年者は、まだ社会経験や判断能力が十分ではないと考えられるため、保護者が必要ですよね。この保護者のことを法律用語で法定代理人(ほうていだいりにん)と言います。通常は親権者(お父さんやお母さん)が法定代理人になります。
未成年者がした契約は取り消せるのが原則!
未成年者が法律行為(契約など)をする場合、原則として法定代理人の同意が必要です。
法定代理人の同意を得ずに未成年者が単独で行った契約は、後から取り消すことができます。
例えば、17歳の高校生が、親に内緒で高額なバイクを買う契約を結んでしまった場合、後から親(法定代理人)や未成年者本人がその契約を取り消すことができる、ということです。

未成年者本人が取り消す場合でも、親の同意は必要ないんですよ。これもポイントです。
【重要】取り消せない例外ケースを覚えよう!
ただし、未成年者がした行為でも、取り消せない例外があります。これは試験でよく狙われるので、しっかり覚えてください!
未成年者が単独で行っても取り消せない行為
- 単に権利を得たり、義務を免れたりする行為
- 例:お年玉をもらう(贈与を受ける)、借金をチャラにしてもらう(債務免除)
- 理由:未成年者にとって有利なだけで、不利益がないから。
- 法定代理人が目的を定めて処分を許した財産の処分行為
- 例:お小遣いで好きなお菓子や漫画を買う
- 理由:親が「この範囲なら自由に使っていいよ」と認めているから。
- 法定代理人が目的を定めずに処分を許した財産の処分行為
- 例:「これで好きなものを買いなさい」と渡されたお金で買い物をする
- 理由:使い道も任されているから。
- 法定代理人から許可を得た営業に関する行為
- 例:親の許可を得て個人で雑貨屋さんを開いている未成年者が、商品を仕入れたり売ったりする契約。
- 理由:許可された営業の範囲内では、大人と同じように扱われるから。
- もし未成年者が宅建業の免許を取得して、親の許可のもとで不動産の売買をする場合も、これにあたりますね!
- 婚姻した場合(成年擬制) ※現在は削除
- 以前は未成年者が結婚すると成人とみなされる「成年擬制」という制度がありましたが、成人年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、この制度はなくなりました。結婚しても18歳未満であれば未成年者として扱われます。
法定代理人が持つ権利(同意権・取消権・追認権・代理権)
未成年者の法定代理人(主に親権者)は、未成年者を保護するために、次のような権利を持っています。
法定代理人の主な権利
- 同意権:未成年者が契約などをする際に、事前に同意を与える権利。
- 取消権:未成年者が同意なしにした契約などを、後から取り消す権利。
- 追認権:未成年者が同意なしにした契約などを、後から認めて有効なものとして確定させる権利。
- 代理権:未成年者に代わって契約などの法律行為を行う権利。
誰が取り消せるの?本人・法定代理人・元未成年者
未成年者が法定代理人の同意なく行った契約は取り消せる、とお話ししましたが、具体的に誰が取り消せるのでしょうか?
取り消しができる人
- 未成年者本人
- 法定代理人(親権者など)
- 承継人(相続人など)
- (行為能力者になった後の)元未成年者(18歳になった後など)

本人が自分で「やっぱりやめる!」って言えるのは心強いですよね。
【判断能力を欠く】成年被後見人の契約 – 後見人の役割と権限
次に、「成年被後見人」について見ていきましょう。判断能力が特に不十分な方を保護する制度です。
成年被後見人とは?どんな人が対象?
成年被後見人(せいねんひこうけんにん)とは、精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)により、物事を判断する能力を常に欠いている状況にある人で、家庭裁判所から後見開始の審判(こうけんかいしのしんぱん)を受けた人のことを言います。
ポイントは「常に判断能力を欠く状況」という点です。自分で自分の財産を管理したり、契約の内容を理解したりすることがほとんどできない状態の方をイメージしてください。
後見開始の審判は、本人、配偶者、4親等内の親族、検察官などが家庭裁判所に請求することで行われます。本人の意思だけでは決まりません。
成年被後見人の契約は原則取り消せる!
成年被後見人は、判断能力が常に欠けている状態とされているため、保護の必要性が非常に高いです。
成年被後見人が行った法律行為(契約など)は、原則として、後から取り消すことができます。
たとえ保護者である「成年後見人」が事前に同意していたとしても、取り消すことができてしまいます。

これは、同意があっても、その通りに行動できるかどうかがわからない、という考え方からきているんですね。だから、成年後見人には「同意権」がないんです。
【例外】日用品の購入は取り消せない!
ただし、成年被後見人の行為がすべて取り消せるわけではありません。日常生活に必要な、ごく少額の買い物まで取り消せてしまうと、かえって本人の生活が不便になってしまいますよね。
成年被後見人が行っても取り消せない行為
- 日用品の購入その他日常生活に関する行為
- 例:スーパーで食料品を買う、コンビニでシャンプーを買う
成年後見人って誰がなるの?役割は?
成年被後見人を保護・支援する人を成年後見人(せいねんこうけんにん)と言います。
成年後見人は、家庭裁判所によって選任されます。親族だけでなく、弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門家や、福祉関係の法人が選ばれることもあります。複数人が選任されることも可能です。
成年後見人は、成年被後見人の財産を管理したり、代わりに契約を結んだり(代理権)、成年被後見人が不利な契約をしてしまった場合にそれを取り消したり(取消権)する役割を担います。
成年後見人が持つ権利(取消権・追認権・代理権)※同意権はない!
成年後見人が持つ主な権利は次の通りです。
成年後見人の主な権利
- 取消権:成年被後見人が行った不利益な契約などを取り消す権利。
- 追認権:成年被後見人が行った契約などを後から認めて有効なものとして確定させる権利。
- 代理権:成年被後見人に代わって財産管理や契約などを行う広範な権利。
先ほども触れましたが、成年後見人には同意権はありません。同意しても意味がない(取り消せてしまう)からです。これは他の保護者との大きな違いなので、しっかり覚えておきましょう!
【判断能力が著しく不十分】被保佐人の契約 – 保佐人の同意が必要なケースとは?
続いては「被保佐人」です。成年被後見人ほどではないけれど、判断能力がかなり不十分な方を保護する制度です。
被保佐人とは?成年被後見人との違いは?
被保佐人(ひほさにん)とは、精神上の障害により、物事を判断する能力が著しく不十分な人で、家庭裁判所から保佐開始の審判(ほさかいしのしんぱん)を受けた人のことを言います。
成年被後見人との違いは、判断能力の程度です。「常に欠いている」のが成年被後見人、「著しく不十分」なのが被保佐人です。被保佐人の方が、少し判断能力が残っているイメージですね。
判断能力のレベル(重い順)
成年被後見人 > 被保佐人 > 被補助人
保佐開始の審判も、本人、配偶者、4親等内の親族などが家庭裁判所に請求します。
基本的には単独で契約できるけど…
被保佐人は、成年被後見人と違って、日常生活に関する行為はもちろん、それ以外の多くの法律行為も単独で有効に行うことができます。
原則として、被保佐人が単独で行った契約は有効であり、後から取り消すことはできません。

成年被後見人とは大きく違うところですね!
ただし、財産に関する特に重要な行為については、失敗すると大きな損害を受けてしまう可能性があるため、保護者である「保佐人」の同意が必要とされています。
【要注意】保佐人の同意が必要な「重要な財産上の行為」リスト
民法では、被保佐人が行う場合に保佐人の同意が必要な行為を具体的に定めています(民法第13条第1項)。これは試験で頻出なので、しっかり覚えましょう!
<被保佐人が行う場合に保佐人の同意が必要な主な行為>
- 元本の領収・利用:貸したお金の元本を受け取ることや、預貯金を引き出すことなど。
- 借財・保証:お金を借りること、他人の借金の保証人になること。
- 不動産その他重要な財産の得喪を目的とする行為:不動産を売買したり、贈与したり、抵当権を設定したりすること。
- 訴訟行為:裁判を起こしたり、和解したりすること。
- 贈与・和解・仲裁合意
- 相続の承認・放棄、遺産分割
- 贈与・遺贈の拒絶、負担付贈与・負担付遺贈の受諾
- 新築、改築、増築、大修繕
- 一定期間を超える賃貸借:土地は5年、建物は3年を超える賃貸借契約を結ぶこと。(この期間も重要!)

たくさんありますね…!特に不動産に関わるものが多いので、宅建受験生としてはしっかり押さえておきたいところです。
もし、被保佐人がこれらの行為を保佐人の同意を得ずに行った場合、後から取り消すことができます。
なお、上記リスト以外の行為については、家庭裁判所の審判によって、さらに保佐人の同意が必要な行為を追加することもできます。
保佐人が同意してくれない場合は?家庭裁判所の許可
もし、被保佐人が同意の必要な行為をしたいのに、保佐人が(正当な理由なく)同意してくれない場合、どうなるのでしょうか?
その場合は、被保佐人は家庭裁判所に申し立てて、保佐人の同意に代わる許可をもらうことができます。
保佐人が持つ権利(同意権・取消権・追認権・代理権)※代理権には条件あり
被保佐人の保護者である保佐人(ほさにん)が持つ主な権利は次の通りです。
保佐人の主な権利
- 同意権:上記の重要な財産行為などに対して同意を与える権利。
- 取消権:被保佐人が同意なしに重要な財産行為を行った場合に、それを取り消す権利。
- 追認権:被保佐人が同意なしに行った重要な財産行為を、後から認めて有効にする権利。
- 代理権:特定の法律行為について、家庭裁判所の審判によって与えられる権利。(本人の同意が必要)
保佐人の代理権は、成年後見人のように当然に広範なものが認められるわけではありません。「この契約について代理権を与える」というように、特定の行為について家庭裁判所が定める必要があり、しかもその際には被保佐人本人の同意が必要になります。成年後見人との違いを意識しましょう!
【判断能力が不十分】被補助人の契約 – 本人の同意と補助人の役割
最後に「被補助人」です。4つのタイプの中で、最も判断能力の低下の程度が軽いケースです。
被補助人とは?被保佐人との違いは?
被補助人(ひほじょにん)とは、精神上の障害により、物事を判断する能力が不十分な人で、家庭裁判所から補助開始の審判(ほじょかいしのしんぱん)を受けた人のことを言います。
被保佐人との違いは、判断能力が「著しく不十分」ではなく、単に「不十分」という点です。軽い認知症や知的障害などで、複雑な契約などは少し心配だけど、多くのことは自分で判断できる、といった状態をイメージすると良いでしょう。
審判には本人の同意が必要!
被補助人の制度の大きな特徴は、補助開始の審判をする際に、必ず本人の同意が必要であることです。
成年後見開始や保佐開始の審判は本人の同意がなくても可能ですが、補助開始の審判だけは本人が「補助をお願いします」と同意しない限り、開始されません。

本人の意思がより尊重されている制度なんですね。
ほとんどの契約は単独でOK!
被補助人は、判断能力の低下の程度が比較的軽いため、原則として、すべての法律行為を単独で有効に行うことができます。
被補助人が単独で行った契約は、原則として有効であり、後から取り消すことはできません。
【ポイント】補助人の同意が必要なのは家庭裁判所が決めた特定の行為のみ
では、被補助人は完全に保護が必要ないのかというと、そうではありません。
被補助人の場合は、保佐人の同意が必要とされている行為(民法第13条第1項)の中から、特に「この行為については補助人の助けが必要だ」と家庭裁判所が認めた特定の行為についてのみ、保護者である補助人(ほじょにん)の同意が必要になります。
<被補助人が行う場合に補助人の同意が必要となる可能性がある行為>
- 家庭裁判所が、保佐人の同意が必要な行為(不動産売買、借金、保証、相続放棄など)の中から、個別に「この行為は補助人の同意が必要」と定めたもの。
もし、補助人の同意が必要と定められた特定の行為を、被補助人が補助人の同意なしに行った場合、後から取り消すことができます。
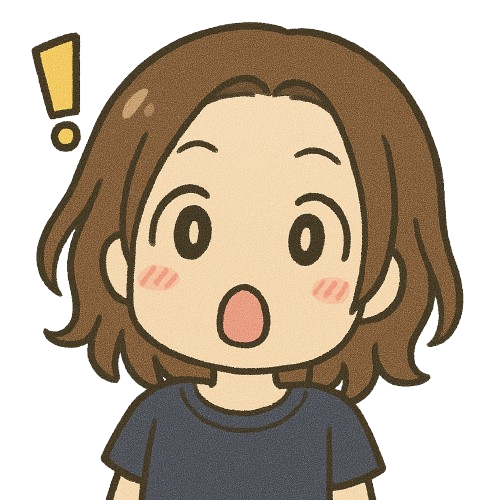
つまり、被補助人の場合は、画一的に「これらの行為は同意が必要」と決まっているわけではなく、その人の状況に合わせてオーダーメイドで同意が必要な範囲が決まる、ということですね!
補助人が持つ権利(同意権・取消権・追認権・代理権)※同意権・代理権には条件あり
被補助人の保護者である補助人(ほじょにん)が持つ主な権利は次の通りです。これも条件付きのものが多いので注意しましょう。
<補助人の主な権利>
- 同意権:家庭裁判所が定めた特定の法律行為について同意を与える権利。(この同意権を与える審判にも本人の同意が必要)
- 取消権:補助人の同意が必要と定められた特定の行為を、被補助人が同意なしに行った場合に、それを取り消す権利。
- 追認権:補助人の同意が必要と定められた特定の行為を、被補助人が同意なしに行った場合に、後から認めて有効にする権利。
- 代理権:特定の法律行為について、家庭裁判所の審判によって与えられる権利。(この代理権を与える審判にも本人の同意が必要)
補助人に同意権や代理権を与えるかどうかは、家庭裁判所が個別に判断します。そして、その審判には必ず本人の同意が必要です。保佐人の代理権付与審判には本人の同意が必要でしたが、同意権付与には不要でした。このあたり、細かくて混乱しやすいので、しっかり整理しておきましょう!
制限行為能力者と契約しちゃった!相手方を守るためのルール【催告権・詐術】
ここまで、制限行為能力者本人の保護について見てきました。契約が取り消せるのは、本人にとっては安心な制度ですが、一方で、契約の相手方からすると、「いつ取り消されるかわからない…」と不安定な立場に置かれてしまいますよね。そこで、民法では契約の相手方を保護するためのルールも定めています。
契約を取り消されたらどうなる?善意の第三者でも対抗できない?
制限行為能力を理由とする取消しは、非常に強力な効果を持ちます。
制限行為能力者が行った契約が取り消された場合、その効果は絶対的です。つまり、契約の相手方が善意(制限行為能力者だと知らなかった)であっても、さらにその人から権利を譲り受けた第三者が善意であっても、取り消しを主張して、目的物(例えば売った土地)を取り返すことができます。
例:
未成年者Aが、親の同意なく自分の土地をBに売却し、Bがさらに事情を知らないCにその土地を転売したとします。
<制限行為能力者との契約取消しと第三者の関係図>
A(未成年者) —(売買契約)—> B —(転売)—> C(善意の第三者)
この場合、後からAやAの親がAB間の売買契約を取り消すと、Aは善意の第三者であるCに対しても「土地を返してください」と主張できるのです。

これは、Cさんにとっては厳しい結果ですよね…。でも、それだけ制限行為能力者の保護が重視されているということなんです。
契約相手の不安を解消!「催告権」って何?
このように、制限行為能力者との契約は不安定な状態になりがちです。そこで、契約の相手方を保護するために認められているのが催告権(さいこくけん)です。
催告権とは?追認するかどうか確認できる権利
催告権とは、制限行為能力者と契約した相手方が、制限行為能力者側(保護者など)に対して、「この契約、取り消しますか?それとも追認(有効なものとして認める)しますか?1ヶ月以上の期間内に返事をください!」と問い合わせる(催告する)ことができる権利です。
相手方としては、いつまでもハッキリしない状態は困りますから、「白黒はっきりさせてください!」と求めることができるわけですね。
誰に催告するかで結果が変わる!
この催告権で重要なのは、「誰に」催告したか、そしてその返事が期間内になかった場合にどうなるかです。パターンによって結論が変わるので、しっかり区別しましょう!
<制限行為能力者の相手方が有する催告権の比較表>
| 契約の相手方 | 催告する相手 | 期間内に返事がない場合 |
| 制限行為能力者 | 保護者(法定代理人、後見人、保佐人、補助人) | 追認したものとみなす |
| 制限行為能力者 | 行為能力者になった後の本人 | 追認したものとみなす |
| 被保佐人 | 被保佐人本人 | 取り消したものとみなす |
| 被補助人 | 被補助人本人 | 取り消したものとみなす |
| 未成年者 | 未成年者本人 | 催告しても意味がない(無効) |
| 成年被後見人 | 成年被後見人本人 | 催告しても意味がない(無効) |
<催告権のポイント>
- 保護者や行為能力者になった後の本人に催告して返事がなければ、「追認」(契約は有効になる)とみなされます。相手方にとっては有利な結果ですね。
- 被保佐人や被補助人本人に催告して返事がなければ、「取消し」とみなされます。(※本人が追認するには、保佐人・補助人の同意が必要な場合があるため、本人の単独の返事だけでは不十分と考えられるからです)
- 未成年者や成年被後見人本人に催告しても、そもそも有効な返事を期待できないため、催告自体が無効です。返事がなくても何も効果はありません。
【注意】制限行為能力者であることを隠されたら?「詐術」の場合
最後に、もし制限行為能力者が、自分が制限行為能力者であることを隠して契約した場合についてのルールです。
詐術(さじゅつ)とは、制限行為能力者が相手を騙す目的で、次のような行為をすることです。
- 「私はもう成人しています」などと、行為能力者であると信じさせるために嘘をつくこと。
- 未成年者が、親の同意書を偽造するなどして、同意を得ているように見せかけること。
このように詐術を用いて相手を騙して契約した場合、制限行為能力者であっても、その契約を取り消すことはできません。

これは当然ですよね。嘘をついて相手を騙した人まで保護する必要はない、ということです。
ただし、単に「自分は制限行為能力者です」と言わなかっただけ(黙っていただけ)では、通常は詐術にはあたりません。積極的に相手を騙す意図があったかどうかが重要になります。
まとめ
今回は、宅建試験の権利関係の中でも特に重要な「制限行為能力者」について、詳しく見てきました。
制限行為能力者とは、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人の4種類があり、それぞれ判断能力の程度に応じて、できることや保護の内容が異なるんでしたね。
- 未成年者(18歳未満): 原則、法定代理人(親)の同意が必要。同意なければ取り消せる。例外あり。
- 成年被後見人(判断能力を常に欠く): 原則、行為は取り消せる(後見人の同意があっても)。例外は日用品の購入など。後見人に同意権はない。
- 被保佐人(判断能力が著しく不十分): 原則、単独で有効にできる。ただし、重要な財産行為(不動産売買など)は保佐人の同意が必要。同意なければ取り消せる。
- 被補助人(判断能力が不十分): 原則、単独で有効にできる。家庭裁判所が定めた特定の行為についてのみ補助人の同意が必要。同意なければ取り消せる。補助開始には本人の同意が必要。
そして、これらの人を保護するために「取消権」が認められていますが、その取消しは善意の第三者にも対抗できる強力なものである一方、契約の相手方を保護するための「催告権」や、制限行為能力者が嘘をついた場合の「詐術」のルールもありました。

覚えることが多くて大変かもしれませんが、それぞれの違いやポイントをしっかり整理すれば、必ず理解できますよ!