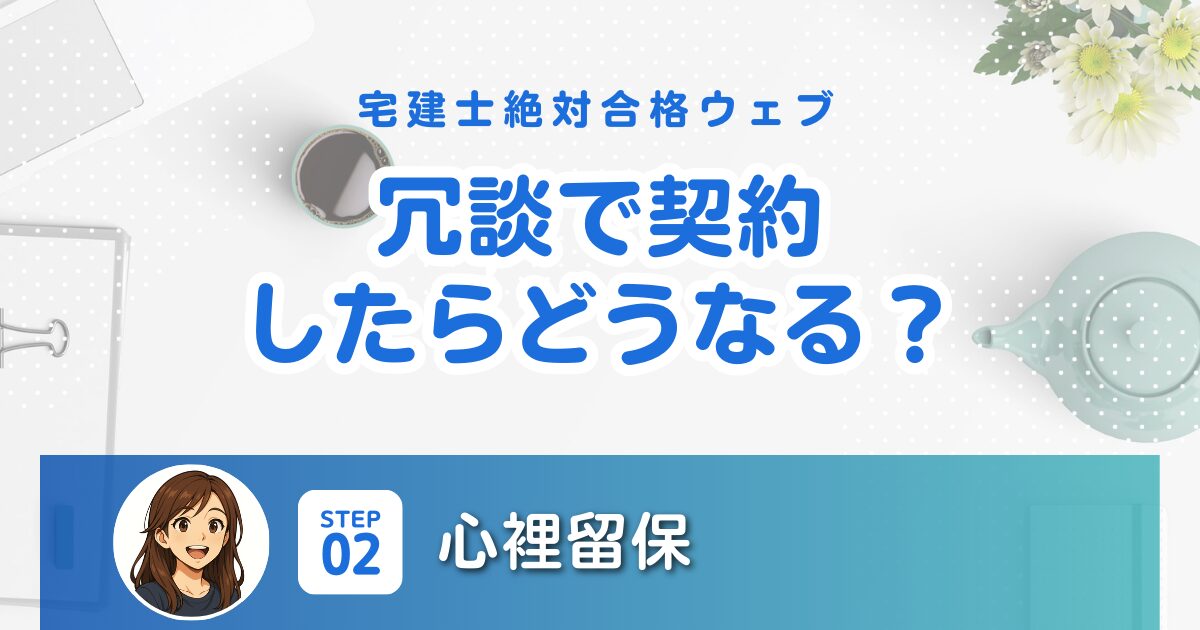意思表示のところで出てくる「心裡留保(しんりりゅうほ)」って言葉、なんだか漢字も難しいし、意味もピンとこない…って感じていませんか?日常生活でも、「あげるつもりないけど、この時計、君にあげるよ!」なんて冗談で言っちゃうこと、あったりしますよね? でも、もし法律の世界で、そんな風に内心とは違うこと(冗談)を言って契約しちゃったら、その契約ってどうなるんでしょう? 「冗談だよ!」って言えば済むの? それとも、本当にあげなきゃいけなくなっちゃうの?
さらに、もしその冗談で言ったことを真に受けた相手が、それをさらに別の人に売っちゃったりしたら…? もう、誰が本当の権利者なのか、わけが分からなくなっちゃいそうですよね。
そんな、ちょっとややこしい「心裡留保」について、この記事では基本からしっかり解説していきます! 「心裡留保ってそもそも何?」という言葉の意味から、「契約の効力はどうなるの?」、「第三者が絡んできたらどうなるの?」といった具体的なルールまで、図や具体例をたっぷり使って、まるで隣で私が説明しているみたいに、分かりやすくお伝えしますね。
この記事を読めば、心裡留保のルールがスッキリ整理できて、「なるほど、そういうことか!」って納得できるはずです。意思表示の問題は宅建試験でもよく狙われる分野なので、ここでしっかり理解しておけば、得点力アップ間違いなし! 他の意思表示(通謀虚偽表示とか錯誤とか)を学ぶ上でも、基礎になる知識ですよ。

さあ、一緒に「心裡留保」をマスターして、民法を得意分野にしちゃいましょう!
- 「心裡留保」って一体何?基本的な意味と具体例
- 冗談で結んだ契約は有効?それとも無効?効力が決まるルール
- 契約相手が冗談だと知っていたか(悪意)、知らなかったか(善意無過失)で結論が変わる理由
- 冗談で譲ったものが第三者に渡ってしまった場合、誰が保護されるのか?
- 民法93条(心裡留保)の条文で押さえるべきポイント
冗談のつもりが大変なことに?「心裡留保」の基本ルールを理解しよう
まずは、「心裡留保」っていう言葉自体に慣れるところから始めましょう! ちょっと難しい言葉に聞こえるかもしれませんが、中身は意外とシンプルなんですよ。
まずは言葉の意味から!「心裡留保」ってどんな状況?(意思の不存在とは)
心裡留保(しんりりゅうほ)。すごく簡単に言っちゃうと、「冗談」や「嘘」で意思表示(契約の申し込みや承諾など)をすることです。
法律の言葉で言うと、「表意者(ひょういしゃ:意思表示をする人)が、真意(しんい:本当の気持ち)ではないことを自分で知りながらする意思表示」のこと。
- 真意ではない:本当はそう思っていない(例:本当は売るつもりはない)
- 自分で知りながら:自分が嘘を言っている、冗談を言っていることを自覚している
- 意思表示をする:口に出して言ったり、書面に書いたりして、相手に伝える(例:「売ります」「あげます」と言う)
つまり、「心の中(意思)」で思っていることと、「口や態度で示したこと(表示)」が一致していない状態なんですね。これを「意思の不存在(いしのふそんざい)」とか「意思の欠缺(いしのけんけつ)」なんて言ったりします。
- 本当はあげるつもりなんて全くないのに、友達に「この限定版フィギュア、キミにあげるよ!」と言ってしまう。
- 売る気はないけど、見栄を張って「この高級車、100万円で売ってやるよ!」と同僚に言ってしまう。
- 内心(あげたくない、売りたくない)と表示(「あげる」「売る」)がズレていますよね。これが心裡留保の典型的なパターンです。

なるほど、「心で思ってること(真意)を留保(隠して)、違うことを表示する」から心裡留保って言うんですね!
登場人物を整理!「表意者」と「相手方」って誰のこと?
心裡留保の話を進める上で、誰が誰なのか、登場人物の呼び方を整理しておきましょう。民法の条文や解説でよく出てくる言葉なので、覚えておくと便利ですよ。
- 表意者(ひょういしゃ):意思表示をする人。心裡留保の場合は、冗談や嘘を言っている本人のことです。さっきの例だと、「フィギュアあげるよ!」と言った友達や、「車売るよ!」と言った同僚が表意者Aさんになります。
- 相手方(あいてがた):その意思表示を受け取る人。心裡留保の場合は、冗談や嘘を言われた相手のことです。例でいうと、「フィギュアあげるよ!」と言われたあなた(Bさん)や、「車売るよ!」と言われた同僚(Bさん)が相手方になります。
契約はどうなる?当事者間&第三者との関係をケース別に解説!
さて、本題です。冗談(心裡留保)で言った契約は、法的にどう扱われるのでしょうか? そして、もしその契約に関わる第三者が現れたら、事態はどう変わるのでしょうか? ケース別に見ていきましょう!
原則有効?例外無効?心裡留保の効果を徹底分析!【当事者間】
表意者Aさんが「本当は売る気ないけど、この土地をBさんにあげるよ!」と冗談で言ったとします。このAさんとBさんの間の契約(贈与契約)は有効になるのでしょうか? それとも無効になるのでしょうか?
結論から言うと、心裡留保による意思表示は、原則として有効なんです!
【原則】相手方が善意無過失なら契約は有効!
えっ、冗談なのに有効なの!?って驚きませんか?
そうなんです。たとえAさんが冗談で言ったとしても、相手方のBさんが、Aさんの言ったことを本気だと信じていて、かつ、信じたことについて何の落ち度もなかった場合は、契約は有効になります。
この状態を法律用語で、相手方Bさんが「善意無過失(ぜんいむかしつ)」である、と言います。
(覚えてますか? 前回の記事でやりましたね! 善意=知らなかった、無過失=落ち度がない、でした。)
相手方Bが善意無過失の場合 → 契約は有効
なぜ有効になるかというと、相手方Bさんを保護するためです。
Bさんからしてみれば、Aさんが内心どう思っていたかなんて分かりませんよね? Aさんの言った言葉を信じて、「やったー!土地もらえるんだ!」と思ったのに、後から「あれ、冗談だったんだゴメン!」で契約がナシにされたら、Bさんは困ってしまいます。取引の安全を守るためにも、原則として表示された通りの効果を認める、というのが法律の考え方なんです。

冗談を言ったAさんより、それを真に受けた(しかも落ち度なく)Bさんを守ろう、ということですね。
つまり、相手方Bさんが善意無過失なら、Aさんは冗談のつもりでも、本当に土地をBさんにあげなければいけなくなる、ということです! 冗談もほどほどにしないと、大変なことになりますね…。
【例外】相手方が悪意または有過失なら契約は無効!
ただし、例外があります。
もし、相手方Bさんが、Aさんが冗談で言っていることを知っていた(悪意:あくい)場合、または、ちょっと注意すれば冗談だと気づけたはずなのに不注意で気づかなかった(有過失:ゆうかしつ)場合は、話が変わってきます。
相手方Bが悪意 または 有過失の場合 → 契約は無効
この場合、BさんはAさんの真意を知っていたか、知ることができたはずなので、Bさんを保護する必要性は低いですよね。むしろ、冗談だと分かっていながら契約を有効にするのはおかしいです。
ですから、相手方Bさんが悪意または有過失の場合は、その心裡留保による意思表示(契約)は無効となります。
- 悪意:Aさんが冗談で言っていると知っていた。
- 有過失:普通なら冗談だと気づけたはずなのに、うっかり気づかなかった。(軽過失・重過失どちらも含みます)
心裡留保が無効になるのは、相手方が「悪意」または「有過失」の場合です。「かつ」ではなく「または」なので、どちらか一方にあてはまれば無効になります。
民法93条1項をチェック!条文から読み解く心裡留保
このルールは、民法の条文にもちゃんと書かれています。
(心裡留保)
第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り(悪意)、又は知ることができたとき(有過失)は、その意思表示は、無効とする。
ちょっと読みにくいかもしれませんが、分解してみましょう。
- 「意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。」
- → 冗談(心裡留保)で言った意思表示でも、原則として有効ですよ、という意味です。
- 「ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り(悪意)、又は知ることができたとき(有過失)は、その意思表示は、無効とする。」
- → 例外として、相手方が悪意または有過失の場合は、無効になりますよ、という意味です。
まさに、これまで説明してきた通りの内容が書かれていますね!

条文の「ただし」の前が原則、「ただし」の後が例外になっていることが多いんですよ!読む時のヒントにしてくださいね。
まとめ表で一目でわかる!心裡留保の効果
ここまでの当事者間の関係を、表で整理しておきましょう。
心裡留保の効果(当事者間)の比較表
| 相手方Bの状態 | 契約の効力 | 理由・補足 |
| 善意無過失 | 有効 | 相手方Bの信頼を保護するため(原則) |
| 悪意 (知っていた) | 無効 | 保護する必要がないため(例外) |
| 善意有過失 (不注意) | 無効 | 注意すれば気づけたはずなので保護の必要性低い(例外) |
宅建試験対策としては、「相手方が善意無過失の場合『のみ』有効、それ以外は無効」と覚えてしまうのが一番シンプルで分かりやすいですよ!
冗談で売ったものが転売されたら?善意の第三者は保護される?【第三者との関係】
さて、今度はもう少し複雑なケースを考えてみましょう。
表意者Aさんが、冗談で相手方Bさんに土地を売る(あげる)と言いました。その後、Bさんがその土地を、事情を知らない第三者Cさんに売ってしまったら…? この場合、元の所有者であるAさんは、Cさんから土地を取り戻せるのでしょうか?
<心裡留保と第三者との関係図>
表意者A →(心裡留保で売却)→ 相手方B →(転売)→ 第三者C
この関係を考えるには、まず「AさんとBさんの間の契約が有効だったのか、無効だったのか」がスタート地点になります。
【ケース1】A・B間の契約が有効だった場合
これは簡単ですね。AさんとBさんの間の契約が有効ということは、Bさんは正当に土地の所有権を取得したことになります。(これは、Bさんが善意無過失だった場合でしたね。)
有効に所有権を得たBさんが、その土地をCさんに売却するのは、もちろん自由です。
したがって、Cさんは有効に土地の所有権を取得します。Aさんは、もはやその土地について何も主張できません。
【ケース2】A・B間の契約が無効だった場合(ここが重要!)
問題はこっちです。AさんとBさんの間の契約が無効だった場合。これは、Bさんが悪意または有過失だったケースですね。
A・B間の契約が無効ということは、本来、土地の所有権はBさんに移転していません。まだAさんのものです。
それなのに、Bさんが勝手にその土地を第三者Cさんに売ってしまった…。さあ、どうなるでしょう?
本来なら、権利のないBさんから買ったCさんも権利を取得できないはず…と思いませんか?
ところが、民法はここでもう一つルールを用意しています。
(心裡留保)
第九十三条 …(第1項は省略)…
2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
これはどういう意味かというと…
A・B間の契約が無効(=第1項ただし書の場合)であっても、その無効を、善意の第三者Cさんに対しては主張できない(対抗できない)、ということです。
- 善意の第三者:A・B間の契約がAさんの心裡留保(冗談)によるもので無効だった、という事情を知らない第三者Cさんのこと。 (ここでの「善意」は、「無過失」までは要求されません。単に事情を知らなければOKです。)
- 対抗できない:AさんはCさんに対して、「あの契約は無効だったんだから、土地を返して!」と主張できない、という意味です。(これも前回の記事でやりましたね!)
つまり、たとえA・B間の契約が無効だったとしても、Cさんが善意(事情を知らない)であれば、Cさんが保護され、土地の所有権を確定的に取得できるんです! Aさんは土地を取り戻せません。

元はAさんの土地なのに、取り返せないの!?って思いますよね。でも、これには理由があるんです。
なぜ善意の第三者が保護されるの?
なぜ、元の所有者Aさんよりも、事情を知らなかった第三者Cさんの方が保護されるのでしょうか?
これには大きく二つの理由があります。
- 取引の安全の保護:もし、後から「実はあの契約、無効だったんで!」という理由で、どんどん取引の結果が覆されてしまうと、安心して物を買ったりできなくなってしまいますよね。Cさんのような、事情を知らずに取引を信じた人を保護することで、世の中の取引全体の安全を守ろうとしているんです。
- 原因を作った人の責任:そもそも、こんなややこしい事態になった原因は、最初に冗談で意思表示をしたAさんにありますよね。自分の冗談が原因で権利を失うのは、ある意味、自業自得とも言えます。それに対して、Cさんには何の落ち度もありません(善意なので)。
このような理由から、民法は、心裡留保が無効とされる場合でも、善意の第三者を保護するというルールを設けているのです。
- 心裡留保が無効な場合でも、その無効は善意の第三者には主張できない。
- 逆に言えば、第三者Cさんが悪意(A・B間の契約が無効だと知っていた)場合は、保護されません。この場合は、AさんはCさんに対して無効を主張して、土地を取り戻すことができます。
この「善意の第三者保護」のルールは、心裡留保だけでなく、後で勉強する通謀虚偽表示(つうぼうきょぎひょうじ)でも同じように出てきます。意思表示の分野では非常に重要な考え方なので、しっかり理解しておきましょう!
まとめ
お疲れさまでした! 今回は民法の「心裡留保」について、基本的な意味から当事者間・第三者との関係まで、詳しく見てきました。
心裡留保とは、「冗談や嘘(真意ではないこと)を自覚しながらする意思表示」のことでしたね。
その効果は、相手方の状態によって変わるのがポイントでした。
- 相手方が善意無過失 → 有効(冗談でも契約成立!)
- 相手方が悪意または有過失 → 無効
そして、たとえ当事者間で契約が無効だったとしても、その無効は「善意の第三者」には対抗できない(主張できない)という、第三者保護のルールもありました。
- 心裡留保:内心(真意)と表示が違うことを知りながらする意思表示(冗談など)。
- 原則有効:相手方が善意無過失なら、冗談でも契約は有効になる。
- 例外無効:相手方が悪意または有過失なら、契約は無効になる。
- 善意の第三者保護:当事者間で無効でも、その無効を善意(事情を知らない)の第三者には主張できない。
心裡留保は、意思表示の基本ルールを理解する上でとても大切です。特に、「相手方の状態によって結論が変わる」ことや、「善意の第三者保護」の考え方は、他の論点にも繋がっていきます。

難しく感じるかもしれませんが、具体例や図を思い浮かべながら、「誰が」「どんな状況で」「どうなるのか」を一つひとつ整理していけば、必ず理解できます!宅建試験合格に向けて、これからも一緒に頑張っていきましょうね!