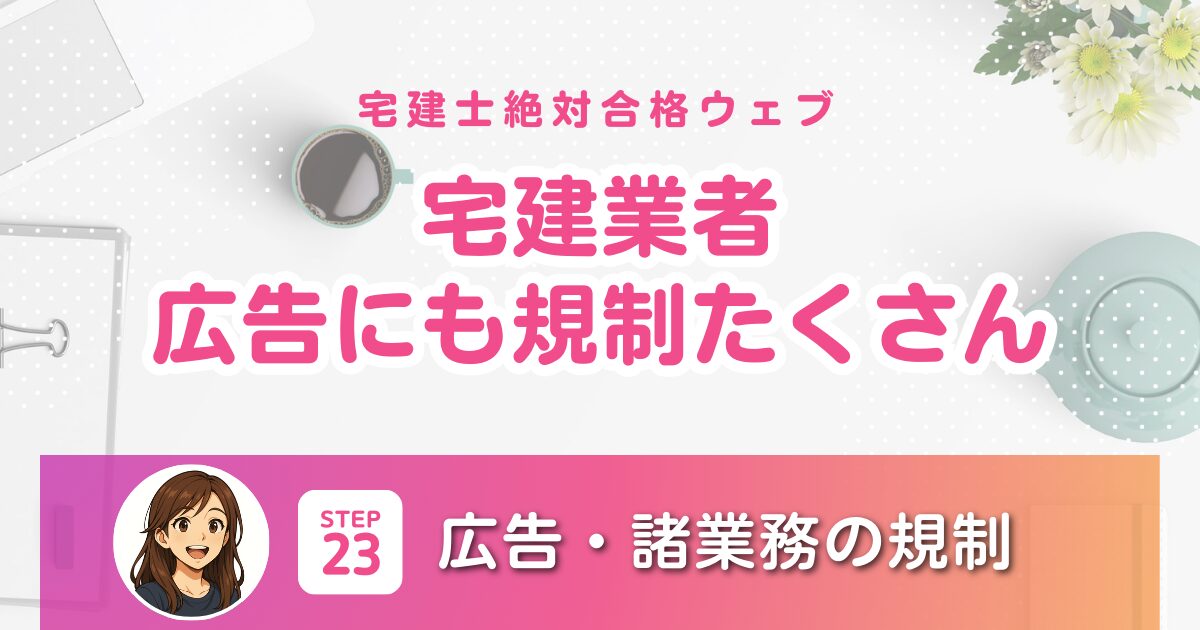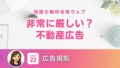前回の記事で、誇大広告の禁止や広告開始時期の制限など、広告に関するルールを学びましたよね。「これで広告はバッチリ!」と思っている方もいるかもしれません。でも、宅建業者が守らなければならないルールは、広告だけじゃないんです!
例えば、「業務上知り得た秘密は漏らしちゃダメ!」という守秘義務。「法律で決まった以上の報酬を要求しちゃダメ!」という報酬の制限。「将来、この土地は絶対に値上がりしますよ!」なんて無責任なことを言っちゃダメ!という断定的判断の提供禁止。さらには、「手付金が足りない? じゃあウチが貸してあげますよ!」といった手付に関する禁止行為など…。
こういったルールって、一つ一つは「まあ、当たり前だよね」と思うようなものが多いかもしれません。でも、意外と「え、これも違反になるの?」とか「例外ってどんな時だっけ?」と、細かい部分で迷うこともありますよね。試験では、まさにそういった「地味だけど重要」なポイントが問われることも少なくないんです!
この記事では、まず「広告に関する規制」の重要ポイントをサクッとおさらいしつつ、広告に関連する補足ルールとして「供託所に関する説明義務」や「ローン金利(アドオン方式)の表示ルール」にも触れます。そして後半では、広告以外の業務において宅建業者が遵守すべき「その他業務上の規制」(守秘義務、報酬、断定的判断、手付関連など)を一つひとつ丁寧に解説していきます。

宅建業法における「やってはいけないことリスト」がほぼ網羅できます! 試験対策はもちろん、将来、宅建業者として働く上でのコンプライアンス意識を高めることにも繋がりますよ。
<この記事でわかること>
- 広告規制の重要ポイント(誇大広告、取引態様、開始時期)のおさらい
- 契約前に行う「供託所に関する説明」とは?
- ローン金利の「アドオン方式」表示がなぜ注意必要なのか?
- 宅建業者の「守秘義務」の内容と例外
- 業務上の禁止事項(高額報酬要求、断定的判断、手付貸付、手付解除妨害など)
【復習&補足】不動産広告のキホン!5つの重要ルールをおさらい
まずは、前回の内容の復習も兼ねて、広告に関する規制のキーポイントを再確認しましょう! 加えて、広告に関連する重要な説明義務や表示ルールも見ていきます。
① 誇大広告等の禁止(宅建業法第32条)
これは基本中の基本でしたね!
- 著しく事実に相違する表示(ウソ)
- 実際よりも著しく優良・有利だと誤認させる表示(大げさ・紛らわしい)
これらは絶対にNGです。物件の内容(所在、規模、環境、利用制限など)や取引条件(価格、ローンあっせんなど)について、正直に、分かりやすく表示することが求められます。おとり広告や虚偽広告も、もちろん違反です。

違反となるかどうかは「一般の消費者が誤解するかどうか」が基準になります。プロの目線ではなく、消費者の目線で考えることが大切ですね!
② 取引態様の明示(宅建業法第34条)
広告を出すとき、そしてお客さんから注文を受けたときには、宅建業者は自分が取引にどう関わるのか、その立場(取引態様)をはっきり示さなければなりません。
- 売主: 自分が物件の所有者
- 代理: 売主や貸主の代理人
- 媒介(仲介): 売主(貸主)と買主(借主)の間を取り持つ
これを明示しないと、消費者は誰と交渉するのか、仲介手数料はかかるのかなどが分からず混乱してしまいます。
③ 広告開始時期の制限(宅建業法第33条)
まだ完成していない宅地や建物(未完成物件)の広告は、フライングしてはいけません。
- 造成工事完了前の宅地
- 建築工事完了前の建物
これらの広告は、開発許可や建築確認など、工事に必要な法令上の許可や確認等の処分があった後でなければ開始できません。許可申請中の段階での広告は違反になります。
④ 供託所に関する説明義務(宅建業法第35条など)
宅建業者は、お客さんと契約を結ぶ前に、万が一のトラブルに備えてお金を預けている場所(供託所)などについて説明する義務があります。これは、主に重要事項説明(35条書面)の中で行われます。
<チェック>供託所に関する説明義務
- いつ? 契約が成立するまでの間(通常は重要事項説明時)
- 何を?
- 営業保証金を供託している場合: その営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所の名称と所在地
- 保証協会に加入している(社員である)場合: 社員である旨、その保証協会の名称、住所、事務所の所在地
- なぜ? もし宅建業者との取引で損害を受けた場合、お客さんは営業保証金や保証協会の弁済業務保証金から弁済を受けられる可能性があります。その手続きに必要な情報を提供するためです。

「もしウチとの取引で何かあって損害を受けたら、ここから補償を受けられる可能性がありますよ」ということを、事前にちゃんと伝えておく、ということですね!
⑤ アドオン方式のみの利率表示の禁止(景品表示法関連・宅建業法第32条解釈)
住宅ローンなどの金利を表示する際にも注意が必要です。特に「アドオン方式」という表示方法だけを使うのは、原則としてNGです。
アドオン方式とは?
借入金の元金全体に対して、返済期間全体の利息総額をあらかじめ計算し、それを元金に上乗せした合計額を、返済回数で割って毎月の返済額を算出する方法です。
この方法だと、見かけ上の利率(アドオン利率)は、実際に負担する利率(実質年率)よりも低く見えてしまうんです。例えば、アドオン利率5%と表示されていても、実質年率に換算すると約9%近くになることも…!
これは消費者に「著しく有利であると誤認させる」表示(誇大広告)につながる恐れがあるため、宅建業法だけでなく、景品表示法に基づく公正競争規約などでも規制されています。
<チェック>ローン金利表示のルール
- アドオン方式のみで利率を表示することは原則禁止。
- アドオン方式で表示する場合は、それがアドオン方式であることを明示した上で、必ず実質年率も併記しなければならない。
広告規制違反は「表示した時点」で成立!
これらの広告に関する規制は、違反となる表示をした時点で直ちに違法となります。実際にその広告を見て契約した人がいなくても、損害が発生していなくても、違反は成立します。媒体もチラシ、ネット、ラジオなど一切問いません。注意が必要ですね!
広告以外も要注意!宅建業者が守るべき5つのルール
さて、ここからは広告以外の場面で宅建業者が守らなければならない、主な業務上の規制を見ていきましょう。「当たり前」と思えるルールも多いですが、改めて確認しておきましょう。
① 秘密を守る義務(守秘義務)(宅建業法第45条)
宅建業者は、その業務を行う上で、お客さんのプライベートな情報(年収、家族構成、売却理由など)を知る機会がたくさんあります。これらの業務上知り得た秘密を、正当な理由なく他の人に漏らしてはいけません。
守秘義務のポイント
- 対象: 業務に関して知り得た秘密
- 義務者: 宅建業者(およびその従業者)
- 期間: 業務に従事しなくなった後(廃業や退職後)も、引き続き義務を負う!
- 例外(漏らしてもOKな場合):
- 本人の承諾がある場合
- 裁判の証人として証言するなど、法令に基づく場合
- 人の生命・身体・財産の保護のために必要で、本人の同意を得るのが困難な場合など、正当な理由がある場合

お客さんの信頼に関わる、とっても基本的なルールですね。辞めた後も秘密は守り続けないといけない、という点がポイントです!
② 不当な高額報酬要求の禁止(宅建業法第46条、第47条の2)
宅建業者が受け取れる報酬(仲介手数料など)の額には、法律で上限が定められています。この上限を超える報酬を受け取ることはもちろん、要求すること自体が禁止されています。
高額報酬要求の禁止
- 法定の上限額を超える報酬を要求すること(たとえ実際には受け取らなくても、要求した時点で違反!)
- もちろん、上限を超えて受領することも違反。
「ちょっと色つけてよ」なんてお客さんに要求するのは絶対にダメです!
③ 断定的判断を提供する行為の禁止(宅建業法第47条)
不動産取引では、将来の価格変動や周辺環境の変化など、不確実な要素がたくさんあります。それにもかかわらず、宅建業者がお客さんに対して、将来のことについて誤解させるような断定的な判断を提供することは禁止されています。
<NG>断定的判断の提供禁止
- 対象:将来の値上がり、環境の変化、交通の利便性など、不確実な事項
- 禁止行為:誤解させるような断定的な判断を提供すること
- 例:「この物件は絶対に値上がりしますよ!」
- 例:「ここに新しい駅ができる計画があるので、間違いなく便利になります!」
- 例:「この周辺は静かなので、将来もずっと変わりませんよ!」

期待を持たせたい気持ちは分かりますが、不確実なことを断定的に言うのはお客さんを惑わせるだけ。客観的な情報に基づいて説明することが大切ですね。
④ 手付の貸付け・信用の供与による契約誘引の禁止(宅建業法第47条)
手付金は、契約の証拠金や解約手付としての重要な意味を持ちます。しかし、中には手付金を用意できないお客さんに対して、「契約を早く結ばせたい」という理由から、宅建業者が手付金を援助するような行為をしてしまうケースがあります。これは禁止されています。
<NG>手付に関する契約誘引の禁止
- 手付金を貸し付けること
- 手付金を分割払いにしたり、後払いにしたりすること(=信用の供与)
- これらの行為によって、契約の締結を誘引すること(=「手付金はこっちで何とかするから契約しましょうよ!」と持ちかけること)
手付金が用意できないなら、本来は契約すべきではないかもしれません。それを業者が肩代わりして無理に契約させるのは、後々のトラブルの元になるため禁止されています。
⑤ 正当な理由なく手付解除を拒む・妨げる行為の禁止(宅建業法第47条)
解約手付のルールでは、買主は手付金を放棄し、売主は手付金を倍返しすることで、相手方が履行に着手するまでは契約を解除できる、と学びましたね。
この手付解除の権利を、宅建業者が不当に邪魔してはいけません。
<NG>手付解除の妨害禁止
- 相手方(お客さん)が手付放棄(または売主が業者なら手付倍返し)によって契約を解除しようとしているのに、正当な理由なく、その解除を拒んだり、妨げたりすること。
- 例:「いやいや、今さら解除なんて困りますよ!」と理由なくごねる。
- 例:手付金の返還手続きをわざと遅らせる。
ただし、「正当な理由」があれば、解除を拒むことはできます。
<OK>解除を拒める「正当な理由」がある場合
- 相手方(宅建業者にとっての契約の相手、つまり買主や売主)が、すでに履行に着手している場合。
- 例:買主が中間金を支払った後で、売主(業者)が手付倍返しで解除しようとする → 買主は拒否できる(業者は解除できない)。
- 例:売主(業者)が物件の引渡し準備(リフォーム等)を始めた後で、買主が手付放棄で解除しようとする → 業者は拒否できる(買主は解除できない可能性がある)。

手付解除は契約当事者の正当な権利。それを不当に妨害しちゃダメ、ということですね。ただし、「履行の着手」があったかどうかは重要なポイントになります。
まとめ
お疲れ様でした! 今回は、宅建業法の「広告に関する規制」の復習・補足と、「その他業務上の規制」について、たくさんのルールを見てきました。
広告規制では、誇大広告の禁止、取引態様の明示、広告開始時期の制限に加え、契約前の供託所に関する説明や、誤解を招きやすいローン金利(アドオン方式)の表示にも注意が必要でしたね。
そして、広告以外の業務上の規制では、
- 守秘義務(退職後も続く!)
- 不当な高額報酬要求の禁止(要求だけでもNG!)
- 断定的判断の提供禁止(「絶対」「間違いなく」は禁句!)
- 手付の貸付け・信用の供与による契約誘引の禁止
- 正当な理由なき手付解除の妨害禁止
といった、宅建業者として誠実な業務を行う上で守るべき基本的なルールを確認しました。
これらの規制は、どれも消費者保護や公正な不動産取引の実現のために設けられています。試験対策としてはもちろんですが、将来宅建士として活躍するためにも、しっかりと身につけておきたい知識ばかりです。

これで、宅建業法の「規制」に関する分野はかなり網羅できたのではないでしょうか! 細かいルールも多いですが、一つ一つ理由を考えながら覚えると、忘れにくくなりますよ!