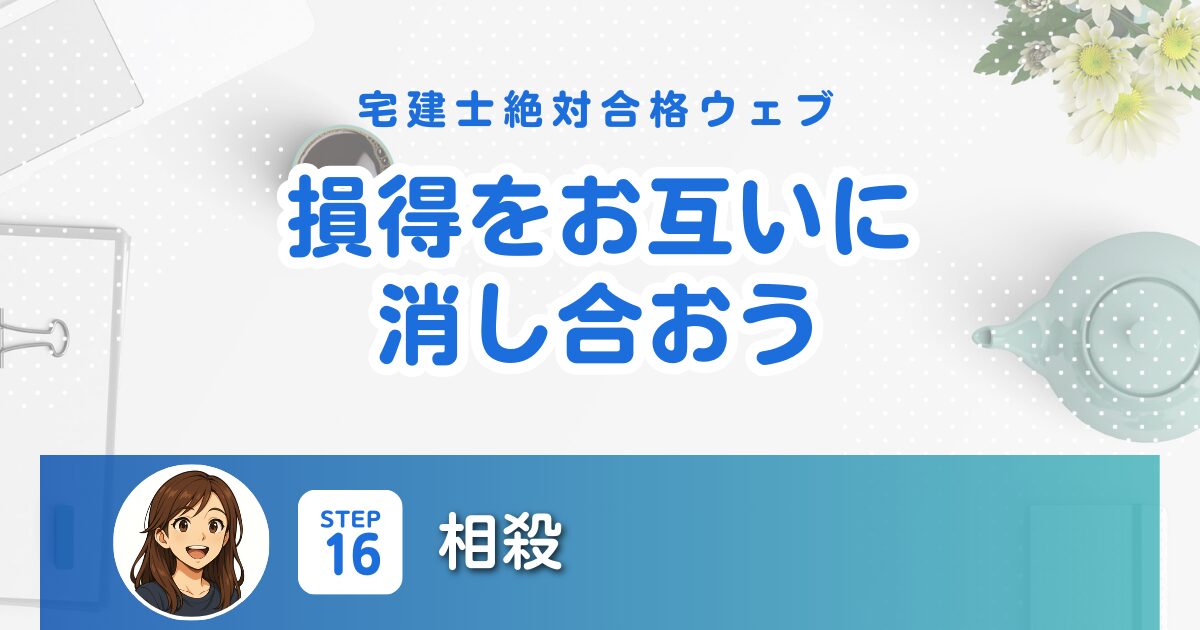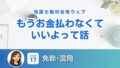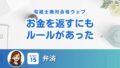民法の債権分野には、いろいろな専門用語が出てきますよね。「相殺(そうさい)」もその一つ。「そうさい」って聞くと、なんとなく「帳消しにする」みたいなイメージは湧くけど、具体的にどんなルールで、どんな場合にできて、どんな場合にできないのかって、ちゃんと説明できますか?「自働債権」?「受働債権」?って言われると、もうお手上げ!なんて方もいらっしゃるかもしれません。

今回は、そんな「相殺」の仕組みについて、基本からしっかり、そして分かりやすく解説していきますね!
相殺は、お互いに金銭の貸し借りがある場合などに、手続きを簡単に済ませられる便利な制度です。でも、どんな場合でも使えるわけではなくて、ちゃんとルールが決まっているんです。宅建試験でも、相殺できる要件(相殺適状)や、相殺が禁止されるケースなどが問われることがありますので、正確に理解しておくことが大切ですよ。
この記事では、相殺の基本的な考え方から、相殺が認められるための条件(相殺適状)、そして「こんな場合は相殺できません!」という禁止ケースについて、具体例や図を使いながら丁寧に解説していきます。この記事を読めば、相殺に関する疑問点が解消され、スッキリした気持ちで学習を進められるようになるはずです!
この記事でわかること
- 相殺の基本的な意味と仕組み(自働債権・受働債権)について理解できる
- 相殺ができるための条件(相殺適状)がわかる
- 相殺が禁止・制限される具体的なケースのポイントが整理できる
- 同時履行の抗弁権や不法行為、差押えと相殺の関係との違いがわかる
- 宅建試験で押さえておくべき相殺の重要ポイントが明確になる
相殺の基本!自働債権・受働債権と相殺できる条件(相殺適状)
まずは、「相殺」がどういう制度なのか、基本的なところから見ていきましょう! 相殺を理解することが、宅建民法攻略の第一歩ですよ。

ここをしっかり押さえるだけで、グッと理解が深まります!
相殺ってなに? – お互いの「貸し借り」をチャラにする仕組み
相殺とは、二人の人がお互いに同じ種類の債権(例えば、金銭債権どうし)を持っている場合に、その債権と債務を、対当額(同じ金額の範囲)で消滅させる意思表示のことです(民法第505条)。
簡単に言うと、お互いの「貸し借り」を帳消しにして、決済を簡単に済ませるための制度ですね。銀行振込の手数料とか、現金のやり取りの手間とかを考えると、とても合理的な仕組みと言えます。
例:
AさんがBさんに100万円貸している(AはBに対する100万円の貸金債権を持つ)。
同時に、BさんもAさんに80万円貸している(BはAに対する80万円の貸金債権を持つ)。
この場合、AさんかBさんのどちらか一方が「相殺します!」と相手に意思表示をすれば、お互いの債権が対当額である80万円の範囲で消滅します。結果として、AさんがBさんに対して持つ債権だけが20万円分残る、という形になります。わざわざAさんがBさんに100万円払い、BさんがAさんに80万円払う、なんて手間をかける必要がないわけです。
<相殺の基本的な関係図>
相殺前:
- A → B (100万円の債権)
- B → A (80万円の債権)
Aが相殺の意思表示をした場合:
- A → B (100万円 – 80万円 = 20万円の債権)
- B → A (80万円 – 80万円 = 債権消滅)
このように、相殺は一方からの意思表示だけで効力が発生する「形成権」と呼ばれる権利の一種です。相手の同意は必要ありません。ただし、意思表示には条件や期限を付けることはできません。
「自働債権」と「受働債権」ってどっち?
相殺を理解する上で、ちょっと専門用語が出てきます。でも、ここでしっかり区別しておけば後が楽ですよ!
- 自働債権(じどうさいけん): 相殺をしようとする側が持っている債権のこと。(上の例でAさんが相殺する場合、AさんがBさんに対して持っている100万円の貸金債権)
- 受働債権(じゅどうさいけん): 相殺によって消滅させられる相手側の債権のこと。(上の例でAさんが相殺する場合、BさんがAさんに対して持っている80万円の貸金債権)
<ポイント>
「自」分から「働」きかけて相殺に使うのが「自働」債権、
相殺を「受」け身でされるのが「受働」債権、
と覚えると分かりやすいかもしれませんね!どちらの債権を指しているのか、しっかり区別できるようにしましょう。これは相殺のルールを理解する上で非常に重要です。
相殺できるのはどんな時?「相殺適状」の4つの条件
では、お互いに債権を持っていれば、いつでも自由に相殺できるのでしょうか? 実はそうではなく、相殺が有効に行えるためには、一定の条件を満たしている必要があります。この、相殺ができる状態のことを「相殺適状(そうさいてきじょう)」と言います。
相殺適状といえるためには、主に以下の4つの条件が必要です。一つずつ確認していきましょう。
条件①:お互いに債権を持っていること(対立)
まず大前提として、二人の当事者がお互いに債権を持っていることが必要です。AさんがBさんに債権を持っているけど、BさんはAさんに何も債権を持っていない、という状況では当然、相殺はできませんね。
条件②:債権の目的が同じ種類であること(同種性)
相殺できるのは、お互いの債権の目的(給付の内容)が同じ種類である場合に限られます。
実務上、そして宅建試験で問題になるのは、ほとんどが金銭債権どうしの相殺です。
<OKな例>
- 金銭債権 ⇔ 金銭債権 → 相殺OK! (例:貸したお金と売買代金)
<NGな例>
- 金銭債権 ⇔ 特定物の引渡請求権(例:車の引渡し) → 相殺NG!
- 物の引渡請求権 ⇔ 物の引渡請求権(種類が違う物、例えば米10kgと鉄骨5トン) → 相殺NG!
お金を返す義務と、特定の車を引き渡す義務を帳消しにすることはできません。もし何でもかんでも相殺できるとなると、契約で約束した給付の内容が変わってしまいますからね。
条件③:相殺する側の債権(自働債権)が弁済期にあること
ここが少しややこしいですが、重要なポイントです!
相殺をしようとする側の債権(自働債権)が、弁済期(支払い期限)を迎えていることが必要です。
自分がまだ相手に「払ってください」と請求できない状態の債権(期限が来ていない債権)を使って、相手が自分に払うべきお金(相手の債務)だけを一方的に消すことはできない、ということですね。相手からすれば、「まだ払わなくていいはずなのに、勝手に消された!」となってしまいます。
<超重要!受働債権との違い>
一方で、相殺をされる側の債権(受働債権)は、弁済期にある必要はありません。
つまり、相手が自分に対して持っている債権の支払期限がまだ先であっても、自分が相手に対して持っている債権(自働債権)の弁済期が来ていれば、相殺することができるんです!
なぜなら、期限が来ていない債務を先に弁済することは、債務者にとっては「期限の利益を放棄する」ことになり、基本的には損ではありません(むしろ有利な場合もある)。相殺をするということは、自分の債務(相手から見れば受働債権)を期限前に履行するのと同じ効果になるため、これは認められているんです。
まとめると:
- 自働債権: 弁済期 到来が必要
- 受働債権: 弁済期 到来は不要
この違いは宅建試験で頻出なので、絶対に覚えてくださいね!
条件④:相殺が禁止されていないこと(性質・法律・特約)
最後に、その債権の性質や法律の規定、当事者間の特約によって相殺が禁止されていないことが必要です。
例えば、「差押えが禁止されている債権」(給料の一部など)を自働債権として相殺することは、その趣旨に反するため制限されることがあります。また、後で詳しく説明する「相殺できない場合」に該当するケースも、この条件に関わってきます。
以上の①〜④の条件がすべて揃って初めて「相殺適状」となり、相殺の意思表示によって債権を消滅させることができる、というわけです。
【ポイント】時効で消えた債権でも相殺できる場合がある!
ここで、ちょっと面白い、でも試験にも出やすいルールをご紹介します。
もし、自分の持っている債権(自働債権)が時効によって消滅してしまった後でも、その時効が完成する「前」に相手の債権(受働債権)と相殺適状になっていた場合には、なんと、時効消滅後であっても相殺することができるんです!(民法第508条)
えっ、時効で消えたのになんで相殺できるの?
これは、「時効が完成する前に、いつでも相殺できる状態だったんだから、その時点で相殺計算をして清算されたものと同じように扱おう」という考え方に基づいています。相殺に対する当事者の合理的な期待を保護するためのルールなんですね。
条件は、あくまで「時効完成前に相殺適状であったこと」です。時効完成後に相殺適状になったとしても、このルールは適用されません。ここをしっかり押さえておきましょう!
これはNG!相殺ができない4つのケースと具体例
さて、相殺適状の条件を満たしていても、「こういう場合は相殺しちゃダメですよ!」と法律で禁止・制限されているケースがあります。これらは宅建試験でも狙われやすい重要ポイントです。主なものを4つ、具体例と一緒に見ていきましょう。

うっかり間違えやすいところなので、注意して見ていきましょう!
ケース①:相手が「同時履行の抗弁権」を持っている場合
まず、相殺をしようとする相手方が、相殺によって消滅させられる債権(受働債権)について「同時履行の抗弁権(どうじりこうのこうべんけん)」を持っている場合は、原則としてその債権を受働債権として相殺することはできません。
同時履行の抗弁権とは、双務契約(売買契約など)において、相手が債務を履行するまで、自分も債務の履行を拒むことができる権利でしたね。「あなたがやってくれるまで、私もやりませんよ!」と主張できる、公平性を保つための大切な権利です。
具体例:
1. AがBに100万円貸している(A→B 貸金債権)。
2. その後、AがBから絵画を100万円で買う契約をした(A→B 絵画引渡請求権、B→A 代金支払請求権)。絵画の引渡しと代金の支払いは同時履行の関係にあります。
<同時履行の抗弁権と相殺の関係図>
状況:
- A → B (100万円の貸金債権: 自働債権候補①)
- B → A (100万円の代金債権: 受働債権候補①、Aは絵画引渡請求権に対応する同時履行の抗弁権を持つ)
- A → B (絵画引渡請求権: 受働債権候補②、Bは代金支払請求権に対応する同時履行の抗弁権を持つ)
- B → A (100万円の代金債権: 自働債権候補②)
なぜ受働債権に同時履行の抗弁権があると相殺できないの?
上の例で、もしBさんが自分の持っている絵画の代金債権(自働債権②)を使って、Aさんに対する貸金債務(元々はA→Bの貸金債権で、Bから見れば相殺される債務、つまり受働債権①)と相殺しようとしたらどうでしょうか?
これはできません。
なぜなら、Aさんは「Bさんが絵画を引き渡してくれるまで、代金は払いません!」という同時履行の抗弁権を持っています。もしBさんからの相殺を認めてしまうと、Bさんは代金を受け取ったのと同じ状態になりながら、絵画の引渡しを拒むことができてしまいます。そうなると、Aさんが持っていた同時履行の抗弁権という担保的な機能(代金と引き換えに確実に絵画をもらう権利)が一方的に奪われてしまい、Aさんにとって著しく不利だからです。
<NG>
受働債権に同時履行の抗弁権が付いている場合、その債権を(受働債権として)相殺することはできない!
逆に、自働債権に抗弁権があっても相殺できるのはなぜ?
では逆に、Aさんが自分の持っている貸金債権(自働債権①)を使って、Bさんに対する絵画の代金支払債務(受働債権①)と相殺しようとした場合はどうでしょうか?
これはできます。
Aさんが相殺するということは、Aさん自身が「絵画の引渡しを受ける前に代金を支払いますよ」と、自ら同時履行の抗弁権を放棄するのと同じ意味合いになります。自分が持っている抗弁権を使わない(=自分に不利になる)選択をする分には構わない、という考え方ですね。相手方Bさんにとっては、代金を確実に回収できるので不利益はありません。
<OK>
自働債権に同時履行の抗弁権が付いていても、(その抗弁権を放棄する形で)相殺することはできる!
この「受働債権についているか」「自働債権についているか」で結論が変わる点、少しややこしいですが、どちらが不利益を被るかを考えると理解しやすいですよ!しっかり区別してくださいね。
ケース②:当事者間で「相殺禁止特約」を結んでいる場合
これは比較的シンプルですね。契約を結ぶ際に、当事者間で「この債権については相殺しちゃダメだよ!」という特約(相殺禁止特約)を結んでいた場合は、原則としてその債権を自働債権として相殺することはできません(民法第505条2項)。契約自由の原則から、当事者の意思が尊重されるわけです。
例:賃貸借契約で、「賃借人は、敷金返還請求権をもって賃料支払債務と相殺することはできない」という特約がある場合などです。
ただし、この相殺禁止特約は、その存在を知らない(善意)かつ知らないことに過失がない(無過失)の第三者には対抗できません。例えば、相殺禁止特約が付いた債権がAからBに譲渡され、Bが特約について善意無過失だった場合、さらにBから債権を譲り受けたC(特約について悪意)がいたとします。この場合、Cが元の債務者に対して、その債権を自働債権として相殺しようとしても、債務者は相殺禁止特約を主張して相殺を拒むことはできません。(※少し複雑ですが、善意無過失のBを保護する必要があるため、その後のCとの関係でも特約を主張できなくなる、というルールです。)
ケース③:【重要】不法行為の被害者の債権を受け身(受働債権)にする相殺
不法行為(交通事故の損害賠償、暴行による治療費など)に基づいて発生した債権を受働債権とする相殺は、原則として禁止されています(民法第509条)。
特に、以下の2つのケースでは、加害者側からの相殺は絶対に許されません。
- 悪意による不法行為に基づく損害賠償債権を受働債権とする相殺
- 人の生命または身体の侵害による損害賠償債権を受働債権とする相殺
<不法行為と相殺の関係イメージ>
加害者B → 被害者A (貸金債権など: Bの自働債権)
被害者A → 加害者B (不法行為に基づく損害賠償請求権: Bから見て受働債権)
この場合に、加害者Bから「貸した金と賠償金はこれで相殺だ!」と主張することは原則NGということです。
なぜ加害者から相殺できないの?(特に生命・身体侵害の場合)
なぜ加害者からの相殺が禁止されているのでしょうか? もしこれが許されるとしたら、大変なことになります。
例えば、AさんがBさんにお金を貸していたとします。Bさんが返してくれないことに腹を立てたAさんが、Bさんを殴ってケガをさせてしまった場合、AさんはBさんに対して治療費などの損害賠償債務を負います。このとき、もし相殺が自由にできるとしたら、Aさんは「貸した金と治療費はこれでチャラ(相殺)だ!」と主張できてしまいます。
こんなことが許されたら、暴力によって債権を取り立てることを認めるようなものですよね。それは社会正義に反します。
また、交通事故などで被害者が治療費や生活費に困っている状況で、加害者が持っている別の債権(例えば昔貸したお金)を持ち出してきて「賠償金と相殺するから払わない」と言えてしまうと、被害者は現実にお金を受け取れず、非常に困ってしまいます。
このように、不法行為の被害者を現実に救済し、保護する必要性が高いこと、そして、不法行為を誘発させないという目的から、加害者側からの一方的な相殺は禁止されているのです。特に、人の生命や身体という最も重要な利益が侵害された場合には、加害者にきちんと金銭で賠償させる必要性が極めて高いと考えられています。
被害者からの相殺はOK!
ただし、注意点があります。このルールはあくまで加害者側からの相殺を禁止するものです。
被害者側から、「加害者に対して持っている別の債権(例えば、以前加害者に商品を売った代金債権など)と、加害者に支払ってもらうべき損害賠償金を相殺してください!」と主張することは認められています。
被害者が自分の判断で相殺を選ぶ分には、被害者保護の趣旨に反しないからです。
【まとめ】不法行為と相殺
・加害者からの相殺(不法行為債権を受働債権とする) → 原則NG(特に悪意・生命身体侵害の場合)
・被害者からの相殺(不法行為債権を自働債権とする) → OK
ケース④:差押えられた債権(受働債権)との相殺
最後に、差押えと相殺の関係です。これも少し複雑ですが、仕組みを理解しましょう。
ある債権(例えば、AさんのBさんに対する貸金債権)が、第三者である債権者Cさんによって差押えられた場合、その差押えられた債権(Bさんから見ればAさんへの支払債務)を受働債権とする相殺は、一定の制限を受けます。
具体的には、差押えの効力が発生した「後」に取得した債権を自働債権として、差押えられた債権(受働債権)と相殺することはできません(民法第511条)。
例:
1. AがBに100万円貸している(A→B 貸金債権)。
2. Aの債権者Cが、AのBに対するこの貸金債権を差し押さえた。
3. その差押えの後に、BがAにお金を貸した(B→A 新たな貸金債権を取得)。
この場合、Bはこの差押え後に取得した貸金債権(自働債権)を使って、Cに差し押さえられたAへの支払債務(受働債権)と相殺することはできません。
なぜなら、もし差押え後の相殺が自由にできてしまうと、差押えをした債権者Cさんの期待(Bさんから直接取り立てられるだろうという期待)が害されてしまうからです。差押えという法的な手続きの効果を無意味にしないためのルールですね。
<ポイント:差押えと相殺の優劣>
差押えと相殺のどちらが優先されるかは、原則として、相殺しようとする側(上の例ではBさん)が自働債権を取得したタイミングと、差押えの効力が発生したタイミングの前後で決まります。
- 自働債権の取得が、差押え効力発生よりも「前」 → 相殺OK (差押え前から相殺できる状態にあった期待を保護)
- 自働債権の取得が、差押え効力発生よりも「後」 → 相殺NG (差押え債権者Cの期待を保護)
ただし、自働債権の取得が差押え後であっても、その発生原因(例えば契約)が差押え前に既に存在していた場合は、例外的に相殺が認められることもあります。少し細かい論点ですが、まずは上記の原則をしっかり押さえましょう。
まとめ
今回は、民法の「相殺」について、基本的な意味から相殺適状の要件、そして相殺ができないケースまで、詳しく解説しました。
自働債権と受働債権の区別や、相殺適状の条件、禁止されるケースなど、しっかり整理できましたでしょうか?宅建の権利関係は覚えることが多いですが、一つ一つクリアしていきましょう!
相殺は、当事者間の決済を簡便にするための合理的な制度ですが、無制限に認められるわけではなく、相手方の利益(特に同時履行の抗弁権)や第三者の権利(差押え債権者など)、そして社会的要請(不法行為被害者の保護)といった観点から、様々な制限が設けられています。
特に、同時履行の抗弁権が付着している場合や、不法行為債権、差押えられた債権との相殺については、「どちらから相殺しようとしているか(自働債権か受働債権か)」や「いつ債権を取得したか」といった点が重要になり、試験でもよく問われるポイントなので、それぞれの理由と結論をセットで理解しておくことが合格への近道です。
この記事のポイントまとめ
- 相殺: お互いの同種の債権を対当額で消滅させる一方的な意思表示。
- 自働債権: 相殺する側が持つ債権。受働債権: 相殺される側の債権。
- 相殺適状の要件: ①債権対立、②同種性、③自働債権の弁済期到来(受働債権は不要)、④相殺禁止でないこと。
- 時効消滅後でも相殺可能: 時効完成前に相殺適状であればOK(民法508条)。
- 相殺できない主なケース:
- 受働債権に同時履行の抗弁権が付着している場合(自働債権ならOK)。
- 相殺禁止特約がある場合(善意無過失の第三者には対抗不可)。
- 不法行為に基づく損害賠償債権を受働債権とする場合(特に悪意・生命身体侵害は加害者からの相殺は絶対不可。被害者からはOK)。
- 差押えられた債権(受働債権)に対し、差押え後に取得した自働債権で相殺する場合(差押え前取得ならOK)。
相殺のルールは、具体的な事例を思い浮かべながら、「誰が誰に対してどんな権利を持っていて、誰が何を主張できて、誰が何を主張できないのか?」を図に書いて整理すると、関係性が掴みやすくなり、理解が深まりますよ。複雑に見えるルールも、その理由付け(なぜそうなっているのか?)と一緒に覚えることで、記憶に定着しやすくなります。

建試験の民法は範囲が広いですが、相殺のような頻出テーマを一つずつ確実にマスターしていくことが、合格への着実な一歩となります。今回の記事が、あなたの学習の一助となれば嬉しいです。