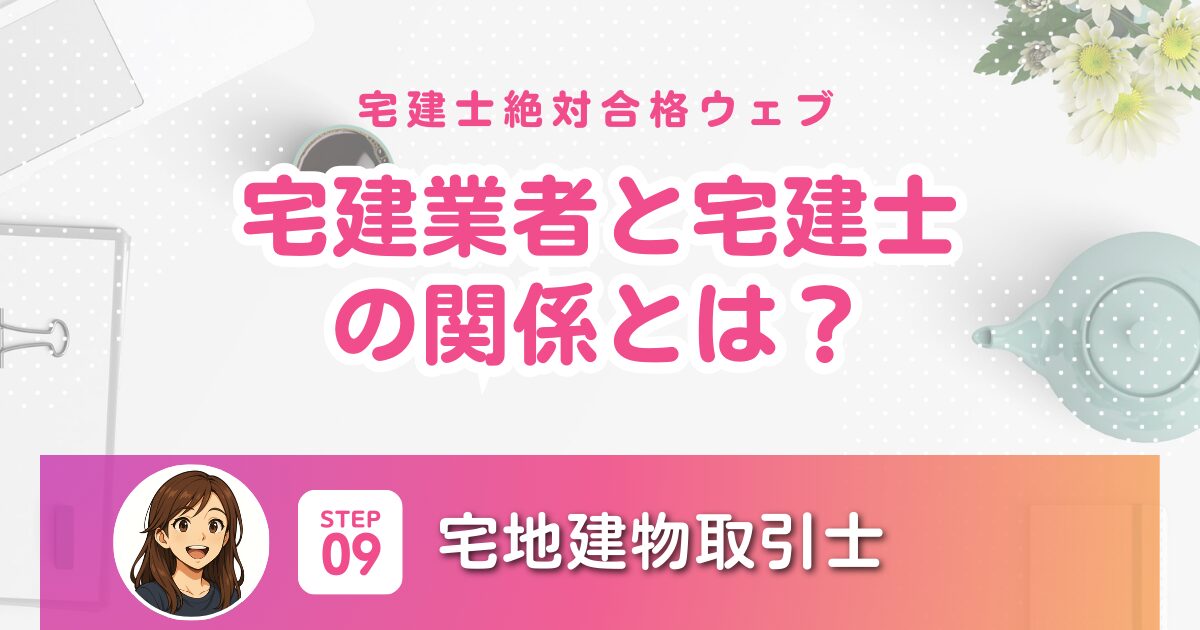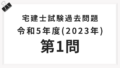宅建試験、合格目指して頑張っている皆さん!あるいは、これから目指そうかなと考えている皆さん!「宅建試験に合格したら、すぐに『宅地建物取引士(宅建士)』としてバリバリ働けるの?」って思っていませんか?実は、試験合格はスタートラインで、その後にいくつかのステップを踏んで、初めて正式な「宅建士」になれるんです!
それに、晴れて宅建士になったら、どんなお仕事が待っているのでしょう?宅建士にしかできない特別な業務があるって本当?そして、プロの資格者として守らなければいけないルールや義務、大切な身分証明書である「宅建士証」の手続きなど、知っておくべきことがたくさんあります。
この記事では、そんな「宅地建物取引士」について、資格取得までの流れ、宅建士ならではの業務や設置義務、プロとしての心得、そして日々の業務で欠かせない宅建士証に関する様々な手続きまで、まるっと分かりやすく解説していきます!これを読めば、「宅建士」の全体像がきっと掴めるはずですよ!
この記事でわかること
- 宅建試験合格後、宅建士になるまでの具体的なステップ(登録・士証交付)
- 宅建士だけが行える特別な業務(独占業務)
- 事務所への専任宅建士の設置義務とルール
- 宅建士として守るべき大切な心構え(品格規定)
- 宅建士証の書換え・提出・返納・提示など、必要な手続き
憧れの国家資格!宅建士になるための3ステップ
まずは、どうすれば「宅地建物取引士」になれるのか、その道のりをステップごとに見ていきましょう!試験合格がゴールじゃないんですよ!
Step1: 難関突破!宅地建物取引士資格試験に合格する
全ての始まりは、もちろん「宅地建物取引士資格試験」に合格することです!これがなければ何も始まりません。毎年多くの人が挑戦する人気の国家資格ですが、合格率は例年15%~17%程度と、決して簡単な試験ではありません。しっかり計画を立てて勉強することが大切ですね!

この難関を突破できた時の喜びは、本当に格別ですよね!頑張った自分をたくさん褒めてあげてください!
試験は誰がやってるの?実施機関について
この宅建試験、法律上は都道府県知事が行うことになっています。でも、実際には47都道府県すべてで、知事が国土交通大臣の指定する者、具体的には「一般財団法人 不動産適正取引推進機構」というところに試験の実施に関する事務(試験事務)を委任しています。
だから、私たちが実際に願書を出したり、試験を受けたりするのは、この「不動産適正取引推進機構」が窓口になっているんですね!知事自身が試験問題を作ったり、採点したりしているわけではないんです。
合格は一生モノ!でも不正はダメ絶対!
宅建試験に一度合格すれば、その合格自体は一生有効です!数年後に登録しよう、ということも可能なんですよ。
ただし!もし試験で不正行為(カンニングなど)をして合格したことがバレた場合、合格が取り消されるだけでなく、3年以内の期間を定めて、再受験を禁止されてしまうことがあります。当然ですが、正々堂々、自分の力で合格を勝ち取りましょうね!
Step2: 合格したら終わりじゃない!都道府県知事への「登録」
試験に合格しただけでは、まだ「宅建士」とは名乗れません。次に必要なのが、都道府県知事への「登録」です。この登録を受けて初めて、「宅建士になる資格のある人」として公的に認められるんです。
どこに登録する?受験地の知事へ!
登録は、どの都道府県知事に対して行うのでしょうか?これは、「試験を受けた(合格した)都道府県」の知事に対して行います。
ここ、重要です!例えば、試験は東京都で受けたけど、今は秋田県に住んでいるという場合でも、登録申請は東京都知事に対して行わなければなりません。現住所の知事ではないので注意してくださいね!
登録の有効期間と必要な要件(実務経験 or 講習)
この知事への登録も、一度受ければ一生有効です。失効することはありません。(ただし、後で説明する欠格事由に該当したり、不正な手段で登録したりした場合は、登録が消除されることもあります。)
ただし、誰でもすぐに登録できるわけではなく、以下の要件を満たす必要があります。
- 要件1:宅建試験に合格していること(これは大前提!)
- 要件2:登録の欠格事由に該当しないこと(破産者で復権を得ない者、禁固以上の刑に処せられて5年経たない者など、一定の条件に当てはまらないこと。詳しくは別の記事で解説しましたね!)
- 要件3:以下のいずれかを満たすこと
- 宅地建物の取引に関して2年以上の実務経験があること
- 実務経験が2年未満の場合は、国土交通大臣が指定する「登録実務講習」を修了すること

そうなんです!合格してもすぐに登録できるとは限らないんですね。不動産会社などで2年以上働いた経験があればOKですが、そうでない場合は、指定された講習(有料です!)を受けて、修了証をもらう必要があるんです。
「実務経験」って? 一般的には、宅建業者の下で、顧客への説明、物件調査、契約書の作成補助など、実際の宅地建物取引に関する業務に従事した経験を指します。単なる一般事務や受付業務などは含まれないことが多いです。 「登録実務講習」って? 実務経験がない人向けの講習で、通信講座とスクーリング(数日間の対面講習)を組み合わせて行われることが多いです。修了試験に合格すれば、2年以上の実務経験があるとみなされます。
Step3: これであなたも宅建士!「宅建士証」の交付を受ける
都道府県知事への登録が無事に完了!これでやっと「宅建士」になれた!…と思いきや、実はもう一つステップが残っています。それが、「宅地建物取引士証(宅建士証)」の交付を受けることです。
この宅建士証を持って初めて、宅建士として重要事項の説明などの法定業務を行うことができるようになります。登録だけではまだダメなんですね。
交付前に必要な講習とは?(免除規定あり)
宅建士証の交付を申請する際には、原則として、その交付申請前6ヶ月以内に行われる「法定講習」(都道府県知事が指定する講習)を受講しなければなりません。
この法定講習は、宅建業に関する法令の改正点や、実務上の注意点などを学ぶためのもので、宅建士として業務を行う上で必要な知識をアップデートする目的があります。
ただし、例外があります!
試験に合格した日から1年以内に宅建士証の交付を申請する場合は、この法定講習の受講が免除されるんです!

これは嬉しいですね!合格したてのホヤホヤの知識があれば、改めて講習を受けなくてもOK、ということですね。合格したら早めに登録・交付申請をするメリットの一つです!
宅建士証の有効期間は5年!更新が必要!
無事に宅建士証が交付されました!これで晴れて宅建士として活動できます!
しかし、注意点が一つ。宅建士証には有効期間があり、それは5年間です。
試験合格や登録は一生有効でしたが、宅建士証は5年ごとの更新が必要なんです!更新する際には、再び法定講習を受講する必要があります。(こちらは合格後1年以内という免除規定はありません。)
有効期間のまとめ
- 宅建試験の合格 → 一生有効
- 知事への登録 → 一生有効
- 宅建士証 → 有効期間5年 (要更新!)
宅建士だけの特別な仕事と設置義務、守るべきルール
晴れて宅建士証を手に入れたら、いよいよプロとしての活動が始まります!ここでは、宅建士にしかできない特別な業務や、宅建業者に課せられる設置義務、そして宅建士として守るべき心構えについて見ていきましょう。
これぞプロの仕事!宅建士の「独占業務」とは?
宅建業法では、不動産取引の安全と公正を確保するために、特に重要な特定の業務については、宅建士しか行うことができない「独占業務」として定めています。具体的には以下の3つです!
- 重要事項の説明(35条説明): 契約を結ぶ前に、物件の内容や取引条件に関する重要事項をお客様に説明すること。
- 重要事項説明書(35条書面)への記名: 説明した内容を記載した書面に、説明者として記名(※)すること。
- 契約書(37条書面)への記名: 契約が成立した後に交付する契約内容を記載した書面に、宅建士として記名(※)すること。
(※ 現在は法改正により、記名のみで押印は必須ではなくなりましたが、実務上は押印も行うことが多いです。)

この3つは、宅建士の資格がなければ絶対にできないお仕事なんです!まさに宅建士の専門性が発揮される場面ですね!
- 契約書(37条書面)の内容説明自体は、宅建士でなくても、例えば事務のパートさんなどが行っても法律上は問題ありません。(ただし、内容の責任は重大なので、実際には宅建士が説明することが多いです。)
- 上記の独占業務は、「宅建士」であれば行うことができます。必ずしも、その事務所の「専任」の宅建士である必要はありません。
事務所には必須!「専任の宅建士」の設置ルール
宅建業者は、その事務所や特定の案内所に、一定数の「専任の宅地建物取引士」を置かなければならない、という義務があります。
「専任」というのは、基本的にはその事務所に常勤して、もっぱら宅建業の業務に従事している状態を指します。他の会社の役員を兼ねていたり、他の場所で常勤していたりすると、原則として専任とは認められません。
専任になれる人、なれない人(未成年者の例外)
専任の宅建士は、原則として成年者(20歳以上、または法改正後の18歳以上)でなければなりません。
ただし、未成年者であっても、以下のいずれかに該当する場合は、例外的に専任の宅建士になることができます。
- 一度でも婚姻したもの: 法律上、婚姻すると成年者と同じように扱われる(成年擬制)ためです。
- 宅建業を営むことについて、法定代理人(親権者など)から営業の許可を得ている場合: この場合も、その許可された営業の範囲内では成年者と同一の能力があるとみなされます。
基本は成年者だけど、未成年でもこの2つのケースならOK!と覚えておきましょう。
何人必要?事務所と案内所での設置基準
では、専任の宅建士を何人置かなければならないのでしょうか?これは、場所によって基準が異なります。
- 事務所(本店・支店など):
- その事務所で宅建業に従事する者(役員、正社員、契約社員、パート、アルバイトなど、業務に携わる人すべてを含みます!)の数の合計に対して、5分の1以上の割合で専任の宅建士を設置する必要があります。
- 例:従事者が10人なら、10人 × (1/5) = 2人以上の専任宅建士が必要。
- 例:従事者が4人なら、4人 × (1/5) = 0.8人 → 切り上げて1人以上の専任宅建士が必要。
- 案内所等(※一定の要件を満たすもの):
- 契約の申込みを受けたり、契約を締結したりする案内所などでは、少なくとも1人以上の専任の宅建士を設置する必要があります。
事務所の「5分の1」計算、しっかりマスターしましょう!従事者にはパートさんなども含む点、計算結果が端数になったら切り上げる点を忘れずに!
もし足りなくなったら?2週間以内の補充義務!
もし、退職や転勤などで専任の宅建士の数が法律で定められた基準(事務所なら5分の1、案内所なら1人)を下回ってしまった場合、宅建業者は2週間以内に、必要な数の専任宅建士を補充するなど、基準に適合させるための措置をとらなければなりません。
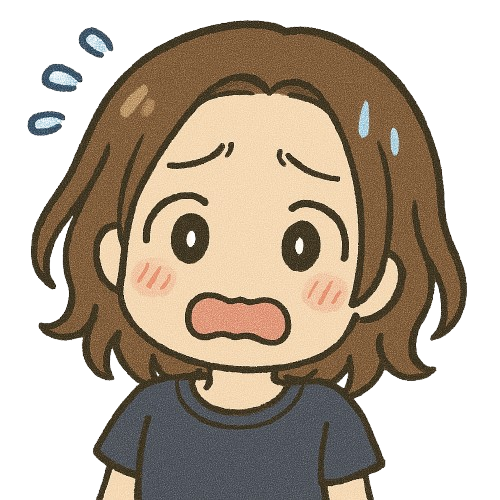
2週間って、結構短いですよね!急に辞められたりすると、会社は大変です…。すぐに代わりの人を探したり、配置転換したりしないといけませんね。
プロとして守るべき「宅建士の心得」3か条
宅建士は、単に法律知識があるだけでなく、高い倫理観と専門家としての自覚を持って業務にあたることが求められます。宅建業法では、宅建士が守るべき基本的な姿勢として、以下の3つを定めています。
①業務処理の原則:公正誠実・連携
宅建士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、「購入者等の利益の保護」及び「円滑な宅地又は建物の流通」に役立てるように、公正かつ誠実に宅建業法に定める事務を行うとともに、「宅建業に関連する業務に従事する者(宅建士外の従業員等)」と連携するよう努めなければなりません。(宅建業法第15条)
自分の利益だけじゃなく、お客様の利益を守ること、取引がスムーズに進むようにすること、そして嘘やごまかしなく誠実に仕事をしなさい、ってことですね。他の従業員とのチームワークも大事!
②信用失墜行為の禁止:信頼を裏切らない!
宅建士は、「宅建士の信用」又は「宅建士の品位」を害するような行為をしてはいけません。(宅建業法第15条の2)
例えば、お客様に対して横暴な態度をとったり、騙すようなことを言ったり、業務上知り得た秘密を漏らしたり…といった、宅建士全体の信頼や評判を落とすような行為はしちゃダメ!ってことです。プロとしての自覚が問われますね。
③知識・能力の維持向上:常に学び続ける姿勢
宅建士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければなりません。(宅建業法第15条の3)
法律や制度はどんどん変わっていきますし、新しい情報も次々に出てきます。一度合格したから終わり、じゃなくて、常に勉強を続けて、知識やスキルを最新の状態に保つ努力をしなさい、ということですね。宅建協会などが主催する研修会に参加するのも良い方法です。
大事な身分証!「宅建士証」にまつわる手続きあれこれ
最後に、宅建士として業務を行う上で携帯が義務付けられている「宅建士証」に関する手続きについて見ていきましょう。これも意外と忘れがちなルールがあるので注意が必要ですよ!
住所や名前が変わったら?「書換え交付申請」
もし、宅建士の住所や氏名に変更があった場合、まずは「変更の登録申請」を登録している都道府県知事に対して遅滞なく行う必要があります。
そして、それに加えて、宅建士証の記載事項(住所や氏名)も変わるわけですから、変更の登録申請と併せて、「宅建士証の書換え交付申請」も行わなければなりません。
引っ越しや結婚で住所・氏名が変わったら、変更登録+書換え交付申請の2点セット!と覚えておきましょう!古い情報のままの宅建士証を使い続けるのはNGですよ。
もしもの時の「提出」と「返納」
宅建士証は、特定の状況下で、一時的に提出したり、完全に返納したりしなければならない場合があります。
事務禁止処分を受けたら「提出」
もし、宅建士が業務に関して不正な行為などをして、都道府県知事から「事務禁止処分」(一定期間、宅建士としての業務を禁止される処分)を受けた場合、速やかに、その交付を受けた都道府県知事に宅建士証を提出しなければなりません。
そして、事務禁止期間が無事に満了しても、宅建士証は自動的には戻ってきません! 本人が「返してください」と返還請求をしない限り、返してもらえないんです。これも注意が必要なポイントです。
登録がなくなったら「返納」
何らかの理由で都道府県知事への登録自体が消除された(取り消された、本人が死亡したなど)場合は、宅建士証はもはや無効ですから、速やかに、交付を受けた都道府県知事に宅建士証を返納しなければなりません。(本人が死亡した場合は相続人が返納します。)

提出は一時的に預けるイメージ、返納は完全にお返しするイメージですね。
いつ見せる?宅建士証の「提示義務」
宅建士証は、常に携帯するだけでなく、特定の場面で相手に提示する(見せる)義務があります。
- 重要事項を説明するとき:
- 説明を始める前に、相手から請求がなくても、必ず提示しなければなりません。これは絶対です!
- 取引の関係者(お客様、相手方の業者など)から請求があった場合:
- 請求されたら、いつでも提示しなければなりません。
重要事項説明のときは、請求されなくても提示必須! これ、試験でも超頻出です! 契約書(37条書面)を読み上げる際には、法律上の提示義務はありません。(ただし、実務上は見せることも多いかもしれませんね。)
従業者証明書との違いは? 宅建業者の従業員は、宅建士かどうかにかかわらず、「従業者証明書」というものを常に携帯する義務があります。これも、取引関係者から請求があった場合は提示しなければなりません。宅建士は、「宅建士証」と「従業者証明書」の両方を携帯し、場面に応じて提示する必要がある、ということですね!
まとめ:宅建士試験合格から登録、業務、義務、取引士証の手続きまで
今回は、「宅地建物取引士」になるための道のりから、その業務、義務、そして大切な「宅建士証」の扱いまで、幅広く解説してきました!盛りだくさんな内容でしたが、宅建士という資格の全体像を掴む手助けになれたでしょうか?
宅建士は、不動産取引のプロフェッショナルとして、専門知識はもちろん、高い倫理観と責任感を持って仕事に取り組むことが求められる、やりがいのある資格です。試験合格、そしてその先の宅建士としての活躍を目指して、頑張ってくださいね!
最後に、今日の内容の重要ポイントを復習しましょう!
- 宅建士になるまで: ①試験合格(一生有効)→ ②登録(受験地の知事へ、実務経験2年or講習、一生有効)→ ③宅建士証交付(法定講習※合格後1年以内免除、有効期間5年)
- 独占業務: ①重要事項説明、②35条書面記名、③37条書面記名
- 専任宅建士設置義務:
- 事務所:従事者の1/5以上
- 案内所等:1人以上
- 不足時は2週間以内に補充!
- 宅建士の心得: ①公正誠実・連携、②信用失墜行為禁止、③知識・能力の維持向上
- 宅建士証の手続き:
- 書換え交付: 住所・氏名変更時に変更登録と併せて申請。
- 提出: 事務禁止処分時に知事へ。(返還は要請求)
- 返納: 登録消除時に知事へ。
- 提示義務: 重説時(請求なくても必須!)、取引関係者から請求時。

これらの知識は、試験合格のためだけでなく、将来宅建士として活躍するためにも不可欠です。一つ一つ着実に身につけていきましょう!