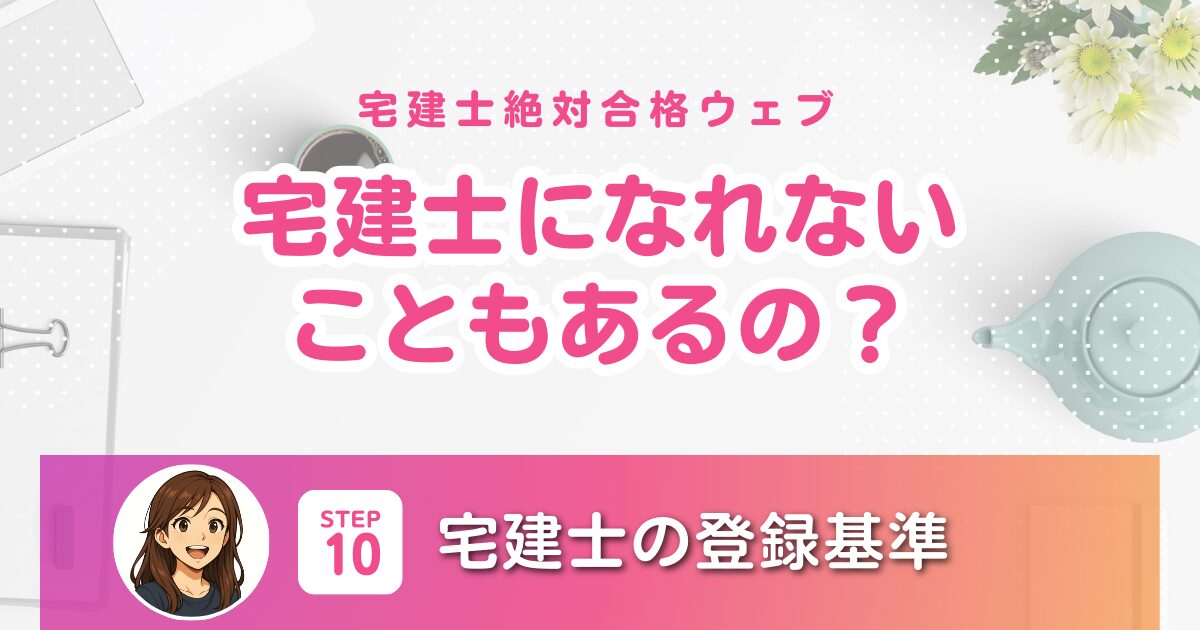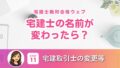宅建士の登録基準、いわゆる欠格事由って、免許の基準と何が違うの?って混乱しちゃいますよね? せっかく難しい宅建試験に合格しても、登録できなきゃ意味がない! そうならないためにも、登録のルール、特に「こういう人は登録できませんよ」っていう欠格事由について、しっかり理解しておくことが大切なんです。
この記事では、宅建士の登録における欠格事由について、免許の欠格事由と比較しながら、特に注意すべきポイントを分かりやすく解説していきます!

今日は皆さんがつまずきやすい登録の欠格事由について、バッチリ解説しちゃいますよ!
この記事でわかること
- 宅建士登録における欠格事由の全体像
- 免許の欠格事由との共通点と相違点
- 特に注意が必要な欠格事由の詳細解説
- 効率的な欠格事由の覚え方のヒント
- 未成年者の登録に関する注意点
宅建士として登録できない!?欠格事由をチェックしよう
そもそも欠格事由って何?
まず、「欠格事由」って言葉自体、ちょっと硬いですよね。簡単に言うと、「宅建士として登録するために満たしてはいけない条件」のことです。宅地建物取引業法っていう法律で定められていて、これに一つでも当てはまっちゃうと、残念ながら宅建士として登録ができない、ということになっちゃうんです。
宅建士は、不動産取引の専門家として、お客様の重要な財産に関わる仕事です。だからこそ、一定の信頼性や適格性が求められるんですね。欠格事由は、その信頼性を担保するための基準の一つと言えます。
宅建士の欠格事由リストを一挙公開!
じゃあ、具体的にどんな人が登録できないのか、リストで見ていきましょう! ここ、しっかりチェックしてくださいね!
- 心身の故障により宅建士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
- 以前は成年被後見人や被保佐人が該当していましたが、法改正で削除されました。現在は、個別の判断になりますが、精神の機能の障害により宅建士の事務を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者が該当します。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 自己破産などをした場合ですね。でも、「復権」を得れば大丈夫! 復権っていうのは、簡単に言うと破産者としての制限がなくなることです。
- 免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(法人の場合は役員も含む)
- 過去に宅建業の免許を取り消されたことがある場合、ペナルティとして5年間は登録できません。
- 免許取消処分の聴聞の期日・場所の公示日から処分決定までの間に、相当な理由なく廃業の届出をした者で、その届出の日から5年を経過しないもの
- これは、免許取消になりそうだからって、先回りして廃業しちゃう、いわゆる「駆け込み廃業」を防ぐためのルールですね。これも5年間のペナルティがあります。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 禁錮刑や懲役刑などの重い刑罰を受けた場合です。執行猶予期間が満了した場合も、そこから5年間は登録できません。
- 宅地建物取引業法、暴力団対策法、または傷害罪・暴行罪・脅迫罪などの特定の犯罪により、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 罰金刑でも、対象となる法律や罪の種類によっては欠格事由になります。ここ、意外と見落としがちなので注意してくださいね!
- <ポイント>
- 対象となる法律:宅建業法、暴力団対策法
- 対象となる罪:傷害罪、現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、背任罪など
- 免許の申請前5年以内に、宅地建物取引業に関して不正または著しく不当な行為をした者
- 具体的な不正行為などが過去5年以内にあった場合ですね。
- 宅地建物取引業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかである者
- これはちょっと抽象的ですが、客観的に見て「この人は不正をしそうだ」と判断される場合です。
- 宅建士として行う事務に関し、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者
- 上記8と似ていますが、こちらは「宅建士としての事務」に限定した視点です。
- 事務禁止処分を受け、その禁止の期間中に、本人の申請により登録が消除され、まだその禁止期間が満了しない者
- これは後で詳しく解説しますが、宅建士としてのルール違反で「事務禁止」という処分を受けた場合の規定です。
- 宅地建物取引業の営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
- 未成年者の扱いですね。これも後で免許基準との違いを詳しく解説します!

結構たくさんありますよね! でも大丈夫、ポイントを押さえれば怖くありませんよ!
免許の欠格事由とほぼ同じ?共通点を押さえよう
さて、このリストを見て、「あれ? 宅建業の免許を取る時の欠格事由と似てるな」って思った方、鋭いですね! そうなんです、1番から8番あたりまでは、宅建業の免許の欠格事由とかなり内容が共通しているんです。
| 項目番号 | 宅建士登録の欠格事由 | 免許の欠格事由との関連 |
|---|---|---|
| 1 | 心身の故障により宅建士の事務を適正に行うことができない者 | ほぼ共通 |
| 2 | 破産者で復権を得ない者 | ほぼ共通 |
| 3 | 免許取消しから5年未経過 | ほぼ共通 |
| 4 | 聴聞公示後の相当理由ない廃業届から5年未経過 | ほぼ共通 |
| 5 | 禁錮以上の刑の執行終了等から5年未経過 | ほぼ共通 |
| 6 | 一定の法律違反等による罰金刑の執行終了等から5年未経過 | ほぼ共通 |
| 7 | 免許申請前5年以内の宅建業に関する不正・著しく不当な行為 | ほぼ共通 |
| 8 | 宅建業に関し不正・不誠実な行為をするおそれが明らかな者 | ほぼ共通 |
| 9 | 宅建士の事務に関し不正・不誠実な行為をするおそれが明らかな者 | 類似(視点が異なる) |
| 10 | 事務禁止期間中に登録消除申請し、期間が満了していない者 | 宅建士登録特有 |
| 11 | 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者 | 扱いが異なる |
効率的な覚え方のヒント!
免許の欠格事由をしっかり勉強していれば、宅建士登録の欠格事由の大部分はカバーできちゃいます! だから、勉強する時は、まず免許の欠格事由を完璧にして、その上で、宅建士登録特有のルールや、免許と扱いが違う部分(特に10番と11番!)を重点的に覚えるのがおすすめです!
ここが違う!宅建士登録で特に注意したい欠格事由2選
さあ、ここからが本番ですよ! 免許の基準と共通する部分が多いとはいえ、宅建士の登録ならではの、特に注意してほしいポイントが2つあります。試験でも狙われやすいので、しっかりマスターしましょう!
ポイント①:事務禁止処分を受けた後の登録について
まず注目したいのが、リストの10番目!
- 事務禁止処分を受け、その禁止の期間中に、本人の申請により登録が消除され、まだその禁止期間が満了しない者
これはどういうことかと言うと…
宅建士が何かルール違反をしてしまうと、「事務禁止処分」っていうペナルティを受けることがあるんです。これは、一定期間、宅建士としてのお仕事(重要事項説明とか、契約書への記名押印とか)ができなくなる処分です。
事務禁止処分の期間は、最長で1年間です。
で、この事務禁止処分を受けている期間中に、「もう宅建士やーめた!」って言って、自分から登録を消してもらう申請(登録消除申請)をした場合の話です。
この場合、たとえ自分から登録を消したとしても、元々定められていた事務禁止の期間が終わるまでは、再登録はできませんよ、っていうルールなんです。
ここ、すごく大事なポイントです! 「自分から登録を消したんだから、すぐに再登録できるんじゃないの?」って思いがちですが、それはダメ! 事務禁止期間が満了するまでは、欠格事由に該当しちゃうんです。
逆に言えば、事務禁止の期間さえ満了すれば、たとえ期間中に登録消除の申請をしていたとしても、すぐに再登録が可能になるってことですね!

ここ、ひっかけ問題で本当によく出題されるんですよ! 『期間満了を待たずに再登録できる』みたいな選択肢に騙されないでくださいね!
ポイント②:未成年者の扱いは免許と違う!
次に注意したいのが、リストの11番目!
- 宅地建物取引業の営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
未成年者の扱いについては、免許の基準と宅建士登録の基準で、明確な違いがあるので、しっかり区別して覚えましょう!
【免許の場合】
宅建業の免許を受ける場合、未成年者であっても、法定代理人(親権者など)から営業の許可を受けていれば、成年者と同じように扱われます。 もし、営業の許可を受けていない未成年者の場合でも、その法定代理人が免許の欠格事由に該当していなければ、未成年者自身は欠格事由には該当しません。
免許の場合の未成年者
- 法定代理人から営業許可あり ⇒ OK(成年者とみなす)
- 法定代理人から営業許可なし ⇒ 法定代理人が欠格じゃなければOK
【宅建士登録の場合】
一方、宅建士の登録の場合は、もっとシンプル! 「営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者」は、それだけで欠格事由に該当します。
つまり、法定代理人がどうとか、営業の許可がどうとかは関係なく、原則として未成年者は宅建士として登録できないんです。
宅建士登録の場合の未成年者
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない ⇒ NG(欠格事由に該当!)

免許と宅建士登録で、未成年者のルールが違うっていうのは、本当に重要なポイントです! ごっちゃにならないように、しっかり整理しておきましょうね!
じゃあ、未成年者は絶対に宅建士になれないの? っていうと、そうでもなくて。 例外として、婚姻している未成年者は、民法上、成年者とみなされる(成年擬制)ので、宅建士登録の欠格事由には該当しません。 また、法定代理人から宅建業とは別の特定の営業(例えば、お店を経営するとか)の許可を受けている未成年者も、その営業に関しては成年者と同一の行為能力があるとみなされるので、登録できる可能性があります。(ただし、宅建業に関する営業許可だけではダメ、という点に注意!)
まとめ
お疲れ様でした! 宅建士の登録基準(欠格事由)、しっかり理解できましたか?
宅建士の登録欠格事由は、免許の欠格事由と共通する部分が多いですが、特に「事務禁止処分後の登録消除」と「未成年者の扱い」については、宅建士登録特有のルールがあるので注意が必要です。
せっかく試験に合格しても、登録できなければ宅建士として活躍できません。今回解説したポイントをしっかり押さえて、スムーズな登録を目指しましょう!
最後に、この記事の重要ポイントをまとめますね。
- 欠格事由とは?:宅建士として登録できない条件のこと。
- 免許との共通点:欠格事由の多く(特に1~8番)は、免許の欠格事由と内容がほぼ同じ。
- 重要ポイント①:事務禁止期間中に自分で登録を消除しても、その禁止期間が満了するまでは再登録できない。
- 重要ポイント②:成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、原則として宅建士登録ができない(免許基準とは扱いが異なる!)。
- 効率的な学習法:まずは免許の欠格事由を完璧にし、その上で宅建士登録特有のルール(10番、11番)を重点的に覚えるのがおすすめ!

これで欠格事由はバッチリですね! 不安な点は解消されましたか? 宅建士試験、そしてその先の登録まで、応援していますよ!